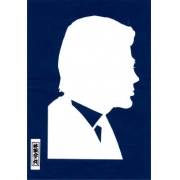【粗筋】
彼岸の天王寺では、無縁仏の供養に引導鐘をつくという。これを聞いた阿呆が、自分もクロという犬のために引導鐘をつきたいと言い出した。
「長い棒で鼻の上を殴られ、クワーンというたがこの世の別れ。ああ、無下性に殴れんもんやな」
という訳で、彼岸で雑踏を極める天王寺へ出掛けた阿呆、坊主に鐘をついてもらうが、ウワン、ウワンといういい音色を聞いて、
「おい坊ンさん、引導鐘三つといいますから、あと一つはわてにつかしとくなはれ」
「さあ、どうぞ、こちらで御焼香なされ」
「御焼香……御当家にお金どっさり儲かって、悪魔払いにたんと、稲荷の数を寄せ集め、伏見では熊鷹稲荷の大明神、権太夫稲荷の大明神……」
「これ、そんな所で乞食の真似をしないな」
「今のウワンウワンを頼むで、ガンガシンニョ、ニョコロ……」
「これ、お前がそないなことを言わんでよい。早うつき」
「ひィ、ふゥのみッツ」
クワーン
「ああ、無下性には殴れんもんやな」
【成立】
「犬の引導鐘」というのが正式タイトルらしい。マクラは『醒酔笑』巻之四「そでない合点」。イタチを捕まえたのを「彼岸だから逃がしてやれ」と言うのを見て、「生まれて初めて彼岸という物を見たが、姿はそのままイタチじゃ」というもの。
【一言】
この噺は、笑福亭家代々のお家芸で、そのため大阪では他の落語家は遠慮して高座にかけないそうだが、東京では、亡き三遊亭百生が一手専売に演じていた。とりたてて筋らしい筋はないが、大阪版与太郎の目を通して活写される天王寺境内のスケッチがなんともたのしい落語だ。有名な石の鳥居にはじまって、ぽんぽん石、亀の池、引導鐘、屋台のおでん、寿司、竹ゴマ屋、のぞきからくり、はては順礼のご詠歌から阿呆陀羅経まで、一瀉千里に喋りまくった百生の特徴あるダミ声が、まだ耳に残っている。「りっぱな鳥居やろ、これが日本三鳥居というねや」といわれて「ほな、ここの坊さんウイスキーつくってはるのか、サントリイちゅうと……」だの、亀に豆をやろうとして「そんな堅いもん噛むかい」「噛まんもんなんで亀という」などという実にくだらないクスグリが、百生のとぼけた味わいにぴったりで、聞くたびにふきだしたものだ。(江國茂・百生は本筋は簡単にして、境内を紹介する方に脱線、落ちは付けなかった)
●
彼岸は彼岸でも、やっぱり春やと思います。仕所は、境内の店の描写やろうな。ここだけはその演者の仕勝手やから。(笑福亭松鶴)
【蘊蓄】
荒陵山敬田院四天王寺は、推古元(593)年に聖徳太子が建立した日本最古の宮寺で、「大阪の仏壇」といわれ、「大坂城と並んで浪速景観の双璧」とうたわれた。
-
落語「は」の23:羽衣(はごろも):そ… 2025.11.28
-
落語「は」の22:羽衣(はごろも):そ… 2025.11.27
-
落語「は」の21:化物屋敷(ばけものや… 2025.11.26
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List