2011年01月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

魔女の一撃
週末のタールフォルスト…といっても、二週間ほど前の週末の様子。小春日和で暖かかった。今日も快晴で似たような天気だったが、気温は真冬の3℃前後。先日、一日風邪で寝込んだ。熟睡して復調した翌朝、顔を洗おうと洗面台にかがんだところ、腰のあたりが「ぎくっ」とな。あたた….やられた、魔女の一撃(Hexenschuss)、ぎっくり腰だ。その日一日、ベッドからほとんど動けず。立ち上がろうとすると、100kgのバーベルをかついでいるんじゃないかと思うほどの負担が腰にくる。背骨が毎日これほどの重量を支えていたとは…。週に1,2回ジムに通っていたとはいうものの、朝から晩まで座っていたり、カメラバック(けっこう重い)を肩からさげて一日中立っていたりと、確かに腰には負担をかけることが多かった。反省。2日ほどで快復したが、これからは気をつけなければなるまい。
2011/01/31
コメント(3)
-

古酒の宴 (5)
時が経つのを忘れワインを語り合う参加者たち。24. 1997 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Weingut Dr. Hermann)澄んで繊細な香り、力強い酸とミネラリティ。酸味が舌の上でビリビリと震える。それまでのワインを、時間という霧の向こうで揺れるともし火とすれば、このワインは明瞭な輪郭をもつサーチライトの光。眩しいほどの若さに未来が香る。25. 1985 Erdener Treppchen Riesling Auslese (Weingut Erben Hubert Schmitges)まるい舌触りにフルーティな甘みとほどよい酸味、澄んで繊細、穏やかな調和。1985は温暖な春に冷涼な夏が続いた。良年になりそうもない、と、やはり冷夏で不作年となった1984の記憶も生々しかった生産者達が悲観的になりはじめたころ、ようやく天候が回復して穏やかな秋晴れが続き、素晴らしいシュペートレーゼ、アウスレーゼが収穫されたそうだ。26. 1985 ?rziger W?rzgarten Riesling Beerenauslese (Weingut Dr. Hermann)なかば茶色に酸化したリンゴを思わせる素朴な味わいの、フランクフルト近郊などで愛好されているアップルワインの香り。貴腐香を伴う明瞭な甘みに軽くカカオが混じる。27. 1991 Erdener Treppchen Riesling Eiswein (Weingut Karl Erbes, ?rzig)閉じている。アプリコット、新鮮なリンゴ、蜂蜜のヒントに繊細な酸味。凝縮してかつ精妙な余韻。1991は6月の冷涼な気候で開花が遅れた後、7月から収穫直前まで太陽が照り続けた年。乾燥と高温で酸が過剰に減ることを恐れて早めに収穫した醸造所もあったという。一方10月末まで完熟を待って収穫した醸造所のワインは、凝縮したフルーツ感とミネラルで若いうちはとっつきにくく、ピリリとした酸味が効いていたそうだ。本収穫が終わってから数週間後の早い時期にアイスヴァインが収穫された。28. 1998 ?rziger W?rzgerten Riesling Eiswein (Weingut Karl Erbes, ?rzig)繊細な香りが広がる。完熟して凝縮したアプリコットの甘みに厚みのある酸味、非常に長い余韻。1998年も11月20~23日という早い時期にアイスヴァインが収穫された年だが、私がモーゼルにやってきた年でもある。猛暑の夏の後、10月は肌寒くしばしば雨が降り、トリーアのハウプトマルクトのヴァインスタンドで飲んだグリューヴァインの暖かさ思い出される。そしてこのワインの若々しさは、12年という歳月が長いようでいて、ほんのつかの間でしかないことを示しているように思われた。29. 2006 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese*** (Jos. Christoffel jun.)エレガントで繊細な甘みにマンゴ、パイナップルなど南国のフルーツのヒント、とても長い余韻。2006年は収穫を目前にした10月初旬の大雨で、貴腐が一気に広がった年だ。完熟した南国のフルーツが華やかに香るワインが多い。Le vin c’est le temps; parsque le temps fait le vin. (Jean-Marc Maugey)ワインとは時間である。なぜなら、時間がワインを造るからだ。30. 2006 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese Urgl?ck GK (Dr. Hermann)完熟した柑橘の香りが華やかに香り立つ。みずみずしくボリューム感のある酒躯に白桃、アプリコットのヒント、ほのかな苦味。「ウアグリュックUrgl?ck」は畑の区画名で、樹齢30~80年の自根の古木が育つ。31. 2005 ?rziger W?rzgarten Riesling Trockenbeerenauslese (Karl Erbes)繊細かつ複雑な香りが華やかに香り立つ。アプリコット、蜂蜜、マニキュア落としのヒント。非常に力強く凝縮しているが、同時に繊細な軽やかさもある。シトラスの香りに爽やかな若々しさ。32. 2007 Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese GK (Dr. Hermann)深みと複雑さを備えた香り。舌の上では果てしなく濃厚で丸く、トロリとしてクリーミィだが軽やかで上品。蜂蜜、熟した南国の果物のヒント。舌の上でとろけるような貴腐。偉大な古酒となるだろう。最後のワインの試飲を終えたときには、既に深夜零時をまわっていた。年配の参加者がおもむろに立ち上がり、言った。「シュテファン。クリスチャン、素晴らしい試飲だった!我々は今日、数多くの古酒を味わった。熟成を待ってから飲むことは、新酒が早々に出回るようになった昨今では古臭いことかもしれない。皆新酒のリリースを心待ちにして、市場に出た端からあれこれ評価して飲んでしまう。残念なことだ。しかし昨今、せっかちな消費への反省と批判の声がしばしば聞かれるようになった。特に2010年産の酸味は、熟成を必要とするだろう。つまり熟成したワインを味わうことは古臭いようでいて、実は新しいトレンドなのだ。今宵、我々はモーゼルの真価を味わうことが出来た。素晴らしい体験だった。ありがとう!」セラーに拍手が木霊し、参加者達は皆疲れた様子もなく上機嫌で、夜のしじまに消えていった。外は霧雨であった。しっとりとした空気を胸いっぱいに吸い込むと、モーゼルの水の匂いがした。(終わり)
2011/01/29
コメント(6)
-

古酒の宴 (4)
16. 1971 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Weingut Gesch. Berres)明るい金色。パセリ、アスパラガスの匂い。軽くほっそりとしてほのかに甘いが、野菜系の香りが面白い。1971は本来優良年として定評のあるヴィンテージだ。1976ほど貴腐の影響は無いが、凝縮した果実味に酸が調和し、理想のリースリングとも言えるエレガントな味わいで、やはりバランスの良い1975と比べても、熟成のポテンシャルでは1971が勝るという。1971年。あの7月は葡萄の葉が黄色に染まり枯れ始めるのほどの猛暑だった。ルーヴァーのカルトホイザーホフは灌漑設備を設置し、6~8週間給水することで収穫を確保した。ザールのフォン・オテグラーフェン醸造所の記録によれば、収穫時の果汁糖度は78~120エクスレ、酸度は8~9g/Literとほぼ理想的な数値。しかし、優良年の定評のある醸造所の優れた葡萄畑に育つリースリングのアウスレーゼでも、こういうワインもあるのが、古酒には避けられないリスクかもしれない。17. 1971 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Jos. Christoffel Jun.)オレンジを帯びた暗い金色。鉛筆の芯、アプリコットの香り。コンパクトにまとまった酒躯に干したアプリコット、カカオのヒント、余韻に乾燥した葡萄のヒント。これはまっとうに熟成している。18. 1971 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese***** (Jos. Christoffel jun.)明るい金色。繊細な香り、ブランデー入りアーモンド菓子(マルチパン)のヒント。エレガントで純粋な甘みにほのかな蜂蜜とアーモンドのヒント。クリアーに澄んだ甘酸の調和、気品、長く美しい余韻。フィネス。歳月を経てもなお、というのではなく、歳月を経たからこそ到達出来た味わいというべきか。供出前にコンディションをチェックするクリスチャン・ヘアマン。19. 1975 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Dr. Hermann)金色。やや控えめな香りにアプリコット、蜂蜜のヒント。軽い酒躯に砂糖に漬けたアプリコットのヒント。長い余韻にごつごつしたミネラル感が残る。繊細な気品を湛えた18.に比べると若干粗野な印象は否めないが、頼り甲斐のある感じ。20. 1976 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Dr. Hermann)ややオレンジがかった金色。熟成香、やや枯れかけている。ほろ苦いカカオのヒント、余韻に繊細な酸味とミネラル感。「やっぱり1975は過小評価されているよ」と参加者の一人。「貴腐ワインの当たり年だった1976の影にかくれているけれど、優良年と飲む度に思う」1976も1959, 1971, 1973同様に猛暑の夏だった。そして収穫期には葡萄畑を包んだ霧が午後に晴れるという、貴腐の繁殖に理想的な天候となったが、酸が不足する傾向があり、熟成能力は1959や1971に及ばないとされる。21. 1976 Graacher Himmelreich Riesling Auslese GK (S.A. Pr?m, Wehlen)黄色を帯びた金色。フルーティなアロマにマッシュルームのヒント。繊細で直線的な構造の酸味とミネラル、余韻に漂う熟成香。ちなみに、S.A.プリュムはカール・ヨゼフ(通称カヨ)とよばれるクリストッフェルJr.醸造所主人の兄の奥さんの実家である。22. 1969 ?rziger W?rzgarten Riesling Beerenauslese (Gesch. Berres, ?rzig)オレンジがかった金色。ほのかに葡萄に繁殖した貴腐菌を思わせる黴くささがあるが、干したアプリコットの凝縮した甘み、ほんのりビターアーモンド、繊細な酸味、長い余韻。23. 1966 ?rziger W?rzgarten Goldwingert Riesling Beerenauslese (Weingut Peter Nicolay, ?rzig)明るい金色。残念ながらコルク臭が目立つが、やわらかな甘みとどうにかこうにか調和しており飲めないことも無い。1969と1966はどちらも良年で似た性格を持っているが、69はどちらかといえばリッチで酸が柔らかく、66は中程度の酒躯に繊細な果実味、上品な酸味が特徴という。試飲会はその後休憩をはさんで1985以降、すなわち温暖化以降のワインに移行した。(つづく)
2011/01/28
コメント(0)
-

古酒の宴 (3)
供出前にワインをチェックするシュテファン・エルベスとクリスチャン・ヘアマン。10. 1979 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Weingut Gesch. Berres)やや明るい麦わら色。ほのかに熟成香、繊細で上品なカラントの甘みにほのかな酸味の調和したほっそりとした酒躯、美しい古酒。1979は葡萄が熟すのが遅く、糖度はほどほどで酸も強かったが、収穫量が低かったぶん凝縮したワインが生産された。若いうちは固く気難しく、6年目位からようやく飲み頃に入ったという。11. 1970 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Weingut M?nchhof, ?rzig)金色を帯びた麦わら色。熟成香にほんのり鉛筆の芯、アプリコットのヒント。甘みは枯れて熟成香と軽い苦み、熟成香の余韻。残念ながら終わっていた。J.J.プリュムの記録によれば、1970は10月になっても葡萄は熟さなかったが、その後訪れた晩秋の好天で挽回出来た。11月半ばから12月半ばまで(!)収穫は続き、それから間もない12月23日と24日にはアイスヴァインが収穫されたという。12. 1967 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese (Weingut Geschw. Berres)オレンジを帯びた金色。ほのかにモルトウィスキーを思わせるスモーキィな香り。コンパクトな酒躯に干した果物の凝縮感があり、繊細で長い余韻に気品を感じる。ものの本によれば1967は恵まれた生産年ではなかった、とある。夏の好天で収穫前まで葡萄は順調に熟したが、その後所により大雨が降ったため醸造所によって差があるそうだが、このボトルは素晴らしかった。13. 1967 ?rziger W?rzgarten Riesling feinste Auslese (Weingut Merkelbach)明るい金色。これだけの歳月を経ても閉じているように感じる香りにシトラス、鉛筆の芯のヒント。軽く繊細な酒躯、ミネラルのほのかな苦味、熟した酸味。14. 1964 ?rziger W?rzgarten Riesling feinste Auslese (Jos. Christoffel jun.)明るい金色。軽く繊細でエレガント、繊細な甘みが花のように香りたち、若々しささえ漂う。ボトルの中で時の歩みが止まっていたかのようだ。1964のワインは一般に酸度は低いが大変充実した酒躯を持つとされる。だが、ザール、ルーヴァーとラインガウは、産地特有の生き生きとした酸味のお陰で酸不足を免れ、とりわけ美しく熟成したという。このクリストッフェルJr.のファインステ・アウスレーゼは中部モーゼルながら、素晴らしい芳しさがあった。ちなみに、昔はアウスレーゼをファイネ・アウスレーゼ、ファインステ・アウスレーゼと数段階に分けてリリースすることが出来た。ルーディ・ヘアマンによれば、ファイネ・アウスレーゼとファインステ・アウスレーゼに法的な基準はなく、醸造所がそれぞれ独自に判断していたという。だから消費者の誤解を招くとして1971年のドイツワイン法で禁止されたわけだが、その後も高品質を目指す醸造所はゴルトカプセル、ランゲ・ゴルトカプセルで区別している。15. 1959 ?rziger W?rzgarten Riesling feinste Auslese (Jos. Christoffel jun.)暗い金色。干したアプリコット、ほのかに鉛筆の芯、カラメルの魅力的な香り。舌の上では軽やかな酒躯に歳月を経て凝縮した味わい、干したアプリコットにほんのりとした苦味、モカのヒント。香りは口中に長く残る。1959は世紀のヴィンテージとして名高い。5月半ばの氷の聖者(アイスハイリゲン)で葡萄の蕾が霜害を受けた後「夏の間中、ず~っと太陽が照り続けていた」と年配の参加者が言うように、ほぼ3ヶ月間雨が降らず収穫の大半はアウスレーゼ以上となったが、酸度が6~9g/Literまで下がった。そのため収穫直後は熟成能力が疑問視されたが、それが杞憂に終わったことは周知の通りである。しかしその日は、1959, 1964, 1969, 1971, 1975, 1976, 1979といった評価の高い生産年も確かに相応のポテンシャルを示していたが、それ以外の、言わば忘れられた生産年とも言うべき1967, 1968, 1973のワインもまた、思いのほか楽しめることに感銘を受けた。「思い出は時とともに色あせていくものである」と先日書いた。ごく一部の奇跡のようなワインだけが、その魅力を保ち続けることができるのではないかと思ったからだ。しかし、古酒はどうやらそれだけではないようだ。(つづく)
2011/01/27
コメント(0)
-

古酒の宴 (2)
5. 1968 ?rziger W?rzgarten Riesling Kabinett (Weingut Fritz Berres, ?rzig)黄色の色調の麦わら色。軽くシトラスのヒントにほのかな甘み、余韻にアーモンド菓子(マルチパン)の香りが漂う。1965よりずっと明瞭な果実の存在感で、生産年の条件の違いを伺わせる。6. 1972 Erdener Treppchen Riesling Kabinett (Joh. Jos. Christoffel-Dr. Hermann)淡い琥珀色。干したアプリコットの繊細な香り、繊細な丸い酸味、熟成香に干した柑橘のヒント。「この年は72エクスレ以上に糖度が上がらなかった」と、ワインを醸造した本人のルーディ・ヘアマンは言った。「昔は90エクスレまで上がれば御の字だったのが、今は110エクスレまで普通に到達する。温暖化の影響だ」実質的に1985年以降、ドイツでは良年が続いている。果汁糖度が70エクスレ止まり、という生産年はもはや皆無だ。してみると、1984年産から始まったこの試飲会は、温暖化以前の生産年を遡るようにして始まった訳だ。7. 1968 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese (Weingut Merkelbach, ?rzig)黄色の色調の麦わら色。ほのかに香るアプリコットのヒントから期待する甘みは枯れていたが、中身の詰まった酒躯にミネラル感があり、余韻に熟成香が漂う。1968年は晩熟な年で、フォン・オテグラーフェン醸造所の記録では11月に入ってから収穫を開始。果汁糖度は63~78エクスレ、酸度は12~13g/Liter。シュペートレーゼは10年以上若々しく非常に上品な新鮮さを保っていたという。8. 1973 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese (Weingut Karl Erbes, ?rzig)金色を帯びた麦わら色。昇華しつつも繊細な甘みがはっきりと感じられ、蜂蜜、干したアプリコットのヒント、長い余韻。今でも十分に楽しめる。「1973年は素晴らしい夏だった。暑くて晴れた日が続いてな。あの夏は今でも忘れられんよ」と、年配の参加者がつぶやいた。厳しい乾燥で葡萄は収穫を目前にしてそれ以上成熟することが出来ず、期待された偉大な生産年にはならなかったものの、熟した果実の味わい深いワインが出来たという。9. 1973 Wehlener Klosterberg Riesling Sp?tlese (Weingut M?nchhof, ?rzig)やや暗い色調の麦わら色。熟成香にハーブ、干した果物のヒント。甘みのすっかり枯れた丸い舌触りの酒躯、辛口の余韻。ワインに集中する参加者。「それにしても、甘みはどこに行ってしまったんだろうね」と一人が首をひねる。「若い時のフルーティな甘みは、熟成すると枯れてしまうのはなぜだろう」「フロリアン・ラウアーから聞いたんだけど」と一人が答えた。フロリアンはモンペリエで醸造学を学んだザールにあるペーター・ラウアー醸造所の若手醸造家だ。「長期間の熟成で糖の分子が結合して、舌の味覚細胞の受容体に収まらないくらい大きくなってしまうらしい。だから糖は存在はしても感知できないから、辛口に感じるそうだ」なるほど、そうなのかもしれない。しかし、熟成を経て甘みが枯れるのは、可愛い子供が成長して大人になり、やがて老いていく人間の辿る過程に似ている気がする。そしてまた、老いてなお魅力を失わないものには、ワインでも人間でも、敬服するに値するのではないだろうか。(つづく)
2011/01/26
コメント(0)
-

古酒の宴 (1)
小説や映画で、夜の森の中を車で走るシーンがある。エルデン村の試飲会の後、ユルツィヒ村に向けてしばらく渓谷の上にある森の中を走った時は、丁度そんな感じだった。雨にぬかるんだ山道にヘッドライトの光芒が揺れ、暗闇の中に森の木立を浮かび上がっては、後ろへと飛び退っていく。対岸にあるユルツィヒまで普段はトレプヒェンの麓を走る国道を使うのだが、その日は氾濫したモーゼル川に水没していたため、葡萄畑がある斜面の背後を大きく迂回しなければならなかった。我々はやがて木組み造りの家屋が軒を寄せ合う村に入り、霧雨に濡れた石畳の上に車を停めた。古酒の試飲会場となったのは、カール・エルベス醸造所の地下セラーだ。醸造所の通りに面した入り口は狭く、一見すると普通の民家にしか見えない。居間を通り抜けてセラーに向かう階段を下りると、壁の目の高さの位置に「Hochwasser 23.12.1993」と日付が記され、1993年のクリスマス・イブの前日にモーゼルの大氾濫があり、このセラーはすっかり水没したことを示していた。それに比べれば今回の氾濫は大したことは無い。「よくある程度」と地元住民は落ち着いていた。積み重なったワインボトルに囲まれた酒庫は、14人あまりの参加者にはいささか狭かったが、却って昔からの知り合いのような、家族のような親密な雰囲気が生まれていた。我々は肩を寄せ合うようにして着席すると、半世紀の歳月を遡る古酒の試飲が始まった。会場全景。参加者にワインをそそいでまわるシュテファン・エルベス。1. 1984 ?rziger W?rzgarten Riesling QbA (Weingut Karl Erbs, ?rzig)明るい金色。熟成香は年相応にあるが、舌の上では意外なほど若々しくエレガントで、繊細な酸が生きていた。「1984は恵まれない生産年と言われているけど、これはなかなか」「ぜんぜんいけますね」と驚きの声があがる。瓶詰めされて以来セラーから動かなかった、理想的な保存状態がうかがえる。2. 1980 Graacher Domprobst Riesling QbA (Ewald Pfeiffer, ?rzig)金色。軽いシェリーのようで、ほのかな苦味に酸の目立つ余韻。「これは終わっている」との声で供出された二本目のボトルは、コンパクトな酒躯に干したグレープフルーツのヒント、スモーキィな香りが余韻に漂った。「この年は花振るいで収穫も少なかったが、そのぶん、しっかりしたワインになった」と、おそらく地元に住む年配の参加者が当時を懐かしむように言った。3. 1965 ?rziger W?rzgarten Riesling natur (Weingut Merkelbach, ?rzig)明るい麦わら色。マッシュルームの匂い。舌の上でもマイルドな酸味とハーブティーにマッシュルームが混じる。セラーでびっしりと黴に覆われたボトルだったのだろうか。カマンベールの白黴を思い出す。私のヴィンテージでもあるこの1965年は、世紀の不作年と言われている。収穫時期に雨が降り続き葡萄が熟さず、酸味の勝る痩せたワインが少量出来たに留まった。ザールのフォン・オテグラーフェン醸造所の記録では、その年の収穫は果汁糖度60~68エクスレ、酸度は12g/Literというから、いかに恵まれない年だったかわかる。「それでもカルトホイザーホフはアイスヴァインを造ったけど、あれは酸がギスギスして飲めたもんじゃなかった」と参加者の一人は言う。ちなみにそのアイスヴァインは果汁糖度109エクスレ、酸度35.3g/Liter(!)であった。4. 1965 Erdener Pr?lat Riesling naturrein (Weingut Fritz Berres, ?rzig)やや暗い色調の金色を帯びた麦わら色。ほのかに甘く繊細な香りが漂い、ほっそりとした酒躯に繊細なガラス細工のような酸味と枯れた甘み、軽くモカのヒント。これも1965年産だが、まだ生きていた。今にも壊れそうなほど儚いが、まだ生きていた。恵まれた葡萄畑と理想的な熟成環境が可能にした、ひとつの奇跡というべきかもしれない。(つづく)
2011/01/25
コメント(0)
-

ワインフォーラム雑感
先週は春の様に暖かかった。新春とはよく言ったものだなどと思いつつ、うららかな陽光を楽しんでいたのだが、今週に入って急に冬に逆戻りして気温は氷点下へと墜落。お陰で喉が痛い。微熱がある(ような気がする)。つまり、風邪気味である。それでも、毎年恒例のワインフォーラムに行ってきた。ラインラント・ファルツ州の品評会で金メダルを受賞したワインが173種類、今日金曜から日曜までの三日間試飲できるのは例年と同じなのだが、ひとつ違うことがあった。2500枚発行された一枚25Euroの入場券が、発売開始から3週間ほどの昨年12月上旬には売り切れていたのである!私はかれこれ10年ほど通っているが、前代未聞の事態であった。確かにこの2, 3年は売り切れていたのは知っていたが、以前は当日でも余裕で入場できたものだ。昨年も3000枚に入場券を限定したが、あふれる人々で会場のローマの浴場跡の保全に差し支えるとクレームがあったらしい。主催者のモーゼルワイン協会は他の場所も探したが、適当な会場が見つからなかったという。もともとは州立博物館で11月に開催されていたのだが、元のさやには戻れなかった訳だ。残念。そんな訳で、私が行ってきたのは午前10時半から1時までの開会イヴェント。州の農業会議所関係者とみられるスーツ姿が目立つ。彼らに混じって手渡された州営醸造所の2009 アフェルスバッハー・ハマーシュタインのリースリング・ファインヘルブを舐めながら、州ワイン農業会議所評議員クリスタ・クラスの開会挨拶を神妙に聞く。ワインフォーラムの開会式。「モーゼルでは8900haの葡萄畑の43%が急斜面にあり、60%でリースリングが栽培されている。とりわけザール(81%)とルーヴァー(89%)ではリースリングが大半を占め、この試飲会でも173種類のうち145種類がリースリング。リースリングのスタイル、個性を語り合う絶好の機会となってほしい。EUワイン市場改革に伴うエチケット上の表記変更が話題になっている。導入される表記である原産地名称保護Gesch?tzte Ursprungsbezeichnung、地理的表示保護 Gesch?tzte geographische Angabeは、その表記にふさわしい内容の伴った規定であるべきなことは言うまでもない。さらに表記事項ははっきりとわかりやすく、情報に富み、説得力があることが必要だ。この試飲会の金賞受賞ラベルはその好例といえる。しかし新しい表記を略称で GU、GgAと表記した場合、どこまで消費者に伝わるだろうか。また、同改革では葡萄畑の開墾制限を撤廃しようとしているが、自由化が画一化につながってはいけない。原産地名称保護の導入とあわせて、産地の個性を守っていかなければならない」とモーゼルの醸造所出身でもあるクラス女史は言う。この原産地名称保護と地理的表示保護の表記導入初ヴィンテージとなる2011年産の農作業開始を目前に控えているが、まだワイン法改正の詳細は煮詰まっておらず、生産者の間でもよくわかっていないようだ。そこで2月上旬にはドイツワイン生産者連盟、VDPドイツ高品質ワイン醸造所連盟、ワイン農業会議所やガイゼンハイムから専門家を集めての討論会がトリーアとノイシュタット・アン・デア・ヴァインシュトラーセで開催される。この改正でドイツワインがどう変わるかは、それから見えてくることになりそうだ。●公的機関の品評会の意味さて、その後引き続いて試飲に移る。著名醸造所のワインは品評会のメダルなど必要としないので、受賞ワインの大半は小規模で無名な醸造所のものである。もちろん、醸造所の規模とワインの品質は関係ない。むしろ小規模の方が、こまめに葡萄の世話を出来るので品質も高いことが多い。実際、今回試飲した中にも魅力的な香り高いワインが多かった。2009年は恵まれた生産年だったこともあるのだろう、辛口から中辛口にかけてはややぽってりとしたクリーミィな舌触りに、熟した柑橘や桃の香りが凝縮して、ミネラルも明瞭なものが多かった。この品質で価格も5~7Euroなら文句のないところである。例えば:Wein- und Sektgut Heinz Schneider (Leiwen)Weingut J?rg Trossen (Traben-Trabach)Weingut Klein-G?tz (Bruttig-Fankel)Weingut G?bel-Schleyer-Erben (Ernst)Weingut L?nartz-Theilmann (Ernst)Weingut Josef Bernard-Kieren (Graach)州の生産者栄誉賞Staatsehrenpreisを受賞した醸造所で、それぞれアロマティックで凝縮感のあるワインだった。とりわけクライン・ゲッツの2009 Bruttiger Elbling QbA trockenはエルプリングでこんなワインが出来るのか!という、驚きがあった。クリーミィでほのかにナッツ、蜂蜜のヒント、しっかりとした酒躯で余韻も長い。まるでよく出来たシャルドネのようだったが、15Euroという価格もまた、ドイツで最も高価な辛口エルプリングかもしれない。レナルツ・ティルマンの2009 Valwiger Herrenberg Riesling Sp?tlese trockenリースリングも凝縮感のある完熟した果実に桃やパイナップル、熟した柑橘が力強く口中に広がり、こなれたミネラルもしっかりしている。金賞を受賞するのもうなづける。だが、会場の一角に出ていたフォン・ヴォイルヴィッツ醸造所の2009 Wei?er Burgunder QbA ?Von Beulwitz“や同醸造所の2009 Kaseler Nie´schen Riesling ?S“ Sp?tlese trocken、あるいはレオ・フックス醸造所の2009 Pommerner Rosenberg Riesling QbA trocken (Weingut Leo Fuchs)、フィリップス・エックシュタイン醸造所の2009 Graacher Domprobst Riesling Sp?tlese halbtrocken (Weingut Philipps-Ecksteiin)を試飲すると、上述の醸造所の好印象が急にかすんでしまったのは否めない。緻密さとバランス、静謐さをたたえた奥行き、たとえアロマティックではなくても、閉じた姿の奥から伝わるポテンシャル。そういった印象を与えるワインは、ワインフォーラムでは例外に属する。確かにどれもよく出来たワインで、魅力的なワインである。それは間違いない。熟成を経て落ち着くなり、開くなりすればまた印象も変わってくるだろう。受賞した醸造家と話しても誠実で、価格も手ごろで、安心して飲めて人にも勧めることのできるワインである。ただ、いくつか例をあげるならファン・フォルクセンやマルクス・モリトールなどの、優れたポテンシャルを持つ葡萄畑を所有し、そこから最上のワインを造ることに存在意義の全てを賭けたような醸造所のワインと比べたときに、品評会で評価される要素(香り、味、調和)を超えたところにワインの本質的なクオリティの差があるような気がする。うまく言えないが。州の品評会とワインフォーラムは、全ての醸造所に平等に与えられたチャンスである。それは葡萄畑を格付けするのではなく、まして醸造所を格付けするのでもなく、グラスの中のワインの品質のみを保証するという、ドイツワイン法における品質保証制度の基本姿勢に通じる。そして評価はよりアロマティックで、より濃厚な酒躯であるほど、高得点となる。それはそれでよいのだが…。要は、ワインに何を求めるかによるのだろう。公的品評会で金賞を受賞したワインは、安心して楽しめるワインであることは間違いない。生産者が、真摯で地道な努力を公平に認めてもらえるチャンスでもある。それだけでも、品評会の意義は十分にあると言える。…などとよしなしごとを考えながら試飲していたところ、黒ジャンパーを着たごつい体格のセキュリティ担当者に声をかけられた。「まだ残りますか」気がつけば午後1時半。開会イヴェントの時間はとうに過ぎ、会場は閑散としていた。午後2時から一般開場され、運よくチケットを購入できた人々は、それから夜8時まで試飲を心行くまで楽しむことができるのだ。地上に出ると入り口脇に誰かの張り紙があった。「求むチケット 日曜用 電話xxxx-xxxxxxx」これはやはり、会場を何とかしたほうがよいのではと思いつつ、遅い昼食を摂りに街中へ向かった。
2011/01/22
コメント(2)
-

香草園の眺め (2)
試飲の様子。手前に並んでいるのがDr.ヘアマンのボトル。Dr.ヘアマンに続いてカール・エルベスの印象。Weingut Karl Erbes1. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese trocken2. 2009 Erdener Treppchen Riesling Sp?tlese halbtrocken3. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese feinherb4. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Kabinett5. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese (11ヶ月澱の上で熟成)6. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese7. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese ?Kranklay“8. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese9. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese*10. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese** ?Kranklay“11. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Auslese***12. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Eiswein13. 2009 Erdener Treppchen Riesling Beerenausleseカール・エルベス醸造所もやはり辛口より甘口に魅力を感じ、とりわけアウスレーゼの星の数が増えるごとに凝縮感と緻密さが増していく様子には迫力があった。1.~3.は谷の時期なのか大人しく酸も控えめ。スパイシーなミネラルのアクセント、3.のファインヘルブにはほのかに桃の香り。4.のカビネットはDr.ヘアマンのそれよりも好印象。軽めでも熟したリンゴにほのかに蜂蜜のヒント、ミネラル感、良好なバランスで楽しめる。5.~7.のシュペートレーゼでは、澱の上で11ヶ月熟した5.は熟したリンゴにフェノール系の軽い苦味を伴う酸味。骨格がしっかりしているのは感じられたが、機会を改めて試飲したい。6.はみずみずしい熟したリンゴ、余韻もフルーティで快適な飲み心地。7.は香草のニュアンスが加わりほっそりとして上品。エルデナー・プレラートに近いすり鉢状になった急斜面の上部に位置するこの区画「クランクライ」Kranklayは1971年にヴュルツガルテンに併合されるまで単一畑だった。Krankと言っても病気ではなく、大きな、偉大な(Grande)に由来するという(出典はこちら)。いずれにしても、ヴュルツガルテンとは一味違う個性とポテンシャルを感じる区画。8.~11.のアウスレーゼは、星が増えるごとに天国への階段を上るような感じで素晴らしくなっていく。8.のアウスレーゼにも軽い苦味を感じたが、繊細で一体感のある甘みと酸味は綺麗。9.のアウスレーゼ*はほっそりとしつつ凝縮した甘み、10.のアウスレーゼ**クランクライはさらにシーファーのミネラル感が明瞭になり、11.のアウスレーゼ***は軽くクリーミィな舌触りに凝縮感のある甘み、白桃、アプリコットのヒント、非常に長い余韻。そして12.のアイスヴァインは独特のアイスキャンディーのアロマ、舌触りは軽くクリーミィ、白桃のヒント、長い余韻。13.のベーレンアウスレーゼは見事な凝縮感で、力強く繊細な甘み、非常に長い余韻。○まとめ両醸造所とも辛口からファインヘルブにかけてはいまひとつ、と感じたが、とりわけシュペートレーゼ以上の甘口は文句無く素晴らしい。アロマティックなDr.ヘアマンと澄んだフルーツ感のカール・エルベスと、近隣の畑でも醸造家でワインの性格も違うところも面白い。しかしいずれも、モーゼル中流の土壌と気候でしか出来ない、繊細さと凝縮感、軽さと濃厚さなど、多様で美しいリースリング甘口の魅力があった。試飲はこの後、場所を移してさらに古酒へと続いた。
2011/01/17
コメント(0)
-

香草園の眺め (1)
Dr.ヘアマンでの試飲の後、とある民家へ。もともとホテルだった建物を、エアデン村出身の弁護士夫妻が2,3年前に購入・改装した、昔はホテルだった邸宅だ。窓の正面に見えるのはユルツィガー・ヴュルツガルテン。テーブルの上にはDr.ヘアマン醸造所とカール・エルベス醸造所の2009年産が、それぞれ一列に並ぶ。ユルツィヒとエアデンに畑を所有するDr.ヘアマンとカールエルベスの両醸造所の設立は、実は1967年と期を同じくしている。そしてほぼ10年前にクリスチャン・ヘアマンとシュテファン・エルベスがそれぞれ父から醸造所を継いだところも同じなら、甘口が生産の大半を占め、北米を中心とする輸出に力を入れている点でも共通する。いわば兄弟のような醸造所だ。まず、Dr.ヘアマン醸造所から。Weingut Dr. Hermann1. 2009 Erdener Treppchen Riesling QbA trocken2. 2009 Erdener Treppchen Riesling QbA trocken Goldkapsel3. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese feinherb4. 2009 Dr. Hermann ?H“ Riesling QbA5. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Kabinett6. 2009 Erdener Treppchen Riesling Kabinett7. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Sp?tlese8. 2009 Erdener Treppchen Riesling Sp?tlese9. 2009 Erdener Treppchen Riesling Sp?tlese ?Hitzlay“ Goldkapsel10. 2009 Erdener Pr?lat Riesling Sp?tlese Goldkapsel11. 2009 Erdener Treppchen Riesling Auslese12. 2009 Erdener Pr?lat Riesling Auslese Goldkapsel13. 2009 Erdener Herrenberg Riesling Eiswein14. 2009 Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese15. 2009 ?rziger W?rzgarten Riesling Trockenbeerenauslese16. 2003 Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese正直なところ、辛口にはピンとこなかった。丁度谷の時期に入っているのかもしれない。2.のQbA辛口GKは香水のような白桃の甘い香りが若干鼻につく。好みにもよるかもしれないが。4.の“H“は好印象。フローラルで白桃系の甘い香りがする他のワインとややスタイルが異なり、熟した柑橘のヒント、まとまり感のあるボディで軽くクリーミィ、ファインヘルブぎみの甘みはほどほどで、アフタがやや短いとはいえ、一本5Euro前後でコストパフォーマンスは非常に良好。5., 6.のカビネットはとても軽く繊細。クリスチャンの父ルーディは「カビネット飲みは1本空けて、続けて2本目が開けたくなるようなワインを求めている」と言うが、確かにそんな感じ。7.のシュペートレーゼから次第に本領発揮、アウスレーゼにかけて甘み、香りだけでなく力強さを増す。9.のヒッツライはエアデナー・トレプヒェンの中でもプレラートに隣接した区画(参考までに、プレラートとその近隣の葡萄畑の歴史から地質などに関する詳細な情報を掲載したMosel Fine Winesのニュースレターはこちら)。温暖な局所気候を感じさせる熟したリンゴ、アプリコット、パイナップルのヒント、香りい高く非常に長い余韻。10.のプレラートのシュペートレーゼGKは熟したフルーツの甘みだけでなく凝縮感を増し、アプリコットに蜂蜜のヒント、余韻も長い。11.のトレプヒェンのアウスレーゼはほっそりとしてエレガント、完熟したグレープフルーツのヒント、ミネラル感に富む。12.のプレラートのアウスレーゼGKは緻密な香りに熟したアプリコット、南国のフルーツに気品が漂う。凝縮して非常に長い余韻。13.のアイスヴァインは蜂蜜入りミルクティーのような香味、アイスヴァインとしてはどちらかといえば優しい味。14.のトレプヒェンTBAは乾燥した葡萄のヒント、濃縮した甘みにアプリコット、蜂蜜、カラメルのヒント、非常に長い余韻。15.も乾燥した葡萄のヒントはあるが、こちらは非常に濃厚で柔らかな舌触りが印象的。16.は2003年産。グラスに注いだ瞬間から「なんだこれは!」と驚く。褐色のトロリとした液体はほとんどメープルシロップ。乾煎りしたアーモンドのヒント、クリーミィで果てしなく濃厚。これはワインを越えて何か別の、異次元の飲み物のような気さえした。(つづく)
2011/01/17
コメント(0)
-

甘口は不幸中の幸い
2010年は最悪の生産年 ----リリース前からそんな評もある生産年だが、それはやがて良い方向で裏切られることになるかもしれない。少なくとも甘口に関しては。土曜日に訪れたモーゼル中流のエルデン村にあるDr.ヘアマン醸造所。我々を出迎えた猫のミーツ。人懐こくセラーまでついてきて、とある樽の上に飛び乗ると毛を逆立てて牙をむいた…なんてことはなかったが、ツェラー・シュヴァルツカッツの伝説を思い出した。二代目主人で醸造責任者のクリスチャン・ヘアマンがガラス管でステンレスタンクからワインを吸出し、我々のグラスに注いだ。ユルツィガー・ヴュルツガルテンのリースリング・カビネットから野生酵母の香りが立ち上った。研磨される前の原石のようだ。収穫時の酸度は13.5g/Liter以上。リンゴ酸のみを減らす単純除酸を行い、発酵で自然に2g/Literほど減少し、9g/Liter前後に落ち着いた。熟したグレープフルーツの甘みに酸味は溶け込んでいて、舌の上に心地よい重みがあった。シュペートレーゼ、アウスレーゼ、ベーレンアウスレーゼと、クリスチャンは次々に注いでまわった。いずれも酸は出しゃばることなく甘みを下から支えるようにして全体に調和し、澄んだフルーツ感にリンゴやアプリコットの魅力的なアロマに満ちて、シーファーのミネラル感が深みをそえていた。最悪の生産年という評価は少なくとも、この醸造所の甘口にはあてはまらない。他の醸造所でも3月以降のリリースで驚かされるワインも多いのではないか。我々は期待に満たされつつセラーを後にした。しかし、辛口に力を入れる生産者には、確かに難しい生産年だったという。適切に除酸を行った醸造所はともかく、自然のもたらしたものを、出来る限り損なわずにワインに込めたいと思う生産者の中には除酸を拒んだところもあり、その結果は意見の分かれるところらしいが、リリースされるまでは確かなことはわからない。その後、クリストッフェルJr.醸造所の2010ユルツィガー・ヴュルツガルテン・アウスレーゼ三ツ星を試飲した。しっかりした骨格と長い余韻に綺麗な白桃とカラントの甘みが広がり、125エクスレに完熟した収穫の、高い酸度が恩恵となって現れていた。それは2010年のモーゼル中流の甘口の仕上がりに、一層の期待を抱かせるものだった。
2011/01/13
コメント(4)
-

モーゼルの氾濫
土曜のモーゼルの氾濫、ユルツィヒの様子。近くまで行くことが出来なかったのだが、河岸のプロムナードが水没している。この様子だとメンヒホフ醸造所のセラーも水没しているはずだ。雪解けによる増水のピークは土曜夜で峠を越し、日曜は少しずつ水位が下がってきた。ライル村の河岸にあるステッフェンス・ケス醸造所のハラルド・ステッフェンスもほっと胸をなでおろしたそうだ。ステッフェンスはブログに1月6日から9日までの様子を、ブログに克明に記録している。http://www.steffens-kess.de/cms/blog/1月6日:樽を土台にベルトで固定し、空の樽には水を詰め、背の高い樽と天井の間に葡萄畑の杭を切って挟みこんで樽が動かないように固定。機材など小物を高い位置に移動。その夜トリーアの水位が8時から9時までの一時間で39cm上昇、水深6mを超える。1月7日:ボトルが水没しないよう、一番下のコンテナを空にして、その上にボトルの入ったコンテナを積み上げる。貨物用エレベーターを最上部で停止、電源から切り離す。移動作業後コンテナと樽の内容と位置をリストアップ。やがてセラーにモーゼルの川水が流入。近郊のツェルは堤防を越えて入りこんだ水で町中が水びたしとなる。セラーへの汚水の逆流を防ぐために下水管を閉じ、水に腰まで浸かっての作業にそなえ長靴を用意。夜、セラー内の水位が1mに達する。1月8日:水位の上昇が続く。セラーの裸電球を破裂の恐れが無いエネルギー節約ランプに取り替える。…と、事態が深刻になりつつも、ステッフェンはタイヤのチューブと板切れで簡易ボートを作り、セラー案内ビデオを作製して公開。よくやるなぁ…。1月9日:水位が下がりはじめる。今回の氾濫は2001年と大体同じで、1994年1月7日、1998年11月1日、1993年1月11日と1997年2月28日よりも水位は低い、と、セラーの壁に記してある記録を示す。過去最悪の1993年12月の氾濫は、彼のブログの写真から25cm上あたりまで達したそうだ。モーゼルの河岸に醸造所がある以上、氾濫があればそれとむきあうのは当然、という。ある意味ドイツ人らしいおおらかさというか、自然とつきあうのが仕事の醸造家らしい姿勢かもしれない。おまけ。日曜夕方のモーゼル河岸。水没したバス停のまわりで水鳥がのんびり泳ぎまわっていた。
2011/01/10
コメント(4)
-

ハレルヤとベートーベン
凍りついた大学の池。この寒さで鴨もどこかに行ってしまって、とても静か。今日は気温が若干上昇し、雪が雨に変わった。融けかかった雪でぬかるんだ散歩道は、歩くにも苦労する。週末、融雪水でモーゼル川沿いは洪水になりそうだ。さて、昨年末から紹介しようと思っていたYou Tubeのビデオ。どこかのショッピングセンターで、突然始まるハレルヤの合唱。なんだか心温まる。http://www.youtube.com/watch?v=ch8DfuGmGxcもうひとつ、最近よく聞くのがベートーベンの弦楽四重奏15番第三楽章。「病より癒えたる者の聖なる感謝の歌」と題されているが、ほんと癒されます。YouTubeにはいくつも動画があるけど、イメージとしていいな、と思ったのがこれ。演奏はかなり端折っているが。http://www.youtube.com/watch?v=Q19oyaCdhroご参考までに。
2011/01/07
コメント(0)
-
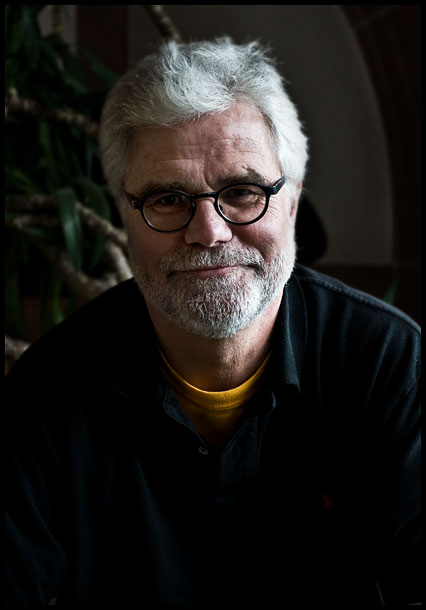
最果ての醸造所 Dr. ジーメンス /ザール (1)
世界の果てと言うのが大げさなら、その醸造所はザールの果てにあった。モーゼルにザールが流れ込むコンツの町から、カンツェム、ヴィルティンゲン、オックフェンと、蛇行する川沿いの渓谷の斜面に広がる葡萄畑の中を走り、小観光都市ザールブルクを過ぎたあたりで風景は急に物寂しさを帯びてくる。鬱蒼とした森林の中を、果たして流れているのかどうか分からないほどゆったりとして、鏡のように穏やかな水面のザール川の様子は、人里はなれた山奥の気配を漂わせている。やがてゼーリヒの村に入ると、そこはせわしない現代から隔絶され、数十年前から時の歩みが止まったような異世界である。細く曲がりくねった街道沿いに無秩序に立ち並ぶ、割れた窓ガラスが住む人のいないことを物語る農家の脇を、のどかな響きを立ててトラクターがゆっくりと走る。人気の無い広場に立つと、どこからから見られているような気がして不安になる。ゼーリヒの村を早足に通り過ぎ、民家が途切れて醸造所の住所が間違っているのではないか思い始めた頃、一本道の一番奥まった先にDr.ジーメンス醸造所がある。かつてのヘレンベルク醸造所で、2005年末に元ジャーナリストのヨッヘン・ジーメンスが、元オーナーのベルト・ジモンの引退を期に、醸造所とその周囲に広がる12haあまりの葡萄畑を購入したのだ。Dr.ジーメンス醸造所のオーナー、ヨッヘン・ジーメンス。ジャーナリストから醸造家へ。57歳で文字通り全く畑違いの業種への転身は、思い切った決断であったに違いない。25年あまり全国紙フランクフルター・ルントシャウに勤務し、2002年まで編集長であったが、経営陣との意見の相違から新聞社を去り、ワイン専門誌「アレス・ユーバー・ヴァイン」の編集長に就任。しかし雑誌は折からの活字不況で2004年にライバル誌「ヴィヌム」に吸収合併され、発展的解消を遂げた。ザールの醸造所を購入しないかという話が持ち込まれたのは、そんな時だった。醸造家になるのではなく、フリーのジャーナリストとして独立するほうが簡単だったのではないか? そう問うとジーメンスは肩をすくめた。「ワイン雑誌の編集に携わるうちに、いつしか実際にワイン造りとはどんなものなのか、醸造家の立場に立ってみたくなったんだよ」と言う。栄養コンサルタントとして活躍するカレン夫人の収入と、醸造所が購入出来るほどの資産があるならば、早期引退は考えなかったのだろうか。「私には二人の息子達がいる。まだ学校に通っているんだ。彼らに一日中何もせずにのらくらしている姿を見せるわけにはいかないよ」と、とんでもない、と言うように軽く口調を荒げた。醸造所を背負って立ち、デスクから離れて葡萄畑で働く姿を息子達に見せてやりたい。締め切りに追われ続けていたジャーナリストの生活から、いつも家族と一緒にいられる生活を、はからずも迎えた転機に選んだのかもしれない。それは、残りの人生をどう過ごすのかという、生き方の選択でもあったはずだ。(つづく)
2011/01/04
コメント(4)
-

最果ての醸造所 Dr. ジーメンス /ザール (2)
仕事場のヨッヘン・ジーメンス。窓から眼下に葡萄畑とザール川が見える。だが、年末に家族とゼーリヒに引越して来て気がついたのは、予想以上の設備の老朽化だった。電気配線に絶縁材料として使われていた古紙を広げてみたら戦時中の新聞だったり、屋根からは雨漏りがするし、窓からは氷点下の寒気が容赦なく入り込み、オーブンのスイッチを入れたとたんにブレーカーが飛んだ。醸造施設も同様で、剥き出しの電線にぶら下がる裸電球の弱々しい光の下に並ぶ合成樹脂のタンクは使い物にならず、解体して廃棄する他なかった。畑も合成肥料のやりすぎで葡萄樹は弱り、購入したトラクターは葡萄の畝の幅が狭すぎて畑に入れることが出来なかったという。さらに、前オーナーは醸造したワインの在庫を全て持っていってしまったから、売ることの出来るワインすらなかった。何から何まで使えるもののない、ゼロからの出発であった。2006年の秋。コンサルタントの指導を仰ぎつつ手探りで始めた農作業の成果が実を結び、期待に胸をふくらませながらの収穫を目前に控えた9月25日から、大雨が降った。その後、夏が戻ったかのような暑さが続いた。水分を吸い上げ、はちきれんばかりに膨らんだ葡萄の房は、瞬く間に繁殖した黴やバクテリアにやられ、灰色に黒ずんでミイラのようにしぼみ、わずか数日で約7割の葡萄が使い物にならなくなった。「あれはまったく、手の施しようがなかった。あらかたの葡萄が『ボン!』と一度に蒸発したような感じだったなぁ」と、ジーメンスは苦い思い出を噛み締めるように笑った。「あの醸造所には手を出さない方がいい。不動産だけでなく、設備にも多額の金をつぎこまなきゃならんから絶対割に合わない。悪いことは言わんから、やめときなさい」と忠告する、知り合いの醸造家に耳を貸さなかったことが、いまさら悔やまれた。「見通しが甘すぎたのよ。これからどうなるのかしらね」と夫人にも嘆かれたが、痛い目にあってみないと、本当のことは分からない。収穫をセラーに持ち込むまでは、何があってもおかしくない。それがワイン造りなのだと、新米オーナーは身をもって悟ったという。(つづく)
2011/01/04
コメント(2)
-

最果ての醸造所 Dr. ジーメンス /ザール (3)
醸造設備。選果台と破砕装置。モーゼルで手作業の収穫した上、さらに圧搾前に選果作業をする醸造所はあまりない。ヨッヘン・ジーメンスが醸造所を購入してから5年の歳月が過ぎた。2006年の仕打ちを償うようにして、自然は2007, 2008, 2009と3年続けて良年をもたらした。その間、醸造設備も約160万ユーロ(約2億800万円)をかけて刷新された。醸造棟に一歩足を踏み入れると、目の高さの壁に空調装置がでんと据えてあり、地上にあるホールから既に温度管理が行き届いていることを示している。一角には収穫を冷却する冷蔵室もある。醸造所のあるザール川沿いに広がる13haあまりの急斜面から持ち込まれた収穫は、ここでまず手作業で選果され、果梗を取り除き、冷却しながらの圧搾が可能な最新式マシンで圧搾する。得られた果汁はポンプを用いることなく、重力を利用して地下一階のタンクに流れ込み、清澄後に再び重力を利用して地下二階に流れ込む。礼拝堂の様なアーチ型をした天井のセラーは年間を通じて約10℃に保たれ、容量1000~2400Literの木樽とステンレスタンクが通路を挟んで向かいあわせに整列し、木樽で発酵後ステンレスンクで熟成したり、あるいはステンレスタンクで発酵後木樽で熟成と、目指すワインのスタイルに応じて使い分けているという。発酵は野生酵母で行い、畑の個性を生かす。おそらく先代オーナーがうらやまずにはおれないほど完璧に整った醸造施設に、ケッセルシュタット醸造所などで働いていた経験豊かなケラーマイスター、フリッツ・レンツを醸造責任者に据えた。醸造設備は完璧だ。おそらくファン・フォルクセン醸造所にもひけをとらないだろう。これで高品質なワインが出来なかったらどうかしている…。醸造所のセラー、地下2階。(つづく)
2011/01/04
コメント(0)
-

最果ての醸造所 Dr. ジーメンス /ザール (4)
● 試飲単独所有するゼーリガー・ヘレンベルクとゼーリガー・ヴュルツベルクの葡萄畑がある斜面の標高差は200m。ザール川の流れに沿って斜面はゆるやかに弧を描き、斜面の上下や区画によって熟し具合に明らかな差があるという。品種はリースリング65%、ピノ・ブラン(ヴァイスブルグンダー)25%、オクセロワ5%、シュペートブルグンダーが5%。平均収穫量は白が50~60hl/ha、赤が40-50hl/ha。2009 オクセロワAuxerroisは仄かにマスカット系の香りがする、軽く綺麗な夏向きの辛口、シトラスのヒント、ややアッサリしているが、無駄がなくスッキリとして、そこが魅力的。アフタに軽いミネラル感が残る。2009 ピノ・ブランPinot Blancは直線的なスタイル、透明感のある果実味にシトラスのヒント、ほのかな甘みがフルーティなアロマを引き立てている。2009スキヴァロScivaroはリースリングのやや辛口(残糖10g/Liter)。スキヴァロScivaroは古高ドイツ語でシーファーを意味するという。やや甘みが目立ち、アロマティックで芳醇な果実味、繊細な香草、リンゴ、アプリコット、白桃のヒント、ミネラル感もしっかり、余韻の長さは普通。2009 ヘレンベルクHerrenberg Riesling Sp?tlese Tはぎっしり詰まったミネラルを包み込む果実味に熟したグレープフルーツのヒント、力強いが同時に軽やかで、余韻に塩気を伴うミネラル感が残る。Tは辛口だが、ワイン法の基準である9g/Literを若干超えることもあるので、あえてTrockenとは記さずTとしている。2009 ヴュルツベルクW?rzberg Riesling Sp?tlese T は深みのある果実味にしなやかなミネラル感、アプリコット、パイナップルのヒント。Herrenbergとの違いがはっきりとしている。2009 ヴュルツベルクW?rzberg Riesling Kabinett feinherbは軽やかで透明感のあるフルーツに熟したリンゴのヒント、クリーンで繊細。2009 ヴュルツベルクW?rzberg Ausleseはミント、タイム、にわとこの実などの香草入りボンボンのアロマ、クリーミィな舌触りの酒躯に白桃のコンポート、リンゴなどのヒント、長い余韻。白はいずれもザールらしい繊細な軽さを備えつつ、しっかりとしたミネラル感にフルーティなアロマが香り立つ。一方、赤の2009 ピノ・ノワールPinot Noirは、しっかりとして充実感のあるラズベリーの果実味、ほのかにヴァニラが漂い、冷涼なザール産とは思えないほどの見事な仕上がりに驚いた。「高品質なワインを造ること。それ以外に成功する道はない」とヨッヘン・ジーメンスは言い切る。試飲したワインは彼のいわば経営哲学を裏付けていたが、これだけの高品質でありながらほとんど無名の状態に留まっているのは不思議に思われた。「天候に恵まれなかった2006年はごく少量しか出来なかったし、2007年産のリリースは2008年だから、市場に参入してからまだ2年あまりしか経っていない。これからだよ」と言う。ジーメンスは1948年生まれの62歳。醸造家としての彼の人生はしかし、まだ始まったばかりだ。*************************醸造所を訪問した9月半ばから2週間あまりしたころ、ザール川沿いを走る列車の車窓からDr.ジーメンス醸造所の畑を見る機会があった。ブルグンダー系品種の収穫を始めたのだろうか、収穫作業者が5, 6人、明るい日差しに照らされた斜面で働いていた。 「ここはザールの一番奥にある醸造所だ。私の畑から先に葡萄畑はない」とジーメンスが言っていたことを思い出した。「でも、見方を変えれば、ザール最初の醸造所でもある。なぜなら、私の畑から下流にむけてザールの葡萄畑は始まるからだ。『ダス・エアステ・ヴァイングート・アン・デア・ザールDas erste Weingut an der Saar』なんだ!」 ザールの果てにある醸造所は、そこが始まりでもあるという逆転の発想が、私は気に入った。終わりとは同時に始まりなのだ…。そう考えることが、勇気と希望を与えてくれる気がした。 Dr.ジーメンス醸造所Weingut Dr. SiemensR?merstr. 6354455 Serrigwww.dr-siemens.de
2011/01/04
コメント(0)
-

シャンパーニュとマロンクリーム
大晦日の風景。午前零時、近所で鳴り響く新年を祝う花火の炸裂音と共に栓を飛ばしたのは、ジャカールのブリュット・モザイク NV。ほのかな熟成香と繊細な酸味、品の良い軽め酒躯と穏やかな泡の刺激。飲み心地よく飲み飽きず、二人で軽く一本空いてしまった。「Frohes neues Jahr!」近所のアパートのベランダから叫ぶ声に、こちらもグラスを挙げて応えた。「Frohes neues Jahr!」今年も縁起物のマルチパンで出来た豚のお菓子を買っておいた。どうぞよい年でありますようにと、豚の目を見て願う。先日メッツで買った栗のペースト。栗餡みたいな味がする。正月にと実家が送ってくれた餅につけて食べてみた。ぜんざいみたいな感じでわりとよくあう。本来はお菓子のモンブランの素材として、あるいはパンに塗ったり、鶏やソーセージの詰め物、肉料理のつけあわせに使うらしい。くどくない甘みだが、リースリングにあわせると残糖がマスキングされ、酸とミネラルが目立つ。甘みが気になるワインを辛口ぎみに補正するのにいいかもしれない。
2011/01/01
コメント(2)
全17件 (17件中 1-17件目)
1










