カテゴリ: 宮城
宮城郡利府町は、いまやイオンの巨大商業施設の町のイメージだが、住みよい地だったのだろう縄文の遺跡、古代の多賀城の経営や合戦を交えた中世の城郭、里山の神社たち、下っては芭蕉も詠んだ近世の情景、などなど、往古のゆたかな歴史をたたえる里だ。
■出典 「時をこえて今に残る 利府町の埋蔵文化財 ~地中からのメッセージ~」利府町教育委員会
1 縄文時代の遺跡
■ 六田遺跡 (ろくだ。総合運動公園の北、沢乙温泉の手前あたり)
砂押川、榎川による浸食で形成された丘陵平坦部の集落跡。県総合運動公園用地造成工事に伴う調査の結果、縄文時代前期の竪穴住居跡12棟など多数の遺構が見つかった。住居跡や隣接する沢を中心として、縄文土器や石器が多数出土。土器の年代から縄文時代前期(約8000年前)の集落跡と判明。生活に伴う石器(石鏃、石錐、石箆(へら)、石匙、石斧など)のほか、玦状耳飾も出土。
■ 浜田洞窟遺跡
海水の浸食による天然の洞窟を利用した遺跡。東北大学の発掘調査が行われており、縄文時代晩期と弥生時代の遺物が出土している。また、付近から貝塚も見つかっている。
2 古墳時代の遺跡
郷楽遺跡 (ごうらく)
三陸自動車道建設工事に伴う発掘調査で丘陵頂部に4基の円墳が見つかった。大きさは12から27mで、6から7世紀の古墳群。一号墳の周溝からは大量の埴輪(朝顔形埴輪、円筒埴輪)が出土。朝顔形は県内に出土例が少なく、保存状態も良好。その他、須恵器や装身具(切子玉、棗(なつめ)玉、管玉)等も出土。
■ 川袋古墳群
3基の円墳がみつかっている。一号墳の横穴式石室の形態や出土遺物の年代から、7世紀代に作られた古墳群。石室内部から、直刀、馬具、刀子、帯金具などの鉄製品がまとまって出土した例は県内でも少なく、保存状態も良好。
■ 八幡崎B遺跡
古墳時代の溝跡がみつかり、堆積土からは赤彩された土師器(高坏、壺)や須恵器(𤭯(はそう))などが出土。全容は把握できていないが、周溝墓に伴う溝跡の可能性。
■ 菅谷横穴墓群
7世紀の初めころから作られ始めた墓群で、横穴の総数は100以上といわれる。東北学院大学などによる学術的な発掘調査が行われ、39基がみつかった。土器(土師器、須恵器)、装身具(勾玉、管玉)、鉄製品(直刀、刀子)等が出土。土師器、須恵器には、東海地方の特徴を有するものが含まれ、交流があったと思われる。
■【コラム】 菅谷不動尊
横穴墓群が位置する丘陵の麓。平安時代、藤原景昌が蝦夷の亡霊を鎮めるために紀州高野山から分霊したのが始まりといわれる。火焔を背負った3mをこえる不動尊像が祀られる。社の裏に湧き出る清水は眼病に効くといわれる。
3 奈良・平安時代の遺跡
春日窯跡群
東西約2.7km、南北2.1kmの広大な範囲に及ぶ。硯沢窯跡、大沢窯跡、春日大沢瓦(ママ)窯跡、春日大沢B窯跡、春日大沢C窯跡、大貝窯跡、中倉窯跡などによって構成されていることがわかっている。
春日窯跡群の存在は古くから知られ、天保13年(1842)から安政4年(1857)に書かれた『仙台金石志巻之二、名蹟一之下、壺碑下』に初見。
これまで三陸自動車道建設工事に伴う発掘調査の結果、多賀城創建期から多賀城Ⅳ期にかけての瓦、須恵器、炭窯跡が多数見つかり、古代の一大生産拠点であったことが明らかに。
■ 硯沢窯跡
春日窯跡群の西端に位置。これまで三陸自動車道建設工事、春日PA建設工事に伴う発掘調査で、奈良時代(8世紀前半)の須恵器窯跡・炭窯跡や平安時代(8世紀末~9世紀)の瓦窯跡・炭窯跡など多数の生産に関わる遺構がみつかっている。
須恵器の中には「宮城郡」と刻書された須恵器があり、形態や製作技法から奈良時代(8世紀前半)のものであり、そのことから既に宮城郡が設置されていたことがわかった。
硯沢窯跡の西端に、県内では数例しか確認されていない平安時代の火葬墓が1基みつかった。骨壺には頸の部分が意図的に割られた須恵器長頸壺(ちょうけいこ)が利用されていた。蓋は須恵器坏が用いられ、倒位で埋納されていた。
炭窯跡も数多く、その中の2基は「横口付木炭窯」と呼ばれる特殊な構造の窯で、国内最北の発見。通常の登窯(のぼりがま)式の炭窯は斜面に対して垂直に構築されるが、横口付木炭窯は斜面に対し平行に構築され、複数の横口が設けられるのが特徴。県内では山元町で同様の炭窯跡があるが発見例が少なく貴重な調査成果。大量に生産された木炭は製鉄に用いされたと思われる。
■ 大貝窯跡
宅地や公共公益施設造成工事に伴い発掘調査。平安時代(8世紀~9世紀前半)の須恵器・瓦窯跡18基、炭窯跡10基、竪穴住居跡9棟など多数の生産に関わる遺構が見つかった。
瓦窯跡の構造は半地下式登窯で底面には転用された丸瓦が階段状に並べられ、焼台が形成されていた。
多賀城政庁に係る窯跡は大沢窯跡、硯沢窯跡でも確認されていたが、大貝窯跡の調査により改めて春日・赤沼地区が多賀城政庁と強い係りをもつ重要な地域であったことがわかっている。
窯跡に隣接して竪穴住居跡も見つかっており、位置関係から作業場の役割を担っていたと思われる。住居跡内の竈(かまど)には構築材として瓦が用いられており、瓦窯跡工人(こうじん)と係わりのある住居跡と考えられる。
■ 郷楽遺跡
標高60mの丘陵頂部、陸奥国府多賀城から北に2kmの地点。三陸自動車道建設などに伴い、これまで6次にわたる発掘調査の結果、奈良から平安時代(8~10世紀)の竪穴住居跡、掘立柱(ほったてばしら)建物跡などが多数みつかり、土器など多数の遺物が出土。この時代は、郷楽遺跡の主体をなす遺構群が形成された時期で、竪穴住居や掘立柱建物が連続して築かれていたと考えられる。
奈良時代(8世紀中~後半)の竪穴住居跡の竈の暗渠排水施設から転用された瓦が出土。また、住居跡内からは多数の須恵器のほか、馬具、刀子、鉄鏃などの鉄製品も出土し、国府多賀城と深い係わりをもった人々の集落と考えられる。
竈の暗渠から多賀城政庁内編年Ⅱ期にあたる刻印のある丸瓦が出土した。この特徴をもつ瓦は仙台市小田原窯跡群や多賀城政庁以外に知られず、それらとの関連が考えられる。刻印には、「伊」「占」「田」などの種類がある。
■ 八幡崎B遺跡
舌状丘陵の頂部に位置。東北新幹線建設工事や県立利府支援学校建設工事などに伴う発掘調査の結果、飛鳥~奈良時代(7世紀後半~8世紀初頭)の竪穴住居跡や平安時代(9世紀)の竪穴住居跡などがみつかっている。各遺構からは、土師器、須恵器などの土器類が多量に出土。8世紀初頭の住居跡出土遺物には「関東系土師器」も含まれ、当時の人や物の流れをうかがうことができる貴重な史料である。
■ 館ヶ沢A遺跡 (利府城跡に裏から向かう道路の北側)
西から東に延びる沢の東奥端に位置し、丘陵麓の南斜面に位置。町営墓地用地造成工事に伴う発掘調査で、竪穴住居跡1軒や土坑、溝跡がみつかった。住居跡の床面からは多量の炭化物が出土したことから、火災にあったと思われる。住居跡内からは土師器のほか、鉄製品(鍬先)や砥石も出土した。遺物の年代や堆積土から、9世紀末から10世紀初頭頃の住居跡と思われる。
■ 熊野堂遺跡 (保健福祉センターの南、沢乙東団地あたり)
北側の南向き斜面に位置。土地区画整理事業に伴う発掘調査の結果、竪穴住居跡7棟、掘立柱建物跡30棟、埋設土器遺構などが見つかっている。これらからは土師器・須恵器などの土器類が出土。土器の年代から飛鳥~平安時代(7世紀後半~9世紀中頃)の集落跡と考えられている。
9世紀の埋設土器遺構から、土師器甕の中に灯明(とうみょう)痕跡がある土師器坏や皿が収められた状態で出土している。
■ 菅谷の穴薬師
道安寺の南にあり、菅谷横穴墓群の一つにあたる。1基の横穴墓が改良され、横穴壁面に刻まれた「磨崖仏」(まがいぶつ)である。
岩切東光寺の磨崖仏(宵のお薬師)、菅谷の「夜中のお薬師」、七ヶ浜町湊の磨崖仏(暁のお薬師)が「三薬師」と数えられ、いずれも9世紀に慈覚大師円仁によって一夜のうちに造られたと伝えられる。
現在は前面にお堂が設けられ安置されている。
4 鎌倉~江戸時代の遺跡
■ 伊沢家景の墓
伊沢家景は平安時代末から鎌倉時代にかけての御家人。文治3年(1187)、源頼朝の家臣であった北条時政に文筆の能力を認められ推挙され、戦場に出る武士ではなく文筆に携わる吏僚として頼朝に仕えた。
建久元年(1190)、前年の奥州合戦の後の混乱に乗じた大河兼任の乱が鎮圧された後、源頼朝によって初代「陸奥国留守職(るすしき)」に任命され、多賀国府に国衙在庁の長官として赴任してきた。『留守旧記』によれば、この時家景に随行してきたのは、宮城・村岡・芳賀・佐藤・南宮・笠上氏などであるといわれる。
その後、家景の子家元以降も代々陸奥国留守職を世襲したため、役職名から留守氏を名乗るようになった。
墓碑は長い年月の間、土中に没していたと言われたが、文政2年(1819)、倒れていた石が墓碑であったことが判明し、当時の水沢領主留守村福(むらやす)が墓石を建て直したと伝えられる。
■ 板碑 (いたび)
鎌倉時代から江戸時代に盛んにおこなわれた死者の追善供養のために建立された平たい石の卒塔婆をさす。室町時代以降になると民間信仰と習合し、多人数が結集して、月待供養や庚申供養などの刻銘のある板碑が全国的に建立された。
鎌倉時代、利府町内には数多くの板碑が建立された。延慶の碑、菅谷の碑、染殿神社の板碑群など。
○ 菅谷の碑 (穴薬師の近く)
梵字:アン(無量寿如来)
造立:正応2年(1289)
高さ:1.5m、幅:0.75m
○ 延慶の碑 (県道利府街道沿い、神谷沢)
梵字:ア(大日如来)
造立:延慶3年(1310)
高さ:1.2m、幅:1.5m
■ 菅谷横穴墓群
13世紀になると、再利用されている。一部の横穴墓の中から10cmほどの扁平な河原石が大量に見つかった。その中の数点には細字漢字でお経が墨書きされた「写経石」が含まれていた。その1つには、「弘安六年庚未九月六日、摩謌摩耶経下巻」と書かれているものもあり、中世に修行信仰の場所として横穴群が再利用されたことがわかった。
■ 十三本塚
十三塚や十三本塚は、全国的に分布する民間信仰による塚であり、一般的に13基の塚で構成され、塚の直径は10m以下のものが大部分。作られた目的は、十三仏信仰に由来するといわれるが正確にはわかっていない。利府町には、十三本塚、十三塚の地名がそれぞれ残るが、現在では塚の一部が現存するのみである。
■ 大貝窯跡
大貝窯跡では中世の製鉄炉跡や鍛冶炉跡などの製鉄に関連する遺構が多数見つかっている。県内の製鉄関連遺跡の調査例は少なく、非常に重要な発見となった。
製鉄炉跡の周囲からは炭窯跡もみつかり、製鉄炉跡に伴うものと思われる。一部の窯の煙出施設において板碑が転用されていたことから、少なくとも板碑の普及する13世紀末以降の炭窯跡と考えられている。また、そのことから、製鉄炉跡も概ね13世紀末以降であると思われる。
■ 大沢窯跡
三陸自動車道建設工事に伴い発掘調査。その結果、江戸時代(17世紀中頃)の瓦捨て場が見つかっている。これは瓦窯跡に伴うもので、中からは、瑞巌寺で見つかった刻印瓦と同じ「太田市兵衛」の刻印のある瓦が見つかっている。瑞巌寺は伊達政宗によって17世紀中頃に再興されており、再興に係わる瓦を付近で焼いていたと考えられる。
大沢窯跡の近くには、瓦焼場という地名が現在も残り、昔から瓦の産地であることを想像させる。
■ 岩切城跡
仙台市岩切と利府町神谷沢にまたがる中世の山城。城跡は標高106mの高森山を中心に尾根を平らに削り、平場を造り出し、空堀、堀切などで構成されている。
岩切城は留守氏の居城といわれるが、構築年代は正確にはわからない。動乱の激しくなった南北朝時代の初めころに築かれたと推定される。正平6年(1351)には岩切城を舞台に激しい合戦が行われている。
岩切城は規模が非常に大きく、保存状態も良好なことから、東北地方の中世史を考える上で重要な遺跡として、国の史跡に指定されている。
■ 利府城跡
標高88mの自然地形を利用した山城。岩切城跡と同様に山を削り平場を造り、そこに施設を設けた守り重視の館跡。
利府城が築かれた時代は正確にはわかっていないが、留守氏の家来であった村岡氏が築いたと考えられている。
その後、戦国の時代を迎え留守氏内部に家督相続問題が起き、永禄12年(1569)留守氏の血筋を守る立場に立った村岡氏は、伊達政景(晴宗の三男、政宗の叔父)を養子に迎え、伊達氏勢力下にあって留守家安泰を図るべきとする伊達派と対立した。この時、村岡氏はこの城にたてこもり戦ったが敗れて滅亡したといわれている。
永禄13年(1570)に政景は岩切城から利府城に移り、地名を村岡から利府に改めたといわれる。また同時に、村岡城とよばれていた城名も利府城となった。留守政景は天正18年(1590)に、伊達政宗から黒川郡大谷に隠退を命ぜられるまでの約20年間本拠地とした。その間、政宗の右腕として活躍したことは有名である。

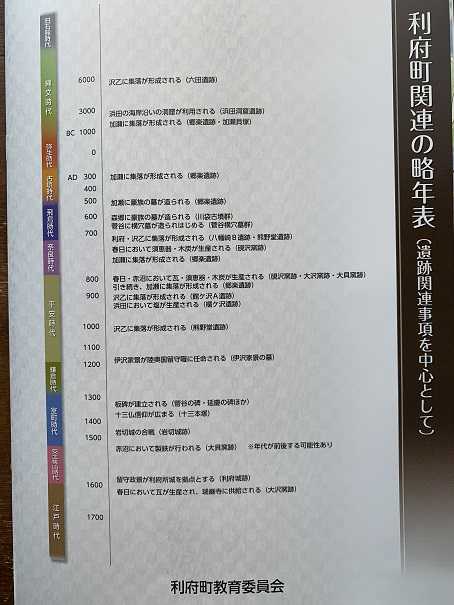
■出典 「時をこえて今に残る 利府町の埋蔵文化財 ~地中からのメッセージ~」利府町教育委員会
1 縄文時代の遺跡
■ 六田遺跡 (ろくだ。総合運動公園の北、沢乙温泉の手前あたり)
砂押川、榎川による浸食で形成された丘陵平坦部の集落跡。県総合運動公園用地造成工事に伴う調査の結果、縄文時代前期の竪穴住居跡12棟など多数の遺構が見つかった。住居跡や隣接する沢を中心として、縄文土器や石器が多数出土。土器の年代から縄文時代前期(約8000年前)の集落跡と判明。生活に伴う石器(石鏃、石錐、石箆(へら)、石匙、石斧など)のほか、玦状耳飾も出土。
■ 浜田洞窟遺跡
海水の浸食による天然の洞窟を利用した遺跡。東北大学の発掘調査が行われており、縄文時代晩期と弥生時代の遺物が出土している。また、付近から貝塚も見つかっている。
2 古墳時代の遺跡
郷楽遺跡 (ごうらく)
三陸自動車道建設工事に伴う発掘調査で丘陵頂部に4基の円墳が見つかった。大きさは12から27mで、6から7世紀の古墳群。一号墳の周溝からは大量の埴輪(朝顔形埴輪、円筒埴輪)が出土。朝顔形は県内に出土例が少なく、保存状態も良好。その他、須恵器や装身具(切子玉、棗(なつめ)玉、管玉)等も出土。
■ 川袋古墳群
3基の円墳がみつかっている。一号墳の横穴式石室の形態や出土遺物の年代から、7世紀代に作られた古墳群。石室内部から、直刀、馬具、刀子、帯金具などの鉄製品がまとまって出土した例は県内でも少なく、保存状態も良好。
■ 八幡崎B遺跡
古墳時代の溝跡がみつかり、堆積土からは赤彩された土師器(高坏、壺)や須恵器(𤭯(はそう))などが出土。全容は把握できていないが、周溝墓に伴う溝跡の可能性。
■ 菅谷横穴墓群
7世紀の初めころから作られ始めた墓群で、横穴の総数は100以上といわれる。東北学院大学などによる学術的な発掘調査が行われ、39基がみつかった。土器(土師器、須恵器)、装身具(勾玉、管玉)、鉄製品(直刀、刀子)等が出土。土師器、須恵器には、東海地方の特徴を有するものが含まれ、交流があったと思われる。
■【コラム】 菅谷不動尊
横穴墓群が位置する丘陵の麓。平安時代、藤原景昌が蝦夷の亡霊を鎮めるために紀州高野山から分霊したのが始まりといわれる。火焔を背負った3mをこえる不動尊像が祀られる。社の裏に湧き出る清水は眼病に効くといわれる。
3 奈良・平安時代の遺跡
春日窯跡群
東西約2.7km、南北2.1kmの広大な範囲に及ぶ。硯沢窯跡、大沢窯跡、春日大沢瓦(ママ)窯跡、春日大沢B窯跡、春日大沢C窯跡、大貝窯跡、中倉窯跡などによって構成されていることがわかっている。
春日窯跡群の存在は古くから知られ、天保13年(1842)から安政4年(1857)に書かれた『仙台金石志巻之二、名蹟一之下、壺碑下』に初見。
これまで三陸自動車道建設工事に伴う発掘調査の結果、多賀城創建期から多賀城Ⅳ期にかけての瓦、須恵器、炭窯跡が多数見つかり、古代の一大生産拠点であったことが明らかに。
■ 硯沢窯跡
春日窯跡群の西端に位置。これまで三陸自動車道建設工事、春日PA建設工事に伴う発掘調査で、奈良時代(8世紀前半)の須恵器窯跡・炭窯跡や平安時代(8世紀末~9世紀)の瓦窯跡・炭窯跡など多数の生産に関わる遺構がみつかっている。
須恵器の中には「宮城郡」と刻書された須恵器があり、形態や製作技法から奈良時代(8世紀前半)のものであり、そのことから既に宮城郡が設置されていたことがわかった。
硯沢窯跡の西端に、県内では数例しか確認されていない平安時代の火葬墓が1基みつかった。骨壺には頸の部分が意図的に割られた須恵器長頸壺(ちょうけいこ)が利用されていた。蓋は須恵器坏が用いられ、倒位で埋納されていた。
炭窯跡も数多く、その中の2基は「横口付木炭窯」と呼ばれる特殊な構造の窯で、国内最北の発見。通常の登窯(のぼりがま)式の炭窯は斜面に対して垂直に構築されるが、横口付木炭窯は斜面に対し平行に構築され、複数の横口が設けられるのが特徴。県内では山元町で同様の炭窯跡があるが発見例が少なく貴重な調査成果。大量に生産された木炭は製鉄に用いされたと思われる。
■ 大貝窯跡
宅地や公共公益施設造成工事に伴い発掘調査。平安時代(8世紀~9世紀前半)の須恵器・瓦窯跡18基、炭窯跡10基、竪穴住居跡9棟など多数の生産に関わる遺構が見つかった。
瓦窯跡の構造は半地下式登窯で底面には転用された丸瓦が階段状に並べられ、焼台が形成されていた。
多賀城政庁に係る窯跡は大沢窯跡、硯沢窯跡でも確認されていたが、大貝窯跡の調査により改めて春日・赤沼地区が多賀城政庁と強い係りをもつ重要な地域であったことがわかっている。
窯跡に隣接して竪穴住居跡も見つかっており、位置関係から作業場の役割を担っていたと思われる。住居跡内の竈(かまど)には構築材として瓦が用いられており、瓦窯跡工人(こうじん)と係わりのある住居跡と考えられる。
■ 郷楽遺跡
標高60mの丘陵頂部、陸奥国府多賀城から北に2kmの地点。三陸自動車道建設などに伴い、これまで6次にわたる発掘調査の結果、奈良から平安時代(8~10世紀)の竪穴住居跡、掘立柱(ほったてばしら)建物跡などが多数みつかり、土器など多数の遺物が出土。この時代は、郷楽遺跡の主体をなす遺構群が形成された時期で、竪穴住居や掘立柱建物が連続して築かれていたと考えられる。
奈良時代(8世紀中~後半)の竪穴住居跡の竈の暗渠排水施設から転用された瓦が出土。また、住居跡内からは多数の須恵器のほか、馬具、刀子、鉄鏃などの鉄製品も出土し、国府多賀城と深い係わりをもった人々の集落と考えられる。
竈の暗渠から多賀城政庁内編年Ⅱ期にあたる刻印のある丸瓦が出土した。この特徴をもつ瓦は仙台市小田原窯跡群や多賀城政庁以外に知られず、それらとの関連が考えられる。刻印には、「伊」「占」「田」などの種類がある。
■ 八幡崎B遺跡
舌状丘陵の頂部に位置。東北新幹線建設工事や県立利府支援学校建設工事などに伴う発掘調査の結果、飛鳥~奈良時代(7世紀後半~8世紀初頭)の竪穴住居跡や平安時代(9世紀)の竪穴住居跡などがみつかっている。各遺構からは、土師器、須恵器などの土器類が多量に出土。8世紀初頭の住居跡出土遺物には「関東系土師器」も含まれ、当時の人や物の流れをうかがうことができる貴重な史料である。
■ 館ヶ沢A遺跡 (利府城跡に裏から向かう道路の北側)
西から東に延びる沢の東奥端に位置し、丘陵麓の南斜面に位置。町営墓地用地造成工事に伴う発掘調査で、竪穴住居跡1軒や土坑、溝跡がみつかった。住居跡の床面からは多量の炭化物が出土したことから、火災にあったと思われる。住居跡内からは土師器のほか、鉄製品(鍬先)や砥石も出土した。遺物の年代や堆積土から、9世紀末から10世紀初頭頃の住居跡と思われる。
■ 熊野堂遺跡 (保健福祉センターの南、沢乙東団地あたり)
北側の南向き斜面に位置。土地区画整理事業に伴う発掘調査の結果、竪穴住居跡7棟、掘立柱建物跡30棟、埋設土器遺構などが見つかっている。これらからは土師器・須恵器などの土器類が出土。土器の年代から飛鳥~平安時代(7世紀後半~9世紀中頃)の集落跡と考えられている。
9世紀の埋設土器遺構から、土師器甕の中に灯明(とうみょう)痕跡がある土師器坏や皿が収められた状態で出土している。
■ 菅谷の穴薬師
道安寺の南にあり、菅谷横穴墓群の一つにあたる。1基の横穴墓が改良され、横穴壁面に刻まれた「磨崖仏」(まがいぶつ)である。
岩切東光寺の磨崖仏(宵のお薬師)、菅谷の「夜中のお薬師」、七ヶ浜町湊の磨崖仏(暁のお薬師)が「三薬師」と数えられ、いずれも9世紀に慈覚大師円仁によって一夜のうちに造られたと伝えられる。
現在は前面にお堂が設けられ安置されている。
4 鎌倉~江戸時代の遺跡
■ 伊沢家景の墓
伊沢家景は平安時代末から鎌倉時代にかけての御家人。文治3年(1187)、源頼朝の家臣であった北条時政に文筆の能力を認められ推挙され、戦場に出る武士ではなく文筆に携わる吏僚として頼朝に仕えた。
建久元年(1190)、前年の奥州合戦の後の混乱に乗じた大河兼任の乱が鎮圧された後、源頼朝によって初代「陸奥国留守職(るすしき)」に任命され、多賀国府に国衙在庁の長官として赴任してきた。『留守旧記』によれば、この時家景に随行してきたのは、宮城・村岡・芳賀・佐藤・南宮・笠上氏などであるといわれる。
その後、家景の子家元以降も代々陸奥国留守職を世襲したため、役職名から留守氏を名乗るようになった。
墓碑は長い年月の間、土中に没していたと言われたが、文政2年(1819)、倒れていた石が墓碑であったことが判明し、当時の水沢領主留守村福(むらやす)が墓石を建て直したと伝えられる。
■ 板碑 (いたび)
鎌倉時代から江戸時代に盛んにおこなわれた死者の追善供養のために建立された平たい石の卒塔婆をさす。室町時代以降になると民間信仰と習合し、多人数が結集して、月待供養や庚申供養などの刻銘のある板碑が全国的に建立された。
鎌倉時代、利府町内には数多くの板碑が建立された。延慶の碑、菅谷の碑、染殿神社の板碑群など。
○ 菅谷の碑 (穴薬師の近く)
梵字:アン(無量寿如来)
造立:正応2年(1289)
高さ:1.5m、幅:0.75m
○ 延慶の碑 (県道利府街道沿い、神谷沢)
梵字:ア(大日如来)
造立:延慶3年(1310)
高さ:1.2m、幅:1.5m
■ 菅谷横穴墓群
13世紀になると、再利用されている。一部の横穴墓の中から10cmほどの扁平な河原石が大量に見つかった。その中の数点には細字漢字でお経が墨書きされた「写経石」が含まれていた。その1つには、「弘安六年庚未九月六日、摩謌摩耶経下巻」と書かれているものもあり、中世に修行信仰の場所として横穴群が再利用されたことがわかった。
■ 十三本塚
十三塚や十三本塚は、全国的に分布する民間信仰による塚であり、一般的に13基の塚で構成され、塚の直径は10m以下のものが大部分。作られた目的は、十三仏信仰に由来するといわれるが正確にはわかっていない。利府町には、十三本塚、十三塚の地名がそれぞれ残るが、現在では塚の一部が現存するのみである。
■ 大貝窯跡
大貝窯跡では中世の製鉄炉跡や鍛冶炉跡などの製鉄に関連する遺構が多数見つかっている。県内の製鉄関連遺跡の調査例は少なく、非常に重要な発見となった。
製鉄炉跡の周囲からは炭窯跡もみつかり、製鉄炉跡に伴うものと思われる。一部の窯の煙出施設において板碑が転用されていたことから、少なくとも板碑の普及する13世紀末以降の炭窯跡と考えられている。また、そのことから、製鉄炉跡も概ね13世紀末以降であると思われる。
■ 大沢窯跡
三陸自動車道建設工事に伴い発掘調査。その結果、江戸時代(17世紀中頃)の瓦捨て場が見つかっている。これは瓦窯跡に伴うもので、中からは、瑞巌寺で見つかった刻印瓦と同じ「太田市兵衛」の刻印のある瓦が見つかっている。瑞巌寺は伊達政宗によって17世紀中頃に再興されており、再興に係わる瓦を付近で焼いていたと考えられる。
大沢窯跡の近くには、瓦焼場という地名が現在も残り、昔から瓦の産地であることを想像させる。
■ 岩切城跡
仙台市岩切と利府町神谷沢にまたがる中世の山城。城跡は標高106mの高森山を中心に尾根を平らに削り、平場を造り出し、空堀、堀切などで構成されている。
岩切城は留守氏の居城といわれるが、構築年代は正確にはわからない。動乱の激しくなった南北朝時代の初めころに築かれたと推定される。正平6年(1351)には岩切城を舞台に激しい合戦が行われている。
岩切城は規模が非常に大きく、保存状態も良好なことから、東北地方の中世史を考える上で重要な遺跡として、国の史跡に指定されている。
■ 利府城跡
標高88mの自然地形を利用した山城。岩切城跡と同様に山を削り平場を造り、そこに施設を設けた守り重視の館跡。
利府城が築かれた時代は正確にはわかっていないが、留守氏の家来であった村岡氏が築いたと考えられている。
その後、戦国の時代を迎え留守氏内部に家督相続問題が起き、永禄12年(1569)留守氏の血筋を守る立場に立った村岡氏は、伊達政景(晴宗の三男、政宗の叔父)を養子に迎え、伊達氏勢力下にあって留守家安泰を図るべきとする伊達派と対立した。この時、村岡氏はこの城にたてこもり戦ったが敗れて滅亡したといわれている。
永禄13年(1570)に政景は岩切城から利府城に移り、地名を村岡から利府に改めたといわれる。また同時に、村岡城とよばれていた城名も利府城となった。留守政景は天正18年(1590)に、伊達政宗から黒川郡大谷に隠退を命ぜられるまでの約20年間本拠地とした。その間、政宗の右腕として活躍したことは有名である。

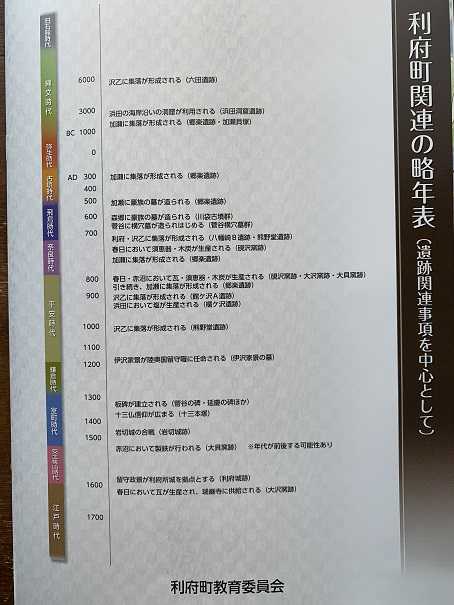
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[宮城] カテゴリの最新記事
-
仙台うまいもの事始め(その3)冷やし中華 2025.11.24
-
日本三大草相撲の地 鳴子 2025.09.10
-
大郷町長選挙の結果 2025.09.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
東北情報ソース
〔記事リスト〕仙台・宮城に関するもの

(1)仙台>地域・経済・都市・政治行政ほか

(2) >教育文化・ひと・事件事故

(3) >シリーズ仙台百景

(4)宮城>地域

(5) >経済・政治行政

(6) >教育・文化・ひと・事件事故

(7)交通・仙台空港・宮城スタジアム

(8)防災・東日本大震災

(9)近現代の仙台・宮城(鉄道敷設史含む)

(10)戦国・藩政期の仙台・宮城

(11)古代・中世の仙台・宮城
〔記事リスト〕東北に関するもの

(1) 東北 >歴史・民俗・産業・政治行政・教育文化

(2) >地域・事件・統計比較・県民性

(3) 青森

(4) 岩手

(5) 秋田

(6) 山形

(7) 福島

(8) 東北博学クイズ!
〔記事リスト〕政治・経済・司法など
〔記事リスト〕その他(教育・文化etc)
編集長のイーグルス応援戦績
カテゴリ
カテゴリ未分類
(42)仙台
(563)宮城
(663)東北
(1234)教育
(52)国政・経済・法律
(135)がんばれ楽天イーグルス
(341)グランディ21・宮城スタジアム
(13)庭の風景・小鳥
(54)雑感
(478)コメント新着
【望子成龍】-Wang Z…
sendai1997さん
おいしいブログページ dnssさん
地方暮らしが変える1… かじけいこさん
徒然なる五星亭 五星亭さん
野球!BASEBALL!!e-EA… barbertakeshiさん
おいしいブログページ dnssさん
地方暮らしが変える1… かじけいこさん
徒然なる五星亭 五星亭さん
野球!BASEBALL!!e-EA… barbertakeshiさん
© Rakuten Group, Inc.










