2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
番外.月末はいつも緊張を持って(2005-05-31)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.月末はいつも緊張を持って《解説》危なかった。月末と言えば、締め作業がある。毎月のことだ。ただ、今月は本当に危なかった。通常の書類のうち、国内のものは問題ないのだが、海外の手続きに漏れそうになったものがあった。4月から、新しい業務に変更になり、4月、5月は、それなりに新しい業務だったせいもあるが、緊張感のなかで仕事が出来ていた。今月は、すこし、気の緩みが出てしまったのだろう。2件の手続きについて、漏れてしまいそうだった。もう一方の関連部門のほうもすっかり手続きを忘れていて、普段は、お互いにチェックし合うはずの体制が、今回に限り、完全に機能していなかった。チェックリストなるものを使って、毎月チェックしてきたのが、今月は、通常業務以外に大変な仕事を抱えている関係で、気づかなかったようだ。そちらのほうに気持ちが傾いてしまい、通常業務への緊張が緩んでしまったのだと思う。来月は、気をつけたい。
2005.05.31
コメント(0)
-
番外.月末の日曜日の約束事(2005-05-30)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.月末の日曜日の約束事《解説》昨日のことだが、朝の任務(掃除機かけ)に関係することだ。毎月、月末の日曜日(雨なら翌週)は、愛機(掃除機)のお手入れの日だ。何種類かあるフィルターのうち、水洗いできるものを水洗いして、きれいにしている。この作業も最近では(自分が決めた)約束事になってきている。この作業のご褒美は、今朝の任務での、愛機の活躍ぶりだ。「元気いっぱい埃を吸い込んでくれそうな」勢いで、任務にあたってくれる。この元気いっぱいの声(実は音だが)を聞いて、今週も1週間がんばろう!と思うのだ。そういう意味で、月曜日をスムーズに気持ちよくスタートさせるための自分の習慣にしたしまっている。そして、最近は特に、夜明けが、早くなったのもあって、家族のみんなが早起きになった。出社時刻の30分以上前に、任務を開始できるようになったため、余裕で出社できるようにもなってきた。こちらも、うれしい限りだ。
2005.05.30
コメント(0)
-
番外.自分は信用されていないのか?-4(2005-05-29)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.自分は信用されていないのか?-4《解説》(昨日の続き)しかし、さっきも言ったけれども「出張した人の中で残業時間に帰着した人が、正しくタイムカードを打刻しているか」というようなことまで、事業部長が正確に把握できている、というような状況でないと(正しくタイムカードの打刻をしている)私だけ目を付けられると言うのは、何とも納得のいかない部分がある。また、この事業部長に関して言えば、(最近特に感じるのだが)部下の指導という点において、全然愛情を感じられない。少なくとも5年前にいた事業部長は、「部下を育てるためにどう指導していくか」ということを意識して、部下を叱咤激励していた。部下は、愛情のこもった叱咤激励は肌で感じることができて、それにこたえようと努力する。少なくとも自分はそうだった。過去の日記で(http://tb.plaza.rakuten.co.jp/papa1311/diary/200307160000/)紹介したこの言葉も、実は、その時の事業部長の言葉なのだ。その事業部長は、今は別の会社に行ってしまったが、今でも当時指導してくれたいろいろなことが、自分の仕事上、役立っているし、その事業部長自身にも感謝している。本来、上司と言うのは(ほんの一面だけでもいいと思うが)ある意味で、部下から慕われてような、そんな存在でもあるべきじゃないのかなぁと思う今日この頃である。(完)
2005.05.29
コメント(0)
-
番外.自分は信用されていないのか?-3(2005-05-28)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.自分は信用されていないのか?-3《解説》(昨日の続き)そして、あろうことか私が、どうもブラックリストに載ったらしい(これは自分の推測)。その理由は、タイムカードに、やたらと外出のための打刻が多いこと、らしい。この1ヶ月で、外出に関する打刻の件で、2回確認指示が上司の部長に入っていた。指示の内容も、私が不正な打刻をしている(かも知れない)事を確認せよとのことだった。(上司の話)これは、私から見れば、とんでもないことで、正しく「タイムカードの打刻をしている従業員」に目をつけて、監視していることになる。私から言わせてもらえば、残業時間帯に、出張から事務所に戻ってくる人たちの中で、どれほどの人が、時間外の移動時間を就業時間にカウントされないように打刻操作しているのか、知りたいものだ。たぶん、かなりの人たちが、打刻操作できていないと思う(自分の推測)。一方で、私のように「正しくタイムカード操作」している人間が、目を付けられるのは、何か間違っているような気がする。確かに、タイムカードの打刻時間に、様々な時刻が記入されていると目立つことも事実だ。これは認める。(明日に続く)
2005.05.28
コメント(0)
-
番外.自分は信用されていないのか?-2(2005-05-27)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.自分は信用されていないのか?-2《解説》(昨日の続き)タイムカードの打刻のルールについてまとめてみると、「残業時間帯であれば、タイムカードを操作して外出することができる」、もう一つは「出張に出かけて、事務所に戻ってくる時刻が残業時間帯に入ってしまったときは、残業時間帯に移動していた時間を集計されないようなタイムカード操作が必要になる」(もっと悪いことに、このルールを知っている人が、かなり少なくなって来ている)やっと本題に入れるところまで来た。我々の組織の上司は、物事をきっちりやる性格の部長さんが上司になったので、仕事では、ある意味にやりやすくなった。ところが、そのまた上司の事業部長が、われわれからみると、少しクセモノなのだ。どんなふうにクセモノかというと(ますます本題に入ってくるが)現在約70名いる事業部の事業部長なのだが、一人一人のタイムカードをチェックしているらしい。(チェックしていることをとがめようというのではない)(明日に続く)
2005.05.27
コメント(0)
-
番外.自分は信用されていないのか?-1(2005-05-26)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.自分は信用されていないのか?-1《解説》今日は、徹底的に愚痴らせて欲しい。まず、今日の愚痴を言う前に、それに関連するうちの会社のタイムカードの打刻のルールについて少し説明をしておきたい。通常の勤務時間を外れていれば(つまり残業時間帯)、タイムカードの打刻することで外出することができる。これは結構便利で、給料日などは、昼休みに銀行に行けなかった場合など、通常の退社時刻を過ぎてから、外出のためのタイムカードを打刻(離席時)して銀行の用事を済ませて、外出から戻ったときにもう一度打刻(帰着時)すればいいルールになっている。もう一つ、出張の時の移動時間の扱いについて、特殊なルールがある。勤務時間内(通常の出勤から退勤までの時間帯)の移動時間は、勤務時間(仕事をしていた時間帯)としてカウントしてもよい。しかし、残業時間帯の移動時間については、勤務時間としてカウントしてはいけないルールになっている。つまり、残業時間帯に出張先から事務所への移動時間は、残業していた時間数として扱われない、と言うことだ。(明日に続く)
2005.05.26
コメント(0)
-
番外.めいっぱい(2005-05-25)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.めいっぱい《解説》今週、来週とやることが「めいっぱい」だ。仕事でも、社外コミュニティでも、プライベートでも、すべてにおいて、予定ややるべきことが、持ちきれないほど、びっちり予定されている。このような中で、トラブルも発生するので、その対応もする。まさに、会社では仕事、家に帰れば、プライベートなイベント、自分に割り当てられた社外コミュニティでの宿題、と大忙しだ。その合間に、娘のノートパソコンの修理(不具合の診断と対応)などをこなしている。一生の中で、一番充実している時期かもしれない。公私共に、こんなに予定が詰まっていて、やるべきことが、次から次へと埋まっていく状況は、未だかつて未体験だ。今は、この未体験ゾーンにいる自分自身を楽しんでいる。体力的には、多少疲れているのに、頭は冴えている感じなのだ。もしかしたら、このまま、燃え尽きちゃうかもしれない、と感じるほどだ、とにかく、あと1ヶ月は、この状態を経験できそうだ。精々楽しみたい、と思っている。
2005.05.25
コメント(0)
-
番外.我が家のパソコン先生(2005-05-24)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.我が家のパソコン先生《解説》私は、自慢じゃないが(こういうときは決まって自慢だ)、我が家では、「パソコン先生」だ。昨夜も、1号のノートパソコンの具合が悪かったらしい。「ウイルスチェックがなかなか終わらない」との事。早速、見てみると、どうやら、ウイルス定義体と、チェックプログラム自身が少し古いようだった。プログラム自身のアップデート(レベルアップ)とウイルス定義体の更新をしてから、再度、ウイルスチェックを実行させたところ、昨夜は、何時間も掛かって終わらなかったのに、30分ほどで終了。1号に感謝された。今日は、大学でパソコンを使う授業があり、ウイルスチェックが終了していないことに心を痛めながら、就寝したようだ。そして、朝になって、魔法のように30分で、修理完了。素人には、「パソコン先生」に見えたみたいだ。数少ない、権威を誇れる分野なので、1号、2号あたりにも抜かれないようにしなければ!と思っている。競い合う環境や心が自分を成長させる原動力になる!
2005.05.24
コメント(0)
-
番外.緩急をつけた投球を希望(2005-05-23)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.緩急をつけた投球を希望《解説》過渡的だが、今は超繁忙期になっている。ピッチャーで言えば、毎日が「全力投球」の繰り返しだ。緩急をつけて投球していかないと、体がもたない、と感じている。週末は、休みにして、翌週の全力投球に備えている。先週の日記にも書いたが、自分自身の目標のために、一つ一つ課題をクリアしてゆく姿勢を持っているものの、今は全力投球にパワーを割いているので、なかなか課題クリアできていない。課題クリアに時間が割けるようにするための対策を計画しているが、それも全力投球でできていない。今は、八方ふさがりの状況だが、課題クリアのための時間を作り出してみせる!
2005.05.23
コメント(0)
-
番外.気持ちいい季節がやってきた(2005-05-22)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.気持ちいい季節がやってきた《解説》今日は、朝の任務(床の掃除機かけ)の話だ。我が家は、和室を除き、床(フローリング)なので、掃除はしやすいが、冬は寒い(というか冷たい)ので、いつも靴下か室内用ブーツを履いて、朝の任務についていたのだ。最近は、陽気も良くなってきたので、朝の任務中に靴下は履かなくても任務をこなせるようになってきた。すると、どういうことが起きるかと言うと、床を直接素足で触れることになるので、任務の遂行状況が、はっきり判るのだ。今までは、目視確認しかできなかったので、見落としがあっても判らなかった。しかし、これからは、素足で、床の状況を確認できるため、任務の仕上がりを直接確認しながら、任務に当たれるということだ。完ぺき主義と言うほどではないが、決めたことはきっちりやりたいほうなので、この素足の感覚で任務に当たれる季節が始まり、何かうれしいきもちがした。
2005.05.22
コメント(0)
-
269.俺ね、目標がわからないんです(2005-05-21)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】269.俺ね、目標がわからないんです《解説》昨日に引き続き、同じサッカー選手の言葉だ。目の前の目標をクリアするたびに、新しい目標が見つかって、最終的に、何が(あるいはどこが)最終目標なのかわからない、という気持ちから出た言葉で、決して消極的な言葉ではない。この言葉を見て、今の自分は甘いな!って感じたのだ。彼はいつも、「もっと(サッカーが)うまくなりたい!」って思っていて、(自分がサッカーがうまくなるための)課題を見つけてそれを克服すること、これの連続だと言う。そして彼は、(サッカー選手として)40歳くらいまでやりたい、徒も言っている。プロ野球の世界でも、なかなか40歳のプレーヤがいないのに、運動量的には、(野球に比べて)かなりハードなのに、それでも、40歳くらいまでやりたい、と言う。さらに、「いくつになっても、あいつは必要だって言われたい」とも言い、(うまくなるために)求めるものが無くなったら、引退の時、と予感している。いま20代半ばの彼のチャレンジは続く。今の自分は、歳のせいにしたりしながら、実は、今の仕事の手を抜いていたかもしれない。久々に、全力投球してみようと思う。
2005.05.21
コメント(0)
-
268.まだ、ぜんっぜんダメ!(2005-05-20)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】268.まだ、ぜんっぜんダメ!《解説》サッカー選手の言葉だ。頭でイメージしていることが、ぜんぜんやれていない、という気持ちを表した言葉だ。この言葉には、彼自身の理想(頭でイメージしていること)に向かって日々努力していることや、去年とは違う強いチームと試合することに、「楽しい」という感覚を持って(ある意味リラックスして)試合に臨んでいるのに、自分の行動には厳しい目を向けている。まだ、「ぜんぜん(自分の思ったとおりに)できていない」と語る彼は、最近、「自分がミスしたプレー」を繰り返し繰り返し見るそうだ。そして、「何故ミスが起きたのか」を理解するのに、そのミスの前で、どうすべきだったのか、を考えるそうだ。感心したのは、「そのミスをどうすべきだったか」ではなく、その前のプレーで何をすべきだったか、どうすれば良かったのか、を考えるのだそうだ。自分は、この記事を読んでいる時ハッとした。自分たちの業務でもそうだが、その不具合(手続き上のミスなど)が発生したら、その不具合にどう対応すればいいのかは、かなり真剣に考えていたが、実は、その不具合が発生する前に何をすべきだったのか、を考える事が必要だったのだと思う。と言うことは、私自身も、今の仕事「まだ、ぜんっぜんダメ!」と言うことだ。
2005.05.20
コメント(0)
-
番外.3号の誕生日に(2005-05-19)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.3号の誕生日に《解説》娘の誕生日だというのに、一緒に祝ってあげられなかった。その代わりと言ってはなんだが、プレゼント(ショートケーキ)を用意した。ただ、少しラッキーだったことに、学校帰りの2号とばったり会ったことだ。2号と一緒にケーキ屋に行って、買い込んだケーキを2号に自宅まで届けてもらえたのだ。自分は帰宅できずに、さらに出張先に向かう途中だっただけに、かなりラッキーだった。2号に会えなければ、自宅まで(ケーキを)届けてから出張に出かけなければならなず、ケーキ屋から、直接出張先にいけたのは、ラッキーだったのだ。おまけに、弁当箱も2号に持たせたので、出張先に持っていく荷物も大幅に減らすことができた。
2005.05.19
コメント(0)
-
番外.3号の帰還の日に思うこと(2005-05-18)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.3号の帰還の日に思うこと《解説》今日は、月曜日に合宿に出かけた、娘3号が帰ってくる日だ。新しい経験をたくさんして来たのだろう。そこまでは、いいだろう。ただ、ちょっと気になったのが、翌日の自宅学習だ。自宅で学習している学生も居ると思うが、我々の頃は、翌日の休みは無かった。あの頃の先生は、タフだったのだと思う。高校までの学生生活で、イベントの翌日が休みになったことは無い。昔と比較するのはあまり好きではないが、どこかの相撲部屋の親方も新聞で言っていたが、最近の若い人は昔に比べて「辛抱」ができ無くなってきている、と言って憂いていた。ゆとり教育もいいし、イベント後の休みもいいと思う。そして、若い人には、どこかの親方が言うように辛抱できるようになって欲しいが、それよりも、学校や家庭ではもっと、各個人が、本当にやりたいこと、を探すことをサポートしていくべきではないか、と思っている。自分が本当にやりたいことに対しては、どんな辛抱でもできるようになると思う。辛抱させることが最初ではなく、「本人が本当にやりたいこと」を探してあげることが、最初のような気がするのだが....
2005.05.18
コメント(0)
-
番外.どちらかのやり方に統一してください(2005-05-17)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.どちらかのやり方に統一してください《解説》手続きミスを犯すきっかけになった言葉だ。「どちらか」ではなく、「こちら」というふうに、統一すべきやり方は決まっていたのだ。しかし、「どちらか」と言う言葉で、判断して判断した結果のやり方が、統一すべきやり方ではなかったので、大変なことになった。統一すべきやり方では無い方法で、やり方を統一したところ、「どちらかのやり方に統一してください」と伝えてきた部署ではないところから、「そのやり方ではうまく行かないので別のやり方にするように」と言われ、のけぞってしまった。今までのやり方を変えるために、調整したいろいろな作業がムダになってしまった。しかも、いったん決めた手続き(もうやり方をけ得ようとした矢先)を元に戻した上で、もともと「統一すべきやり方」でやるための方法を再検討しなければならない。アメフトで、ペナルティ(スタート場所を後退させられる罰則)を受けたような感覚に襲われた。言葉一つで、えらい目にあってしまった。とは言っても、早いこと、新しいやり方で業務を始めてしまう前だったのを、「不幸中の幸い」ととらえて、業務に当たることにしよう。
2005.05.17
コメント(0)
-
番外.研修旅行に出発(2005-05-16)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.研修旅行に出発《解説》うちの娘3号が、今朝(7時学校集合で)出かけていった。中学生にもなると、さすがに自分のことは自分でできるようになってきているなと感じた。車酔いしやすいので、薬を飲み、帰り用の薬も自分で準備できるようになっている。週末は、バスの中でやるレクリェーションのために、なにやら画用紙(10枚ほど)に、絵を描いていた。彼女は、絵を描くのは好きだが、その絵を人に見せるのは、あまり好きではなかったのに、レク係ということで、頑張っていたらしい。大人の世界でもそうだが、泊まりでどこかに一緒に出かけると、「同じ釜の飯を食べる」のに近い環境になるので、団結力が上がるような気がしている。今、参加しているコミュニティでも、過去2回合宿したのだが、だんだん団結が強まってきたと思う。3号にも、団結できる仲間を作って欲しいと思っている。
2005.05.16
コメント(0)
-
番外.練習は物事の基本(2005-05-15)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.練習は物事の基本《解説》今日、サッカーの練習を見学(昨日は見学できなかったので)してきた。そのときに、感じた気づきの言葉だ。小学校(あるいはそれより小さい頃)から、「練習」ということをしてきたと思う。練習の対象は、運動だったり、勉強だったり、いろいろあったと思うが、どちらの分野にしても、練習しないでうまくなることは無い。これは、共通した事実だろう。特に小学校では、よく居残り組がいて、授業がよく理解できていない児童を残して補習をしていたと思う。これは、他のこどもと同じ練習量では、身につかなかった子供に対するサポートだったと思う。私も、足し算までは、順調だったのに、引き算で引っかかった。引き算のテストで20点(100点満点で)どうしても、100-89、これが計算できなかった。答えが21になってしまうのだ。21の答えが間違っていることには気づいた(21+89=110)ものの、100-89の考え方がどうしても分からなかった。小学校の補習(居残り)が無かったら、私は、小学校の頃から、挫折していたかもしれない。今日の話に戻そう。今、なかなか勝てずにいるチームの監督は、選手たちに、繰り返し、繰り返し、基本動作を練習させていた。基本の練習、私が小学校でつまづいた引き算の考え方のような、この基本の練習に立ち戻って、次の試合には勝って欲しい。
2005.05.15
コメント(0)
-
番外.家族の心遣いに感謝(2005-05-14)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.家族の心遣いに感謝《解説》最近は、毎週、週末はサッカーの試合か、そのチームの練習風景を見学している。と言うことで、我が家の家族カレンダー(予定表)には、毎週のように、その計画が記入されている。今朝は、練習風景とサッカーの試合と、両方をはしごしようと計画していたのだが、やはり、かなり厳しいスケジュールだったので、個人的には、(家族カレンダーの修正はしておかなかった)試合観戦だけの計画に変更した。そして、おもむろに、朝の任務につこうとしたときに「掃除機ならかけておくから、練習見に行ってもいいよ」と言われた。その瞬間、ありがたい気持ちと、家族予定表を書き直しておかなかった、自責の念にさいなまれた。これは、すこし大げさに書きすぎたが、家族の気持ちはとてもありがたかった。
2005.05.14
コメント(0)
-
番外.2号の意気込み!(2005-05-13)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.2号の意気込み!《解説》高校の最終学年の2号は、今朝いつもより、早く学校に出かけた。好きな席に座ればいい学校なので、早く行っていい席を取ろうと言うのだ。その意気込みたるや、先週までは、学校に始まる時間に間に合うぎりぎりに出て行ったのに、えらい変わりようだ。聞くところによると、最近は、レポート提出時期と言うことで、いつもより、教室を使う生徒が多いらしい。それで、座る席が無くなってしまうらしい。こんな理由で、早く家を出るように(今朝から)したらしい。いずれにしても、周りの環境の変化に自分で対応したところを買いたい。受身での対応でなかったところがよかった。おまけに、娘が早く起きたお陰で、朝の任務(掃除機かけ)も完璧に実施できた。
2005.05.13
コメント(0)
-
267.やってみてから考えろ(2005-05-12)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】267.やってみてから考えろ《解説》今日も、「常識破りのものづくり」にあったことばで、「著者 語録」のものだ。この言葉は、自分のモットーの一つ「どうせ後悔するなら、行動して後悔したい、何もしなかった事を後悔したくない」に通じる言葉だと思った。とは言っても、行動を起こすのは、とてもパワーの要ることだ。ただ、このパワーが自分自身を磨き、自分自身のポテンシャルを上げているのだと思う。自ら行動できない人は、オーラというか、存在感が薄い、という感じの人が多いように感じる。昨日も少し書いたが、心配症の人は、前に進むことにも慎重になりすぎて、結局前に進めず、自分自身に磨きがかけられない、という悪循環に陥る可能性を持っている気がする。そこで、気持ちをチョットだけ変えてみるだけで、前に進めるようになるはずだ。例えは悪いが、「経験」と言うのは、「宝くじ」のような要素があると思う。必ず当たるという保証は無いが、「買わないことには絶対当たらない」。経験も、この経験をすれば、こういう効果がある、という保証は無いが、経験しなけば、どういう効果にしろ手に入れる事はできない。また、宝くじに似ているのは、大当たりから外れまであることだ。自分が挑戦する経験の効果はいつも大当たり、といきたいが、なかなかうまくいかない。これも、人生のおもしろいところではないか、と思う。
2005.05.12
コメント(0)
-
番外.心配症の功罪(2005-05-11)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.心配症の功罪《解説》午前中にやった打合せで、感じたことを書いておきたい。新しい業務の説明を午前中に実施した。これは、初めて使うシステムでやる新しい業務なだけに、受講者にやたら心配症の人がいた。そして、説明の度に(そのときどきに思いついた)心配事を質問していたのだ。その質問も、そうとう細かい内容から、あまり発生しないようなケースまで、あらゆる、想定条件について、確認していたので、最終的には、説明そのものが、先に要求されてしまった。おかげで、説明会の時間は、大幅にのびてしまった。疑問に思ったことは、後でまとめてくれたらよかったかな、と思った。
2005.05.11
コメント(0)
-
266.技能の差を評価せよ(2005-05-10)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】266.技能の差を評価せよ《解説》今日も、「常識破りのものづくり」にあったことばだ。技術者への尊敬と、技能と品質の差を正面から認める仕組み(システム)作りこそ、現在の製造業復権の早急の課題、とも言っている。まったくそのとおりだと思っている。そして、私が向けている分野は、ソフトウェア開発に携わるIT技術者の技能や技術だ。実際の取引では、おかしなことも起こっている。ソフトウェア開発においては、効率的に開発できる人(IT技術者)に、仕事が集中する。なのに、効率的に開発できない人とあまり変わらない給料しかもらえない。効率の悪い人と良い人とでは、2倍以上も生産性に差があっても、給料が2倍と言うことは無い。前にも書いたけれど、ダラダラ仕事をする人が、たくさん給料をもらう、こういう給与体系では、IT技術者の士気を下げることはあっても、士気を上げることは無い。ここで、間違ってはいけないのは、「人を評価する」のではなく、その人の「技能」を評価するのだ。人は人を評価できないのだから。
2005.05.10
コメント(0)
-
265.不必要な分業は人の能力をそぐ(2005-05-09)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】265.不必要な分業は人の能力をそぐ《解説》今日も、「常識破りのものづくり」にあったことばだ。人の能力をダメにしたのは、組織の中の分業だそうだ。自分もそう思った。人の仕事と自分の仕事を明確にしたがる人がいるが、みんな悪だとは思わない。「責任の所在をはっきりさせる」目的なら問題ないだろうと思う。 問題になるのは、人の仕事と自分の仕事を明確にする目的が、「ここから先は(自分の責任範囲じゃないから)知らないよ」というための境を決めるのならば、これは、自分自身の能力を退化させる考え方なのだと思う。仕事の分業が進んだ職場で、一人で何でもできるようになれば、自然に、その人に情報や仕事が集まってくる。すると、その人は、ますます忙しくなってくる。ここまでなら、個人の能力を進化させているのだが、この後の対応(フォロー)も重要だと思う。ここで、(別途取り上げる予定だが)その人の評価(具体的に言うと給料)がどう見られるか、でその人の士気はぜんぜん違ってくる。せっかく、能力を進化させたのに、それに見合った評価がさせないと、「自分の能力を上げたために忙しくなっただけ」になってしまう。この結果、自分の能力を進化させても、なんの評価もされないなら、進化させる必要性が無い、と考えられてしまうだろう。従業員のみならず、会社自身を退化させてしまうことになりかねない。
2005.05.09
コメント(0)
-
264.仕事は自分を向上させる道具だ(2005-05-08)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】264.仕事は自分を向上させる道具だ《解説》昨日に引き続き、「常識破りのものづくり」にあったことばだ。今日の言葉を変えて表現すると、こうも言えると思う。 自分自身は自分の仕事で磨く昨日も書いたが、「与えられた仕事」を「今までどおりのやり方」でこなしていたのでは、当然、自分自身進化できない。せいぜい「与えられた仕事と従来どおりのその仕事のやり方を覚えた」程度の進化だろう。ところが、このままの状態に満足して「進化したつもり」でいると、世の中の方が進化して行ってしまうので、自分自身は、世の中から取り残されて、どんどん退化して行ってしまうのだ。退化したくなかったら、自分を磨くしかないだろう。また、進化しようとする社員が居ない会社は、会社そのものが「退化」してしまうということだろう。考えてみれば、仕事をしながら「自分を向上できる」とすると、こんないいことは無いのではないか。給料をもらいながら、自分を磨けるって事だろう。来週以降、チョット打って出てみようと思う。軌道に乗ったら、またここに記録することにしたい。
2005.05.08
コメント(0)
-
263.大企業は優秀な社員を退化させる(2005-05-07)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】263.大企業は優秀な社員を退化させる《解説》「常識破りのものづくり」にあったことばだ。ここでは、どんな企業にいると社員が退化するかというと、 前例重視で「昨日と同じ仕事をしていればいい」という組織だここで、ドキッとしてしまった。日記にも書いたと思うが、昨年から、いろいろな業務が、別の部門から我々の部門に移管されてきたのだが、一向に人は増えなかったのだ。仕事は増えるのに、人は増えない。どうやって、仕事をまわせばいいのか、と(同僚も含めて)反発に似た気持ちを抱えつつ仕事に就いていた。この本にあった、この言葉で、目が覚めた感じがした。「仕事量が増える」という現実に対して、今までどおり対応しようとしていたのだ。これでは、今までどおりでやれるわけが無いのは、火を見るより明らかだ。このことをどうやって対応すれば良いのかを考えも、実践もしないで、ただ反発の気持ちを持ったままで、仕事に就いていたのが、恥ずかしい。話は変わって、昨日の新聞に出ていた「60歳定年から年金が支給される65歳までの5年間をどう過すか」の記事には、「仕事に就け!」と書いてあったが、このままの考え方(前例重視の保守的な仕事の仕方)では、60~65歳になったときに、仕事をもらえなくなってしまう。今から、あと15年足らずだが、定年後の再就職に向けて、自分に(企業から魅力的になるように)磨きをかけてゆきたい。
2005.05.07
コメント(0)
-
番外.多品種少量生産がエコライフの原点(2005-05-06)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.多品種少量生産がエコライフの原点《解説》いまや、大量生産の時代ではないことを痛感させられた。NHKスペシャル「常識の壁を打ち破れ~脱・大量生産の工場改革」を見たからだ。大量生産そのものが悪いのではない、問題は、長いベルトコンベアの上に乗った「半製品」の数が多いこと、だと思う。組立工程の数だけ、組み立て工の人たちが必要になり、複雑なものであるほど、長いベルトコンベアが必要になり、「半製品の数」も多くなる。半製品は、ムダな存在なのだ。モデルチェンジなどで別の製品を作るときに、ベルトコンベアに乗っている「半製品」を捨てても、製品に組み上げても、ゴミになるか、不良在庫になるかの違いだけで、みんなムダな物になってしまう。この番組では、この解決策として、一人ですべてを組み上げてしまう生産方式(これを多能工という組み立て工が実施)を紹介していた。この方式なら、組み立て工は一人なので、「半製品」になるのは、その組み立て工が組み立て中の1台だけだ。モデルチェンジするとしても、今、組み立てているものを組み上げてしまえば、大量の不良在庫を作ることも無い。さらに、一人の組み立て工がすべての組立工程を担当することで、組み立ての仕事が、海外に流出することは無い。一人に一工程しか担当させない生産方式では、この組み立ての仕事は、単価の安い海外に流出してしまう。この番組を見終わったときに、感じたのは、「事務しかできません」と言っていると、そのうち、事務専門の派遣者に仕事を追われてしまう、という危機感だった。事務しかできない事務員からの脱却を強く感じた。このことに気づかなければ、リストラされていたかもしれない。この番組を見られたことは幸せだった。
2005.05.06
コメント(0)
-
番外.こどもの日に思うこと(2005-05-05)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.こどもの日に思うこと《解説》今日は、菖蒲湯に浸かって、柏餅を食べて、武者人形は飾らなかったが(みんな娘なので)、端午の節句にまつわる事をしてみた。娘たちがずっと小さかった頃は、お菓子付の小さい鯉のぼりを買ってきては、家の中に立てておいた(外に出すと男子誕生と間違われては大変なので)5月4日時点で、15歳までが子供の日の対象者だそうだが、人口に占める割合は14%台ということで、先進国の中でもっとも少ない比率だそうな。うちは、娘ばかりだけれど、3人、世の中に送り出しているものの、一向に若人が増えていかないみたいだ。もっとも、娘たちは、まだ結婚していないし、学生だから、子供を生める状態じゃない。でも、このまま、出生率が下がり続けていくと、次の世代を担う若者がどんどん減っていってしまう。自分たちは、若い人たちに支えてもらわなくてもいいような準備が必要と言うことか?このあいだ、企業年金の説明があったが、制度の見直し(給付パターンを選択できる)と共に、給付金額の減額(これも見直し)になるとの事。将来に備えようと思っても、自分たちを取り巻く環境もなかなか追い風になってはくれないようだ。いずれにしても、自分の身は、自分で守るしか無いみたいだ。
2005.05.05
コメント(0)
-
番外.効率化ってどういうこと?-2(2005-05-04)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.効率化ってどういうこと?-2《解説》(昨日の続き)今度は、取引と言う面で見てみると、効率的にソフトウェアを開発すると、同じ成果を出すならば、開発作業期間が短いと「効率化」が図れた、とされる。そして、短くなった開発期間は、どのような結果をもたらすかと言うと、「契約金額が少なく」なるのだ、受注者から見ると「同じ作業を効率的にやると売上げが減る」、逆に言えば、発注者から「ダメだ」と言われない程度にダラダラ開発をすれば、それなりの売上げが上がる。発注者が言う、ソフトウェア開発での「効率化」は、発注金額の抑制効果、としてとらえているに過ぎない。先に書いたように、開発費の抑制だけが目的の「効率化」は、とても危険だ。なぜなら、開発費を減らして、「バグ」という不具合が増えない(ソフトウェアの品質が確保できている)ならいいが、開発費をケチったために、バグという不具合にあとで悩まされたのでは、かえってソフトウェアの開発費は効率化できない。結論は、ソフトウェア開発における効率化を進めるに当たっては、「ソフトウェア品質が変わらない」という前提の下で、開発の効率化を進めるのでないと、意味が無くなってしまう。かえって、余分な開発費が必要になってしまう、ということだ。「安物買いの銭(ぜに)失い」と言うことにならないように、目先の利益(本当の利益ではないのだが)にとらわれてしまわないように気をつけたい。(完)
2005.05.04
コメント(0)
-
番外.効率化ってどういうこと?-1(2005-05-03)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.効率化ってどういうこと?-1《解説》景気低迷が続くと、「効率化せよ」という言葉が、いろいろな部門から要求されている。今日は、ソフトウェア開発において、この効率化を進めることの意味について、考えてみた。事務作業で言えば、同じ時間で、今まで以上の事務件数をこなす事、これが効率化だろう。ソフトウェアの開発で言えば、同じ時間で、今まで以上の機能を開発すること、かと言うとそうではない。ソフトウェアの開発について言えば、「同じ時間でたくさんのものを作ること」が必ずしも「効率化したこと」にならないのが厄介だ。なぜなら、ソフトウェアというものは、事務作業や(物理的な)物を作るの違い、出来上がりを良いか悪いか判断しにくいのだ。物理的なものならば、外観でまず大まかな良し悪しを判断できる。ところが、ソフトウェアは、実際に動作させて見ないと、良し悪しが判断できない。もっと厄介なのは、動作させただけでは判明しない「バグ」と言われる不具合(ソフトウェアが動かなくなるなど)が潜んでいる可能性があることだ。ソフトウェア開発の世界では、効率よくソフトウェアを作ることができても、この「バグ」という不具合が潜んでいては、その後、そのバグという不具合を修正する必要が出てきて、結局、開発期間は短縮できたのに、修正のために、もっと時間が掛かってしまったのでは、最終的に「効率がいい開発では無かった」事になってしまう。(明日に続く)
2005.05.03
コメント(0)
-
番外.新しいフェンス張替えに悪戦苦闘-4(2005-05-02)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.新しいフェンス張替えに悪戦苦闘-4《解説》(昨日の続き)すべての束を切り終わるのに、夕飯の時刻までかかってしまったので、実際にルーフバルコニーに設置するのは、次の日にした。次の日は、応援するサッカーチームの試合があるので、午前中の早いうちに仕上げなければならないというプレッシャーもあり、朝の任務もそこそこに、早速、すだれによるフェンスの設置に取りかかった。あと設置するだけのはずだったが、簾とすだれをつなぐためのテープが足りないことが分かった。近くの日曜大工店のオープン時間を目指して、自転車で出かけた往復で5キロほどだし、重い買い物ではなかったのでこれは楽々こなすことができた。やっとの思いでここまで準備ができた。あとは設置だけだ。悪戦苦闘して、やっとの思いで8年ぶりのルーフバルコニーのフェンスリニューアルをすることができた。体のあちこちが痛くて、仕方がないが、やり遂げた達成感もひとしおだった。(完)
2005.05.02
コメント(0)
-
番外.新しいフェンス張替えに悪戦苦闘-3(2005-05-01)
【こころに残るCDW-17Jan2003の言葉】番外.新しいフェンス張替えに悪戦苦闘-3《解説》(昨日の続き)最初の1束を切り始めて感じたのは、13束すべてを切るのは無理。ということだった。よっぽど近くの日曜大工店に行って、電動ノコギリ切ってもろうと思ったほどだ。ところが、「当店でお買い求めいただいた商品のみのご利用に限ります」とのことであきらめた。不幸中の幸いだったのが、あらかじめ電話して確認したことだ。これが、12束の(重い)すだれを持ち込んで断られた。さらに大変な思いをするところだった。自分で切る事しか残された道がないとなれば、気持ちは変わるもので、どうやってあと12束を切るか、を集中して考えることにした。1束目は、「切る位置の印を付けて、切る」という作業で進めたが、すべての束の切る位置の印を付けてから、すべての束を切ろうと決めた。(明日につづく)
2005.05.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-
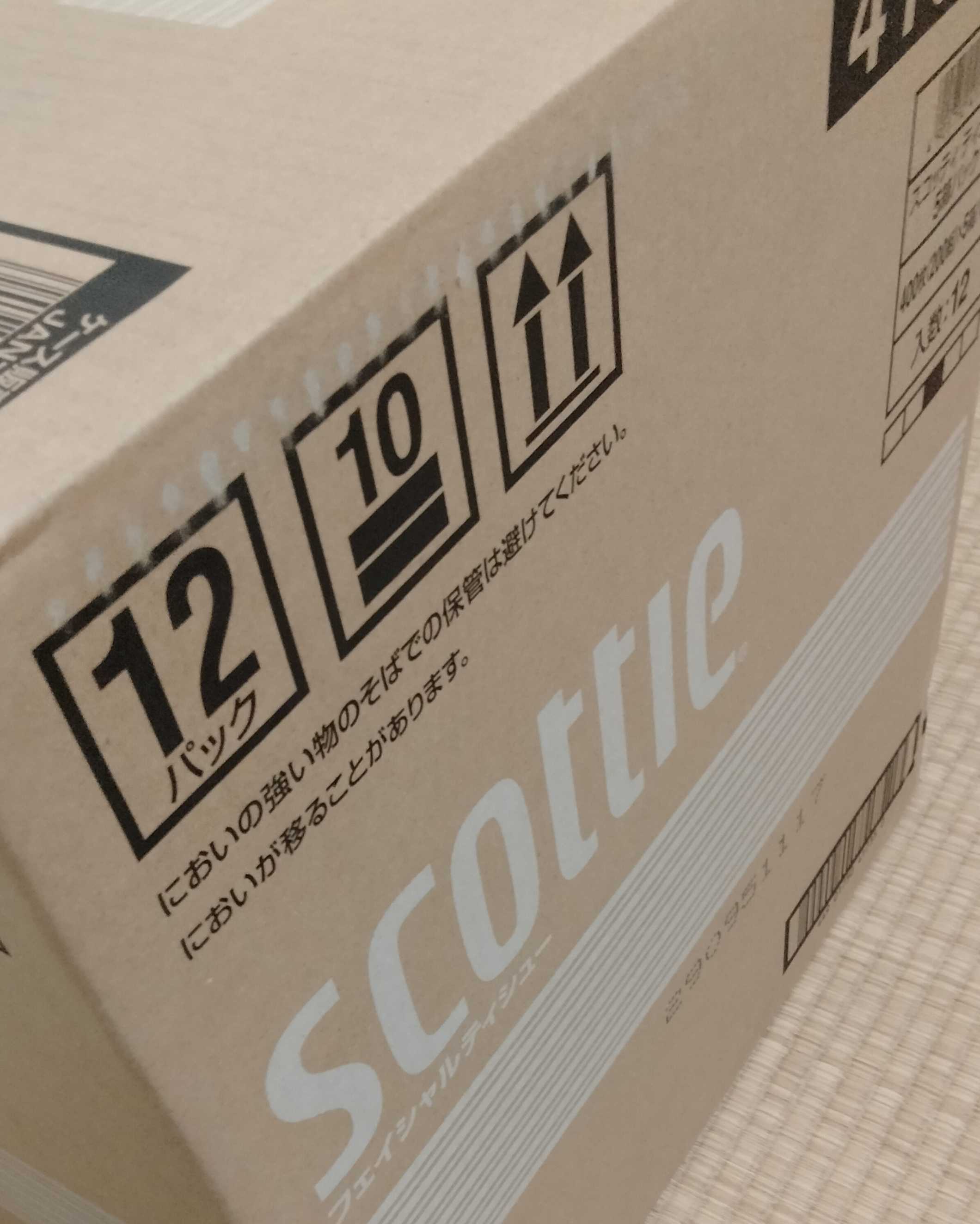
- 株主優待コレクション
- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…
- (2025-11-15 18:27:26)
-
-
-

- 楽天写真館
- [Rakuten]「カレンダー」 検索結果
- (2025-11-15 22:03:23)
-
-
-

- 楽天市場
- [Rakuten]「カレンダー」 検索結果
- (2025-11-15 21:59:33)
-







