2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2013年02月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
センター国語必勝法2
センター国語の読解問題の場合、最大のポイントは、「もっさりしていてどうもピントがボケているが、これといって明確な誤りがないもの」が正解であるといういううことである。 これをふまえ、まず今回間違えちゃった問題を反省する。私が間違えたのは前回35番と書いたが、28番だった。古文の最後の問6である。なおセンターは今なお国語の問題をHPに公開していないため見にくいがhttp://www.asahi.com/edu/center-exam/shiken2013/kokugo/を参照していだきたい。 私はこの問6をほとんど無警戒に1とした。この問題に至る時点で、ほぼ問題文は完全に読み取っていると思い込んでいた(罠)。2は「女君」には敬語が使われていないというのが明らかな間違い。普通に使っている。3は「右衛門督」は別に周りの承認など全然気にしていない。4は二人の恋は既に昨日の夜に成立しているのであり、別に今日の歌で徐々に深まるわけではない。5は特に間違いはわからないが(罠)、いかにもしょぼい(罠)。この問題文の焦点は「右衛門督」と「女君」の恋なのに、脇役である他の人物にしか言及していない。 というわけで「右衛門督」と「女君」に言及し、これといった間違いのない1が正解である・・・ だが正解は5であった。ええ?5はしょぼくないか? しかしこれこそまさにセンター国語の罠である。 1はいかにも正解である。田舎に都に劣らない素晴らしい女性がいるというのはこの種の物語の定番だし、この物語では特に琴の聴覚的効果がキーとなっている。昨夜琴の音にひかれた「右衛門督」が「女君」のもとを訪れ、笛と琴で合奏することを通じて深い仲になったことは、問題文前のあらすじ説明と注5の補足説明を総合的に判断すれば、明らかである。ああああ!そこか! つまり二人の恋のいきさつが明らかになるのは、問題文前のこれまでのあらすじ部分と、昨日起こったことに対する注の補足説明であり、問題文そのものには昨夜の説明はないのである・・・・ これに対して5は弟その他の描写が「巧み」かどうかは意見の分かれるところであろうが、これといって明確な間違いはない。5を外すためには、明確な間違いを発見する必要があった。大分センター国語というゲームになれたつもりだったが、いつのまにか「最も適当なもの」の罠にかかっていた。しょぼくてもいい、ピント外れでもいい。「最も適当なもの」とはそれが素晴らしい選択肢だ、ということではなくて、明確な間違いが無いというという意味である。
Feb 4, 2013
コメント(1)
-
センター国語必勝法1
一月はむやみに忙しいのとFBで遊んでいたため更新が滞りました。 こんなところを高校生が見るのかどうか不明ですが、新連載はセンター国語必勝法。 毎年チャレンジしてるのだが、今年は過去最高の192点を記録した。間違えたのは8点の古文35のみ。そろそろ必勝法が完成形に近づいた思われるので公表します。 え、大学の先生のくせに満点取れないの?なかなか取れませんw 多分理学部数学科の先生がセンター数学にチャレンジした場合、老教授ならともかく若い講師とか簡単に満点だと思われる。しかし国語だけは別である。なぜかというと文学研究者感覚だとどう見ても選択肢に正解がない、と思われる問題がいくつかあるからである。こんなピンボケが正解なのか!という問題がある。これはマークシートという回答形式を前提とした場合、ある意味当然である。そんないい答えがあれば、誰でも正解をマークしちゃうからである。 清水義範の小説に『国語入試問題必勝法』という小説がある。これはパロディー小説であり、「長短除外の法則」(一番長い選択肢と一番短い選択肢は誤答)とかふざけた必勝法が書いてあるのだが、本質を射抜いている部分もある。それは正解の選択肢はピンボケだということであり、これはセンター試験には実際に当てはまっていると思われる。私立大のマークシートは必ずしもそうではない。一般に教員はまず正解を作る。次に誤答を作る。純情な教員ほど正解は懸命に、誤答は嫌々ながら作るので、文体の力強さが違う。そういう試験の場合素直に考えれば、それが正解である。しかしセンター試験の場合複数の合議で作られているので、おそらくそこまでくっきりと正解だとまずいんじゃないか、という議論が行われているのではないだろうか。(続く)
Feb 2, 2013
コメント(1)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-
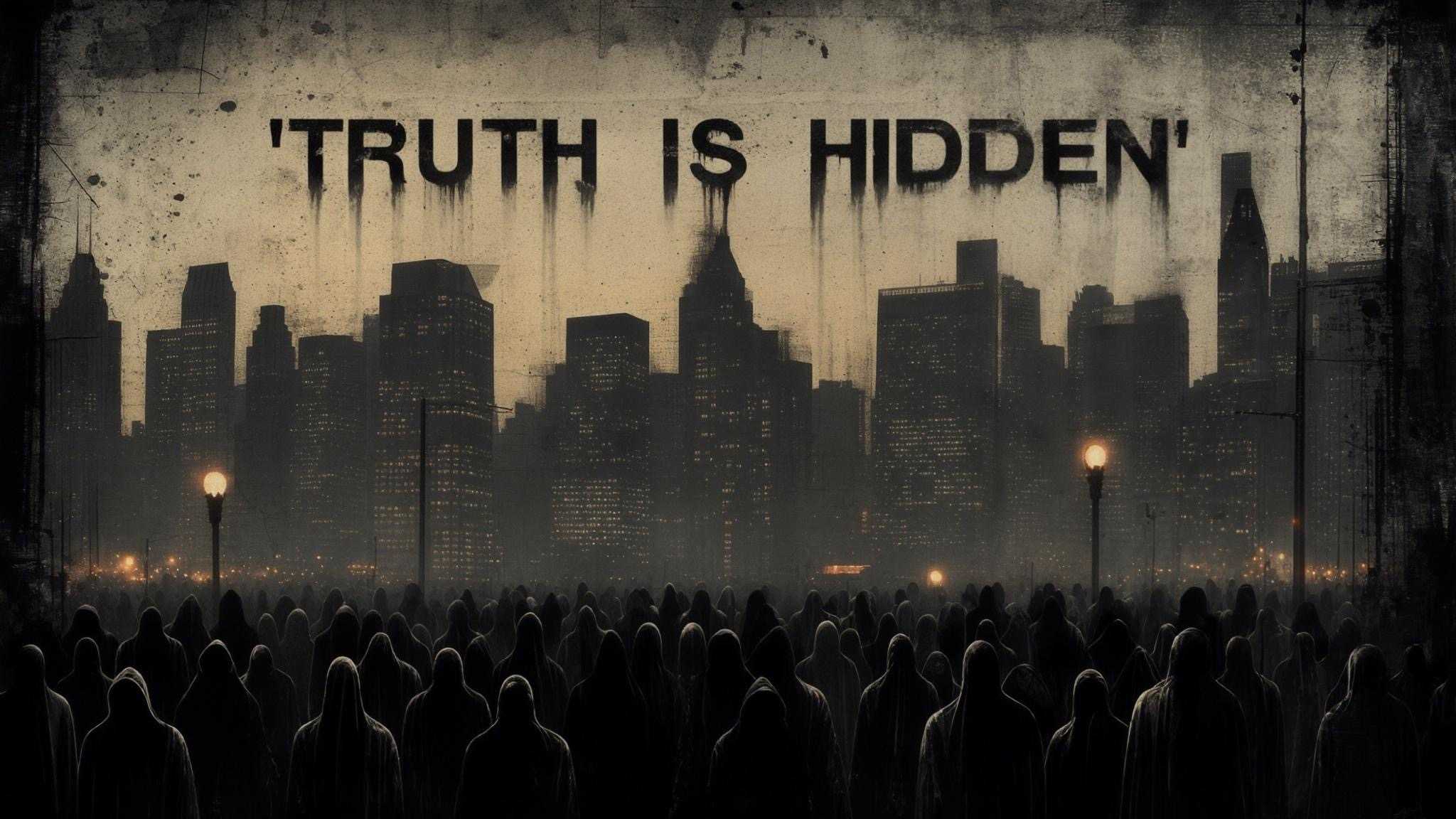
- 人生、生き方についてあれこれ
- 陰謀論はなぜ生まれるのか|権力の不…
- (2025-11-21 12:57:17)
-







