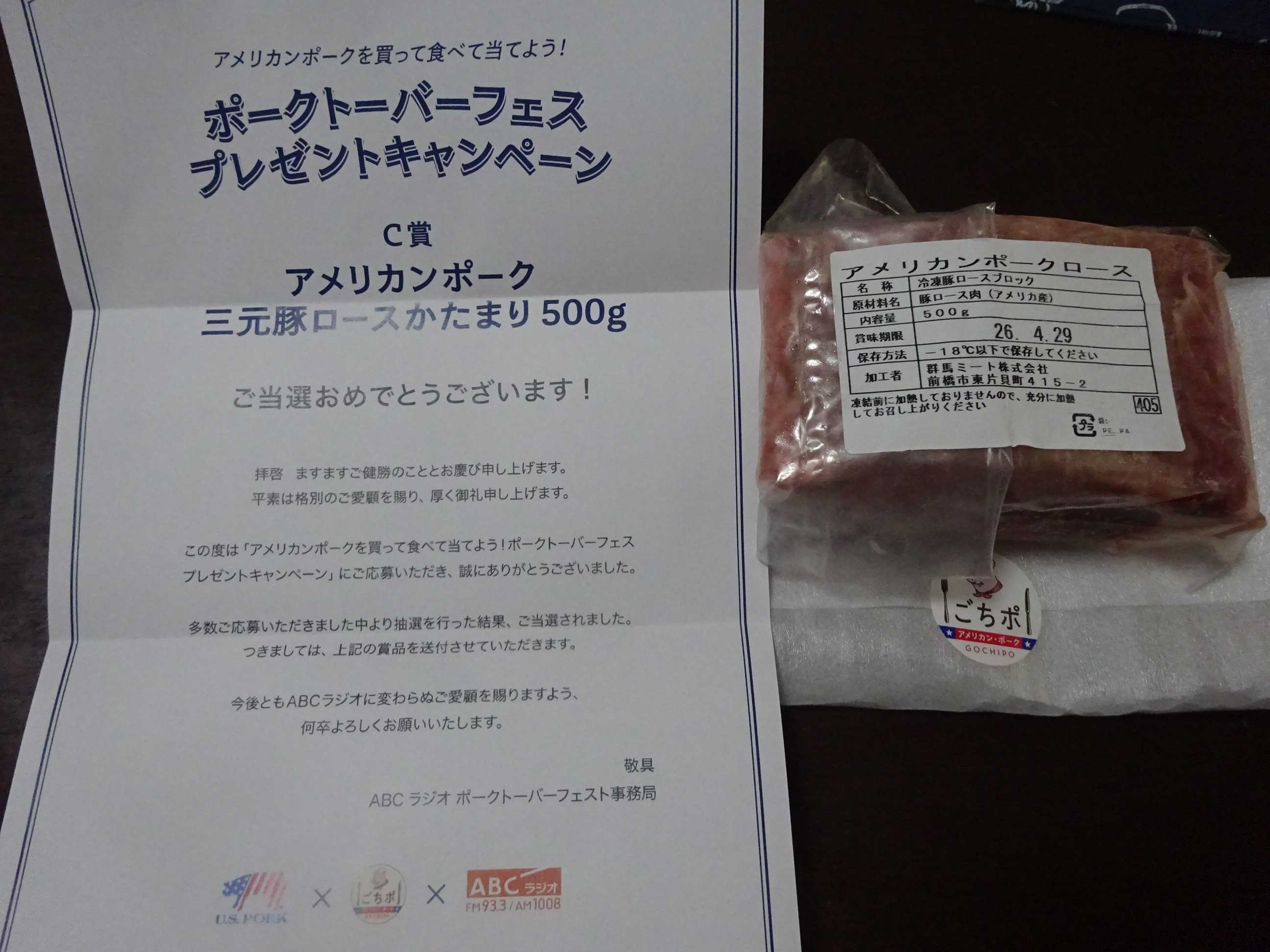2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

しっかりと生きる
何か人と変わったことをしようとしたときに、『こんなことをしたら、みんなどう思うだろう?』『変に思われるかな?』と考えたり、誰かが思いがけないことをしたときに、『なぜあの人はこんなことをしたのだろう?』と思うことがあります。 こんなふうな思いがよくある人は、自分の気持ちよりも他人の気持ちを優先して生きています。 「他人の気持ちを優先している」というと、何か善い人のように聞こえますが、実際は、他人の評価を上げるためにその場だけ他人の期待に合わせて自分をごまかして生きている、そして当然相手の人もごまかして生きている、ずる賢いやつ、とも言えるのです。 その生き方をどう表現するかどうかはどうでもいいことで、一番問題なのは、『その生き方は、自分を100%生きることができない』ということです。 いくら、一所懸命生きてもその努力は、他人の期待に合わせることに費やされますから、自分をしっかり生きることができないのです。 だから、がんばって生きているのに充実感があまりない。 他人に評価してもらったときだけ、充実感のような感じを味わいますが、他人の評価は、結局他人しだいですから、その充実感の裏には、いつも評価が下がる怖れを感じているのです。 いずれにしろ、自分を生きる満足感を味わえないのです。 人生をしっかり生きるためには、まず、自分の気持ちを優先することが必要です。 けっして、他人の期待や評価やアドバイスを無視するというようなことではないのです。 まず、自分の気持ちをしっかりと自覚すること。そして、全体の中でその気持ちを自分が納得できるように(つまり、ここでも自分の気持ちを優先して)調整させればいいのです。 幸せとは、自分を生きているという実感なのです。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 31, 2007
コメント(0)
-

感情と因縁
感情、たとえば、それが怒りだとすると、「怒りの原因はあいつが私をだましていたからだ」という言い方がされることがあります。 仏教に「因縁」という言葉がありますが、それは「直接的な原因」と「間接的な縁、きっかけ」という意味です。 つまり、一般に同じように捉えられている感情の理由を「因」と「縁」の二つに分けて見ているということですね。 多くの人は、感情の直接的な原因が自分の外側にあるという考え方をしています。 ですから、幸せになるために自分の外側を変える必要があるという結論になります。 悟りとは、その「因縁」の違いを正しく見ることができること、正しく考えることができることでもあります。 感情の真の原因は、自分の心、考えにあると見ているのです。 欲や囚われが感情の真の原因で出来事は、そのきっかけ(縁)に過ぎないです。 自分の外側を自分の思い通りに変ええることは大変難しいことですし、すべての人が満足することはまず不可能です。なぜなら、たとえば、「明日は晴れて欲しい」「明日は雪になって欲しい」というように対立する考えを持った人がいる可能性が高いですから、その両方を満足させるように外側を変えることは、まず不可能なのです。 ですが、自分の考えから、欲や囚われを手放すことはすべての人が同時に可能なのです。 そのことに気づくことが悟りなのです。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 29, 2007
コメント(0)
-

愛さずにはいられない
女優、石原真理子さんの本「ふぞろいな秘密」が話題になったようですが、その新聞広告に、「あの頃、私は愛さずにはいられないかった」みたいなコメントが載っていました。(確か(^^;) ぜんぜん、お勧めしない本ですが、(^^;この「愛さずにはいられない」という言葉が彼女の性格や行動の原因を物語っています。 「愛さずにいられない」というと、何かロマンチックな響きがしないでもないですが、私から言わせると、それは病的な傾向です。 実は、共依存の特徴のひとつに1.「何か」をしなければならないという強迫行動に突き動かされている。(ロバート・ヘムフェルト/フランク・ミナース/ポール・メイヤー 著水澤都加佐 訳『他人が気になって仕方ない人たち』PHP研究所 P25)というものがあります。 これが愛さずにいられない理由なのです。 ほかにも、・お酒を飲まずにいられない(アルコール依存症)・ドラッグが止められないとかがあります。 アルコールやドラッグなどは、アル中(アルコール中毒)という言葉があるように、その薬物に中毒している状態と、そうではなく、精神的に依存している状態とが混在しているために誤解されやすいのですが、共依存については、この中毒の部分を除外した精神的な依存の部分を言っています。 つまり、中毒していなくても、依存していれば共依存的な傾向ということです。 失恋や仕事がうまくいかないからと自棄酒(ヤケ酒)を飲むのも、その苦しみからお酒の力で逃げようとしているということで、共依存的状態といえるわけですね。 アルコールや薬物の場合、それに依存を続けることで、結果的に中毒をも引き起こし、両方が混在した状態になります。(逆にいうと、回復させようとするなら、中毒と依存症の両方のケアが必要だということです) しかし、その精神的な依存に着目すると・仕事を休むことができない(ワーカーホリック)・セックスへの依存・パチンコ依存症・ギャンブル依存症・虐待、・摂食障害、・手を何度も洗ってしまう癖、・物を数える癖、・物を正確に同じように並べる癖など、『えっ、こんなものまで』というくらい、いろいろとあります。 これをただ漠然と読んでも、心理学的な説明の知識を得るだけに過ぎません。 でも、この「~しないではいられない」という行動は、お釈迦さまがいう、「苦しみを超える(悟る)ためには、欲を手放すことが必要」という場合の、「欲望」のことだと気づくと話は大きく違ってきます。 仏教の悟りについては、何にも人によって語られていますが、それが一般の人に『ああ、そういうことなのか』と分りやすく説明されてはいません。 しかし、この共依存の特徴のひとつ「~しないではいられない」が悟りを妨げる煩悩といわれていたもののひとつだと分ると、仏教を科学的な視点から、もっと分りやすく紐解いていくことができるのです。 「お金をいくら手に入れても、もっともっととお金を欲しがるのが欲望だ」としているだけなのと、それが共依存の特徴であり、その表れなのだと理解しているのでは、対策が立つか立たないかの差になってくるのです。 お釈迦さまは、『多くの人を苦しみから救いたい』と願い、望みを持って、布教をしていましたが、それは、一般的な欲の概念からしたら、お釈迦さまの欲ということになるのではないでしょうか? しかし、そうなると、仏教自体が矛盾をはらんだ間違ったものということになりかねませんが、実際に高僧と言われるような人を見ると、仏教はそんないいかげんなものではなく、悟りというものが本当にあるらしいと思われます。 それについては、{「欲」の概念が、凡夫と覚者では違う、一般の人が「欲」と考えている概念対象が「悟った人には、二つに分かれて見えている」}と考えれば矛盾がなくなります。 私(ヒカリズム)の言葉で言えば、それは、「欲」と「望み」です。 その違いは、共依存が他者の評価を気にして他者の期待に応えようとしてしまう特徴がある。とわかると、一般的な概念の欲を分けて見るときに、基準が他者にあるか、自分にあるかという区別ができることも分ってきます。 そして、お釈迦さまが自灯明という言葉で「自分を中心にしなさい」と言った真意が見えてくるのです。 お釈迦さまは、「共依存から回復しなさい」と言ったのです。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 24, 2007
コメント(0)
-

自分探しの旅と無我
「自分探しの旅」という言葉があります。 よく考えてみると、自分を探しているのが自分なのですから、おかしな話です。 つまり、ここでいう「自分」というのは、探している自分とは違う概念の自分だということですよね。 「自分とは何か?」これは哲学的な問いでもあります。 あなたはこの問いになんと答えますか?主婦です○○会社の部長です小学校の先生ですetcそれは本当にあなたでしょうか? この問いに答えるためには、実は、基準となる前提をはっきりさせる必要があります。先ほどの答えは、社会の構成員としての自分の肩書きを答えたものといえます。 悟りで、無我の境地という言葉があります。石原慎太郎さんの「法華経を生きる」という本の中で、確か、「禅で無我になれというけれど、そんな難しいことは誰にでもできるというものではない」というような意味のことが書いてあったように記憶しています。(今、本が手元にないので、違っていたらすみません) 確かに「無我になる」というのは難しい気がします。自分であるのに、自分になるな、などというのは、できっこないという気もします。 しかし、禅の言葉というのは、二元対立を超えることを示す指なのです。「自分探しの旅」の「自分」と共通していますよね。 実は、心理学では、本当の自分と偽りの自分というものを概念化していることがあります。先ほどの主婦としての自分先生としての自分なとどいうのは、ユングのペルソナであるといえるでしょう。ごく簡単にいえば、仮面としての人格とでもいえば、いいでしょうか。仮面ですから、本当の自分ではない。その仮面の奥に本当の自分がいる。良き主婦になろうと努力し、でも、掃除もダメ選択もダメ、料理もダメ、良き主婦になろうとしてもドジばかりで、落ち込み、もしかしたら、ウツになってしまうこともあるかも。良き主婦というのは理想の自分ともいえますが、偽りの自分ともいえます。A.W.シェフは、その著書「嗜癖する社会」斎藤学(さとる):監訳 の中で、社会自体が、その構成員(つまり私たち)にある程度の共依存であることを強いていると言います。 簡単にいえば、社会という機構自体が社会の構成員に良き主婦であれ、良き先生であれ、etcという社会機構を維持するために必要な仮面を生きることを強いている部分がある、ということです。確かに、社会の最小単位である家族の中で、すべての親がたとえば、子育てを放棄したら、社会自体が成り立たなくなります。 この仮面(偽りの自分)自体が問題なのではありません。 共依存という訳語を作った斎藤学(さとる)さんは、共依存と共依存症という言葉を分けて使っています。 日常生活に問題が出るほど生きにくさを感じるものを共依存症と呼びわけているのです。 簡単に言うとたとえば、「良き主婦でなければならない」と強く思い、自分をガチガチに枠にはめて、本当の自分を押し殺して生きていて、生きにくさを感じていると心を病むことになります。「良き主婦でありたいなあ」(A)と達成できるかどうかにこだわらない思いで努力しているだけなら生きがいにこそなれ、心を病むことはないのです。 さて、「無我である状態」とは、そのような「良き主婦でなければならない」とか「良き主婦でありたいなあ」という思いをいったん手放した状態なのです。 そのとき、人は状況と一体化します。淡々とこなしている、淡々と生きている、という感じでしょうか。そして、そこから再び「良き主婦でありたいなあ」(B)に戻ってくる。 そうすると一見しただけでは、Aの状態と区別がつかない。 ところが、Aの状態は、ともすれば結果に執着し、「良き主婦でなければならない」になりかねない。 それに比べてBの状態は、戻っても淡々とした状態なのです。 うろ覚えなのですが、確か、栄西だったかが、その師が亡くなったとき、おいおいと大声で泣くのを見て、周りの人が、「あなたは悟った人だと思っていたが、普通の人と同じように泣くのですか?」と疑問を呈したそうです。それに答えて「もちろん、悲しいときには泣く」と答えたそうです。 実は、この違いは、Aは、社会の要請に応えようとする思いからでているもので、Bは、自分で選んだものなのです。Aの場合、社会の要請がきつくなれば、場合によっては、「良き主婦でなければならない」も戻ってしまう。Bは、周りの期待や要請は関係ありませんから、周りに影響されることがない、そして、自分で選んでいるのですから、苦しかったりして嫌になれば選ぶのをやめるはずです。つまり、栄西(だったと思うのですが、誰か知っていたら教えてください)が悲しんで泣いていたのは、自分がそれをしたかったからなのです。自分が中心それが、自灯明ということです。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 20, 2007
コメント(0)
-

バラバラ殺人事件
最近、残念なことに連続してバラバラ殺人事件が起きてしまいましたね。 そのうちの一件の容疑者の実家が、なんと私の町内だったので、うちにもテレビ局の人が聞き込み?にやってきました。 事件が発覚した日は、容疑者の実家の前に各テレビ局のカメラマンとかが張りついていて一時はかなり騒然としていました。今も徹夜でずっと張り込んでいます。大変ですね。 ところで、ニュースやワイドショーでは、その原因を浮気や酒癖の悪さ、暴力など表面的な直接原因を追究するにとどまっています。 刑事事件の原因としては、それでいいのでしょうが、こういう事件をなくそうと思うなら、それらの原因が、すでに共依存の結果なのですから、さらに踏み込んで共依存の原因に対して対策しなければならないでしょう。供述の中で「私の存在を否定するような、自分が今までしてきたことを全然認めてくれなかった」という部分がありますが、これは、他者の評価で自分の存在価値を保とうとする共依存の特徴がでていると思います。夫婦の生活ぶりや相手を選ぶ動機、生き方なども他者の評価を気にして生きているところが現れていますよね。 他人より秀でることで、他者の評価をあげて自分の価値をあげようとする生き方は、決して人を幸せにすることは無いでしょう。 それは、一見幸せそうに見えても、常に他者に勝ち、他者の評価を得なければならない、つまり闘い続けないといけないのですから、心に平安が訪れることは無いからです。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 14, 2007
コメント(0)
-

言葉と悟り
悟りは言葉では表せないといいます。それはそのとおりです。体験は、同じ体験をしたものが、その体験を指し示すことで理解できるものだからです。 「定義がナンボのもんじゃい!」と乱暴なことをいう人もいますが(^^;言葉それ自体ではなんの役にも立ちません。 言葉とは、意味やある概念を指し示すために、口で言ったり字に書いたりする単なる記号に過ぎないのです。 外国語などを考えればわかると思いますが、知らない外国語は、単なる記号にしか見えません。 運転免許をとるときに、標識の意味を覚えますが、標識自体は、単なる記号で、意味を覚えていない人には、推測できる場合もありますが、基本的にどんな意味も示していません。 大切なのは、この言葉という記号を使う人が、その記号が指し示す意味や概念を覚えることです。 しかも、私たちは、ある範囲の概念を自分で選んで調整しています。 たとえば、「いい子でいる」という言葉が指し示す概念は、親の前と友達の前と恋人の前では別の状態ではありませんか? そこに共通点はあります。だからこそ、ひとつの言葉でそれらの概念が指し示されているのです。 定義するとは、概念の内容を限定し、他の概念から区別することです。 今の例で言えば、「(概念があいまいなんだけど)良い子ってどういう意味よ?」それに答えることが定義するってことですよね。(ちなみに共通するものは、相手の要求に従うこと)(つまり、「良い」とは、要求される基準を満たしていること) 悟りのような一般的に明確に概念化されていないものについては、その言葉が指し示す概念を受け取る側がはっきりもっていないのです。 それは食べたことがないものの味を概念化できないのと同じことです。 しかし、そこを近似体験、部分体験から指し示すことができます。 それが月をさす指ということ。 平面状を線で指し示すことができれば、二本の線の交点にそれはあります。 線にぶれがあり、幅があったり、方向が微妙にずれているときは、二本以上の指し示す線が必要でしょう。 三次元空間であれば、最低三本の線の交点です。 悟りに対しては、いったい何本で指し示せばいいのか、それはわかりませんが、複数の指し示す言葉の先にあるものを見つめて、絞っていくことで、悟りを開くことができます。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 10, 2007
コメント(1)
-

タオを生きる
幸せになるにはどうしたらいい? それは簡単なこと。幸せを選びさえすればいい。 ん?むずかしい? それはそうだ。コップに新しいものを入れるには、まずコップを空にしなくちゃならないんだよ。 そんな簡単なことはわかっているけど、『今のままで幸せ』を入れるために『今のままでは不幸せだ』という思いを手放せないのは、なぜなんだい? 今の状態、それ自体に意味などありはしない。 あなたが今の状態に極をなす状態に「幸せ」と名づけたから、意味付けたから、今の状態があなたにとって「不幸せ」に感じられているに過ぎない。 ただあるがままに眺めてごらん。 そのとたんに、あなたのコップは空になってしまう。 さあ、空のコップにはなんでも入れられる。あなたの好きなものを入れたらいい。ためしに、これを入れてごらん。 「私は幸せです、ありがとうございます」 ほら、さっきまで、幸せじゃないと思っていた今が、幸せになっただろう? どうだい、からっぽってすごいだろう! ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 10, 2007
コメント(0)
-

傷ついた天使へ
君は今、傷ついて輝きを失ってしまったでも、私には見えるよ輝く天使が本当は、人は誰でも光り輝く存在なんだよただ、それを忘れてしまうときがあるだけなんだ人は、いつだって誰だって、すぐにその輝きを取り戻すことができるそして、その輝きを他の誰かにも与えられるんだだから、誰だって本当は輝く天使なんだよ■自分らしく輝くことそれは誰かから刷り込まれた「こうあるべき」という正しさをちょっとだけ、わきにおいて、自分が正しいと感じることを選ぶだけでできるんだ。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 6, 2007
コメント(0)
-

母親失格
今日からテレビで始まった昼の連続ドラマ「母親失格」を偶然見ました。 今、ダイヤモンド社の「こころのチキンスープ」を読んでいました。 その中で、大学生の調査で、アメリカのあるスラム街で育った子供たちの将来には期待できないと思われていたのに、180人のうち176人が人並み以上の成功を収めていたという奇跡のような結果がありました。 その当事者たちに成功した理由を尋ねると、誰もがある先生のおかげだと言ったのです。そして、その先生にいったい何をしたのかと尋ねるとパッと顔を輝かせ、口元に微笑を浮かべると「とても簡単なことです。私は生徒たちを愛したのです」と答えたのでした。 この場合の「愛すること」それは、子供のあるがままの存在価値を認めることです。そして、可能性を信じることです。 母親失格とは、何が失格かと言えば、子供のあるがままの存在価値を認めることができないことでしょう。 そして、それができないのは、共依存の連鎖でその母親自身があるがままに愛されていなかったから。 自分のあるがままを認められない人が、他人のあるがままを認められるはずがありません。 なぜなら、同じ価値観で判断するからです。 大切なのは、まず自分を本当に愛すること。この場合の本当にとは、何ができる、どこが優れているではなく、あるがままに、ということなのです。 愛・・・それは、あるがままを受け容れることなのです。 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 4, 2007
コメント(2)
-

今を生きる
今を生きるとは、結果ではなくプロセスを重視して生きることです。 どうやればそれができるかというと、誰かの期待に応えようとして行動すると、それは自ずと結果を重視することになります。 そうではなく、自分がしたいことをするとそれは自ずとプロセスを生きることになるのです。 つまり、今を生きるとは、「自分を生きる」ということなのです。今を生きる、プロセスを生きる、自分を生きる、言い方は違っても、それらは同じことなのです。 悟るということは、それが体感的に感じられるということです。 すでにそこを生きて体験しているから、体感的に感じられるのです。 それを踏まえて、道元のこの言葉を読むとその意味が見えてくるのではないでしょうか? 到達地点と道は一つである。 道元 ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 3, 2007
コメント(1)
-

元旦
元旦とは、一月一日のことではなく、その朝のこと。 新しい年になりました。あけましておめでとうございます。m_ _m 元旦の「旦」の字の「日」の下の「一」は、水平線を意味し、海から昇ったばかりの状態を示しているので朝ということになんですね。 さて、元旦はなぜか気も引き締まり、いつもと違う感じがするものです。 でも、動物たちや違うカレンダー、たとえば陰暦で生活している人には、今日は特別な一月一日ではないわけですから、気の持ち方も違うはずです。 つまり、私たちの心、気持ちというものは、そのように外で勝手に起きていることを自分の中の考えで色付けして解釈して、その解釈によって心が変化しているのです。 朝、飲んだお茶に茶柱が立ってた、『これは正月早々縁起がいい(^o^)』とうれしくなるのも、自分の考えに基づく解釈がなせるわざ。 基本的にどういう考えを持っているかがその人のすべてを決めていると言っても過言ではないのです。 新年の初めに当たり、『今年はこれまでとは違った自分、これまでより成長した自分になろう!』と決心された方も多いことでしょう。 それを効果的に実行するためには、まず、これまでの自分を習慣付けていた考えを改めることです。こうありたい自分を創造できる目的に合った考えを選択することです。 基本的な考えを望むものに改めれば それに見合った行動に変わります。 日々の行動が変われば、それが良い習慣となります 習慣が良いものに変われば 望む人格に変わります 望む人格に変われば 人生がよりすばらしいものに変わります ■今回のブログはいかがでした?(^-^) 『まあ、いいんじゃない(^^)』と思われたら、 ランキングボタン↓を押してね(^^)♪
Jan 1, 2007
コメント(3)
全11件 (11件中 1-11件目)
1