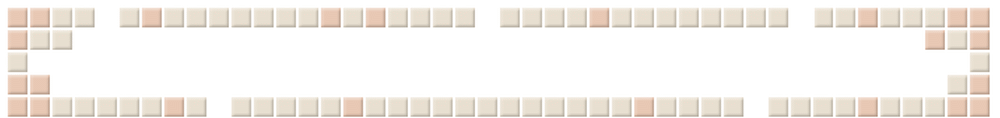全て
| カテゴリ未分類
| 占い
| 占いや人生相談
| 恋愛鑑定
| 親子の関係
| 人間関係
| 二度のお墓の移転
| 地デジ用デザインアンテナ
| 生き方
| 日常生活
| 読書
| 食器の断捨離
| 国語
| 暦
| 英語
| オランウータン
カテゴリ: カテゴリ未分類
1.妻
2.家内
3.かみさん (上さん)
4.女房
5.山の神
6.嫁
とりあえず、上に6通り掲(かか)げてみました。実は、この中に、明らかに間違っているのがひとつあります。皆さんは、おわかりでしょうか。
では、順に解説してまいります。
2の家内については、実は、私の父が、よく使っていた表現でしたね。私の母は専業主婦でしたから、文字通り、「亭主が家の外で、妻が家の内」という意味では、実人生に合致していましたね。
3の「かみさん」は、テレビで作曲家の 宇崎竜童(うざき りゅうどう)さんが、「うちのかみさんです」と奥様を紹介していらっしゃいましたね。「かみさん」は、字は「上さん」と書きます。
つまり、上(かみ)さんは、御上(おかみ)さんで、商家などの女主人を呼んでいたのが語源です。その後、親しい間柄で、「僕が主人じゃなくて、こちらが女主(おんな・あるじ)さ。こっちがお上(かみ)で、僕が尻に敷かれていて、僕が下だよ」という冗談や卑下から、自分の妻のことも言うようになったみたいです。
だから、「うちの上(かみ)さんです」と紹介する場合は、「亭主関白ではなくて、妻が上です」くらいの、ブラック・ユーモアがこめられているのでしょうね。あくまでも親しい男友達などに、ふざけて紹介していたのが、上(かみ)さんの使い始めでしょうね。
4の「女房」ですが、なかにし礼さん(作詞家)が、この表現を使っていましたね。NHKの歌謡番組で、「『石狩挽歌』の作詞ができた時は、思わず女房に、できたぞぉと叫んでいました」とおっしゃっていました。
皆さんは、右心房右心室、左心房左心室をご存知ですよね。この表現でおわかりの通り、房は部屋を意味します。
平安時代の貴族社会で、宮中に仕える女性の使用人たちの中で、自分専用の部屋を持っている人を「女房(にょうぼう)」と呼んでいました。
清少納言や紫式部なども女房でした。
妃(きさき)に仕える女性を女房と呼んでいたために、「部屋つきの女性だから偉い」あるいは、「偉いから自分の部屋を持っている」と思われていたようです。女優さんの世界で大部屋女優という表現があるらしいですが、それも名残(なご)りでしょうかね。
5の「山の神」は、妻として正しい表現です。私の知る範囲では、新聞記者や学者、教育者の男性たちが、「わが山の神」と言って、奥様を、人に紹介していらっしゃいますね。
山は土地であり大地ですからね。地を支配して、五穀豊穣(ごこく・ほうじょう)を司(つかさど)るのは女の神とされていたそうです。そして、山の神は女性と考えられていたことから、女の神様(山の神)が嫉妬をしないように、男性の入山(にゅうざん)は許されるけど、人間女性は(入山を)禁じられた山が多かったようです。いわゆる女人禁制です。
最後になりましたが、6の「嫁」。これは、息子の妻という意味ですから、明らかに間違いです。
20代や30代の男性で、「僕の嫁」とおっしゃる人がいらっしゃいますが、嫁というのは「(親からみた)息子の妻」という意味です。だから、自分の配偶者という意味で嫁を使うのは明らかに誤用です。
上には掲(かか)げなかったですが、私の母は、世間で、「うちの愚妻(ぐさい)です」と配偶者を紹介する男性に出会うと、「教養がある男性だな」と敬服するらしく、母にとって愚妻は好きな表現だそうです。
文責 占いイズム ルビー (チャット鑑定担当)
私は、この日記を中学生や高校生にも読んでもらいたい主旨で執筆しています。
↓ クリックして下さると、励みになります。 皆さんの誠意に感謝します。
ブログランキング【くつろぐ】
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.