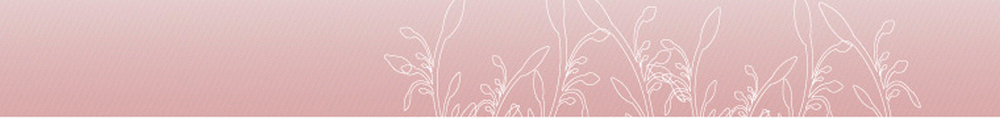PR
Calendar
Freepage List
Keyword Search
精神・発達・知的障害の障害年⾦不⽀給率が約1.9倍に急増!
東京都自閉症協会×発達障害当事者協会が共同声明を発表
6/16(月)厚生労働省に共同声明を提出し、記者会見を行いました
厚生労働省が6⽉11⽇に公表した
では、
精神・発達・知的障害の障害年⾦不⽀給率が
約1.9倍に急増という実態が明らかになりました。
看過しがたい深刻な事態を受け、
東京都自閉症協会(理事長 杉山雅治)
と発達障害当事者協会(代表 新 孝彦)は、
共同声明を6月16日(月)に厚生労働省へ提出しました。
精神・発達・知的障害の障害年⾦不⽀給率が
約1.9倍に急増という深刻な事態
障害年金の不支給判定が急増しているという報道を受け、
厚生労働省は6⽉11⽇に
「令和6年度の障害年⾦の認定状況についての調査報告書」
を公表しました。
報告書によると、
精神・発達・知的障害の障害年⾦不⽀給率が
前年度6.4%から12.1%へと
約1.9倍に急増していることがわかりました。
また、不⽀給
「目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」
又は
「目安が2つの等級にまたがるものについて、
下位等級に認定され不支給となっているケース」
の割合が75.3%となっている実態も明らかになっています。
改善と是正を求め、
東京都自閉症協会×発達障害当事者協会が共同声明を発表
本来であれば⽀給される可能性があった⽅々、
専⾨医の診断では⽀給相当と判断された⽅々の
4分の3が不⽀給になっている現状は看過できません。
この深刻な状況を受け、
東京都自閉症協会は発達障害当事者協会と共同で、
厚生労働省に状況の改善と、
今度の是正を求め、声明文を提出しました。
また、6月16日(月)に記者会見を実施。
不支給率が倍増している背景には、
現行のシステムに課題があることや、
発達障害への無理解が背景にあることを訴えました。
精神・発達・知的障害のニーズを配慮した評価基準の見直しを!
報告書にある通り、内部及び外部障害は、
医学的な検査数値等の客観的な指標が
障害認定基準に定められているため、
支給決定の公平性が保たれています。
一方、精神・発達・知的障害については
医学的な指標だけでは判断することが難しく、
極めて個別性の高い社会的なハンディキャップがあります。
生活上のさまざまな困難について現行の認定基準では、
公平に判断できないことが、
今回の異常事態の原因となっている可能性は否定できません。
これを機に、障害年金に関して
関係機関や当事者団体へのヒヤリングを進めるとともに、
当事者を含めた障害年⾦専⾨の部会の開催を⼀⽇も早く求めます。
発達障害当事者の実態と声を反映した制度改⾰を⾏うことで、
すべての発達障害者が
希望を持って⽣活できる社会の実現を望みます。
【共同声明】厚⽣労働省「障害年⾦認定状況調査報告書」を受けて
発達障害者の⽣存権を脅かす深刻な実態の改善を緊急に求めます
令和7年6⽉11⽇に厚⽣労働省が公表した
「令和6年度の障害年⾦の認定状況についての調査報告書」
のサンプル調査により、
23年度に⽐して24年度は内部障害・外部障害の不⽀給割合は
ほぼ横ばいなのに対し、
精神・発達・知的障害の障害年⾦不⽀給率が
前年度6.4%から12.1%へと約1.9倍に急激に悪化した
深刻な実態が明らかになりました。
私たち発達障害当事者・家族は、
この事態を重く受け⽌め、政府に対して緊急の改善を求めます。
精神障害・発達障害・知的障害に偏って不⽀給が急増した原因の説明を求めます
わずか1年で精神・発達・知的障害に限って
不⽀給率が約1.9倍になるという異常事態には、
必ず明確な原因があるはずです。
なぜこのような急激な変化が起きたのか、
詳細な説明と原因についての⾒解の報告及び再発防⽌策を求めます。
ボーダーケースの75%が不⽀給という異常な状況
報告書によると、不⽀給となった85件中64件(75.3%)が
「(⽀給とされる)ガイドライン⽬安より厳格判定」
によるものです。
本来であれば⽀給される可能性があった⽅々、
専⾨医の診断では⽀給相当と判断された⽅々の4分の3が
不⽀給になっている現状は看過できません。
⾏政判断の基本原則である「疑わしきは市⺠ の利益に」を貫き、
ボーダーケースでは⽀給⽅向で判断する原則の確⽴を求めます。
特に⽣存に関わる社会保障制度では、この原則がより重要になります。
不⽀給時の理由説明を異議申し⽴て可能な内容に
報告書にもあるように、理由付記⽂書が
「申請者にとって分かりにくい記載」
で⾏政⼿続法第8条・第14条及び
最⾼裁判例が求める⽔準を満たしておらず、
事実上異議申し⽴てが不可能になっているケースがあり、
不⽀給の場合はその理由の開⽰が
異議申し⽴て可能な程度に具体的であることを求めます。
就労=困難解消という重⼤な誤解の是正を
報告書に
「週4⽇飲⾷店で援助なくバイトしており、通勤も⽚道1時間できている」
として不利益判定を受けた事例が記載されていますが、
発達障害への根本的な無理解があります。
発達障害者の就労継続には、
健常者の何倍もの精神的エネルギーが必要です。
感覚過敏による苦痛、コミュニケーションの困難、
実⾏機能障害など、⾒えない困難との毎⽇の闘いがあります。
働いているからこそ、
より多くの⽀援が必要な場合が多いのです。
就労の「質」を詳しく評価し、
就労以外の⽣活への影響を考慮し、
持続可能性を重視した適切な評価基準の策定を求めます。
時代遅れの認定基準を現代に合わせた改定を
現在の障害年⾦認定基準である国⺠年⾦法施⾏令別表の
1級9号・2級15号包括条項は、
1959年に制定された古い基準です。
「働く」か「働けない」かの⼆者択⼀的な発想で、
現代の多様な働き⽅に全く対応していません。
私たち発達障害者が求めているのは、
⼼⾝の状態に合わせた無理のない働き⽅と、
不⾜分を年⾦で補う安⼼できる⽣活設計です。
部分的就労を前提とした認定基準、持続可能性を重視した評価、
⽣活の質を考慮した基準、
多様な働き⽅に対応した基準への抜本的改定を求めます。
法的・国際的義務の遵守を
障害者基本法第2条は障害者を
「障害及び社会的障壁により継続的に
⽇常⽣活⼜は社会⽣活に
相当な制限を受ける状態にあるもの」
と定義していますが、
現在の認定基準は「社会的障壁」の視点が完全に⽋如し
、機能障害のみを重視する医学モデルに偏重しています。
また、2022年10⽉の国連障害者権利委員会総括所⾒では
「社会モデルに基づく制度設計が必要」
とされています。
国内法と国際法の両⽅の義務を果たすため、
特に精神・発達・知的の各障害については
医学モデルのみならず
社会モデルを取り⼊れた認定基準への転換を求めます。
当事者を含めた専⾨部会の早期開催
及び当事者団体へのヒアリング
これらの様々な問題を解決するために、
既に厚⽣労働⼤⾂が国会答弁で検討を表明したところの
当事者を含めた障害年⾦専⾨の部会の開催を⼀⽇も早く求めます。
また、専⾨部会の開催のみならず、
障害年⾦に関する当事者団体へのヒアリングを⾏い、
発達障害当事者の実態と声を反映した制度改⾰を⾏うことで、
すべての発達障害者が
希望を持って⽣活できる社会の実現を望みます。
◆ 東京都自閉症協会
・代表者名 杉山雅治
・所在地 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3丁目43−11 福祉財団ビル 7F
・公式HP https://autism.jp/
・主な活動 自閉スペクトラム症と家族、まわりの人たちが幸せに暮らせる世の中をめざす。
◆発達障害当事者協会
・代表者名 新 孝彦
・所在地 東京都新宿区西早稲田2-18-21羽柴ビル202
・公式HP https://jdda.or.jp/
・主な活動 当事者の「声」を集め共生社会づくりをともに考える。
以上
【PRTIMES】 
6月16日(月)厚生労働省に声明文を提出
決まり切ったことがきちんと適用されなくなると、
あちこちに弊害が起きますね。 ☄
にほんブログ村
にほんブログ村
-
「自閉症の兄がいたから、今の私がいる」… 2025.10.20 コメント(9)
-
大阪万博が教えてくれた大切なこと 〜発達… 2025.10.19 コメント(8)
-
「専門学校を強制的に退学させられた」 30… 2025.10.18 コメント(9)