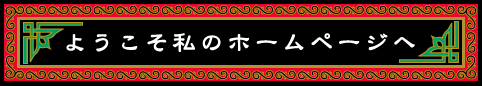フリーページ
全て
| カテゴリ未分類
| 新着テキスト
| 今日にちなむ
| 修正テキスト
| リンクのない新着テキスト
| 明治世相百話(リンクのない新着テキスト)
| お知らせ
カテゴリ: 明治世相百話(リンクのない新着テキスト)
明治狂歌の盛衰記
昔髪しのぶ天明調の復活
蜀山以来平民の気を吐いた狂歌も、今は一部の人々によって辛くも命脈を保つ有様。最近やや復興の兆もあるが、明治の中頃は元老の諸大人始め若手も加わって、相応に狂歌界も賑わった。その思い出を少々。
明治の世も治まって八、九年頃から、狂歌もぽつぽつ復活、代々の判者四世絵馬屋、二世琴通舎、面堂、春の屋始め梅屋、文の屋、弥生庵、岩上亭、桃の屋などを先達に月次会の催し、連中も本町側、小槌側、浅草側、あるいは八雲連、寿連、糸巻連そのほかいろいろ。十六、七年頃には、発会とか判者披露とか折々の大会に出詠の狂歌山をなし、いよいよ本格の繁昌。なかんずく天明ぶりの本町側が盛んで、十七年に『狂歌共楽集』を始め絵入りの『月並集』を出版、少し気のある連中はこうなると己れも一つと頭を捻《ひね》る。
二十年代には花鳥風月のほか、時事問題も詠み込まれ、大いに狂歌の特長を発揮した。その後、興雅会とか鶯蛙会とか各派聯合の会も起り、神田の今金、鍛冶橋の油屋などに時々集合、二十八年に出た『鶯蛙狂歌集』はその産物で、明治狂歌の代表的出版。そのうち元老連は追い追い浮世の花を見捨て斯界ようやく寂寞、三十年から三十五、六年を全盛期として以後は天明ぶりの妙味も世に合わず、|執心《しゆうしん》の輩も減る一方。
初名|和歌《わか》の門《と》鶴彦、後改めて和歌の屋となった先代大倉男は人も知る狂歌の先達、江戸時代から斯道で苦労した本町側の大先輩、その後援もあって大正五年に出来たのが面白会、風雅な維誌『みなおもしろ』を発行して同十四年まで、十年近く続いたのは狂歌界空前のお手柄、お蔭で盛り返した狂歌の一党、ちかごろ鶯蛙会の再興、第二の元老蟹の屋、秋の屋、花の屋の諸老が踏み止まって昔をしのぶ風流陣。
昔髪しのぶ天明調の復活
蜀山以来平民の気を吐いた狂歌も、今は一部の人々によって辛くも命脈を保つ有様。最近やや復興の兆もあるが、明治の中頃は元老の諸大人始め若手も加わって、相応に狂歌界も賑わった。その思い出を少々。
明治の世も治まって八、九年頃から、狂歌もぽつぽつ復活、代々の判者四世絵馬屋、二世琴通舎、面堂、春の屋始め梅屋、文の屋、弥生庵、岩上亭、桃の屋などを先達に月次会の催し、連中も本町側、小槌側、浅草側、あるいは八雲連、寿連、糸巻連そのほかいろいろ。十六、七年頃には、発会とか判者披露とか折々の大会に出詠の狂歌山をなし、いよいよ本格の繁昌。なかんずく天明ぶりの本町側が盛んで、十七年に『狂歌共楽集』を始め絵入りの『月並集』を出版、少し気のある連中はこうなると己れも一つと頭を捻《ひね》る。
二十年代には花鳥風月のほか、時事問題も詠み込まれ、大いに狂歌の特長を発揮した。その後、興雅会とか鶯蛙会とか各派聯合の会も起り、神田の今金、鍛冶橋の油屋などに時々集合、二十八年に出た『鶯蛙狂歌集』はその産物で、明治狂歌の代表的出版。そのうち元老連は追い追い浮世の花を見捨て斯界ようやく寂寞、三十年から三十五、六年を全盛期として以後は天明ぶりの妙味も世に合わず、|執心《しゆうしん》の輩も減る一方。
初名|和歌《わか》の門《と》鶴彦、後改めて和歌の屋となった先代大倉男は人も知る狂歌の先達、江戸時代から斯道で苦労した本町側の大先輩、その後援もあって大正五年に出来たのが面白会、風雅な維誌『みなおもしろ』を発行して同十四年まで、十年近く続いたのは狂歌界空前のお手柄、お蔭で盛り返した狂歌の一党、ちかごろ鶯蛙会の再興、第二の元老蟹の屋、秋の屋、花の屋の諸老が踏み止まって昔をしのぶ風流陣。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[明治世相百話(リンクのない新着テキスト)] カテゴリの最新記事
-
薄田泣菫「茶話」「ニツク・カアタア」 2006年02月05日
-
薄田泣菫「茶話」「栖鳳の懐中時計」 2006年02月05日
-
薄田泣菫「茶話」「食物の味」 2006年02月05日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.