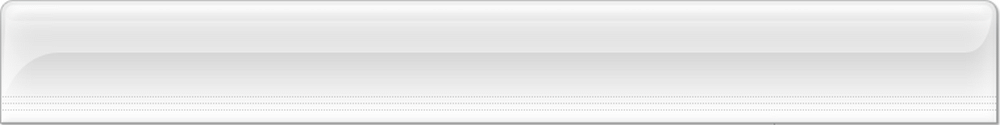カテゴリ: 考えごと
このところ、「その人が何を言っているか」という内容そのもの以上に、「その人がどういう語り口で語るか」ということの方が、何倍も何倍も重要だということを痛感する。
私が心地よいと感じる語り口の基準は二つある。
ひとつは、「自分が間違っているかもしれない」ということを、どこかで考えながら語る、ということ。
もちろん、人がもつ意見は、その人の経験や知識や様々なものに基づいて出てくるものだから、ある側面では、間違いなく真実である。
しかし重要なことは、それ以上に、わたしたちの考え方や発想が「常識」や「パラダイム」に規定されているということだ。
「絶対の真実」などない。
「絶対の真実」を伝えると思われている科学ですら、そうである。
アインシュタインだったか誰だったか有名な科学者が、「科学者の業績とは、次の新しい理論が生まれるまでできる限り長く応用される(そしてできれば、次の理論ができたあともその一部として生き延びられる)理論を作り出すということに他ならない。」というようなこといっている。
その時代時代で信じられてきた「絶対の真実」が、いとも簡単に崩れ去り、塗り替えられてきた事実は、歴史を見れば瞬時にわかることである。
だから、私は「自分が絶対に正しい」と信じ、「結論が最初から決まっている」人の語り口は好まない。
「自分が絶対に正しく」「結論が最初から決まっている」という人との会話は、コミュニケーションにならないのだ。
会話を通じたコミュニケーションというのは、それ自体が非常にクリエイティブな作用で、相手と自分とのやり取りの中で、新しい考えを一緒に作り出していく作業である。
話している過程で、今まで自分の中で思いもつかなかったような発想や結論が出てきた経験を誰しも体験したことがあるのではないだろうか。
(もしもないなら、自分が「閉じたコミュニケーション」をしているのではないかと、疑った方がいいと思う。余計なお世話だが。)
しかし、「結論が最初から決まっている」人と話すと、言葉を重ねれば重ねるほど、コミュニケーションの無力感を感じてしまい、相手が理解からほど遠くなっていく。
それは、新しい考えをともに作る、という発想がないからではないだろうか。
よって、たとえ、どのような意見をもっていようとも、「自分は間違っているかもしれない」という可能性を常に残した語り口をもつ人、
また、どれほど意見が違おうとも「相手の話に一部の理を見つけよう」という努力をする、という語り口を持つ人を、私は好むのである。
この態度さえあれば、どれほど意見が違っても、友達になれるし、お互いを尊重し合える。
繰り返すが、大事なことは「何を語ったか」ではない。「どう語ったか」なのである。
私が心地よいと感じる語り口の基準は二つある。
ひとつは、「自分が間違っているかもしれない」ということを、どこかで考えながら語る、ということ。
もちろん、人がもつ意見は、その人の経験や知識や様々なものに基づいて出てくるものだから、ある側面では、間違いなく真実である。
しかし重要なことは、それ以上に、わたしたちの考え方や発想が「常識」や「パラダイム」に規定されているということだ。
「絶対の真実」などない。
「絶対の真実」を伝えると思われている科学ですら、そうである。
アインシュタインだったか誰だったか有名な科学者が、「科学者の業績とは、次の新しい理論が生まれるまでできる限り長く応用される(そしてできれば、次の理論ができたあともその一部として生き延びられる)理論を作り出すということに他ならない。」というようなこといっている。
その時代時代で信じられてきた「絶対の真実」が、いとも簡単に崩れ去り、塗り替えられてきた事実は、歴史を見れば瞬時にわかることである。
だから、私は「自分が絶対に正しい」と信じ、「結論が最初から決まっている」人の語り口は好まない。
「自分が絶対に正しく」「結論が最初から決まっている」という人との会話は、コミュニケーションにならないのだ。
会話を通じたコミュニケーションというのは、それ自体が非常にクリエイティブな作用で、相手と自分とのやり取りの中で、新しい考えを一緒に作り出していく作業である。
話している過程で、今まで自分の中で思いもつかなかったような発想や結論が出てきた経験を誰しも体験したことがあるのではないだろうか。
(もしもないなら、自分が「閉じたコミュニケーション」をしているのではないかと、疑った方がいいと思う。余計なお世話だが。)
しかし、「結論が最初から決まっている」人と話すと、言葉を重ねれば重ねるほど、コミュニケーションの無力感を感じてしまい、相手が理解からほど遠くなっていく。
それは、新しい考えをともに作る、という発想がないからではないだろうか。
よって、たとえ、どのような意見をもっていようとも、「自分は間違っているかもしれない」という可能性を常に残した語り口をもつ人、
また、どれほど意見が違おうとも「相手の話に一部の理を見つけよう」という努力をする、という語り口を持つ人を、私は好むのである。
この態度さえあれば、どれほど意見が違っても、友達になれるし、お互いを尊重し合える。
繰り返すが、大事なことは「何を語ったか」ではない。「どう語ったか」なのである。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[考えごと] カテゴリの最新記事
-
ブランドを作るのは人の思いなんだと改め… March 12, 2008 コメント(87)
-
複雑なものを複雑なまま理解する March 10, 2008
-
自分を知りたければ友達を見よ March 9, 2008
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
おざーんblog
おざーんさん
My wife is ... にわとりのあたまの裏さん
にわとりのあたま にわとりのあたまさん
●尾崎友俐● ◇尾崎'友俐◇さん
今宵もガイショクざ… 東京スヌーピーさん
My wife is ... にわとりのあたまの裏さん
にわとりのあたま にわとりのあたまさん
●尾崎友俐● ◇尾崎'友俐◇さん
今宵もガイショクざ… 東京スヌーピーさん
Comments
Freepage List
© Rakuten Group, Inc.