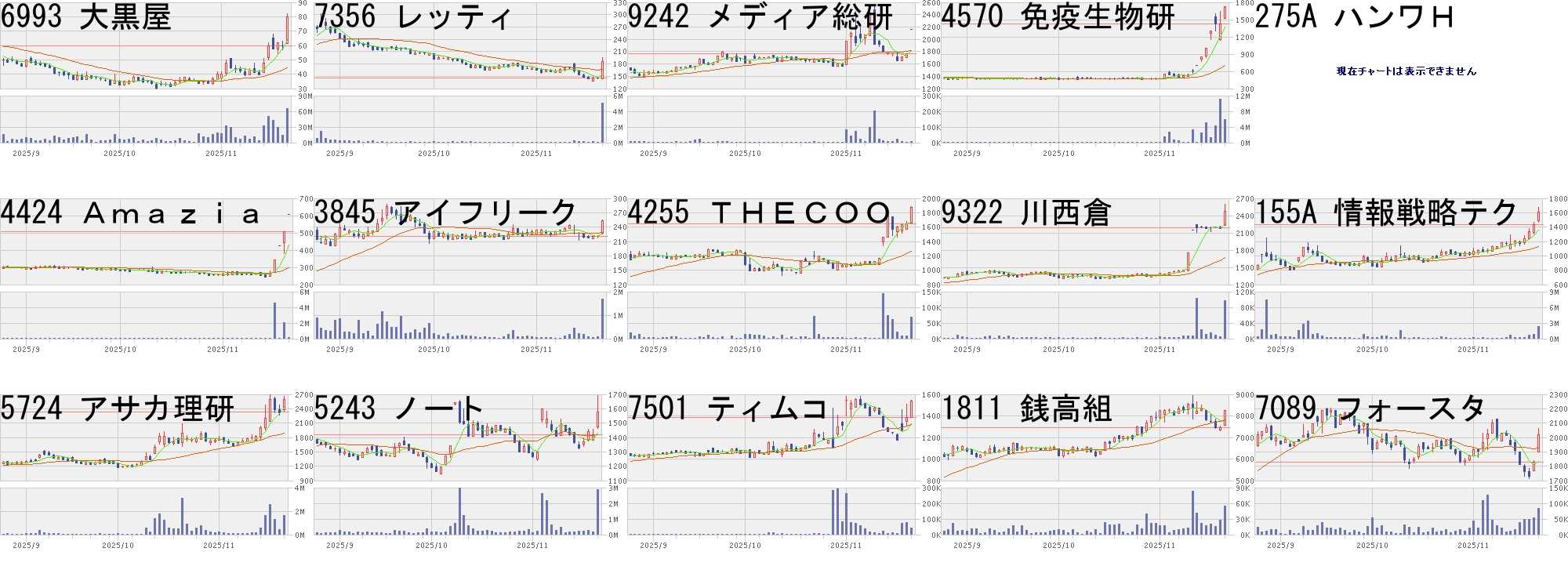全742件 (742件中 1-50件目)
-
新しいブログに引っ越ししています。
こちらのブログにおいで下さった方、ありがとうございます。ブログは下記に引っ越しました。「英語教室Bright English Club多読ブッククラブ」教室の問合せなどはこちらへお願いします。bright24_sun(アットマーク)yahoo.co.jp アットマークは@に変えてください。
2015.09.09
-
問合せメール変更
教室の問合せなどはこちらへお願いします。bright24_sun(アットマーク)yahoo.co.jp アットマークは@に変えてください。2012年5月からブログはこちらに移動しています。「英語教室Bright English Club多読ブッククラブ」
2012.11.12
-
「9月23日 英語多聴多読〜講演会〜おしゃべり会@成増」のお知らせ
9月23日(日曜日)午後1時半~4時半場所:成増アクトホール5階 東上線成増駅から2分「西友」の上です。入り口は4階です。参加費:無料です。主催者: Bright English Club (katakuri)講演者:酒井先生、繁村さん定員:40人です。申し込み連絡先:bright78_cat(アットマーク)yahoo.co.jp英語多聴多読について、酒井先生と繁村さんに語っていただいた後、いろいろおしゃべりをする集まりです。当多読クラブの会員さんや一般タドキストさんを中心に、新しい方との交流も深めていただけたらと思います。古いタドキストさんも、新しい方も、多読を始めてない方も大歓迎です。是非、熱い語りを聞いて、話して多読の楽しさを感じてください。
2012.08.20
-
ブログを変更しました。新ブログ案内
いろいろ思う所があって、ブログの日記は今後こちらの方へ書く事にしました。どうぞよろしくお願いします。「英語教室Bright English Club多読ブッククラブ」教室の説明や案内は今まで通りに残しておきますので、上の「HOME」をご覧下さい。今までの記録は当分の間残しておきますので過去の記録を見る方はこの日記の下の方でご覧下さい。
2012.05.30
-

最近の読書記録(英語)
最近2ヶ月くらいで読んだ英語の本です。お薦めばかりではありませんので、ご注意を! これは本は読んだのはなくて全部Audible.comの朗読で聞きました。とても聞きやすい朗読です。タドキストの間で人気のあるDebbie Macomberさんの作品。テイストは"A Shop on the Blossom Street"に似ています。母親の介護、昔の恋人の思い出、中年の恋、思春期の娘の子育てに悩んだり、と日本人でもよくある話。親しみを感じて読めると思います。重い内容に疲れた時のお休みにいいかもしれません。 こちらも聞いた本です。朗読は児童書なんですが、Macomberの物より難しく感じました。感動もこちらの方が深い。児童書はいつも大人の本より考えさせられます。内容については検索を! ご存知、映画"Hugo"の原作です。映画の公開前に読み終わらず、後から読みました。これもAudible.comの朗読を半分聞き、後は紙の本で読みました。映画に劣らず感動的です。本の厚さに圧倒されますが、絵が半分以上ですから意外にすぐ読み終わります。文章もすばらしいですが、白黒のイラストがまたすばらしい。 これが私の最近の一押し。左が英語版、右は日本語翻訳版です。絶対左の方が想像をかき立てますよね。唐傘をさす少女と少年でしょうか。シアトルが舞台、戦争前、戦争中、そして戦後数十年経ってからの物語です。切ないラブストーリーですがそれだけではない、訴える物があります。映画になりそうな予感がします。こちらは作者のインタビューです。http://www.youtube.com/watch?v=qvfUXAVth5Y
2012.05.17
-

読書の記録
しばらく旅行の話ばかりでした。本を読んでいなかったわけではなかったのですが書く心の余裕がなかったというか!次のイギリス報告に進む前に読書記録を書いておきます。 まずは和書から 旅行の直前に読んだ本です。イギリス人の・映画監督リドリースコットさんのお宅のハウスキーパーを勤めた女性のイギリス批評本です。おもしろおかしく、厳しく、でも愛情込めたイギリス批評です。私が見たイギリスとは違うとは思います。 唯一旅行に持参した和書、ライトノベルズと言われる分野かと思います。一番気楽に読めそうなのを選んで持って行って大正解でした。でも面白すぎてすぐに読み終わってしまって、もう1冊持ってくれば良かったと思いました。読書好き、本好きの人にはきっと気に入ってもらえる本です。それに鎌倉が舞台というのもいい雰囲気です。 旅行から帰って眠れない日が続き、本箱で待機中だったこの本を読み出したのですが、もっと眠れなくなってしまいました。 上の2冊とは正反対の本です。恐いですが深いと思います。犯罪者、被害者ともに傷つき、またその家族遺族も深い傷を負って、しかし生きて行かなければならない。読み始めてあまりに重い内容に後悔半分、でも絶対途中でやめたら意味がない、と最後まで読んで強く思いました。
2012.05.17
-

Finland報告-3
タンペレの滞在2日目の続き。2日目は1時まで学校訪問をした後、以前からTwitterで知り合った日本人女性と会う約束をしていたムーミン博物館へコーディネーターさんの車で送ってもらいました。約束の時間までまだたっぷり時間がありましたので、ゆっくりムーミン博物館を見学。ここは写真撮影禁止なので何にもお見せする事が出来ないのでホームページのリンクをご紹介します。 http://inter9.tampere.fi/muumilaakso/index.php?lang=jp 博物館に展示されているのは本物の原画なので、よく見られる可愛いムーミンのイラストとは違った雰囲気です。息子たち(もう大人だけど)も大好きなムーミングッズをお土産に買いました。これは前から持っているムーミンの原画が描かれた私のお気に入りのマグカップムーミン博物館の見学を堪能した後は同じ建物(図書館)の上の階にあるカフェに行って休憩。とってもいいカフェでした。ムーミン博物館に行く事があったら是非お薦めです。ひろびろしていて、ゆったり落ち着きます。ケーキとコーヒーでねばりました。初対面のMさんとおしゃべり。不思議なものです。初対面とは思えないほどすぐに打ち解けました。何回もTwitterでお話していると人柄がわかるのですね。とても穏やかなやさしい方、本当にいろいろなお話をしてくださいました。一つ驚きだったのはフィンランドの中学生は中1~2くらいでハリーポッターを”英語”で読んでいるという事です。 いくら小学3年生から英語やっているとは言え日常的にはフィンランド語で暮らし、外国人もそれほど会うわけでもなし、どうして~~?と思います。中学校訪問に行った学校でも、英語を話す人が来たから是非英語で話しかけてください、と日本人である私に言うくらいです。そんなに外国人が多いわけでもないでしょう。 2時間ほどMさんとお話して、またコーディネーターさんがお迎えに来てくれました。歩き回るのが苦手になって来た私(年ですから)、本当に助かりました。 次の日は3日目はコーディネーターさんとご主人と赤ちゃんも一緒にタンペレ観光です。まあ、赤ちゃんの可愛い事。お見せしたいくらいですが、個人的な写真なので、、、。タンペレは内陸で海に面していませんが、一見海かと思うほど大きな湖があります。湖のそばに建つ家々のすばらしかった事! これでタンペレは終了。4日目の午前中駅まで送ってもらってヘルシンキへ。ヘルシンキで半日ブラブラして中央駅のすぐそばのホテルに宿泊。いよいよ、イギリスへ。 湖が見える家々ステイのお宅のキッチンインテリア。ワイヤーネットで出来たかごや飾り物があちこちにおいてあります。同じような物が欲しくて探しに行きましたが見つからず残念でした。
2012.05.16
-

Finland 報告その2
旅行社さんを通してホームステイを探してもらったのですが、タンペレにコーディネイターさんがいるとは全然聞いてなかったのです。タンペレ駅のホームに降りたら可愛い女性が私の名前を書いた紙をもってて日本語で「こんにちは!」と話しかけられてびっくり。その彼女は日本に留学した事がある日本大好き女性で、まだ10か月の赤ちゃんがいる方。ステイ先の奥さんと彼女のご主人が姉弟という関係で、毎日私と一緒に行動して毎日私と一緒に夕食を食べて家族の様に過ごしました。ステイ先の奥さんはお料理が上手で今までのホームステイでは最高の料理。ご主人は日系企業に勤務する方でもちろん日本にも行った事がある方。でも日本語は出来ず、英語はもちろんペラペラです。お子さんが小5と小3の2人。普段はわんぱくらしいのですが、とってももの静か、恥ずかしそうにしています。私が英語で話しかけても分かっているようでも、Yesとか小さい声で答えるだけ。3年生の子はちょっと分からなかったみたいです。2人とも何でも自分で自分でします。朝起きて来ると自分でお皿を出して、パンを出してサンドイッチを作って学校へ持って行ったり。給食はもちろんあるのですが、おやつ代わりに持って行ってもいいんだそうです。とてもおおらか!2日目は学校訪問です。10時から1時まで。給食もいただきました。そこで私を待ち構えていたのは日本語を習っているという中2の女の子。「初めて本物の日本人と話せる~! 」と興奮気味、それは英語で言いましたが、これが私にはびっくり、中2でスイスイと英語が口をついて出て来る!カウンセラーの先生2人とコーディネイターさん、オタクの中2の女の子がずっと一緒に過ごしました。カウンセラーはその学校では大変重要な役目を果たしているようです。進路のこと、授業の選択等、個人個人を大切にした教育が行われている事を感じました。 その中の1人のカウンセラーさんの授業に見学に行きました。いきなり私に自己紹介してください、と。英語で先生っぽくちょっと話しました。日本の事知ってる?って聞いたら、すぐに「つなみ」と。それから日本の学校では制服を着てるのかとか、掃除は生徒がするって本当かとか。中学2年生ですが、英語で質問してきます。たいしたもんです。 少人数学級(18人くらい)でのびのびゆったりしている感じです。語学はその半分の人数です。中学校の入り口。コンピューター室工芸室生徒のバイク(15歳か16歳で学校に乗って行ってもいいんだそう!)カフェテリア(広々してきれい!)
2012.05.12
-

Finland 報告その1
フィンランド報告です。今回の旅の目的は地元に住む人々とじっくりコミュニーケーションを取る事でした。今回はいつもより長く4泊ホームステイしました。3日間をヘルシンキから列車で2時間のタンペレという町に滞在しました。いつもフィンランドの旅行の時に手配をお願いしている旅行社からタンペレの旅行社へと手配をお願いしてホームステイ先を見つけてもらいました。ヘルシンキ中央駅から列車で約2時間、フィンランドでは初めての長距離列車、車内でWifi無料で使えてうれしい。ヘルシンキ中央駅タンペレには中3日間滞在。1日目は以前からインターネットで知り合った日本人女性とお会いする事に。タンペレからさらに2時間くらいのポリという町まで出かけました。小さい町ですが、落ち着いた感じ住み安そうな町です。町は歩いて通り抜けられそうです。駅前へ向かえに来てもらって町の中心へ行っておしゃべり。出版や翻訳など活躍されている方で大変忙しくされている方なのにわざわざ時間を取ってくださって大感謝です。いろんな事を聞きたかったのにちゃんと整理して行かなかった事を反省。取り留めない話になってしまって申し訳なかったと思います。彼女の生活、税金に対する考えなど市民感覚の話が聞けました。おおむねフィンランド人は今の生活レベルや福祉に満足している印象です。学校や病院、年金など日本人が一番心配な事が整備されているので安心して暮らしているという印象です。 ポリ市内のマーケット。魚が豊富で日本人は住みやすいと思いました。
2012.05.12
-
帰ってきました。
8日の朝8時55分着のフィンランド航空、到着してすぐに9時半の和光市行きの高速バスに乗れたので家には11時半には到着できました。旅行中全然疲れていないと思ってたのですが、やっぱり帰ってみると体というより、気持ちや神経が疲れていたのか、何もしたくなく動く気力がなくて顔を洗って着替えて即ベッドへ。2~3時間寝て食事、そしてテレビをぼ~と眺めてまた寝て、今日になってしまってました。 でも今日は元気な小学生のクラスです。それで一気に目が覚めました。体にも力がみなぎってきます。やっぱり子どもたちの笑顔が元気のもとです。シャッキっとするから不思議です。土日には中学2~3年生の補講もあるのでがんばらなくては~。 ぼちぼちと旅行記は書きます。今回はほとんど観光はしてないので書く事もあまりないのですが、いろいろ失敗談ががいっぱいです。 2週間留守にしていた間、すっかり季節が移っていました。和光市の駅前から家までのタクシーの中からは緑の濃くなった街路樹が美しくて日本は奇麗だなあ、って思いました。フィンランドはまだやっと湖の氷が溶けたところ、スコットランドは石造りの家が寒いのなんの、日本はこの季節が最高です。
2012.05.09
-
明日からお休みです。
明日から2週間のお休みにさせていただきます。5月8日に帰ってきます。教室は9日から通常通りに実施いたします。今回の旅は、フィンランドに5泊のホームステイ、イギリスでも4泊がホームステイ、残りは安いB&Bに滞在します。普通の田舎の生活を味わってきたいと思っています。フィンランドでは首都ヘルシンキではなく、西に2時間ほど行ったタンペレという小さな町に滞在します。田舎の普通の人々と交流したいという気持ちで敢えて首都をはずしました。幸いに学校訪問も出来るという事で、前回に学校を見せていただいた時の疑問などもっと掘り下げて聞いてみたいと思っています。 イギリスではインターネットで知り合ったCさんの所に泊めていただきます。1月に日本に来られた時に秋田の田舎へ一緒に旅をした人です。 フィンランドでもインターネットで知り合った日本人の方数人と会える事になりました。数年前に比べると 格段の違いです。何と便利な世の中になった事でしょう。帰って来るとすぐに中学生の中間テストが始まります。例年より1~2週間早まってちょっとあせります。帰って来たらすぐに土曜日と日曜日は補講を実施いたします。では皆さん、帰って来たらまた報告します。
2012.04.24
-

3匹の子豚のもう一つの見方 "The Ture Story of the 3 Little Pigs"
この絵本も3匹の子豚から派生した絵本。これも大人の会員さんたちの間に人気の絵本です。先日紹介したのはオオカミの立場と豚の逆転でしたが、これはオオカミが、自分の罪を言い訳しているというか、自分を分かって欲しいと訴えている絵本です。これもかなり笑えるし、こっちの方が本当かもね~と、ちょっとオオカミさんに同情したくなるかもしれません。
2012.04.21
-

中学生の一緒読みで"The Nose Book"
中高生は多読時間1時間と個人レッスン30分+ワークなど、という組み合わせレッスンをしています。 必ずやっているのは自由会話、QA100~300などのパターンのある会話、チャンツ、それと、一緒読みです。 この一緒読みの一環としては2年生になるとTotally Trueに入りますががまだ難しい中1やレベル的に不安な生徒の場合は私と一緒に絵本を 読みます。 教室内のかごに入れてある「繰り返し読んで欲しい本」の中から簡単な物から一緒に読んでいます。1冊の本を3週読みます。先日から読み始めたのが"The Nose Book"です。この前は"The Foot Book"でしたのでこれを読み出したのですが、とても面白い事に気づきました。初めて読んだ時はスルーしていた事なのに生徒と一緒に読むとじっくり読んで気づかされる事がいろいろあります。 最初のページ、Everybody grows a nose" ここで、へ~、こんな時にgrowを使うんだ~、と。今度は"They grow on every kind of head" ほう、headに鼻ね~、私はheadが頭部全体をさす事は理屈的にはわかってますけど、やっぱりここではfaceじゃなくてheadなんだ~と。 でも、中学1年生は小学生の時から英語をやっている生徒がほとんどだからなんでしょうか、そんな日本語の意味なんておかまいなしの様子です。私一人、昔の学校英語で習った日本語との比較をしてしまって勉強になるなあ~、と。 これは、Dr.Seussの本をいっぱい出しているBright &Early Booksの絵本で、Dr.Seussの絵とそっくりですが、作者がAl.Perkinsです。Dr. Seussは名前をいくつも使っているのすが、スースではなさそうです。"Who Was Dr.Seuss"には名前についても書かれているので興味のある方は読んでください。
2012.04.21
-
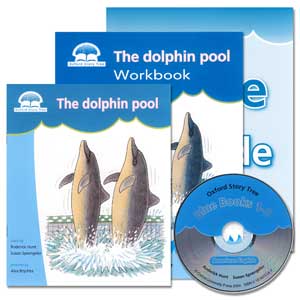
OST(Oxford Story Tree)で一緒読みとワーク
小学生は70分レッスン。最初の20~30分は聞き読みの多読の時間です。その後、自分のペースのワーク。その後は一緒読み。この一緒読みに今日からOxford Story Tree(OST)を使い始めました。これはOxford Reading Tree(ORT)の中からレベルによって6~8冊を1セットにして教材用に書き直されたものです。今年の4~5年生クラスでは2番目のレベルのBlueセットを使う事にしました。かなり読める様になっている子となかなかの子が一緒にいるグループレッスンでは簡単かな、というくらいのものをたくさん読む方が効果的と考えています。今日は早速この本を全員に配って1人で読めるかな~、とやってみました。物語としてはORTの方で読んでいるのでだいたいは知っている内容です。みんな、読める読めるとどんどん読み出しました。多少、勝手な読み方もありましたが、自信を持って読み出しました。このOSTには1冊ごとにワークブックが付いているのがありがたい!絵がいっぱい、絵を見ながら単語を確認したり簡単な文を書いたり、丁寧に進んで行きます。3~4週間で1冊の本とワークを丁寧に読んで書いて行くというレッスンです。多読と平行してきちんと読むというレッスンも大切だと思います。
2012.04.18
-

会員さん同士でお薦め本
ここ数週間大人の多読クラブの会員さんのおすすめで次から次へとみんなさんが借りて行ってくれた本が今日返ってきました。普通の3匹の子豚のイメージとは正反対の、恐い大豚とやさしいオオカミのお話です。普通バージョンのオオカミなんて問題じゃないくらい恐いすごみのある豚です。このギャップが皆さんに受けるのでしょう。今日が2回目の新入会員の方がとても嬉しい事をおっしゃって下さいました。多読って英語をがんばって読むのかと思って来たら、絵本を楽しく読んでいけばいいんですね。これなら出来ると思いました、と。英語多読ってやっぱり英語の勉強って思ってしまうようです。でも、実際始めてみると絵本の楽しさにはまって行く大人の会員さんたちがいっぱい。結果を急がず、楽しく読んでいればいつの間にか英語がおまけについて来る、そんな気持ちでいっぱい読んでもらいたいと思います。
2012.04.13
-
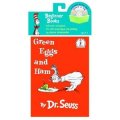
今月はDr.Seuss月間にしちゃいました。
今日、タドキスト友人とおしゃべりしていて突然思いついてしまいました。あっ、そうだ!今月はDr.Seuss月間にしよう! というわけでDr.Seussの絵本をかごにまとめていれました。廊下の本棚にバラバラに入っていたのをまとめてみました。全部で15冊くらいあります。短い物は200語くらいから、長いものは2000語以上あります。読みやすさレベルも0レベルから3くらい までと幅広くあります。 どれもリズム感いっぱい。韻をを踏んだ言葉遊びがいっぱいです。意味は深く考えなくても十分楽しむ事が出来ます。 どうぞ、大人も子どもも楽しんでください。
2012.04.11
-

DVDで”「サンセット大通り」
ツタヤの定期レンタルをやってます。月4枚のDVDで980円。適当に思いついた時にリストに入れておくと届きます。今日見たのは「サンセット大通り」。白黒の古い映画です。どうして借りる気になったのかすっかり忘れしまってましたが、予想外に面白かったです。 これがミュージカルになっていたなんて全然知らなかった!映画が出て来ると思って「サンセット大通り」で検索していたら、なんとミュージカルが出てきました。6月に日本初演だそうです。もう一つ驚いたのは、主人公役の俳優さんが息子たちが習っていたピアノの先生の息子さんだったこと!声楽科を出られてミュージカル俳優になられた事は知っていたのですが、いきなり知っているお顔が出て来てびっくりしました。 http://www.horipro.co.jp/usr/ticket/kouen.cgi?Detail=178 アンドリュー・ロイド・ウェーバーによるブロードウェイミュージカルとしてトニー賞最優秀ミュージカル作品賞を獲得した作品だという事です。 映画の地味な雰囲気がどんな風にミュージカルになっているのか興味がわきます。
2012.04.03
-
今日から新学期スタート
今日から新年度がスタートしました。数日前から全改訂になった問題集がどっさり届いてこれを早く生徒たちに渡してしまわないと置き場所に困る状態です。中学生は今年度から教科書大改訂になったので、今までの準拠問題集は全部廃棄処分です。いつも在庫をおいていたので、どっさり捨てる事になってしまいました。もったいないけど置き場所がないからしかたがない!本物の教科書は学校配布が終わってからでないと売ってもらえないので、もう1~2週間は買えません。その代わりに教科書ガイドを買ったのですが、これが高くて!たいして読まないのにもったいないけど仕方がない。中学生は多読1時間と教科書の音読を必ずやっているので教科書は必需品です。今まで使った事がなかったNew Crownの中学3年生用にFinlandの事がのっていて、びっくり。今まではメジャーな国しか載ってなかったのでちょっとうれしい!その中に出て来るフィンランド人の女性の名前がMari Suominenさん、国名みたいですが、名字にもあるのでしょうか。今度フィンランド人にあったら聞いてみよう。 今日は学校はまだ春休みですが、うちの教室は新学期。新しい問題集やワークブックを渡したら、なんか気分が変わってうれしいね!と高校生。内部進学に決めている高校3年生、「受験英語をしなくてもいいから会話や多読がいっぱいできてうれしい!」と私も嬉しくなりました。留学をめざして本物をやりたいそうです。今週木曜日の午前中は大人の多読クラブも始まります。ますますにぎわって来ています。お楽しみに!
2012.04.02
-

映画 “The Help"「心がつなぐストーリー」
今日から公開の"The Help"「心がつなぐストーリー」を見てきました。 笑いあり、涙あり、そして感動あり。あんな時代があって今に至ったアメリカはここ数十年で劇的に変わって来たのだとあらためて思います。 それにしても映画に出て来る上流階級の女性たちの愚かさ、それに反して黒人女性たちの賢さ、あまりに対照的で笑える! 原作はちょっとだらだらした所もありましたが、それをばっさりと切ったのは良かったような気がします。家政婦役の2人の女優さんがすばらしかった!
2012.03.31
-
4月から多読クラブの時間が変更になります。
4月からのクラスがほぼ決まりました。中高生の「多読プラス個人レッスン」は満員状態になってしまいました。小学生クラスは水曜日と木曜日。4時半~5時40分の70分です。そのため水曜日と木曜日は多読クラブのオープン時間は6時~10時です。月曜日、火曜日、金曜日は5時~10時です。大人の方の木曜日と金曜日午前中の多読クラブの日は月3回、毎月のカレンダーでご確認ください。 4月2日(月曜日)から新年度スタートです。今、本箱がスカスカ状態。皆さんたくさん借りて行ってくれました。いっぱい読んで来てくださいね。
2012.03.25
-
iPhoneにはまってます。
先週iPhoneを買いました。これで家族全員iPhoneの使用者になりました。普段から携帯電話は電話とたまにメールしか使わなかったのでそれほどスマートフォンにする意味を感じていなかったのですが、ひょんなことから買うことになってしまいました。最初はオタオタビクビクものでしたが、使い始めたらこれがものすごく便利なのです。私は10年以上パソコンはマックなので特にそう感じるのかも。iPhoneは、iPodも使える、カメラにも使えるくらいの知識だったのですが、なんとMacBookパソコンに繋いだらデータが連動していたのです。うれしくなって今ちょこちょこいじってまるでおもちゃのようです。忙しい忙しいと言いながらiPhoneで画像見たり、iPodの朗読や音楽聞いたり、今までご無沙汰だった人にメールしたり、楽しんでます。電車の中で携帯ばかりいじってる人見て、何やってんだろうと不思議でしたが、今自分がそれになってしまいました。
2012.03.20
-
映画 "The Iron Lady" 「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」
マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 - goo 映画昨日(19日)と今日は2日続けての春休みです。来週1週間も春休みです。特に何の予定もないのですが、普段は絶対出来ない、平日午後遅くからの外出が出来る事がちょっとうれしいです。きのうは「マーガレット.サッチャー 鉄の女の涙」を見てきました。この最後の「涙」っていうのがなんだかいらない気がするんですけどね。今はアルツハイマー病になり現実と幻覚の間を行き来するサッチャーさんですが、絶対に涙を見せずにがんばり抜いた人だと思います。サッチャーさんの政治的な評価はいろいろで悪い評価も多いのですが、この映画はそういう言う事には全く触れず、歴史的な事実を事実として描きます。その中でのサッチャーさんの「鉄の女」と言われるほどの強い姿勢にはあらためて驚きを禁じ得ません。イギリスでは女王様が君臨した歴史が長いので、政治の世界ではそれほど差別はなかったのではないかと思ってましたが、それは全く違っていたのですね。また階級差別。Grocery Storeの娘で全くの平民の出身者が政界に出る事は並大抵の努力ではなかったのです。メリルストリープさんの演技力、メイクアップどれもこれも驚きです。これこそ映画でしか描けない物だと思いました。またアメリカ人であるメリルさんにとってイギリス英語は難しかったそうです。言葉が強くはっきり発音されていて聞き安いのでBritish Englishを堪能するにもいい映画だと思います。
2012.03.20
-

Oliviaシリーズ5冊そろいました。
昨年暮れにもご紹介したシリーズです。5冊分入ったCDを買ったのでその5冊をなんとかそろえたくてずっと待っていたのですが、やっと全部そろいまいした。 昨日届いたのは季節外れですが、"OLIVIA helps with Christmas"。真っ赤な表紙の印象的な絵本です。この絵本はぜひぜひCDで聞き読みしてください。朗読の初めに必ず「Beautifully read by me!」って言ってるくらいですから。 絵本も芸術ですが、朗読もすばらしい芸術です。
2012.03.14
-

"A Peach of a Murder" by Livia J. Washburn
この前に読んだ本が南部なまりや古い表現が多くて読みにくく感じたので、この本は読みやすくて助かりました。が、ちょっと刺激が乏しかったかな。Murderというタイトルがついてますが、それほどハラハラドキドキもありません。主人公は退職した学校教師。子どもたちも巣立って夫も亡くなり、大きな家で退職教師のための下宿屋を営んでいます。古い友人たちと家族の様に暮らすというこの雰囲気に惹かれます。彼女の周りで次々に殺人事件が起こります。息子は警察官、首を突っ込むなと言われても探偵をやめるわけにはいかない主人公です。この設定はまるで土曜ワイド劇場か火曜サスペンス(今はいつでもやってるけど)。結末は私の推理通りになってしまったのは、私のサスペンスドラマ好きの成果か、だれにでもわかってしまうのか、、気楽に読めるミステリーです。でも、これはちょっと切なかった。
2012.03.14
-
映画 "Hugo" 「ヒューゴの不思議な発明」
原作はタドキスト(多読する人たち)の間で数年前に評判になっていた本ですが、読む機会を逸していたのですが、映画を見て原作も読みたくなりました。 映画は2D(普通の)と3Dがあってどうせ見るならと3Dメガネをつけてみました。初めての体験でしたが、字幕部分が浮かんで見えたり、走る場面は自分のそばを走っているような感覚にびっくりしました。すごい迫力です。 ストーリーも面白いですが、映像の細かさ、美しさに驚きました。場面は大きな駅と時計の裏側がほとんどですが、生き生きした場面の細かい描写がすばらしい。それに駅の中の人々の表情、会話、動きが生き生きしていて楽しめました。 本も絵がいっぱいだと聞いていたのでじっくりと楽しみたいと思います。
2012.03.11
-

映画 "War Horse" 「戦火の馬」
映画戦火の馬 - goo 映画今日は"War Horse"「戦火の馬」を見てきました。さすが、スピルバーグです。スケールが大きい、映像が迫力ある。感動的です。馬のジョーイと少年アルバートの別れの場面や随所に泣ける部分も満載です。でもなんかだ物足りない気分なのはやっぱり原作を読んでしまったからでしょうか。原作は馬のジョーイ自身が語る形で描かれていたので細かい描写が省かれているので、それがちょっと残念なところです。でも馬も精一杯演技していました。馬の目が語っているような気がしました。戦場を自由を求める様に全力で疾走する場面は感動的でした。戦争映画というより、少年と馬との愛情物語だと思います。
2012.03.06
-
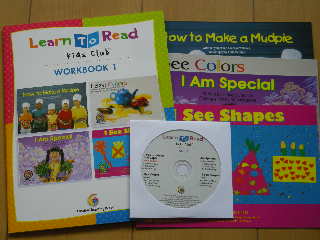
小学生クラスのためのCTP絵本のワークブック
多読を教室で取り入れる前からCTP(Creative Teaching Press社)の絵本はたくさん持っていましたが、ORTやLLLなどのような物語性の高い絵本からみると、子どもたちには魅力に欠けて進んで読んでくれなくなってしまっていました。ずっと本箱の中で眠っている状態でしたが、最近多読と平行して必ず実施している「一緒読み」にCTPも読む様になりました。繰り返しの多いすばらしい本なのでいろいろ活用したいと思っていた所、すばらしいワークブックが出来ている事を発見しました。すばらしいカラー刷りのワークブックです。1冊につき5ページのワークがあります。本を全員で読んだあとに簡単にできるワークで読める書けるという自信をつけるには簡単なワークは効果的です。来年度の小学生はこれを使おうと今から楽しみです。
2012.02.29
-
パット・ハッチンスさんの絵本
パット・ハッチンスさんの絵本が4冊になりました。そろえてかごに入れましたのでみんさん読んでください。最近買ったのはうちの子どもたちが小さい頃に大好きだった「ティッチ」です。3人きょうだいのティッチはおにいちゃんやお姉ちゃんが持っているおもちゃや乗り物がうやらましくてなりません。自分はまだ小さいから何でも一番小さいものです。お兄ちゃんやおねえちゃんの得意そうな表情、ティッチの悔しそうな表情がすてきな絵で描かれています。ハッチンスさんの絵本はどれも絵を丁寧にじっくり見て欲しい絵本ですね。CD付きのものもありますが、ページごとに少しずつ変わって行く様子はじっくり見ないともったいないです。"Don' t Forget the Bacon"とずっと言い続けていたのにとんでもないものに変わってしまう様子など、じっくりと絵を見ながらゆっくり読んで楽しんで下さい。文は簡単なので小学生も大人もみんな楽しめる絵本です。
2012.02.29
-
イギリスの児童書 "Horrid Henry"シリーズ
友人のタドキストさんから薦められて購入してみました。本は1冊だけもっていましたが、Audibleの朗読と音響のすばらしさを聞いていたので買って聞いてみたら、本当にすばらしい録音です。まるでドラマを聞いているようです。男の子ものでイギリス英語の物が少なかったので、これはイギリス英語の音が好きな人にはちょうどいいシリーズです。アメリカで発売された本と朗読では単語に少し違いがありますが、あまり気にしないで読んでください。この主人公のHorrid Henryは本当にとんでもなくひどい子(Horrid)なのですが、問題が起きそうなところではそれらしい緊迫感のある音楽、音楽と効果音がうまく使われています。Horrid Henryには正反対のPerfet Peterという弟がいます。Henryが悪い事をするにはどうもこの弟があまりにいい子過ぎる事も原因のようです。Henryは大決心をしてHorridをやめる事にしますが、今度はPeterがHorridになってしまいます。いつまでそれが続くのか、、、こんな男の子が2人家にいたら親は相当に忍耐が必要です。うちも男の子が2人、一時は相当にすごい状態でしたが、それも過ぎ去ってしまえば懐かしい思い出です。
2012.02.27
-
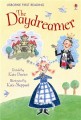
Usborne First Readingシリーズ
この教室で大人気のUsborne Young Readingよりもっと簡単なシリーズが入りました。しばらくUsborneのサイトを見てなかったらこんなシリーズが出ていた事で嬉しくなって6冊ほど買いました。当教室のレベル分けでは赤レベル(YL0.5~0.9)位だと思います。朗読CDが付いていても割と安めなのもUsborneシリーズの嬉しい所です。朗読は前半がイギリス英語、後半がアメリカ英語になっています。大人の人でもイギリス英語が苦手という人が多いのでこんなふうなCDで聞き分けてみるのもいいと思います。
2012.02.26
-
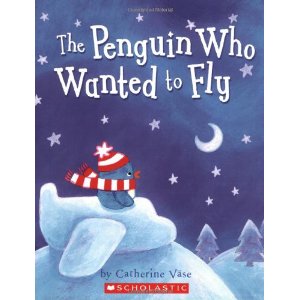
大人の多読クラブでの印象的な絵本
今日の午前中は大人の多読クラブでした。出席者は5人。今日は最後にお茶を飲みながら前回から読んだ本で印象に残った本の事を一言ずつ話してもらいました。皆さん、絵本ばかり読んでいるのではないのですが、なぜか絵本を取り上げてくださいました。 以前にブログで書いた絵本もあるかと思いますが、また違った印象でお話くださってとても嬉しかったです。"Mr. Gumpy's Outing"の中で繰り返し出て来るせりふが、ガンピーさんの船に乗せてください、一緒に連れて行って、という表現がありますが、それがいろいろな表現で言われている事に気づいて教えていただきました。"May we come with you?""Can I come along""I'd like a ride.""Will you take me with you?""Can you make room for me?"と他にもいろいろ出てきます。それに対してガンピーさんがいろいろ条件を付けるのですが、これもどれもこれも”勉強になる”表現ばかりです。でもこれを勉強ではなくて感心しながら読んで味わっているうちに体にしみ込んでくるんではないでしょうか。絵本はすごい!です。"The Penguin Who Wanted to Fly"を紹介してくださった方はこれをお子さんと一緒に読んだそうです。お子さんもとてもお気に入りだったということです。ペンギンが飛べないという事を知っていて、飛べるわけないのに、と言いながらお母さんと一緒に、一度は英語でその後は日本語の解説付きで楽しんだそうです。こんな読み方もいいですね。絵がとても可愛くてちょっと長くても絵がわかりやすいのでお子さんでも理解しやすい絵本だと思います。シンシア・ライラントさんの絵本はやはり大人気です。Christmas in the Countryを紹介してくださった方に、これも同じ作家さんですよ、と他の本を紹介すると他の方からそうそう、これ大好きという声が上がりました。シンシアさんは大人に人気の絵本作家さんですね。The Tiger Who Came to Teaの話題が出たのでJudith Kerrさんの生い立ちの話をしました。作家さんを知る事はまた本の話題が広がります。本の話題から読みたい本が広がり、多読の楽しみが増えてくださればと思います。
2012.02.23
-
"The Help" by Kathryn Stockett
もうすぐ日本でも公開予定の映画、「The Help」の原作です。映画の原作である事を知って買おうと思ってた所へ、友人のタドキストからすばらしかったと聞いて読み出したら、なんと、、、本当にすばらしい作品です。寝る間も惜しんで読んだ本です。映画が公開される前に読み終わらなくては、くらいの気持ちで読み始めたのですが、どんどん引き込まれて止められなくなってしまいました。そんなに昔の事ではない、私の記憶にははっきり残っているケネディ大統領の暗殺のあった年、公民権運動が盛んだった時代、でもまだまだ南部ではsegregationが当たり前だった時代の話です。場所も最も黒人差別が激しかったミシシッピーです。「以下、ネタバレあり注意」大学を卒業して実家に戻って来たスキーターに母親はうるさく結婚を勧める。自分は作家志望で出版社で働きたい、でもいくつもの出版社に履歴書を送ってもなかなか仕事は見つからない。やっと見つかった仕事がコミュニティー紙の家事の悩み相談コーナー。でも自分は全く家事をした事がない。すべて黒人の家政婦がやってくれて、自分を育ててくれたのも家政婦でした。家政婦のことはmaidではなく、この小説の中ではhelpと言っています。その記事を書くために友人エリザベスのHelpであるエイブリーンに相談します。それがきっかけで、Helpの人たちは白人のために働く事をどう思っているのかインタビューをして本を書く事を思い立ちます。これがどんなに危険を伴う物だったのか、徐々に分かってきますが、初めは拒否していたHelpたちも協力する様になって生きます。キング牧師の公民権運動が徐々に大きなうねりとなって行った事や、白人による黒人指導者の暗殺などがHelpたちを動かして行きます。とても深刻な内容ですが、ユーモアいっぱい、笑う場面満載です。映画の紹介がコメディー映画として紹介されていたくらいです。映画の予告編のYutueもどうぞ。The Help これがこの作者の初めての作品と知ってこれも驚きです。
2012.02.21
-
絵本 “Henry's Freedom Box" by Ellen Levine
今日届いてすぐに読んで感動して、すぐに中学生と高校生にすすめて読んだもらいました。やっぱり感動というか、ショックを受けたようです。最近の子どもたちにとってはアメリカの奴隷制度のことはあまりに遠い世界の出来事なのでしょう。すばらしい絵と感動的な文章、静かな語り口で大きな感動を与えてくれる絵本です。教室内でたくさんの人に読んでもらいたいのでしばらくは貸出禁止のボックスに入れてあります。
2012.02.20
-
DVDで”シャンハイ”
シャンハイ?-?goo?映画久しぶりの週末全く用事のない2日間でした。のんびりとリビングの大きい画面のテレビでDVDが見られました。いつもひっそりと小さいパソコンで見る事が多いので39インチのテレビでも嬉しいのです。これは大画面で見る価値のある映画でした。シャンハイというだけで何ともいえない響き、魅力があります。戦前からドロドロした駆け引きが行われた場所、退廃的な娯楽が溢れていた場所、スパイや諜報員が活躍した場所、そんなイメージです。これは日本が徐々に中国を占領し始め、シャンハイにも今にも日本軍の支配に落ちそうな時代の話です。時代が大きく動く時の緊迫感が伝わってきます。渡辺謙さんが軍人としての冷徹な部分と、男として人間としての揺れ動く姿を好演していると思います。歴史もの、戦争ものそして恋愛物としても楽しめる映画です。ところで中国人のコン・リーさんやチョウ・ユンファさんの英語はとても聞きやすいのですが、やっぱり渡辺謙さんの英語は聞きとりにくいのはなぜでしょう。十分に上手なんですが、彼の台詞のときだけしっかりと聞こうとしないと耳に入って来ない。日本語の発声が英語や中国語の発声からは遠いからかなあ、というのが私の推測です。アメリカ人、中国人、日本人といろいろな英語が聞けるという点でもある意味楽しめる映画です。
2012.02.12
-
こんな猫でも好きですか?Bad Kittyの絵本
先日ご紹介したBad Kittyシリーズと違いが分からず注文してあったCD付きが届きました。でもこれは奇麗な装丁のABC絵本でした。Good Kiddy がBad Kittyになった理由がAからZまであるのですが、全くもってとんでもない事なんです。。それにしても凄まじきBad Kittyぶりです。約500語です。YLは1くらい。朗読はいかにもBadぶりが強調されるすばらしい読み方です。先日ご紹介したのは児童書のシリーズです。教室には4冊あります。Bad Kittyの凄まじきBadぶりが、これでもかと書かれているのは絵本と同じですが、文章がグ~ンと増えて2000語から4000語くらいまであります。YLは2くらいでしょうか。Dr Murrayが時々出て来て、猫についての解説する所も面白いです。その部分以外は絵本と漫画の中間のような描き方です。絵がいっぱいでレベルの割には読みやすいでしょう。Bad Kittyの家にやって来たBabyもまたすごい!Bad Kitty対Babyの対決やいかに、と最後まで目が離せません。赤ちゃんの生態もこうやって描かれると相当にひどい物です。でも作者の目にはどちらも愛すべき大事な存在なのです。ちょっとホロッツする所もあります。
2012.02.10
-
大人の多読クラブの日を増やします。
今日は木曜日午前中の大人の多読クラブの日でした。先週よりまた増えて今日の参加者は7人+おちびちゃんでした。教室に入りきらず、となりの個人レッスン部屋も開放しました。2部屋使っても9人で満杯です。貸出用の本を探す時は教室と廊下の本箱の前は混み合ってました。貸出本の記入が終わっていざ本読みの時間はし~んとして読んでいます。時々私が話しかけるのも申し訳ないほど、皆さん集中して読んでいます。皆さんとても熱心でもっと来たいけど、夜は出られないという方がほとんどです。そこで、来月からは金曜日も月に1回多読クラブの日とする事にしました。3月の午前中の多読クラブの日は8日(木曜日)、16日(金曜日)、22日(木曜日)の3回になります。
2012.02.09
-

チャンツ本 "I Like Coffee, I Like Tea"
小学生クラスではこのチャンツの本を使っています。この小さな本の中に絵本の数冊分の内容がぎっしり詰まっています。今日は3年生のクラスでこの中のThree Little Pigsをやりました。今日で2回目。A: Little pig , little pig, Let me come in.B: No by the hair on my Chinny chin chin.A: Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.このクラスはダンスや劇にするのが大好きなクラスなのですが、やっぱりこれも劇に変化してしまいました。。私がオオカミの台詞を大げさに言ったらそれが気に入ったらしく、これを1人で言いたいというので、やってもらいました。驚いた事にしっかりオオカミらしく言って大盛り上がりでした。今日は台詞だけでした、来週は演技もつけてやってもらおう。いつも自分たちで作り出してくれる楽しいクラスです。A:
2012.02.09
-
2月から新年度体制に移行
6年生の生徒さんたちは今月から中学生と同じスタイルのレッスンに移行しました。今までの全員一緒のスタイルではなく、「多読+個人レッスン」スタイルになります。6年生は全員本を読む事が大好きなので今までの30分の多読から1時間以上になっても全く抵抗ない様子です。先週から変わりましたが、1時間読んで「いっぱい読んだ~。」と、満足した様子。中学生になると部活などで忙しくなって本を借りて行かずに教室内だけの多読になる生徒が多いのですが、現在の中学1年生を見ていて、たくさん読んでいる人と、教室内でやっと数冊という人ではやはり大きな違いが見られます。毎週月曜日に来るAさんは6年生の1月から英語まっさらの状態で教室に来たのですが、毎週5冊以上の本を借りて行きます。すでに10万語を超えて、初見でもスラスラと読める様になってきました。また、毎回QA-100の会話をしますが、テキストの文はスイスイ読み、私との自由会話もしっかりと答えてくれます。読んでいる量がちゃんと結果に出ているんだと思います。また彼女は2時間以上教室にいて、宿題はもちろん全部終わらせてから帰ります。自分より遅く来た人が帰ってもまだ読んでいるときもあります。多読記録手帳には楽しいコメントがいっぱいです。中学生は多読の他に30分の個人レッスンでは学校の教科書もしっかり音読します。でもこれだけではつまらないから他の本も音読しています。これは人によっていろいろ違いますが、Aさんは私とMouse Talesを一緒読みで音読しています。他の人は絵本でチャンツになっているものや繰り返しの多いものを音読しています。それも1回だけではなく先週読んだものをもう1回読んでから新しいものに進むというようにしています。会話も音読も多読もワークもといろいろ欲張ったレッスンですが、英語が単なる学科としてではなく、世界と繋がるための手段である事をもっと伝えて行けたらと考えています。
2012.02.06
-
児童書 "When Hitler Stole Pink Rabbit" by Judith Kerr
「お茶の時間に来たら」"The Tiger Who Came to Tea"ですっかり魅了されてしまって、この作家さんにも興味を持ちました。Judith Kerrさんはイギリスの作家さんですが、戦前にドイツから逃れた避難民だったのです。すでに90歳を超えたJudithさんはヨーロッパの大きなうねりの中で生き抜いて来た人だったのです。そんな彼女が書いた児童書です。児童書ですから、難しい言葉を出来るだけ使わずに書いているような気がします。読みやすい文章です、微笑ましい所もいっぱいあって楽しめます。是非読んでみてみてください。以下ネタバレあり、ご注意!!1933年の選挙でヒットラーが台頭してきます。まだまだ楽観的に考える人も多く、まさかヒットラーの政党が第一政党にはならないと予想している人も多くいた時期に、有名な作家で学者であったお父さんの本が焼かれたり、著名人のパスポートが取り上げられるという情報を得て、一家は大急ぎでベルリンを逃れます。 その後一家はスイスへ、その後はパリへ。一家は定住の地を求めて行きますが、フランスの出版社や新聞社からの仕事が減って経済的には困窮した日々を過ごします。 そんな中でもAnnaと兄のMaxは子どもらしい楽しみを見つけて、友達も出来て学校生活も楽しみます。2年足らずの間にフランス語を修得して行く様子はさすが子どもの能力はすばらしい。 Sarah's Keyを読んだ後にこの本を読んだので、このまま、パリに住んでいたら、Annaの一家(すなわちJudith Kerrさんの一家)はSarahの一家と同じ様な運命になっていたかもしれない、どんな風にイギリスに逃れたのだろうというハラハラする気持ちで読みました。 それを思うとSarahの一家のように普通に慎ましく暮らし、自分たちをフランス人と信じ、フランスが守ってくれると信じていた人々にその後に起きた出来事はあまりにも酷いと思います。
2012.02.05
-
DVDでミレニアムシリーズ NO2 とNO3
ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女?-?goo?映画だいぶ前に1作目の「ドラゴン・タテューの女」を見て衝撃を受けて、でも暴力も凄まじく凄惨な場面もあり、避けて来たのですが、謎が解決されていなくて続きが気になっていました。最近アメリカでリメイクされたとことを知ってやっぱり続きが見たくなりました。昨日と今日で2作連続で見ましたが、本当にすごい作品です。背景が複雑でちょっ混乱しそうになりながらも徐々に明らかになって行く真実、気の緩む暇もないくらいな展開です。どうしてドラゴンタテューを彫ったのかと質問される場面がありましたが、その理由は分からずじまい、それが気になります。アメリカのリメイクはどんな風に描かれるのかそれも楽しみです。
2012.02.03
-
絵本"Would You Rather..."
Would you rather?って言う表現は絵本を読んでいるとよく出て来るような気がしますが、自分ではなかなか使えない表現です。このratherって言うのがどうも学校英語的に変な訳が付いてて、「むしろ~の方が」みたいに習ってしまって、そこからなかなか抜け出せないのです。この絵本は日本語版を書店で見てあまりに奇想天外で大笑いでした。どれがいいって言われたって、どれも嫌だよ~、って言う物ばかりなんですから。でもこれで、すっきりratherがわかります。勉強になるからばかりでなく、この絵のほんわかした表情、想像力の逞しさ、本当にすてきな絵本です。
2012.01.31
-
児童書 "Bad Kitty Gets a Bath" と半身浴
猫好きのタドキストの友人に紹介されて購入した本です。私は猫好きではないのです。嫌いでもないですが、猫や犬をだっこしたりは出来ないんです。なので見ててかわいいなあ~、って思う程度。猫や犬の可愛い姿には癒されますものね。教室には癒し系の猫本、Mr Putter and Tabbyシリーズとか、犬ものだったらHenry & Mudgeとかありますが、みんな可愛いのですが、このBad Kittyはタイトル通り、Badです。Bad Kittyをどうにかして風呂に入れようと言う顛末が描かれています。風呂に入れるためにはまずは大きな覚悟が必要なのです。準備しておくもののリストには, a suit of armor, an ambulance in your driveway with the engine running, よろいかぶとに、救急車まで?それほどの覚悟して風呂に入れなくてはならないほど、猫は風呂が嫌いなのだそう。私、この本をお風呂で半身浴しながら読んだのですが、大笑いでした。大きな文字、大きな絵がふんだんにあって、漫画と小説がいったいになったような雰囲気の本です。2000語程度ですのでお風呂読書にぴったり。お風呂で読書する時の注意:お風呂のふたの上にバスタオルを敷く。本にはビニールカバーをかけておく。読む時は絶対に本を持ち上げず、ふたの上においた状態で読む。肩にはタオルをかけて冷えない様にする。手が濡れたらタオルで拭く。こうやって読んでいると20~30分くらいで額に汗が出てきますので、その辺で終了する。こうやって読むと本を濡らす事もなく、心地よく、半身浴と読書が同時に出来ます。読書しながら健康に!です。
2012.01.27
-
再び "Sarah's Key"のこと!
年末に映画「サラの鍵」の事を書きました。その後本は読まずにただAudible.comで買ったaudio bookを聞いていましたが、散歩に行く時間が減って来ていつまでも進みません。1月半ばになって面白くなって来て、紙の本を読み出したらどんどん引き込まれて一気に読み終わりました。朗読で聞いていても泣きそうになりますが、道ばたで泣く訳にも生きません。泣きそうな本はベッドで読むに限ります。映画を見てから読むといういつもとは逆の順番でしたが、だいたいの場合は映画になるとかなり変更されている部分がありますが、これはかなり原作に忠実に描かれています。ユダヤ人のフランス国内での強制収容の話とそれに巻き込まれた人々の話。こういうストーリーは映画にいっぱい描かれていますので潜入感が入りがちです。映画のポスターを見た時も、またホロコーストの話か、恐ろしいものは見たくない、とちょっと引く部分もありましたが、全然違います。是非、多くの人に見て欲しい映画、読んで欲しい小説です。小説の方が感動は大きいと思います。言葉1つ1つに重みを感じます。ホロコーストは人数の多さ、あまりの残酷さに、目を覆う事実ですが、1人1人にそれぞれの物語や人生があった、残された人々はずっと傷を抱えて生きて行かなければならなかった、それに焦点を当てた作品です。Sarahに関わった人々の温かい目、Sarahの事件後数十年も秘密を胸に隠しながら苦しんだ人、ジャーナリストして仕事として関わった事が、偶然にも自分の家族がサラに深く関わっていた事実を知り、過去を掘り下げる事が正しいのかどうか、と突きつけられるJulia。Julia自身の人生も大きく変わって行きます。Remember. Never forget!というSarahの言葉が心に響きます。この1年で読んだ本の中では最も感動した小説です。
2012.01.26
-
ORT(Oxford Reading Tree)のすすめ
ORTすなわちOxford Reading Treeシリーズは全部で200冊くらいあるシリーズものです。うちの教室にはStage 1から9まですべての本にCDが付いています。Stage 10と11は昨年新たに買い足したのですが、主人公たちの年齢が上がってレベルも難しくなっています。ORTはイギリスの小学校では教科書として使われているシリーズです。うちの教室ではこのシリーズを多読の基本図書として使っています。このシリーズだけは、大人も子どもも皆さんに読んでもらいたいシリーズです。なぜすばらしいかというと、1冊が一つの物語として完結していること。絵とお話がぴったりあっていて絵が多くの事を教えてくれる事。同じ単語や表現が繰り返し出て来て知らず知らずに単語や文法が身に付くように工夫されている事。何より読む事が楽しい絵本です。小学生も中学生も既に2回くらい読んでいる人が多いのですが、これからも繰り返し読んでもらえるよう、今月と来月はORT強化月間です。今までも約15分は超簡単な本を読む事をすすめていましたが、今月はORTの下のレベルを2パック読む様にすすめています。こんなに工夫されていて、しかも楽しい本はなかなかありません。是非大人の会員さんにも楽しんでもらいたいと思います。
2012.01.20
-
児童書 "So Far from the Bamboo Grove"
日本人として忘れては行けない物があると思います。戦後65年以上たって徐々に戦争を知っている人たちがなくなって来ています。日本がアメリカと戦争した事さえも知らない子どもがいるそうです。朝鮮半島や満州にたくさん日本人が住んでいた事も忘れられてしまうのかもしれません。英語で児童署を読むことがきっかけであらためて考えさせられます。この本は朝鮮半島の中国に近い北側に住んでいた日本人家族の逃避行の物語です。想像を絶する悲惨な長い逃避行です。戦後の満州からの逃避行の物語はNHKBSで放送されている「開拓者たち」でも描かれていますが、この物語の特徴は11歳の少女の目で描かれている事です。また、悲惨さだけでなく、どんな状況でも誇り高い日本人の生き方にも感動します。やっとの思いで日本にたどり着いた家族は食べ物を探す事さえも大変な中で、学校に行くこと、勉学を続ける事を第一と言う母親の強い希望で、駅の中で暮らしながらも学校へ通います。この小説はいろいろな賞を受賞しているそうですが、日本語には翻訳されていないそうです。評価されながらも微妙な問題があるということです。詳しくはこちらをご覧下さい。ウィキペディア(So Far~~)
2012.01.19
-
今週の土曜日(21日)中学生クラス説明会
年末にお知らせしましたが再度の掲載です。新中学1年生保護者のための中学生クラス説明会を実施いたします。1月21日(土曜日) 午後1時~2時半ごろまで現在の生徒さんが優先ですが、外部の方でご関心のある方もどうぞご連絡ください。小学生クラスとは全く違ったシステムでのレッスンになります。また多読がどんな物なのかを詳しくお話いたします。多読+個人レッスンですのでその個人レッスンの部分も詳しくお話させていただきます。ご関心のある方は下記までご連絡ください。連絡先:bright78_cat(アットマーク)yahoo.co.jp (アットマークを@に変えてください)電話:048-461-9180
2012.01.17
-
ネット友達と鎌倉へ!
先週の土曜日、すばらしい天気でした。鎌倉で待ち合わせした人はまだ一度も会った事がないイギリス人の女性です。私と同じ年の女性、ネット上の写真でしか知らない人です。実はこんなサイトがあるのです。Lang-8ここに自分のアカウントを作って日記や作文を書きます。シェアをする場所ですので、私は日本語を添削してあげて、英語の母語話者の人は私の英語の作文や日記を添削してくれうというわけです。そこで知り合った人がこのイギリス人の方です。ネット上には本当の事を書かない方がいいとも言われますが、私のような年齢の場合はちゃんと年齢を書いた方が安全。もちろん本名は書きませんが。そしたらあちらも私と同じ年、イギリス大好きな私としては話があって、お互い添削したり、共通の友人と一緒にスカイプで話す様になりました。1月に他にも用事があって日本に来る事になったそのCさんと鎌倉の駅で待ち合わせすることになったというわけです。鎌倉で顔をみて、想像通りのすてきな可愛い人で初めて会ったとは思えないほどすぐに打ち解けました。3人とも(もう1人の日本人の友人と)信じられないね~、ネットで知り合うなんてこの間まで考えられなかったのがこうやって友達になってる~、と大感激でした。普段スカイプでは日本語の練習をしたいというCさんのために日本語中心で、時々英語で説明したりしていたのですが、鎌倉ではさすが、日本語は難しかったので、英語で1日過ごしました。鎌倉はシーズンオフですのであまり混んでいなくて、散策もゆっくり出来ました。八幡宮から大仏、長谷寺と、一緒に行った友達が最高の場所を案内してくれて私もひさしぶりの鎌倉を楽しみました。友人と別れたあと、まだ時間が早いからと2人で銀ブラ(古いかな、この言葉)銀座をブラブラと歩きました。だんだん暗くなって来て、街路樹がライトアップされて雰囲気最高。奥まった店に骨董屋を見つけたり、珍しいものを見つけて、銀座もとてもすてきでした。Cさんというイギリス人の方は全く学校にも行かず、独学で日本語を勉強しています。どんどんパソコンやIphoneを使って日本語のサイトを見つけて勉強しています。私もまだまだがんばらなくてはと思います。
2012.01.09
-
中学生の親子で多読
中学生のお子さんと一緒に多読していらっしゃる方がいます。一緒というか、せっかく借りて行った本をお母様もどうぞ読んでください、とお薦めしたのですが、その後はどうなったのか知らずにいたら、何とすばらしい事になっています。昨年の1月からすでに60万語読んでいる中学生のお子さんの方もすごいのですが、そのお母様もいつのまにか40万語だそうです。お母様はこちらに来られず、お子さんの借りて行った同じ本を読んでいるのですが順調に読んでいらっしゃいます。同じ本を読み、おしゃべりしたり、楽しそうな様子が目にうかびます。理想的な親子多読ですね。これからが楽しみです。
2012.01.09
-
「壬生義士伝」 浅田次郎著
年末から読み始めたのですが、寝る前だけ読んでいたらなかなかすすまなかったこの本、この2日間で読み終わった。この2日間何回涙を拭ったことか。大声を上げて泣いてしまった。浅田次郎は泣かせる名手ですね。幕末の歴史には関心があっていくつか読んでいますがが、これは有名な人の話ではないので全く展開が読めませんでした。でも、本当に面白かった。前半4分の1くらいのころはなんだか話しが進まず投げようかと思いながらも、読み進むごとに惹き付けられて行きました。貧しさのどん底にあっても身分の低さのために這い上がれない武士の不条理。脱藩して天下国家のために命をかけて戦った多くの浪士もいたけれど、家族を救うために脱藩した武士もまた必至で生きたのです。幕末の人間たちの凄まじいまでの人間ドラマです。読みながら絶対映画になったら面白いと思って調べてみたらもうDVDが出ているんですね。絶対に見ようと思います。
2012.01.03
-
絵本 ”Library Lion" と The Tiger Who Came to Tea"
今日届いたばかりの絵本です。どちらも猛獣のお話です。でも、ちっとも怖くないのです。本当は恐ろしいのかもしれないけど、怖がらない事がおかしいのです。ある日突然図書館に大きなライオンが現れます。子どもたちと一緒に絵本の読み聞かせの時間になるとおとなしく聞いています。図書館司書のMerriweatherさんはとてもルールに厳しい人なんですが、静かにしていればライオンでもだれでも図書館にいてもかまわないといいます。だから毎日ライオンはおとなしく図書館に通って来てたのですが、、、いつの間にか図書館にはライオンがいる事が当たり前になってしまっていたのに、、、。ほんわか暖かい絵がすてき、でもちょっぴりしんみりしてしまうかもしれません。こんな温かいライオンのいる図書館だったら行ってみたい。これも大きなトラのお話です。ある日、トラがお腹がすいていると言ってやって来たらどうします? どうぞ、って言ってお茶を出して上げたら全部のんじゃって、どうぞってお菓子を出したら全部食べちゃって、冷蔵庫の中身もからっぽになっちゃって、でもこのおおらかな家族は全然気にしていないみたいです。何にもなくなっちゃったから、じゃあ外食ねって、それでいいの? どこまでもおおらかな家族です。この2冊ともお人好しのお話なんでしょうか。それとも何か大きな哲学があるのでしょうか。子どもだったらそんな事考えずにこんな大きな動物に憧れてしまいますね。
2011.12.29
全742件 (742件中 1-50件目)