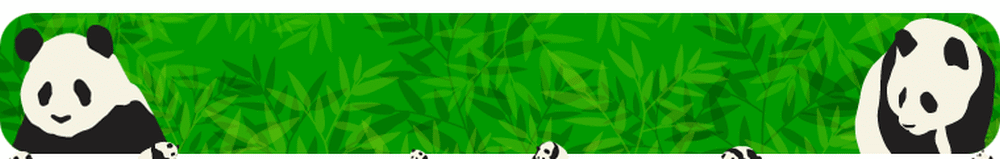2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年02月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

鴨良弼『刑事訴訟における技術と倫理』(日本評論社)
日本評論社から名著がオンデマンド版で復刻されています。オンデマンドにしては比較的良心的な値段だと思うんですけど。私はとりあえず鴨先生の本を買いました。
2008年02月29日
コメント(0)
-

加藤哲夫『破産法 第4版補正版』 その2
以前におかしなところを指摘しましたが(こちら)、訂正表が弘文堂のホームページに載ってました(こちら)。解消されたところもあるんですが、訂正してもやっぱりおかしなままなところがあります。○266頁訂正表にしたがって直すと、以前指摘した記述を含む段落はつぎのとおりになります。(《 》が追加された部分)「この範囲で財団債権とされる範囲以外の租税に関する請求権は破産債権であり(97条かっこ書き)、《破産手続開始前の原因に基づくものについては、》一般の優先権がある債権として優先的破産債権となる(98条1項)。破産財団に関し破産手続に関し破産手続開始後の原因に基づいて生じる租税などの請求権は、破産財団の換価及び配当に関する費用の請求権に該当するものに限り財産債権となるが(148条1項2号)、それ以外のものについては、劣後的破産債権となる(99条1項1号、97条4号)。」 かならずしも間違っているというわけではないけれど、記述が多少追加されても不正確な記述であることはあんまし変わっていません。租税債権について破産法上の区別を整理すると、A 破産開始手続前の原因に基づいて生じた債権 a 開始当時納期限が到来していないもの、または納期限から1年を経過していないもの b 開始当時納期限が到来しており、かつ納期限から1年を経過したものB 破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権 c 破産財団の換価及び配当に関する費用 d 破産財団に関して生じたもの e cd以外のものとなっており、それぞれ、Aa 財団債権(148条1項3号で財団債権となる) b 優先的破産債権(2条5項で破産債権とされ、98条1項で優先的となる)Bc 財団債権(97条かっこ書き、148条1項2号で財団債権となる) d 劣後的破産債権(97条4号で破産債権とされ、99条1項1号で劣後的となる) e 破産債権とはならないとして扱われることになります。訂正後の記述にこの記号を代入すると、「a以外の租税に関する債権(bcde)は破産債権であり(97条かっこ書き)、bは、一般の優先権がある債権として優先的破産債権となる(98条1項)。cdのうち、cは財産債権となるが(148条1項2号)、dについては、劣後的破産債権となる(99条1項1号、97条4号)。 この記述の問題は、1 eが破産債権であるように読めてしまうこと2 cが破産債権であるように読めてしまうこと3 bが破産債権となる根拠条文が2条5項であることが明示されていないこと(98条1項は「破産債権」であることを前提にそれが優先的になることを規定するものであって、同項によっていきなり優先的破産債権になるわけではない。ましてや97条かっこ書きはbには無関係。)4 dが破産債権となる根拠条文が97条4号であることが明示されていないこと(一番後ろには書いてあるが、本来は第1文の(97条かっこ書き)と書いてあるところで引用すべき)にあります。おそらく「以外」という言葉を無節操に使っているのが大きな原因なんだと思います。決して間違ってるということをいいたいのではなく、不親切だということ。 だから、もとの記述をできるかぎり尊重するにしても、たとえば、「a以外の租税に関する債権(bcde)のうち、破産開始手続前の原因に基づいて生じた債権でaに該当しないもの(b)及び破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権で破産財団に関して生じたもの(cd)は破産債権とされる(2条5項、97条4号)。 そのうち、aは、一般の優先権がある破産債権として優先的破産債権となる(98条1項)。cdのうち、破産財団の換価及び配当に関する費用(c)は財団債権となり(97条かっこ書き、148条1項2号)、それ以外(d)は劣後的破産債権となる(99条1項1号)。」とするか、「破産債権に該当」→「財団・優先/劣後に格上げ/格下げ」という二元的な書き方をやめて、「破産開始手続前の原因に基づいて生じた債権でaに該当しないもの(b)は優先的破産債権となる(2条5項、98条1項)。他方、破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権で破産財団に関して生じた債権のうち、破産財団の換価及び配当に関する費用(c)は財団債権となり(97条かっこ書き、148条1項2号)、それ以外のもの(d)は劣後的破産債権となる(97条4号、99条1項1号)。」とすべきでしょう。ちなみに、最後に「なお、破産財団に関しないで破産開始手続後の原因に基づいて生じた債権(e)は、破産債権とはならない。」と付け加えると親切でしょう。法律書は往々にして、条文の裏側を書かないという悪弊がありますので。 なお、266頁7行目で「そのため破産手続開始後1年以内に納期限が到来するもの」に財団債権を限定するとありますが、これは破産手続開始「前」の間違いで、それに伴い「到来した」に変えた方がいいでしょうね。○166頁 延滞税、国税、加算税等が劣後的破産債権とされていることについての記述を、訂正後の記述に書き換えると次の通りとなります。「延滞税などについての破産手続開始後の部分は(1)破産手続開始後の利息などと性質上同じであること(つまり、本税部分に付帯する性質を有する)から、(2)国税などであっても破産手続開始後に破産財団の管理・換価費用として発生するもの以外は劣後的破産債権とされていることとの均衡、また、(3)加算税なども劣後的破産債権とされていることとの均衡に鑑みて、劣後的破産債権とされている。」 ここでも、(2)で「以外」という言葉を無節操につかって、本来はdだけに限定すべき記述がその他の租税債権も劣後的破産債権とされているように読めてしまうのが問題なわけです。また、延滞税、国税、加算税が劣後的破産債権とされていることの説明の後に、延滞税が劣後的破産債権とされている理由だけを書いているのかがよくわかりません。国税や加算税が劣後的破産債権とされている理由はどうしてここに書かないのでしょう。 135頁や266頁とのクロスリファレンスもきちんとしてほしいところです。 また、166頁1行目では「破産手続開始後の」延滞税という限定がないせいで、延滞税全般が劣後的破産債権として扱われているように読めてしまいます。 このように何かおかしな記述のある本ですが、今時の教育的配慮を尽くした教科書を受動的に読むよりも、なんかおかしいんじゃないかという眼で気をつけて読むようになる、という意味では逆に良い本かもしれませんね。ブログのネタにもなってくれるし。
2008年02月22日
コメント(0)
-

新堂幸司『新民事訴訟法』(第三版補正版)
去年の12月に、ショウタロウさんという方からメッセージをいただいていましたが、全く気がつきませんで申し訳ありません。いまさら回答してももはや手遅れでしょうが、一応お答えだけしてみようと思います。メッセージの趣旨は、新堂幸司先生の『新民事訴訟法』の(注)の部分を飛ばして通読しても一定の理解を得ることは出来るのかということでした。どの程度のものを「一定の理解」というかにも違ってきてしまうので何ともいえませんが、注をとばしても読めることは読めます。別にとばしてもいいよなあっていう注もあることはありますし。ただ、私の印象として、難易度については、本文と注とでそれほど厳密な違いがあるようには感じませんでした。本文も注も、難しいところは難しいし。むしろ、注を読むことで本文の理解が進むというところもあるように思います。読んでておもしろいなっていう注もありますし。要するに、注によりけりということですね(それをここで個別的にあげることはさすがに大変だし、最近は目を通してないのでよく覚えていません)。なので、読み方としては、本文と注とで形式的に区別して読むのではなく、本文も注も区別しないで、自分が理解できないところは後回しにして読むという読み方でいいんじゃないかと思います(ただ、限られた時間の中で読まなければならないという現実的な状況にあるならば、本文と注で区別するという形式的な読み方も一つの合理的な方法だと思います)。民事訴訟法は、手続が一通り分かっていないと理解できないところもありますし。これは本文・注の問題とは別の、手続法特有の問題です(その意味では、新堂先生の教科書のような分厚い本をいきなり読むのでは、迷子になるのではないでしょうか)。また、特に未修の方ですと、民法などの実体法の勉強が進んでいないと理解できないところもありますし。新堂先生の教科書の記述について、理解はできないまでも、どこが重要なのかが分かる程度のレベルになってから読んだほうが、スムースに勉強が進むように思います。とりあえず思いついたことを書きましたが、何かあったら追記します
2008年02月21日
コメント(2)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …
- (2025-11-21 12:38:54)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY3
- (2025-11-22 19:22:48)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 禁忌の子/山口 未桜
- (2025-11-16 18:00:05)
-