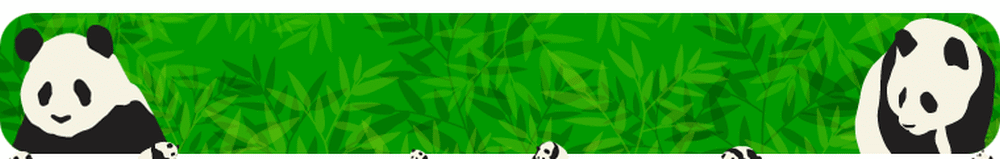PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: こわれてく民法
外国判決の承認という形で代理母問題を扱った最高裁平成19年3月23日決定に絡めて、その辺の問題をあれこれ論じてみたいのですが、さしあたり印象のみ。
(以下、「代理母」については依頼女性が卵子を提供するタイプ(依頼女性=卵子提供者)を前提にします)
・結論自体は最高裁に同意できますが、身分関係は「身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるもの」であるにもかかわらず、親子関係がどういう場合に成立するのか直接明記した規定がないってのはどうかと思います。これは最高裁決定の問題ではなく法律の問題。
・「分娩者=母」ルールは、法律に明記されたルールではなく、判例が作り出したルールにすぎないわけですよね。だからこのルール、国民の合意に基づいてできあがったものじゃないわけです。そして、決定ではこのルールの根拠としては一義的に明確な基準だからだとされています。
そうだとすると、1親子関係は遺伝子により判定する、2母子関係はわざわざDNA鑑定をしないでも分娩によりこれを推定する、3父子関係は婚姻中に懐胎したらこれを推定する(772条1項)、というルールでも別に不明確じゃないし、現行法にも反しないから、採用可能なルールですよね。
にもかかわらず、現行の「分娩者=母」ルールを維持するってのを、単に明確性というだけで理由付けるのは不十分でしょう。これまでのルールを変えたくない、かえるなら立法でお願いします、てことか、あるいは、代理母ビジネスに与えるよろしくない影響を鑑みたか、倫理の問題があるからか、いずれにしても別の理由付けが必要なはずです。
しかも、本件ではあくまで外国判決の承認ルートにおける公序要件の問題であって、日本法(というか判例法)のルールを変更せよ、といってるわけじゃないから、単に明確性というだけで、裁判所でつくった「分娩者=母」ルールが日本の公序の根幹をなすことの理由として十分かも疑問です。
最高裁は、立法におまかせします的なことを言っていますが、立法で変更できる程度のルールが公序といえるのかどうか。複数のルールを認めるならば、一義的でもなくなりますし。
私としては、「分娩者=母」ルールそれ自体を公序の内容とするのではなく、なんら法規制がない状態で代理母を認めてしまうことが日本社会として耐えられるのか、あるいは、子の側からみて分娩者との親子関係を断絶されてしまうことが許されるのか、という観点から公序の内容を構成すべきだと思っています。
捨て子が母子関係存在確認の裁判を起こした場合、子が証明しなければならないのは、分娩という事実であって遺伝的なつながりではないってことでいいんですか。遺伝的なつながりが証明できてもそれだけで親子関係が証明されるのではなく、遺伝的なつながりがあれば通常分娩もしてるだろうという事実上の推定がなされるというだけなのか。
これにあわせて父子関係についても、遺伝的なつながりがあるだけでは足りず、自然生殖によるものだとの証明をしなければならないのか。
このへんは要件事実が何かという問題でもあります。私には、遺伝子的なつながりが主要事実であり分娩はこれを立証するための間接事実だと思えるのですが、最高裁の立場は分娩自体が主要事実だということのようです。
・とにかく実子じゃなきゃいやだっていうのは養子は実子よりも下だということ?
・「分娩者=母」ルールを壊して実子を拡げるというやり方と、養子縁組を手続がしやすいように整備しつつ養子を法的にも社会的にも実子と同等にしていくやり方とで、子の福祉に何か違いがあるか。
・例の件では、代理母契約の問題で養子縁組できないとのことのようですが、日本じゃ代理母が認められないってことを知ってたなら、契約締結のときに「もし日本で母子関係が認められなかったら養子縁組に協力してね」って条項を入れることもできたはず。それをしないでおいて、母子関係が認められないと子の福祉が害される、っていうのは、子を自ら危険に晒しておいて他人に助けなさいと言ってるようなものでしょ。本当に子供のためを思うなら、事前に養子縁組ルートを確保しておくべきなのに、とにかく実子がいいという大人側の理屈でそれを閉ざしちゃったと。将来の問題解決のために自分の子供を犠牲にするのはあまり褒められたものではないでしょ。
ルールは守らなきゃいけないとも言っているようですが、なんでネバダ州のルールを絶対視する一方で日本のルールは守ろうとしないんでしょう。一次的には代理母ルートを望むにしても、それがだめだった場合に、日本のルールの中で最大限子供の福祉を確保できる手段をあらかじめ考えておく必要があったんじゃないですか。
将来、子が日本の裁判所で代理母に対して扶養請求をしたとしたら、ネバダ州の裁判は通則法上の公序ルートで排除されて代理母が子の母親とされる可能性が高いから、特別養子縁組を結んであげることのほうが代理母のためになるし(裁判管轄や執行の問題はありますが)。というか、縁組しないことのほうが契約違反となりそうで心配。
・代理母を認めるということは、子の側からみると、母となりうる者が複数いるにもかかわらず、子の意思を無視して一方的に分娩者との関係を断ち切ってしまうわけですよね(逆に、「分娩者=母」ルールを維持するということは、分娩者以外の者との関係を断ち切ってしまう)。
代理母を認めないことは自分の子供が欲しいという女性の権利を侵害している、といわれますが、逆に、代理母を認めることは自分を産んでくれた人とのつながりを維持したいという子供の権利を侵害しているわけです。分娩者が法的には実親とされていなくても出産してくれたという事実は消えないから何ら子供の権利は侵害していない、なんていうのであれば、卵子提供者が法的には実親とされていなくても遺伝的につながっているという事実は消えないから何ら女性の権利は侵害していない、ということもできますよね。
代理母・依頼者間の決めごとを、生まれてきた子供に押しつけてもいいのかどうか。そういう意味で、私は、代理母と子との関係を完全に断ち切ってしまう本件代理母契約は、分娩者と子との関係を保障している日本のルールからは受け入れないと考えています。
・養子縁組というのは、実親/養親と、親と呼ばれる人を2種類作り出す制度なわけです。人工生殖についても、現行の実子ルールに押し込めて、とにかくいずれか一方だけを母親とし他方を全くの他人と決めてしまうのではなく、(両者間に優劣があるとしても)なにがしかの形で両者とも親的なものであるような制度をつくるのもありなんじゃないかと思っています。
・実子か養子かなんて、所詮国が作った制度内での人為的な取り決めなんだから、そこまで制度上の実子にこだわる必要があるかは疑問。だけども、まったく同じ理由で「分娩者=母」ルールにこだわる必要があるのかも疑問。
・代理母を禁止したいからといって、それによって生まれた子を依頼女性の実子とは認めないという手段によって抑止するのは、非嫡出子の相続分を差別するのと同じ、大人の不始末を子に償わせることになって最悪のやり方ですよね。
だから、代理母を認めるかどうかということと実子ルールをどうするかということは、区別して考えるべきでしょう。代理母は社会的に受け入れられないとして依頼者・代理母や実施機関にペナルティを課すとしても、誰を実親とすべきかは、一般的にみて誰との間に親子関係から生ずる権利義務を発生させることがよいか、という観点から決めるべきでしょう。で、どちらかを実親とすると制度決定したとしても、個別具体的な事情により子の福祉にかなわない場合のために、全くの他人を養子縁組する場合とは異なった規律によって養子縁組的な制度を用意すべき、だと考えています。
大人の事情と子供の福祉を区別しなきゃいけないというのは「赤ちゃんポスト」問題もおんなしような話で、無責任に子供をつくることを防ぐことで不幸な子供が生まれてくることを減らす一方で、できてしまった子供を救うことで現に不幸な子供を減らさなきゃいけないってことです。一般予防効果を弱めたくないからといって、そのために、現実に生まれてきてしまった子供を犠牲にするわけにはいかないでしょう。
(以下、「代理母」については依頼女性が卵子を提供するタイプ(依頼女性=卵子提供者)を前提にします)
・結論自体は最高裁に同意できますが、身分関係は「身分法秩序の根幹をなす基本原則ないし基本理念にかかわるもの」であるにもかかわらず、親子関係がどういう場合に成立するのか直接明記した規定がないってのはどうかと思います。これは最高裁決定の問題ではなく法律の問題。
・「分娩者=母」ルールは、法律に明記されたルールではなく、判例が作り出したルールにすぎないわけですよね。だからこのルール、国民の合意に基づいてできあがったものじゃないわけです。そして、決定ではこのルールの根拠としては一義的に明確な基準だからだとされています。
そうだとすると、1親子関係は遺伝子により判定する、2母子関係はわざわざDNA鑑定をしないでも分娩によりこれを推定する、3父子関係は婚姻中に懐胎したらこれを推定する(772条1項)、というルールでも別に不明確じゃないし、現行法にも反しないから、採用可能なルールですよね。
にもかかわらず、現行の「分娩者=母」ルールを維持するってのを、単に明確性というだけで理由付けるのは不十分でしょう。これまでのルールを変えたくない、かえるなら立法でお願いします、てことか、あるいは、代理母ビジネスに与えるよろしくない影響を鑑みたか、倫理の問題があるからか、いずれにしても別の理由付けが必要なはずです。
しかも、本件ではあくまで外国判決の承認ルートにおける公序要件の問題であって、日本法(というか判例法)のルールを変更せよ、といってるわけじゃないから、単に明確性というだけで、裁判所でつくった「分娩者=母」ルールが日本の公序の根幹をなすことの理由として十分かも疑問です。
最高裁は、立法におまかせします的なことを言っていますが、立法で変更できる程度のルールが公序といえるのかどうか。複数のルールを認めるならば、一義的でもなくなりますし。
私としては、「分娩者=母」ルールそれ自体を公序の内容とするのではなく、なんら法規制がない状態で代理母を認めてしまうことが日本社会として耐えられるのか、あるいは、子の側からみて分娩者との親子関係を断絶されてしまうことが許されるのか、という観点から公序の内容を構成すべきだと思っています。
捨て子が母子関係存在確認の裁判を起こした場合、子が証明しなければならないのは、分娩という事実であって遺伝的なつながりではないってことでいいんですか。遺伝的なつながりが証明できてもそれだけで親子関係が証明されるのではなく、遺伝的なつながりがあれば通常分娩もしてるだろうという事実上の推定がなされるというだけなのか。
これにあわせて父子関係についても、遺伝的なつながりがあるだけでは足りず、自然生殖によるものだとの証明をしなければならないのか。
このへんは要件事実が何かという問題でもあります。私には、遺伝子的なつながりが主要事実であり分娩はこれを立証するための間接事実だと思えるのですが、最高裁の立場は分娩自体が主要事実だということのようです。
・とにかく実子じゃなきゃいやだっていうのは養子は実子よりも下だということ?
・「分娩者=母」ルールを壊して実子を拡げるというやり方と、養子縁組を手続がしやすいように整備しつつ養子を法的にも社会的にも実子と同等にしていくやり方とで、子の福祉に何か違いがあるか。
・例の件では、代理母契約の問題で養子縁組できないとのことのようですが、日本じゃ代理母が認められないってことを知ってたなら、契約締結のときに「もし日本で母子関係が認められなかったら養子縁組に協力してね」って条項を入れることもできたはず。それをしないでおいて、母子関係が認められないと子の福祉が害される、っていうのは、子を自ら危険に晒しておいて他人に助けなさいと言ってるようなものでしょ。本当に子供のためを思うなら、事前に養子縁組ルートを確保しておくべきなのに、とにかく実子がいいという大人側の理屈でそれを閉ざしちゃったと。将来の問題解決のために自分の子供を犠牲にするのはあまり褒められたものではないでしょ。
ルールは守らなきゃいけないとも言っているようですが、なんでネバダ州のルールを絶対視する一方で日本のルールは守ろうとしないんでしょう。一次的には代理母ルートを望むにしても、それがだめだった場合に、日本のルールの中で最大限子供の福祉を確保できる手段をあらかじめ考えておく必要があったんじゃないですか。
将来、子が日本の裁判所で代理母に対して扶養請求をしたとしたら、ネバダ州の裁判は通則法上の公序ルートで排除されて代理母が子の母親とされる可能性が高いから、特別養子縁組を結んであげることのほうが代理母のためになるし(裁判管轄や執行の問題はありますが)。というか、縁組しないことのほうが契約違反となりそうで心配。
・代理母を認めるということは、子の側からみると、母となりうる者が複数いるにもかかわらず、子の意思を無視して一方的に分娩者との関係を断ち切ってしまうわけですよね(逆に、「分娩者=母」ルールを維持するということは、分娩者以外の者との関係を断ち切ってしまう)。
代理母を認めないことは自分の子供が欲しいという女性の権利を侵害している、といわれますが、逆に、代理母を認めることは自分を産んでくれた人とのつながりを維持したいという子供の権利を侵害しているわけです。分娩者が法的には実親とされていなくても出産してくれたという事実は消えないから何ら子供の権利は侵害していない、なんていうのであれば、卵子提供者が法的には実親とされていなくても遺伝的につながっているという事実は消えないから何ら女性の権利は侵害していない、ということもできますよね。
代理母・依頼者間の決めごとを、生まれてきた子供に押しつけてもいいのかどうか。そういう意味で、私は、代理母と子との関係を完全に断ち切ってしまう本件代理母契約は、分娩者と子との関係を保障している日本のルールからは受け入れないと考えています。
・養子縁組というのは、実親/養親と、親と呼ばれる人を2種類作り出す制度なわけです。人工生殖についても、現行の実子ルールに押し込めて、とにかくいずれか一方だけを母親とし他方を全くの他人と決めてしまうのではなく、(両者間に優劣があるとしても)なにがしかの形で両者とも親的なものであるような制度をつくるのもありなんじゃないかと思っています。
・実子か養子かなんて、所詮国が作った制度内での人為的な取り決めなんだから、そこまで制度上の実子にこだわる必要があるかは疑問。だけども、まったく同じ理由で「分娩者=母」ルールにこだわる必要があるのかも疑問。
・代理母を禁止したいからといって、それによって生まれた子を依頼女性の実子とは認めないという手段によって抑止するのは、非嫡出子の相続分を差別するのと同じ、大人の不始末を子に償わせることになって最悪のやり方ですよね。
だから、代理母を認めるかどうかということと実子ルールをどうするかということは、区別して考えるべきでしょう。代理母は社会的に受け入れられないとして依頼者・代理母や実施機関にペナルティを課すとしても、誰を実親とすべきかは、一般的にみて誰との間に親子関係から生ずる権利義務を発生させることがよいか、という観点から決めるべきでしょう。で、どちらかを実親とすると制度決定したとしても、個別具体的な事情により子の福祉にかなわない場合のために、全くの他人を養子縁組する場合とは異なった規律によって養子縁組的な制度を用意すべき、だと考えています。
大人の事情と子供の福祉を区別しなきゃいけないというのは「赤ちゃんポスト」問題もおんなしような話で、無責任に子供をつくることを防ぐことで不幸な子供が生まれてくることを減らす一方で、できてしまった子供を救うことで現に不幸な子供を減らさなきゃいけないってことです。一般予防効果を弱めたくないからといって、そのために、現実に生まれてきてしまった子供を犠牲にするわけにはいかないでしょう。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[こわれてく民法] カテゴリの最新記事
-
代襲相続の謎と細切れ要件事実論(その2) 2007年08月03日
-
代襲相続の謎と細切れ要件事実論(その1) 2007年08月01日
-
一親多子と一子多親 2007年05月12日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.