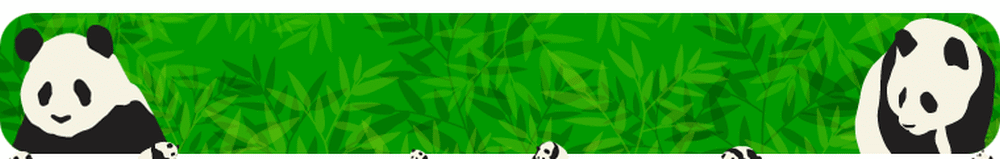PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: こわれてく民法
不可分債務、保証(債権総論)、賃貸借(契約各論)、債務の相続、遺産分割(相続法)とそれぞれの領域にまたがっているせいで、どこを読めばこういうことが書いてあるのか見つかりません。判例があるところは断片的に記述があるんだけども。
以下、未整理かつ何の解決もできていないので、ちょこちょこ書き加えていくと思います。
A賃貸人 B賃借人 C保証人
〈事例1〉
1 AB間 土地賃貸借契約
2 AC間 保証契約
3 Bが死亡しDEが相続
・ Bの賃借人の地位はDEに相続される。この時点ではDEの賃借人の債務は不可分債務である(判例)。
・ DE間で、DがBの地位を相続するとの遺産分割協議が成立した場合、これをAに対抗できるのか?
どうせAにとっては誰が賃借人になろうが賃料が現実に入ってこなければ債務不履行解除できるんだから差し支えない、といえそうですが、Aが、とにかく出て行ってもらえればそれでいいと考えているんだったらそういうことでいいんでしょうが、未払賃料が相当な額になっていてこれを回収したいと考えている場合は、未払債務を誰が相続するかは非常な関心事ですよね。
共同賃借人の賃料債務が金銭債務なのに不可分債務であることの趣旨を推し進めれば、そして、金銭債務を特定の相続人に相続させるには免責的債務引受の要件が必要となることからすれば、ここでも同様の要件を必要とすべきでしょうか。ただ、通常の金銭債務の相続の場面では「法定相続分による分割債務か特定人への相続か」という選択肢ですが、この場面では分割債務ではなく「不可分債務」にもなりうるので、通常の金銭債務とは違った判断要素が含まれていることになります。
仮に、債務引受の要件を必要とすべきだとして、これは過去の未払賃料債務の相続だけに要求されるのか、債権債務が一体となった賃借人の地位そのものの相続にも要求すべきなのか。
あれこれ書きましたが、こういう問題はすべて、「相続は賃借権の「譲渡」(民法612条)にあたらないから賃貸人の承諾なく自由に行うことが出来る」という解釈だけで割り切ることができますか(もちろん、そもそも不可分債務か否かという問題は612条では解決できませんが、612条により相続が自由ならば、不可分債務だろうが何だろうが相続人側が自由に結論を左右できるということになって、遺産分割されてしまえば不可分債務か否かを問う実益がなくなるというわけです)。
けど、民法612条は「権利」の譲渡とあって「債務」については明記していないし、譲渡の場合に承諾がいるからって非譲渡の場合にはおよそ承諾がいらないという反対解釈が直ちにでてくるわけではないでしょ。
「A(譲渡)ならばB(要承諾)である」が真だからといって「非Aならば非Bである」が真とは限らないわけです。前件からでてくるのは「非Bならば非Aである(承諾がいらないならば譲渡ではない)」が真だということ。だから、反対解釈が文字通り通用するのは、民法612条から、譲渡にあたらない場合には承諾を要求してはいけない、というところまで規制を及ぼしているという趣旨が読み取れる場合に限られるわけです。でも、そこまでのことは読み取れないでしょう。
というわけで、債務については612条は全く規律していないので通常の債務引受に従うとしたり、権利に伴う債務については賃借人の地位の移転に含まれるが過去の未払債務については相続する権利に伴うものではないので、過去の未払債務の相続は通常の債務引受に従う、という解釈もありうるわけです。
909条を援用して、賃貸人は同条にいう「第三者」に該当しないから相続人は遺産分割を賃貸人に対抗できる、っていうのも同じことでしょ。債務の相続だって、その債務の債権者は「第三者」とはいえないけど、免責的債務引受の要件が要求されるわけだし。
〈事例2〉
1 AB間 土地賃貸借契約
2 AC間 保証契約
・ Cの保証人の地位はFGに相続される。この場合、FGの債務は不可分債務か可分債務か。ア過去の未払債務、イ将来の賃料債務、ウ賃借物返還債務(これに保証が及ぶことは判例)の(保証債務の)どれかによって区別されるか?
・ FG間でFがCの地位を相続するとの遺産分割協議が成立した場合、これをAに対抗できるのか?
・ C死亡前に未払賃料があった場合、これを保証人の地位の相続とともにFのみに相続させることができるのか、これをAに対抗できるのか?また、未払債務のみはGに相続させることはできるのか。
主債務の賃料債務が不可分債務となる場合に、これに対する保証債務まで不可分債務になるのかどうか。主債務としてのアイが金銭債務なのに不可分債務とされたとしても、これにあわせて保証債務までもが不可分債務となってしまうのか。
特に〈事例2〉では主債務者はB1人のままなので、現状では主債務の不可分債務性は顕在化していないにもかかわらず、保証債務だけが不可分債務となるのか。まあ、〈事例2〉で「4 Bが死亡しDEが相続」した途端、FG保証債務も不可分債務化するというのもおかしな話なので、FG相続の時点で不可分債務か可分債務かどちらかに決めないといけないんでしょう。
共同賃借人の賃料債務は不可分債務であるという判例、賃貸借の保証債務には賃借物返還債務という性質上の不可分債務が含まれるという判例から、判例のない隙間部分を想像力豊かにうめていくと、賃貸借の保証債務はすべて不可分債務になるような気がしますが、何ら法的根拠はありません。通常の金銭債務が連帯債務だった場合でも、複数人に相続された場合は分割債務になるって判例もあることだし。
遺産分割の問題は〈事例1〉と同様
以下、未整理かつ何の解決もできていないので、ちょこちょこ書き加えていくと思います。
A賃貸人 B賃借人 C保証人
〈事例1〉
1 AB間 土地賃貸借契約
2 AC間 保証契約
3 Bが死亡しDEが相続
・ Bの賃借人の地位はDEに相続される。この時点ではDEの賃借人の債務は不可分債務である(判例)。
・ DE間で、DがBの地位を相続するとの遺産分割協議が成立した場合、これをAに対抗できるのか?
どうせAにとっては誰が賃借人になろうが賃料が現実に入ってこなければ債務不履行解除できるんだから差し支えない、といえそうですが、Aが、とにかく出て行ってもらえればそれでいいと考えているんだったらそういうことでいいんでしょうが、未払賃料が相当な額になっていてこれを回収したいと考えている場合は、未払債務を誰が相続するかは非常な関心事ですよね。
共同賃借人の賃料債務が金銭債務なのに不可分債務であることの趣旨を推し進めれば、そして、金銭債務を特定の相続人に相続させるには免責的債務引受の要件が必要となることからすれば、ここでも同様の要件を必要とすべきでしょうか。ただ、通常の金銭債務の相続の場面では「法定相続分による分割債務か特定人への相続か」という選択肢ですが、この場面では分割債務ではなく「不可分債務」にもなりうるので、通常の金銭債務とは違った判断要素が含まれていることになります。
仮に、債務引受の要件を必要とすべきだとして、これは過去の未払賃料債務の相続だけに要求されるのか、債権債務が一体となった賃借人の地位そのものの相続にも要求すべきなのか。
あれこれ書きましたが、こういう問題はすべて、「相続は賃借権の「譲渡」(民法612条)にあたらないから賃貸人の承諾なく自由に行うことが出来る」という解釈だけで割り切ることができますか(もちろん、そもそも不可分債務か否かという問題は612条では解決できませんが、612条により相続が自由ならば、不可分債務だろうが何だろうが相続人側が自由に結論を左右できるということになって、遺産分割されてしまえば不可分債務か否かを問う実益がなくなるというわけです)。
けど、民法612条は「権利」の譲渡とあって「債務」については明記していないし、譲渡の場合に承諾がいるからって非譲渡の場合にはおよそ承諾がいらないという反対解釈が直ちにでてくるわけではないでしょ。
「A(譲渡)ならばB(要承諾)である」が真だからといって「非Aならば非Bである」が真とは限らないわけです。前件からでてくるのは「非Bならば非Aである(承諾がいらないならば譲渡ではない)」が真だということ。だから、反対解釈が文字通り通用するのは、民法612条から、譲渡にあたらない場合には承諾を要求してはいけない、というところまで規制を及ぼしているという趣旨が読み取れる場合に限られるわけです。でも、そこまでのことは読み取れないでしょう。
というわけで、債務については612条は全く規律していないので通常の債務引受に従うとしたり、権利に伴う債務については賃借人の地位の移転に含まれるが過去の未払債務については相続する権利に伴うものではないので、過去の未払債務の相続は通常の債務引受に従う、という解釈もありうるわけです。
909条を援用して、賃貸人は同条にいう「第三者」に該当しないから相続人は遺産分割を賃貸人に対抗できる、っていうのも同じことでしょ。債務の相続だって、その債務の債権者は「第三者」とはいえないけど、免責的債務引受の要件が要求されるわけだし。
〈事例2〉
1 AB間 土地賃貸借契約
2 AC間 保証契約
・ Cの保証人の地位はFGに相続される。この場合、FGの債務は不可分債務か可分債務か。ア過去の未払債務、イ将来の賃料債務、ウ賃借物返還債務(これに保証が及ぶことは判例)の(保証債務の)どれかによって区別されるか?
・ FG間でFがCの地位を相続するとの遺産分割協議が成立した場合、これをAに対抗できるのか?
・ C死亡前に未払賃料があった場合、これを保証人の地位の相続とともにFのみに相続させることができるのか、これをAに対抗できるのか?また、未払債務のみはGに相続させることはできるのか。
主債務の賃料債務が不可分債務となる場合に、これに対する保証債務まで不可分債務になるのかどうか。主債務としてのアイが金銭債務なのに不可分債務とされたとしても、これにあわせて保証債務までもが不可分債務となってしまうのか。
特に〈事例2〉では主債務者はB1人のままなので、現状では主債務の不可分債務性は顕在化していないにもかかわらず、保証債務だけが不可分債務となるのか。まあ、〈事例2〉で「4 Bが死亡しDEが相続」した途端、FG保証債務も不可分債務化するというのもおかしな話なので、FG相続の時点で不可分債務か可分債務かどちらかに決めないといけないんでしょう。
共同賃借人の賃料債務は不可分債務であるという判例、賃貸借の保証債務には賃借物返還債務という性質上の不可分債務が含まれるという判例から、判例のない隙間部分を想像力豊かにうめていくと、賃貸借の保証債務はすべて不可分債務になるような気がしますが、何ら法的根拠はありません。通常の金銭債務が連帯債務だった場合でも、複数人に相続された場合は分割債務になるって判例もあることだし。
遺産分割の問題は〈事例1〉と同様
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[こわれてく民法] カテゴリの最新記事
-
代襲相続の謎と細切れ要件事実論(その2) 2007年08月03日
-
代襲相続の謎と細切れ要件事実論(その1) 2007年08月01日
-
一親多子と一子多親 2007年05月12日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.