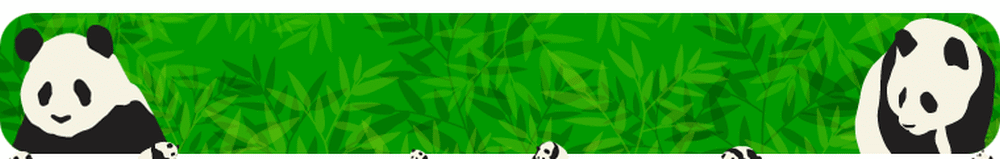PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: はんぱに裁判員制度
以前にもどこかで書いたと思いますが、国民に対して何をすれば処罰されるのかを事前に知らせる行為規範性を強調しておきながら、個々の解釈論としては普通の人に理解できないような説をとなえているのは、おかしいんじゃないかと。
行為規範性を強調する方向の行く先は、裁判官が裁判で用いる裁判規範は厳密なものとしておき、それとは別に行為者に対する簡単な内容の行為規範を用意しておくか、裁判規範ごと国民に理解しやすい内容にしてしまうか、ですよね。
それでも、従来は「行為者」に対する関係(規範を向けられる側)でどうするかってことだけを考えてればよかったんですが、これからは「裁判員」というもう一つのタイプの国民との関係(規範を用いる側)を考えなければならなくなりましたよね。
とすると、裁判員制度の導入趣旨から考えて、もはや刑法解釈論なんてものは放棄してしまい、条文だけを手がかりにあとは国民の処罰感情とかいうものだけをストレートに結論に反映させればいいんですか。
あるいは、裁判員制度はあくまで「手続問題」だということで、刑法解釈論には影響はない、あるいは影響を及ぼすべきではない、ということになりますか。
行為規範性を強調する方向の行く先は、裁判官が裁判で用いる裁判規範は厳密なものとしておき、それとは別に行為者に対する簡単な内容の行為規範を用意しておくか、裁判規範ごと国民に理解しやすい内容にしてしまうか、ですよね。
それでも、従来は「行為者」に対する関係(規範を向けられる側)でどうするかってことだけを考えてればよかったんですが、これからは「裁判員」というもう一つのタイプの国民との関係(規範を用いる側)を考えなければならなくなりましたよね。
とすると、裁判員制度の導入趣旨から考えて、もはや刑法解釈論なんてものは放棄してしまい、条文だけを手がかりにあとは国民の処罰感情とかいうものだけをストレートに結論に反映させればいいんですか。
あるいは、裁判員制度はあくまで「手続問題」だということで、刑法解釈論には影響はない、あるいは影響を及ぼすべきではない、ということになりますか。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[はんぱに裁判員制度] カテゴリの最新記事
-
常識的犯罪論の断層 2007年05月15日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.