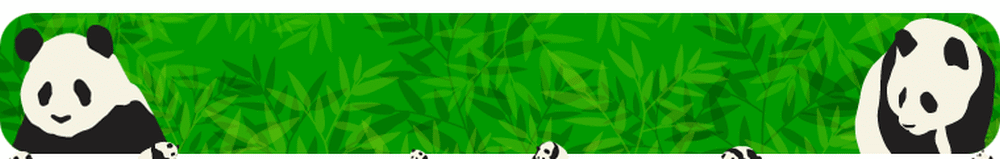PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: 及び腰か勇み足な書評
以前の日記で書いた代理母がらみの最高裁決定について、樋口範雄先生が法学教室322号で「人工生殖で生まれた子の親子関係」という論文を書かれています。
で、これに対して、森田博志先生の ブログ で詳しく批判的検討がなされています。
私も、樋口論文にはどこか違和感を感じているのですが、森田先生ほどの的確な批判ができるわけでもないので、印象論どまりの話をします(にもかかわらず、だいぶ勇み足となります)。
・
樋口先生自身の結論は、最高裁決定に批判的で、卵子提供者と子との母子関係を認め(たネヴァタ州の判決を承認す)るべきだ、というものです。
変なところに括弧をつけたのは、最高裁決定自体は「外国判決の承認」という国際民事訴訟法上の問題であるのに、樋口先生の論述は、「子の福祉のために親子関係を認めるべきか」という実質法レベルの話にとどまっていて何かずれている気がしたからです(気のせいなら幸いです)。
・
いきなり「結びに代えて」のところからいうと、「法律論の限界に気づかざるをえない」なんていうけども、それは当たり前でしょうと思いました。
法律論に限界がないならば、法解釈に関するあれやこれやのルールも、もはや不要ですよね。というか、法律の存在そのものがいらないのかもしれません。ここで何か喩えを挙げて「法律が存在していながら法律論に限界がない」という状態を説明しようと思ったのですが、どうにも想像ができませんでした。
とんち和尚だって、立て札にちゃんと漢字で『橋』と書かれているにもかかわらず、これを勝手に同音である『端』に読みかえて橋の端を渡ったとしたら、それはとんちでもなんでもなく、単なる無法者にすぎません。幸い立て札をひらがなで書いていてくれたおかげで、同音異義語に読み替えることができたわけです。
つまり、いくらとんちとはいえ、ひらがなならまだしも、漢字で書かれているものを同音に読みかえるのはさすがにまずいでしょう、という、とんち解釈の限界があるからに他なりません。
問題はどこに「限界」を引くかということだと思います。
・
法解釈者は、その法律がどこに線を引いているのか、あるいはひくべきかを議論しているわけです。
最高裁の線引きに納得がいかないからといって、法律論には限界がある(のはおかしい)などと法の専門家がいうのは自分の仕事を自ら否定しているように聞こえます。
法解釈者としては、その線引きがおかしいと正面から批判すればいいことです。実際、(内容はともかく)「結びに代えて」に至るまでの樋口論文の中身ではそうしているのであって、法律論には限界があるなんて誤導的な捨てセリフを残す必要はないでしょう。
とんち和尚の事例でも、「ひらがなの場合は同音ならどの意味でとってもよい」というところに線を引くのか、「ひらがなの場合は文脈から可能な範囲に限定する」というところに線を引くのか、という線を引く場所の議論をするわけです。「線なんか引かなくていい」なんていいだしたら法律はその役割を終えることになってしまいます。
・
裁判所自身もこれまで、親子関係につき、文言上認知となっているのを分娩と解釈してみたり、推定規定を(事実上)拡大したり、制限したりして、それなりに工夫してきているわけです。なので「法律論の限界に気づかざるをえない」などと突き放したようなことをいうのではなく、いいところを伸ばしてやればいいわけです。
いずれにしても、限界を設けることが法律の役割であることは、変えようがないと思います。
・
一方当事者側にたって鑑定書を書いたせいで当事者の感情に引っ張られてしまったんでしょうか。法律論には解釈論も立法論もあるのに、これを区別しないで法律論とまとめて言ってしまっていることとか、法律論には限界があるとか言ってしまっているあたりも、自分が納得いかない裁判に対して非法律家の人がいう常套句だし。
ちなみに、現政権や前政権を見れば、立法論には限界がないんだなあと実感せざるをえないですよね(極端な例は、手続「法」の内容を緩くすることで硬性「憲法」をやわらかくしちゃうところとか)。
・
最高裁自身は、お腹を痛めた人が母親だという日本のルールとは違うルールを認めてもよいのかという身分法秩序のことしか触れていませんが、代理母を正面から認めることによって犠牲を被る人も出てくることも考えなければならないはずです。
しかも、子の福祉を保護することは、何も卵子提供者との間に「親子関係」というものを認めることによってしか果たせないわけではありません。親がいるからといって必ず幸せになれるわけでもなければ、親がいないからといって必ず幸せになれないわけではありません。
だから、
子の福祉 対 身分法秩序
という抽象化された図式は正確ではなく、
代理母による親子関係を認めることによる得失 対 認めないことによる得失
という事実関係そのままで対比させなければ、正確な議論ができなくなってしまいます。前者の図式では、あたかも代理母否定説が子の福祉を考えていないようなレッテルを張られてしまいますが、必ずしもそうではないということ、また、代理母肯定説が、子の福祉をはかる手段を親子関係の設定しか考えていないことや、代理母による親子関係を認めることによって生ずる犠牲のことを十分考慮していないことも見えにくくなってしまいます。
・
また、最初に述べたように、樋口論文が、実質法レベルの議論をしているのか国際民事訴訟法レベルの話をしているのか、区別されているようには思えません。最高裁決定の批判をしているというスタイルからすれば、国際民事訴訟法レベルの話をしなければならないはずですが、民事訴訟法118条上の「公序」とは何か、ということについては正面から論じていないように思います。
こういう区別が得意なのは、やはり国際私法の学者の側なんでしょうか(ちなみに、道垣内先生は、実質法と抵触法を、蟻と鳩の比喩で対比しています。や、別に他意はありません)。
・
以上、批判的な物言いになっていますが、「法律論の限界に気づかざるを得ない」という記述に対する批判だったり外在的な批判であって、樋口先生個人の見解そのものに対して批判しているわけではありません。
それに、樋口先生が文字通り「法律論の限界に気づかざるを得ない」などと本気で思っているとはどうも考えにくいですし。私が勝手に邪推するに、「最高裁決定の理由は硬直的で結論は不当である」という主張に、どこからか当事者の感情が混入した結果、そういう表現になったんでしょうか。
フォローじゃなく本音として、樋口先生の作品はおもしろいと思いますよ。たとえば、
「アメリカ信託法ノート(1)」 「アメリカ信託法ノート(2)」
内容は非常におもしろいですが、無闇なスペースを減らせばA4判1冊で足りたはず。
「フィデュシャリー「信認」の時代」
信認概念について、日本法の解釈論にどう反映させられるのか、いろいろ考えてみたくなります。
「アメリカ代理法」
FAのAってエージェント(代理人)のこと、ってところから始まるアメリカの代理のお話。
で、これに対して、森田博志先生の ブログ で詳しく批判的検討がなされています。
私も、樋口論文にはどこか違和感を感じているのですが、森田先生ほどの的確な批判ができるわけでもないので、印象論どまりの話をします(にもかかわらず、だいぶ勇み足となります)。
・
樋口先生自身の結論は、最高裁決定に批判的で、卵子提供者と子との母子関係を認め(たネヴァタ州の判決を承認す)るべきだ、というものです。
変なところに括弧をつけたのは、最高裁決定自体は「外国判決の承認」という国際民事訴訟法上の問題であるのに、樋口先生の論述は、「子の福祉のために親子関係を認めるべきか」という実質法レベルの話にとどまっていて何かずれている気がしたからです(気のせいなら幸いです)。
・
いきなり「結びに代えて」のところからいうと、「法律論の限界に気づかざるをえない」なんていうけども、それは当たり前でしょうと思いました。
法律論に限界がないならば、法解釈に関するあれやこれやのルールも、もはや不要ですよね。というか、法律の存在そのものがいらないのかもしれません。ここで何か喩えを挙げて「法律が存在していながら法律論に限界がない」という状態を説明しようと思ったのですが、どうにも想像ができませんでした。
とんち和尚だって、立て札にちゃんと漢字で『橋』と書かれているにもかかわらず、これを勝手に同音である『端』に読みかえて橋の端を渡ったとしたら、それはとんちでもなんでもなく、単なる無法者にすぎません。幸い立て札をひらがなで書いていてくれたおかげで、同音異義語に読み替えることができたわけです。
つまり、いくらとんちとはいえ、ひらがなならまだしも、漢字で書かれているものを同音に読みかえるのはさすがにまずいでしょう、という、とんち解釈の限界があるからに他なりません。
問題はどこに「限界」を引くかということだと思います。
・
法解釈者は、その法律がどこに線を引いているのか、あるいはひくべきかを議論しているわけです。
最高裁の線引きに納得がいかないからといって、法律論には限界がある(のはおかしい)などと法の専門家がいうのは自分の仕事を自ら否定しているように聞こえます。
法解釈者としては、その線引きがおかしいと正面から批判すればいいことです。実際、(内容はともかく)「結びに代えて」に至るまでの樋口論文の中身ではそうしているのであって、法律論には限界があるなんて誤導的な捨てセリフを残す必要はないでしょう。
とんち和尚の事例でも、「ひらがなの場合は同音ならどの意味でとってもよい」というところに線を引くのか、「ひらがなの場合は文脈から可能な範囲に限定する」というところに線を引くのか、という線を引く場所の議論をするわけです。「線なんか引かなくていい」なんていいだしたら法律はその役割を終えることになってしまいます。
・
裁判所自身もこれまで、親子関係につき、文言上認知となっているのを分娩と解釈してみたり、推定規定を(事実上)拡大したり、制限したりして、それなりに工夫してきているわけです。なので「法律論の限界に気づかざるをえない」などと突き放したようなことをいうのではなく、いいところを伸ばしてやればいいわけです。
いずれにしても、限界を設けることが法律の役割であることは、変えようがないと思います。
・
一方当事者側にたって鑑定書を書いたせいで当事者の感情に引っ張られてしまったんでしょうか。法律論には解釈論も立法論もあるのに、これを区別しないで法律論とまとめて言ってしまっていることとか、法律論には限界があるとか言ってしまっているあたりも、自分が納得いかない裁判に対して非法律家の人がいう常套句だし。
ちなみに、現政権や前政権を見れば、立法論には限界がないんだなあと実感せざるをえないですよね(極端な例は、手続「法」の内容を緩くすることで硬性「憲法」をやわらかくしちゃうところとか)。
・
最高裁自身は、お腹を痛めた人が母親だという日本のルールとは違うルールを認めてもよいのかという身分法秩序のことしか触れていませんが、代理母を正面から認めることによって犠牲を被る人も出てくることも考えなければならないはずです。
しかも、子の福祉を保護することは、何も卵子提供者との間に「親子関係」というものを認めることによってしか果たせないわけではありません。親がいるからといって必ず幸せになれるわけでもなければ、親がいないからといって必ず幸せになれないわけではありません。
だから、
子の福祉 対 身分法秩序
という抽象化された図式は正確ではなく、
代理母による親子関係を認めることによる得失 対 認めないことによる得失
という事実関係そのままで対比させなければ、正確な議論ができなくなってしまいます。前者の図式では、あたかも代理母否定説が子の福祉を考えていないようなレッテルを張られてしまいますが、必ずしもそうではないということ、また、代理母肯定説が、子の福祉をはかる手段を親子関係の設定しか考えていないことや、代理母による親子関係を認めることによって生ずる犠牲のことを十分考慮していないことも見えにくくなってしまいます。
・
また、最初に述べたように、樋口論文が、実質法レベルの議論をしているのか国際民事訴訟法レベルの話をしているのか、区別されているようには思えません。最高裁決定の批判をしているというスタイルからすれば、国際民事訴訟法レベルの話をしなければならないはずですが、民事訴訟法118条上の「公序」とは何か、ということについては正面から論じていないように思います。
こういう区別が得意なのは、やはり国際私法の学者の側なんでしょうか(ちなみに、道垣内先生は、実質法と抵触法を、蟻と鳩の比喩で対比しています。や、別に他意はありません)。
・
以上、批判的な物言いになっていますが、「法律論の限界に気づかざるを得ない」という記述に対する批判だったり外在的な批判であって、樋口先生個人の見解そのものに対して批判しているわけではありません。
それに、樋口先生が文字通り「法律論の限界に気づかざるを得ない」などと本気で思っているとはどうも考えにくいですし。私が勝手に邪推するに、「最高裁決定の理由は硬直的で結論は不当である」という主張に、どこからか当事者の感情が混入した結果、そういう表現になったんでしょうか。
フォローじゃなく本音として、樋口先生の作品はおもしろいと思いますよ。たとえば、
「アメリカ信託法ノート(1)」 「アメリカ信託法ノート(2)」
内容は非常におもしろいですが、無闇なスペースを減らせばA4判1冊で足りたはず。
「フィデュシャリー「信認」の時代」
信認概念について、日本法の解釈論にどう反映させられるのか、いろいろ考えてみたくなります。
「アメリカ代理法」
FAのAってエージェント(代理人)のこと、ってところから始まるアメリカの代理のお話。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[及び腰か勇み足な書評] カテゴリの最新記事
-
佐藤英明『スタンダード所得税法』 2009年05月04日
-
大内伸哉『雇用はなぜ壊れたのか-会社の… 2009年05月03日
-
コリンP.A.ジョーンズ『手ごわい頭脳… 2009年05月02日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.