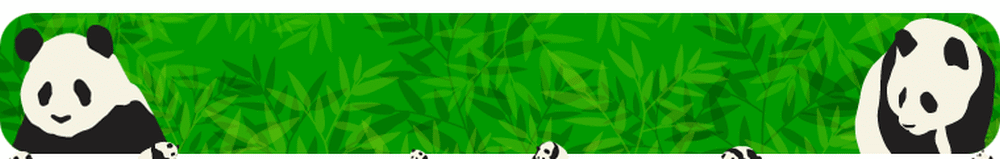PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: カテゴリ未分類
たとえば、「カラスはすべて黒い」というのは、あくまで仮説であって1匹でも黒くないカラスが見つかったら、覆っちゃう程度のものですよね。
あるいは、飛行機が飛ぶのはどういう原理かっていうのも、今支持されている原理が絶対的に正しいわけじゃなくって、今のところ、その原理を覆す事例(その原理に従っているのに飛ばない、その原理に従っていないのに飛ぶ)が見つかってないってだけですよね。
つまり、科学における学説っていうのは、事例1の場合は飛ぶ、2の場合は飛ばない、3の場合は、・・っていう「事例」(「原因」と「結果」といいかえてもいいと思います)を前にして、それらを整合的に説明できる「理屈」を考え出すってことですよね。そうすると、これまで支持されてきた学説と整合しない事例Xを見つけた場合には「発見」といっていいと思いますけど、「理屈」を考え出すことは、これまでに確認されている事例と矛盾していないものにすぎずそれが真実であるとは限らないから、「発見」とはいいにくいんじゃないですか。
ということで、科学というのは、いくつかの「原因」と「結果」があって、それらに合う「理屈」を考える、そしてその「理屈」に合わない事例が生じた場合にはさらなる「理屈」を考える、そういう営みなんだと思うわけです。
科学なんて自分にとって門外漢なことを偉そうに語ったのは、法学ってもっとひどいんじゃないかと思ったからです。
たとえば、刑法で、「二重抵当の場合に背任罪は成立するか」って論点に関して言うと、二重抵当という「原因(事例)」と刑法247条という「条文」だけではどういう「結果(結論)」(背任罪は成立か不成立か)がでるかが決まらずに、「条文」に論者が思い思いの「理屈」をくっつけた上で、自分の良しとする「結果(結論)」を自由に決められるからです。
科学では、「原因」と「結果」は任意に動かすことはできないから、それに合わない「理屈」はどんどん排除されるわけだけども、法学では、「理屈」の部分を任意に動かすことで「結果」をどちらにも転ばすことができてしまうわけです(科学のレベルでも、観察者によって「原因」と「結果」の見え方が異なるとか、観察したことによって「原因」が動いてしまい「結果」が変わってしまうとか、そういう話は置いておいて)。
科学 〔原因〕→ 理屈 →〔結果〕
(〔 〕は動かせない部分)
私の言葉の使い方が特殊なのかもしれないので、一応整理しておくと、科学における「事例」には、「原因」と「結果」の両方を含めていますが、法学でいう「事例」には、「原因」しか含めておらず「結果」はそこに入れてません。要するに、法学における「結果」はあらかじめ決まっているものではないので、「事例」の中に入れられないということです。
科学 「原因+結果」(=事例)
法学 「原因」(=事例・要件事実) 「結果」(=結論・効果)
もちろん、法解釈にもお作法があるから「理屈」の範囲は全くの無限ではないけども、同じ「条文」から全く逆の「結果」がでてくるような「理屈」が導き出せるなんていうのは、法律家以外の人からみたら、どうかしてるとしか思えないんじゃないですか。
さらにいえば、立法論という形で「条文」自体をかえることもできちゃうので、変わらないのはただ一つ、「原因」だけだということになります。
法学 〔原因〕→ 条文+理屈 → 結果
(立法論も含めて考えた場合)
だからといって、私は、「法学は科学たるべき」などというつもりはなくって、ただ、法学なんてのはこういうものなんだよ、と言いたかっただけです。
・
こういう文脈で「自然法思想」なんてのをながめると、「理屈」に対して、単なる法解釈上のお作法以上の限定をかけていくことで、好き勝手な結果を導き出せないようにする考えなんじゃないかと思えるわけです。
(《 》は自然法による限定がかけられている)
けども、その自然法の中身自体が、科学で言う「原因」と「結果」のように動かせないものではありません。なので、自分の良しとする結果を導くために、あるいは、自分の良しとしない結論を導かないために、自然法の中身を自由に決めることができてしまいます。
その他、法実証主義以外の考えってのは、ほとんどこういうことが当てはまるんじゃないかと思います。
法律には、こういう目に見えない限定ではなくって、「憲法」による限定というのもあります。けども、憲法自体も「条文」によってできているので、憲法による限定の中身も解釈により導き出さなければなりません。
憲法による限定は、憲法の条文がある以上、「自然法」とかとは違って融通無碍ってわけにはいきませんが、それでも、憲法解釈によってある程度自由にコントロールすることができます。しかも、憲法の条文は抽象的な規定が多いから、「法律」の解釈よりも解釈の幅が広いはずです。
・
さらにいえば、法が裁判の場で適用されるということを考慮に入れて、裁判で認定される事実は、裁判官が主観的に認定したものにすぎず、過去に起こった事実をそのまま再現したものではない、などといいだしたら、「原因」さえ不確かなものになってしまいます。
誰が決めるのかという観点でいうと、
原因 実務家。最終的には裁判官
↓
条文 立法者
+
理屈 学者、実務家。最終的には裁判官
↓
結果は、上の3つが決まれば必然的に決まるはずですがどうでしょうね。
ここまでくるときりがないので、このへんで止めておきます。
・
追記:
科学の場合も、「原因」と「結果」があらかじめ与えられているのではなく、ある特定の「結果」を導き出すためにどういう「原因」がそろえばよいかを探究する、という営みもあるわけですね。たとえば、生ゴミを有効な資源に変えるためにはどうしたらいいのか、とか。
科学の場合は、任意に「結果」を設定すればいいんでしょうが、法学の場合は、建前上、原因・条文・理屈がそろえば必然的に「結果」が決まることになっているわけですよね。
「効果から要件を考える」という発想というのは、ここでいう科学の場合と似ているわけですが、論者が任意に設定した「結果」の正しさというのは、どこで担保されることになるんでしょうか。
立法論の場合には、任意に「結果」を設定できるだけでなく、その結果を導くための「原因」(要件)も自由に設定できてしまうわけだけども、一応民主主義の手続に乗っ取ってやりました、という言い訳ができると。
あるいは、飛行機が飛ぶのはどういう原理かっていうのも、今支持されている原理が絶対的に正しいわけじゃなくって、今のところ、その原理を覆す事例(その原理に従っているのに飛ばない、その原理に従っていないのに飛ぶ)が見つかってないってだけですよね。
つまり、科学における学説っていうのは、事例1の場合は飛ぶ、2の場合は飛ばない、3の場合は、・・っていう「事例」(「原因」と「結果」といいかえてもいいと思います)を前にして、それらを整合的に説明できる「理屈」を考え出すってことですよね。そうすると、これまで支持されてきた学説と整合しない事例Xを見つけた場合には「発見」といっていいと思いますけど、「理屈」を考え出すことは、これまでに確認されている事例と矛盾していないものにすぎずそれが真実であるとは限らないから、「発見」とはいいにくいんじゃないですか。
ということで、科学というのは、いくつかの「原因」と「結果」があって、それらに合う「理屈」を考える、そしてその「理屈」に合わない事例が生じた場合にはさらなる「理屈」を考える、そういう営みなんだと思うわけです。
科学なんて自分にとって門外漢なことを偉そうに語ったのは、法学ってもっとひどいんじゃないかと思ったからです。
たとえば、刑法で、「二重抵当の場合に背任罪は成立するか」って論点に関して言うと、二重抵当という「原因(事例)」と刑法247条という「条文」だけではどういう「結果(結論)」(背任罪は成立か不成立か)がでるかが決まらずに、「条文」に論者が思い思いの「理屈」をくっつけた上で、自分の良しとする「結果(結論)」を自由に決められるからです。
科学では、「原因」と「結果」は任意に動かすことはできないから、それに合わない「理屈」はどんどん排除されるわけだけども、法学では、「理屈」の部分を任意に動かすことで「結果」をどちらにも転ばすことができてしまうわけです(科学のレベルでも、観察者によって「原因」と「結果」の見え方が異なるとか、観察したことによって「原因」が動いてしまい「結果」が変わってしまうとか、そういう話は置いておいて)。
科学 〔原因〕→ 理屈 →〔結果〕
(〔 〕は動かせない部分)
私の言葉の使い方が特殊なのかもしれないので、一応整理しておくと、科学における「事例」には、「原因」と「結果」の両方を含めていますが、法学でいう「事例」には、「原因」しか含めておらず「結果」はそこに入れてません。要するに、法学における「結果」はあらかじめ決まっているものではないので、「事例」の中に入れられないということです。
科学 「原因+結果」(=事例)
法学 「原因」(=事例・要件事実) 「結果」(=結論・効果)
もちろん、法解釈にもお作法があるから「理屈」の範囲は全くの無限ではないけども、同じ「条文」から全く逆の「結果」がでてくるような「理屈」が導き出せるなんていうのは、法律家以外の人からみたら、どうかしてるとしか思えないんじゃないですか。
さらにいえば、立法論という形で「条文」自体をかえることもできちゃうので、変わらないのはただ一つ、「原因」だけだということになります。
法学 〔原因〕→ 条文+理屈 → 結果
(立法論も含めて考えた場合)
だからといって、私は、「法学は科学たるべき」などというつもりはなくって、ただ、法学なんてのはこういうものなんだよ、と言いたかっただけです。
・
こういう文脈で「自然法思想」なんてのをながめると、「理屈」に対して、単なる法解釈上のお作法以上の限定をかけていくことで、好き勝手な結果を導き出せないようにする考えなんじゃないかと思えるわけです。
(《 》は自然法による限定がかけられている)
けども、その自然法の中身自体が、科学で言う「原因」と「結果」のように動かせないものではありません。なので、自分の良しとする結果を導くために、あるいは、自分の良しとしない結論を導かないために、自然法の中身を自由に決めることができてしまいます。
その他、法実証主義以外の考えってのは、ほとんどこういうことが当てはまるんじゃないかと思います。
法律には、こういう目に見えない限定ではなくって、「憲法」による限定というのもあります。けども、憲法自体も「条文」によってできているので、憲法による限定の中身も解釈により導き出さなければなりません。
憲法による限定は、憲法の条文がある以上、「自然法」とかとは違って融通無碍ってわけにはいきませんが、それでも、憲法解釈によってある程度自由にコントロールすることができます。しかも、憲法の条文は抽象的な規定が多いから、「法律」の解釈よりも解釈の幅が広いはずです。
・
さらにいえば、法が裁判の場で適用されるということを考慮に入れて、裁判で認定される事実は、裁判官が主観的に認定したものにすぎず、過去に起こった事実をそのまま再現したものではない、などといいだしたら、「原因」さえ不確かなものになってしまいます。
誰が決めるのかという観点でいうと、
原因 実務家。最終的には裁判官
↓
条文 立法者
+
理屈 学者、実務家。最終的には裁判官
↓
結果は、上の3つが決まれば必然的に決まるはずですがどうでしょうね。
ここまでくるときりがないので、このへんで止めておきます。
・
追記:
科学の場合も、「原因」と「結果」があらかじめ与えられているのではなく、ある特定の「結果」を導き出すためにどういう「原因」がそろえばよいかを探究する、という営みもあるわけですね。たとえば、生ゴミを有効な資源に変えるためにはどうしたらいいのか、とか。
科学の場合は、任意に「結果」を設定すればいいんでしょうが、法学の場合は、建前上、原因・条文・理屈がそろえば必然的に「結果」が決まることになっているわけですよね。
「効果から要件を考える」という発想というのは、ここでいう科学の場合と似ているわけですが、論者が任意に設定した「結果」の正しさというのは、どこで担保されることになるんでしょうか。
立法論の場合には、任意に「結果」を設定できるだけでなく、その結果を導くための「原因」(要件)も自由に設定できてしまうわけだけども、一応民主主義の手続に乗っ取ってやりました、という言い訳ができると。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.