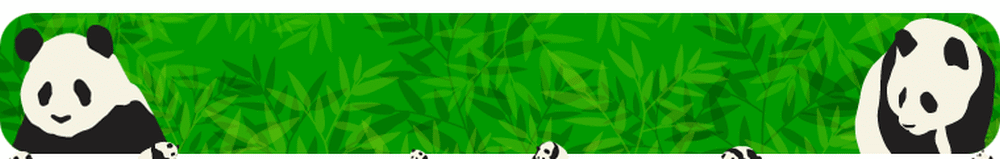PR
X
コメント新着
カテゴリ
カテゴリ未分類
(8)及び腰か勇み足な書評
(54)いたづらにむつかしい刑法
(17)ついつい批判的にみてしまう会社法
(18)かなしいけど積読よ
(5)とりあえず買ってみましたが
(10)こわれてく民法
(13)知的財産法だって法律でしょ。
(10)いくら法律じゃないからって、憲法
(2)困ったら裁量で行政法
(2)国際私法は国境を越えない?
(8)法律書への想いをこじらせて
(9)はんぱに裁判員制度
(2)生まれることと終わること
(3)ネットで論文を
(3)手続と実体で倒産法
(1)カテゴリ: 及び腰か勇み足な書評

・
この本は、ひとつひとつの取引ごとに、損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)、キャッシュ・フロー計算書(CS)のどの数字がどのように変わるか、3表のどことどこがつながっているか、という観点から記述されていて、財務諸表の動き方やそれぞれの役割を理解するにはとても分かりやすい本です。
通常の会計のルールでは、財務諸表はある一定期間経過後に作成するものですが、この本ではひとつひとつの取引ごとに、逐一新しい財務諸表を作成しているようなものです。
通常のルールのもとでは、「BSはストック、PLはフローを表す」とか言われても、どっちも期末に期中取引をまとめて作成してしまうので、その違いがよく分からないかもしれません。他方で、このやり方だと、PLの数字は増える一方なのに、BSの数字は増えたり減ったりするという違いが分かったり、PLの数字の中でも「利益」だけはBSの数字と同じように増えたり減ったりする、そしてそこがBSとPLがつながってるところだ、とかいったことが分かったりします。
つまり、通常の会計のルールとは違う側面から財務諸表を見ることで、より財務諸表の機能に対する理解が深まるということです。
・
この本では、PLとBSのつながりは、
1 PLの当期純利益とBSの利益剰余金はつながっている。
というふたつのルールで表現されています(先日の話との関連ということで、CSとのつながりは省きます)。
たとえば、事務用品を現金5万円で購入したという例では、
1 PLに事務用品費5万円が計上されるので、当期純利益は-5万円となる。よって、BSの利益剰余金も-5万円となる。
2 BSの右側が5万円減ったので、これとバランスさせるため、左側の現金も5万円減らす。
と表現されることになります。
通常のルールで勉強されている方であれば、2の記述に違和感を感じるかもしれません。というのも、2の記述は、複式簿記のルールである「取引の二面性」が反映されていない記述だからです。簿記のルールにしたがえば、費用の発生と資産の減少は「同時に」起こっているのであって、BSの右側が減ったからこれにあわせて左側も減らそう、という手順を踏む必要はないはずです。
また、BSなりPLの数字を動かすには、あくまで「仕訳」を通さなければならないのが簿記のルールです。ところが2の記述では、BSの右側が減ったから左側もこれにあわせようといっており、なにか仕訳とは別のところで数字を動かそうとしているように読めてしまうわけです(ただし、簿記の世界でも、まさに損益の処理のところで「英米式」とかいって仕訳を通さない処理方法があったりしますが)。
なぜ、この本がこういう記述をしているかといえば、「複式簿記」の知識がなくても読めるように、という読者に対する配慮からです。なので、読者に理解しやすくするため、という意味ではよく分かりますが、読者が「おこづかい帳(単式簿記)思考」のままで、2の記述を額面通りに理解しようとすると、変な誤解をしてしまうのではないかとも思います。
・
ここまで書いてきて、私が何をいいたいのかというと、先日指摘した記述も、「当期純損失が発生したからBSをバランスさせるために資産を減少させよう」と言っているように読めるところが、こういった「おこづかい帳思考」によるものではないかと思ったということです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[及び腰か勇み足な書評] カテゴリの最新記事
-
佐藤英明『スタンダード所得税法』 2009年05月04日
-
大内伸哉『雇用はなぜ壊れたのか-会社の… 2009年05月03日
-
コリンP.A.ジョーンズ『手ごわい頭脳… 2009年05月02日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.