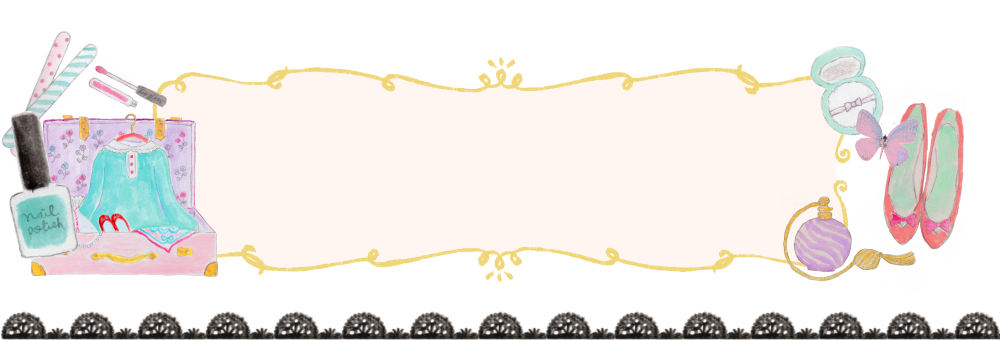2007年02月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

【一億Σヒストリー】通商国家の盛衰(カルタゴ)
<Ginga Opera へ ワープッシュ!~☆>◆ 第十一話 ◆ 旧技術先進国の憂鬱イーゼス国技術者(高級労働)階級は、デジタル・クローン技術でのユピタルク帝国と、マーシェム共和国の圧倒的な進化が追いつき追い越していく現実に、タダ手をこまねいていた。2世紀前までは圧倒的にイーゼスの技術力は他国を圧倒していた。全ての技術先端発表論文が世界中で解読され手本とされていた。学会では先端技術の花盛りで、イーゼス国技術者の講演は常に満員盛況であり、知的財産権でもTOP水準を突き進んでいた。25世紀のいま、学会で他国がイーゼス国技術者の講演を聴講する姿はまれとなった。当たり前すぎる改良技術の延長では、誰も実質的な魅力を感じるはずはなくなったのである。過去ローマ帝国の時代に凋落の通商国家があった。それは、21世紀のJAPANが経済戦争で崩壊する姿に似る。歴史から学ぶことは、同じ轍を踏んではならない事である。同質の闘争や技術で競合したところで結果は誤差でしかない。カルタゴの教訓は、システム改造あるいは進化を嫌った政治体制にこそ敗北の真因があった。カルタゴ現在のチュニジア共和国の首都チュニスに程近い湖であるチュニス湖の東岸にあった北アフリカの古代都市である。今は歴史的な遺跡のある観光地となっている。カルタゴ(Carthage)という言葉は、「新しい町」を意味するフェニキア語のカルト・ハダシュト(Kart-Hadasht)に由来し、カルタゴ語では母音を抜いてQrthdstと綴る。カルタゴの成立カルタゴは、紀元前814年頃、ティルスのフェニキア人移住者によって建設された。町の守り神は、元の町と同じくメルカルトであった。伝承によると、女王ディドが建設したといわれており、町の起源に関する様々な神話が、古代ギリシアやローマの記録に残っている。地中海に面するカルタゴの初期は、農耕を営む者と海で働く者との長い闘争の歴史であった。都市は、主に交易で成り立っていたため、海運の有力者たちが統治権を握っていた。紀元前6世紀の間、カルタゴは西地中海の覇者となりつつあった。商人や探検家たちは、広大な通商路を開拓し、そこを通って富や人が行き来した。紀元前6世紀前半、海洋探検家のハンノは北アフリカ沿岸のシエラレオネにまで辿りついたと推測されている。その後、シエラレオネは、マルカスという指導者のもと、アフリカ内陸と沿岸一帯に領土を拡大した。紀元前5世紀初頭より、カルタゴはこの地域の商業の中心地となり、それはローマによる征服まで続いた。カルタゴは、フェニキア人の古代都市やリビアの諸部族を征服し、現在のモロッコからエジプト国境に至る北アフリカ沿岸を支配下におさめた。地中海においては、サルデーニャ島、マルタ島、バレアレス諸島、シチリア島の西半分を領有し、イベリア半島に植民都市を建設した。第一次シチリア戦争カルタゴの成功の要因は、海賊や他国が恐れる強力な海軍力にあった。カルタゴの進出と覇権の拡大は、地中海中央部で確固たる勢力をもつギリシアとの対立を増大させた。 カルタゴの玄関口にあたるシチリア島が、戦争の舞台となった。ギリシアやフェニキアは、以前よりこの大きな島の重要性を認識しており、海岸線に沿って多くの植民都市や交易拠点を造っていた。 これらの植民者の間で何世紀にも渡って、小競り合いが続いてきたが、紀元前480年、カルタゴが大規模な軍事行動を開始した。事の発端は、ギリシアに支援されたシラクサの僭主ゲロンが、島を統一しようとしたことに始まる。この明白な脅威に対して、カルタゴはアケメネス朝と連携をとりながら、ギリシアとの戦争に踏み切った。ハミルカル将軍のもと、三十万人の軍隊が集められたと言われているが、この数字は大軍を示しているだけで実数ではないと考えられる。 しかし、シチリア島に向かう途中、悪天候に見舞われ、多数の人員を失った。その後、現在のパレルモにあたるパノルムスに上陸したが、ハミルカルは、ヒメラの戦いでゲロンに大敗してしまった。ハミルカルは、戦闘の最中に戦死したか、名誉の自決を遂げたと伝えられている。 カルタゴは、この敗北により大損害を受け弱体化し、国内では貴族政が打倒され共和政に移行した。第二次シチリア戦争共和政による効果的な政策の結果、紀元前410年までには、カルタゴは回復を遂げていた。再び現在のチュニジア一帯を支配し、北アフリカ沿岸に新たな植民都市を建設した。また、サハラ砂漠を横断したマーゴ・バルカの旅行や、アフリカ大陸沿岸を巡る海洋探検家ハンノの旅行を後援している。 しかし、同じ年、金や銀の主要産地であったイベリア半島の植民都市がカルタゴから分離し、その供給が断たれた。 ハミルカルの長男ハンニバル・マーゴは、シチリア島の再領有に向けて準備を始めた。版図を拡大するための遠征は、モロッコからセネガル、大西洋にまで及んでいた。紀元前409年、ハンニバルはシチリア島への遠征を行い、現在のセリヌンテにあたるセリヌスやヒメラといった小都市の占領に成功して帰還した。 しかし、敵対するシラクサはまだ健在であったため、紀元前405年、ハンニバルはシチリア島全域の支配を目指して、二回目の遠征を開始した。 遠征は、頑強な抵抗と不運に見舞われた。アグリジェントの包囲戦の最中、カルタゴ軍に疫病が蔓延し、ハンニバルもそれにより亡くなってしまった。彼の後任として軍を指揮したヒメルコは、ギリシア軍の包囲を打ち破り、ゲラを占領した。さらに、シラクサの新たな王ディオニシウスの軍も破ったが、ヒメルコもまた疫病にかかり、講和を結ばざるを得なくなった。 紀元前398年、力をつけたディオニシウスは、平和協定を破りカルタゴの要塞モーチャを攻撃した。ヒメルコはただちに遠征軍を率いてモーチャを救出し、逆にメッシーナを占領した。紀元前397年には、シラクサの包囲にまで至るが、翌年、再び疫病に見舞われ、ヒメルコの軍は崩壊した。 シチリア島はカルタゴにとっての生命線であり、カルタゴは固執しつづけた。以後60年以上にわたり、この島でカルタゴとギリシアの小競り合いが続くこととなる。 紀元前340年、カルタゴの領土は島の南西の隅に追いやられ、依然として不穏な情勢にあった。第三次シチリア戦争紀元前315年、シラクサ王アガソクレスは、現在のメッシーナにあたるメッセネを包囲した。紀元前311年には、カルタゴ最後の要塞を攻撃し、アクラガスを包囲した。 探検家ハンノの長男ハミルカルは、カルタゴ軍を率いて事態を打開し、好転させた。紀元前310年にはシチリア島のほとんどを占領し、シラクサを包囲した。 死に物狂いになったアガソクレスは、アフリカ本土にあるカルタゴを攻撃させるため、秘密裏に14,000人の兵士を送った。この作戦は成功し、ハミルカルの軍は本土に呼び戻された。紀元前307年、追撃してきたアガソクレスは破れたが、シチリア島に戻り、停戦した。ギリシアのエピロス王ピュロス紀元前280年から紀元前275年にかけて、ギリシア・エピロス(ラテン語ではエピルス。現在のギリシャ共和国のアドリア海側)の王ピュロスは、西地中海におけるギリシアの影響力を維持し、拡大するために2つの大きな戦争を起こした。一つは、マグナ・グラエキアと呼ばれた南イタリアにあるギリシアの植民都市に対するローマの攻撃に対抗するためのものであり、もう一つはシチリア島西部にあるカルタゴの領土を征服しようとするものであった。 しかし、ピュロス王は、イタリア半島とシチリア島の両方で敗北した。カルタゴにとっては以前の状況に戻ったに過ぎなかったが、ローマはタレントゥム(現在のターラント)を占領し、イタリア全域を支配するようになった。 その結果、西地中海における政治勢力に変化が現れ始めた。シチリア島におけるギリシアの拠点は、明らかに減少する一方、ローマの強大化、領土拡大の野望は、カルタゴとの直接対決を導くこととなった。メッシーナの危機紀元前288年、シラクサ王アガソクレスが死去すると、彼の雇っていた傭兵たちはメッシーナの町を乗っ取った。彼らはマメルティニ (Mamertini、マルスの子ら) と名乗り、恐怖政治を敷いた。 この集団は、カルタゴとシラクサにとって脅威となりつつあった。紀元前265年、シラクサ王ヒエロ2世は、カルタゴと共同してマメルティニを攻撃した。 その大軍に直面したマメルティニたちの意見は2つに分かれた。一方は、カルタゴへの降服を主張し、もう一方は、ローマの救援を仰ぐというものであった。結局彼らは、カルタゴとローマの両方に使者を派遣した。 ローマの元老院が取るべき道を議論している間に、カルタゴとシラクサの軍はメッシーナに到着した。完全に包囲されたマメルティニは、カルタゴ軍に降服した。メッシーナにはカルタゴの守備隊が置かれ、港にはカルタゴの艦隊が停泊した。 イタリア半島に程近いメッシーナにカルタゴの軍隊が駐屯したことは、ローマにとって明らかな脅威であった。そのため、消極的ではあったが、メッシーナをマメルティニの手に戻すためにローマはカルタゴと開戦し、軍隊を派遣した。ポエニ戦争ローマ軍が、メッシーナのカルタゴ軍を攻撃したことで、約1世紀にも渡るポエニ戦争が始まった。西ヨーロッパにおけるローマの覇権を確定し、もって西ヨーロッパの命運を決めることになったこの戦いは、3つの大きな戦争からなる。第一次ポエニ戦争 (紀元前264年 - 紀元前241年) 第二次ポエニ戦争 (紀元前218年 - 紀元前202年) 第三次ポエニ戦争 (紀元前149年 - 紀元前146年) ポエニ戦争では、ローマが常にカルタゴに勝利した。第三次ポエニ戦争によって、カルタゴは滅亡し、ローマの政治家・軍人である小スキピオの指示のもと、その都市は完全に破壊された。このカルタゴ陥落の際に小スキピオは自国ローマの未来を重ねたといわれている。 カルタゴが再び復活することがないように、カルタゴ人は虐殺されるか奴隷にされ、港は焼かれ町は破壊された。陥落時にローマが捕虜としたのは五万人にも上ったとされる。カルタゴの土地には雑草一本すら生えることを許さないという意味で塩がまかれたという通説があるが、これは定かではない。
2007.02.25
コメント(0)
-

【一億Σ聖記】 ◆ 第七話 ◆ シンデレラ・コーストでの望郷
Ginga opera ◆ 第七話 ◆ シンデレラ・コーストでの望郷 テラ星シンデレラ・コースト 地域は、反量子銀河連邦帝国で最高のバカンス・リゾート地である。全銀河から、各国の政治家首脳級の要人から、TOPスターや大富豪たちが、数千年前まで栄えた反量子テラ星系の都であるこの惑星の地を、地上での生活を再生させて、本来の人類系が失いかけている惑星大自然の感性を呼び戻せる貴重な楽園である。同時に、多くの反量子銀河系での秩序法律や経済界での本質的な決め事の裏舞台としてのリゾートLANDでもある。とりわけ夜の12時(反テラ星時間)での衛星を回る月を眺める風景は、格別のノスタルジーを人類のDNA合成で高度化した頭脳にも「愛情」という過去の動物的なインスピレーションを、髣髴とさせてくれる効果は、反量子銀河の人類系たちにとってはこの上ない喜びである。 (過去に愛したひと達のデータベースによる、NETインスピレーション交信に最適な場所である) 多くの「愛と喜び」の逸話が残され、NET物語として幼いDNAクローン人類子孫達に語り継がれている場所でもあり、全反量子銀河系における人類系の永遠の憧れであり、果たせしたい夢、訪れたい憧れの時空間地域でもある。奇しくも、彼も久方ぶりに行き詰った政権運営での傷を癒しに、僅かばかりの時間をリラクゼーションのために専用光速スピーダーで訪れていた。そう、ここは彼の一族が数千年前までは実際に、幸せにごく平凡な生活していた地なのである。多くの科学進歩と競争と戦闘と駆け引きが終わり、再び再生された都の名残を残すリゾートとして生まれ変わった所だ。 イーゼス国首相の鯉が淵氏は、8年前の当選選挙公約であったNET キャッシュレス インベステイメント銀行の完全個人化法案を否決され背水の陣で、巻きなおし選挙へ打って出ていた。ユピタルク国のここ1世紀に近いクローン製造技術力による イーゼス国の産業空洞化で生き残った企業収入も減少の一途である。これまで国政で支えてきた財源問題もついに「個人化」と命名した実質的な外国金融企業への身売りによって、重税を回避しながら国民不満を他国へ誘導し 政策的な限界を包み隠す戦法で、延命策を講じてきた。既に1世紀前までは世界的な製造技術水準と規模で他国を圧倒してきた先技術も、今は過去の栄光となってしまい。技術研究資源での優位性でかろうじて国家の製造水準を維持している状態にまでなっている。大半の企業は ユピタルク国や近隣の帝国企業へ買収され、イーゼス国企業の中でNET社員を雇用できている人員数は、国民のNET就労人口の1/3程度 となってきている。国家そのものの存在意義が問われているのである。 それでも、NETキャッシュレス インベステイメント銀行を手放してでも守ろうとするものは、圧倒的な資産階級である鯉が淵氏の関連企業や政治家集団の国際利益である。 帝政をしく他の貿易大国への従属は、そのまま資産没収への道となる。 NET帝政国家と成りたくない「自由国家」であり続けたいイーゼス国国民の圧倒的な支持で首相となって8年間、「NET産業改革」と称する経済政策を元老院で可決成立させ続けてきたが、重税を嫌がる国民に法的には強制力を行使できない外国銀行資本へのNETキャッシュレス インベステイメント銀行開放により、外貨を直接導入しかつNET取引での海外資本取り込みを狙った戦略を進めてきた。諸外国とは別の手法でのNET銀行帝国化を目論でいたが、法案可決直前で裏の仕組みが国民へ知れることとなり、廃案へと急転直下の事態となり、所属政党そのものの不信任問題となっている。元老院の解散再選挙を首相として宣言し、過半数を自分の政治家で固めて一気に帝政化へ突き進む勝負に出てきた。対抗野党派閥のNET情報企業集団グループは、政治家スキャンダル攻勢で阻止し逆にNET銀行集団の従属化を狙っている。 ***<DATA>****************************************スタースピーダー3000 StarSpeeder 3000機種名:スタースピーダー3000 製造元:スター・ツアーズ社 級種:乗客輸送艇 分類:宇宙戦闘機 大きさ:全長12.19メートル、全幅4.88メートル、全高4.27メートル 速度:不明 操縦要員:RXドロイド 1体、アストロメク・ドロイド 1体 乗員定員:40名 搭載機:なし 積載重量:不明 航続期間:不明 価格:不明 動力機構:不明 推進機構:ハイパードライブ 航行装備:航法コンピュータ、シールド、各種センサー 武装:ライト・ブラスター・キャノン 2基 機体材質:不明 スタースピーダー3000の導入は、スター・ツアーズ社の誇りだった。同社はこの小型宇宙スピーダーを現存する最高の輸送艇であると宣伝しており、その事実は高速ハイパードライブと10億光年を超える航行記録、そして3,000回にもおよぶ無事故で快適な銀河系旅行によって裏づけされている。同社の主張によれば、スタースピーダー3000は最高の信頼性を誇る最新式RXドロイドによって操縦され、くつろぎの空間に座ったまま、旅を楽しむことができるというのだ。スタースピーダー3000は旧型機種だが、年式以上の価値を証明している。この宇宙船は銀河共和国の衰退期から絶え間なく使用され続けており、銀河系全域の宇宙港やドッキング施設でその姿を見ることができる。スタースピーダー3000はRXドロイドによって操縦され、ナビゲーションはR2アストロメク・ドロイドが担当している。そのため、スター・ツアーズ社は乗員用の生命維持システムを最小限に抑えることができ、船に搭載されたすべての資源を乗客用モジュールに集中させることで、全体スペースを減少させることに成功したのだった。小さな船はそれだけ効率が高くなり、スター・ツアーズ社にとってもコストの低減というメリットが得られるのだ。しかし、この船は快適とは言いがたいのも事実である。偏向シールドは可能な限り最低限の仕様に抑えてあり、宇宙船製造時における安全基準を辛うじて満たしているだけなのだ。また、スタースピーダー3000は1対のライト・ブラスター・キャノンを装備しているが、これらは宇宙を漂うゴミを撃つために設計されたものである。内部もそれほど良くはなく、前面を向いたビュー・ポートと、40人の乗客が共有する小型ディスプレイが1つずつ付いているだけの簡素な乗客室となっている。スター・ツアーズ社を選択することは確かに経済的ではあるが、決して豪華な旅は望まないほうがいいだろう。石油の戦争とパレスチナの闇 著者: ジョン・コールマン /太田竜 本書は「石油」という高価な宝を狙う国イギリスが、アメリカという共犯者の賛助を得て、胸の悪くなるような悪行と虚偽の限りを尽くした、イラクに対するあからさまな侵略の歴史である。 1章 なぜイラクを侵略するのか、それは石油が存在するからだ(イラクの「黒い宝」をめぐる醜悪な暗闘の歴史/アメリカ国民を強烈に洗脳する「キリスト教原理主義者」 ほか)/2章 日本民族が知らされないパレスチナ、その怨嗟の歴史(「岩のドーム訪問」に秘められたシャロンの意図/パレスチナが「ユダヤの故国」だという大欺瞞 ほか)/3章 全面戦争へのファイナル・カウントダウン、パレスチナ緊急報告(一方的な「イスラエル独立宣言」がもたらした災禍/少数派が占拠する「いびつな国家」の誕生 ほか)/4章 黒い貴族は少数エリートの暗黒支配社会を目指す(現代でも活溌に蠢いている「ブラック・ノビリティ」/「十字軍によるベネチア興隆」が黒い貴族の基盤となった ほか)/5章 はたしてユダヤとは何か、ユダヤ人とは誰か(キリスト教原理主義者が利用する「洗脳済みのアメリカ国民」/巧妙に隠蔽された「人口構成比」という根本問題 ほか) コールマン,ジョン(Coleman,John)1935年、英国生まれ。元・英国諜報機関将校。英王室と諜報機関が「300人委員会」を中核とする闇の世界権力の忠実な道具であり、英国国民のみならず、全世界人類と諸民族国家の敵である事実を秘密文書によって知り、英国諜報部を脱出、1969年にアメリカに移住、帰化。以後30余年にわたって300人委員会等の秘密謀略機関の活動を徹底して暴露、警告を続けている ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare、沙翁(沙吉比亜からの異称)、洗礼日1564年4月26日 - 1616年4月23日)イギリス(イングランド)の劇作家、詩人。ストラットフォード・アポン・エイヴォンの生れ。エリザベス朝の代表的な作家で、最も優れた英文学の作家とも言われている。その卓越した人間観察眼と内面の心理描写は、後の哲学や、19~20世紀の心理学・精神分析学を先取りした物ともなっている。1585年前後にロンドンに出たといわれ、1592年には新進の劇作家として活躍。四大悲劇『ハムレット』『マクベス』『オセロ』『リア王』をはじめ、『ロミオとジュリエット』『ヴェニスの商人』『夏の夜の夢』『ジュリアス・シーザー』など、傑作を残した。物語詩『ヴィーナスとアドーニス』『十四行詩』なども重要な作品。
2007.02.24
コメント(0)
-

【一億Σ聖記】 ●第一章● ◆第二節◆ MOON LIGHT SHADOW
●第一章● ◆第二節◆ MOON LIGHT SHADOW太陽系惑星 地球はその脇に月を従えた水惑星である。そう、人類系がその生存の基本特性を形成し得た重要な銀河系の母なる土地と歴史の原点である。 人類系のDNAの90%以上は他の地球上の生命と同等である。進化としては大きな差異は少ない。残りの10%こそ人類系がこの水惑星で特別な知性を基に君臨できるようになった根源的な理由である。 特に、人類系の女性種では満月の時、すなはち太陽からの直接光線が地球の背面から照射される最大の照度となるとき、夜の地球側からは、その追従小天体の表面は「満月」と言われる光と引力によって、地球上の生命体に原始的で重大な生殖上の影響を過去与え続けてきたのだ。 この月の明かり「MOON LIGHT」を感じる時、人類には多くの歴史的な事件が刷り込まれてきた。 そう地球自身の重力だけでなかった事が、人類系の生命活動を一層周期的に確実に成長進化させる原動力となっていた。それは、水惑星に棲む生命体の体内の水成分比率が66%以上あることが、結果としてこの月の引力により扇動されることで、女性種が子孫の誕生を自然にプログラムされ、DNA再結合の機会を与える事で確実な遺伝子配列合成の進化が、遠い過去に埋め込まれたシナリオに従って数万年かかって、あるべき時を刻むようにその周期が計算されていた。 遠く過去にそのDNAプログラムを埋め込んだ「イブ」の子孫達は、25世紀に遂にその目的の銀河系惑星世界で、求められた進化を達成しつつあるのだった。 そして、同時代に起こる知性生命の運命との出会いに確実に同期し始めていた。既にこの月は周囲に無い太陽系惑星間に人工的な衛星を作り上げて移住している人類系の多くは、正常なDNA再生維持のために、個々の人工惑星の周囲に「MOONLIGHT SHADOW(擬似推進引力)」重力装置を置いて、同一の人体周期を司る事を学んでいた。 月は、太陽系の惑星やほとんどの衛星と同じく、天の北極から見て反時計周りの方向に公転している。軌道は円に近い楕円形。軌道半径は38万4400kmで、地球の赤道半径の約60.27倍である。 月の秤動(ひょうどう)月は地球に対して27日周期で少しずつ違った面を見せている。この月の見かけ上の揺れのことを月の秤動(ひょうどう)という。これにより月面の59%が地上から観測可能である。この画像は27日分の月の映像を、時間を縮めて並べたもの。大きくなったり小さくなったりしているのは、月が地球の周りを公転するさいに地球との距離が近くなったり遠くなったりしているため。月の自転周期は27.32日で地球の周りを回る公転周期と完全に同期している。つまり地表からは月の裏側は永久に観測できない。これはそれほど珍しい現象ではなく、火星の2衛星、木星のガリレオ衛星であるイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト、土星の最大の衛星タイタンなどにもあてはまる現象である。ただし、一致してはいても月の自転軸が傾いていることと軌道離心率が0でないことから、月面の59%は地上から観測可能である。月の重力は地球に影響を及ぼし、太陽とともに潮の満ち引きを起こしている(潮汐作用)。地球上の生物のホルモンリズムにも影響を及ぼしていると俗説では言われることもある(いわゆるバイオリズム)が、月によって人間に加わる重力は、蚊一匹分と非常に小さいものにしかならないため、科学者の中では否定的な意見のほうが圧倒的である。月の潮汐作用により、主に海洋と海底との摩擦(海水同士、地殻同士の摩擦などもある)による熱損失から、地球の自転速度がおよそ10万年に1秒の割合で遅くなっている。また、重力による地殻の変形によって、地球-月系の角運動量は月に移動しており、これにより月と地球の距離は、年約3.8センチメートルずつ離れつつある。この角運動量の移動は、地球の自転周期と月の公転周期が一致したところで安定となるため、地球-月間の距離はそこで安定すると考えられている。約50億年後には地球と月は常に同じ面を向けることが予測されている。月はほとんど大気を持たず、表面は真空であると言える。そのため、気象現象が発生しない。このことは月面着陸以前の望遠鏡の観測からも推定されていた。また地質学的にも死んでおり、マントル対流が存在せず火山も確認されていない。水(熱水)の存在も確認されていないため、鉱石は存在しないと推定されている。地球のような液体の金属核は存在しないと考えられており、磁場は地球の約10000の1ときわめて微弱である。<ムーンライト>第13回 ジュエリーベストドレッサー賞20代部門受賞米倉涼子さんプレゼント商品クロスフォーブランドより「MOON LIGHT」という名にふさわしい女性らしいジュエリー4×4ミリ・クロスフォーカットのキュービックジルコニアを6ピース、背中合わせにぎゅっと集め、40センチ・ボールチェーンを合わせました。世界16ヶ国で特許を持つクロスフォーカットにより宝石の中に十字の輝きを持つ最高級のジュエル。可愛らしいフォルムから360度、全ての方向へ向けてその美しい輝きを放ちます。その輝きは、まさに月明かりのように優しく、サイコロみたいにキュート★コロンと可愛い上質のキラメキは乙女の表情を合わせ持つ、大人の女性の優雅な雰囲気。凝ったデザインでも全体の仕上がりがシンプルだから合わせるスタイルを選びません。貴方の胸元にも、ロマンチックな月明かり♪a Cross for you・・・・愛を貴方のために★ Serenata おやすみリラクシン アーティスト: res. ほか 作曲: ホメロ・ルバンボ ほか 寝苦しい夜もこの1枚があれば大丈夫? リスナーをスムーズに眠りの世界へと誘ってくれるヒーリング・コンピレーション。ジャズからワールド・ミュージックまで、収録ジャンルは多彩。 アーティスト:res./レン{ブグジー}・シャープ/トム・キーン/nanan/ホメロ・ルバンボ/トーマス・ハーディン・トリオ/吉川忠英/オータサン/アール・ブルックス/つのだたかし/重実徹作曲:ホメロ・ルバンボ/オータサン/つのだたかし/グスタフ・マーラー曲目タイトル:1. 波(自然音) 2. ルス 3. レイトリー 4. サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー 5. 波(自然音) 6. モナ・リザ 7. ルイーザ 8. 月の光 9. 波(自然音) 10. ムーンライト・セレナーデ 11. ハワイ 12. ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ 13. 波(自然音) 14. ケ カリ ネイ アウ 15. 雨の匂い 16. 亡き王女のためのパヴァーヌ 17. 波(自然音) 18. 青い影 19. グリーンスリーブス 20. 交響曲第5番第4楽章~アダージェット 21. 波(自然音)
2007.02.23
コメント(1)
-

【一億Σ聖記】 ◆ 第三十話 ◆ 太陽系は女王陛下のもの
【一億Σ聖記】 ◆ 第三十話 ◆ 太陽系は女王陛下のもの 18世紀我らの母なる地球をかつて大英帝国が制覇していた頃、世界は女王陛下に傅いたとか...。25世紀の現在、この太陽系内銀河惑星系は、明らかに女性種の支配が完成した世界であろう。実際に多くの問題も抱えてはいるが、母星から飛び出した人類系種族が、最も合理的に人口を制御できうる確率を求めるとき、両性バランスがふさわしいとは言いがたい。実際に最近の研究では、明らかに地球には数万年前に、哺乳類系を超えた知性を持ったDNA移植か生成技術による人工的な細胞操作をしたであろう脳細胞の一部が、人類系に備わっていることが分かって来ている。そうなのだ、我々の祖先というよりも細胞DNA構造配列の一部は、アフリカ猿人に近い段階で書き込まれているという事だ。なぜ、そうなったいるのか、一体この銀河のどこからその技術を持った生命体異性人?は地球へ来て、人類系の基礎的な仕組みを施したのか? 人類系が自らDNAをデジタルDNA解析技術とDNAのデジタル変換生成技術を手に入れたことで、本当の不自然な痕跡を自ら理解できるようになってきたのだ。 おそらく過去の地球へ長い旅をして到着した科学者?来訪者は、女性であっただろう。アダムとイブの聖書のくだりは神話であろうが、DNAをプレゼントした「神?」は、70%以上女性であろう。 23番目のXY染色体(男性)は、23番目XX染色体(女性)の分裂時点で、DNAデジタル変換をしたものなのだ。 その後、再度の変換はなされていない様である。それ以降は忠実にタンパク質生成をするRNAポリメラーゼの自動製造工程が脈々と受け継がれてきたのだろう。こうした事実は人類系の歴史は多くの変遷を経るうちに、キリスト教の影響もあり「男性優位の社会」構造や思想へ変えられた。それは、地球上では生存が制限的ではなく安定であったからである。一度大気圏外へ飛び出せば、生存確率の0.1%の差でも重要な問題である。究極の状態でも子孫を受け継げる摂理を選択するしかないからだ。いま再び人類系は惑星系国家へと拡大展開されてしまい、この法則が確実に働いている。まさに事実そうだが、太陽系は地球と火星の惑星空間に浮かぶ人工地球衛星島「ソフィアース」の女王が太陽系元老院議長を務めている訳であるから、「女王陛下のもの」とも言える訳だ。 女王陛下は、人工地球衛星島で栽培される紅茶が大好物とか。 なるほど、何世紀経っても、宇宙時代になっても女性は普遍らしい。%%%%%%%%%%%%%%% <話題の映画> %%%%%%%%%%%%%%%マリー・アントワネット・ドートリッシュ(Marie Antoinette d'Autriche, 1755年11月2日 - 1793年10月16日)は、フランス国王ルイ16世の王妃。フランス革命が掲げた自由・平等・博愛の近代民主主義の諸原理は、今日では日本を含む世界中の多くの国家が取り入れるに至っている。他にも民法、メートル法など、フランス革命が生み出した制度や思想は、世界史上に多大な影響を残している。本人のささやかな希望とは裏腹に、皮肉にも世界に素晴らしい文明思想を普及させてしまった、人類の大恩人となった女性なのである。オーストリア・ハプスブルク家のマリア・テレジアとその夫、神聖ローマ皇帝フランツ1世の間の娘(第9子)。結婚前のドイツ語名はマリア・アントーニア・ヨーゼファ・ヨアンナ・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲン(Maria Antonia Josefa Joanna von Habsburg-Lothringen)。フランス革命の混乱の中で革命政府から死刑判決を受け、ギロチンで斬首刑にされた。18世紀のヨーロッパ各国では、啓蒙思想が広まって新しい社会の息吹が聞こえていた。責任内閣制を成立させ産業革命が起こりつつあったイギリス、自由平等を掲げ独立を達成したアメリカ合衆国は、他国に先駆けて近代国家への道を歩んでいた。プロイセンやロシアでも、絶対君主制の枠を超えるものではなかったものの、政治に啓蒙思想を実践しようとした啓蒙専制君主が現れた。しかしフランスでは18世紀後半に至っても、ブルボン朝による絶対君主制の支配(アンシャン・レジーム)が続いていた。アンシャン・レジーム下では、国民は三つの身分に分けられており、第一身分である聖職者が14万人、第二身分である貴族が40万人、第三身分である平民が2600万人いた。第一身分と第二身分には年金支給と免税特権が認められていた。一方でアンシャン・レジームに対する批判も、ヴォルテールやルソーといった啓蒙思想家を中心に高まっていた。自由と平等を謳ったアメリカ独立宣言もアンシャン・レジーム批判に大きな影響を与えた。 【Aポイント付】マリー・アントワネット Soundtrack / Marie Antoinette (輸入盤CD) 収録曲:(マリーアントワネット)Disc-1:1. Hong Kong Garden / Siouxsie And The Banshees - 3:102. Aphrodisiac / Bow Wow Wow - 2:573. What Ever Happened / Strokes - 2:484. Pulling Our Weight / Radio Dept. - 3:215. Ceremony / New Order - 4:226. Natural's Not in It / Gang Of Four - 3:067. I Want Candy [Kevin Shields Remix] / Bow Wow Wow - 2:398. Kings of the Wind Frontier / Adam Ant - 3:569. Concerto in G - 2:3110. The Melody of a Fallen Tree / Windsor For The Derby - 8:1611. I Don't Like It Like This / Radio Dept. - 4:0812. Plainsong / Cure - 5:08Disc-2:1. Intro Versailles - 0:372. Jynweythek Ylow / Aphex Twin - 2:353. Opus 17 / Dustin O'Halloran - 2:034. Il Secondo Giorno [Instrumental] / Air - 4:575. Keen on Boys / Radio Dept. - 4:496. Opus 23 / Dustin O'Halloran - 3:087. Les Barricades Mysterious / Francois Cauperin - 2:358. Fools Rush In [Kevin Shields Remix] / Bow Wow Wow - 2:199. Avril 14th / Aphex Twin - 1:5810. K. 213 / Domenico Scarlatti - 4:2211. Tommib Help Buss / Squarepusher - 2:1012. Tristes Appretes, Pales Flambeaux {From Castor et Pollux} / Jean-Philippe Rameau & Arts Florissant - 5:5413. Opus 36 / Dustin O'Halloran - 1:4514. All Cats Are Grey / Cure - 5:23
2007.02.18
コメント(4)
-

【一億Σ聖記】 ◆ 第十五話 ◆ DNAクローン細胞量子回路技術の遺物
◆ 第十五話 ◆ DNAクローン細胞量子回路技術の遺物 イーゼス国の古き地球の都、T&KY+では一人の天才が今後デジタル・クローン技術を応用した量子電子回路の基礎となる電気回路方式を特許化した。それは、かつて「液晶」という25世紀では既に無い映像装置表示装置の描画回路方式をDNA細胞伝送へ応用したものだった。 彼は、それまでのデジタルといえば「0と1」という2値符号化された電圧伝送方式を時間の多少という符号信号時間幅で表現する方式を、微小な電荷電流を一定のスピン電圧で安定的に流す事で、均質で品質の良い映像をDNA頭脳の中に映し出す原理を発明した。その当時はごく平凡な特許と思われていたが、実はこの原理こそすべてのデジタルDNA素子だけでなく、それをクローン技術で合成して、DNAクローン細胞CPU-NET駆動原理そのものへ発展するのである。 25世紀の現代では、この基本的な原理はより量子CPUなどを含めて、常識的な利用の世界で満ち溢れているが、超伝導とかが注目されている中では、あまりに控えめに見えたスタートであった。 イーゼス国の技術院の正門玄関には彼の銅像が飾られて居る。 ごくありふれた大げさな風景であるが、全銀河衛星諸国家は感謝して余りある貢献をしているのだった。特に、イーゼス国ではこの後さらに、覇権復帰への足がかりとして、この技術の深みに実に感動させられずにはおかないからである。先祖の功績を数世紀後にして、本質から理解することとなっていく。(OPERA 参考資料 21世紀初頭のDNA応用技術レベル)■分子エレクトロニクス - 単一分子素子とは? 1974年にIBMのアビラム(A.Aviram)やラトナー(M.A.Ratner)が理論的に可能であることを示した分子ダイオード(整流素子)は電子回路の非常に基礎的なパーツである。「電子」一つ一つを一方向にしか移動させない。この分子ダイオードはA(アクセプター、緑)とD(ドナー、青)が、1(絶縁体、赤)によってつながれた非対称な構造をしている。AとDはπ電子共役系になっており、非局在化した電子は比較的自由に移動することが出来る。Aは還元されやすく、Dは酸化されやすいという性質を持っている。つまり電子輸送から考えれば、Aは電子を受け取りやすく、Dは電子を提供しやすいというわけだ。 まず電極1をマイナスに、電極2をプラスにした場合(1)、電極1から還元されやすいAへ電子が渡され、酸化されやすいDは電極2から電子を引きぬかれる(2)。するとAはマイナスに帯電し、Dはプラスに帯電する(3)。これでは分子の内部で電子が偏って存在してしまうことになるので、Aの過剰な電子がDへ受け渡されて、元の安定な状態に戻る(4)。(1)から(2)のステップを通してみると、電極1から電極2へ電子が一つ移動したことになる。これと逆に、電極1をプラスにして電極2をマイナスにした場合はどうか。電極1はAから電子を引きぬき、電極2はDに電子を与える。これでは、Aが酸化されDが還元されたことになり、分子は非常に不安定になってしまう。このような状態は取りにくいため、逆方向に電圧をかけても電子輸送は起こらない。●電場によってひねりを加える 分子スイッチ その1 下図のように、3つのベンゼン環がメチルでつながれ、そのひとつにニトロ基(NO2)とアミノ基(NH2)が付いた分子がある。この分子はスイッチング素子として機能。 ベンゼン上では環にそって比較的自由に動ける電子が分布している。この電子は「π電子」と呼ばれ、複数のベンゼン環にまたがって移動することができる。つまりこの分子は電気を通す。それぞれプラス、マイナスの性質を持っているため、この電圧を加えて電界が生じると図のように分子がねじれた構造になる。こうすると分子全体のπ共役性が失われ、分子は電流を通さなくなる。外部からの印加によって分子にひねりを加えることで、スイッチのオンオフを行っている。これによってこの分子はスイッチング素子として機能する。●シャトルを移動 分子スイッチ その2 記憶素子としての条件を満たすためには、0と1というデジタル情報を保持するために安定な状態が二つ(以上)あり、しかもその状態の間を比較的容易に行き来できる必要がある。 上図のようにバーベルの軸にリングが挟まったような分子を総称して「ロタキサン」と呼んでいる。この分子はリングが二つの安定な位置に行ったり来たりすることで分子の軸方向の導電性が変化する。したがって二つの準安定状態を0と1に対応させ、導電性を検出すれば、1bitの記憶素子として利用することができる。●金属にも半導体にも 分子ワイヤ 電子回路を実現するために、複数の素子を繋いでやるワイヤ(配線)が必要となる。この分子ワイヤ素材が「カーボンナノチューブ(CNT)」であるカーボンナノチューブをチャンネルに利用したCNT FET(Carbon NanoTube field Effect Transistor)。実際は、CNTの直径が数nmであるのに対し、ソースやドレインの幅は数十nm~100nm程度なので、この図よりも大小差が顕著になっている。FETの動作原理については「トランジスタ」のページを参照。 まず、文字通りCNTのワイヤ幅は数m程度で、現在(そして将来)の半導体微細加工技術がとても及ばない領域にある。この太さゆえにCNTは典型的な量子細線と見なせ、直径やカイラリティーをかえることで半導体や金属といった導電性が変化することが分かっている。ということは、直径やカイラリティーの違うCNTどうしをくっつけてやれば、ダイオードなどを作ることも可能だ。また、CNTをチャンネルに使った電界効果トランジスタも盛んに研究されている。極端な話、すべて炭素原子の分子素子というのも可能なのだ。分子ナノテクノロジー 著者: 松重和美 /田中一義 出版社: 化学同人 サイズ: 単行本 ページ数: 232p 発行年月: 2002年06月 【内容情報】(「BOOK」データベースより)本書は分子ナノテクノロジーの進展と現状を紹介するために、先端的な研究者の参画を得て編まれた入門的な解説書である。 【目次】(「BOOK」データベースより)1部 分子ナノテクノロジーのためのツール開発(SPMによるナノスケール分子制御/バイオミメティック手法によるナノ構造作製技術/DNAのナノカッティング ほか)/2部 分子ナノデバイス開発(分子ワイヤとしてのオリゴチオフェンの設計と合成/分子性ナノワイヤの構築/ナノ連結系によるエネルギー・電子移動デバイス ほか)/3部 分子ナノ素子を用いる回路開発(量子コンピュータの原理/NMRを用いる量子コンピュータのアーキテクチャ/分子コンピュータの構築 ほか) DNAコンピューティング 著者: ゲオルゲ・パウン /グシェゴシュ・ローゼンバーグ 出版社: シュプリンガー・フェアラーク東京 サイズ: 単行本 ページ数: 444p 発行年月: 1999年12月 【内容情報】(「BOOK」データベースより)ポスト・ノイマン型コンピュータの有力候補DNAコンピュータ。それは、4種類のDNA塩基を演算素子にした超並列コンピュータである。たとえば原理的には、1gのDNAの中に3兆枚のCDと同量の情報を格納できる。またDNAコンピュータの演算速度は、スーパーコンピュータの100万倍、エネルギー効率は10億倍と試算されている…。シリコンからカーボンへ、マイクロチップからDNAへ!いま、全く新しい発想に基づく計置メカニズムの探究が始まった!本書は、DNAコンピュータに関する、日本語で初めてのガイドブックである。 【目次】(「BOOK」データベースより)第1部 背景と動機(DNA:その構造と働き/分子計算のあけぼの)/第2部 数学的理論(形式言語理論入門/スティッカーシステム/ワトソン・クリックオートマトン/挿入・削除システム ほか)
2007.02.17
コメント(2)
-

【一億Σヒストリー】銀河太陽系の法則 発見者たち
【一億ΣGinga】銀河太陽系の旧定義 発見者たちガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei, ユリウス暦1564年2月15日 - グレゴリオ暦1642年1月8日)はイタリアの物理学者、天文学者、哲学者である。 パドヴァ大学教授。その業績から天文学の父と称され、フランシス・ベーコンと共に科学的手法の開拓者としても知られている。 天文学ガリレオは望遠鏡を最も早くから取り入れた一人である。オランダで1608年に望遠鏡が発明されると、すぐに10倍の望遠鏡を入手し、さらに20倍のものに作り変えた。これを用いて1610年1月7日、木星の衛星を3つ発見。その後見つけたもう1つの衛星とあわせ、これらの衛星はガリレオ衛星と呼ばれている。これらの観測結果は、1610年3月に、『星界の報告』(Sidereus Nuncius)として論文発表された。(この論文には、3月までの観測結果が掲載されているため、論文発表は4月以降と考えられたこともあるが、少なくとも、ドイツのヨハネス・ケプラーが4月1日にこの論文を読んだことが分かっている)この木星の衛星の発見は、当時信じられていた天動説については不利なものであった。金星の観測では、金星が満ち欠けする上に、大きさを変えることも発見した。当時信じられていた天動説に従うならば、金星はある程度満ち欠けをすることはあっても、三日月のように細くはならず、また、地球からの距離は一定のため、大きさは決して変化しないはずであった。さらに、望遠鏡での観測で太陽黒点を観測した最初の西洋人となった。ただし、中国の天文学者がこれより先に太陽黒点を観測していた可能性もある。形や位置を変える黒点は、天は不変で、月より遠い場所では永遠に変化は訪れないとする天動説には不利な証拠になった。これは、アリストテレス派の研究者と激しい議論となった。なお、ガリレオは晩年に失明しているが、これは望遠鏡で太陽を直接見たためだと考えられている。(ただし、1610年代には既に望遠鏡の接眼レンズの先にスクリーンを置く手法は開発されていた。この方法を発明したのはガリレオではないが、他の観測者があまり知らなかったこの方法を用いることによって、ガリレオはより詳しく太陽黒点を観測することができた)ガリレオは1597年にケプラーに宛てた手紙の中で既に地動説を信じていると記しているが、17世紀初頭までは公にそれを公言することはなかった。主にこれら3点(木星の衛星、金星の満ち欠け、太陽黒点)の証拠から、地動説が正しいと確信したガリレオは、この後、地動説に言及することが多くなった。ヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler、1571年12月27日 - 1630年11月15日)は、ドイツの数学者、自然哲学者。天体の運行法則に関する研究でよく知られている。理論的に天体の運動を解明したという点において、彼は天文学者というよりも天体物理学者であると言う方がふさわしい。サー・アイザック・ニュートン(Sir Isaac Newton, ユリウス暦:1642年12月25日 - 1727年3月20日、グレゴリオ暦:1643年1月4日 - 1727年3月31日)は、イングランドのウールスソープ生まれ。イギリスの錬金術師・自然哲学者(物理学・天文学)・数学者。近代の大科学者の一人と評されている。主著"Philosophiae Naturalis Principia Mathematica"「自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)」(1687年7月5日刊)のなかで万有引力の法則と、運動方程式について述べ、古典数学を完成させ、古典力学(ニュートン力学)を創始。これによって天体の運動を解明した。またゴットフリート・ライプニッツとは独立に微積分法(流率法)を発明した。光学において光のスペクトル分析などの業績も残した。ニュートン式反射望遠鏡の製作でも有名である。(なお、反射望遠鏡の発明者だとする伝記は誤り。)ニュートンは、地球と天体の運動を初めて実験的に示し、太陽系の構造について言及した。また、ケプラーの惑星運動法則を力学的に解明した一人であり、天体の軌道が楕円、双曲線、放物線に分かれることを示した。また、光の粒子説を唱えたことでも知られている。また、白色光がプリズム混合色であるとして色とスペクトルの関係について唱えた。虹の色数を7色だとしたのも彼である。アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein、1879年3月14日 - 1955年4月18日)は、ドイツ出身の理論物理学者。相対性理論をはじめとする多くの業績のほか、特異な風貌とユーモアあふれる言動によって、専門分野を超え世界中に広くその存在が認知されており、しばしば天才の例としてひきあいに出される。光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明によって1921年のノーベル物理学賞を受賞。従弟に音楽学者でモーツァルト研究者のアルフレート・アインシュタインがいる。20世紀最大の理論物理学者である。1905年に特殊相対性理論を発表。ニュートン力学とマクスウェルの方程式を基礎とする物理学の体系を根本から再構成した。特殊相対性理論では、質量、長さ、同時性といった概念は、観測者のいる慣性系によって異なる相対的なものであり、唯一不変なものは光速度cのみであるとした。一般相対性理論の解として、宇宙は膨張または収縮をしているという結論が得られる。アインシュタインは重力による影響を相殺するような宇宙項Λを場の方程式に導入することで、静的な宇宙が得られるようにした。しかし、エドウィン・ハッブルによって、宇宙の膨張が発見されたため、アインシュタインは宇宙項を撤回した。後に宇宙項の導入を「生涯最大の失敗」と述べている。しかし、宇宙望遠鏡による超新星の赤方偏移の観測結果などから、宇宙の膨張が加速しているという結論が得られており、この加速の要因として、宇宙項の存在が再び注目されている。エネルギー(E) = 質量(m)×光速度(c)の2乗この公式で、質量1キログラムをエネルギー変換すると次のようになる。89,875,517,873,681,764 J(ジュール)と等価 24,965,421,632 kWh(キロワット時)と等価 21.48076431 Mt(メガトン)のTNTの熱量と等価 特殊相対性理論の誕生20世紀初頭の物理学では、力学の理論的な帰結であるニュートン力学と、電磁気学の理論的な帰結であるマクスウェルの方程式が矛盾することが理論面での大きな問題となっていた。ニュートン力学によると、一定速度 V で動いている電車を座標系 R とし、地上を座標系 S とすると、電車の中で静止しているボールは、電車の中からみたボールの速度 VR は 0、地上からみたボールの速度 VSは V で運動しているように見える。すなわち、VS = VR + V の関係が成り立つ。この関係をガリレイ変換とよぶ。電車の中の座標系 Rでも、地上の座標系 Sでも、同じ力学の法則が成り立つことから、「ニュートン力学から導かれる力学の法則はガリレイ変換に対して不変である」(ガリレイ不変)ことが知られていた。これに対し、マクスウェルの方程式では真空中の電磁波(光)の速度が、座標系の採り方によらずに一定であることが示されていた。上記のボールの代わりに電磁波(光)を使うとすると、マクスウェルの方程式からは、電車の中からみた光の速度 VR と、地上から見た光の速度 VS は等しい、つまり、VS = VR でなければならない。これをもとにヘンドリック・ローレンツ (Hendrik Lorentz) は1900年に「マクスウェルの方程式から導かれる電磁気学の法則はローレンツ変換に対して不変である」(ローレンツ不変)ことを発見した。力学の法則はガリレイ不変であるが、電磁気学の法則はローレンツ不変であるという矛盾に対し、数学者のアンリ・ポアンカレはローレンツ変換に対して不変とした力学の法則を提示した。この力学では、光速に近い速度では物体の長さが減少するという「ローレンツ収縮」が導入されているなど、後の特殊相対性理論の萌芽的なものであったが、統一的な理論を創りあげるまでには至らなかった。このような背景のもと、アインシュタインは、次の二つの仮定(公理)のみをもとに思考実験によって新しい理論を考え出した。力学法則はどの慣性系においても同じ形で成立する(相対性原理)。 真空中の光の速さは光源の運動状態に無関係に一定である(光速不変の原理)。 この仮定を満たすために、それまで暗黙のうちに一様で変化しないとみなされていた空間と時間が変化するという結論が導かれた。「光の速度に近い、加速していないロケットから、光の速度が c に見えるようにするためには、どうすればよいか。」 アインシュタインの答えは、「ロケットの時間が地上と同じように進むとすると、ロケットからは光の速度がのろく見えてしまい、不自然である。ロケットの中の時間の進み方が遅くなるとすれば、ロケットの中から見ても光速度(即ち"距離÷時間")は変わらないだろう。」 というものだった(静止していない慣性系での光速度不変についてはマイケルソン・モーリーの厳密な光速度測定において考えられていた)。このように考えると、確かに、ロケットからも光の速度が地上と同じ c に見える。これが1905年にアインシュタインが提示した特殊相対性理論である。ハッブル宇宙望遠鏡(-うちゅうぼうえんきょう、Hubble Space Telescope、HST)とは地上約600km上空の軌道上を周回する宇宙望遠鏡である。長さ13.1メートル、重さ11トンの筒型で、内側に反射望遠鏡を収めている。主鏡の直径2.4メートルのいわば宇宙の天文台である。大気や天候による影響を受けないため、地上からでは困難な高い精度での天体観測が可能。
2007.02.15
コメント(0)
-

【一億Σヒストリー】イエスの体を刺した槍 - 「ロンギヌスの槍」
【一億Σヒストリー】Ground-Zero&硫黄島 - 「ロンギヌスの槍」「聖戦」:それは無益な人類系の永遠に繰り返される「愚かさ」の報復 1億超Gingaでも繰り返されてしまう...神と人の間にて...もGround-Zero その日は、なんとなく重苦しい雨が午前中降り続いていた。ジョージはいつもの仕事であるNETセールスマンとして、ブログコマーシャルを作成しながら、窓辺にある金魚の水槽を眺めた。すこし雨がやみ始めてきた。スーザンが部屋に入ってくるなり叫んだ。「なんて酷い!」 ジョージは何のことか直ぐには分からなかった。「どうしたんだ!」 しばし沈黙があったあとでスーザンが言葉をだした。「ジョージ、はやくNET-NEWSに切り替えて。」 ジョージは何がなにやら、兎に角PCの作業画面の表示アイコンから NET-NEWSのアイコンを選ぶとクリックした。即座にサンマーロイ帝国NEWSの画面が写った。 「先ほど5分前に、サンマーロイ国首都ワルセイドの首相官邸近くにある200階建てのメトロ・スカイ・シテイーに、メルカトロイ国と 思われるクローン人造人間操縦の対戦スペースジェットが突っ込み、 約10万人のメトロ・スカイ・シテイー市民への電力、酸素、エネルギー供給ライン、物流ライン系統の機能が停止しました。クローン人造人間の頭脳メモリ装置への指令系統にバグがあった模様です。」 このメトロ・スカイ・シテイーは、サンマーロイ国の技術の粋を集めた 国家威信を掛けた国力を象徴する超支配階級の豪邸や別荘がある人口 都市である。 この事件が、事故なのかそれとも宗教的な対立国家の陰謀なのか..。 これは、ひとつの発端であった。 スペイン内戦1937年、バスク地方の小都市ゲルニカがフランコの依頼でドイツ軍に空爆され、多くの死傷者を出した。この事件をきっかけに、ピカソは有名な『ゲルニカ』を制作した。死んだ子を抱いて泣き叫ぶ母親、天に救いを求める人、狂ったようにいななく馬などが強い印象を与える縦3.5m・横7.8mのモノトーンの大作であり、同年のパリ万国博覧会のスペイン館で公開され、大きな反響をよんだ。パブロ・ピカソ(Pablo Picasso, 1881年10月25日-1973年4月8日)はスペインに生まれ、フランスで制作活動をした画家・彫刻家。キュビスムの創始者であり、20世紀以降で最も有名な芸術家である。生涯におよそ13,500点の油絵と素描、100,000点の版画、34,000点の挿絵、300点の彫刻と陶器を制作し、最も多作な画家であるとギネスブックに記されている。スペイン内戦がフランコのファシスト側の勝利で終わると、ピカソは自ら追放者となって死ぬまでフランコ政権と対立した。『ゲルニカ』は長くアメリカのニューヨーク近代美術館に預けられていたが、スペインの民主化が進んだ1981年、遺族とアメリカ政府の決定により〈スペイン国民〉に返還された。現在はマドリードのソフィア王妃芸術センターに展示されている。硫黄島の戦い硫黄島の戦いで、日本軍は守備兵力20,933名のうち20,129名(軍属82名を含む)が戦死した。捕虜となった人数は3月末までに200名、終戦までにあわせて1,023名であった。アメリカ軍は戦死6,821名、戦傷21,865名の損害を受けた。硫黄島の戦いは、太平洋戦争後期の島嶼防衛戦において、アメリカ軍地上部隊の損害が日本軍の損害を上回った唯一の戦闘である。2月23日に星条旗を摺鉢山に掲げた6名の海兵隊員のうち、生きて故国の地を踏むことが出来たのは3名のみであった。第3、第4、第5海兵師団は硫黄島の戦いで受けた痛手のために沖縄戦には参加できなかった。硫黄島の奪取によってアメリカ軍は日本本土空襲の為の理想的な中間基地を手に入れた。終戦までの間に2,251機のB-29が硫黄島に不時着。その全てが技術的な問題を抱えていたわけではなかったと思われるが、それにしても延べ2万名以上の乗員の生命が救われたとされている。アメリカ陸軍航空軍の中で実際に爆撃機を運用していた各爆撃兵団の司令官達は、単発戦闘機の長距離護衛を面倒なお荷物としてかなり低く評価していたが、現実的には双発の邀撃機の活動を昼間は不可能にしたばかりか、日本軍戦闘機の邀撃を困難にした。活動を本格的に活発化させたアメリカ軍爆撃兵団は、東京大空襲(1945年3月10日)、名古屋大空襲(12日)、大阪大空襲(13日)を続けざまに実施した。題材とした作品戦史書防衛研修所戦史室、『戦史叢書 中部太平洋陸軍作戦(2)ペリリュー・アンガウル・硫黄島』、1968年 Alexander, Col. Joseph H., USMC (Ret). Closing In: Marines in the Seizure of Iwo Jima, Marines in World War II Commemorative Series, History and Museums Division, United States Marine Corps, 1994.(米国公刊戦史) Bartley, Lt.Col. Whitman S., USMC. Iwo Jima: Amphibious Epic, Marines in World War II Historical Monograph, Historical Section, Division of Public Information, United States Marine Corps, 1954.(米国公刊戦史) 武市銀治郎、『硫黄島―極限の戦場に刻まれた日本人の魂』、大村書店、2001年、ISBN 4756330150 写真集潮書房雑誌『丸』編集部編、『写真集 硫黄島』、光人社、2007年、ISBN 4769813341 ノンフィクションリチャード・F・ニューカム、田中至(訳)、『硫黄島』、光人社、1966年、2006年新装改訂版ISBN 4769821131 ビル・D・ロス、湊和夫監訳、『硫黄島 勝者なき死闘』、読売新聞社、1986年、ISBN 4-643-54810-X 上坂冬子、『硫黄島いまだ玉砕せず』、文藝春秋、1993年、ISBN 4167298112 栗林忠道、吉田津由子・編、『「玉砕総指揮官」の絵手紙』、小学館、2002年、ISBN 4094026762 堀江芳孝、『闘魂 硫黄島―小笠原兵団参謀の回想』(文庫)、光人社、2005年、ISBN 4769824491 梯久美子、『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』、新潮社、2005年、ISBN 4104774014 津本陽、『名をこそ惜しめ 硫黄島 魂の記録』、文藝春秋、2005年、ISBN 4163241507 栗林忠道、半藤一利、『栗林忠道 硫黄島からの手紙』、文藝春秋、2006年、ISBN 4163683704 留守晴夫、『常に諸子の先頭に在り―陸軍中將栗林忠道と硫黄島戰』、慧文社、2006年 ISBN 4905849489 ジェイムズ・ブラッドリー/ロン・パワーズ、島田三蔵(訳)、『硫黄島の星条旗』、文藝春秋、2002年、ISBN 4167651173 ジェームズ・ブラッドレー、大島英美(訳)、『父親たちの星条旗』、イースト・プレス、2006年、ISBN 4872577302 秋草鶴次、『十七歳の硫黄島』、文春新書、2006年 ドキュメンタリー『鎮魂硫黄島』(1985年日本アメリカ、監督:松本正志、ROBERT NIEMACK、東北新社) 『硫黄島決戦~壮絶なる死闘・そして玉砕!!』(1992年日本、日本クラウン) 『硫黄島:壮絶なる戦い』(2004年アメリカ、ヒストリーチャンネル) 『硫黄島:地獄の火山島』(2005年アメリカ、ヒストリーチャンネル) 『NHKスペシャル 硫黄島 玉砕戦~生還者 61年目の証言~』(2006年日本、NHK) 『硫黄島 地獄の36日間』(2006年アメリカ、アップリンク) 映画『硫黄島の砂』(1949年アメリカ、日本公開は1952年、監督:アラン・ドワン、主演:ジョン・ウェイン) 『海軍特別年少兵』(1972年東宝、監督:今井正、主演:地井武男) 『父親たちの星条旗』(2006年アメリカ、監督:クリント・イーストウッド、主演:ライアン・フィリップ) 硫黄島からの手紙』(2006年アメリカ、監督:クリント・イーストウッド、主演:渡辺謙) ドラマ『硫黄島~戦場の郵便配達~』(2006年フジテレビ) アニメーション『アニメンタリー”決断”第23話「硫黄島作戦」』(1971年日本テレビ・竜の子プロダクション) キリストの磔刑キリスト教の聖典である新約聖書の四福音書に書かれているエピソードの1つ。 ナザレのイエスが、エルサレム神殿を頂点とするユダヤ教体制を批判したため、ユダヤ人の指導者たちは、死刑の権限がないので、その権限のある支配者ローマ帝国へ反逆者として渡し、公開処刑の死刑である十字架ないしは杭に磔になって処刑されたというものである。「ロンギヌスの槍」神の子を自称したとされ、最高法院の裁判にかけられた後、ローマ帝国側に引き渡されて、反逆者として磔刑に処せられた。(最後の晩餐、キリストの磔刑)その後、十字架からおろされて埋葬されたが(キリストの墓 )3日後に弟子たちの前に現れた。(キリストの復活)40日間、地上にあったイエスは弟子たちの前で天に昇っていった。(キリストの昇天)
2007.02.12
コメント(8)
-

【一億Σ聖記】 太陽系銀河への天体キャッシュ航法
【一億Σ聖記】 太陽系銀河への天体キャッシュ観測&航法「テラ星への航行を楽しくさせているのは、時空空間をWARPした後に素晴らしい銀河の眺めと、とりわけテラ星を含む太陽系Ginga周辺の空間の素晴らしさ。まだ生誕まもない銀河たちの初々しさは、我々老いた反量子銀河から訪れる者にとっては、感動以外の何物にも変えがたい慶びを味わうのだった...。」(時空制御局アンリ・アイントシュタイン日記より @ Σ14142#22369+20%+10$)反量子人類系の数億年に及ぶ太陽系テラ星でのDNAクローン細胞生命環境の制御は最終段階にきていた。辺縁系をアクセス・ウィンドーとしながら、オリオン大星雲団をキャシュ銀河として、大マゼラン星団の宇宙引力を利用して極めて効率的な銀河衛星WARP航法を使っている。各Ginga星団に張り巡らされた生命体DNA-NETによって、ほぼREAL-TIMEに母星団である反量子銀河生命系銀河衛星群である反量子太陽系銀河での時空ミラーによるモニタリング衛星アクセス検証が可能となっている。銀河太陽系テラ星での出来事が99%宇宙時空の転送時空遅延後の実体が観測できる。観測だけでなく、このエネルギー伝送時空パイプラインは宇宙航行にも利用される。サンマーロイ国の首都ワルセイドからは、これまで多くの銀河衛星生命研究科学者や、銀河歴史創出管理局の官僚や軍人たちが、銀河太陽系テラ星へ移住したり、帰還している。まだ未開のテラ星を含めた銀河太陽系や銀河系での大ドミノ・シフト以降の銀河産業・軍事文化・文明での国家の覇権を優位とするための先行投資がなされてきた。最も資金力と政治力のあるサンマーロイ国が主力となって開発が推進され、まさにドミノ・シフトもカウントダウンに入ってきたのである。エッジワース・カイパーベルト天体(Edgeworth-Kuiper Belt Object、略してEKBO。本稿でもEKBOの略称を使う)は、太陽系の中で海王星軌道より遠い天体(海王星以遠天体、TNO)のうち、エッジワース・カイパーベルトにある天体、つまり、軌道長半径が約30 AU~約48 AUの天体の総称。単にカイパーベルト天体ともよばれる。仮説上のオールトの雲や内オールトの雲よりは内側の天体である。小惑星帯で最大の(1) ケレス(直径約950 km)を超えるものもいくつかあり、総質量はメインベルト小惑星の数百倍と推算されている。(134340) 冥王星やカロン(冥王星の第1衛星)、 (50000) クワオアーなどがEKBOに含まれる。また、軌道長半径が約48 AU以上で離心率が大きい散乱ディスク天体 (SDO) をEKBOに含めることがある。SDOとしては (136199) エリスなどがある。ただし、(90377) セドナは、軌道が非常に大きいだけでなく、近日点 (76 AU) でもエッジワース・カイパーベルトよりかなり外側なので、EKBOには含めない。(2060) キロンなどケンタウルス族や、海王星の衛星トリトン、土星の衛星フェーベなどは、その軌道および成分などから、元はEKBOだったと考えられている。散乱ディスク天体 (SDO) 軌道長半径が約48 AU~約400 AUで、離心率が大きい天体。近日点距離は約30~40 AU(ほとんどは約30 AUを大きく超えない)、遠日点ははるか遠く(約70~数百 AU)にある。海王星の重力によって、エッジワース・カイパーベルトから散乱させられた天体である。太陽から遠く暗いため、未発見の大きなものが多数あると推測されている。最大の (136199) エリスもSDOである。なお、SDOをEKBOに含めないこともある。 (90377) セドナを便宜上SDOに含めることがあるが、EKBOには含めない。 ケンタウルス族を、内側への散乱天体として、外側への散乱天体であるSDOと一括してあつかうことがある。 狭義のEKBO 共鳴天体(共鳴TNO、共鳴EKBO) 海王星との軌道共鳴により、公転周期が整数比(尽数関係)にある天体。海王星との永年共鳴と摂動により、離心率と軌道傾斜角が増大している。軌道が大きくSDOの定義に当てはまるものは、SDOに分類することもある。なお、以下の「3:2」などは公転周期の比だが、角速度の比を表す(つまり3:2の代わりに2:3とする)流儀もある。 冥王星族(プルーティノ) 海王星との3:2共鳴天体。公転周期約247年、軌道長半径約39.4 AUで、エッジワース・カイパーベルトの内縁付近に位置する。(134340) 冥王星など。 トゥーティノ族 海王星との2:1共鳴天体。公転周期約330年、軌道長半径約47.7 AUで、エッジワース・カイパーベルトの外縁付近に位置する。(26308) 1998 SM165など。族名のtwotinoは、two + plutinoからの造語である。 他に、4:3、5:3、7:4、5:2共鳴天体などが知られている。1:1共鳴天体もあるが、EKBOではなく海王星のトロヤ群である。 キュビワノ族(古典的TNO、古典的EKBO) EKBOのうち、SDO・共鳴天体以外のもの。海王星の永年共鳴を受けないため、軌道傾斜角も離心率も低く、ほとんどは離心率0.2以下、軌道傾斜角10°以下である。近日点距離は35 AU以上で、あまり海王星には近づかない。軌道長半径は、ほとんどがトゥーティノと冥王星族の間の、41 AU~48 AUである。族名は、最初に発見された (15760) 1992 QB1(キュービーワン)からきている。 2006年のIAU総会で、静水平衡、つまり重力でほぼ球形になった天体(惑星・衛星以外)は矮惑星 (dwarf-planet) に分類された。EKBOでは(134340) 冥王星と (136199) エリスが矮惑星に属する。今後の観測・研究によって、さらに増えると予想されている。なお、EKBOを含めTNOは世界各地の創世神話にちなんで命名すると決められている。例えば、クワオワーはアメリカ先住民トングヴァ族の、セドナはイヌイットの創世神話から名づけられた。主なEKBOおよび関連天体主なEKBO(背景色は種類を表す)と関連天体(白背景・斜体)。名前の付いたもの、大きいものなど。 確定符号 名前か仮符号 種類 直径 / km 公転周期 / 年 衛星 発見 備考 Saturn IX フェーベ 土星の衛星 220 (29.46) - 1898 逆行衛星 2060 キロン ケンタウルス族 132~142 50.54 - 1977 最大のケンタウルス族 Neptune I トリトン 海王星の衛星 2707 (164.77) - 1846 逆行衛星 (未登録) 2001 QR322 海王星トロヤ群 50~160 165.7 - 2001 15386 1995 DA2 4:3共鳴天体 40~140 220.2 - 1995 38083 ラダマントゥス 冥王星族 約160 245.79 - 1999 90482 オルクス 冥王星族 840~1880 247.94 - 2004 134340 冥王星 冥王星族 2320 248.54 3 1930 矮惑星。最初に発見された Pluto I カロン 冥王星族 1186 (248.54) - 1978 冥王星の衛星 28978 イクシオン 冥王星族 822以下 248.63 - 2001 38628 フヤ 冥王星族 300~700 250.36 - 2000 55637 2002 UX25 キュビワノ族 約910 277.31 - 2002 20000 ヴァルナ キュビワノ族 約936 283.20 - 2000 136108 2003 EL61 キュビワノ族 1960×1520×1000 285.4 2 2003 通称サンタ 50000 クワオアー キュビワノ族 1250±50 285.92 - 2002 15760 1992 QB1 キュビワノ族 約120 289.225 - 1992 「EKBOとしては」最初に発見 53311 デュカリオン キュビワノ族 90~300 295.54 - 1999 58534 ロゴス キュビワノ族 80 305.80 1 1997 19521 カオス キュビワノ族 約560 309.10 - 1998 136472 2005 FY9 キュビワノ族 1600~2000 309.87 - 2005 通称イースターバニー 55565 2002 AW197 キュビワノ族 700±50 327.25 - 2002 26308 1998 SM165 トゥーティノ族 130~400 327.38 1 1998 84522 2002 TC302 5:2共鳴天体 1200以下 408.03 - 2002 SDOに含めることも (未登録) 2004 XR190 散乱ディスク天体 425~850 430.91 - 2004 136199 エリス 散乱ディスク天体 2400 557 1 2003 矮惑星。冥王星を含めても最大 15874 1996 TL66 散乱ディスク天体 約630 754.83 - 1996 最初に発見されたSDO 87269 2000 OO67 散乱ディスク天体 28~87 11624 - 2000 90377 セドナ 不明 1180~1800 12050 - 2003 エッジワース・カイパーベルトの分布範囲は概ねヘリオポーズの内側にあるが、このベルトに属する一部の天体はヘリオポーズを出入りしたりその外側に位置する場合もあると考えられる。現在発見されている太陽系天体で最大の軌道長半径を持つセドナは、近日点付近以外の大部分の期間ヘリオポーズの外側にいるとも考えられるが、太陽圏の形が不明確であるため定かではない。オールトの雲は完全にヘリオポーズの外側にある。2005年、ボイジャー1号が人工物として初めて、太陽からおよそ90天文単位の位置で末端衝撃波面に到達した模様である、と報じられている。2005年5月24日、ボイジャー1号はヘリオポーズに到達した最初の惑星探査機となり、同時に1号・2号の観測によってヘリオポーズが宇宙の磁場の影響を受けて歪んでいることを突き止めた。ヘリオポーズ (Heliopause) とは、太陽から放出された太陽風が星間物質や銀河系の磁場と衝突して完全に混ざり合う境界面のこと。太陽風の届く範囲を太陽圏、または太陽系圏、ヘリオスフィア (Heliosphere) などと呼ぶが、その宇宙空間との境目を表す用語である。太陽の外縁部に達した超音速の太陽風は、まず星間物質や星間磁場によって亜音速にまで急減速されて末端衝撃波面(Termination Shock)を形成し、低速度の太陽風と星間物質とが混ざり合うヘリオシース (Heliosheath) という領域を経て、ヘリオポーズで完全に星間物質に溶け込んでいる、とされている。更に、太陽系は銀河系の中を公転しているため、ヘリオポーズ外側の公転の進行方向には、公転による星間物質とヘリオポーズとの衝突で生じるバウショック(Bow Shock)と呼ばれる衝撃波面が形成されていると考えられている。ヘリオポーズまでの距離は学説によりばらつきがあるが、概ね太陽から50~160天文単位(太陽から冥王星までの距離のおよそ1.2~4倍)の位置にあると推定されている。そもそも太陽圏の形や大きさは、太陽活動の変化や太陽が通過する星間空間の物質密度などによって常に変化していて、銀河磁場の影響で進行方向の反対側に流されて広がった、ちょうど巨大な彗星のようないびつな形をしていると考えられるため、ヘリオポーズの位置や太陽からの距離を厳密に特定するのは難しい。
2007.02.10
コメント(4)
-
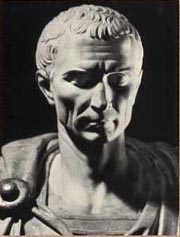
【一億Σ聖記】 ◆ 第五話 ◆ Bland of Venul (カエサルの憂鬱)
◆ 第五話 ◆ Bland of Venul 大陸の西域ヴェヌル共和国の首都フィロレンツアは、遠い過去文明の 起源を築いてきた自負心高き人種の都らしく、クローン製品が氾濫し 人間型ロボットの模造品すら安売りされているこのDigital戦争の時代に、崇高な精神性を世界に与え続ける荘厳な寺院や哲学学校の立ち並ぶ美しい都市である。町の建造物や装飾物は厳密に国家院統制局で管理され、住民は生涯の生活権限を保障されていると同時に、オリジナル製品憲章に基づくテクノロジー製品を、自前のブランドでNET貿易できる環境が整備されている。当然ながらそれに見合った高額の国税を毎年デジタル貨幣かクレジットで支払うのだが。 国民ひとりひとりが優秀なデジタルNET商人に育てられ、世界中との 貿易競争力で経済運営能力により国家指導者を輩出してきたために、 現状は国民に税金支払いの不満は大きくない。しかし、その背後には サンマーロイ国の世界制覇戦略の影が忍びつつある。 ユピタルク国のクローン技術の氾濫による、このヴェルヌ共和国の貿易収支の悪化は最悪の事態へと進みつつある。ユピタルク国には、形状から機能、性能にいたるまで完璧に類似のクローン製品が低価格で登場 し続けている。ヴェルヌ共和国は輸入関税を最高度の緊急防御レベルの Z勧告水準で掛けており、やっと純粋なヴェルヌのオリジナル製品と同等の価格で、折り合いをつけている状態である。 近くヴェルヌ共和国は、ユピタルク国へクローン技術自体の使用課税法案を導入するように宣言する。つまり、ヴェルヌ共和国国民がユピタルク国製品を購入した場合への増税処置を議会で可決するのである。 だが、本質的な対抗策を講じきれない苦しみが次第に覆ってきている。 digitalクローン技術は簡単な機械生産から生命模造細胞、人造人間までいまや可能にしてしまっている。簡易X線メガネで透視すれば一目瞭然だが、それでも肉眼では区別つけにくい動物ペットも増えた。 全世界がdigital-NET帝国となってすでに1世紀が経ち、ヴェルヌ共和国とイーゼス国、マーシェム国を除く大半が幾つかの帝国NET憲法が制定されており、クローン製品の取引はNET-貨幣で決済されるため、開発販売開始から数秒で、全世界に売られていく。 貿易を律側するのは、生産能力と輸送時間だけ。 先進国家であったヴェルヌ共和国は、あきらかに後発国ユピタルク国の 貿易戦争戦略に屈しかけてきていた。多くの有名ブランドを作り出してきた歴史が、そのブランドもろともNET貿易戦争のうねりに飲み込まれていくのだ。 ガイウス・ユリウス・カエサル生涯 生い立ち~政治キャリアのスタート古代ローマの古くからの名門貴族(パトリキ)であるユリウス氏族に属するカエサル家の子としてローマに生まれる。父は同名のガイウス・ユリウス・カエサル、母は、アウレリア。父の妹ユリアがガイウス・マリウスに嫁いでいたため、幼少の頃より民衆派(ポプラレス)と目されていた。紀元前84年に有力な民衆派のルキウス・コルネリウス・キンナの娘であったコルネリア(Cornelia)と結婚。マリウスやキンナの政敵であるルキウス・コルネリウス・スッラが独裁官になると、スッラはカエサルとコルネリアとの離婚を命じたが、カエサルは従わず、紀元前81年ローマから逃走した。スッラが紀元前78年に逝去すると、ローマに帰還した。コルネリアは紀元前68年に逝去し、その後はスッラの孫であるポンペイア(Pompeia)と結婚した。ポンペイアは裕福だったため、カエサルはその財産を買収や陰謀に使い、政治的なキャリアを積み重ねていった。紀元前65年には高級按察官(aedilis curulis)に就任。紀元前63年には異例の若さで共和制唯一の終身職である最高神祇官(pontifex maximus)に当選。紀元前62年には法務官(praetor)に当選した。三頭政治紀元前60年、執政官をめざすカエサルは、オリエントを平定して凱旋した自分に対する元老院の対応に不満を持ったポンペイウスと結び執政官に当選する。ただこの時点で、すでに功なり名を成したポンペイウスに対し、カエサルはたいした実績もなく、ポンペイウスと並立しうるほどの実力はなかった。そこでポンペイウスより年長で、騎士階級(経済界)を代表し、スッラ派の重鎮でもあるクラッススを引きいれてバランスを取った。ここに第一回三頭政治が結成された。民衆派として民衆から絶大な支持を誇るカエサル、元軍団総司令官として軍事力を背景に持つポンペイウス、経済力を有するクラッススの三者が手を組むことで、当時強大な政治力を持っていた元老院に対抗できる勢力を形成した。執政官在任中には、元老院体制におけるタブーであった農地法を成立させる。当初、元老院はこの法案に激しく反対したが、カエサルは職権で平民集会を招集、巧妙な議事運営で法案を成立させるとともに、全元老院議員に農地法の尊重を誓約させることまでした。これも三頭政治が有効に機能した結果といえよう。ガリア戦争紀元前58年、カエサルはガリア・キサルピナおよびガリア・トランサルピナを任地とする属州総督に就任した。カエサルは、ヘルウェティー族のローマ属州ガリア通過要求を拒否した。これを契機に、ヘルウェティー族との間で戦争状態になった。これが彼のガリア戦争の発端である。その後カエサルはガリア人の依頼を受けてゲルマニア人のアリオウィストゥスと戦って勝ち、翌年にはガリアの北東部に住むベルガエ人諸部族を制圧した。これらの遠征により、カエサルはガリア全土をローマ属州とした。カエサルはガリア遠征について、自らの著書『ガリア戦記』にまとめている。同書は雄渾で簡潔な文体で知られ、ラテン散文の傑作とされる。カエサルはこの戦争でガリア人から多数の勝利を得、ローマでの名声を大いに高めた。彼は「新兵は新軍団を構成し、既設の軍団には新兵を補充しない」という方針を採ったため、長期間に渡る遠征を共にした軍団は兵数を通常の定足数より減らしたが、代わりに統率の取れた精強な部隊になり、ローマにではなくカエサル個人に対し忠誠心を抱く兵士も多かったと言われる(事実、ルビコン以後ではローマの為というより、自分達の最高司令官の名誉のために戦う、と明言した者も多い)。 これらのガリア征服を通して蓄えられた実力はカエサルが内戦を引き起こす際の後ろ盾となったのみならず、ローマの共和派のカエサルに対する警戒心をより強くさせ、共和派の側からも内乱を誘発させかねない強攻策を取らせることとなった。ローマの内乱カエサルがガリアに遠征していた紀元前53年、パルティア王国攻略に出ていた三頭政治の一角であるクラッススの軍が壊滅し、クラッススは戦死した。これにより、三頭政治は崩壊し、元老院派に取り込まれたポンペイウスとカエサルとの対立が顕在化した。紀元前49年、カエサルのガリア属州総督解任および本国召還を命じる元老院最終勧告(事実上の非常事態宣言)が発布された。カエサルは自派の護民官がローマを追われたことを名目にして、軍を率いてルビコン川を越え、国家を内乱へと導いた。当時ルビコン川以南への軍の侵入は禁じられていた。1月10日、ルビコン川を渡る際、彼は有名な言葉「Alea jacta est. (賽は投げられた。)」を残している。ルビコン川を越えたカエサルの行動は迅速だった。即日リミニ入城、アドリア海沿いにイタリア半島の制圧を目指した。対するポンペイウスはローマにあったため即時の軍団編成を行えず、ローマおよびイタリア半島を放棄し自身の勢力地盤であったギリシアに離脱、軍備の再編成を行なった。これによりカエサルはローマの実質的な支配権を手にした。スペインにいるポンペイウス派の将軍を倒して後方の安全を確保したカエサルは、2回目の執政官当選を果たした後、ギリシアへポンペイウスを追撃に出た。数で劣るカエサル軍は、包囲戦を展開した緒戦のドゥラキウムの戦いでは撤退の憂き目にあったものの、ファルサルスの会戦では優れた戦術を駆使してポンペイウス軍に圧勝した。ポンペイウスは逃亡したが、エジプト(アレクサンドリア)に上陸しようとした際に、迎えの船の乗組員に殺害された。その数日後アレクサンドリアに着いたカエサルは、そこでポンペイウスの死を知った。アレクサンドリアポンペイウスの死を知ったカエサルはエジプトの首都、アレクサンドリアに上陸した。当時、エジプトでは先王プトレマイオス12世の子であるクレオパトラ7世とプトレマイオス13世の姉弟の間で後継者争いが繰り広げられていた。この地でカエサルはクレオパトラ7世と特別な関係となり女王の側に立って政争に介入した。弟王との間で戦われたアレキサンドリア戦役の結果、カエサルは弟王を打ち破った。カエサルがクレオパトラ7世に与した理由は諸説あるが、フランスの哲学者ブレーズ・パスカルが「クレオパトラの鼻、それがもう少し低かったら、大地の全表面は変わっていたであろう」と著書『パンセ』で述べているような、彼女の美貌に惑わされたからという訳ではない。プトレマイオス13世とその周辺が反ローマ的であったためであり、エジプトの掌握をより容易にするためである。また、弟王側にポンペイウスを謀殺した犯人らがいたと言う事実も見逃すことができない。当時ポンペイウスはまだ元老院に籍を置くローマの公人であり(カエサルがポンペイウス側の要人の官職を剥奪していなかったため)ローマの新たな指導者となったカエサルには前執政官の暗殺を見過ごすわけにはいかなかっという理由が挙げられる。さらに、カエサルは小アジアまで足を伸ばし、ポントス王ファルナケスを破った。この時に元老院に送った戦勝報告が、かの有名な「Veni, Vidi, Vici. (来た、見た、勝った。)」である。かくして紀元前47年、カエサルはローマに凱旋し、熱狂的な市民の歓呼に迎えられ、任期5年間の独裁官に任命された。なお、このときカエサルは、クレオパトラとの間にできた息子とされるカエサリオンを伴っていた。終身独裁官~暗殺紀元前46年、北アフリカにて抵抗を続けていた共和派の残党を討ち果し(タプトスの会戦)、その支配権を確固たるものとしたカエサルは共和政の改革に着手する。属州民に議席を与えることで元老院への権力集中を防ぎ、機能不全に陥っていた民会、護民官を単なる追認機関とすることで有名無実化をした。さらに、自らが終身独裁官に就任し、権力を1点に集中することで統治能力の強化を図ったのである。この権力集中システムは元首制(プリンキパトゥス)として、後継者のオクタウィアヌス(後のアウグストゥス)に引き継がれ、帝政ローマ誕生の礎となった。だが、カエサルへの権力集中に対し危機感を抱いたブルートゥス、カッシウスらにより、紀元前44年3月15日、カエサルは元老院が開催されていたポンペイウス劇場に隣接する列柱廊にて暗殺された。数日後、遺言に従い、18歳の養子のガイウス・ユリウス・カエサル・オクタウィアヌス(アウグストゥス)が後継者に指名された。ブルートゥスに暗殺された際に残した「Et tu, Brute! (ブルートゥス、お前もか!)」という言葉は有名だが、これは後世イギリスのシェークスピアによって作られた戯曲『ジュリアス・シーザー』の台詞である。
2007.02.06
コメント(0)
-

【超Ginga-微粒子Genzai】 テラ(地球)20世紀式旧式化石エンジンの終焉
【超Ginga-微粒子Genzai】 テラ(地球)20世紀式旧式化石エンジンの終焉 21世紀、銀河太陽系テラ星(地球)は、20世紀に開発発展した化石燃料発火エンジンの排出する過去の化石が蓄えたCO2(二酸化炭素)の排出による濃度の増加に伴う薄いテラ外周を取り巻く大気環境の高温化と汚染に愚かにもがいていた...。 デイ・アフター・トゥモロー 気候学者ジャックは地球温暖化によって生じた大規模な氷棚を発見する。異常を察知し警告を発するが誰も信じようとはしなかった。だが、天候の変化で世界規模の大災害が起こりはじめた。大作パニック映画。 制作年度:2004制作国:アメリカ出演:デニス・クエイド/ジェイク・ギレンホール/イアン・ホルム/エミー・ロッサム/原康義/浪川大輔/小林恭治/小笠原亜里沙監督:ローランド・エメリッヒ脚本:ローランド・エメリッヒ/ジェフリー・ナクマノフ音楽:ハラルド・クローサー製作:マーク・ゴードン撮影監督:ユーリ・ステイガーその他:カレン・グーレカス ある者はその状況は経済的な問題といい、ある者は政治的なプロパガンダだと非難していた。まだ、銀河系へ自由に飛行できるCOSMO航行エンジンを知りえないことから、自らの住む衛星の地中に埋蔵された化石の時経変化による燃料噴射発火エネルギーを用いた原始的な装置を使っていた為に、宇宙への飛翔も衛星上での移動でも、自らの生活圏を破壊しながら言い訳をして、ろくな衛星制御技術も持ち合わせないでいた。さらに、時に原子分裂エネルギーを放出させる破壊兵器を使って、種族ごとの小競り合いで数億人単位で殺戮しあっていた時代だった。 人類系の進歩と進化を維持しつつ、テラ星の衛星制御を実現する科学についての基礎的な準備がこの当時漸くできつつあった。多少乱暴なシナリオの映画であったが、大きな影響を政治、経済、科学、文化、教育、産業へ確かな正しい影響を与えた。 JAPANがこの頃産業投下していく、化石燃料エンジンから生物精製合成燃料エンジンと超効率発電エンジンそして、イオン・エンジンとROBOTICS-CARへの生産移行により、経済支配構造や政治体制原理、人類系活動範囲の宇宙銀河への拡大が本格化し、いよいよ衛星制御自体が極めて大きな産業化となっていくのだが...。まずは、21世紀初頭に活動した大統領の歴史的な記事を紹介しよう...もう賢明な読者は気が付かれたであろう...。人類系の進んだ道が...元米副大統領のアル・ゴア氏が訴える地球の危機(各メデイアの報道内容抜粋)クリントン政権下で副大統領を務め、2000年の大統領選挙で現在の米大統領であるブッシュ氏に破れたアル・ゴア氏。彼は全米規模のコンピュータネットワークを構築するという情報スーパーハイウェイ構想を提唱した人物として知られる。現在でもAppleの取締役やGoogleのシニアアドバイザーを務めるなど、テクノロジー業界に縁の深い人物だ。 地球の平均気温は20世紀の間に約0.6度上がったと言われており、このまま行けば2100年にはさらに1.4~5.8度上昇するという予測もある。「たいしたことないと思うかもしれないが、これが自分の子どもだったらどうだろう。体温が36度の平熱から5度上昇して41度になったとしたらかなり重大な問題だ」(ゴア氏)。もし自分の子どもが熱を出せば、ただちに病院に行って医者のアドバイスに従うだろう。同じように、温暖化の問題には、警鐘を鳴らす科学者たちの声に耳を傾けるべきだとゴア氏は訴える。 ゴア氏は1960年代後半から温暖化問題に取り組んでおり、1997年に採択された京都議定書の交渉にも尽力した。米国では連邦議会が議定書の批准を渋り、ブッシュ政権になってからは議定書からの離脱を正式に表明している。この点についてゴア氏は「本来なら米国がリーダーシップを発揮すべき分野だ」として現政権を批判。同時に、この会議で議長国を務めた日本には、引き続き温暖化問題でリーダーシップを発揮して欲しいと期待を寄せた。 地球の温暖化は進んでいるが、ゴア氏は「いろいろな解決策が出てきており、時間もまだ残されている」と語る。二酸化炭素の排出量を減らすような技術も登場しており、足りないのは「行動する意志」(ゴア氏)というわけだ。不都合な真実のウェブサイトには、誰でもできる取り組みとして「白熱電球を電球型蛍光灯に交換する」などの方法が挙げられている。 映画を通じて温暖化の問題を世界中に訴え、1人1人がこの問題を解決するための一員になって欲しいと語るゴア氏だが、再び政治の世界に戻るつもりはないのだろうか。ゴア氏に聞くと、このような答えが返ってきた。「再び立候補するつもりはありません。この温暖化問題がいかに切迫したものであるかを世の中に伝え、解決に結びつけるための活動で手一杯ですから」一人一人が行動を~映画「不都合な真実」アル・ゴア氏 2007/01/17 「不都合な真実」は、世界各国を飛び回るゴア氏の講演活動を追いながら、具体的なデータとともに地球温暖化対策の必要性を訴える。ゴア氏は学生の頃から環境問題に興味を持ち続け、議会活動・国際会議の場で温暖化対策の必要性を訴えてきた。1992年には著書「地球の掟・文明と環境のバランスを求めて」を発表。2000年の米大統領選でブッシュ大統領に敗北したことを機に、環境問題への取り組みを本格化。世界中で計1000回以上の講演を行っている。 映画化に同意した理由について「今の政治システムを変えるためには、すべての個人、家族、そして国民にじかに話しかけていくしかない。米国の政府を変えるには、世論を動かすしかないと思ったわけです」と話した。 さらにゴア氏は、日本語の「危機」という言葉について「英語で“クライシス”という言葉は危機と訳しますが、危険な部分だけを強調していて、“希望”と言う意味が言葉にはありません。日本の“危機”の危は“危険”の危ですが、機は“機会”という意味があります。(環境問題は)人類が直面する大変危険なことですが、大きな機会、チャンスも含まれています」と語った。「現状を悲観するだけではなく、一人ひとりが力を合わせるチャンスととらえ、希望を持ちましょう」と語りかけた。 また、ゴア氏は「(人類は)多くの技術を持っているが、足りないのは行動する意志です」とも話した。「行動できる意志」は「再生できる資源」であり、「映画を観る時には目と耳だけではなく心で受け止め、問題を解決する一員となってほしい」と、ホールを埋め尽くした観客に語りかけた。「特に日本は、京都議定書のホスト国として、世界に先駆けて環境問題に取り組む姿勢を示したことで、歴史に残ると思います。(京都議定書は)この問題に人類が取り組む転換になったできごとだと思います」とも話した。 最後に、ゴア氏は「もし子供が熱を出したら、医者に連れて行くでしょう。医者の指示に従うでしょう。今、地球は熱がある状態です。4~5度高いだけでは感じにくいかもしれませんが、もし体温が36.5度から41.5度になったら、かなり重い変化だと思います。熱を出している地球に対して、科学者が出しているアドバイスを実行していなかければならなりません」と話し、舞台挨拶を締めくくった。 ゴア氏が「地球温暖化阻止のためには一人一人の意志を持った取り組みが必要であり、その取り組みは再生できる資源だ」と言い切ったことに、私も非常に強い勇気をもらった。「不都合な真実」を観た人たちが、自分の意識を変化させ、行動に移し、波及させていくことが、病んでいる地球を救うための大きな原動力となるよう願いたい。××××× 「不都合な真実」監督:デイビス・グッゲンハイム出演:アル・ゴア1月20日、TOHOシネマズ六本木ヒルズ・日劇PLEXほかで公開。作品の詳細は公式サイトまで。 (木戸満知子) 【関連書籍】【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 蜂のように暮らす―なにも傷つけないビジネス/第2章 同意を撤回する―民主主義の実践/第3章 コヨーテに草を育ててもらう―生物多様性の回復/第4章 リバー・ランズ・スルー・イット―水を守る/第5章 種を守る人々―良い食べ物を育てる/第6章 ジャガーの気配を感じるか―森は誰のもの?/第7章 アホウドリの鳴き声―海の魚を捕り尽くさないで/第8章 プルトンとの闘い―有毒物質を減らし、大気を浄化する/第9章 小箱から抜け出す―新しい考え方、学び方
2007.02.04
コメント(0)
-

【超芸術】 板橋 廣美 いたばし ひろみ (Ginga陶芸)
板橋 廣美/Hiromi ITABASHI 1948年東京都生まれ、三鷹市在住。多治見市陶磁器意匠研究所修了。1977年、朝日陶芸展に風船から石膏型を取った鋳込みによる無釉白磁のオブジェを出品し、朝日陶芸賞を受賞。以後、白くデリケートな磁土の感触とゆるやかな曲線を描くフォルムをもつオブジェを、さまざまな空間に設置した作品で、陶芸の表現に新しい感覚を取り込んでいきます。また90年代中頃からは、粘土を焼成して粉砕したシャモット(焼粉)と呼ばれる素材に注目し、釉薬をしみ込ませた原型をシャモットの中に埋め込み、窯の中で釉薬が溶けて磁器化する際に自然に生まれる形を活かした新しい造形に取り組みます。本展では、鋭く切り立った白磁のオブジェが夥しく林立した空間や、シャモットの危うく繊細なイメージを活かした不思議な形状のオブジェなどを出品します。1948 東京生まれ 1975 岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所入所日本陶磁器デザインコンペティション'75デザイン学生賞受賞日本陶磁器デザインコンペティション奨励賞受賞 1976 日本陶磁器デザインコンペティション優秀賞受賞 1977 岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所退所岐阜県陶磁器デザイン総合展入選朝日陶芸展朝日陶芸賞受賞 1978 中日国際陶芸展入選 以後5回入選伊藤慶二氏に師事朝日陶芸展入選 以後5回入選 1979 岐阜県陶磁器デザイン総合展奨励賞受賞 1980 東京都三鷹市牟礼に築窯吉祥寺近鉄百貨店にて個展MINOバトルロイヤル展企画出品チヨダギャラリー(横浜)にて個展 以後個展開催多数 1983 日本陶芸展入選 87年も入選朝日陶芸展朝日陶芸賞受賞 1984 中日国際陶芸展中日大賞受賞 1985 朝日現代クラフト展受賞 以後3回受賞中日国際陶芸展愛知県知事賞受賞 1986 八木一夫賞現代陶芸展入選 87年も入選美濃国際陶磁器フェスティバル入選 1987 美濃国際陶磁器フェスティバル選抜展ワシントン・シアトル・セラミック展日本クラフト展入選 1988 カフェノアール入選(ベルギー)セラミックアネックスシガラキ'88「ブータン国王へのメッセージ展」 ギャラリーいそがや 1989 朝日現代クラフト展招待出品'89美濃国際陶磁器フェスティバルデザイン部門銀賞(中小企業長官賞)受賞岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所展現代日本クラフトデザイン展 Trillium Court Area(アメリカ・ワシントン州ベリンハム市) 盛り付け秘伝 器と料理 【内容情報】(「BOOK」データベースより)器づかいにこだわりをもつ和洋中の実力派シェフ3人が、現代一流作家15人の土の器、木の器に創作料理を盛る。五感を研ぎ澄まして対峙する、器と料理の真剣勝負135番。すべての「盛り付け」に、シェフ自身のコメントとシェフ同士の相互批評を収載。 【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 人気絶頂の気鋭の作家の器に盛る(黒田泰蔵/星正幸/三谷龍二/太田修嗣/大蔵達雄)/第2章 日本を代表する個性派作家の器に盛る(鯉江良二/鈴木五郎/小川待子/隠崎隆一/須田菁華/伊藤慶二/坂田甚内/滝口和男/山田和/板橋廣美) 板橋廣美略歴 国際陶芸アカデミー会員 1948 東京三鷹市生まれ 1973 日本大学法学部卒 1977 岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所修了 1978 陶芸家伊藤慶二氏師事 1992 武蔵野市障害者総合センター講師1996 ウインズ陶芸研究所開設 1998 上越教育大学講師 1999 金沢卯辰山工房講師多摩美術大学講師 2000 NHK「やきもの探訪」放映BS2 2005 ヴァロリス AIR 制作 (フランス) 作家活動個展1995 ギャラリー彩陶庵(山口) 1996 ギャラリエアンドウ(東京)・目黒陶芸館(四日市) 1997 足利乾ギャラリー(栃木)・ライフギャラリー点(福岡) 1998 コンテンポラリーアートNIKI(東京)・ギャラリエアンドウ(東京) 1999 ギャラリー炎舞(名古屋) 2000 ギャラリーたち花(東京) 2001 ギャラリエアンドウ(東京) 2002 ギャラリーたち花(東京)・目黒陶芸館(四日市)ギャラリー炎舞(名古屋) 2005 ギャラリーたち花(東京)ヴァロリスAIR(フランス) 企画展1988 セラミックアネックスシガラキ88 (滋賀県立美術館) 1989 朝日現代クラフト展招待出品 92 (朝日新聞社)現代日本クラフトデザイン展 (ベルンハム市・アメリカ) 1993 UTSUWA (埼玉県近代美術館) 1995 金沢工芸大賞コンペテイション招待 (金沢市)ファエンッアの風 (セラトピア土岐・土岐市) 1996 机上空間の為のアートワークス展 若き陶芸の旗手達 (愛知県陶磁資料館)「磁器の表現」1990年代の展開 (東京国立近代美術館工芸館)女はどう表現されてきたか (岡山県立美術館) 1997 ソウル セラミック アート ビエンナーレ (ソウル市立美術館・韓国) 2000 「陶芸の路」陶芸展招待出品 (コペンハーゲン・デンマーク) 2001 現代陶芸の精鋭 21世紀を開くやきものの手法と形 (茨城県立陶芸美術館)大韓民国ワールドセラミックエギジビション (ソウル・韓国) 2002 現代陶芸100年史 岐阜県現代陶芸美術館 (多治見市) 2003 第17回 日本陶芸展招待出品 (毎日新聞社主催)アベラネーダセラミック シンポジウム招待 (アルゼンチン)工芸の現在 アメリカ・ヨーロッパ・アジア・21人展(金沢) 2004 かたちを切る 日本の現代陶芸 (岐阜県現代陶芸美術館) 2005 第18回 日本陶芸展招待出品 (毎日新聞社主催) 2006 日本陶芸100年の精華(茨城県立陶芸美術館)陶芸の現在、そして未来へIACラトビア展(ラトビア リガ) 受賞1975 日本陶磁器デザインコンペディション・75デザイン学生賞 (日本陶磁器デザイン協会)日本陶磁器デザインコンペティション・奨励賞 (日本陶磁器デザイン協会) 1976 日本陶磁器デザインコンペティション・優秀賞 (日本陶磁器デザイン協会)朝日陶芸展・77朝日陶芸賞 (朝日新聞社 主催) 1979 岐阜県陶磁器デザイン総合展・奨励賞 (岐阜県) 1983 朝日陶芸展・83朝日陶芸賞 (朝日新聞社 主催) 1984 中日国際陶芸展・84大賞 (中日新聞社主催) 1985 中日国際陶芸展・特賞 (中日新聞社主催) 1989 国際陶磁器美濃・デザイン部門・銀賞 (岐阜県 多治見市) 1991 47イタリア ファエンッア国際陶芸展買い上げ賞 (イタリア ファエンツア) 1997 出石磁器トリエンナーレ・97大賞 (兵庫県出石市) パブリックコレクション1990 近代美術館「日本の家」(アルゼンチン)蓼科ブライトンホテル 1991 ファエンッア 国際陶芸博物館 (イタリア) 1996 石川県九谷焼陶芸研究所 1997 兵庫県出石町ソウル市立美術館 (韓国) 2003 岐阜県立現代陶芸美術館 2004 金沢21世紀現代美術館ベナキ博物館 (ギリシャ)兵庫県立陶芸館 2005 ワールド・セラミック・ファンデーション(韓国)アリアナ美術館(スイス)ヴァロリスAIR(フランス)
2007.02.02
コメント(0)
-

【一億Σ聖記】 ◆ 第四話 ◆ Clones
【一億Σ聖記】 ◆ 第四話 ◆ Clones 世界的な指導力は、これまでも政治的な優位性を貨幣価値を決める国が 支配してきた。これは変わることのない原理であろうが、サンマーロイ国がこの覇権を永久に握っていたいとする限り、陣営には強力な政策を支援する国々が存在する。それがクローン製造に仲間しているが規模の点と賃金のアンバラスな関係に位置するサチュラウス諸国である。 これらは、ユピタルク国にはこれまで目の上のタンコブ的な存在である。 イーゼス国と友好的な生産体制を提供することで、ユピタルク国の敵対貿易国であるが、一方でサンマーロイ国の覇権を支える製造輸出国という点では、ユピタルク国を盟主と担ぐ同胞でもある。 人種的にも、歴史的にも極めて近い。 マーシェム国が、近年圧倒的な技術立国政策を取ることで、超強力な非クローン製造国となって来た。そしてユピタルク国を大きな市場と位置づけ戦略を仕掛けできたのである。市場性の低いこうしたサチュラウス諸国は、急激に地位低下を引き起こしている。ユピタルク国とサンマーロイを巻き込んだクローン大量生産戦争の時代へ突入していく。これは、イーゼス国を自然回復的に救っていく追い風となっていった。 カナダトップクラスの品質を誇る高級ベルギーチョコレート「ベルナルド・カラボー」。1911年ベルギーで創業し、現在は本拠地をカナダのアルバータ州カルガリー市に置いています。チョコレート作り最適な最高級の原料は、創業地のベルギーから取り寄せ、世界一の腕を持つカラボー氏が一粒一粒心をこめ、こだわりと独創性で作り上げた最高級チョコレートです。 モーツァルト~ザ・ベスト・オブ・クラシカル~ ~ザ・ベスト・オブ・クラシカル~【大作曲家シリーズ・ヨーロッパ直輸入盤】(収録時間:75分余)―【アイネクライネ・ナハトムジーク】―1)第1楽章 アレグロ2)第2楽章 ロマンス:アンダンテ3)第3楽章 メヌエット:アルグレット4)第4楽章 ロンド:アレグロ―【交響曲第40番ト短調より】―5)モルト・アレグロ6)メヌエット・アレグレット7)交響曲第29番イ長調より アレグロ・モデラート8)ディベルテイメント二長調より「メヌエット」9)トルコ行進曲10「フィガロの結婚」序曲11)ピアノ協奏曲21番「エルヴィラ・マディガン」より アンダンテ12)交響曲第35番二長調「ハフナー」より メヌエット13)ピアノ協奏曲第20番二短調より ロマンス14)フルート協奏曲第2番二長調より アレグロ1)~4)、7) *カメラータ・ラバセンシス *指揮:アレクサンダーフォン・ピタミック5)、6) *モーツアルト・フェスティバル・オーケストラ *指揮:リチャード・エドリンガー8) *チャンバー・オーケストラ・チボー・バーガ *指揮:チボー・バーガ9) *ピアノ:シルヴィア・カポヴァ10) *ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 *指揮:アルフレッド・シュルツ11)、12) *モーツアルト・フェスティバル・オーケストラ *指揮:アルベルト・リッツィオ13) *ミュンヘン交響楽団 *指揮:アルベルト・リッツィオ14) *モーツアルト・フェスティバル・オーケストラ *指揮:アルベルト・リッツィオ ■ピアノソロめだめカンタービレの世界
2007.02.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 何を買いましたか?
- ブラックフライデー 覚え書き
- (2025-11-27 15:30:04)
-
-
-

- ワンピース・ドレス
- ベルーナから、ベロア素材の紺・緑の…
- (2025-11-11 23:54:10)
-
-
-
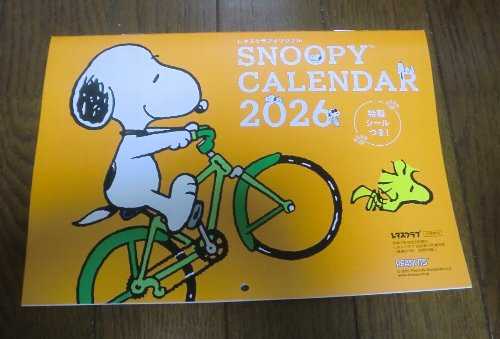
- 雑誌・本の豪華付録
- レタスクラブ SNOOPYカレンダー2026
- (2025-11-26 03:48:49)
-