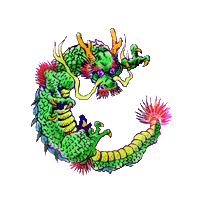PR
カレンダー
八尾空港ランウェイ2… m-cyanさん
何年ぶりの50キロ代… funafunafufuさん
取り寄せグルメ自炊… ベルバンさん
お笑いブログ さる… こーじ2002さん
戦場の薔薇 ジュンちゃん9392さん
パンダちゃん日記 釜山茂吉さん
珍国際の書斎 珍国際さん
IBBQ(井原バーベキュ… IBBQさん
熊野の楽しい縁起物… 平八工房さん
コメント新着
「初心忘するべからず」入学式や結婚式などでよく聞く言葉です。「始めたときの、真剣な気持ちを忘れるな。」といった意味でよく使われています。
しかし、「初心忘するべからず」について、今読んでいる本に、興味深いことが書いてありました。
著書名は"「葉隠」の叡智"で、著者名は、小池喜明氏です。 講談社現代新書から出版されています。その興味深い場所は、P22 にありました。
===引用開始===
世阿弥は、その壮年期の著作『風姿花伝』で、青春期の一時的、一回的な美しさを「時分の花」、芸により鍛えあげられた美しさを「まことの花」と呼び、単なる身体的な美にすぎぬ前者を後者と錯覚する青年期の慢心を「初心」と規定した。初心とは悪い意味なのである。そして、この初心の語が「初心忘るべからず」などという熟語・標語として登場してくるのは、彼の晩年の『花鏡』においてである。たとえば、「是非の初心を忘るべからず」「時々<じじ>の初心を忘るべからず」「老後の初心を忘るべからず」などとしてである。
===引用終了===
要するに、初心というのは、単なる身体的な美にすぎぬ青春期の一時的一回的な美しさを、芸により鍛えあげられた美しさと錯覚する青年期の慢心ということらしい。
グーグルで検索してみると、熊本学園大学付属高等学校 学校長 坂口 潮氏の入学式の祝辞の中に次のような文章がありました。
何事であれ、努力を続けられるのは、まず、そのものを好きになることから始まる。そして、その気持から発した初心を大切に生き続ける事が決定的に重要であると思う。「初心忘るべからず」と言う。志したときの意気込みや謙虚さを失わないようにしよう、とか、習い始めたときの純真な気持を忘れるなということである。
この言葉が能(能楽)の大成者として有名な世阿弥(推定一三六三~一四四三)の言葉であること、そして彼が、この言葉で言いたかった意味が、今言ったような今日普通に使われているものとは全く違っていたことを、最近、私は知った。周知のように世阿弥は、北山殿(金閣寺)で有名な足利義満の時代の人で、「風姿花伝(花伝書)」がよく知られているが、この言葉は「花鏡」という伝書(能について自分の考えや経験を伝えるためにまとめて書いたもの)の中に出てくる。彼にとっての初心とは、初めて失敗や試練から学んだ心得とでも言うようなものであった。だから、この言葉の本当の意味は、これまでの失敗や試練をどう乗り越え切り抜けてきたのか、それをよく考え忘れないことが、やがては次の成功につながるということなのである。試練といっても何も大げさな苦難の事態だけでなく、何か新しいことであれば、それはすべて試練である。即ち、初心とは新しいことに対処する際の方法や、試練を乗り越えていく戦略なのであった。世阿弥は「失敗や試練の経験の無いものは、ついには本当の成功はおぼつかない」と言いたかったのである。これが、この言葉の本義であった。
===引用終了===
やはり、ダイエット ドラゴンは、「初心忘するべからず」の意味をまちがえて覚えていたようです。
でも、ひょっとすると、『世阿弥が考えた「初心忘するべからず」と、現代の日本語としての「初心忘するべからず」とは、意味の違う言葉である。』というのが、正解なのかもしれません。
だけど、日本語って難しいですね。日本語の 初心
者ではないつもりなんですが。
-
エコポイントに気をつけろ!! 2009年05月13日 コメント(1)
-
ダエイット ドゴラン の たぼしいう ねし… 2009年05月09日
-
ペプシのCMには、赤い服を着たサンタは、… 2008年12月21日
キーワードサーチ
フリーページ
カテゴリ
カテゴリ未分類
(30)Javaによるオブジェクト指向プログラミング
(2)Androidプログラマーへの道
(1)3Dレンダリングに挑戦
(1)本日のスウィーツ(また太ってしまいそう)
(7)LinuxMonkeyでubuntu
(3)エレクトロニクス骨董屋
(2)なんだこりゃ写真館
(18)ヒミツのオハナシ
(71)食べ物の話
(59)こんなとこ 行ってきました
(25)こんな はなし 知っていますか
(39)CD DVD 借りた 返した
(8)ダイエット
(88)パソコン
(7)快適PALM環境
(1)PICで電子工作
(4)妄想です
(9)やっぱりハードロックが好き
(2)情報処理技術者試験
(2)マジです
(9)誰か教えてください
(7)Wikipediaで調べてみました!
(6)本日読了
(17)一番欲しい物
(5)インターネットセキュリティソフト観察日記
(2)最近のお気に入り
(22)落語
(12)フリーソフトで快適環境
(5)V型八気筒エンジン
(1)ウォーキング動物園
(10)グーグルアース動物園
(1)怒っているんだぞ!
(22)オッサンの知恵袋
(2)CDコレクション
(5)32ビットプロセッサV850で遊ぶ
(2)Turbolinux事始め
(2)もう一度、食べたいあの味
(2)大人の科学
(3)Safari(Appleのタブブラウザ)を使う
(2)dsPIC解体新書
(1)骨董屋 飢龍(ダイエットドラゴン)
(2)DS lite
(3)英会話 始めました
(4)CASIO QV-2300UX
(3)緊急連絡
(1)GYAO[ギャオ]
(1)YOUTUBE(ユーチューブ)
(1)Windows7 テストルーム
(1)計算しよう!そうしよう!
(4)iPhoneプログラミング
(4)・2025年10月
・2025年09月
・2025年07月