カテゴリ: カテゴリ未分類
今日のまとめ
1. 中国では薬は主に病院で処方される
2. 薬価統制があり価格改定は頻繁に行なわれる
3. 新薬開発コストは大変低い
4. 中国の製薬業界は零細企業が乱立している
中国の病院ならびに薬局事情
中国の病院は政府によって第一種から第三種、さらにその他の4種類に分類されています。このうち一番規模の大きいのは第三種で普通、大学病院のような教育施設に付随しています。第二種病院は地方都市の総合病院などです。この第二種病院に限って民営化が許可されています。さらに第一種というカテゴリーがあるのですが、これは特定疾病分野に特化した専門病院などです。第一種病院の特徴は予算規模が大きく専門医も沢山抱えている点です。
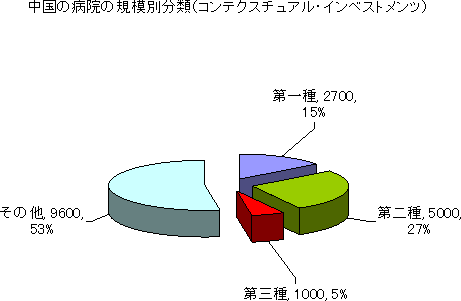
中国では米国のように医薬分業にはなっておらず処方薬については病院内の薬局で購入するのが一般的です。上のグラフの第二種病院だけが現在民営化を許されており、民間企業の病院が現れ始めていますが今のところ大部分の病院は国有です。それらの国有病院において薬が処方される際、その病院の承認リストに載っている薬に限って処方してよいことになっています。それぞれの病院が承認リストを作成するにあたっては労働社会保障省(MLSS)が選んだ薬のカタログの中からそれぞれの地方政府が独自の承認リストを作成するという方式が取られています。MLSSのカタログに収録される薬はティア1とティア2に分類され、ティア1に分類された薬は必ず地方政府の承認リストに含まれることが義務づけられています。さらにティア1に分類された薬は100%保険で払い戻しが効き、患者の自己負担はありません。ティア2に分類された薬は地方政府の裁量で承認リストに載せるか載せないかを独自に判断することが出来ます。ティア2に分類された薬は80~90%保険が利き、差額が患者の自己負担になります。このことは中国で処方薬を製造している製薬会社にとってMLSSのカタログに収録されるということが売上伸長の為にたいへん重要になることを意味します。しかし実際にはどの薬がカタログに採用されて、どの薬が落選するかは運・不運による面が多く、製薬会社にとって不確実性が高いと言えるでしょう。さて、処方薬ではなく店頭(OTC)薬に関してみると、こちらの方は主に薬局で買われてゆきます。中国人は軽い症状なら病院へ行かず薬局で店頭薬を買って済ませてしまう人が多いです。中国の薬局は零細企業が多く市場はたいへん細分化されています。
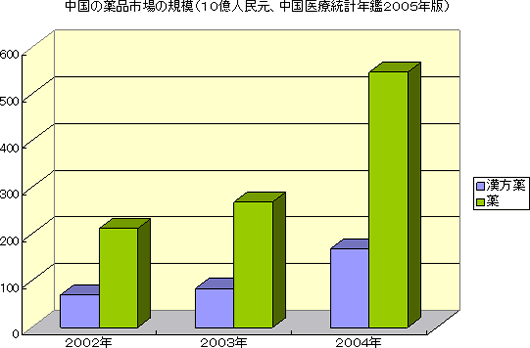
中国には昔から漢方薬が存在することは皆さんもご承知だと思いますが中国では漢方薬は西洋薬と全く分け隔てなくカタログに採用され、病院で処方されています。漢方薬は中国国内で消費される全ての薬の中で約30%程度を占めており、今後もこの比率は安定的に推移すると考えられます。
製薬業界の監督当局
中国の製薬業界を監督しているのはSFDA(China State Food & Drug Administration)です。中国国内で薬を製造したり販売したりするためにはSFDAから承認を受けることが必要となります。新薬はSFDAから承認されることが必要ですが、ひとたび承認されて売り出された薬は5年間モニタリング・ピリオド(監視期間)が義務付けられます。この5年間の間は政府がその新薬が安全であるかどうかなどを観察するために設けられた期間です。重要な点としてはひとたび或る新薬がモニタリング・ピリオドに入ると全く同様の薬効を持つと思われる類似薬に関しては新薬承認申請書類を受け付けないし、外国の製薬会社の薬の輸入承認や中国国内における生産も受け付けないという点です。つまりモニタリング・ピリオドは言葉を替えて言えば独占販売許可期間であるという風に考えても良いでしょう。薬の製造に関する規定としてはSFDAが承認した品質基準(GMA=Good Manufacturing Practice)をクリアした工場でのみ生産が許されます。
薬価統制について
一括購入
地方政府はその管轄下にある病院の薬を仕入れるに際して競争入札で大量買付けするケースがあります。この入札で決められた落札価格がその年の実質的なカタログ定価になります。この定価は1年間有効です。製薬会社としてはこれらの地方政府ごとの応札事務を代理店に任せるわけにはゆきません。代理店販売網に加えて自前の営業組織を維持する必要があるのはこのためです。
新薬開発
中国国内で新薬を開発する際の典型的な研究開発費用はひとつの新薬あたり約590万ドル程度であると言われています。これは米国の平均的新薬開発費用(8億ドル)に比べると大変低い数字です。これは製薬会社の研究スタッフの給与水準が米国のそれの10分の1以下であること、さらに臨床試験に要する費用が安いことなどがその主な理由です。
零細製薬会社の乱立
中国の製薬業界は歴史的に新規参入が比較的容易であったことなどから2004年末の時点で4700社もの企業が乱立しています。従って比較的小さい市場のパイを沢山の会社が奪い合っている構図になっています。中国で最大級の製薬会社でも国際的な比較で見るとその業容は大変貧弱です。このことは今後中国の製薬業界は統合の嵐に晒されることを暗示していると思われます。実際に企業の買収のみならず商品群の買収は頻繁に起こっており、買収による成長を標榜する企業は市場のパイそのものの成長率より遥かに早いペースで急成長しています。
医療サービス業界の不正腐敗の粛清
近年中国の医療サービス業界は医療機器の購入や薬品の一括購入に際するわいろなどいろいろな不正腐敗がはびこっていました。中国政府はこの事態を重く見て営業倫理の粛清に乗り出しました。その結果、去年から今年にかけてはヘルスケア・セクター全体で営業活動が一時的に止まったりするなどの影響が出ました。この粛清は一応峠を越えたように見えますがまだ終わったと決まったわけではありません。一時的な営業の停滞はこのセクターの業績に対する不透明感を増し、その結果として薬品株や医療機器メーカーの株はどちらかというと敬遠されてきたと言えます。
1. 中国では薬は主に病院で処方される
2. 薬価統制があり価格改定は頻繁に行なわれる
3. 新薬開発コストは大変低い
4. 中国の製薬業界は零細企業が乱立している
中国の病院ならびに薬局事情
中国の病院は政府によって第一種から第三種、さらにその他の4種類に分類されています。このうち一番規模の大きいのは第三種で普通、大学病院のような教育施設に付随しています。第二種病院は地方都市の総合病院などです。この第二種病院に限って民営化が許可されています。さらに第一種というカテゴリーがあるのですが、これは特定疾病分野に特化した専門病院などです。第一種病院の特徴は予算規模が大きく専門医も沢山抱えている点です。
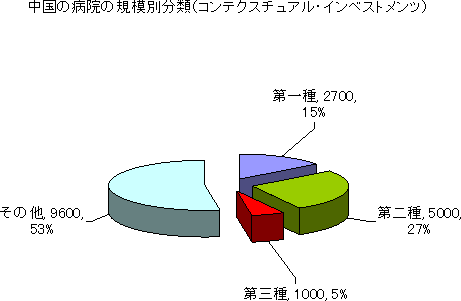
中国では米国のように医薬分業にはなっておらず処方薬については病院内の薬局で購入するのが一般的です。上のグラフの第二種病院だけが現在民営化を許されており、民間企業の病院が現れ始めていますが今のところ大部分の病院は国有です。それらの国有病院において薬が処方される際、その病院の承認リストに載っている薬に限って処方してよいことになっています。それぞれの病院が承認リストを作成するにあたっては労働社会保障省(MLSS)が選んだ薬のカタログの中からそれぞれの地方政府が独自の承認リストを作成するという方式が取られています。MLSSのカタログに収録される薬はティア1とティア2に分類され、ティア1に分類された薬は必ず地方政府の承認リストに含まれることが義務づけられています。さらにティア1に分類された薬は100%保険で払い戻しが効き、患者の自己負担はありません。ティア2に分類された薬は地方政府の裁量で承認リストに載せるか載せないかを独自に判断することが出来ます。ティア2に分類された薬は80~90%保険が利き、差額が患者の自己負担になります。このことは中国で処方薬を製造している製薬会社にとってMLSSのカタログに収録されるということが売上伸長の為にたいへん重要になることを意味します。しかし実際にはどの薬がカタログに採用されて、どの薬が落選するかは運・不運による面が多く、製薬会社にとって不確実性が高いと言えるでしょう。さて、処方薬ではなく店頭(OTC)薬に関してみると、こちらの方は主に薬局で買われてゆきます。中国人は軽い症状なら病院へ行かず薬局で店頭薬を買って済ませてしまう人が多いです。中国の薬局は零細企業が多く市場はたいへん細分化されています。
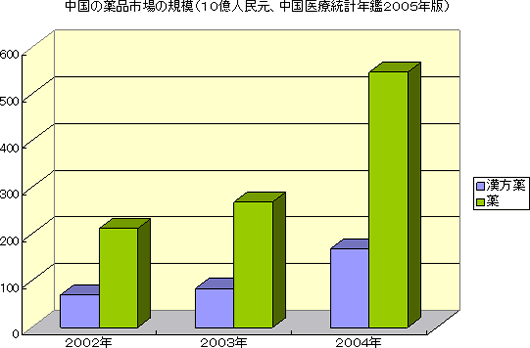
中国には昔から漢方薬が存在することは皆さんもご承知だと思いますが中国では漢方薬は西洋薬と全く分け隔てなくカタログに採用され、病院で処方されています。漢方薬は中国国内で消費される全ての薬の中で約30%程度を占めており、今後もこの比率は安定的に推移すると考えられます。
製薬業界の監督当局
中国の製薬業界を監督しているのはSFDA(China State Food & Drug Administration)です。中国国内で薬を製造したり販売したりするためにはSFDAから承認を受けることが必要となります。新薬はSFDAから承認されることが必要ですが、ひとたび承認されて売り出された薬は5年間モニタリング・ピリオド(監視期間)が義務付けられます。この5年間の間は政府がその新薬が安全であるかどうかなどを観察するために設けられた期間です。重要な点としてはひとたび或る新薬がモニタリング・ピリオドに入ると全く同様の薬効を持つと思われる類似薬に関しては新薬承認申請書類を受け付けないし、外国の製薬会社の薬の輸入承認や中国国内における生産も受け付けないという点です。つまりモニタリング・ピリオドは言葉を替えて言えば独占販売許可期間であるという風に考えても良いでしょう。薬の製造に関する規定としてはSFDAが承認した品質基準(GMA=Good Manufacturing Practice)をクリアした工場でのみ生産が許されます。
薬価統制について
一括購入
地方政府はその管轄下にある病院の薬を仕入れるに際して競争入札で大量買付けするケースがあります。この入札で決められた落札価格がその年の実質的なカタログ定価になります。この定価は1年間有効です。製薬会社としてはこれらの地方政府ごとの応札事務を代理店に任せるわけにはゆきません。代理店販売網に加えて自前の営業組織を維持する必要があるのはこのためです。
新薬開発
中国国内で新薬を開発する際の典型的な研究開発費用はひとつの新薬あたり約590万ドル程度であると言われています。これは米国の平均的新薬開発費用(8億ドル)に比べると大変低い数字です。これは製薬会社の研究スタッフの給与水準が米国のそれの10分の1以下であること、さらに臨床試験に要する費用が安いことなどがその主な理由です。
零細製薬会社の乱立
中国の製薬業界は歴史的に新規参入が比較的容易であったことなどから2004年末の時点で4700社もの企業が乱立しています。従って比較的小さい市場のパイを沢山の会社が奪い合っている構図になっています。中国で最大級の製薬会社でも国際的な比較で見るとその業容は大変貧弱です。このことは今後中国の製薬業界は統合の嵐に晒されることを暗示していると思われます。実際に企業の買収のみならず商品群の買収は頻繁に起こっており、買収による成長を標榜する企業は市場のパイそのものの成長率より遥かに早いペースで急成長しています。
医療サービス業界の不正腐敗の粛清
近年中国の医療サービス業界は医療機器の購入や薬品の一括購入に際するわいろなどいろいろな不正腐敗がはびこっていました。中国政府はこの事態を重く見て営業倫理の粛清に乗り出しました。その結果、去年から今年にかけてはヘルスケア・セクター全体で営業活動が一時的に止まったりするなどの影響が出ました。この粛清は一応峠を越えたように見えますがまだ終わったと決まったわけではありません。一時的な営業の停滞はこのセクターの業績に対する不透明感を増し、その結果として薬品株や医療機器メーカーの株はどちらかというと敬遠されてきたと言えます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月28日 16時09分38秒
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
© Rakuten Group, Inc.









