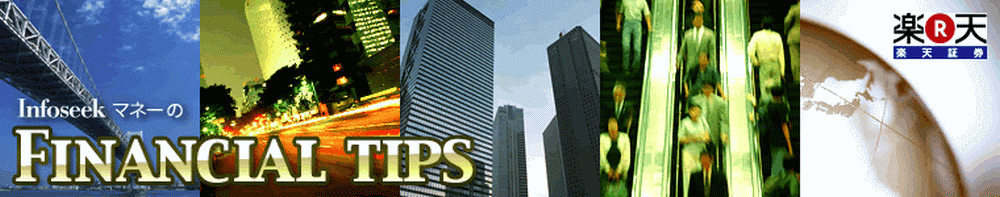カテゴリ: 投資信託
「金融商品取引法」の施行で、証券会社や銀行等は対応におおわらわとなっているといわれます。
金融商品取引法(金商法)は、株式や債券、投資信託はもとより為替先物取引、デリバティブ預金、変額年金保険など投資性のある幅広い金融商品を対象として、その販売・勧誘、投資運用、管理サービスなどに関する法律となるよう、現行の証券取引法を抜本的に改正したものです。法律は去年6月に成立していましたが、細かい規則などを整備して、この9月30日から施行されました。この金商法の施行によって投資信託の販売はどう変わるでしょうか、主な注目点を見てみましょう。
まず、金融商品の販売を行う証券会社や金融機関等は、顧客に対して今まで以上に十分な商品内容の説明を行うことが義務づけられました。投資信託などの広告や目論見書では、リスクと手数料について詳しい情報提供が求められます。とりわけリスクについて、従来は投資信託への投資は投資元本を割り込むリスクがありますと説明すればよかったのですが、今後は、そのリスクがどのようにして発生するのかという仕組みについても説明しなければなりません。また、手数料については、「手数料、報酬その他いかなる名称によるかを問わず顧客が支払うべき対価」と定義され、その合計額か上限額または計算方法を示すこととされました。投資信託の場合は、販売手数料、信託報酬、信託財産留保額、監査報酬、組入証券の売買手数料などあらゆる経費の開示が行われることになり、投資コストの全容の把握が容易になるでしょう。
さらに、顧客への目論見書の交付に関しては、上記のリスク情報や手数料の詳細その他顧客の判断に影響する重要な事項について、「顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をすること」が求められています。これは、説明義務を尽くしたかどうかの判断基準として「適合性の原則」が適用されることを意味しています。
適合性の原則とは、金融商品の売買にあたって金融商品取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという考え方を言います。証券取引法時代から、適合性の原則は販売会社が遵守しなければならない最も基本的なルールですが、金商法では適合性の原則の要件として、「金融商品取引契約を締結する目的」が追加されました。この要件に追加により、たとえば投資信託の知識があり資産も十分にもっていても、元本の安全性を目的にしている顧客にハイリスクハイリターンの商品を勧めることは適合性の原則に反することになります。
金商法は、また、証券会社や金融機関の販売勧誘ルールを強化しています。その中で注目される新しいルールは、個人顧客について「顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話・訪問により勧誘する行為」の禁止です。これは当初の規則案では、抵当証券・商品ファンド・金融先物取引に限定されていましたが、最終的なルールでは金融商品取引全般を対象とするとされました。
投資信託はいま、証券会社、銀行等金融機関それに郵便局も加わって熾烈な販売競争を繰り広げていますが、中には、顧客の意向に沿わないファンドを勧めたり、十分な説明をしないで販売しているケースもあると聞きます。金商法は投資家保護の徹底を図ることを目指して上記のようにルール強化を図っていますが、投資家としても、投資は自己責任であることをよく認識して、自分で十分理解できるまで説明を求めるという態度が必要です。
(金融アナリスト:新藤正悟)
金融商品取引法(金商法)は、株式や債券、投資信託はもとより為替先物取引、デリバティブ預金、変額年金保険など投資性のある幅広い金融商品を対象として、その販売・勧誘、投資運用、管理サービスなどに関する法律となるよう、現行の証券取引法を抜本的に改正したものです。法律は去年6月に成立していましたが、細かい規則などを整備して、この9月30日から施行されました。この金商法の施行によって投資信託の販売はどう変わるでしょうか、主な注目点を見てみましょう。
まず、金融商品の販売を行う証券会社や金融機関等は、顧客に対して今まで以上に十分な商品内容の説明を行うことが義務づけられました。投資信託などの広告や目論見書では、リスクと手数料について詳しい情報提供が求められます。とりわけリスクについて、従来は投資信託への投資は投資元本を割り込むリスクがありますと説明すればよかったのですが、今後は、そのリスクがどのようにして発生するのかという仕組みについても説明しなければなりません。また、手数料については、「手数料、報酬その他いかなる名称によるかを問わず顧客が支払うべき対価」と定義され、その合計額か上限額または計算方法を示すこととされました。投資信託の場合は、販売手数料、信託報酬、信託財産留保額、監査報酬、組入証券の売買手数料などあらゆる経費の開示が行われることになり、投資コストの全容の把握が容易になるでしょう。
さらに、顧客への目論見書の交付に関しては、上記のリスク情報や手数料の詳細その他顧客の判断に影響する重要な事項について、「顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法・程度による説明をすること」が求められています。これは、説明義務を尽くしたかどうかの判断基準として「適合性の原則」が適用されることを意味しています。
適合性の原則とは、金融商品の売買にあたって金融商品取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという考え方を言います。証券取引法時代から、適合性の原則は販売会社が遵守しなければならない最も基本的なルールですが、金商法では適合性の原則の要件として、「金融商品取引契約を締結する目的」が追加されました。この要件に追加により、たとえば投資信託の知識があり資産も十分にもっていても、元本の安全性を目的にしている顧客にハイリスクハイリターンの商品を勧めることは適合性の原則に反することになります。
金商法は、また、証券会社や金融機関の販売勧誘ルールを強化しています。その中で注目される新しいルールは、個人顧客について「顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話・訪問により勧誘する行為」の禁止です。これは当初の規則案では、抵当証券・商品ファンド・金融先物取引に限定されていましたが、最終的なルールでは金融商品取引全般を対象とするとされました。
投資信託はいま、証券会社、銀行等金融機関それに郵便局も加わって熾烈な販売競争を繰り広げていますが、中には、顧客の意向に沿わないファンドを勧めたり、十分な説明をしないで販売しているケースもあると聞きます。金商法は投資家保護の徹底を図ることを目指して上記のようにルール強化を図っていますが、投資家としても、投資は自己責任であることをよく認識して、自分で十分理解できるまで説明を求めるという態度が必要です。
(金融アナリスト:新藤正悟)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年10月04日 09時07分47秒
[投資信託] カテゴリの最新記事
-
クラスB受益証券の落とし穴 2007年10月26日
-
バイオバブルの終焉:ジーエヌアイの初値… 2007年09月27日
-
サブ・プライム問題で投資信託の人気は離… 2007年09月20日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
© Rakuten Group, Inc.