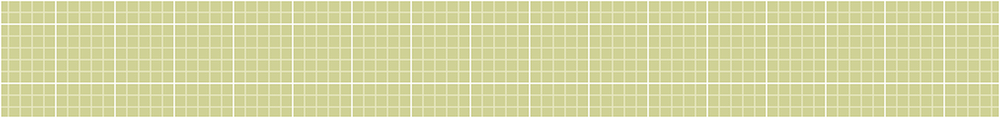2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010年08月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

ピアニスティックの源流をたどる その7 ツィンバロンとダルシマー
ピアニスティック、すなわちピアノらしい表現の源となったのは、ダルシマー音楽の発展形であり芸術昇華したパンタレオンの音楽であった・・・と、文章で書くのはやさしいが、そもそもダルシマー音楽とはどんなものだったのか。実はこの楽器はいにしえより世界中に広まっており、その音楽がどのようなものであったのか一つの例を挙げて語るのは不可能だ。だが、それらはロマ、すなわちジプシーたちが各地を転々とする中で、ある場所からある場所へ伝えたりされていた。また、ジプシーが居留した場所でそれらの音楽が発展する例がヨーロッパ各地で見られる。その中にはスペインのフラメンコ、ハンガリーのフォークロアがあるが、特にダルシマー音楽はハンガリーにおいて発展した。ダルシマーとは写真のように台形のボディーに金属製の弦が張り巡らされた構造で、大きさは様々である。ジプシーに好んで用いられた理由はやはりその携帯性であろう。それはヴァイオリンが彼らに好まれたのと同様である。ハンガリーにおけるジプシー音楽は深い叙情性と超絶技巧が特徴と言えるだろう。それはクラシック音楽の中でハンガリーのロマ音楽をモチーフにした作品・・・チャルダッシュ、ハンガリー舞曲、ハンガリー狂詩曲・・などなど・枚挙に暇がないが、これらの作品群にも表れている。それでは、実際にハンガリーのジプシー音楽におけるダルシマー演奏がどのようなものであったか聞いてみたいと思う。これはかなり「ピアニスティック」な部類に入るが、見かけはシンプルなこの楽器からこんな表現が生まれてくるのは驚異的である。ダルシマー演奏(Hungarian Concerto)つづいてツィンバロンである。この楽器はさらに発展して、大きさも大きく機構も複雑になっている。ピアノのようにダンパーペダルがついている。近代ではハンガリー民族音楽でよく用いられている。ダルシマーよりも表現が豊かだ。ハンガリーのジプシー歌曲をCsics? N?meth J?noの演奏で。ツィンバロン演奏(Hungarian Gipsy Song)ダルシマーと言う楽器はヨーロッパから東アジアまで広く行き渡っていた。所によってサントゥールとか楊琴などと呼ばれている。この写真は中国の楊琴(ヤンキン)である。横に日本人形が置いてあるのは単に博物館の管理人が東洋文化をよく理解していないだけで、この楽器が和楽器でもあったということではない。しかし日本にも伝わっていた可能性は十分にあると思う。いずれにせよこの楽器が世界中の音楽文化の運び手となっていたのは事実である。ダルシマーと似ているが、弦をはじくことで音を出す「プサルテリウム」という楽器がある。系図上はダルシマーの前の段階の筏チターから派生したものであるが、プサルテリウムはまもなくチターへと発展していったのであまり広まらなかったようだ。僕が見たことあるのはブリュッセルとゲッティンゲンの楽器博物館の計2台のみで、あまりお目にかかれるしろものではない。ダルシマーがピアノの先祖とされるのに対し、プサルテリウムはチェンバロの先祖とされている。
2010.08.07
コメント(2)
-

ピアニスティックの源流をたどる その6 Weissenfels
メルゼブルクの牧師にかくまわれていたパンタレオン・ヘーベンシュトライトはやがて自由の身となり1698年、ヴァイセンフェルスの王宮で音楽家およびダンサーとしての職を得ることとなった。ヴァイセンフェルスはメルゼブルクから約30キロ南、ナウムブルクから北東約10キロのところにある。ちょうどハレとヴァイセンフェルスを結ぶ直線の真ん中にメルゼブルクがある。町の中央には小高い丘があり、その丘の上に王宮が建っている、いわば城下町だ。このころからパンタレオン・ヘーベンシュトライトはツィンバロン奏者としての頭角をあらわし始めた。ライプツィヒやドレスデンで活動し、1705年にはフランスで演奏旅行し、パリで御前演奏を行った。この時ルイ14世からこの楽器の名前を「パンタレオン」と呼ぶように命ぜられたという。それから、パンタレオン・ヘーベンシュトライトはフランスやドイツなど各地を演奏してまわり、当時の音楽家や楽器製造家に衝撃を与えた。だれもがあんな演奏をしたい・・・とは思うがツィンバロンを彼のように演奏するのは普通の人間には至難の業であった。そこで、チェンバロのような鍵盤楽器にハンマーをくっつければ、もっと容易にあのような素晴らしい演奏ができるのではないか。この要望が、やがてピアノ発明の「母」となったのだ。ところで、ヴァイセンフェルスはハインリッヒ・シュッツが少年期を過ごした町でもある。ハインリッヒ・シュッツと言えば宗教曲やバロック愛好家には知られている作曲家で、J.S.バッハよりちょうど100年前に生まれたバロック初期の作曲家だ。ちょうど王宮の丘の麓のマルクトに面したあたりにハインリッヒ・シュッツ博物館がある。僕がこの町に着いたときは既に午後4時で、博物館に入館するにはぎりぎりの時間だった。王宮の博物館とシュッツ博物館とどちらにしようか迷ったが、結局シュッツ博物館に入ることにした。入場料1ユーロと、とても安い。内部は2部に分かれていて、右側はシュッツの生い立ちなどの説明、左側は楽器の展示と作品の紹介であった。年表などが展示されている右側の展示室はとりあえずさっと見て、左側の楽器の展示されている部屋に入る。すると、係員がCDをかけてくれる。このCDはシュッツの作品の演奏と、展示されてあるどの楽器が使用されているかという解説であった。その解説にしたがって見物するという仕組みだ。僕自身もそうであるが、シュッツと言えば声楽曲、宗教曲というイメージが強いのではなかろうか。少なくとも僕はそれしか聴いたことがなかった。だが、ここで聞いてみると意外に器楽曲もけっこうあるものなのだ。バロック初期であるから、現在使われていない楽器も中にはある。中でも、左写真の右側に写っている「ツィンク」という楽器はめったにみることはない。見た目には縦笛にトランペットのマウスピースをつけたような、シンプルで原始的な趣きのある楽器だ。だが、演奏を聴いてみると何とも澄んだ、バロックトランペットをさらに鋭くしたような音がする。こんな原始的な楽器からこんな音がするなんて信じられない。僕が興味深そうに「ツィンク」を眺めていると、係員の人が寄って来て、「この楽器、持ってきましょうか」と言い、奥の倉庫からなんと「ツィンク」を取り出してきた。手に持ってみるととても軽い。一応楽器分類上金管楽器ということになるのだろうけど、木製の管に皮を巻きつけた構造だった。係員に「ちょっと吹いてみてください」と言うと、「私は吹けないので、あなたがどうぞ」と言う。それではからずも「ツィンク」にチャレンジすることになった。なんとかトランペットの要領で吹こうとするが、ただ「ブー」という情けない音がするのみだ。それに、どの穴を押さえても全く音程が変化しない。これはどういうことなのだろうか。横で係員が何かニヤニヤしているが、いったいどうやって音を出すのだろう、この楽器。一度生で演奏しているところを目撃したいものである。こうしてパンタレオン・ヘーベンシュトライトの足跡を追ってみたのだが、見事なほどに彼は足跡を残していない。ドイツには彼の名前にちなんだ道の名前さえ全くないのである。しかし、こうして見ると彼の働いた場所はバロック音楽の中心でおのずとその影響は多々受けたであろう。同時にダンス音楽のエキスパートでもあったことからそのような折衷が彼独特の音楽を生み出したと言えるのかもしれない。
2010.08.07
コメント(1)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- Yes【イエス】ロンリーハート~ビッ…
- (2025-11-25 21:23:42)
-
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪新曲『ビリヤニ』初日売上…
- (2025-11-26 18:06:40)
-
-
-

- コーラス
- 町の文化祭で発表(11/10)
- (2025-11-26 21:03:53)
-