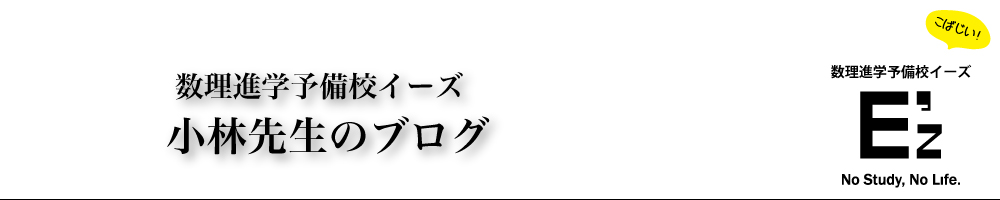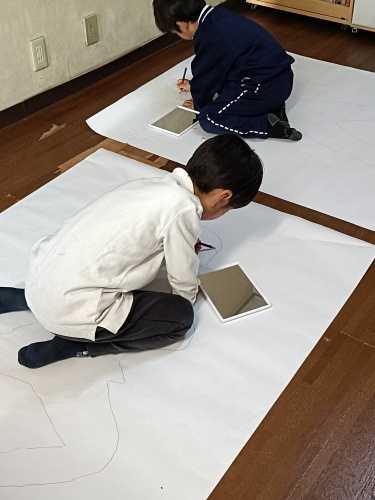2024年08月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
共テを時間内に終わらせるために
「時間がない!」どーも、そういう生き方はしたくないなぁと思っている小林です。共通テストの結果を生徒に聞くと、「時間が足りなくて、、、、」という話をよく聞く。「焦ると、焦ったところがボロボロで、、、」ってのも、同じくらいよく聞く。ゆえに、「どうしたらいいですかっっっ!!!!」と。そもそも、時間が足りない原因は何が考えられるのか。1、文章を読むスピードそのものが遅い(特に英語、国語)2、計算スピードが遅い(特に数学、化学)3、悩んでいる時間が長い(気づいていない子は多い)このあたりを答える子が多い。そして、ここで終わる。もう一歩先へ進んでみよう。1、なぜ文章を読むスピードが遅いのか →言葉・単語が難しくて、スムーズに読めない(単語力の欠如) →英語の場合、文構造をちゃんと理解して読めていない(読み直しが増える) (このタイプは、単語拾い読みでしか英文が読めていない) →単純に目を動かす速度が遅い →文脈など前の段落等の内容を覚えていられない(読み直しが増える) 2、なぜ計算スピードが遅いのか →四則演算が不慣れ →そもそも立式までが遅い(計算を始めるまでが遅い) →計算が合わなくてやり直すことが多い(計算ミスをよくする) →計算の工夫がない細分化していくとこのような詳細が出てくる。具体的にどう対策したらいいのか言えるところまで分析しないといけない。ちなみに、ここで出てきた分析内容は、時間をかけてできるようしていくタイプの対策がほとんどだ。単語力、語彙力はコツコツ身につける必要がある。英語の文構造はちゃんと丁寧に理解してから、スムーズにわかるように練習する必要がある。文脈を覚えつつ読むのも、意識しながらやる練習が必要。慣れないうちは、メモをうまく使いたい。四則演算も、計算ドリルみたいなもので慣らしたい。立式が遅いのは、問題の理解と、解法をちゃんと覚えているかによる。知っている段階から、覚えている段階に移っていないと立式は遅い。その他ケアレスミスは、普段から見つけていって減らしていきたい。ところが、3の「悩んでいる時間が長い」はどうか。立式が遅いこととも似ているが、考えてもわからない問題に悩んでいる子は多い。そもそも知識不足なのに、たくさん考えたら答えにたどり着けるかも、と考えてしまう。そんな問題、共テじゃほとんどないよ。生徒たちに悩みに悩んで時間をかけた問題ができたか聞くと、たいていできていない。全体の得点率を考えて、その1問に長時間割く意味はあるのだろうか。まとめると、共テを時間内に終わらせるには、①時間がかかっているところを詳細に分析して見つける②悩んでいる時間を減らす③知識の習得度合いを上げる④余計なミスを減らすこの取り組み方になる。「焦って解く」なんて、微塵も入らない。意味ないからね。素早く先へ解き進めていくことと、焦って解くことは、まったくもって別物だからね。焦ると解けた問題も間違うからね。今自分のできる最高速度を伸ばす訓練をして、その結果、時間内に終わる状況を作りに行こう。焦るには、まだまだまだまだまだまだ早いのだから。
August 28, 2024
コメント(0)
-
時間がかかること=時間をかけろってこと。
夏くらいになると、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、と焦りだす子がいる。焦ること自体は悪いことではない。でも、それで計画を変更したり、中途半端になってしまうのはよろしくない。現役生だろうが、浪人生だろうが、やることってのは、変わらなくて、勉強の内容・段階が、最初の理解の段階なのか、基礎レベルを定着させる段階なのか、応用レベルまで理解する段階なのか、応用レベルを定着させる段階なのか、演習して、知識ではない部分に慣れる段階なのか、どこにいるかで、やることが変わるだけだ。最初の段階とか、定着させる段階は、どうしても時間がかかる。時間がかかると、遅いんじゃないかと思い始めて、焦って、違うことをやりだす人がいる。まてまて。最初の理解をちゃんとしておかないと、その後の定着は悪い。周りがいつまでに○○をやらないとやばい、とか言ってさらに煽ってくるけど、それはそれ。正しく、丁寧にやろう。雑にしても、後で結局やり直すことになるぞ。スタートのタイミングが異なれば、現役生だろうが、浪人生だろうが、時期はずれるでしょうよ。時間がかかることは、きちんと時間かけていこう。丁寧にやっていけば、2周目、3周目は明らかに早くなるから。1周目から雑だと、2周目も3周目も、時間がかかることになるぞ。どうしていいかわからないときは、ちゃんとわかる人に相談しようね。
August 25, 2024
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1