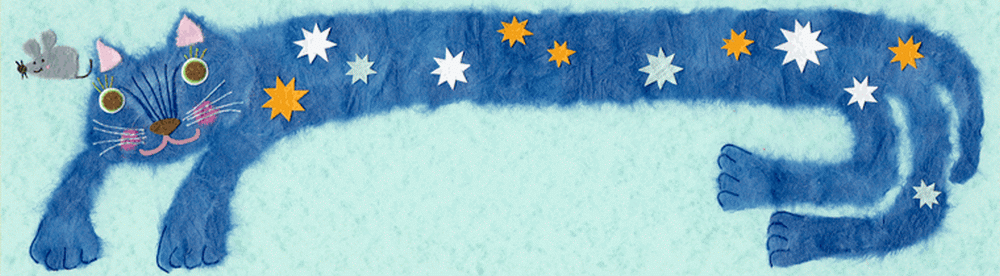いろいろあって休みがちなので、いまだに単衣が完成せず
それでも徐々に終わりが見えてきたので、気が早いですが次は着倒すための木綿着物を仕立てたいと思っています
とはいえ、片貝木綿などは初心者の私が縫うにはもったいないので、お手軽価格で私好みのものを探してみました


そんな時に見つけた目から鱗の素敵な情報
私も初めて聞いた方法でした。
転載OKだそうなので、着物好き和裁好きの皆さんにもお知らせすべく紹介しますね
↓ ↓ ↓
現在生産されている着物はたいてい3丈2尺(約12m)程度ありますが、昔の
反物や綿の着尺の場合は3丈(11.4m)程度しかない場合があり、最近の背の高い
体格のいい方の場合はそれでは身丈がでないことが多々あります。今日はそんな
丈の短い反物を着物に仕立てる裏技を解説させて頂ます。
インターネットで検索してみたんですが、おはしょりの部分に別生地を入れる
というような方法を紹介しているものが多いんですが、これは正確におはしょ
りの隠れる部分に生地を入れるのが意外と難しく、出来上がりもあまりきれい
ではありません。
そこで今回の方法です。これを読む方にお願いなんですが、インターネットで
検索してもほんとに全く出てこなかったので、もしブログなどをお持ちの方が
いらっしゃればこの方法を転載して広めていただけたら嬉しいです。お問い合わ
せがかなり多いので恐らく困っている方も多いと思いますので...。
なお、こちらの方に転載の連絡や図の使用の連絡をしていただく必要はござい
ません。ご自由にお使いください。
まずはこの図をご覧ください。

通常の裁ち方が上の方の図です。身頃や袖を取った後、衽と衿の部分を左右で
取って仕立てるのが通常のお仕立方法ですが、身丈が足りない場合の裁ち方は
少々違います。
身丈が足りない場合は反物の左右で衽を取ってしまいます。そうすると図のよう
に主衿の部分と掛衿を同じ長さで取らざるを得ませんが、主衿の部分を真ん中から
裁ってしまってその間に別生地を入れるんです。
その別生地の上にはもちろん掛衿が重ねられますので別生地を継いでいる部分は
全く見えなくなります。これで意外とかなりの生地の節約になりますので3丈しか
ない着物でもある程度の身丈まで出すことが出来ます。
また、最近の若い方は体格がよく、手足の長いモデル体型ですので反物の幅が狭い
場合、裄がでないことが多々あります。
裄は肩幅と袖幅を足したもので、それぞれ反物の幅の長さから縫い代を引いたも
のが限界の長さですので例えば36cmしかない反物ですと縫い代が2cmとして
34cm×2=68cmまでしか裄が出ません。これだとちょっと背の高い方は足りなく
なってくると思います。
そういう場合は生地を前幅から取って肩口のところに継いでしまいます。前幅は
24cm~26cmしか使いませんので、36cm程度の幅の反物でも10cm程度の幅が余る
ことになりますので、その余った10cmを肩口のところに継いで裄を出します。
残念ながら柄によってはこの方法は使えませんが(もちろん気にしない方なら
構いません)、縦縞やごく細かい柄の小紋などでしたらほとんどわからないよう
にお仕立てできます。
なかなかこの方法はインターネットでも紹介されていないので、ブログなどを
お持ちの方はぜひ掲載して頂いて、この方法が広まって短い反物をお持ちで
お悩みの方の助けになれば嬉しいです。
昔のウールはもちろん、綿の着尺で水通ししたら3丈にも足りなくなってしまった
ということはよくありますので、お悩みの方はきっと多いと思います。
↑ ↑ ↑
どうぞみなさんのブログでも紹介して
この方法を広めましょう。^^
-
単衣制作中 2025年01月04日
-
昨年(2024年)に間に合った振袖 (笑) 2025年01月03日
-
振袖を縫うぞ!! 2020年01月25日