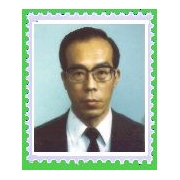カテゴリ: 美術・博物・展示
今日は、お天気が悪かったのと、少し風邪気味だったため、外出はせず、パソコンデータのバックアップ、書類の整理などで過ごした。
3日前に行った「大坂歌舞伎展」について紹介する。この展覧会は、大阪市立歴史博物館で10月1日から11月23日まで開催されている。
歌舞伎は、1609年出雲の阿国が京の四条河原で演じたのが最初とされている。その後、江戸と大坂でそれぞれ発達し、江戸の荒事(あらごと)に対し、大坂の和事(わごと)と言われる。展示の内容は、大坂歌舞伎の役者絵を中心に歌舞伎の歴史を紹介したもので、下記の3つの部門に分かれていた。
1.歌舞伎への情熱
2.一大ライバルー璃寛と芝翫
3.ライバルの世代交代
1.では、当時の庶民が歌舞伎に熱中した模様が紹介されていた。役者の似顔絵は、江戸では1750年頃から、大坂では1780頃から売られるようになる。これらの絵や資料を集めてスクラップブックのように貼った貼込帳というものが、マニアの間で作られていたそうだ。立派な収容箱付きで、展示では、吉野五運、歌賀家狂人鬼哉、木村黙老のものが紹介されていた。
役者絵本も作られるようになる。江戸の役者はキリっとした顔であったのに対し、大坂のは当初は漫画的な似顔絵であった。松好斎半兵衛画の役者絵26点と大坂と江戸の役者絵本数点が展示されていた。
次に人気を得たのは、流光斎如圭(1777-1809活動)。流光斎の画いた狂諺図巻、梨園書画、中村座劇場内部、大坂歌舞伎役者大首絵などは立派である。また、嵐雛助 嵐三五郎などの歌舞伎役者の生いたちを内容とした役者一代記といったものも作られた。役者のまわりには、贔屓筋で作るサークルができ、役者は、法要とか快気祝などの節目に、摺物という立派な浮世絵を作って贔屓連中に配布した。
璃寛と芝翫は、共演したことはなかったが、ファンの勧めで、二人は遂に1821年夏、一大ライバルの夢の競演を行うことに同意した。しかし、契約直後の9月、璃寛が急逝したため、結局実現しなかった。
3.では、璃寛死後の大坂歌舞伎の推移を紹介している。しばらくは、芝翫の独壇場が5年ほど続くが、やがて2代目璃寛が台頭する。芝翫も代を市川蝦十郎に譲る。こうして大坂歌舞伎のブームは幕末まで続く。
贔屓連中の層も厚くなり、役者絵も大量に作られた。山村友五郎は、歌舞伎の舞踊を専門に振り付けするようになり、山村流初代となる。
なお、今回の浮世絵はじめ展示品の多くは、大英博物館からの借り物であることを知り、寂しい気持ちになった。外国の美術館が持ち帰ったため、きれいなまま保存されたとも言えるが、元々日本のものが日本では見られないというのは残念なことである。里帰りの美術品を見る度に思うことである。
写真は、左:入場券、右:北州画、芝翫の加藤正清と璃寛の惟喬親王

阪神は、横浜にサヨナラ勝ちで、今シーズン最終戦を飾り、下柳が15勝目を上げ最多勝を決めた。ヤクルトが中日に勝ったため、3位とのゲーム差が0.5となり、熾烈な3位争いが最後まで続く気配だ。

3日前に行った「大坂歌舞伎展」について紹介する。この展覧会は、大阪市立歴史博物館で10月1日から11月23日まで開催されている。
歌舞伎は、1609年出雲の阿国が京の四条河原で演じたのが最初とされている。その後、江戸と大坂でそれぞれ発達し、江戸の荒事(あらごと)に対し、大坂の和事(わごと)と言われる。展示の内容は、大坂歌舞伎の役者絵を中心に歌舞伎の歴史を紹介したもので、下記の3つの部門に分かれていた。
1.歌舞伎への情熱
2.一大ライバルー璃寛と芝翫
3.ライバルの世代交代
1.では、当時の庶民が歌舞伎に熱中した模様が紹介されていた。役者の似顔絵は、江戸では1750年頃から、大坂では1780頃から売られるようになる。これらの絵や資料を集めてスクラップブックのように貼った貼込帳というものが、マニアの間で作られていたそうだ。立派な収容箱付きで、展示では、吉野五運、歌賀家狂人鬼哉、木村黙老のものが紹介されていた。
役者絵本も作られるようになる。江戸の役者はキリっとした顔であったのに対し、大坂のは当初は漫画的な似顔絵であった。松好斎半兵衛画の役者絵26点と大坂と江戸の役者絵本数点が展示されていた。
次に人気を得たのは、流光斎如圭(1777-1809活動)。流光斎の画いた狂諺図巻、梨園書画、中村座劇場内部、大坂歌舞伎役者大首絵などは立派である。また、嵐雛助 嵐三五郎などの歌舞伎役者の生いたちを内容とした役者一代記といったものも作られた。役者のまわりには、贔屓筋で作るサークルができ、役者は、法要とか快気祝などの節目に、摺物という立派な浮世絵を作って贔屓連中に配布した。
璃寛と芝翫は、共演したことはなかったが、ファンの勧めで、二人は遂に1821年夏、一大ライバルの夢の競演を行うことに同意した。しかし、契約直後の9月、璃寛が急逝したため、結局実現しなかった。
3.では、璃寛死後の大坂歌舞伎の推移を紹介している。しばらくは、芝翫の独壇場が5年ほど続くが、やがて2代目璃寛が台頭する。芝翫も代を市川蝦十郎に譲る。こうして大坂歌舞伎のブームは幕末まで続く。
贔屓連中の層も厚くなり、役者絵も大量に作られた。山村友五郎は、歌舞伎の舞踊を専門に振り付けするようになり、山村流初代となる。
なお、今回の浮世絵はじめ展示品の多くは、大英博物館からの借り物であることを知り、寂しい気持ちになった。外国の美術館が持ち帰ったため、きれいなまま保存されたとも言えるが、元々日本のものが日本では見られないというのは残念なことである。里帰りの美術品を見る度に思うことである。
写真は、左:入場券、右:北州画、芝翫の加藤正清と璃寛の惟喬親王

阪神は、横浜にサヨナラ勝ちで、今シーズン最終戦を飾り、下柳が15勝目を上げ最多勝を決めた。ヤクルトが中日に勝ったため、3位とのゲーム差が0.5となり、熾烈な3位争いが最後まで続く気配だ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[美術・博物・展示] カテゴリの最新記事
-
淀屋研究会の講演を聞く 2025.10.04
-
「北欧のあかり展」を見る 2025.04.01
-
大阪城梅林が見頃 2025.03.02
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Category
Calendar
電動リクライニング…
 New!
ビッグジョン7777さん
New!
ビッグジョン7777さん
我流達人のHP garyu33さん
自分が好きな曲 関空快速1649さん
DIARY OF A.K 歳… kissakemさん
千波の隠居の日記 中澤 照道さん
 New!
ビッグジョン7777さん
New!
ビッグジョン7777さん我流達人のHP garyu33さん
自分が好きな曲 関空快速1649さん
DIARY OF A.K 歳… kissakemさん
千波の隠居の日記 中澤 照道さん
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.