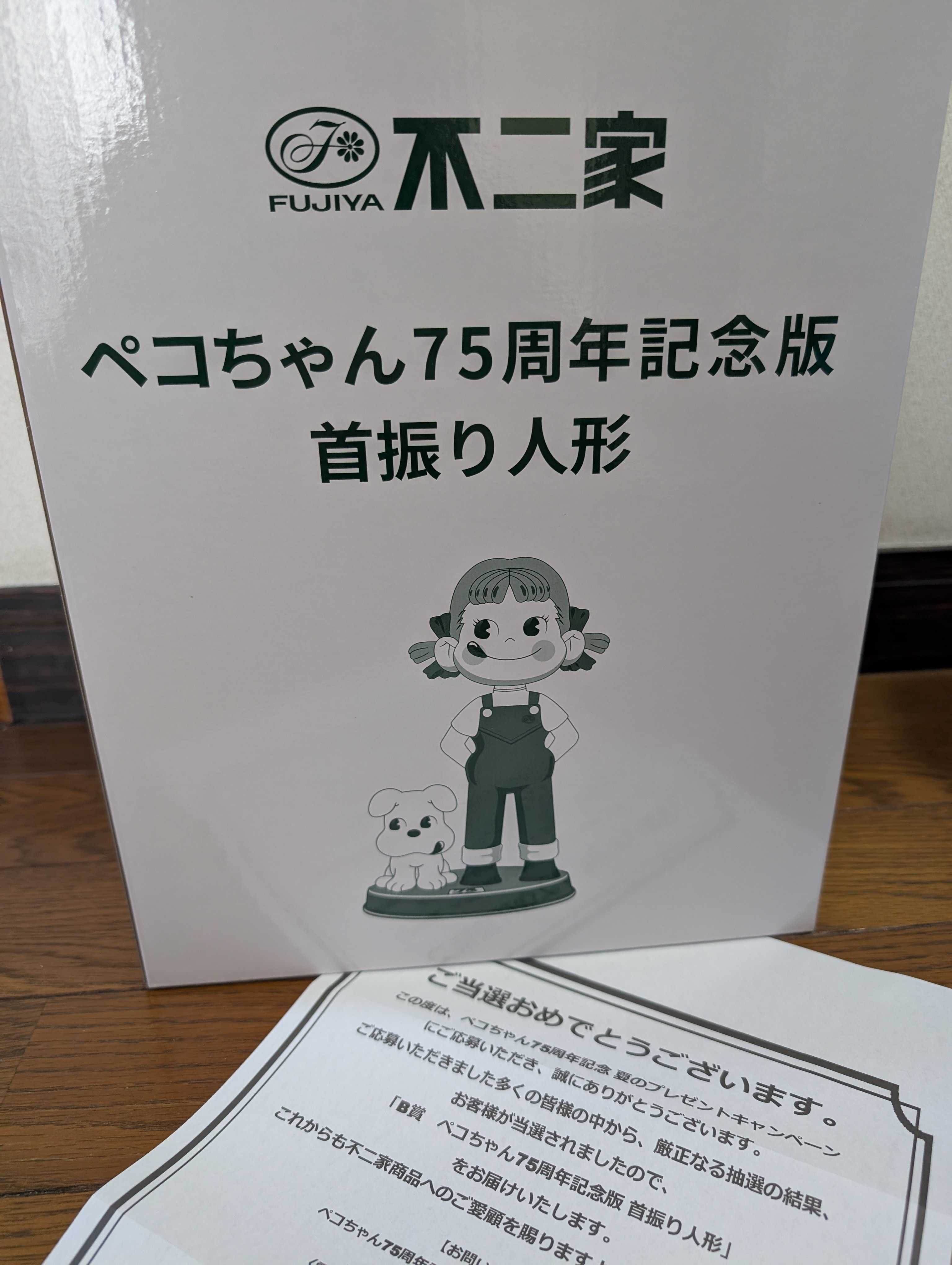2008年09月の記事
全52件 (52件中 1-50件目)
-
条件づけ
(生と覚醒(めざめ)のコメンタリー1:p40:クリシュナムルティ:大野純一(訳):春秋社)より引用『条件づけ自体が、問題、葛藤を生み出す』
2008年09月30日
コメント(0)
-
身心学道
(現代文/正法眼蔵1:p76:道元:河出書房新社)より引用(自分勝手訳)『身体をもって学びなさい 身体まるごとで学道に励みなさい やがて身は学道そのものになるであろう この身が全世界である この身が生き死にそのものである 身体そのものが全世界のあらわれ 身体そのものが生死の流れのあらわれである この身をまるごと学道に投げ出しなさい』
2008年09月30日
コメント(0)
-
変化
(智恵からの創造:p294:クリシュナムルティ:星雲社)より引用(自分勝手訳)『変化にとって大切なのは、変化したいという願望が終止することです。だけどそれは、現状に満足する、という意味ではありません。 変化する目標を持たないことです。 こうなりたいという目標を持った変化をあきらめることです。 そのときはじめて、予期せぬ変化がふいに起こる可能性がひらけるでしょう』
2008年09月30日
コメント(0)
-
戯論(けろん)の消滅というめでたい縁起のことわり
(クリシュナムルティの瞑想録:p195:大野純一(訳):サンマーク文庫)より引用『意見あるいは意見を調べてみるといった事柄は、真実とは無縁である。多種多様な意見の是非をめぐって果てしない論議を戦わせることはできる。しかし意見というものはどれほどよいもので、筋道立っていても、それは真実ではない。 意見は常にその当人の属している文化や受けた教育、知識によって偏り、色づけられている。それゆえ精神を意見や、あれこれの他人に対する見方、印象、あるいは書物、観念といったもので充満させておいてよいものだろうか。なぜ精神を空しくしておかないのだろうか。精神があっけらかんとしていてはじめて、はっきりとものが見えるようになるのである。』
2008年09月30日
コメント(2)
-
天使あらため石ころ
「ぼくは天使だ」と言ってたら、弟子に「言ってること、わかりますけど、ぜんぜんイメージちがいますよ」と言われた。「じゃあ何?」と尋ねたら、「石ころ、ですね」 なるほど…道元さんと同じようなこと言ってるじゃないか…道元さんの表現だと「土壁瓦礫」かな(ちょっと文脈はちがってそうだけど)…弟子は道元さんなんて読んでない(たぶん)はずなのに…さすが弟子、するどい!
2008年09月30日
コメント(4)
-
際限のない報酬
(エックハルト説教集:p43:田島照久(編訳):岩波文庫)より引用(一部変作)『この命において人が苦しむものすべてには終わりがあるが、それに対して神が与える報酬は永遠である』
2008年09月29日
コメント(0)
-
奇跡
「この世界」には「はんぶん人間はんぶん天使」として生まれるんだろう。
2008年09月29日
コメント(0)
-
出来事への恋
物や言葉に恋するように、出来事に恋をしてしまえば…出来事は瞬間ごとに起こってて、これはちょっとついてくのがたいへんだけど…たぶん瞬間ごとであってしかもひとつ(永遠)としてとらえる、といったようなところ…
2008年09月29日
コメント(0)
-
天使
どういうわけか天国にさまよいこんだ天使は、はじめのうちは何もかも物珍しくってきれいでうれしくて、ねぇ見て見てって、はしゃぎ回ってるんだけど、そのうちまわりに天使がひとりもいないことに気づいてさみしくなっちゃうんだ。でも、ひとりぼっちでも天国は鮮やかで驚きに満ちているので、まあいいやひとりでも、ってつぶやいてるんだけど、やっぱりさみしいんだ。 天国はだだっ広くて、天使の人口密度というか、天使密度はかなり低いんだろうね。 そんなふうな年月がすぎて、きれいなだけではさみしくてもうそろそろへこたれそうになったころ、天国のほうでもさすがにかわいそうに思ってくれたのか天のめぐみというか、もうひとり、天使を目の前に送ってくれるんだ。もうひとりぼっちじゃない、ふたりならだいじょうぶ。こうなったらもうこっちのもんだよね。 とまあ、ちょっとできすぎみたいなおはなしなんだけど。
2008年09月28日
コメント(5)
-
「悩み」
「悩みがない」という状況のひとつとして、頭では(理屈では)「自分はこれこれのことで悩んでいる」というのが理解できるけれども、「悩んでいる」という実感がないので、言わば「悩みがない」状態、というのがあるだろう。
2008年09月28日
コメント(0)
-
智恵
(智恵からの創造:p292:クリシュナムルティ:星雲社)より引用(略式勝手訳)『私たちは、ねたみ、恐れ、非難、比較とともに生きているのですが、それではダメだからこんなふうに生きるのはやめよう、と思ったところでうまくはゆきません。 自分がねたみ、恐れ、非難し、比較していることを、しかたがないことだとか悪いことだとか判断せず、ただ見るならば、ふと、ねたみや恐れの感情が遠ざかっていて、ねたみや恐れの感情の遠ざかりとともに、ねたみや恐れそのものの質が、まったく異なったものになっていることに気づくでしょう』
2008年09月28日
コメント(0)
-
橋本治
『人はなぜ「美しい」がわかるのか:橋本治:ちくま新書』 さすが、現代日本のインテリ、養老孟司さん、高橋源一郎さんが勧めるだけあって、橋本治さんはめちゃくちゃインテリですね。「枕草子」と「徒然草」との関係なんてあたり、感心しますよ。
2008年09月24日
コメント(0)
-
「思考がやむ」
『瞑想:クリシュナムルティ:中川吉晴(訳):星雲社』序文の「この本によせて」にて、「瞑想とは、思考がやむことです」と書かれている。とすると、この本は、「思考がやむ」ことをめぐって書かれた本ということになるのだろう…
2008年09月24日
コメント(2)
-
身心は化け物
身心はとらえようによっては、穏便な表現を使わなければ、化け物である。
2008年09月24日
コメント(0)
-
「音が聞こえている」
「目を閉じて耳を澄ませる」というのは、どことなく、「息を止めて何か(特定の物)をじっと見つめる」というのに似ている。「息を止めてじっと見つめる」という実験がひとつのきっかけとなって「全体がただ、くっきりとはっきりと、きれいに見えている」状態が起こる可能性があるのだとしたら、同様に、「目を閉じて耳を澄ませる」という実験がひとつのきっかけとなって「(目は開いていても)全体がただ、くっきりとはっきりと、静かに聞こえている」状態が起こる可能性があるのかもしれない。
2008年09月24日
コメント(3)
-
「何も無い」
「じゃあ今から考えないでいよう」「どうやって?」「何を見てもきれい、だとか、いわゆる幸福感、だとかも無い」「そんなのおもしろくないよ。きれいじゃなくちゃ」「きれいでしあわせならそれでいいけど、そのことと何も無いのとは別なんだ」「わからないな」「何も無くって、静か…」「どうやって?」「考えなければいい。さあ…」「たんに考えないって、目は関係ない、って言うけど…」 あれ? 言葉が届いてないよ。「聞こえてる?」「ん?…ああ…考えちゃだめだよ…」 なるほど…「目の変化」を伴わない「何も無い静けさ」というのも、たしかにあるんだろうけど…でも…やっぱり…そんなの…
2008年09月24日
コメント(1)
-
「この世界のひろがり」への気づき
こちら側「思考・感情・知覚」だけでなく、「この世界のひろがり」(空っぽの、際限ない容器)に気づいてないと、脳はうまく機能しなくなる。
2008年09月21日
コメント(0)
-
瞑想
(瞑想:p21:クリシュナムルティ:中川吉晴(訳):星雲社)より引用『瞑想の美しさというのは 自分がどこにいるのか どこへむかっているのか その果てになにがあるのか けっしてわからない ということです』
2008年09月21日
コメント(0)
-
エックハルト
(エックハルト説教集:p42:田島照久(編訳):岩波文庫)より引用『人々はよくわたしに向かって、「どうぞ、わたしのためにとりなし祈って下さい」という。そのときわたしは、「なぜあなたがたは外に向ってもとめていくのか。なぜ、あなたがたは自分自身の内にとどまって、あなたがた自身の宝をつかまないのか。あなたがたはすべての真理をあなたがたの内に本質的にもっているではないか」と心の内でつぶやくのである。』
2008年09月21日
コメント(0)
-
夢
ひさしぶりに夢を見ました雪の中見知らぬ人とふたり立ちつくしていました雪はゆったり落ちてきますこの雪…永遠みたいだねそうね…永遠に降りつづくみたいそれにしてもきれいな雪…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2008年09月21日
コメント(0)
-
人はひとつの光の内に住むことができる
(エックハルト説教集:p29:田島照久(編訳):岩波文庫)より引用(略式勝手訳)『神がすべてを創造したときの今も、わたしが話しているこの今も、神のうちでは等しい今であり、ひとつの今にほかならない。 人はひとつの光の内に住むことができる。光の内では、すべての物事が本質的なあり方で存在している。それゆえに、光の内に住む人は未来に起こるであろういかなる出来事にもふりまわされない。 その人はつねに新たな絶えることのないひとつの今に住んでいるからである。』
2008年09月20日
コメント(0)
-
弟子に聞く
(正法眼蔵随聞記:道元:p53:水野弥穂子(訳):ちくま学芸文庫)より引用『仏道を学ぶ人は、師匠の所へ行って法を聞くときは、よくよく究極のところまで聞き、何度も重ねて聞いて、心に疑いのないようにすべきである。問うべきを問わず、言うべきを言わないで過ごしたなら、それは自分の損であろう。 師匠というものは、必ず弟子の質問を待って発言するものである。だから、わかったつもりでやってきたことでも、何度も尋ねて疑いのないようにすべきである。師匠のほうでも、弟子によくよくわかったかとたずねて、言って聞かすべきである。』 師匠と弟子ってこういう関係なら、1年前ならいざしらず、今となっては(半分くらいは)ぼくはぴのきおさんの弟子だな。 ぴのきおさんは、ぼくが質問したら答えてくれるけど、ぼくにとって何が疑問かぴのきおさんには見当もつかないので(「スクリーン」や「瞑想」ということばがわからないなんて、見当もつかなかったらしい)、ぼくのほうで疑問なことを、きちんと聞かなくてはならないのでしょうね。
2008年09月19日
コメント(2)
-
「これ」と「瞑想」と「感覚」との関係
このことは、弟子の説明(ただし、弟子のほうは、師匠に説明した自覚はほとんどなし)により、やっと、はっきりしたことです。「この世界のひろがり」の中で知覚は起こっている。「この世界のひろがり」は、言葉にすれば、存在の入れ物である。「この世界のひろがり」そのものは「空」である。「瞑想」は知覚(こちら側)ではなく、「この世界のひろがり」(全体)で起こる。
2008年09月19日
コメント(0)
-
雨の音
降ってくる音が聞こえてるわけじゃない(暴風雨なら聞こえるのかな?)雨粒が地上の物たちに降りそそぎ ぶつかる 音ぶつかった場所からその無数の場所から出会いの音たちが ひろがってゆく
2008年09月19日
コメント(0)
-
瞑想
(瞑想:p96:クリシュナムルティ:中川吉晴(訳):星雲社)より引用『瞑想には 始まりも 終わりもありません 瞑想においては 成功や失敗というものはなく なにかをつみあげることも 放棄することもありません 瞑想は 終わりのない運動です』
2008年09月17日
コメント(4)
-
瞑想法(音)
(112の瞑想カード(説明書):p20:経典(スートラ)より引用:田中ぱるば(訳/編):市民出版社)より引用『音のただ中で音に浴する。たとえば絶え間ない滝の音の中で。 あるいは耳に指を入れ、音の中の音を聴く。』そういえば弟子も、「大音量で音楽を聴く」とか言ってたな。
2008年09月17日
コメント(0)
-
なぜかは知らないが、これでいい
(人はなぜ「美しい」がわかるのか:橋本治:p242:ちくま新書)より引用『「なぜそうなったか?」を考えて意味があるのは、その後の結果に納得がいかない時だけです。「なぜかは知らないが、これはこれでそういうもんだから、これでいい」と思っている時は、「なぜそうなったか?」はどうでもいい問いなのです。』
2008年09月16日
コメント(0)
-
瞑想法(ぴのきお風)
コーヒー豆を挽くとき、目を閉じて、音だけに集中して、その音をガリガリとかって言葉に訳さず、頭の中を音だけでいっぱいにする。
2008年09月16日
コメント(0)
-
悟り
師匠「「これ」が「瞑想」なら、ひょっとして、私たちは悟ったんだろうか?」弟子「え? 悟り? 師匠、なに寝ぼけたこと言ってるんですか! ただ目が覚めただけでしょ」師匠「なるほど、それもそうだねぇ…」(注:「私たちは悟った」という表現がもう、ダメですね。そもそも(わかってもないことを、さもわかったかのようにしゃべってみますが)『人間が(部分が)悟るのではなく、世界が(全体が)悟る』のでしょうから…)
2008年09月16日
コメント(6)
-
愛情
(人はなぜ「美しい」がわかるのか:橋本治:p231/232:ちくま新書)より引用(一部(だいぶ?)変作)『相手に干渉せずに見守り、その相手の中に「なにか」が育つのを待つというのが愛情です。 人を愛するとき、もしかして一番大切なのは、「愛おしさの中の素っ気なさ(干渉しないこと)」かな、とも思います。ある種の素っ気なさがないと、相手への依存(執着)が起こります。 また、素っ気ないだけだと、「愛情」として機能しません。だからこそ、愛おしさと素っ気なさの配合は重要だなと思うのです。』
2008年09月15日
コメント(2)
-
姪「タラマイカ語やウンドゥル語には、絶対に訳す事のできない言葉があるらしいです。私の知り得ない想像も出来ない〈何か〉ということなのかな。
訳す事のできない言葉とは何なんだろうか不思議だね。」 タラマイカ国にしかなく、日本で暮らしておれば生まれてこのかた、見たことも聞いたこともないような〈何か〉については日本語に訳せない、といったことだと思うけど。 それはたとえば、立場を逆にしてとらえてみると、タラマイカ国にテレビがなく、テレビに関する情報がまったくタラマイカ国には流れない(見たことも聞いたこともない)なら、生まれてこのかたタラマイカ国から出たことのない人にとっては、「テレビ」というのは「知り得ない想像も出来ない〈何か〉」だから、「テレビ」という日本語はタラマイカ語に「訳す事のできない言葉」なんだと思う。 でもまあ、「訳す事のできない言葉」といったって、その言葉が指し示している「物事・現象・状況・状態」を提出してくれれば、なんとかそれなりに訳せる(だいたいの感じが伝わる)んだとも思うけどね。 そもそも「言葉」と「言葉の指し示しているもの」は別なんだから、自国語であってさえ、出来事や現象を言語化するときには、(自国語だと習慣化してて気づきにくいだけで)かなり無理矢理、ある種の翻訳をしているのだろうしね。
2008年09月15日
コメント(0)
-

I'M NOT O.K.
クイズです。これは姪のデザインしたTシャツですが、Tシャツに印字されている「I'M NOT O.K.」の出所は何でしょう?姪とこのことについて前もって話はしていませんでしたが、常識がないと言われているぼくは、一発でわかりました。
2008年09月15日
コメント(2)
-
「これ」=「瞑想」
師匠「それにしても瞑想って、何のことなんだろうね?」弟子「「瞑想」って「これ」のことでしょ」師匠「ん? 何言ってるんだよ?…あれ?…おおお!!、ああそうか、そういうことだったのか!!!」…「瞑想」って「この世界にいること」「この世界で起こっていること」「これ」のことだったんですね!
2008年09月15日
コメント(0)
-
瞑想
(瞑想:p58:クリシュナムルティ:中川吉晴(訳):星雲社)より引用『瞑想は ひらかれた場のなかでおこります そこには 秘密が入りこむ余地はまったくありません あらゆるものが むきだしのまま くっきりと あらわになっています』
2008年09月15日
コメント(0)
-
此処がごくらく
にんげんて 死ぬでしょだからつかのま生きてしまうときのことはぜんぶ せつなくて いとおしくてじんるいて 死ぬでしょだからなにかしら 残そうとしてもぜんぶ 消えて むなしくてにんげんじんるいいのちぜんぶ つかのまの ゆめじんせいは 生きてるからってにんげんを とくべつな死に場所へ運んでくれやしない生きておれば 生き場所で 起こるのはただ ただむねが ときめいて身とか こころとかしろく とけていまここでいまここの永遠の喜び 見せてくれるばかり
2008年09月14日
コメント(0)
-
思考 瞑想 自由
(瞑想:p26:クリシュナムルティ:中川吉晴(訳):星雲社)より引用『思考が花ひらき そして 枯れはてるときにのみ 瞑想は意味をもちます 思考が花ひらくのは 自由のなかだけです』
2008年09月14日
コメント(0)
-
cocoro
こころは 果てしなく自由だけど 選べないだから 楽しもう と、おもうどこまでも 自由に(ぴのきお27さんが書いたものですが、何度読み返しても気分がよくなるので、勝手に引用させてもらいました。ぴのきお27さん、あしからず)
2008年09月13日
コメント(0)
-

ことの次第(映画)
2008年09月12日
コメント(0)
-
世界の移動
お釈迦さん「シャーリプトラよ、おいで おいで こっちにおいでよ」シャーリプトラ…いつのまにやら移動して…シャーリプトラ「ああ…これは…」(仏典より引用:略式勝手訳)
2008年09月12日
コメント(2)
-
身心学道
(現代文/正法眼蔵1:p73:道元:河出書房新社)より引用(略式勝手訳)『いろんな質問をしたり、それに答えたりして学びましょう。 だけどこのとき、一方通行でのやりとりが起こっているのではありません。質問したり、それに答えたりするのは、一方的な出来事ではないのです。 質問側であろうが、答える側であろうが、自分も学び、相手も学んでいるのです。学道とはそうしたものです。』
2008年09月11日
コメント(0)
-
「母には僕の顔が見えてて、僕は鏡を使わないと僕の顔が見えません。見えてるものが違うのにこころは分けられないのですか?」
お母さんが君の顔を見る目は、お母さん個人の脳につながっているお母さん個人の目だよね。 そして、君が鏡に映った君の顔を見る目、(もしくは)鏡がなくて君の顔が見えない君の目は、君個人の脳につながっている君自身の目だ。 別の脳につながってる目だから、見えてるものが違う。君とお母さんとは、別のものが目に映っている。 だけどね、「こころ」はね、たとえて言えば、「鏡を使って君自身の顔を見ている君と、鏡を見ている君をいとおしく思いつつ見ているお母さんと、ふたりのいる空間」なんだよ。 その空間は、君の脳がわざわざ情景を思い浮かべようが浮かべまいが、(誰のものでもない)「こころ」としてひろがってるんだ。「こころ」は誰かの持ち物じゃないんだよ。 じつは、ここはむずかしいところで、どうしてむずかしいかと言うと、ふつうは、学校とかで先生も友だちも、君の心と友だちの心を分けて考えるからなんだけど、もちろん、そういう考え方も日常生活では必要なんだけど、生きることのすばらしさを感じるためには、(ここでの言葉遣いでの)「こころ」に触れなくちゃ、せっかく生まれてきたのに、もったいないんだなぁ…(何を伝えたいか、わかりにくいだろうなぁ…ごめんね) ということで、君とお母さんがいる空間全体が「こころ」なんだ。 君とお母さんとでは目が違うから、見えてるものが違う。それはそうなんだけど、「こころ」はふたりのいる空間なんだから、ひとつしかないんだよ。 わかりにくいかもしれないけど、師匠としては、せいいっぱいしゃべってみたよ。 質問、ありがとうね。
2008年09月09日
コメント(2)
-
鍵
「あなたの目の変化」の鍵は誰が持っているのかというと、あなたが持っている。あなたの心の奥深くに潜ってゆけば、ふと、そこにある。 あなたの外側の世界を探したって見つからない。見つけたと思っても、それは、あなたのための鍵ではない。「目の変化」が起こった「ある人の鍵」が外側の世界に落ちていたとしたって、その鍵はその人のための鍵でしかなく、その鍵であなたの扉はひらかない。 だから、心の奥深くに潜ってゆく、自分に向いた方法を探すことになる。
2008年09月09日
コメント(0)
-
「心は脳じゃないのか?」(弟子の息子さんの質問)への返事
脳というのはね、ひとりにひとつ、与えられてるんだよ。だからね、君の脳と、お母さんの脳は別なんだ。 だけどね、心はそんなふうに分けられないんだよ。君がたったいま見たり聞いたり考えたり(たとえば「心は脳じゃないのか?」って考えたりね)してるとき、お母さんもまた、君といっしょにいて、君といっしょに見たり聞いたり、君といっしょになって「心は脳じゃないのか?」ってことについて考えたりしてる。そんなふうに、君とお母さんがいっしょになって見てる世界、いっしょになって考えてる世界が、たったいまの君の心だし、お母さんの心なんだよ。 そしてね、驚いたことに、この世には、たったひとつの世界のひろがりしかないのかもしれないんだ。だとしたら、もしかしたら、心はたったひとつしかないのかもしれないね。
2008年09月08日
コメント(4)
-
身心学道
(現代文/正法眼蔵1:p71/73:道元:河出書房新社)より引用(略式勝手訳)『まず全自然、これこそ心である。 全自然は、見る者によって見られるところは同じではない。 にもかかわらず、心とは、みな等しく、全自然である。 心とは、ただ想念であり作用である。 世界がなければ、意識も情念の作用も起こらない。 だから人の心の一念一念は、一つ一つの世界と言うほかない。 心は遠くにあるのでも、近くにあるのでもない。 心は、始めがあり終わりがあるという概念には入りきれない。 学道には視野を広げるということがある。 しかしその広さは長さでは測れない。』
2008年09月07日
コメント(1)
-
縁
夜中にまちがい電話で起こされて、目が覚めてしまい、こうしてブログを読んだり書いたりしているうち、ああそうか、まちがい電話なんかじゃなかったんだ、こういう縁なんだな…
2008年09月07日
コメント(0)
-
ゴキブリ
(人はなぜ「美しい」がわかるのか:橋本治:p37:ちくま新書)より引用(一部変作)『ゴキブリをじっと見ないで逃げだしたり叩きつぶしたりする人に、ゴキブリの美しさはわからない』
2008年09月06日
コメント(4)
-
8月のゲスト
この世は舞台であり、ぼくらはみな、知ってか知らずか、俳優兼観客なんだろう。せっかくこの世という舞台に生まれたんだから、身を起こし、心を起こし、生き生きと、軽やかに、ときにはゆるやかに、ときにはすばやく、ダンスを踊ってみましょう。じつのところ、生きている間のぼくらの体の動きは、知ってか知らずか、ずっとダンスしている状態でもあるのでしょう。(8月のこと研のゲストは、ヒップホップダンスとミュージカル「エリザベート」(なんと、せりふを全部覚えているそうです!)と般若心経と線香に興味のある若者でした。ゲストと弟子は線香の話で盛りあがっておりましたが、師匠はついてゆけませんでした…)
2008年09月06日
コメント(0)
-
身心学道
(現代文/正法眼蔵1:p70/71:道元:河出書房新社)より引用(一部変作)『仏道というものは、学んで得られるものではないと疑っているうちは学び得ません。そんなふうに疑うならば仏道は遙かに遠いものになってしまいます。 心をもって学び、身をもって学びなさい。 思考を重ねて学び、あるいは思考を離れて学びなさい。 世間的な思考を離れた思考によって学びなさい。 修行の成果が現われないときでも諦めずに習い行うことによって、いつのまにやら修行の成果が現われ、どのように凡庸な者にでも伝わるのです。それは遙か古来からの法則であります。』
2008年09月04日
コメント(2)
-

散歩
2008年09月03日
コメント(1)
-

∞(無限大):小
きょうはじめて、携帯で撮った写真をパソコンに送る方法を、4年ほど前、子供が携帯がほしいというのでついでに買ったときの取扱説明書を引っぱりだしてきて調べました。こんなに簡単にできるのだったなんて! 知ってたらずいぶん前から使ってたでしょうね。まあ、たいがい常識知らずですから、いまさらそんなことも知らなかったのか、というほどの感慨もないのですが…
2008年09月02日
コメント(0)
全52件 (52件中 1-50件目)