カテゴリ: アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
GYAO!は3月でサービスを終了しましたが、
ドキュメンタリーだけれど、
映像がとても美しく、
ブルースを育んだアメリカ南部の風土や、
ゆったりした時間の流れを体感できた佳作。
登場するミュージシャンは年寄りばかりなのに、
歌や演奏はほんとうに素晴らしく、
ブルース好きならいつまででも見てられる内容でした。
ゴスペルも取り上げられていましたし、
カントリー風の曲や8ビートの曲が演奏されるのも興味深かった。
ちなみに、この映画は、
カナダ人によって制作されている。
同じくGYAOでは、
「ランブル~音楽界を揺るがしたインディアンたち」
というドキュメンタリー映画も配信されていて、
こちらは米国音楽史における先住民の貢献を探る内容でしたが、
やはりカナダ人による作品でした。
米国音楽に関するドキュメンタリーなのに、
そうした映画を作るのは、
わたしは、
CBCとNetflixのドラマ「アンという名の少女」が、
米国側の事情で打ち切りになったと思っているのですが、
それと同じ背景を感じてしまいます。
つまり、
北米大陸の人種問題の歴史に向き合ってるのは、
アメリカには、いまだ人種間の分断があるということ。
プロテスタントの多いカナダと、
南部にラテン系カトリックの住民を抱える米国とでは、
政治的な姿勢も違うし、歴史的な差異もある。
被写体となる黒人や先住民も、
カナダの白人であればこそ心を開くのかもしれません。
◇
もうひとつGYAOで観たのは、
「ゴーギャン~タヒチ、楽園への旅」という映画。
もともとゴーギャンやルソーの絵画は、
ファンタジックでピースフルな雰囲気があって好きだった。
その異国趣味は、
ドビュッシーやサティの音楽にも通じてると感じてました。
しかし、当然ながら、
そこには植民地での支配/被支配の関係があるわけで、
たんに優雅なコロニアル趣味では済まされない面もある。
パリにいながら異国を想像しただけのルソーと、
実際に植民地まで行ったゴーギャンを比べても、
その暴力性には、だいぶ違いがあるのかもしれません。
◇
映画では、
本国フランスでの理解が得られずに、
タヒチへ渡ってサバイバルな生活に挑みながら、
画家としての成功も、現地妻の愛情も失って、
ふたたび本国へ戻るゴーギャンを悲劇的に描いていました。
けれど、
ほんとうに目を向けるべきなのは、
宗主国の白人が、本国の妻子を捨て置き、
植民地のポリネシアで幼い少女を現地妻とし、
エキゾチックな視線を向けていくことの暴力性ですよね。
それをポスコロ的な視点で描いたら、
まったく別の映画になってしまう気がします。
山田五郎のYoutubeチャンネルによれば、
ゴーギャンの発想は、
のちの「フォークロアアート」の先取であるとのこと。
しかし、その背景には、
やっぱり植民地主義的な暴力性があるわけです。
◇
カナダの白人と、
米国南部のラテン系の白人に差異があるのと同じく、
オランダ人の生真面目なプロテスタントだったゴッホに対して、
フランス人のゴーギャンは、
いわば罰当たりなカトリック信者だったわけで、
そこにはラテン気質の野獣的な奔放さがあった感じがします。

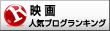

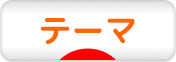
ドキュメンタリーだけれど、
映像がとても美しく、
ブルースを育んだアメリカ南部の風土や、
ゆったりした時間の流れを体感できた佳作。
登場するミュージシャンは年寄りばかりなのに、
歌や演奏はほんとうに素晴らしく、
ブルース好きならいつまででも見てられる内容でした。
ゴスペルも取り上げられていましたし、
カントリー風の曲や8ビートの曲が演奏されるのも興味深かった。
ちなみに、この映画は、
カナダ人によって制作されている。
同じくGYAOでは、
「ランブル~音楽界を揺るがしたインディアンたち」
というドキュメンタリー映画も配信されていて、
こちらは米国音楽史における先住民の貢献を探る内容でしたが、
やはりカナダ人による作品でした。
米国音楽に関するドキュメンタリーなのに、
そうした映画を作るのは、
わたしは、
CBCとNetflixのドラマ「アンという名の少女」が、
米国側の事情で打ち切りになったと思っているのですが、
それと同じ背景を感じてしまいます。
つまり、
北米大陸の人種問題の歴史に向き合ってるのは、
アメリカには、いまだ人種間の分断があるということ。
プロテスタントの多いカナダと、
南部にラテン系カトリックの住民を抱える米国とでは、
政治的な姿勢も違うし、歴史的な差異もある。
被写体となる黒人や先住民も、
カナダの白人であればこそ心を開くのかもしれません。
◇
もうひとつGYAOで観たのは、
「ゴーギャン~タヒチ、楽園への旅」という映画。
もともとゴーギャンやルソーの絵画は、
ファンタジックでピースフルな雰囲気があって好きだった。
その異国趣味は、
ドビュッシーやサティの音楽にも通じてると感じてました。
しかし、当然ながら、
そこには植民地での支配/被支配の関係があるわけで、
たんに優雅なコロニアル趣味では済まされない面もある。
パリにいながら異国を想像しただけのルソーと、
実際に植民地まで行ったゴーギャンを比べても、
その暴力性には、だいぶ違いがあるのかもしれません。
◇
映画では、
本国フランスでの理解が得られずに、
タヒチへ渡ってサバイバルな生活に挑みながら、
画家としての成功も、現地妻の愛情も失って、
ふたたび本国へ戻るゴーギャンを悲劇的に描いていました。
けれど、
ほんとうに目を向けるべきなのは、
宗主国の白人が、本国の妻子を捨て置き、
植民地のポリネシアで幼い少女を現地妻とし、
エキゾチックな視線を向けていくことの暴力性ですよね。
それをポスコロ的な視点で描いたら、
まったく別の映画になってしまう気がします。
山田五郎のYoutubeチャンネルによれば、
ゴーギャンの発想は、
のちの「フォークロアアート」の先取であるとのこと。
しかし、その背景には、
やっぱり植民地主義的な暴力性があるわけです。
◇
カナダの白人と、
米国南部のラテン系の白人に差異があるのと同じく、
オランダ人の生真面目なプロテスタントだったゴッホに対して、
フランス人のゴーギャンは、
いわば罰当たりなカトリック信者だったわけで、
そこにはラテン気質の野獣的な奔放さがあった感じがします。
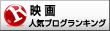

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.04.07 11:00:07
[アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。] カテゴリの最新記事
-
朝ドラ「花子とアン」総集編。村岡花子の… 2024.01.20
-
上白石萌音 ミュージカル「ジェーン・エア… 2022.05.09
-
NHK「アンという名の少女」シーズン4&上… 2022.03.07
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(237)テクノロジー・科学技術
(20)ドラマレビュー!
(303)NHK大河ドラマ
(66)NHK朝ドラ
(63)NHKよるドラ&ドラマ10
(38)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(241)メディア問題。
(46)音楽・映画・アート
(92)漫画・アニメ
(29)鬼滅の刃。
(14)岸辺露伴と小泉八雲。
(30)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(18)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)日本史・世界史
(29)東宝シンデレラ
(92)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(54)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(41)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(70)汝の名~三千円~舞いあがれ!
(16)トリリオン~ONE DAY~ゼンケツ!
(29)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!
(15)捜査一課長~恋マジ~あのクズ!
(42)「エルピス」の考察と分析。
(11)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(12)北斎と葛飾応為の画風。
(20)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(22)スポーツも見てる!
(43)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(12)パワハラ
(7)ドミトリー&ゴミ税
(40)夢日記&その他
(7)© Rakuten Group, Inc.









