テーマ: どんなテレビを見ました?(78078)
カテゴリ: プレバト俳句を添削ごと査定?!
熱帯魚アクリル越しのオーディション 夏空や石鯛掲ぐ父の遺影 夏日影水槽の下掻い潜る 夏の昼ペンギンの様に手を引かれ 鯱戯け尾ひれかみかみ南風 ゴンドウ鳴く水族館を出て白夜 夏のほかペンギンの飛ぶ大水槽
プレバト俳句。
お題は「水族館」。
フジモンにパクリ疑惑が浮上しています(笑)。
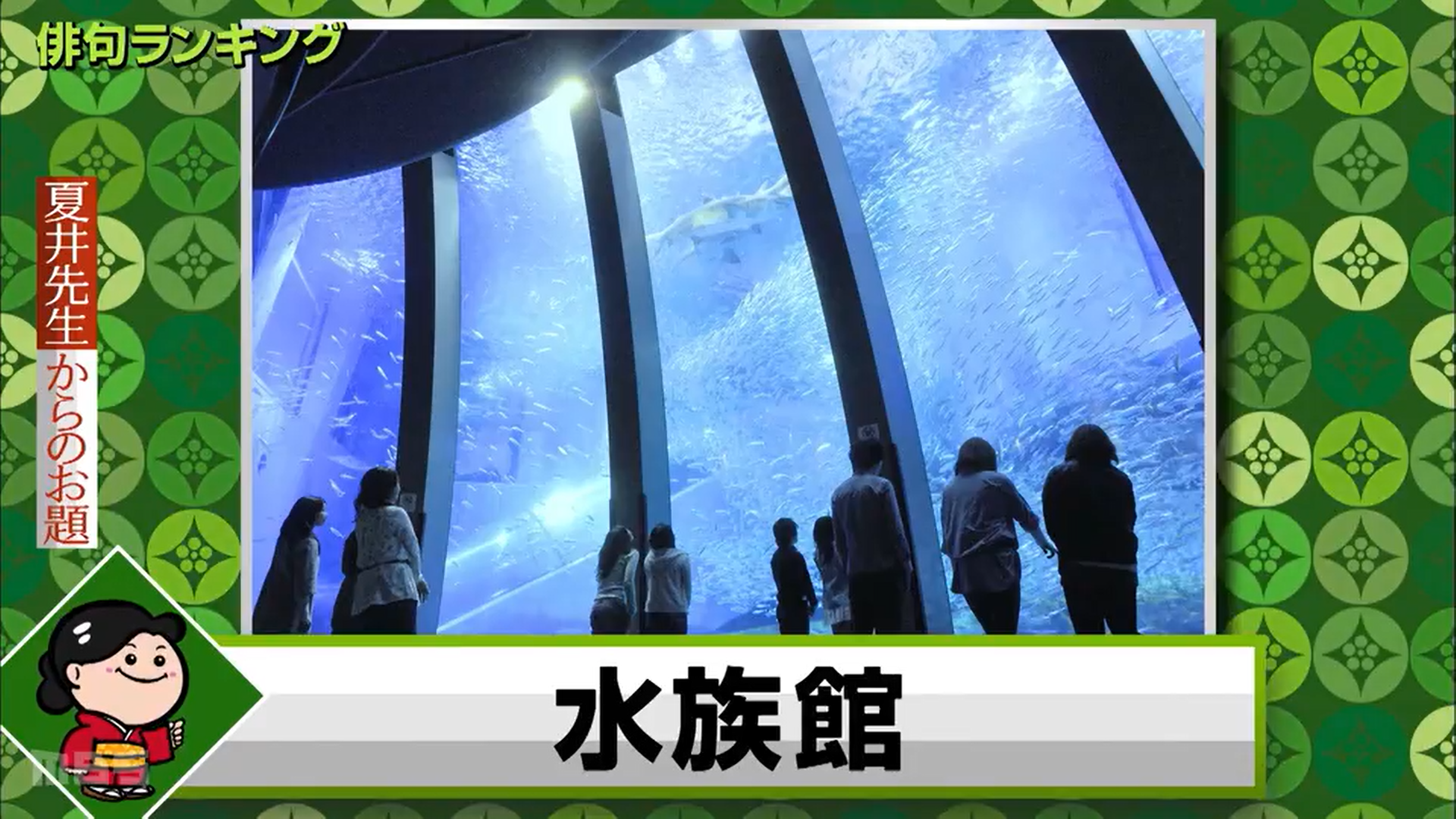
◇
まずは梅沢富美男。
夏のほか ペンギンの飛ぶ大水槽
季語の「夏の外 ほか 」は、
《そこだけ涼しげで夏じゃないみたいだ》という述語ですから、
通常ならば中七や下五に置いて「○○は夏の外」という形を取るべき。
映像でもなければ、時候ですらもなく、
それ自体としては何の具体性もない述語にすぎないし、
上五にいきなり「夏のほか」と置いたところで、
読み手の側は「何が??」となるのがオチです。
しかも、
上五で切って二句一章の形式を取っているため、
意味も映像もないカットだけ浮いてるように見える。
まあ、理屈としては、
「ペンギンの飛ぶ大水槽は夏の外である。」
という散文を、
「夏の外である、ペンギンの飛ぶ大水槽は。」
日本語として妙な印象は拭えません。
たんに珍しい季語に挑んだというだけの理由で、
番組ではやたらと称賛されていましたが、
けっしてこの季語の模範的な用法とはいえません。
◇
ゴンドウ鳴く水族館を出て白夜
季語は「白夜」で夏。
一読して気になるのは、
なぜ「海豚 イルカ 」や「鯨 クジラ 」ではなく、
わざわざ字余りで「巨頭 ゴンドウ (鯨)」を選んだかという点です。
もともと「海豚」や「鯨」は冬の季語ですが、
むろん「巨頭鯨」も小季語になるだろうから、
どれを選んでも季重なりは回避できないはずですよね。
それでもあえて「ゴンドウ」を選んだ理由は何なのか。
そこに実景としての必然性があるのかどうか。
…
じつは、対馬康子の先行句に、
鯨 鳴く水族館を出て 小雪
という作品があるそうです。
フジモンの句は、
2つの単語を入れ替えただけなので、
たんに「類想」の範疇を超えて「剽窃」の疑いがあります。
過去には東国原のパクリ疑惑もありました。
この句の場合は、
入れ替えた単語も似かよっています。
「巨頭鯨」は「鯨」の一種だし、
「白夜」の寒々とした光景も「小雪」の情景に通じます。
よく似た内容を、語彙だけをすこし変えて、
まったく同じ形で詠んだようにも見えます。
冒頭に「ゴンドウ」を選んだのは、
先行句との僅かな差別化を図るためだったのでしょうか??
…
とはいえ、
結果的に「白夜」を選んだことで、
季節が冬から夏に変わっただけでなく、
舞台が大きく北極圏へと移っているので、
先行句よりも地域色が強まってる感じはあります。
巨頭鯨は、
北極圏だけに生息しているわけではないのですが、
なぜか「ゴンドウ」までもが「白夜」に相まって、
ある種の地域性を体現しているようにも錯覚させる。
はたして「白夜の巨頭鯨」という素材に、
どれほどのリアリティがあるのか分からないし、
現実の光景か幻想かも判別しがたいのですが、
なにかしら独創的な詩情が生まれてる気がしなくもない?!(笑)
…
事実上、
個別の俳句や短歌をどんなに引用しても、
著作権侵害に問われることはありませんし、
寺山修司の剽窃騒動を挙げるまでもなく、
もともと盗用もパロディも本歌取りも"込み"の文化という面はあるし、
あとは「読み手がそれを面白がるか侮蔑するか」の問題ですね。
かりにフジモンが意図的に借用したのなら、
先行句を上回る独創性があるのかどうかを問われるところだし、
上6の字余りの必然性も評価の分かれ目になるかと思います。
…
なお、YouTubeでは、
「巨頭鯨の鳴き声」が聞けますが、
まるでウミネコみたいなけたたましい鳴き声です。
ちょっと悲しげにも感じられます。
それが白夜に聞こえているわけですね。
◇
中田喜子。
鯱 しゃち 戯 おど け尾ひれかみかみ 南風 みなみかぜ
南風 なんぷう や シャチの尾ひれを噛むシャチも (添削後)
そもそも「鯱が鯱の尾を噛む」なんて場面を見たことがないし、
そんなことがあるとも知らなかったので、
どんな状況を詠んでるのか、まったく理解できませんでした。
「鯱」を「シャチホコ」と読む可能性や、
「戯ける」という擬人化も、さらに理解を困難にしています。
たとえば、
「犬や猫のように自分の尾に戯れてる?」とか、
「ウロボロスみたいに自分の尾を噛むシャチホコ?」とか、
「獅子舞ならぬ鯱舞みたいなものがあるのかしら?」とか、
そんな誤読にもなりかねません。
中田喜子は、
ひそと待つ花街のひと 花衣
のときにも「ha」「hi」「mat」の韻を連ねていましたが、
ここでも「o」「ka」「mi」の韻を連ねています。
音韻の技巧にとらわれすぎて、
かえって内容の描写に失敗している感じもある。
…
なお、歳時記によっては、
「海豚」や「鯨」と同様に、
「鯱」も冬の季語にしているかもしれませんが、
水族館の鑑賞動物なので、季語としての力は弱いし、
先に挙げた対馬康子の俳句でも、
主たる季語は「小雪」であって「鯨」ではないはずです。
むろんフジモンの句も主たる季語は「白夜」です。
先日のプレバトでは、
「季語の動植物は漢字で書く」との原則が示されましたが、
逆にいうと、それをあえてカタカナで書けば、
季語としての力を弱められるのかもしれません。
◇
山西惇。
熱帯魚 アクリル越しのオーディション
作者が意図したのは、
アクリル製の水槽のなかで、
「熱帯魚がオーディションされている」という擬人化です。
しかし、作者の意図とは裏腹に、
感染防止のアクリル板とも解釈できるので、
「コロナ禍のオーディション会場で水槽の熱帯魚が泳いでる」
と誤読できてしまう。
実際、そう誤読したうえでの高評価になりました。
(ほんとうならば凡人以下にすべきですが)
◇
紺野まひる。
夏空や 石鯛掲ぐ父の遺影
石鯛を掲げる遺影 夏の空 (添削後)
内容的には二句一章ですが、
本来なら「掲ぐ」の連体形は「掲ぐる」なので、
形式的に三段切れになってしまっている。
下6の字余りも添削で修正されています。
◇
橋本良亮。
夏日影 水槽の下掻 か い潜 くぐ る
巨大水槽潜れば夏のひかり降る (添削後)
原句は意味不明。
本来なら「掻い潜る」という動詞は、
「障害物をよける」というニュアンスを含むし、
吊り下げられた沢山の金魚玉を避けているのかしら?
みたいな解釈をするのが精一杯です。
なお、季語の「夏日影」は、
夏の「日陰」ではなく、夏の「陽光」のことだそうです。
◇
蛙亭イワクラ。
夏の昼 ペンギンの様に手を引かれ
ペンギンのごと手を引かれ吾子の夏 (添削後)
おそらく「昼」の一語が最大の敗因。
季語を映像化する観点からいって、
上五の「夏の昼」では具体性がなさすぎるし、
たんに時間の説明の意味しかもっていません。






プレバト俳句。
お題は「水族館」。
フジモンにパクリ疑惑が浮上しています(笑)。
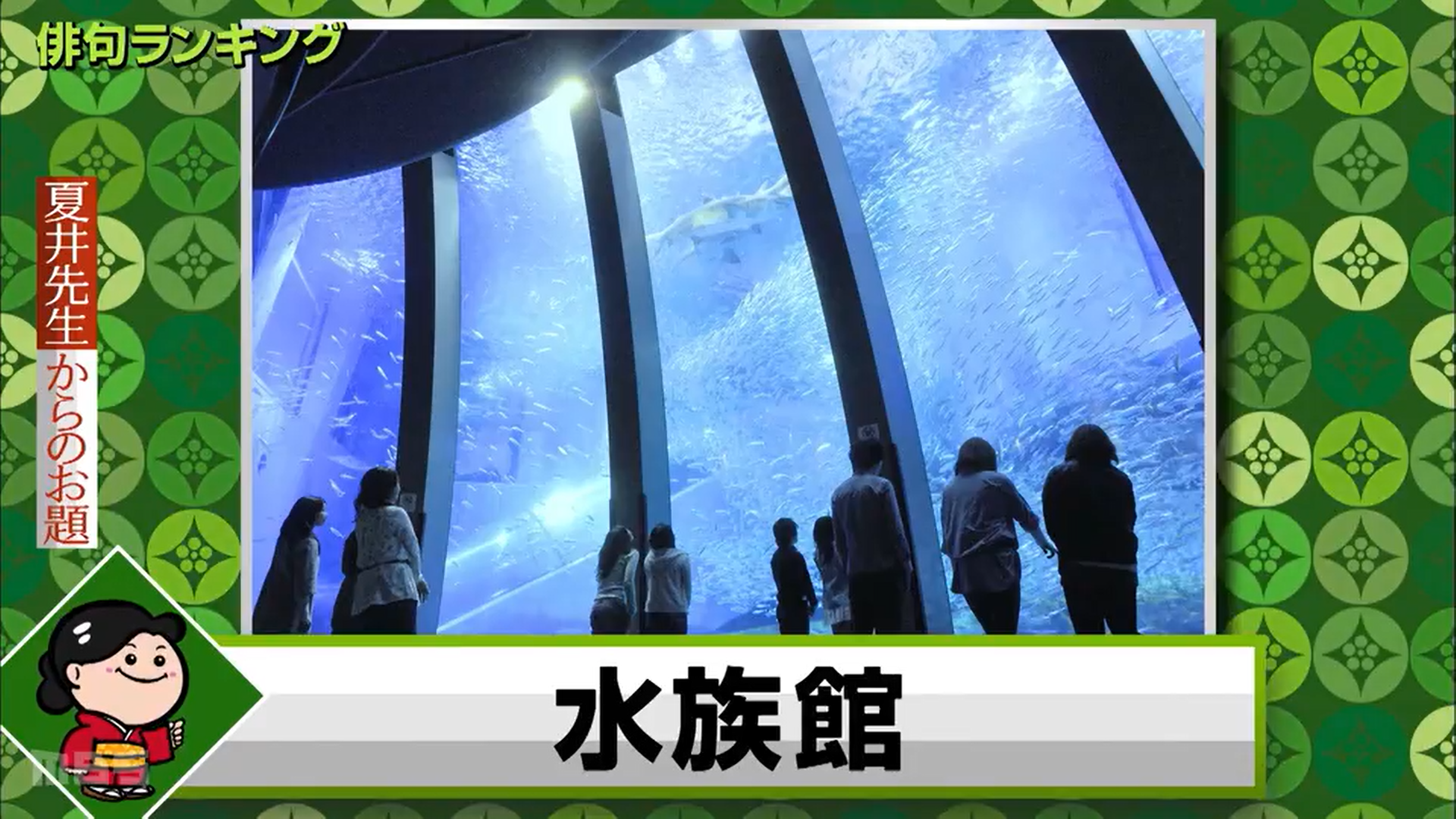
◇
まずは梅沢富美男。
夏のほか ペンギンの飛ぶ大水槽
季語の「夏の外 ほか 」は、
《そこだけ涼しげで夏じゃないみたいだ》という述語ですから、
通常ならば中七や下五に置いて「○○は夏の外」という形を取るべき。
映像でもなければ、時候ですらもなく、
それ自体としては何の具体性もない述語にすぎないし、
上五にいきなり「夏のほか」と置いたところで、
読み手の側は「何が??」となるのがオチです。
しかも、
上五で切って二句一章の形式を取っているため、
意味も映像もないカットだけ浮いてるように見える。
まあ、理屈としては、
「ペンギンの飛ぶ大水槽は夏の外である。」
という散文を、
「夏の外である、ペンギンの飛ぶ大水槽は。」
日本語として妙な印象は拭えません。
たんに珍しい季語に挑んだというだけの理由で、
番組ではやたらと称賛されていましたが、
けっしてこの季語の模範的な用法とはいえません。
◇
ゴンドウ鳴く水族館を出て白夜
季語は「白夜」で夏。
一読して気になるのは、
なぜ「海豚 イルカ 」や「鯨 クジラ 」ではなく、
わざわざ字余りで「巨頭 ゴンドウ (鯨)」を選んだかという点です。
もともと「海豚」や「鯨」は冬の季語ですが、
むろん「巨頭鯨」も小季語になるだろうから、
どれを選んでも季重なりは回避できないはずですよね。
それでもあえて「ゴンドウ」を選んだ理由は何なのか。
そこに実景としての必然性があるのかどうか。
…
じつは、対馬康子の先行句に、
鯨 鳴く水族館を出て 小雪
という作品があるそうです。
フジモンの句は、
2つの単語を入れ替えただけなので、
たんに「類想」の範疇を超えて「剽窃」の疑いがあります。
過去には東国原のパクリ疑惑もありました。
この句の場合は、
入れ替えた単語も似かよっています。
「巨頭鯨」は「鯨」の一種だし、
「白夜」の寒々とした光景も「小雪」の情景に通じます。
よく似た内容を、語彙だけをすこし変えて、
まったく同じ形で詠んだようにも見えます。
冒頭に「ゴンドウ」を選んだのは、
先行句との僅かな差別化を図るためだったのでしょうか??
…
とはいえ、
結果的に「白夜」を選んだことで、
季節が冬から夏に変わっただけでなく、
舞台が大きく北極圏へと移っているので、
先行句よりも地域色が強まってる感じはあります。
巨頭鯨は、
北極圏だけに生息しているわけではないのですが、
なぜか「ゴンドウ」までもが「白夜」に相まって、
ある種の地域性を体現しているようにも錯覚させる。
はたして「白夜の巨頭鯨」という素材に、
どれほどのリアリティがあるのか分からないし、
現実の光景か幻想かも判別しがたいのですが、
なにかしら独創的な詩情が生まれてる気がしなくもない?!(笑)
…
事実上、
個別の俳句や短歌をどんなに引用しても、
著作権侵害に問われることはありませんし、
寺山修司の剽窃騒動を挙げるまでもなく、
もともと盗用もパロディも本歌取りも"込み"の文化という面はあるし、
あとは「読み手がそれを面白がるか侮蔑するか」の問題ですね。
かりにフジモンが意図的に借用したのなら、
先行句を上回る独創性があるのかどうかを問われるところだし、
上6の字余りの必然性も評価の分かれ目になるかと思います。
…
なお、YouTubeでは、
「巨頭鯨の鳴き声」が聞けますが、
まるでウミネコみたいなけたたましい鳴き声です。
ちょっと悲しげにも感じられます。
それが白夜に聞こえているわけですね。
◇
中田喜子。
鯱 しゃち 戯 おど け尾ひれかみかみ 南風 みなみかぜ
南風 なんぷう や シャチの尾ひれを噛むシャチも (添削後)
そもそも「鯱が鯱の尾を噛む」なんて場面を見たことがないし、
そんなことがあるとも知らなかったので、
どんな状況を詠んでるのか、まったく理解できませんでした。
「鯱」を「シャチホコ」と読む可能性や、
「戯ける」という擬人化も、さらに理解を困難にしています。
たとえば、
「犬や猫のように自分の尾に戯れてる?」とか、
「ウロボロスみたいに自分の尾を噛むシャチホコ?」とか、
「獅子舞ならぬ鯱舞みたいなものがあるのかしら?」とか、
そんな誤読にもなりかねません。
中田喜子は、
ひそと待つ花街のひと 花衣
のときにも「ha」「hi」「mat」の韻を連ねていましたが、
ここでも「o」「ka」「mi」の韻を連ねています。
音韻の技巧にとらわれすぎて、
かえって内容の描写に失敗している感じもある。
…
なお、歳時記によっては、
「海豚」や「鯨」と同様に、
「鯱」も冬の季語にしているかもしれませんが、
水族館の鑑賞動物なので、季語としての力は弱いし、
先に挙げた対馬康子の俳句でも、
主たる季語は「小雪」であって「鯨」ではないはずです。
むろんフジモンの句も主たる季語は「白夜」です。
先日のプレバトでは、
「季語の動植物は漢字で書く」との原則が示されましたが、
逆にいうと、それをあえてカタカナで書けば、
季語としての力を弱められるのかもしれません。
◇
山西惇。
熱帯魚 アクリル越しのオーディション
作者が意図したのは、
アクリル製の水槽のなかで、
「熱帯魚がオーディションされている」という擬人化です。
しかし、作者の意図とは裏腹に、
感染防止のアクリル板とも解釈できるので、
「コロナ禍のオーディション会場で水槽の熱帯魚が泳いでる」
と誤読できてしまう。
実際、そう誤読したうえでの高評価になりました。
(ほんとうならば凡人以下にすべきですが)
◇
紺野まひる。
夏空や 石鯛掲ぐ父の遺影
石鯛を掲げる遺影 夏の空 (添削後)
内容的には二句一章ですが、
本来なら「掲ぐ」の連体形は「掲ぐる」なので、
形式的に三段切れになってしまっている。
下6の字余りも添削で修正されています。
◇
橋本良亮。
夏日影 水槽の下掻 か い潜 くぐ る
巨大水槽潜れば夏のひかり降る (添削後)
原句は意味不明。
本来なら「掻い潜る」という動詞は、
「障害物をよける」というニュアンスを含むし、
吊り下げられた沢山の金魚玉を避けているのかしら?
みたいな解釈をするのが精一杯です。
なお、季語の「夏日影」は、
夏の「日陰」ではなく、夏の「陽光」のことだそうです。
◇
蛙亭イワクラ。
夏の昼 ペンギンの様に手を引かれ
ペンギンのごと手を引かれ吾子の夏 (添削後)
おそらく「昼」の一語が最大の敗因。
季語を映像化する観点からいって、
上五の「夏の昼」では具体性がなさすぎるし、
たんに時間の説明の意味しかもっていません。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.06.12 17:54:00
[プレバト俳句を添削ごと査定?!] カテゴリの最新記事
-
プレバト俳句。お題「初デート」に異議あ… 2024.06.10
-
プレバト俳句。お題「洗濯」に異議あり?… 2024.06.03
-
プレバト俳句。お題「新茶」に異議あり?… 2024.05.27
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(227)ドラマレビュー!
(416)映画・アニメ・音楽
(158)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(187)岸辺露伴は動かない
(14)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(17)「鬼滅の刃」の考察と分析。
(29)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ
(31)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(58)ぎぼむす~3年A組~ちむどん!
(22)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)「エルピス」の考察と分析。
(10)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(10)北斎と葛飾応為の画風。
(13)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(29)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)家政夫ナギサさん
(6)半沢直樹!
(5)探偵ドラマ!
(7)倉光泰子
(4)パワハラ
(7)ドミトリー
(37)ゴミ税
(3)その他。
(1)夢日記
(4)© Rakuten Group, Inc.









