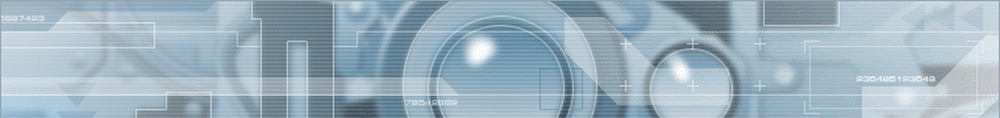PR
カレンダー
キーワードサーチ
ヒラタケ菌を植えて実験中のカシの木短木の1ヶ月後の様子です。

 3月11日
3月11日
前回3月11日から比べると、菌の勢いが弱くなったようで、色が黄味がかってきています。
左は、生木になにもせずに下部にのみ植菌したもので、全体的にあまり伸びてません。
右は、消石灰水に浸けた生木の下部にのみ植菌したものです。どんどん伸びて行ったのですが、途中で止まった感じです。

右の木の上部にカビかコケのようなものが出てきて、緑色に変わってしまいました。この切り口は、頂いたときの切り口だったので、こうなったものと思われます。消石灰水に浸けても、殺菌出来ていなかったようです。
それが原因で、菌糸が上まで伸びて行かないのではないかと思われます。
しかし、右と左の菌糸の伸び方は、明らかに右の消石灰に浸けたものの方が速く伸びることがわかりました。
また、途中まで、密閉していたのですが、伸びなくなったので、ティッシュでフィルターをつくりました。が、あまり変化はみられませんでした。


こちらは同じ日に消石灰水に浸け、同じ日に接種し、フィルター付き培養袋へ入れ、途中まで室温で、途中から温室に入れていたカシの木です。
下部のみ接種しようとしたのですが、上部にも少し落ちてしまい、そのままにしていました。上部にも種菌があったとはいえ、全体に菌糸が廻っています。
これらとは別に、クヌギの木で、室温で、消石灰水に浸けたものと浸けなかったものもありまして、浸けたものは薄っすら全体に菌糸幕が張っていて、浸けなかったものは、接種した下部のみ菌糸が少し伸びている状態です。
1ヶ月でこのように差がでました。この結果、原木を消石灰水に浸けることは有効であり、当初は密閉状態でも廻っていきましたが、最後まで廻るかどうかは不明。両木口に植菌することも有効である、と言えます。
消石灰水に浸けると、原木の表面に付いている雑菌が死滅し、その後に接種されたキノコの菌が、雑菌にジャマされることなく、伸びていけるのではないか?と考えています。
-
収穫 ヒラタケ菌床ブロック 2010.11.07
-
ヒラタケ短木栽培8 2010.06.13
-
ヒラタケ短木栽培7 2010.04.29