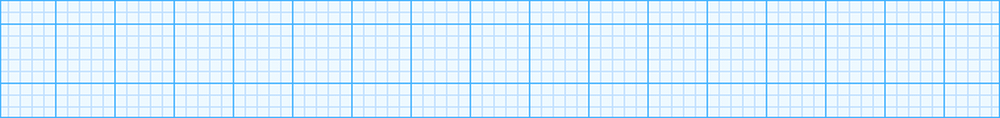「老人保健事業(保健所)」「介護予防・地域支え合い事業(福祉保健課)」「保健福祉事業(介護保険課)」の3事業を再編整備することで創設された地域包括支援センターは、地域支援事業における「総合相談・支援」「権利擁護」「包括的・継続的マネジメント支援」「介護予防ケアマネジメント支援」「介護予防ケアマネジメント」の役割を担うとともに、指定介護予防支援事務所として要介護者のケアマネジメントを実施しています。ここでは、地域包括支援センターの「設置主体」「人員基準」「設立基準」を簡単に解説します。
・地域包括支援センターの設置主体
包括的支援事業などを実施する地域包括支援センターは、市町村または市町村から委託をうけた法人によって運営されます。包括的支援事業の委託を受けることができるのは、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人とされ、具体的には、「在宅介護支援センター」の設置法人(民間企業、社会福祉法人、NPO法人、など)のほか、社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人、その他市町村が適当と認める法人とされています。ただし現状では、包括的支援事業の介護給付額が低いため、運営主体ととなっているのは、市町村もしくは市町村の補助金を受ける社会福祉法人やNPOがほとんどのようです。
・地域包括支援センターの人員基準
地域包括支援センターの人員基準は、1号被保険者数3000~6000人に対して、「保健師等が1人以上」「社会福祉士等が1人以上」「主任ケアマネジャー等が1人以上」と、必要に応じて「経験のある看護師」「高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事」を配置、という原則が示されています。ただし、小規模市町村の場合などには例外基準が設けられています。
・地域包括支援センターの設置基準
地域包括支援センターの設置は、原則として、市町村ごとに1つ設置された「地域包括支援センター運営協議会」によって行われます(ただし、複数の市町村によって共同でセンターを設置運営する場合は運営協議会も1つ)。また「センターの設置に係る具体的な担当圏域設定は、人口規模、業務量、運営財源、専門人材確保の状況などから市町村が独自で判断する」とされていますが、実際には「中小学校区に1ヵ所程度」設置されているようです。
-
【藤井聡】おはよう寺ちゃん 活動中【木曜… 2021.01.16
-
素人の騙し方、具体的な事例 2016.05.18
-
韓国人男性と結婚した日本人女性!結婚後… 2015.03.17