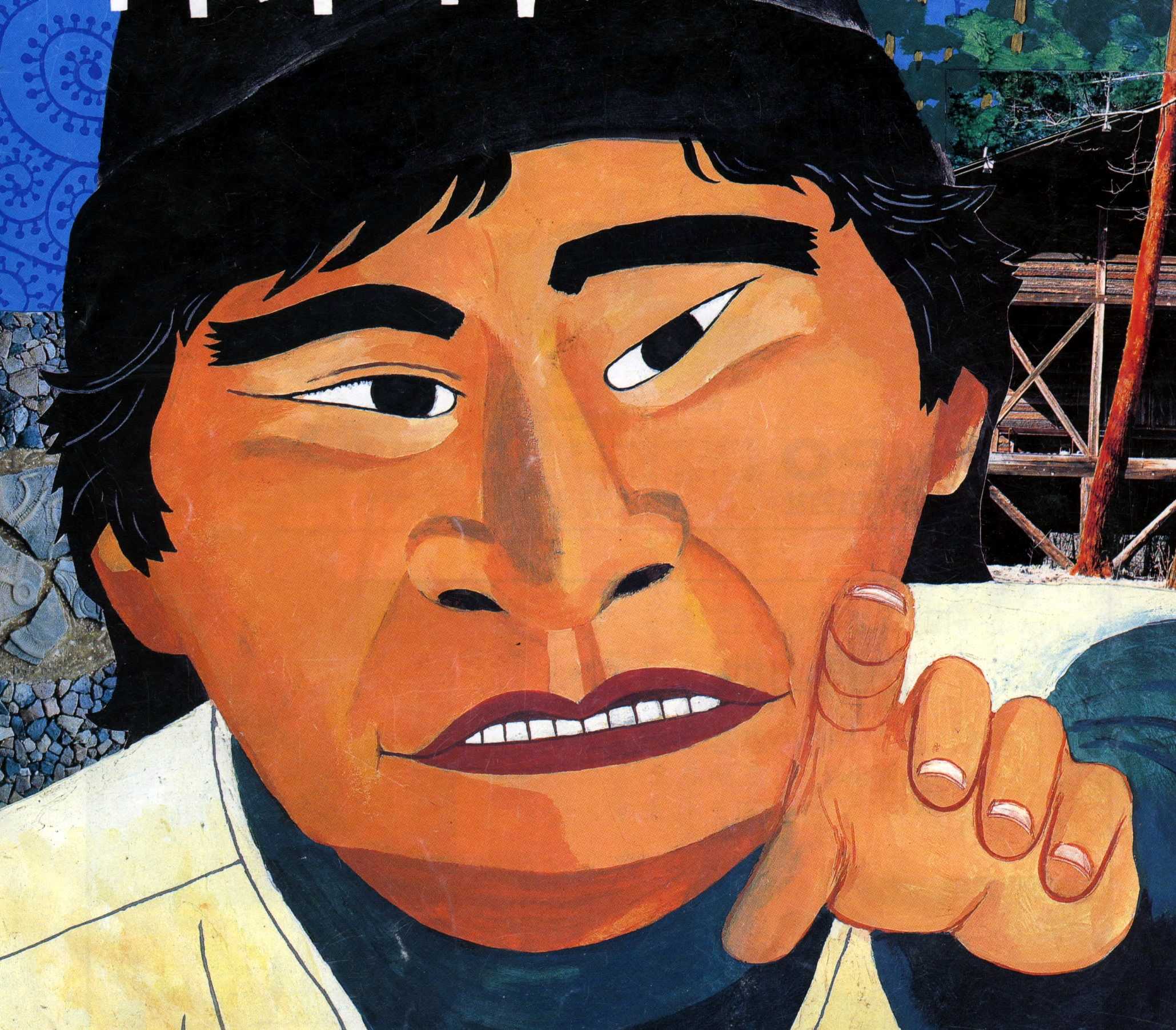編年体□日本古典文学史 嘉 永 四年 ~ 万 延元年
『国文学』2月臨時増刊号
学燈社 昭和52年 刊
この期の特記事項
◆ペリー浦賀来航する。
◆河竹黙阿弥、小団次との提携。
◆安政の大地震が起こる。
◆コレラで死者多し。
’ ◆安政の大獄
◆坪内逍遥生まれる。
天保改革に挫折し、謹慎のまま嘉永四年(1851)二月十日(公けには十六日)、水野忠邦は寂寥のうちに五十八歳の生涯を閉じた。以後の十年間における、政治上の事件の主なるものは【安政の大獄】であり、又芸術上の事件の主なるものに黙阿弥・小団次の提契による江戸歌舞伎の爛熱である。
ペリー来航
嘉永六年(1853)六月二日、ペリー提督の率いる旗艦サスクェハナ以下四生の軍艦の浦賀来航は夜もねられぬ程の不安を招いた。
周章狼狽する幕府諸役人を尻目に、ペリーは六月九日久里浜に上陸、米国国書を手交した。ペリー退去の後老中阿部正弘は一般の町人にまでその対策を答申するように勧めた。これより処士横議が盛んに行われることとなった。
安政元年(1854)正月十六日、ペリーに再び来航、遂に羽田冲まで侵入したが、幕府の申出により神奈川で交渉、三月三日、【日米和親条約十二箇条】が調印された。
この交渉の問に両国間で贈答が行われ、米国側からは電信機や蒸気機関車の模型の献上があった。この四分の一の模型は後、江戸竹橋辺に移されたが、将軍侍講見習たる十八歳の成島柳北は、六月二十七日に実見、その日記に
「実ニ奇器ナリ。然リト雖も玩物ト称ス可キノミ」
と書き付けている。運転の指揮は江川英龍であった(「成島柳北」)。続いてハリスが来日、安政三年八月五日、伊豆下田玉泉寺に総領事旗を揚げるに至った。更に日米通商条約の締結を目ざして翌四年十月十四日遂に江戸に入り、将軍家定との謁見を行っている。
老中堀田正睦は同条約の勅許を得るべく、努力を重ねたが、攘夷論の前に難行していた。その最中、将軍継嗣問題が起った。即ち家定は生来病弱で癇癖があったため、長命も嗣子誕生も望み薄と見られていたからである。候補としては一橋慶喜(一七歳、前水戸藩主徳川斉昭の子)と、紀州藩主徳川慶福(八歳)が考えられ二閣老は越前藩主松平慶永・薩摩藩主島津斉彬等が支持し、後者は彦根藩主主井伊直弼等譜代大名達が支持した。血統を以て将軍とすべしとの考えである。慶喜やむなしとする正睦の上京ともに継嗣問題は京都に波及したが朝廷では将軍家の内部の問題とし、一橋派の運動は効を奏さなかった。
条約勅許も未解決のまま正睦は帰着。三日後の五年四月二十三日、井伊直弼大老に任ぜられ、五月一日継嗣を慶福と内定、十八日に発表する予定の処、
その前日ハリスが下田より神奈川に到り、海国に勝った英・仏両国が目本に大艦隊を派遣し有無を言わせず、米国より苛酷な通商条約を結ぼうとしている旨を告げ、日米間の条約調印をせまった。
十九日ポ-ハタン艦上で勅許をまたず調印。更に徳川斉昭は慎、松平慶永は隠居・慎という風に処罰されたため一橋派は憤激、政局は混迷した。梁川星厳などが画策し、朝廷より条約調印に反対等の勅諭が直接水戸藩に下り、井伊直弼支持の関白九条尚忠は更迭された。
ここに京都における志士の逮捕がはじまった。【安政の大獄】 である。【五手掛り】という厳しい取調べと井伊大老の独断で、頼三樹三郎、吉田松陰等は死罪に処せられた、が、梁川星厳は猛威をふるったコレラに罹り逮捕寸前の九月二目死亡したため「詩に上手」と言われたが、妻の紅蘭は硯獄中に在った(尚このコレラのため他に山東京山・市川米庵・柳下亭種員’緑亭川柳・一立斎広重等が鬼籍に入った)。星厳はその居鴨泝小隠
(嘉永二年九月より、京川端丸太町。安政四年一〇月より鴨西三本木)で閑雲野鶴を友とするやに見せて、その実志士達と密議をこらし、最期に臨んで門弟松本尺永に七十余名の連判状を託したと言う(「梁川星厳の「記事二十五首」(安政六年)は、
仏蘭英吉湧鯨波。
豈止俄羅美理哥。
八面紛争皆勁敵。
中流砥柱奈吾何。
の如く時事を詠じた誌としられる。
かくて強引な政敵の弾圧に一応成功した井伊直弼は更に水戸藩を威嚇した。ここにおいて万廷元年(1860)三月三日、水戸浪士十八名により桜田門外の雪を紅に染める事となったのである。直弼の首と胴体は藩医により縫い合わされたが、その夕方三代目中村伴藏は、奥方が首のない掃部様を見て、「コリヤどうじや」と驚いたという落咄を聞いている(「手前味噌」)。
まことにお上には我関せず、太平の逸民と言うの外はない。
仲藏と同様、芝居国に憧れたのが若き日の黙阿弥である。三十六歳嘉永四年(1851)河原崎座頭顔見世興行「升鰹滝白旗」二番目を初作とし、生涯に三百六十に及ぶ作を残したと言う(「黙阿弥全集首巻」。この黙阿弥が自決作者と呼ばれるに至ったのは泥棒を得意とする四世市川小団次との提携によるのである、が、それは馳阿弥、が真の立作者となった、嘉永七年(1854)河原崎座弥生興行、「都鳥廊白浪」にはじまる。その原因は忍ぶの惣太に扮した小団次の意に染まぬ箇処を、何度も小団次のダメによって書直し、遂に大当りをとった事にあるが、チョボを加えた点が眼目と言う(「市川小団次」)。
翌二年十月二日、夜四ツ時江戸全市中が大地震に襲われた。母を救わんとして藤田東湖、が圧死した所謂安政の大地震である。
その時然阿弥は寄席に行っていたが日頃の用心深さから梯子の降り口に至って居た爲、すぐに飛び出し無事であった。
場末の真打にようやくなれた三遊亭円朝は早稲田の素人寄宿に出演中であったが、借家は倒壊したものの無事(「三遊亭円朝」)。二世松林伯円は京橋三十間堀の釈場茂松で「曽我物語」を読んでいる最中。釈台に首をつっ込んで無事であったが、養父の初代伯円は圧死した。この三名は後に例えば伯円原作の「鼠小僧」を、「鼠小紋東君新形」(安政四年一月)として黙附弥が劇化、円朝が「鰍沢」を演ずれば、その二度目を黙阿弥が同じく三題噺に作るという風に、密接な関係を持つようになる。
この地震は七千人の死者を出す一方世直しの大地震と呼ばれた拐で、職人は大いに潤い、手間賃が四、五倍に高騰し、寄席は大入りを続けた。そのために、「たがや」の演出が変り、たが家の首が飛ぶのか、武士の方に変ったと言う
(「古典落語」三)。
黙阿弥と小団次の提携はいよいよ密度を加えた。門閥に左右される梨園にあって小団次の天分・努力もさることながら才能を十分に生かした脚本を生みだした黙阿弥の功多大なものがあった。
小団次の得意としたのは人情を穿ち、微細に風俗を写した演技にあった、が、九年後かかる地芸が禁じられ遂に憤死するに至る。
安政六年(1859)五月二十二日、演劇改良を志す事となる坪内逍遥が、美濃田太田宿に生まれた。この少年に中仙道の宿場町で、黙阿弥の所謂【がんどう返し】の世を垣間見る事となろう。
(延広真治氏著)
-
郵便制度と国境警備 シーボルト 江戸参… 2022年03月28日
-
日本国内旅行の考察(仮題) シーボルト… 2022年03月28日
-
シーボルト 江戸参府紀行(1) 訳者… 2022年03月28日
PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ