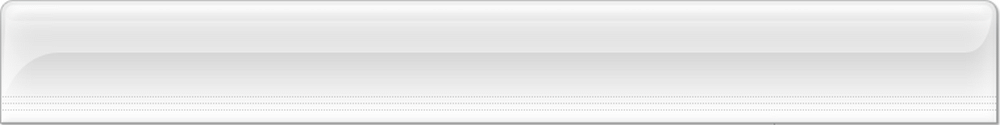2008年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
「迷説般若心経・178」
第十四章(6) 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃ゲンちゃん(玄奘)は高僧だ。だからイタズラ坊主だ。ここでもヒネクレた(優しい)ワナを仕掛けた。この文節のとらえかたで涅槃が変わる。それぞれが、どんな涅槃を想像し創造するか?クスクス笑いながら心経を書いたのだろうなぁ。ワナは、ほとんどが落ちるように仕掛ける。そして・・・見事に、ほとんどが落ちた・・・。でも、これを見破るには知識はいらない。堅苦しい理屈もいらない。素直にみれば、判るように書いてある。「夢想の反対(転倒)などとは遠く離れた境地だぜ」(つまり、夢想が沢山ある境地だぜ)だが心経は大般若経という難しいお経のエッセンスだ。だから、きっと難しい真理が濃く詰まっているに違いない。そうだ、そうに違いない・・・そう思った解説者達は、自分や他人の知識をフル稼動して訳す。そして、見事にワナにはまる・・・。この世の仕組みは、知識じゃ無ぇ、理屈じゃ無ぇといっているのに・・・。例えれば、長屋の八っつあんや熊さんに説いているんだぜ。
2008/01/31
コメント(0)
-
「迷説般若心経・177」
第十四章(5) 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃「顛倒夢想」の訳し方で意味が正反対になる。「夢想のような転倒した心」というのが一般的。ワシは独善でヒネクレているから、「転倒した夢想」つまり「キマジメな心」と訳す。「顛倒夢想」を素直に訳せばワシに近いと思うぞ。涅槃にはどちらが溢れているか?夢想の無いキマジメな心ばかり?夢や空想や希望が沢山ある境地?自由は夢と空想で溢れていると思うぜ。そして、ブッちゃんは自由の素晴しさを説いている。「空と無」で・・・。それにしても夢想の転倒した心という表現はいいなぁ。夢想の反対の心・・・。「キマジメ」と直接いうより味がある。優しさもある。ワシのように「キマジメ」をからかうのは優しさが足りない。
2008/01/30
コメント(0)
-
「迷説般若心経・176」
第十四章(4) 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃誰かが言ってたなぁ。「生死即涅槃」ついでに「煩悩即菩提」こっちのほうがワシの性に合っている。愚かな衆生のワシには合っている。そして、ブッちゃんはワシ等の為に説いてくれた。生きていれば、そこは涅槃でもある。気づくか、気づかないかの違いだ。特別な修行も精進も必要ない。魂は自然に柔らかくなる。何度も生死を繰り返して。それでも、苦しむのは嫌だろう。それを観るのも、忍びない。だからブッちゃんは経を説いた。涅槃の悦びを少しでも味わえるようにと。要は本人次第なのだ。だから、万人に万物に経は活かせる。
2008/01/29
コメント(0)
-
「迷説般若心経・175」
第十四章(3) 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃知ったかぶりで解説している人達がいる。もちろんワシもその中の一人だ。い、いや、ワシは知ったかぶりじゃない。最初から独善迷説だといってる。決して謙遜じゃないぞ。誇張でも斜に構えたわけでもない。経を読むのではない。経を記した人(ゲンちゃん)を感じるのだ。経を説いた人(ブッちゃん)に共鳴するのだ。同じ人間だもの、できるさ。ただし・・・正誤真偽は問わないぜ。評価としては偉人だろう。だが優しいオッサンには変わりない。衆生やケモノや妖怪の苦しみを軽減したいのだ。難しい屁理屈はいらない。ならば、誰だって仏陀や玄奘に共鳴できる。誰もが共鳴できる柔らかさが、偉人という意味なのだ。一部の頭でっかちが理屈で解説する人達じゃないぜ。
2008/01/28
コメント(0)
-
「迷説般若心経・174」
第十四章(2) 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃通常訳は間違いだろう。無理もないのだ。誰も涅槃に行った事がないのだ。だから、そんなツマラン訳になる。夢も希望も無い、涅槃になる。涅槃は、そんな無味乾燥した境地じゃないだろ。そんな所には行きたくなくなるから。自分で行った事も無いのに、決め付ける。涅槃には恐れも、迷いも、夢想もない。「無」の意味を勘違いしているからだ。「何も無い」のが「無」だと思っている。だから涅槃が無味乾燥の境地になる。「無い」と訳すと、経が観えなくなる。心経は「空」と「無」の訳し方で姿を現す。
2008/01/27
コメント(0)
-
「迷説般若心経・173」
第十四章(1) 遠離一切顛倒夢想 究竟涅槃一般訳は「顛倒した夢想妄想から遠く離れ、涅槃の境地に辿り着く」などという直訳が多いようだ。そんな境地はツマランだろうなぁ。少なくてもワシはツマラン。夢想も妄想も無いような人とは付き合いたくない。ロボトミー手術して理想郷を作ろうとした物語があった。バカな感情が無く、マジメなロボットのような人々の国。夢は見ない。空想はしない。ワシなら、そんな人とは付き合いたくない。ブッちゃんもゲンちゃんも、そんな人とは違う。夢想空想妄想大好き人間だろう。イタズラ坊主だぜ。夢想だらけだ。明るい未来を夢想して経を説いているんだ。キマジメな修行に明け暮れると、幸せにはなれない。夢想や空想や妄想が適当にあってこそ、愉しい人生だぜ。
2008/01/26
コメント(0)
-
「迷説般若心経・172」
第十三章(12) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖「心や身体の不都合にとらわれるなよ。といって、無視していいわけ無ぇだろ。それぞれ可愛がれよな。それが養生ってことだ。養生を意識し行うと、楽になるぜ。不都合が有っても治せばいいんだ。すると、恐怖が必要以上にならない。恐怖が有っても、大丈夫になるのさ。まぁ、適当な大きさで恐怖を感じられる。これは、結構大切なんだぜ。恐れも知らないと、ロクなモノになれ無ぇ。人間もケモノも妖怪も、適当に恐怖が必要さ。必要以上は、いら無ぇけどな。まぁ、般若ってのは、暮らすのが楽になるコツだ。」
2008/01/25
コメント(0)
-
「迷説般若心経・171」
第十三章(11) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖ワシ的訳。「(前章からの続き・般若というのは)心の悩みや迷い、心のダメージが有っても大丈夫だ。その事に固定しなければ、勝手に変わる。いろいろが有って当たり前だ。だが、心は変化しやすいんだぜ。一々思い出して、こだわらなけりゃ変わるぜ。身体の病や怪我も有る。必ずといっていいほど、降りかかる。だが、それでも大丈夫だ。回復したり、軽減したりするコツがある。身体も常に変わっているのが事実だぜ。しかも回復方向に変わっているんだぜ。生きているってのは、必ず回復に向かっているんだ。回復を邪魔しているのは、自分の固定概念なんだよ。変化している事を認めろよなぁ。不都合があるのを認める。同じく、回復している事も認める。要は、常の変化を認めるって事だ。それが、こだわらない、イイカゲンって事だ。それが、般若って事だ。」
2008/01/24
コメント(0)
-
「迷説般若心経・170」
第十三章(10) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖「恐れ」も見直してみよう。生きる事は恐れが付随する。生命は必ず尽きる。何時、何処で、如何なる理由でかは判らない。誰にも判らない。だから「恐れ」は必ず付随する。「恐れ」の表面には無智がある。勘違いもある。だが底には、この世の仕組みがある。仕組みの奥深さを感じるのだ。「恐れ」は「畏れ」になる。恐れる事は、単純に不都合なモノじゃない。ブッちゃんは、その事を含めて「有」を使った。恐れを知らない生物は、必ず自滅する。自滅だけじゃない。他の生物の迷惑となるのだ。この世は多種多様なモノと共存共生で成り立つ。恐れを無くしては、この世にいる意味が無くなるのだ。
2008/01/23
コメント(0)
-
「迷説般若心経・169」
第十三章(9) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖この世の出来事を全て肯定する。その上で、歩き方のコツを教えてくれる。それが説法ってことだろう。理屈や机上論や正真論では、実際は役にたたない。心の乱れ、病、恐れ、を有ると認めて先に進める。それらは「無いのだ!」などと力説しても解決できない。「実相界では幻だ」などと、この世で言っても意味が無い。この世は、舞台上なんだぜ。本名や本当の姿を明かすのは、マヌケだぜ。~しなければならない、のではない。~してはならない、のでもない。何でもアリなのだ。その上で、実生活として、歩き方を教えてくれているのだ。心経は、正しさの理屈じゃないんだぜ。
2008/01/22
コメント(0)
-
「迷説般若心経・168」
第十三章(8) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖「無有恐怖」も表面の訳が多い。「~故に恐れが無い」などと訳すようだ。それなら「無恐怖」で事足りる。「有」の字が入っている意味を無視している。何度もいう。「無」を「無い」と訳すから意味が汲み取れないのだ。「無」は「こだわらない・気にしない」と訳すのだ。「こだわらない」と訳せれば「有」の字が活きる。恐怖が無くなる、のではない。恐怖が有っても大丈夫だぜ、と言ってくれている。ブッちゃん(仏陀)は優しいんだ。理屈で「無くなる」なんて強調しない。生きている、というのは「恐れ」と共生しているのだ。先が見えない(恐怖)から、この世で生物として存在しているのだ。恐れの無い生物は存在できない。無くなったら、この世にいる意味が無い。肉体を持っている意味は、結構深いんだぜ。そんな事は当たり前だろ。
2008/01/21
コメント(0)
-
「迷説般若心経・167」
第十三章(7) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖いままでの心経の訳には身体が抜けている。心の部分だけ取り上げていた。心経は心(精神)分野の経だと思われている。それは、とても大きな間違いだと思う。肉体(物質)が無い世界なら魂が主役だ。だが、この世界(色界)は物質(肉体)が優先する。心や魂が重要なのは解るが、優先するのは肉体だ。心や魂が肉体に影響するが、増して肉体が心や魂に影響する。底の浅い宗教や、宗教まがいの組織の教えは似ている。精神的正しさを強調した教え。肉体の無い世界でしか通用しない理屈。それで肉体を持った衆生やケモノや妖怪は救われない。心は誤魔化せるが、肉体は誤魔化せないのだぜ。
2008/01/20
コメント(0)
-
「迷説般若心経・166」
第十三章(6) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖心無罫礙 無罫礙故が同じ意味なら・・・「心無罫礙故」の一節でいい。どこが違うか?一目瞭然。前節に「心」があり、後節にはない。つまり「無罫礙故」の網や石は心の事じゃない。心でなければ、身体だ。身体の網は病の事だ。石は怪我の事だ。(この訳は多分、日本でもワシ一人だと思う)ゲンちゃんは、わざわざ心と身体を区別して書いたのだ。この世界では、心も肉体も同等に重要なのだ。つい、心や精神を重要視しがちだが、それは間違いやすい点だ。同等だが、むしろ肉体が優先する世界だぜ。精神世界スキスキ人間は、ここで必ず間違える・・・。
2008/01/19
コメント(0)
-
「迷説般若心経・165」
第十三章(5) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖「無罫礙故」に、また仕掛けがある。今までの「色不異空」と「空不異色」。「色即是空」と「空即是色」などと同じだ。そのまま字面を訳したら、マヌケだろ。ゲンちゃん(玄奘)はボケてない。せっかく心経という凝縮経にしているのだ。同じ意味言葉の繰り返しなどしない。だから、ここも違う訳にして欲しいのだ。通常の訳者が間違うのは、訳者の立場だからだ。書き手の立場になれば判る。まして、イタズラ坊主のゲンちゃんだ。書き手は、文章に仕掛けをしたいものなのだ。短い文章になればなるほど仕掛ける。詩や俳句や短歌をみればいい。言葉に様々な仕掛けを付ける。訳し手や読み手の事など、少し度外視してしまう。書くのが愉しいから、そういう仕掛けをする。創る愉しみは個人的な愉しみが必ず入る。何事も個性があってこそ活きる。
2008/01/18
コメント(0)
-
「迷説般若心経・164」
第十三章(4) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖網に引っかかっても、気にするなよ。石につまづき転がるなんて、普通だぜ。網を無くそうなんて考えなくていい。石を避けようなんて思わなくていい。先の事は判らねぇ。誰も先は見えねぇもんだ。生きるってのは、闇の中で歩いている。人により、真っ暗か薄闇かの違いはある。先に光を感じるかどうかの違いもある。それは大きな違いかもしれねぇ。それでも網に絡まる。薄闇でも光を感じても、石に転がる。絡まる、転がるのは大前提さ。そんな事ぐらいで、立ち止まる必要は無ぇぜ。
2008/01/17
コメント(0)
-
「迷説般若心経・163」
第十三章(3) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖網に引っかかるな、と言っても絡まる。石につまずくな、と言っても転がる。それが人間で生きているって事だ。その大前提を認めた上で説法が活きる。心の中は多種多様なモノが沢山ある。不都合なモノだけ無くせ、というのは無理だ。多種多様で心を形成しているのだ。清く正しいだけの心は存在しないし存在できない。そんな事もわからないで心の領域に踏み込もうとする。宗教家や教育者や生真面目な人達。言っている本人も自分の心にフタをしている。嘘をついている。あるいは、観る目も無いのに理屈で話す。だから落ちこぼれは救われない。閉じこもりも出られない。心に正しさを押し付けても回復しないのだ。
2008/01/16
コメント(0)
-
「迷説般若心経・162」
第十三章(2) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖単純に「心に引っかかり(罫礙)が無ければ・・・」などと訳しても意味が無い。「清く正しく美しく生きましょう」などと平気で言う宗教言葉のようなものだ。だからワシは宗教は詐欺だと思っている。平気でそういう言葉を言う人を信用しない。心が簡単に動かせるなら、世界は何千年も前から楽園だ。人間は皆、神様級の超高等精神体だ。もちろん、宗教組織など必要あるまい。皆が悟っているのだ。ブッちゃん(仏陀)は本物の優しいオッサンだ。無理な事は言わない。出来もしない事を言わない。誰でも出来うるヒントを話しているのだ。最終的には本人が自分で歩く道だ。
2008/01/15
コメント(0)
-
「迷説般若心経・161」
第十三章(1) 心無罫礙 無罫礙故 無有恐怖前章の続きだ。その前に、罫礙(けいげ)の説明だ。(注:罫のトが無い字だが、変換できない)罫は網で礙は石。網にからまったような心。石につまずくような心。何故、網や石に束縛されるか。「こだわり」が網や石を引き寄せる。「無(こだわらない)」なら、網や石も邪魔じゃない。世の中には網も石もあるのだ。網や石が無くなるわけじゃないぜ。だが邪魔にならなければ、不都合じゃない。落とし穴も沢山ある。しかも先が真っ暗の時もある。それでも歩かなければならない。毎日生きているからだ。
2008/01/14
コメント(0)
-
「迷説般若心経・160」
第十三章(12) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故「誰でも菩薩なんだけどよ、菩薩として生きるコツがあるんだ。そのコツを知って実行すると、楽に生きられる。苦しむと、生きるのが大変に思えるだろ。苦しむ菩薩より、愉しめる菩薩になりなよ。そのコツが般若ってヤツだ。何も難しい事じゃ無ぇ。何度も言っているだろ。この世の仕組みはイイカゲンだ。だから、イイカゲンに心を合わせるのさ。万物が流転しているし、諸行は無常だろ。心を固定したら苦しくなるのは当たり前だ。毎日身体だって変化しているんだ。心だけこだわるのは不自然だろ。それに気づく事が、般若ってことさ。」
2008/01/13
コメント(0)
-
「迷説般若心経・159」
第十三章(11) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故ワシ的訳。これは次章に繋がる部分だから途中までの訳になる。「お前ぇ等は皆菩薩なんだぜ。生き物ってのはよ、その立場立場で生き方が違う。それでも方向は同じなんだぜ。気づいても気づかなくても同じ方向に歩いている。この世界に生まれて、死ぬまで生きる。一人一人の個性で生きる。個性は共生を活かす為のもんだ。この世ってのはよ、多種多様なモノが合わさって出来ている。どんな立場でも、他の役に立っているんだ。だから、気づいても気づかなくても菩薩だ。もちろん一度の人生で完成するわけが無ぇ。何度も生まれ変わるのさ。いろいろな立場を経験するのさ。そして、少しづつ進むんだ。幸せ、そのものの境地に向かっているんだ。生きているってのは、幸せに向かう事なんだぜ。」
2008/01/12
コメント(0)
-
「迷説般若心経・158」
第十三章(10) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故生きる事は趣味なのだ。個性で生きる事(趣味)が本道だ。だからグレちゃん(創造主)は別々に創った。一人一人、一つ一つ、個性がある。「個性で生きろよ」そういうメッセージだろう。生きる事。最後まで大切に生き続ける事。それが菩薩行になる。個性があるのは、個性ある菩薩行が必要だからだ。遠慮しないで、個性溢れる生き方をしよう。ただし・・・肉体生命は期限がある。生命は最後まで大切に扱う意味だ。立派に生きなくてもいい。だが、大切に生きるのは、当たり前なのだ。その、当たり前を話しているのがブッちゃん達だ。難しい理屈じゃない。
2008/01/11
コメント(0)
-
「迷説般若心経・157」
第十三章(9) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故ボランティアは個人趣味なのだ。趣味を超えたら、ボランティアではなくなる。菩薩行ではなくなる。菩薩行は個人趣味なのだ。社会の為、人の為と言い出したら偽善だ。詐欺も勘違いも同じだ。心の奥は別なモノでドロドロしている。個人が好きで行ってこそボランティア。趣味で行ってこそ菩薩行。まして組織が音頭をとっている場合は怪しい。薄汚い企みがあるものだ。神や仏の名前を使って信者を動かす。騙されやすい人を信者に加える。自立すれば、他を煽動などしない事が判る。自立は共生(菩薩行)の土台だぜ。
2008/01/10
コメント(0)
-
「迷説般若心経・156」
第十三章(8) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故生物全てが菩薩といってもなぁ・・・ミジンコやアメーバやゴキブリもかぁ・・・などと種科目で差別するのは止めておこう。彼等には彼等なりの菩薩行がある。あるんじゃないかな?わからないけど、ある、って事で・・・。どうやら菩薩は肉体のある生物だけじゃないようだ。肉体が無くなった後の精神(魂)体も含むらしい。例えば、地蔵菩薩や弥勒菩薩等々。他の幸せに貢献しようとする意識体だ。如来にだってなれる立場なのにならない。如来になったら、ただ光っているだけ。それよりも、他と係わりたいモノ達だ。いわば・・・ボランティア精神かなぁ・・・。
2008/01/09
コメント(0)
-
「迷説般若心経・155」
第十三章(7) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故菩薩行に必要なのは正しい心ではない。正しさを判断する智恵でもない。優しさであり、明るさだ。イタズラ小僧のような、愉しさだ。正しさに「こだわらない」生き方。だから「無」を付ける。生きる事を愉しめる心。それを菩薩心という。愉しむ、とは押し付けない係わり合いだ。何でも認める優しさがあって愉しめる。その優しさを生活に活かす「般若」という智恵。だから生きとし生けるモノ全てが対象となる。「般若」を知る事が菩薩行となる。
2008/01/08
コメント(0)
-
「迷説般若心経・154」
第十三章(6) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故出来が良くても悪くても、菩薩は皆同じ方向を歩む。菩薩道という道を歩く。自他が幸せになるように歩く。その為の方法が「般若」というわけだ。ここで間違えやすいのが「正誤」や「真偽」だ。菩薩は正しい行いをするものだ、と考え違いをする。まだ人間だぜ。正しいと思い込むと、争いをする生物だぜ。菩薩行の逆なのが「正しさの追求」ってヤツだ。ほとんどの宗教は菩薩行を邪魔しているのが現実だ。宗教者は争いが好きなのだ・・・。菩薩行は誤りを認めるものだ。至らなさを優しく抱きしめるものだ。正しさに導き、押し付けるものじゃないぜ。未成熟の生物に必要なのが菩薩行だ。未成熟同士お互い様だから必要なのだぜ。
2008/01/07
コメント(0)
-
「迷説般若心経・153」
第十三章(5) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故誰でも菩薩。だが、現段階では差がある。同じ人間でも菩薩として、大きな差があるのだ。例えば、故マザー・テレサ。例えば、ダライ・ラマ法王。毎日の生活が菩薩行として成り立っている。同じ人間とは思えないがワシも人間の一人。同じ人間とは思えないが、政治家や官僚も人間の一人。菩薩としてマザー・テレサやダライ・ラマとは差がある。ある、なんてもんじゃないほど、ある。だから、皆菩薩、といっても褒められたもんじゃねぇ・・・。どんな段階でも一応菩薩。餓鬼道でも畜生道でも菩薩。出来の悪い菩薩達(つまり我々・・・)の為に説法する。出来のいい菩薩達は指導など必要ないのだ。説法は慈悲の心と共にあるんだぜ。
2008/01/06
コメント(0)
-
「迷説般若心経・152」
第十三章(4) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故同じ人間でも様々だ。というより、一人として同じではない。形や心や能力が違う。国や人種や年代が違う。違いはあるが、偉さの差はない。偉さではないが、段階のような違いがある。ある意味、差といってもいいだろう。経験値といってもいいだろう。誰でも通る道だけど、先と後がある。決定的な差ではないが、現段階では差がある。何度も生まれ変わって、経験を積む。いろいろな悲しみ、苦しみ、嬉しさ、楽しさを味わう。それは菩薩行として役立つ経験となる。苦も非も哀も嬉も楽も役に立つのだ。どんな人生も無駄じゃないぜ。
2008/01/05
コメント(0)
-
「迷説般若心経・151」
第十三章(3) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故広い意味では全てが菩薩。狭い意味では「幸せに向かう」事を意識して生きるモノ達だろうな。この「意識する」っていうのが、あらゆる事に優先する。「意識する」だけで、方向の確かさも速度も段違いになるのだ。幸せに向かう事の具体的行動の一つに利他がある。他の為に(も)生きる。だがら、利他行が菩薩の生き方、ともいえる。それほど立派な事じゃない。地球上の生物としては、当たり前なのだ。人類種だけが、かなり外れているだけだ。つまり、仏教とは、当たり前の生き方を説いただけだ。ブッちゃんは、理屈で話したのじゃない。生物として、当たり前の生き方を話した。人間だけが外れすぎていたので、当たり前が菩薩行となった。こんなワシも、そんなアンタも菩薩なんだぜ。
2008/01/04
コメント(0)
-
「迷説般若心経・150」
第十三章(2) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故菩薩が「幸せに向かうモノ」で生命体全てだ。ならば如来とは何か?簡単だ。「幸せになってしまったモノ」だ。当然、生命体を超えてしまっている。悟ったら人間ではいられない、という意味はここにある。超えたら、生命体でいる理由が無い。つまり、人間でいて「私は悟りを開いた」というのは無理なのだ。そういう人は、嘘か詐欺か勘違いなのだよ。ツマラン宗教にひっかからないでね。ブッちゃん(仏陀)は気づいたのだ。悟りを得るのは自然にまかせる。人でいる間は、生きる事を大切にする。だから衆生やケモノや妖怪に優しい。だから生あるモノ達に「慈悲」という言葉を使った。悲しみも苦しさも含め、認めての方法だ。
2008/01/03
コメント(0)
-
「迷説般若心経・149」
第十三章(1) 菩提薩多 依般若波羅蜜多故菩提薩多を略して菩薩という。その菩薩とは何者か?サトリを求める者。他の為に生きる者。如来になる前の役職?ワシは「幸せに向かって歩く者」と訳した。ならば、生きとし生けるモノ全てが当てはまる。生命は意識する、しないに係わらず、幸せに向かうものだ。向かわないのなら、生命は続かない仕組みだ。当たり前なんだけどなぁ。わざとらしく菩薩というが、実は全てが菩薩だ。生命全てが仏でもあり、神でもあり、天使でもある。ワシのような欠陥オッサンでも菩薩なのだ。ワシは菩薩を自覚している。天使も自覚している。ワシが菩薩というのに異論はあるだろう。がモンクは言わせない・・・。モンクを言ってもいいけど、聞く耳は持たない。聞く耳はあるけど、マトモに聞かない・・・。どうだぁ、まいったかぁ・・・。 (注:薩多の多は土へんに垂だが、変換できないので多とした)
2008/01/02
コメント(0)
-
「迷説般若心経・148」
第十二章(11) 無智亦無得 以無所得故ワシ的訳。「欲しがる心から自由になれよ。それは僧達も同じだぜ。物欲や肉欲だけが対象じゃ無ぇぞ。欲しがる心が、大切なモノを観えなくしているんだ。欲しがる心に、こだわらなくなる。欲しがっても、いつでも放せる。するとな、サトリからも自由になれるんだぜ。サトリを得る事なんざ、どうでもよくなる。サトリを追いかけるのは、趣味の一つだ。サトリがどうでもいいなら、その為の修行や智恵の追及もどうでもいい。智恵からも放れる、放せる。それで、やっと、大切なモノが観える。大切なのは、毎日の暮らしだ。(サトリを)欲しがる心にこだわらなくなると、当たり前に気づくようになる。」
2008/01/01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 株主優待コレクション
- 【配当】ホカホカでおすすめ!増配株…
- (2025-11-26 18:00:07)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 届いたscope便と楽天ブラックフライ…
- (2025-11-26 22:13:16)
-