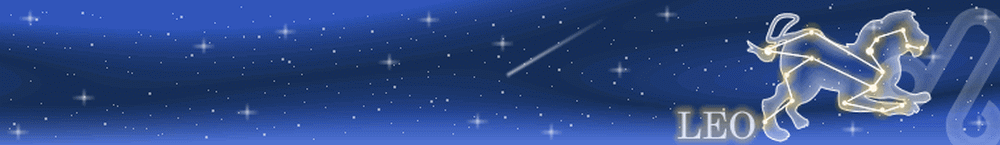実は前回で終わりのつもりだったが、皆さんはまだ続くことを期待しているようだ。
確かにホラーと言いながら、皆さんを恐がらせてはいない。
しょうじきなところ私は、遊園地なんかにいっても絶対に「お化け屋敷」には入らないタイプだ。
そんな私が皆さんを恐がらせる事ができるのか、疑問は残るが、何とかがんばってみよう。
小島のお通夜には私たち4人のほかにも同級生がたくさん来ていた。
小島の母親は気丈に振舞っていたが、私達4人の顔を見たとたん・・・泣き崩れてしまった。
一緒にキャンプにやればこんな事にならなかったのにと言う悔しさだったのではないだろうか。
酔っ払い運転をして小島を轢いた犯人は、警察で取調べを受けており、その犯人の父親と言うのが焼香に来ていたのだが、小島の両親は目を合わせなかった。
お通夜が終わり、私達4人は鈴木の家の社員寮に集まった。
数日前、小島を入れて5人で泊まった部屋・・・・・・・
あの時は楽しい話だけだったのに今は・・・・・・本当にお通夜のような・・・誰もが無言で・・・・・・
特に、最初に「キャンプをしよう」と言い出した成田の落ち込みはひどいものだった。
陸上短距離の選手だから、どちらかと言うとたくましい筋肉・・・しなやかな筋肉を持っているはずだったが、今の彼の姿は、一回り小さくなったような気がする。
鈴木が成田の慰め役にまわったが、鈴木にしたってこの部屋をみんなに提供した責任を感じていた。
「港に近いから、みんなをここに泊めたんだけど、行く予定の3人だけで泊まればよかったんだよな」
私にしたって、私が下北半島出身でなければ脇野沢をキャンプの場所にえらばなかっただろうという負い目があった。
それぞれが責任を感じ、自分を責めていた。
鎌田はキャンプには行かなかったものの、5人の中では最後に小島と会話をした仲間として、「あの時、もう少し引き止めていれば」というような引け目を感じていただろう。
4人が4人とも無言のまま、一時間を過ごした。
鈴木の母親が、夕飯用にどんぶり物の出前を取ってくれていたが誰も手をつけない。
「俺、明日まで水泳部の練習があるから、今日はこれで帰るわ」
鎌田が言い出したのをきっかけに、この場を解散することにした。
鎌田と私は同じ方向に帰るので一緒に出た。
落ち込みのひどい成田は、鈴木の父親が心配して車で送ってくれることになり、私と鎌田が先に鈴木の家を出たのだが、ゆっくり歩いている私達を、鈴木の父親の車が追い越していく。
後部の座席に、鈴木に肩を抱かれた成田の姿が見えた。
「あいつ大丈夫かな」
車のテールランプが赤く光り、続いてウインカーが右折の合図をしたのを見送りながら、鎌田がそういった。
大丈夫か・・・・なんて私にはわからない・・・・・私自身がどうにかなりそうな感じがしていたのだ。
「小島はなあ・・・・ほかの誰でもない・・・俺にジンマシンを出させて自分が死んだことを教えてきたんだ・・・」
鈴木から私のジンマシンの事を聞いていた鎌田は、「それは・・・・」と言ったきり、何もいえない・・・・
確かに5人の中で一番仲がよかったのは私かもしれない。
それでも、なぜ私なのか・・・なぜ私にジンマシンを出させたのか・・・・理解ができなかった。
途中で鎌田と別れ、私は一人アパートに戻った。
「風呂に入りたいなあ・・・」
時計を見ると、まだ銭湯に行く事のできる時間だった。
すぐに銭湯に行く準備をし、アパートをでて10分ほどで銭湯につく。
銭湯にはまだ3人ほど入っていて充分な時間が残っていた。
湯を浴び体を洗ってから浴槽に入る。
まだ焼香の匂いが残っているような感じだったのが全て流い洗されたような気分。
小島のことを忘れたわけではないが汗を落としてさっぱりしたような気分だった。
体を温め、洗い場の腰掛に座って髪を洗う。
シャワーで髪をぬらし、手でシャンプーをあわ立て髪に撫で付けるのだが、いつもより余計出たのか泡立ちがいい。
私は髪の毛を洗うとき、どうしても目をつぶってしまうのだが、奇妙な感覚に襲われた。
髪の毛をこすっているときに誰かが私の髪の毛をちょっとだけ引っ張っているのだ。
もちろん、誰かが悪戯しているのではない。
しかし、誰かに髪の毛を引っ張られている感触はあるのだ。
「気のせいだ」とも思うのだが、その感触がいつまでも消えない。
私は髪の毛を洗うのをやめてシャワーでシャンプーを洗い落とす。
すぐにタオルで顔を拭き、あたりを確認するのだが、ほかの客3人は全て浴槽に入っていて、洗い場にいるのは私一人だった。
「今日は汗を落とすだけでいいや」
私は独り言をいって湯をかぶり、そのまま浴槽に入った。
私が浴槽に入るとなぜかそれまで入っていた3人の客が次々と出てゆき、浴室から出ていって脱衣場で着替えを始めたから、とうとう私独りになった。
そして不思議なことに、風呂の温度がどんどん下がっていくような気がした。
浴槽の近くに温度計があり、その目盛りは41度を指して動かないのだから、私の気のせいだと思うのだがなんだか水風呂に入っているような気分になって、私は気持ちが悪くなり、浴槽を出た。
シャワーを浴びたのだが、そのシャワーも冷たく感じた。
「コリャだめだ」・・・・・わたしは着替えるために浴室を出た。
わたしは銭湯に行くといつもコーヒー牛乳を飲むのだが、その日はもう遅い時間なのかコーヒー牛乳が売り切れていて、ラムネしか残っていなかった。
「今日はラムネを飲むか」
番台に料金を支払いラムネをあけて飲んでみると、ラムネの味がしない。
炭酸なのだが甘くない・・・・・
それはほろ苦いビールの味だったのだ。
半分ほど飲み、あとは残してしまった。
今日はやっぱりおかしい・・・・・早く帰って寝よう・・・・・
私は番台に挨拶をして帰ろうとした。
「おじさん、おやすみ・・・・」
そのとき番台が妙な顔をした。
「あれ、あんちゃん来るとき一人だったかい?・・・・もう一人いたような気がしたんだけどなあ?」
しかし浴室にも脱衣場にもだれひとり残っていない。
「変だなあ・・・マア俺の勘違いかもしれない」
わたしは直感で、小島がついてきていると感じた。
「さよなら」
銭湯を出て、私は急ぎ足でアパートに戻った。
誰かがわたしの跡をつけてくるような感覚・・・・・・それも同じスピードで・・・
「ぴた、ぴた、ぴた、ぴた、・・・・・・・」
その足音が近づいてくるのだが、私には振り返る勇気がない。
足音?・・・・いや音は聞こえないのだ・・・・・・しかし・・・・
「ぴた、ぴた、ぴた、ぴた・・・・・・」
幻聴なのだろうか?
その足音が横に並び、そしてとうとうわたしを追い越していった。
一瞬目をつぶりすぐに薄目で見る。
そこには・・・・・わたしを追い越していった・・・・雑種の犬が一匹歩いていた。
「なんだ・・・・犬だったのか」
わたしは少しほっとしたのだが・・・そのとき、その犬が頭だけ振り返って「ニヤッ」と笑った。
驚いて立ち止まった私!
しかしその犬は、そのまま街灯の向うの暗がりに消えて行ったのだ。
「ぴた、ぴた、ぴた、ぴた・・・・・・」
その足音もだんだん遠ざかっていく。
立ち尽くしたままの私だったが、しばらくしてようやく気を取り戻し・・・震える足を押さえながら、私はアパートに戻った。
アパートに戻ると、私が出るとき消し忘れたのか、ドアの外からでもわかるほど大きなテレビの音がした。
「いや・・・・・俺、鈴木の家から帰って真っ直ぐ風呂屋に向かったからテレビをつけてない」
消し忘れていない・・・・テレビのスイッチを入れてなかったのだ。
そういえば明かりのスイッチは確実に消したはずだ・・・・しかし今は室内灯が煌々とついている。
わたしは恐る恐るドアを開けた。
つづく
ハイブランド好き(*´… お買い物中毒【悪女】ハイブランド購入品♪さん
kei恵0112 kei恵0112さん
Cutie Pie cheeky_angelさん
さ・や・ん~sayang~ かほ(*^-^*)さん
Calendar
Comments