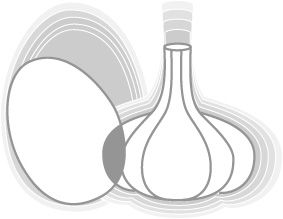PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 離乳食は順調ですか?(684)
カテゴリ: 食事
年も改まり、さまざまな「初・・・」が各地で行われています。毎年の定番として広く普及しているものから地域密着型のものまで、ユニークなものはニュースで取り上げられたりするので、比較的知られていたりするのですが、あまり目立たないものまで入れると、新年の行事は非常に多いのではないでしょうか。そんな新年の行事とは関係なく、それでも「初」が付く行事の一つとして、「お食い初め」があります。
お食い初めは、地方によっては110日や120日というところもあるそうですが、よく知られたところでは生まれた日も含めた100日目の日に、「子供が一生食べ物に困らないように」「いつまでも丈夫な歯で何でも食べられ、健康長寿でありますように」といった願いを込めて行われる行事で、箸揃い、お箸初め、歯固めの祝いとも呼ばれる事があります。
平安時代に生後100日目を祝ってお餅を入れた重湯を作り、子供の口に含ませる「百日(ももか)の祝い」や、その後、本格的な食事に切り替える準備として、初めて肉や魚を口にする日に「魚味始(まなはじめ)」という行事が行われていたので、その二つの行事が合わさった、もしくは片方を簡略化し、片方のみとなったのが今日の「お食い初め」になったのではと考えられます。
生後100日目、まだまだ本格的な食事も作法も程遠い状態なので、介添人が子供には付けられ、多くの場合一族の長老格の異性となっているので、男の子にはお婆さん、女の子にはお爺さんが付く事となります。最近では100日目と限定せず、子供の体調が良さそうな日に離乳食を使ってという家庭も増えているそうですが、本式に行うには本膳と二の膳を用意し、男の子は朱塗りの、女の子には外側を黒く塗った朱塗りの膳に、大盛りのご飯とその上に小さなおにぎりを2、3個。汁物と尾頭付きの焼き物、副菜に梅干5個。小皿には歯固めの意味を持った小石を3個乗せ、二の膳には紅白のお餅5個を盛るという独特な用意が要ります。ヨーロッパにも同じように「一生食べるに困らないように」とスプーンを新生児に送る習慣がある事から、洋の東西を問わず親の願いは同じような形に出てくるものです。
お食い初めは、地方によっては110日や120日というところもあるそうですが、よく知られたところでは生まれた日も含めた100日目の日に、「子供が一生食べ物に困らないように」「いつまでも丈夫な歯で何でも食べられ、健康長寿でありますように」といった願いを込めて行われる行事で、箸揃い、お箸初め、歯固めの祝いとも呼ばれる事があります。
平安時代に生後100日目を祝ってお餅を入れた重湯を作り、子供の口に含ませる「百日(ももか)の祝い」や、その後、本格的な食事に切り替える準備として、初めて肉や魚を口にする日に「魚味始(まなはじめ)」という行事が行われていたので、その二つの行事が合わさった、もしくは片方を簡略化し、片方のみとなったのが今日の「お食い初め」になったのではと考えられます。
生後100日目、まだまだ本格的な食事も作法も程遠い状態なので、介添人が子供には付けられ、多くの場合一族の長老格の異性となっているので、男の子にはお婆さん、女の子にはお爺さんが付く事となります。最近では100日目と限定せず、子供の体調が良さそうな日に離乳食を使ってという家庭も増えているそうですが、本式に行うには本膳と二の膳を用意し、男の子は朱塗りの、女の子には外側を黒く塗った朱塗りの膳に、大盛りのご飯とその上に小さなおにぎりを2、3個。汁物と尾頭付きの焼き物、副菜に梅干5個。小皿には歯固めの意味を持った小石を3個乗せ、二の膳には紅白のお餅5個を盛るという独特な用意が要ります。ヨーロッパにも同じように「一生食べるに困らないように」とスプーンを新生児に送る習慣がある事から、洋の東西を問わず親の願いは同じような形に出てくるものです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.