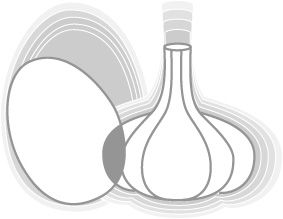PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 食事
今でも好きな和菓子の一つとなっているのですが、子供の頃、和菓子屋の店先で鉄板の上で焼かれていた金つばが大好きでした。四角く成型された餡は通常の餡よりも水分量が少なく、6面すべてに薄くかけられた小麦粉の生地は引きがあって食べ応えがあり、もともと粒餡が好きな私にとって理想的なお菓子のように思えていました。
金つばはその名の通り刀装具の一つである「鍔」が語源となっている事は容易に想像が着くのですが、時代劇の中では武骨な武芸者か忍者が用いる刀にしか金つばのような形状の鍔は見られず、どことなく違和感を感じてしまいます。
金つばについて江戸時代の国学者、喜多村信節(きたむらのぶよ)は興味深い記載を残しています。信節は江戸時代の後期に活躍した国学者で、考証を専門としながら多くの著述を残しています。民間の風俗や伝承の記録、考証に努めた事で知られ、江戸時代の風俗研究には欠かせない人物ともいわれます。
その信節によると「今時のどら焼きは、また金つばともいう」「どら焼きのどらとは銅鑼に似ているから名付けられたもので、銅鑼と同じように大きな物をどら焼きと呼び、形が小さな物は金つばと呼ぶ」と記されていて、どら焼きと金つばの間には大きさ以外の違いがない事が伺えます。
今日ではどら焼きと金つばは完全に別のお菓子となっていて、間違える人はほとんどいないといえるのですが、信節の頃は同じ物であった事になり、餡を小麦粉の生地で包んで焼いた物であった事が判ります。形状もどら焼きと同じく丸いものであった事から、刀の鍔に見立てられても違和感のない物であったという事ができます。
どら焼きの生地に卵が使われて、ふんわりと焼いて餡を挟むようになるのは明治時代になってからの事とされます。金つばが今日のように寒天で固めた餡に、小麦粉の生地を薄く塗って焼き上げるようになったのも明治時代の事となっています。
大本は江戸時代の中期に京都で考案された上新粉で作った生地で餡を包み、平たく焼いた「銀つば」であったとされます。それが江戸の街に伝えられ、上新粉が小麦粉に変わって景気が良い銀から金に呼び名が変えられたといいます。
今日でも当時の名残りを残す円形の金つばも作られていて、鍔のような紋様を入れる物も存在しています。現在のスタイルである四角い形状の物は神戸元町の本高砂屋創業者、杉田大吉によって考案されたといわれます。富山市では三角形の金つばが作られているそうですが、三角形は鍔の形状ではないと思えるので、何故そうなったのか大いに気になっています。
金つばはその名の通り刀装具の一つである「鍔」が語源となっている事は容易に想像が着くのですが、時代劇の中では武骨な武芸者か忍者が用いる刀にしか金つばのような形状の鍔は見られず、どことなく違和感を感じてしまいます。
金つばについて江戸時代の国学者、喜多村信節(きたむらのぶよ)は興味深い記載を残しています。信節は江戸時代の後期に活躍した国学者で、考証を専門としながら多くの著述を残しています。民間の風俗や伝承の記録、考証に努めた事で知られ、江戸時代の風俗研究には欠かせない人物ともいわれます。
その信節によると「今時のどら焼きは、また金つばともいう」「どら焼きのどらとは銅鑼に似ているから名付けられたもので、銅鑼と同じように大きな物をどら焼きと呼び、形が小さな物は金つばと呼ぶ」と記されていて、どら焼きと金つばの間には大きさ以外の違いがない事が伺えます。
今日ではどら焼きと金つばは完全に別のお菓子となっていて、間違える人はほとんどいないといえるのですが、信節の頃は同じ物であった事になり、餡を小麦粉の生地で包んで焼いた物であった事が判ります。形状もどら焼きと同じく丸いものであった事から、刀の鍔に見立てられても違和感のない物であったという事ができます。
どら焼きの生地に卵が使われて、ふんわりと焼いて餡を挟むようになるのは明治時代になってからの事とされます。金つばが今日のように寒天で固めた餡に、小麦粉の生地を薄く塗って焼き上げるようになったのも明治時代の事となっています。
大本は江戸時代の中期に京都で考案された上新粉で作った生地で餡を包み、平たく焼いた「銀つば」であったとされます。それが江戸の街に伝えられ、上新粉が小麦粉に変わって景気が良い銀から金に呼び名が変えられたといいます。
今日でも当時の名残りを残す円形の金つばも作られていて、鍔のような紋様を入れる物も存在しています。現在のスタイルである四角い形状の物は神戸元町の本高砂屋創業者、杉田大吉によって考案されたといわれます。富山市では三角形の金つばが作られているそうですが、三角形は鍔の形状ではないと思えるので、何故そうなったのか大いに気になっています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.