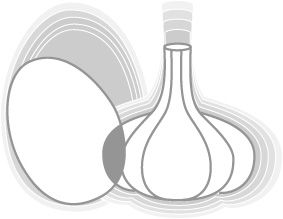PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 食べ物あれこれ(51661)
カテゴリ: 食事
高校、大学と同じ学校で学んだ後輩がバイクのレースに出場していて、一度、バイクメーカーの広大な工場の敷地内にあるサーキットで開かれた耐久レースの様子を見に行った事があります。
50ccの原付バイク、レーシングライセンスを持たない素人も参加可能という事で、トップクラスのチームと中堅以下では相当な力の差が見受けられたのですが、休日を利用した地元の草レースという感じがほのぼの目に映った事が思い出されます。
その際、後輩に聞かされたところでは、レース場に行く前に少し遠回りをすると熊本空港の近辺へ行ける事から、航空燃料を少し分けてもらい、燃料のガソリンに混ぜるとバイクの馬力が上がるという事でした。その話や巨大な航空機をものすごい勢いで飛ばすジェットエンジンの原動力になるという事から、航空燃料はガソリンよりも火力が強く、危険なものというイメージを持っていました。
後に航空燃料はガソリンよりも可燃性が高く、爆発する危険性を持ったものではなく、「ケロシン」と呼ばれる家庭でストーブなどの燃料として使われている灯油のようなものである事を知り、燃えにくいものを燃やすからこそ巨大な力が得られるのだと、変な納得をしてしまいます。
ケロシンという呼び名はギリシャ語で「ろう」や「ワックス」を意味する「ケロス」に由来していて、成分的にはほとんど灯油と同じとされ、実際、ケロシンランプなどでは灯りのための燃料として使用されています。しかし、日本ではケロシンというとほぼ航空燃料の事として認識されており、特殊で高価なものというイメージが定着しています。
最近、そのケロシンの代替燃料としてバイオ燃料を使用する新たな手法が試みられ、家庭や加工メーカーから排出される廃食用油のリサイクルへの道が開かれる可能性が出てきています。
これまで日本国内でもバイオジェット燃料を使った試験飛行は行われていますが、使用された燃料は外国製のものだけで、大手航空会社で最近になって導入が発表されたものも外国製となっていて、国産のバイオジェット燃料が商用化されるのはまだ先という感じがしていました。
今回、新たなバイオジェット燃料を作り出したのは九州を中心とした産学官の連携で、広島のバイオ燃料の会社、佐賀市、北九州市立大がタッグを組み、佐賀市から無償提供された廃食用油をベースに製造が行われています。
精製する工程で特殊な触媒を用いる事で水素消費量を抑えた事や、廃食用油を用いた事がコストダウンに繋がっているとされ、現在の試算価格は1リットル当たり販売段階で150円程度としています。近日中にバイオ燃料の会社が実証プラントを完成させると製造コストは大幅に下げられる事が考えられていて、やがては100円以下という現在の石油系燃料と同じ水準の価格となる事も予想されています。
日本国内で排出されている廃食用油は54万トンにも上るとされ、今後も安定的に安価に原料の入手が行われる事が考えられます。二酸化炭素の削減にも繋がる事から期待が高まってくるのですが、バイオ燃料を搭載した車の横にいて、排気ガスが揚物屋の排気ダクトのような臭いがする事に気付いたり、その後、その車が燃料に含まれていた不純物によって燃料フィルターを目詰まりさせて止まってしまった場面を見てしまうと、バイオジェット燃料の飛行機には少しだけ乗りたくない気がしてしまいます。
新たなバイオジェット燃料はまだ試作段階ですが、すでにジェット燃料の国際規格も満たしているとされ、早ければ第一便が東京オリンピックの応援へと向かう佐賀空港から東京への便に採用されるといいます。揚物はあまり作らない我家ではあまり貢献はできそうもないですが、廃食用油のリサイクルがさらに広がるその時を待ちたいと思っています。
50ccの原付バイク、レーシングライセンスを持たない素人も参加可能という事で、トップクラスのチームと中堅以下では相当な力の差が見受けられたのですが、休日を利用した地元の草レースという感じがほのぼの目に映った事が思い出されます。
その際、後輩に聞かされたところでは、レース場に行く前に少し遠回りをすると熊本空港の近辺へ行ける事から、航空燃料を少し分けてもらい、燃料のガソリンに混ぜるとバイクの馬力が上がるという事でした。その話や巨大な航空機をものすごい勢いで飛ばすジェットエンジンの原動力になるという事から、航空燃料はガソリンよりも火力が強く、危険なものというイメージを持っていました。
後に航空燃料はガソリンよりも可燃性が高く、爆発する危険性を持ったものではなく、「ケロシン」と呼ばれる家庭でストーブなどの燃料として使われている灯油のようなものである事を知り、燃えにくいものを燃やすからこそ巨大な力が得られるのだと、変な納得をしてしまいます。
ケロシンという呼び名はギリシャ語で「ろう」や「ワックス」を意味する「ケロス」に由来していて、成分的にはほとんど灯油と同じとされ、実際、ケロシンランプなどでは灯りのための燃料として使用されています。しかし、日本ではケロシンというとほぼ航空燃料の事として認識されており、特殊で高価なものというイメージが定着しています。
最近、そのケロシンの代替燃料としてバイオ燃料を使用する新たな手法が試みられ、家庭や加工メーカーから排出される廃食用油のリサイクルへの道が開かれる可能性が出てきています。
これまで日本国内でもバイオジェット燃料を使った試験飛行は行われていますが、使用された燃料は外国製のものだけで、大手航空会社で最近になって導入が発表されたものも外国製となっていて、国産のバイオジェット燃料が商用化されるのはまだ先という感じがしていました。
今回、新たなバイオジェット燃料を作り出したのは九州を中心とした産学官の連携で、広島のバイオ燃料の会社、佐賀市、北九州市立大がタッグを組み、佐賀市から無償提供された廃食用油をベースに製造が行われています。
精製する工程で特殊な触媒を用いる事で水素消費量を抑えた事や、廃食用油を用いた事がコストダウンに繋がっているとされ、現在の試算価格は1リットル当たり販売段階で150円程度としています。近日中にバイオ燃料の会社が実証プラントを完成させると製造コストは大幅に下げられる事が考えられていて、やがては100円以下という現在の石油系燃料と同じ水準の価格となる事も予想されています。
日本国内で排出されている廃食用油は54万トンにも上るとされ、今後も安定的に安価に原料の入手が行われる事が考えられます。二酸化炭素の削減にも繋がる事から期待が高まってくるのですが、バイオ燃料を搭載した車の横にいて、排気ガスが揚物屋の排気ダクトのような臭いがする事に気付いたり、その後、その車が燃料に含まれていた不純物によって燃料フィルターを目詰まりさせて止まってしまった場面を見てしまうと、バイオジェット燃料の飛行機には少しだけ乗りたくない気がしてしまいます。
新たなバイオジェット燃料はまだ試作段階ですが、すでにジェット燃料の国際規格も満たしているとされ、早ければ第一便が東京オリンピックの応援へと向かう佐賀空港から東京への便に採用されるといいます。揚物はあまり作らない我家ではあまり貢献はできそうもないですが、廃食用油のリサイクルがさらに広がるその時を待ちたいと思っています。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[食事] カテゴリの最新記事
-
薄焼きの・・・ 2023年09月24日
-
不振の理由 2023年08月23日
-
嫌われ者と救世主(3) 2022年06月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.