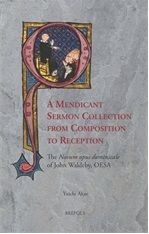
Yuichi Akae
,
A Mendicant Sermon Collection from Composition to Reception. The Novum opus dominicale of John Waldeby, OESA
,
Brepols, 2015
著者の赤江雄一先生は慶應義塾大学文学部准教授で、わが国で西欧中世説教研究を精力的に進めていらっしゃる研究者です。本書は、先生がリーズ大学に提出された博士論文をもとに、ベルギーのブレポルス社から刊行されている「説教
Sermo
」シリーズの一冊として刊行されました(同じ叢書の著作として、本ブログでは
マリア・ジュゼッピーナ・ムッツァレッリ編『言葉から行いへ―後期中世における説教活動の効果性―』
を紹介したことがあります)。
先生の邦語論文としては、以下の研究があります。
「
14
世紀イングランドにおける説教者の図書館―ヨークの一托鉢修道院の事例から―」『西洋史学』
210
、
2003
年、
1-23
頁
「中世後期の説教における
Curiositas
の重要性」『史学』
74-4
、
2006
年、
21-52
頁
「中世ヨーロッパの「マスメディア」―説教集を読む視角と方法―」『創文』
498
、
2007
年、
10-14
頁
「中世後期の説教としるしの概念―
14
世紀の一説教集から―」『西洋中世研究』
2
、
2010
年、
9-20
頁
「聴くことと「見る」こと」『歴史と地理』
671
(世界史の研究』
238
)、
2014
年、
24-32
+図巻末
1
頁
「語的一致と葛藤する説教理論家―中世後期の説教における聖書の引用―」ヒロ・ヒライ/小澤実編『知のミクロコスモス―中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒストリー―』中央公論新社、
2014
年、
14-41
頁
また、本書の紹介・書評として、邦語では以下が挙げられます。
・木村容子氏による書評(『西洋史学』
262
、
2016
年、
88-90
頁)
・坂本邦暢氏による紹介(『西洋中世研究』
8
、
2016
年、
243-244
頁)
本書の構成は次のとおりです。(部・章の標題は木村さんの書評の訳によります。)
―――
図版リスト
文献略号
写本略号
謝辞
翻刻
transcription
に関する注記
序論
第一部 場面設定
第一章 ジョン・ウォールドビーと『新主日説教集』
第二章 説教とアウグスティヌス隠修士会の修道院教育
第三章 説教師の図書館
第二部 『新主日説教集』の説教分析
第四章 ウォールドビーの説教形式
第五章 しるしの概念
第六章 『新主日説教集』の全体デザイン
結論
付録1 説教一覧表
付録2 アウグスティヌス隠修士会ヨーク修道院付属図書館蔵書目録の構成表及び「製本図書」リスト
付録3 『新主日説教集』の典拠
付録4
参考文献目録
索引
―――
序論は、本書の主人公ジョン・ウォールドビーが『新主日説教集』を執筆した時代の背景(教育システム、書物の流通、托鉢修道会におけるアウグスティヌス隠修士会の位置づけ)と本書の構成が紹介されます。ここでは、書物(説教集)の大量産出にとってのペキアシステム(分冊方式により写本作成を容易にする手法。詳細はこちら参照)の重要性を相対化し、托鉢修道会の役割を強調する近年の研究動向が紹介されており興味深かったです。
第一章では、ウォールドビーの経歴(知的背景、高い教育水準、評判など)と『新主日説教集』を中心とした彼の著作が紹介されます。
第二章は、まず『新主日説教集』の序文から、その著作が修道会の若者教育を念頭において執筆されたことを明らかにした上で、説教活動のためのアウグスティヌス隠修士会の教育の状況を描きます。
2003
年の邦語論文も参照。)
第四章は、『新主日説教集』と、ベイスヴォーンのロバートの『説教形式』を比較し、二人が同じ知的背景を有していたことを示すとともに、『新主日説教集』の内容や構成を詳細に分析します。本書で最もページ数が多く、また重要な章です。
第五章は、『新主日説教集』の中で重要なやくわりを果たす「しるし」の概念の分析を通じて、記憶術の問題にも言及しつつ、説教の内容が最終的な聴衆に共有されることをウォルドビーが意図していたことを示す興味深い試みです。(上掲『西洋中世研究』
2
所収論文も参照。)
第六章は、『新主日説教集』の全体的な構成と意図を論じます。ここで興味深かったのは、教理上重要なテーマ(アヴェ・マリアなど)が同説教集で省略されているが、それは1つの日曜説教で扱うには広大すぎるテーマであるため、彼が別途概論を書いて『説教集』を補完している、という指摘です。ここからも、ウォールドビーがその著作の全体を通じて修道会の教育にかかわっていたことがうかがえます。
結論は、以上の議論を明快に整理し、本書の意義を示します。
私の関心よりも少し後の時代の説教を扱っていますが、学ぶところの大きい著作でした。
西欧中世説教に関する研究をいろいろ読んできているつもりですが、その中ではあまり先行研究に対する批判が見られないという印象を持っていました。しかし本書では、史料の綿密な分析は当然として、先行研究も丹念に読み込まれており、先行研究への批判(「範例説教」の範囲についてなど)も見られるのが興味深かったです。
・西洋史関連(洋書)一覧へ
-
Christoph T. Maier, Crusade Propaganda … 2024.03.16
-
Claude Bremond, Jacques Le Goff et Jean… 2023.12.02
-
Valerie I. J. Flint, Ideas in the Medie… 2023.11.12
Keyword Search
Comments










