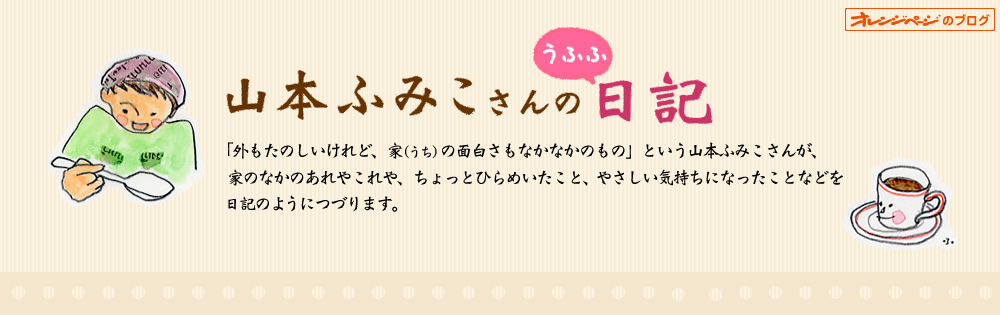サイド自由欄

随筆家。1958年北海道生まれ。つれあいと娘3人との5人暮らし。ふだんの生活をさりげなく描いたエッセイで読者の支持を集める。著書に『片づけたがり』 『おいしい くふう たのしい くふう 』、『こぎれい、こざっぱり』、『人づきあい学習帖』、『親がしてやれることなんて、ほんの少し』(ともにオレンジページ)、『家族のさじかげん』(家の光協会)など。
カレンダー
2025/10
2025/09
2025/07
キーワードサーチ
3人の子どもたちは皆、0歳から保育園に通い、そういうこともあって、わたしは20数年前から、持ちものの名前つけがくせになっている。
布のオムツにも名前をつけた。
肌着にも、小さなTシャツにも。
ズボンにも。
帽子や手袋にも。
ハンカチーフにも。
遠足に持たせる弁当箱や水筒にも。
みかんにも。
バナナにも。
名前つけは、ひと様の持ちものと自分のとを区別するためにするんだと思う。団体生活をする場合には、ひとたび名前のないモノを落せば、すぐに自分のものではなくなり、「落としもの」になってしまう。
名前つけが習慣になってきたある日。
自分の気持ちのなかにある名前つけが、持ちものに名前をつけて無事モノの持ち主を決めるため、なんてことを超えていることに気づく。
名前をつけるときに、モノに何かを宿らせるような心持ちになっている。
「えいっ」(とは声に出さないまでも……)と、何かを念じる。
いろんな事故に遭いませんように。
たのしいことがありますように。
元気で過せますように。
というようなのが混ざった願いを名前にこめる、と言ったらいいだろうか。お守り、といったら言い過ぎだろうか。
しかし、存分に名前つけの腕が(?)ふるえるのも、子どもが小学生のうちだ。
上ふたりの子どもが中学生になったとき、
「わたしたちのパン○○や、ブラ○○にまで、名前つけする必要ある?」
と、詰め寄られたことがある。
た、たしかに、それは不要かもしれない……と言う。
そう言いながらも、お守りをくっつけたい心持ちが、ついネームペンを手に握らせる。
さすがにこのごろは、パン○○や、ブラ○○の名前つけはがまんしているが、右と左の合印でもあるんだからさ、と言いわけしながら、家じゅうのくつしたには、いまだに名前をつけている。
ところで。
いま、小学4年の末の子どもは成長さかんで、ちょっと着たり履いたりした洋服や靴が、あっという間に小さくなってしまう。おさがりに大いに助けられた経験から、好きでそろえたモノは、わたしたちも、もらってもらうことにしている。
好きだった洋服に、白いまんまの名前テープをアイロンで貼りつけて、わたす。
これも、お守りのつもり。
伝わっていてもいなくても、そうせずにはいられない。
ことにおさがりの場合は、そこに新しい使い手の名前が書きこまれるとき、モノは新しい暮らしをはじめる覚悟を決めるのではないかな。

布製の名前つけ用のテープ。
細めの幅、太めの幅のを持っています。
文房具に名前をつけるときは見出し用のシール(インデックス)を
2つに切ったものに書いて、貼りつけます(上からセロハンテープでとめる)。

黒いくつした、白いくつしたなど、大人用子ども用、紳士用婦人用の区別が
つきにくいでしょう? その上、同じ日に何足も洗濯することもあり、
「どれとどれで1足なのー?」と、こんがらがります。
左右を合わせるためにも、合印をつけておきます。
合印は☆と☆、★と★、□と□、○と○など。

わたしが家にいられない日のおやつに、
バナナ王子に登場してもらうことがあります。
最近、実力があって容姿のいい男の子を「〜王子」と呼ぶようですが、
バナナ王子は、古顔です。
なかなかハンサムでしょう?
もちろん実力もあります。

右端は、みかん姫。
子どもの弁当の「食後」に持たせるみかんには、いつもマジックで、顔を描きます。
冬休み明け、学童クラブの保護者会に行ったとき、
壁に、たくさんの、ひからびたみかんの顔が貼りつけてあるのを見たときは驚きました。ちょっとした人気者だったんだそうです、みかんたち。
中学2年くらいになると、「お母さん、みかんに顔は描かないでねっ!」と、
釘を刺されます。
でも、時を隔てると、また描いてもよくなります。
いまは、大学生の二女の弁当には、
みかん姫ほか、にこにこみかん、鬼みかん、イケメンみかんなど、
いろいろ添えて持たせています。