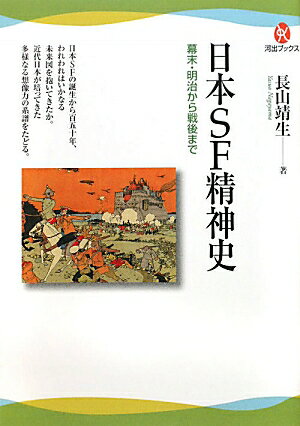PR
キーワードサーチ
フリーページ
ぱふぅ家のお勧めガジェット
セキュリティ対策グッズ
自分買い特集
2005年「役に立つ1冊」
2006年「役に立つ1冊」
2007年「役に立つ1冊」
2008年上期「役に立つ1冊」
2008年下期「役に立つ1冊」
2009年上期「役に立つ1冊」
2009年下期「役に立つ1冊」
2010年上期「役に立つ1冊」
2010年下期「役に立つ1冊」
2011年上期「役に立つ1冊」
2011年下期「役に立つ1冊」
2012年「役に立つ1冊」
2013年「役に立つ1冊」
2014年「役に立つ1冊」
2015年「役に立つ1冊」
2016年「役に立つ1冊」
2017年「役に立つ1冊」
2018年「役に立つ1冊」
2019年「役に立つ1冊」
2020年「役に立つ1冊」
2021年「役に立つ1冊」
2022年「役に立つ1冊」
2023年「役に立つ1冊」
2024年「役に立つ一冊」
2025年「役に立つ一冊」
最新プリンタ
自作PC特集
インフルエンザ対策
花粉症対策
癒やし特集
あったかグッズ
最新PC特集
防災特集
デジタル一眼レフカメラ
フレッシュマンにおすすめ
| 著者・編者 | 長山靖生=著 |
|---|---|
| 出版情報 | 河出書房新社 |
| 出版年月 | 2009年12月発行 |
先日、SF界の重鎮・小松左京さんが亡くなった。小松さんを偲んで、本書を手にした。幕末から昭和 40 年代に至るまで、日本の SF の変遷について紹介している。
著者によると、ペリー艦隊の来航に刺激され、「儒学者の巌垣月洲が安政 4(1857)年に書いたとされる『西征快心編』」(14 ページ)が最初の SF という。この本の主人公は「世界の秩序を回復させると、領土を拡張することなく自国に戻る」(16 ページ)という、儒学の思想に基づいた理想的な人物であった。
明治期に入ると、「尾崎行雄が「科学小説」の語を提示したのが明治 19(1886)年で」(84 ページ)、技術者出身の幸田露伴や、星新一の父で星製薬を興した星一が SF を書いている。
そして、「冒険小説界をリードすることになる押川春浪が『海底冒険奇譚 海底軍艦』を文武堂から刊行して本格的にデビューしたのは明治 33(1900)年 11 月」(110 ページ)になる。
大正期に入ると、ミステリー作家の江戸川乱歩が活躍するようになった。彼の門下に集まった一人、海野十三は現代の SF の直接の先祖とも言える存在である。晩年の海野が才能を認めたのが手塚治虫だった。
戦後になると、「星に続いて、『宇宙塵』の同人からは、小松左京、筒井康隆、豊田有恒、眉村卓、平井和正、光瀬龍、加納一朗、石川英輔、広瀬正などが次々とプロデビューしていく」(187 ページ)ことになる。
「昭和 31 年 7 月に『日本空飛ぶ円盤研究会』が発足した」(182 ページ)が、この中には作家の石原慎太郎(現東京都知事)や三島由紀夫が名を連ねていた。調べてみると、石原さんはネッシー探検隊を結成し隊長としてネス湖に行ったこともあるという。さらに、2007 年に政府が「UFO の存在は確認していない」という答弁書を出したことに対し、「私も見たいと思いますけどね」と答えている。
本書の最後に紹介されている『日本 SF シリーズ』が刊行された時期に生まれた私の少年時代は SF の黄金期だった。小松左京さんの『日本沈没』に恐怖し、星新一さんのブラックユーモアに笑った。筒井康隆、豊田有恒、平井和正、大伴昌司、野田昌宏‥‥こうした人たちの作品を図書館でむさぼるように読んだ。SF/空想科学小説といって馬鹿にしてはいけない。本書で紹介されているように、開国から今日まで、太平洋戦争という弾圧期はあったにせよ、SF は常に自由な上昇志向に支えられてきた。
近代詩や文学史という教科書的な話ではなく、自分に連なっている歴史を知ることができ、じつに興味深い内容であった。
-
【西暦2007年、人類は全面核戦争に突入】… 2025.11.08
-
【三重連星系から人類殲滅艦隊がやって来… 2025.10.27
-
【プログラマにおすすめ】「分かりやすい… 2025.09.14