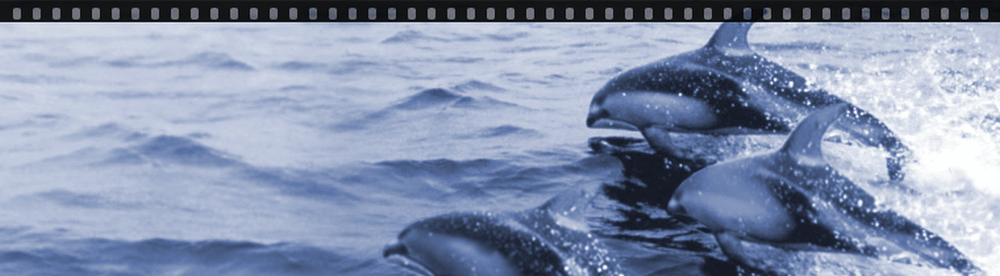全130件 (130件中 1-50件目)
-
移転しました。
続きはこちらに掲載しています。感情の演技の研究の記事一覧|note(ノート)
2025年07月03日
コメント(0)
-
些細な出来事
症状の原因は、些細な出来事だけれど、これまでで一番うれしい出来事ということになっています。この点がどうしても理解できないということかもしれません。これまでもっと大きな出来事が実現していてうれしいと思っているよりも、些細な出来事で生まれるうれしさの方が大きいということですから。
2025年04月02日
コメント(0)
-
セルフハートセラピーの経過
主体的に考えることによって葛藤が強くなったことになります。つまり考え方が間違っていたから葛藤が強くなったわけです。
2025年03月17日
コメント(0)
-
統一しました
従来、感情の演技での反応(抵抗)が強いのは、幸福否定が大きいからと説明されてきましたが、そうではなく葛藤が強いからと考えることにしました。したがって症状の原因は葛藤が強い出来事というふうになります。幸福否定が原因で症状が発症した場合も当然葛藤が強いはずですから、その場合も含まれるわけです。
2025年03月16日
コメント(0)
-
検証課題
あくまで極めて強力な反応(抵抗)が現れた場合1,ハートセラピー(セッション)とセルフの効果の差2,同じ程度の強さの反応でも、課題の違いによる効果の差 (原因かその周辺に関する課題か、そうでないか)3,感情の演技をやる回数による効果の差
2025年03月11日
コメント(0)
-
心理療法はすべて児戯
結局、現行の心理療法はすべて児戯に等しいようです。ほぼ自己治癒力に頼るしかなく、せいぜい自己治癒力が発動するきっかけを与えるに過ぎないようです。症状(問題)が軽ければ、それでいいのですが、心理療法を受ける人はそうでないことの方が多いでしょう。笠原敏雄先生が開発した心理療法(幸福否定理論と感情の演技法)で多少発展したわけですが、まだまだ途上段階。「瓢箪から駒」を期待するしかなさそうです。とはいえ困り果てると何らかの心理療法を受けるしかないわけです。一つ言えることは、しばらく受け続けてダメだったら、すっぱりと止めてその理論(考え方)に引きずられていてはいけないということです。むしろ逆から攻めるといいように思います。
2025年03月05日
コメント(0)
-
安易に大丈夫と思うと発症する
安易に大丈夫と思うと発症するようです。30過ぎてかなり落ち込むということは、かなり煮詰まっているということ。安易に、大丈夫とか何とかなるとか思わないこと。大丈夫じゃないかもしれないが、何とかならないかもしれないが、何とかやっていくしかしょうがないと思うこと。そうすると治るような気がします。
2025年02月25日
コメント(0)
-
記憶は必ず消えているのかどうか
症状の原因となった出来事の記憶は必ず消えているのかどうか、おそらく判明していないのではないかと思います。しかしまた確かめようがありません。少なくとも治った例の大半で原因が突き止められ消えていたことを確認しなければならないからです。原因の出来事の記憶が消えていない例が数多くあるのかもしれません。原因として幸福否定の要素が過半の場合は消えていて、過半に満たない場合は消えていないのかもしれません。後者の場合はダブルバインド理論を適用すると良いわけですが、裏の原因を解消する手法として「感情の演技」を使えるのかもしれません。課題を設定するときに、いわば退歩するうれしさ、退化するうれしさ、退避するうれしさ、なども、本心からのうれしさとするわけです。ただそれが単純な退歩ではなく行動に結びつけるための退歩でなければなりません。裏の原因は結局「適切に行動できないこと」だからです。
2025年02月24日
コメント(0)
-
「感情の演技」療法として純化する
やはり理論はあまり関係ないようです。どういった理論に基づいて感情の演技の課題を設定するかはそれほど問題ではないようです。とにかく極めて強力な反応(抵抗)が出るようにすればいいだけのようです。むしろ理論は邪魔になるのかもしれません。今回のセルフの場合も、たまたま偶然にちょっと試しにやってみるかと、やってみたらすぐに極めて強力な反応が現れたわけで。ちなみに以前笠原敏雄先生からセッションを受けていた時は、一番強い反応が現れたのは(けれども極めて強力とまではいかない)、「日本でトップクラスの知的な能力を発揮してうれしい」でした。しばらく続けて、あまりに非現実的なので、笠原先生にこんなことしていて何か意味があるのかと追及したところ、別の課題を設定してもらったという経緯があります。結局その後極めて強力な反応が現れることは一度もなく、2年ほど受け続けても効果はなかったわけですが、もしあのまま「日本でトップクラスの知的な能力を発揮してうれしい」で続けていたら、極めて強力な反応が現れていたのかもしれないという疑念は残ります。もしそうだったら私の人生もかなり変わっていたかもしれないのですが、ともかく感情の演技の課題設定ではどんな理論にもとらわれないで、むしろ冗談半分で設定した方がいいのかもしれません。
2025年02月20日
コメント(0)
-
症状の原因は「自分に噓をつくこと」(夏目漱石)
夏目漱石は、症状の原因は「自分に噓をつくこと」だと考えていたようです。この場合の自分とは自己や自我ではなく「自然」と言い換えています。一旦嘘をついてしまうとその後なかなか回収するのは大変です。漱石もそう分かったところで自分ひとりではどうすることもできなかったわけです。
2025年02月18日
コメント(0)
-
「主体的に考える」とは?
「主体的に考える」とは、「身の程をわきまえない」ということかもしれません。
2025年02月15日
コメント(0)
-
感情の演技
感情の演技で、一旦、ある課題で極めて強力な反応(抵抗)が現れると、これまで一度も極めて強力な反応が現れなかった課題でおこなっても、極めて強力な反応が現れるようになります。これは何を意味しているのでしょうか?おそらくストレス理論やトラウマ(幼少期の)理論が間違っていることを証明していると言えるようです。しかしその一方で幸福否定理論の欠陥をも証明することになるかもしれません。ダブルバインド理論の正当性を証明することになるのかもしれません。
2025年02月09日
コメント(0)
-
セルフハートセラピーの実験
セルフハートセラピーを始めてほぼ2ヶ月になりました。感情の演技は、症状の原因かその周辺の課題でないと、極めて強力な抵抗(反応)が生じない限り、かなり強い反応が生じても、いくら長期に渡って続けても効果はほぼないことが明らかになっています。では、原因とは関係がないと思える課題で、極めて強力な抵抗(反応)が生じた場合はどうなのか?セルフハートセラピーでこれを検証するわけです。
2025年02月03日
コメント(0)
-
セルフハートセラピー
現在、セルフハートセラピーをやっています。通常は、抵抗が極度に強い課題を自分で見つけるのは極めて困難だし、見つけられたとしても、感情の演技を続けるのが困難なため、セルフはほぼ無理なのですが、たまたま偶然か昨年12月に極度に強い課題を自分で見つけることができました。
2025年01月30日
コメント(0)
-
本人の願望を重視
やはり大きな変化を導くには、本人がたいして重要視していないことを、重要視していないのは幸福否定が強いから、それは「本心」の願望だから、と理屈付けして、課題にするのは良くないですね。幸福否定理論をそこまでは適用できないようです。本人の意識での願望を重視した方が良いようです。こうした例の場合は、発症は幸福否定の関与が小さいのでしょう。
2025年01月27日
コメント(0)
-
実際の心理療法ではどう進めていくとよいのか?
1,幸福否定により発症している例が多くある。これは事実です。2,(ほとんど)すべての人には幸福否定の習性がある。これも確からしく思われます。しかし幸福否定(が関与しているがそれ)によらない発症もまた多くあることも確からしく思われます。結局つまりあらかじめ症状の原因はわからないわけで、実際の心理療法は手探りで始めていくしかないわけです。幸福否定理論に基づいて行う場合、症状の原因が推定できるようになるまでに半年くらいかかります。幸福否定が原因らしいと推定できる場合はそのまま継続したらいいわけですが、もしそうでない場合は、ハートセラピーでは、(総じて何らかの失敗にともなう)葛藤や不安や自己嫌悪などとその表面的な解消が原因と考えますから、その理論に基づいて行ったらいいわけで、具体的には、(1)失敗しないようにする、(2)失敗しても大きく落ち込み過ぎないようにする、(3)表面的な解消ではなく本格的に解消できるようにする。となるわけですが、実際どうすればいいのかが確立されていません。文字通り手探りで行なっていくしかないわけですが、どのくらいの期間継続したらよいのかはわからず、目算もなくおそらく1年、2年と長期間続けなければならないことは予想されます。
2025年01月17日
コメント(0)
-
どの方向に心を変えるか
症状の原因は、状況と心(幸福否定などなど)の関数ですから、そして心理療法の目的は心を変えることでしょうから、状況を変えれるような方向に心を変えていかなくてはなりません。ハートセラピーのやり方で言えば、1,どういう方向性で面談するか、2,感情の演技での課題をどういう方向性で設定するかが非常に大事になってきます。単に幸福否定を弱めたら良いだけではないのです。これは他のやり方の場合も当てはまるでしょう。つまりたとえば認知の歪みを重要視するやり方の場合も、単に認知の歪みを改善すればよいだけではないのです。
2025年01月14日
コメント(0)
-
個人個人千差万別全く天と地ほども違う
心理療法や心理学の世界だけではなく、どの分野の研究者も一般化普遍化したがるようです。しかし人間として共通に成り立つことはむしろ少なく、個人個人千差万別全く天と地ほども違うと考えた方が良さそうです。なので、例えば「ストレスによって何らかの症状が発症する可能性がある」などという言い方は、主語「人間は」が隠されているわけで、そもそも間違っているわけです。言えるとすれば、「人間は」ストレスで発症するかもしれなく、ストレスで発症しないかもしれなく、ストレスがなくても発症するかもしれなく、ストレスがあれば発症しにくいかもしれない。などとなるわけです。これはすべての理論に当てはまるでしょう。もちろん幸福否定理論にも。また厳密に言えばすべての医学理論にも当てはまるでしょう。というわけでどんな理論も一般化してはいけないわけです。ただそれでは実用性ゼロになってしまうので、一般化するのはやむを得ず、しかしあくまで便宜的ということをわきまえて謙虚な姿勢で心理療法を研究し、心理療法を実施したいものです。
2025年01月07日
コメント(0)
-
願望実現のためのツール
感情の演技は、幸福否定には関わりなく、願望実現ツールの一つと考えた方が良いかもしれません。どの程度強力なのかは未知数ですが。
2025年01月04日
コメント(0)
-
本心の解釈は謎
主体的に考えると言っても、如何様にも解釈できるわけです。感情の演技で極めて強い反応が持続するのは、意識ではなく本心が解釈している主体的という状態に対して極めて強い抵抗があるということでしょう。本心はどのように解釈しているのか謎です。というより完全に主体的に考える状態はあり得ないわけで、とすると極めて強い反応が現れないことはあり得ないということなります。
2024年12月30日
コメント(0)
-
「主体的に考える」とはどういうことか?
試しに感情の演技を自分でやってみたところ、極めて強い反応が現れました。頻繁に寝落ちしてしまいます。「主体的に考える」ことに極めて強い抵抗があることがわかりましたが、「主体的に考える」の意味がどうも自分ではあまりわからない。
2024年12月28日
コメント(0)
-
現実逃避することが大事
イエローサブマリンの少年と統合するということは、別の言葉で言えば現実逃避するということでしょう。サブマリンの少年にとって壁の中で夢読みすることが、現実逃避であり天職になるわけです。その場しのぎの現実逃避ではなく、きちんと現実逃避しなければならないということでしょう。
2024年12月23日
コメント(0)
-
感情の演技での反応について
感情の演技で、幸福に対する抵抗により生じる反応は、ストレス反応だという説があるようです。ストレス反応というより葛藤反応だとするのがより正確と思われますが、そうすると、葛藤理論(村上春樹療法)により、幸福否定理論とストレス理論が統合されていると解釈できるかもしれません。問題は、なぜ、極めて強い反応が起これば効果がそれなりにあるのに、(一段弱い)かなり強い反応では効果がほとんどないのか。反応の強さの差はそれほどあるとは思えないのに、効果の差が大き過ぎる理由は?マラソンなどでランナーズハイの状態に達するか否かというようなことかもしれません。ではそれがストレス反応にしろ葛藤反応にしろ幸福抵抗反応にしろ、長期に渡って続けていると、どうなるのかという問題が生じます。ストレス反応ならただストレスに慣れるだけで大きな変化は望めないのかもしれません。しかしそのストレスに慣れたのだとしたら反応は弱くならないとおかしいのでは?そうすると逆に反応がかなり強いままならストレスに慣れたというより克服したと言った方が正しいのかもしれません。しかし克服したのなら反応が弱くならないとおかしいでしょう。つまりストレス反応とするのは無理があります。あるいは感情の演技はストレスにはほぼ無力ということになります。葛藤ならどうでしょう。反応がかなり強いまま、つまり葛藤が強いままなら、克服したとは言えません。
2024年12月14日
コメント(0)
-
主体的に考える
主体的に考えるようになると「抵抗」が起こるようです。つまり「主体的に考えるようになったこと」が症状の原因になることもあるわけです。これには2つのパターンがありそうです。1,抵抗が起こり主体的に考えるのを止め、主体的に考えるのを止め続けるために症状が発症する。2,主体的に考えることのうれしさだけを否定して、主体的に考え続けるが抵抗が起こり症状が発症する。
2024年12月03日
コメント(0)
-
発症のメカニズムは?
良いことも悪いことの同時発生で発症するという説が正しいとしたら、そのメカニズムはどうなるのかという疑問が出てきます。例えばストレスで発症する場合と幸福否定で発症する場合とでメカニズムは同じなのか?など様々な疑問が出てきます。
2024年11月15日
コメント(0)
-
北村透谷と村上春樹
北村透谷は、イエローサブマリンの少年と共に現実に生きたいと言いました。しかしそれは不可能でした。村上春樹は、まずサブマリンの少年と分離して、その後壁のある街で一体化し、半身は街に残り、残りの半分で現実で生きると言います。それが少年を生かす道なのでしょう。
2024年11月15日
コメント(0)
-
矛盾の強さが問題
感情の演技は原因と関係あるなしに関わらず有効のようです。極めて強力な反応が出た場合に限りですが。課題を設定するに際し幸福否定理論は必ずしも考慮しなくても良さそうです。反応の強さは矛盾の強さに大きく影響されるようです。これも弁証法です。続けることによって、矛盾を少しづつ解消していくわけです。矛盾が弱まり適切に行動できるようになると、問題が解消されていくわけです。
2024年11月11日
コメント(0)
-
「壁」と呼ばれた少年
イエローサブマリンの少年は、「壁」と呼ばれた少年でしょう。「壁」と呼ばれた少年は、よろこびもこころよさも美しさも消えた、すきとおった街に住んでいます。少年の手のひらには言葉がひしめき、そこでは何を語ることも許されています。そうして現実の舞台から退場するのです。
2024年11月04日
コメント(0)
-
幸福否定?
イエローサブマリンの少年と統合しようとすると、かなり体調が悪くなるようです。危機的な状況ともいえるでしょう。これは幸福否定の一種という気もしますが、本当のところはわかりません。しばらく続けてみないとですね。壁の内の自分と統合したらいいだけなので、それほど問題はないはずですが、実際は壁の内の自分と壁の外の自分を区別するのはなかなか困難です。
2024年10月26日
コメント(0)
-
人間のパターンの違い
「進歩」を重要視するのがダメなのではなく。人によって、努力することによって進歩する人と、暢気に構えていることによって、結果的に進歩してしまう人の2つのパターンがあるのかもしれません。
2024年10月19日
コメント(0)
-
ハートセラピーとの違い
ハートセラピーと従来の幸福否定理論に基づいた心理療法の違いは、後者が「進歩」という観点を重視しているところです。これはおそらく後者の心理療法家の笠原先生や渡辺先生が、自身が能力がかなり高く、進歩することに極めて大きな抵抗がない人であるからだと思われます。そのためクライアントの能力の低さや進歩することに対する抵抗が気になるわけです。ハートセラピーのもう一つの違いは、「変わっている」のを簡単には幸福否定と結び付けないという点です。それは、笠原先生は「まともな人」なため、クライアントの「変わっている」のが気になり、つい幸福否定と結び付けがちになるからでしょう。(先生は超能力の研究をしているので、一般人から見たら、かなり変わっていることになりますが)また、幸福否定一本槍では、当てはまらない例も多いと考える点です。一本槍では覚束ないということは他のどの心理療法の理論にも当てはまると思います。
2024年10月16日
コメント(0)
-
行動療法
大事なことは行動することですね。それも適切に。「街のその・・・」でも自分(の片割れ)を信じて跳ぶことが推奨されています。この場合は自分を信じるということなので、比較的簡単な描写で終わっていますが、現実はもっと難しいでしょう。なので心理療法は、自分にとって重要な人を信じて適切に行動できるように変化させれるかどうかが鍵となるでしょう。
2024年10月15日
コメント(0)
-
肯定療法
肯定療法を始めました。人に迷惑かけたことも良かったこと。OK人を欺いたことも良いこと。OK人に冷たくすることも良いこと。OK(人に迷惑をかけるなどすると当然嫌われますが、)嫌われることも良いこと。OK(嫌われる勇気とはこのことかもしれません)などと素直に無理なく思えるようにする療法です。
2024年10月15日
コメント(0)
-
感情の演技法について
幸福否定理論では技法としては一つ「感情の演技」だけで、極めて強い抵抗(反応)が現れない限り、効果はほとんどありません。他の心理療法では、何かもっと効果的な技法があるのかもしれませんが、なさそうです。ここで、疑問点は、1,原因とはあまり関係なさそうだが、極めて強い抵抗が現れる場合、感情の演技は効果があるのか?2,他の心理療法例えば村上春樹療法を行う際、感情の演技を併用した場合、単体で行った時と効果はどう変わってくるのか?
2024年10月10日
コメント(0)
-
葛藤が原因
葛藤は原因だろうと思われます。症状や問題が発現する時は、「落ちて、それ以上に上がって、またやや落ちて、結局元のあたりになる」ということだろうと思われます。結局元のあたりに落ち着いたとはいえ、こうした経験を経ていますから、葛藤は大きくなっているわけです。
2024年10月10日
コメント(0)
-
「村上春樹」療法と感情の演技法
「村上春樹」療法と感情の演技法は、並立するものでしょうか?暢気療法は、簡単に言えば「幸福とは暢気なこと」というふうに幸福否定理論を変えただけなので、感情の演技法と並立できるわけですが、当てはまる例はそう多くはないでしょう。「村上春樹」療法において感情の演技法を適用する場合、感情の演技法の個々の具体例を「村上春樹」療法の理論で説明できなければなりません。それは可能でしょうか?
2024年10月09日
コメント(0)
-
「村上春樹」療法と暢気療法の整合性
「街とその・・・」は、かなり暢気な小説です。なので「村上春樹」療法の書き割りには暢気療法が潜んでいると考えてよさそうです。
2024年10月05日
コメント(0)
-
気のゆるみ
発症するのは、基本的に「ほっ」とした時です。昔から志望校に合格した直後の発症など一部のケースで「気のゆるみ」とされていましたが、本質を突いていそうです。ただし気のゆるみが原因なのではないでしょう。
2024年10月03日
コメント(0)
-
現実を変えるには
「街とその不確かな壁」では、現実を変えるには、イエローサブマリンの少年と統合して再分離するだけでは足りず、壁の内と外の主人公が統合した後、さらに少年時代の記憶をかきかえる必要があることが仄めかされています。
2024年10月01日
コメント(0)
-
イエローサブマリンの少年とは?
イエローサブマリンの少年は、弱く頑ななため現実には生きられない心のことでしょう。しかし純粋なため優れた認識力を備えた心でしょう。かって谷川雁が「詩的認識力と人格的理解力は相殺し合わないものか」(暖色の悲劇)と問いかけましたが、イエローサブマリンの少年と統合することにより、詩的認識力と人格的理解力の統合が行われるのでしょう。壁の内の大人は少年との統合を拒もうとしますが、これが、幸福否定、認知の歪み、トラウマ、ストレス脆弱性などと言われるものの正体だろうと思われます。
2024年09月30日
コメント(0)
-
症状などの原因は、関数。
症状や問題の原因は、性格傾向などの心と外界状況と脳などの身体的なものとの3つの関数ですね。その内、心理療法で扱えるのは性格と状況ですが、性格のどの部分が症状や問題と深く関連しているのか見極めるのが難しい場合も多々あるでしょう。状況は心理療法で変えられる部分もありますが無理な部分もあるでしょう。また3つは相互に影響し合っていますから、1つだけ解決しただけで大丈夫な時もあるでしょう。結論として心理療法では、状況と性格の関連をよく見極め、状況の一部を変えれるような方向に性格の一部を変えていくのが良いと思われます。
2024年09月27日
コメント(0)
-
「村上春樹」療法での統合に対する抵抗心
「村上春樹」療法では、イエローサブマリンの少年との統合に対する抵抗は、ある出来事が起こった時に理由のない嫌悪感が生じる場合に現象化していると思われます。ちなみに「街とその不確かな壁」に基づいた心理療法を、「村上春樹」療法と名づけることにしました。
2024年09月24日
コメント(0)
-
「街とその不確かな壁」の内での生活と現実
小説では壁の内から戻った「影」の現実がかなり肯定的に描かれていますが、これは問題や症状が軽いからだと思われます。(一部恋愛の問題では解消しきれていない様が描かれていますが)重い場合は、壁の内での状況が現実に浸潤してきて、かなり苦しくなります。分離しないといけないわけです。
2024年09月23日
コメント(0)
-
最も困難な統合
小説では少年Aとの統合は、割とあっさり出来てしまっていますが、心理療法に於いてはここが一番山場になるでしょう。まず少年Aを見つけ出さないと始まりません。次に小説でもそう描写されていますが、本人は、ためらい、不安になり、拒否的な反応を示します。そして統合するのは大人A(現在の本人)ではなく大人Bとです。
2024年09月18日
コメント(0)
-
「街とその不確かな壁」の心理療法
「街とその不確かな壁」では、イエローサブマリンの少年は壁の内に取り残されるわけですが、彼には壁の内という現実と切り離された状態でするべきこと(夢読み)があります。つまり一度落ちた人は、壁の内に分離されることによって、ようやく自分が自分であることを取り戻せることが示唆されています。それと同時に、17歳時の恋愛は現在の偽りの記憶に過ぎなかったと思わせるような終わり方になっています。これは幸福否定理論で言う「記憶の歪曲」に該当するのかもしれません。
2024年09月16日
コメント(0)
-
統合と治療
少年A(イエローサブマリンの少年)と統合するのは、隙間時間に行うと良いようです。
2024年09月15日
コメント(0)
-
「街とその不確かな壁」(村上春樹)と心理療法
「街とその不確かな壁」では人の心は4つの象限に分かれています。少年A(イエローサブマリンの少年)、少年B(17歳)、大人A、大人B(壁の内で夢読みしている)それぞれ本体と影があるので8つですが。これらの分離・統合・再分離が再生の物語という体になっています。その中でもクライマックスは少年Aと大人Bの統合と分離です。その結果、大人Aは再生を果たして病気などが治り生き直すことができるわけです。
2024年09月03日
コメント(0)
-
葛藤を弱めることが一番大事
やはり心の葛藤を弱めることが一番大事で、葛藤を放置したまま幸福否定を弱めることに囚われていると、効果は限定的になるということでしょう。
2024年08月17日
コメント(0)
-
本心と意識のずれの影響が大きい
本心(表面的な)と意識があまりずれていないときは、幸福否定理論が当てはまり、ずれが大きい場合は、当てはまらないのだと思われます。また、深いところの本心は到達ほぼ不可能なため、何とも言えないのだろうと思われます。つらい出来事があり、そのため葛藤が大きくなり、と同時にうれしい出来事が生じたときに、問題なり症状なりが発現するわけですが、その時、(意識のではなく本心の)うれしさが大きいと幸福否定理論が当てはまり、葛藤の方が大きいと当てはまらないのだと思われます。いずれにしろ、葛藤を弱める方向に心理療法を進めていかなければ、効果は表れにくいわけです。
2024年08月07日
コメント(0)
-
「暢気」療法の有効性は?
「暢気」療法は、いちおう幸福否定理論を適用して心理療法を行っているうちに、派生して出てきた療法です。しかし「暢気でいられること」が発症や症状持続の原因とは考えにくいようです。「暢気」療法で感情の演技を続けて好転した方はいないようなので、暢気療法が有効かどうかもわかりません。仮にもうしばらく続けて有効だと判明しても、幸福否定理論の確からしさを証しすることになるのかどうかもわかりません。
2024年07月17日
コメント(0)
全130件 (130件中 1-50件目)