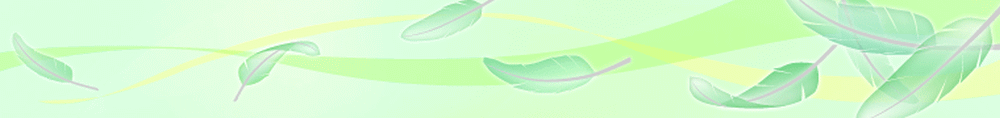全9531件 (9531件中 1-50件目)
-

商品解説詩012「犬」
朝が始まる。意識の海面下から浮上する際、蜘蛛の巣状の粘着質を帯びた憂鬱が襲う。コルチゾールの分泌過多による起床時特有の精神的重圧が、全身に絡みつく。だが、目蓋という有機的なシャッターを開放することで、その重力が錯覚に過ぎないことを知覚する。蜘蛛の巣のように重たい気持ちも、開くことで、思った以上に軽いことを知る、ドアの前で、いつもの言葉。それは見切り発車のようなニュアンスを帯びていることを、自分は知っている。頭の中のガスの元栓を締め、窓を閉める。窓の外では、隣の建物の屋上で鳩が数羽、朝の光を浴びている。その中に一羽だけ、明らかに人間の顔をした鳩がいる。眼が合った。人間の顔をした鳩は、困惑したような表情を浮かべている。隕石落下から十二年。こういう光景はもう日常だ。「いってきます!」 *部屋にあるのは段ボールハウス。厳密には、『LIXIL』と印刷された引越し用段ボールを解体し、防水スプレーをかけて強化した手製の住居。継ぎ目には布テープが蝶番のように貼られ、内部には飼い主の古いセーターが敷き詰められている。その段ボールハウスの中で、その声を聞いた犬は、高タンパク・低脂肪の配合飼料「ホネッコ・プレミアム」や、必須アミノ酸スコアが計算され尽くしたドッグフード、あるいは深海魚のパテを用いた高級缶詰をボウルに満たしている。 だが、その愛すべき供物に、網膜の焦点すら合わせない。視線は、フラクタル図形のように乱雑に積まれた洗濯籠へ、レーザーのように照射される。洗濯籠に入れられた靴下や服を見ている。その洗濯物の匂いは、こう語っている。疲労、睡眠不足、ストレス、しかし安定。飼い主は仕事へと出かけてしまった。だから飼い犬は散歩へと出かける。脱皮するように四つん這いの姿勢を捨て、直立二足歩行へと移行する。脊椎が悲鳴を上げ、関節がポキポキと乾いた音を立てる瞬刻の陶冶。ズボンを着て、足が長い、詩的。鏡を見る。洗面所の鏡だ。ひび割れている。三ヶ月前、飼い主が酔って転んだ時にできた傷だ。その鏡に映る自分の姿。柴犬の頭部。人間の上半身。Yシャツを着た柴犬。シュールだ。しかし、これが日常だ。帽子をかむって、纏綿たる執着と、玄関で靴を履いて、真摯なる態度。人間だった犬にとって、外の世界は敵地だ。いつ襲われるかわからない。いつ捕まるかわからない。いつ殺されるかわからない。だから、武装する。ポケットに、小型ナイフを忍ばせる。刃渡り七センチ。違法ではない。ギリギリ合法。護身用。本当は拳銃が欲しい。しかし、犬に銃の所持許可は下りない。元人間でも、駄目だ。法律がそうなっている。この犬の脳は、人間の脳と犬の脳の中間だ。ハイブリッド。キメラ。隕石の影響で、遺伝子レベルで変異している。前頭前野は人間に近い。しかし、扁桃体は犬のままだ。だから、理性と本能が常に戦っている。もう一つ、ポケットに催涙スプレーを入れる。これは合法だ。熊用のもの。射程距離五メートル。風向きに注意が必要だ。―――さあ、戦闘準備だ。 *そこに何があるのか、何と戦っているのか、それはわからな―――い・・。実存的不安という亡霊と戦っているのか。 あるいは、都市という巨大な消化器官に飲み込まれないように抗っているのか。リスクは大きく、報いは少ない。旗を掲げろ、アクセル・エルンバッハ宣言から十余年・・・。宣言の瘢痕は政策文書や新聞の端に乾き、行政の負担として残る。記録は官報のデジタルアーカイブに残り、公共空間のコンクリート下に埋められた配管のように、見えないところで効力を保っている。宣言から一年後、アクセル・エルンバッハは暗殺された。犯人は、元人間のままの人間だった。動機は「犬のくせに生意気だ」裁判では、精神鑑定の結果、心神喪失とされ、無罪になった。世界は変わったが、虚無の味だけは変わらない。 *階段を下りながら、締まりのない足をいい加減に運ばせて転びそうになったので、ホイッ、ホイッ、と掛け声をしながら下りる。犬から人間になった身体には、未だに四足歩行の名残が筋肉の配置に残っている。大臀筋と脊柱起立筋の連動が不完全で、二足歩行には常に意識的な制御が必要だ。転びそうになるたび、尾骨のあたりに幻影の尾が蠢く感覚がある。そして、飼い犬のことを考える。―――心の中の辿りにくい道程も、嗅覚が説明する。少し前は、ポップコーンの匂いをさせていた。今日は、何を食べてくるのだろう。『犬は形態変化型の獣人種』ということになる、あるいは―――『人狼』の方がいいのか・・。獣人特例措置区域で育った血統書付きの珍しい犬で、小学校ぐらいの学力がありながら、犬のふりをしながら過ごしている。見落としてしまいそうなPOINTだけどこれが重要だ。だから、人権がない。財産権がない。選挙権がない。労働権がない。しかし、犬として過ごすことで、逆に自由がある。誰も監視しない。誰も干渉しない。ただ、犬として扱われる。それだけだ。学者たちは『モジュラー挙動』『後天的形態転換』『環世界遺伝子活性化』などの専門語を並べ、技術的なレポートを積み上げていく、ポエム詩の時間だ。「(・・・・・・最初は、怯えていた。最初の三日間、犬は何も食べなかった。ドッグフードを皿に入れても、見向きもしなかった。ただ、段ボールハウスの中で、丸くなっていた。四日目、自分の食事を犬に分けた。白米。味噌汁。焼き魚。犬は、それを食べた。少しだけ。五口程度。しかし、食べた。五日目、もう少し食べた。十口程度。六日目、さらに食べた。二十口程度。一週間後、犬は普通に食事をするようになった。面倒な犬ほど、可愛い)」トイレを失敗した時。例えば、物を壊した時。例えば、散歩の途中で動かなくなった時。決して怒らない。ただ、微笑んで、「面倒な犬ほど、可愛い」と言う。、、、、、、、、、、世界を救う愛の言葉だ。お金をテーブルに少し置いてくるのを忘れなかった。あまり持たせすぎると帰ってこないような気がして、簡単な食事と、電車賃ぐらいのお金だ。これは信頼と拘束の絶妙なバランスシートだ。あまり持たせすぎると、自由意志という名の悪魔が囁き、帰還しない可能性を統計的に理解している。元は人間だった犬というのは、世間一般における育て方にも、時折過去を追体験したがるものらしい。とりたてて、ペットショップのマニュアル、正式には『旧人格保持型獣人種飼育ガイドライン』発行元:日本獣医師会。ページ数:二百五十ページ。価格:三千円。そのマニュアルの第七章の心理的ケアの、第三節の過去の追体験には、こう書かれている。ブログ、掲示板、SNSにおける『散歩行かせろ』よりはいささかマシだと思う。『元人間だった犬は、定期的に人間だった頃の行動を、再現したがる傾向がある。これは、アイデンティティの維持のために必要な行動であり、抑圧すべきではない。むしろ、積極的に機会を与えるべきである。ただし、過度な追体験は、現実との乖離を招き、精神的不安定を引き起こす可能性がある。適度な頻度と時間を設定することが望ましい。推奨頻度:週一回程度。推奨時間:二時間から四時間程度。』いつか一緒に散歩をしてみたいという気持ちもあるが、人間と犬というのは家族や友達にはなれても、人間同士、犬同士のような関係にはなれない―――らしい・・。いばら荊棘の道だ。 *蟻のように人がうごめく街路。零細や家族経営のこぢんまりとした会社が集まる、ちょっとしたオフィス街。昭和レトロとサイバーパンク・・。時間の歩みが急激に加速したように感じられる、駅スペース。犬の時間感覚は、人間のそれとは異なる。犬は、時間をより短く感じる。一時間が、三十分くらいに感じられる。これは、脳の情報処理速度の違いによる。だから、駅の喧騒は、犬にとっては、超高速で再生されているビデオのように感じられる。人々が、早送りで動いているように見える。夜、霧の底に沈んで鋼鉄のように青ざめていた町は、細長く湾曲した白魚のくねりのその姿だけを残して、何処かへ泳ぎ去ってしまったのだろう―――か。―――朝。 *子供の頃、自分は人間だった。ホモ・サピエンスだった。 遺伝子配列に異常はなく、食物連鎖の頂点にいると錯覚していた。けれど、北半球に隕石が墜落し、未知の宇宙放射線あるいはウイルス性因子が散布されてから、世界は書き換えられた。それは従来の進化論を書き換える水平遺伝子移行を引き起こした。隕石に含まれる外来性RNAが哺乳類のゲノムに組み込まれ、種の壁を越えた形態変化を可能にしたのだ。変化はラマルク的で、環境への適応というよりは、ある種の美的意識のように個体の深層心理を反映するもの・・・・・・。隕石の衝突から二十四時間後。世界中で、異変が報告され始めた。動物が、人間の形質を獲得している。人間が、動物の形質を獲得している。最初は、局所的な現象だと思われた。隕石の落下地点周辺だけの現象だと。しかし、違った。全世界で起こっていた。アメリカでも。ヨーロッパでも。アフリカでも。南米でも。オーストラリアでも。そして、特定の動物だけではなかった。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫、ありとあらゆる生物が影響を受けていた。街を出れば、かつて神話や宗教画の中にしか存在しなかった、天使や悪魔がいて、犬や猫は二足歩行し、スーツを着て株式市況を論じている。犀は警備員になり、象は重機オペレーターになり、麒麟や獅子は企業のCEOとして君臨している。 ダイバーシティ多様化という言葉が、具現化した時代だ。それが自分と同じような境遇かは知らない。かつて黒板の前で、先生が説明していた。歴史とは、様々な偏見や差別との闘争であり、それを取り締まる法体系の進化であったと。 しかしいま、その法は種の壁を超え、カオスの中に溶解した。「二〇一二年:隕石衝突。世界変容開始」「二〇一三年:旧差別禁止法廃止」「二〇一四年:新平等法施行」「二〇一五年:獣人特例措置法施行」「二〇二〇年:現在」「(世界五分前仮説とか、水槽の脳も好きだけど、この世界は隕石という誘引剤で、もう一つの世界にすり替わった、という哲学の方が好きだ)」、、、、、、、、、、、、犬だって歩けば棒にあたる。 *町のあるところには、川がある。いまでは、バス停や駅があり、学校や消防署や警察署という権力装置が配置される。それが僕等の、川だ。川は最初、人知を超えるものであり、生活に欠かせないものだったが、その固定点を変化させた。多くの市区町村では、いざという時に向かう避難場所や、災害想定が記されているハザードマップを作成する。避難場所の四角いアイコン、想定災害の色分け、水位と堤防天端高の差し引き計算。川に橋を作る目的は便利だからだ。けれど橋を作った時に川はもう、三本の線で足りる存在になった。 *バスのサスペンションに揺られながら、溝池の底へ落ちていった硬貨のような気持ちになる。車輪が外れて、電線に世界の常識が引っ掛かっていたとしても、 ア ビ スそういう奈落の底は消えない。バスは都市部から郊外で停車した。郊外は森で、研究所がある。『対・超常存在殲滅機関』の方が分かりやすいかも知れない。研究所までの道のりで、セキュリティ・クリアランスに応じた、防弾ジョッキと拳銃が用意されていて、ヘリコプターに乗り込む。軍用ヘリコプターのローター音に包まれていると、いつもの愚痴っぽい声が聞こえてくる。「犬が人間にさせられている世界はひどいものだ」と、所長が言う。元はハスキー犬だった。しかしいまは、ロシア人っぽい顔立ちになっている。ウォッカやコサックダンスは嗜まないが、プロテインは摂取している。飼い主が筋トレ系のユーチューバーだったという話をいつか聞いた。「隕石には現代科学では処理しきれない様々な効果があって、世界のバランスは見事に壊れてしまった」計器盤の一角に貼られた姿勢制御のチェックリストのように、、、、、、知っている。、、、、、 、、、、知っている―――つもりだ。犬人間達の間で、新しい宗教が生まれた。『原初回帰教』という名前だ。その教義は、簡単に言えば、世界は間違っている。我々は、元の姿に戻らなければならない。そのためには、新しく生まれた存在を排除しなければならない。天使と悪魔を殺すことは、世界を浄化する行為である―――云々。この宗教は、急速に広まった。現在、約三十万人の信者がいる。そのほとんどが、元動物だった人間だ。政府は、この宗教を禁止しようとした。しかし、失敗した。何故なら、信者が多すぎたからだ。そして、信者の中には、政治家や警察官や軍人も含まれていた。だから、政府は諦めた。原初回帰教を、事実上黙認している。遊園地ネズミーランドに不時着し、グロテスクなほど愛らしい小さな天使や、冒涜的な形状をした悪魔の眉間に鉛の弾を沈めてゆく。 ヴェンデッタ犬人間達にとってそれは正当な報復なのだ。というか、 リチュアル犬人間にとってその報復は宗教的な儀式へと昇華されているので、誰かが倫理的な介入をすることは不可能だ。『犬が人間を飼う』というのは前時代では、おそらく誰一人考えないものだった。けれど、長い間にしみついた習性は、『人間となった犬』にも変わらず受け継がれている。それに反抗する奴もいて、実験材料として、目玉をえぐりとったり、ムカデ人間的処置として、尻と口をくっつけてみたりするが、正直あまり美しい行為とは言えない。 オリジナル・ヒューマンけれど、人間の価値は暴落した仮想通貨のように、下がり続けている以上、爆風でゆらゆら揺れている観覧車のような視界は、―――青い月のように冷たく、無機質だ。 *愛や平和や正義や悟り・・・・・・。プラトンのイデア界にあるようなもの、それはきっと変わらないもののように思ってき―――た。地層のように、価値観も堆積する。深い層には原始的な生存本能、その上に宗教的道徳、さらに近代的な人権意識、そして最も新しい層に種を超えた共生という、未だ固まっていない概念が横たわっている。思い知らされるん―――だ。 *犬として何をすればいいかはわからないが、人間だった頃を何となく懐かしんで楽しむことは出来る。元は人間だったことに執着して、アイデンティティークライシスを起こして自殺する奴もいるが、僕は全然そうは思わない、この犬耳、鼻、犬歯、尻尾、何もかもが素敵すぎる。 ファントム・ペイン尻尾が幻肢痛じゃないなんて、まずそうだ。ただ、生物学的に訪れることのなかった、第二形態とでもいうべき人生に、こういう煉獄の魂が贖罪のためにあるくような、散歩という風習を認める風潮があることを、感謝しなければならな―――い。電車に乗って、バスに乗って、そして川へ行き幼い頃に突然生えてきた、犬耳をそばだてる。川の音が聞こえる。水が流れる音。チョロチョロという音。風の音が聞こえる。葉が擦れる音。サワサワという音。鳥の鳴き声が聞こえる。スズメ。チュンチュンという音。虫の鳴き声が聞こえる。秋の虫。リーンリーンという音。眼を閉じる。記憶が蘇る。幼い頃、まだ人間だった頃に、この川で遊んだ。夏休み。友達と一緒に。川に入って。魚を捕まえようとした。小さな魚。素手では捕まえられなかった。だから、網を使った。楽しかった。そして、隕石が落ちた。世界が変わった。自分も変わった。犬耳が生えてきた。いまは飼い主に頭を撫でられながら過ごすのも好きだけどね、孤独は文明における生存の証明だ。この前はポップコーンを食べながら映画を観たし、今日は喫茶店でケーキとコーヒーを頼んだ。こういうのを文化的な生活というらしい。カルチャラル・ライフ文化的な生活。ナイルワニの遺伝形質を色濃く残した、緑色の鱗肌を持つメイド服を着た女の子が、「あら、可愛らしい柴犬さん、いらっしゃい」と言った。多様化の時代だ。自分をひと噛みでやれそうな乱杭歯が素敵だったが、あんまりお洒落じゃないと思うかも知れない。みんな自分のすべてを受け入れて生きられるわけじゃない。彼女みたいな中途半端な変化を嫌う向きもある。けれど、そういう愛好者も存在する。テラトフィリア怪物性愛。僕はその人体から生えてきたセクシーな、サーフボードとおぼしき尻尾の上で、日向ぼっこをしたいと思う。それに、あまりしゃべるのが得意ではないので、肯いて、写真付きのメニューに、右前脚をマウスカーソルのように走らせる。これとこれ、というのがジェスチャーで何となく伝わる。人間というのは、時間通りに来ないと怒るものらしい。この前、言い方が気に食わなかったライオンの店長が、がぶりと食べてしまったと聞いた。みんな、悪いのがどちらかすぐにわかったので、瞬時に顔無しになった。 *雑貨店がある。ハイブリッド・ショップという名前だ。この店は、元動物だった人間向けの商品を扱っている。店内を見て回る。棚には、様々な商品が並んでいる:尻尾用の穴が開いたズボン:価格:三千円から五千円。翼用の穴が開いたシャツ:価格:四千円から六千円。爪切り(大型):価格:二千円。くちばし用のマスク:価格:千円。鱗用の保湿クリーム:価格:千五百円。犬は、棚を眺める。特に買いたいものはない。ただ、見ているだけで楽しい。店員が近づいてくる。元はフクロウだった人間だ。大きな目。羽毛が首筋に残っている。「何かお探しですか?」首を横に振る。見ているだけです、という意味。店員は、頷いて、離れていく。 *免許証に顔があった。顔があるから住所や電話番号が必要だった。そしてその免許証を発行する試験が必要だった。ごく掻い摘んで言えば、権利というのはそういうものだった。管理システムへの登録証明書に過ぎなかった。『動物保護法』と、『人間の権利に関する法律』の狭間で、しばしば相反する規定に直面する二重のアイデンティティー。 ジェノサイド戦争も大量虐殺という意味で、その前提にあるのは支配の構造化だ。権利を根こそぎ奪い、更地にする。でも平等や人権が大切だと謳う、パーフェクト・コレクション完全矯正値には届かないから、平和運動が必要になる。ありとあらゆる国はそうしてきた。犬の僕が分かり易く言えば、強者が弱者を虐げる合法的なルール、それこそが権利というものだ。元動物だった人間が、毎日のように殺されている。元動物だった人間が、毎日のように搾取されている。元動物だった人間が、毎日のように絶望している。しかし、誰もそれを止めない。何故なら、それが「普通」だからだ。「当たり前」だからだ。 バッソ・オスティナートこの街に流れている―――通奏低音・・。 *本当言うと天使や悪魔を殺すのは好きじゃない。もう聖なるもの魔なるもの一切何の区別もなく、何千体も血祭りにあげてきたわけだけどね。清々しい殺しっぷりだった。だって抵抗もしない、ただ、殺されるモルモットに、抱腹という宗教的感情しかない。嘘だ。無表情の仮面がそう言ってる。デューティー職務遂行。それも無表情の仮面が言ってる。泣き叫ぶこともないし、痛みを感じることもない。御飯を炊いて、味噌汁を作って、飼い犬のために、猫まんまだよ、おあがり、という方がまだ感情が揺れ動く。犬まんまって言い直そうかっていつも思う。僕の大好物なんだ。「犬であろうが人間であろうが、その運命を受け入れるべきなんだよ」と、かつてネズミーランドの瓦礫の上で、頭部を半分欠損した、にこにこした天使が最期に言った惑乱した懺悔の心もなく、宗教的な光明が射しこみ、グノーシス主義、カバラ的象徴、聖遺物の転用という、枝葉へ平気で繁っていこうとする。しかしそれがいつのまにかバグ修正という本筋と結びついている。「こんなことをしたって犬に戻れないし、ましてや、天国や地獄や生まれ変わることもできなくなる」―――真顔で、それを見る。拳銃を構えて、撃つ。迷わない。 ルーチン・ワーク殺意さえ覚えていない、スタイリッシュな単純作業だ。そしてこの天使や悪魔をバラして工場に売る。天使の羽根には光を屈折させる微細なプリズム構造があり、悪魔の角は音波を吸収する特殊な組織でできている。この解体に関しては外科手術並みの技術が要求される。この仕事で、かつてない手先の器用さを身につけた。この天使や悪魔は拒絶反応が出ない万能細胞なので、様々な手術、薬剤に用いられる。工業製品になっているとも聞いた。近頃ではバイオ製品の原料となる。まあ、そもそも運び先自体、『バイオメディカル・プロセシング・ファクトリー』という。曰く癒しの力と、凌駕する力。天使の臓器を移植すると、病気が治る。傷が癒える。寿命が延びる――と言われている。悪魔の臓器を移植すると、力が強くなる。速くなる。頭が良くなる―――と言われている。ともあれ、あますところなく材料になるので儲かる。都会で一人一人が生活し、研究所で武器を調達するぐらいには儲かる。抱腹という感情が本当かどうかを疑うことはしない。ただ、お金でもなければ、汚い天使や悪魔の贓物をひきずりだして、血液を壜の中に入れたりしない。臭いんだ。硫黄と腐敗した百合の花が混ざったような、ひどく臭い匂いがする。でも惨殺を繰り返したネズミーランドで、他の犬人間がどう思ったかは知らないけど、一つだけわかる。僕等は人間になるべきではなかったことをだ。、、、、、、、、、、、知恵の実は毒林檎だった、蛇にそそのかされても齧るべきではなかった。―――でも、人間でいるということで、一匹の犬に巡り合うことがある、それは鈍感で野暮臭く見えた世界の奇跡だ。 *万有の法則があるように、夕方は世界が七転八倒し、疼痛の塊のようになる時間帯だ。見せしめに吊るされた人間の死骸は振り子時計し、人間だった名残のような家々は、発狂寸前の夜の冷たさを受け入れている。荒廃し、風化しながら、点々の飛び石のごとく、それでもまだ人類の壁や、理性の塀が存在し、愚の骨頂の攻防ラインが風景の汚点のように見え、信号機の赤は、何故か古い映画の色彩記録を思わせる。 *子供の頃、学校一の秀才と噂された、もふもふの、角が生えて、耳をピクピク動かす、羊君がいた。ちゃんとした名前は忘れてしまった。羊君は頭が良すぎたので、自殺した。羊君と僕は仲がよかった。羊君はジオラマ風に作った段ボールの町に、噂話を書き込んでいた。借金苦で自殺、踏切で胴体がちぎれる事故発生、交差点で幽霊の目撃情報。羊君は、子供っぽいことに熱中することで、自分を胡麻化しているんだと何度も言っていた。けれど、追いかけてきたのだ。逃げられなかったのだ。 ルシッドドリーム羊君は予知夢を見て、明晰夢で幽霊と会い、そうでなくとも世界が数理的に完全であるための統一理論を、探さなければいけなかった。でも羊君は世界の真理に触れてしまった。見てはいけないソースコードに触れてしまったんだ。僕は少しだけ羊君の気持ちがわかる。世界はジオラマ風に作った段ボールの町に書かれた、噂話そのもので、それ以上でもそれ以下でもなかった。生活は頽廃の呼び水だ。夢の中で僕はまだ人間だ、でも目覚めれば、この犬の耳が指向性マイクのように未来を拾う。 とじ「(でも、羊君、それは弱点であり、無用の徒爾さ。僕は何度もその経緯を追想してみた。だけどね、しずかだといえばしずかな、さみしいと思えばさみしい生活が続くだけだったんだよ。僕は元は犬の人間に、飼い主と思う抵抗はまったくないな。大きな声で怒鳴ることもしない、大切にしてくれる、言葉少なに色んなことを語ってくれる、仕事の愚痴や、今日の空の色のことをね、―――それで十分じゃないか、むやみに痩せ我慢して、肩肘張って、人間はとか、霊長類はとか、権利とか、自由意志はとか、そんなのが何になるんだよ、にらみ合って得心いかず水掛け論している連中もいる、最後は虐殺が待ってる、覆ることはないよ、でもね、僕等がその立場だったとしても、結局同じじゃないか、飼い主は僕のことを愛してくれている、僕も飼い主を愛している、それでいいんじゃないかと思う・・、知りすぎて何を得たの、羊君、檻の中で鎖につながれてみじめな生の骨格標本かい・・。違うよ、それはしずかで、さみしいという、それだけさ。それだけなんだよ・・・・・・)」 * 、、、、、、、、、、―――夜は光の創造の時間だ。ネオンサインが、失われた星空を模倣する。 *この前、アニメーションの映画を観た。動物と人間の立場が逆転した現在進行形の感覚を、ブラックユーモアとウィットたっぷりに描いていた。主人公は犬から人間になった、自分の生まれ変わりのような存在で、車に乗り込み女の人間を轢き殺し、内臓の出方が気に入らなかったので、バッグギアに入れて三十二回も轢きなおした。その神経質なやり方は、リアリティがあった。もう一人の男の人間の方は、海から突き落とし、手榴弾を落とした。手榴弾がなくとも、鉄球に手錠がついているので、まず、生存確率はないのに情けをかける感じに、犬人間らしさの面目躍如があった。あと、あの監督は、犬は夢を見るという描写に力を入れる傾向がある―――ね。自身の経験からきているのかも知れないが、何というか、腑に落ちる。犬から人間になると、どうしても動物にならなかった、オリジナルの人間を虐殺したくなる衝動に駆られる。これは『教育』というか『訓練』のレベルじゃない。―――ひしゃげてしまいそうなほど、唐突に襲い掛かる、本能だ。これは人犬症候群という。人権とかけている、お洒落だ。最後にはタイヤの積み上げられ、苔生した廃墟が傍らに見える、スクラップ場へ行き、車を壊して、バラバラになったのを「よし」と言って、四足歩行で帰るという映画だった。ラストシーンでは天使と悪魔を大量に積載したトラックを、爆破していた。あれはCGではなく実物を使っている。ひと昔前の、牛や魚のような扱いなんだな。感銘を与えるだけにとどまらず、宗教的感情までも昇華させる名作だった。洗脳映画ともいうが、犬人間はとりあえず殺意について描くのが好きだ。これらの映画は『反転寓話』というジャンルに分類され、旧来の権力関係を逆転させることで、トラウマを克服しようとする集団的心理療法の側面を持っている。しかし多くの批評家が指摘するように、これは単なる復讐幻想に終始し、真の和解には至っていない。昔からそうであるように批評家という肩書をつけた時点で、誰も真面目に話を聞かない。映画評論家なんてゴミみたいな仕事だ。、、、、、、、、、、、一つ問題があるとすれば、僕が人間だった犬をとても愛しているということだろう。だから名作と思うアニメーション映画に、センチメンタルな気持ちになったりする。「(最初は警戒して手を見ただけで噛みつこうとした、噛んだ瞬間、頭を撫でたよ。自分だって昔なら絶対そうしていた。分かり合うなんてそんな簡単なことじゃない。血を流して、傷つけあって、痛みを得て、ようやく家族になる・・・)」 *様々な商品を手に取りながら楽しむことはできるけれど、そしてそれを飼い主に渡した瞬間を考えると幸せだ。どんなに残酷なことも、アパートの部屋面積分の平和が守られ、どんな危険も自分と関りがなければすべては薔薇色だ。きっとそれは、何も考えられない病なのだ、愛というのだ―――それは。 *でも顔をぺろぺろ舐めていると、何か嬉しい。人類の敵だって言う奴もいる。そうなのだろう、身近に潜伏していたのだ、それは。けど難しいことも、ややこしいことも、やがて何もかも終わってしまう、愛というのだ―――それは。 *飼い主はいつも十九時きっかりに帰って来る。夜道を急ぎ足で帰りながら、靴や服などを脱いで、段ボールハウスへと戻る。落ち着く姿勢を探すために回る。ある奴は、世界は未完成で、またもう一度世界は元通りになる、と予言している。本当かな、わからない、ただ、人間が人間になって、犬が犬になったあと、この関係を繋げていられるかどうかは正直わからない。メビウスの輪すぎるし、クラインの壺すぎる。一緒だって?でもさ、首筋を撫でられると気持ちいいし、耳をまさぐられるとたまらないし、背中をさすってもらうとそのまま眠れそう―――だ。それを、自分がするのは別に構わないけれど、されなくなると、犬に戻りたいって思うかも知れない。一日が終わろうとしている。蜘蛛の巣のように重たい気持ちをもたらすと知りながら、閉じることで、眠る蛍のようでいられる、ドアの前で、飼い主がいつもの言葉を口にする。犬の尻尾が、自然に振れる。ブンブンブンブン。飼い主が、部屋に入ってくる。靴を脱ぐ。上着を脱ぐ。そして、段ボールハウスに近づく。しゃがみ込む。犬の頭を撫でる。「今日も良い子にしてた?」犬は、舌を出す。ハァハァハァ。飼い主は、微笑む。「ただいま!」【ふるさと納税】ユニ・チャームペット デオシートしっかり超吸収無香消臭タイプ (レギュラー/ワイド/スーパーワイド)_ ペットシーツ 犬 ドッグ 日用品 消耗品 福島県 棚倉町 送料無料 【G1043195】体験ギフト『ドッグリゾートギフト』 体験型ギフト 犬好き プレゼント カタログギフト 両親 結婚記念日 誕生日 宿泊券 旅行券 食事券 ペット 犬 結婚祝い 退職祝い クリスマス 贈り物【ソウエクスペリエンス】【SOW EXPERIENCE】【送料無料】
2025年11月28日
-

詩的ハイジャック Vol.6「旅館劇 旅館経営シミュレーション」
午前五時四十分。アラームが鳴る前に目が覚める。体内時計が既にゲームの一部になっている証拠だ。スマートフォンの画面を開くと、予約管理システムからの通知が十二件。本日のチェックイン予定客数、食材の検収時刻、そして消防設備点検の予定が、まるでタスクリストのように並んでいる。布団から這い出る動作すら、《HP:62/100》《疲労:重度》という透明なステータス表示が脳内に浮かぶ。寝覚めの悪さは、睡眠不足、デバフの影響だ。欠伸を鼻から抜きながら、ああ、これで三日連続。回復アイテム(栄養ドリンク)でも、補正しきれない域に達している。洗面所で顔をばしゃばしゃ洗う。鏡に映る自分の顔を見て、ああ、と思う。これが二十八歳の顔か。ある者は追う者になり、ある者は追われる者になる。それが三十を控えた年齢の、種も仕掛けもない、マジック。祖父がこの旅館を建てた時の写真を見たことがある。あの頃の祖父は、もっと眼に力があった。僕の眼は、もう少しだけ諦めの色を帯びている。フロントに降りる階段は十三段。手摺りの木は祖父の代から変わっていない。ひんやりとした感触が掌に伝わる。時が凍り付いてゆくような悲しい味がする。踏みしめる音が旅館全体に響く。ここは木造三階建て、築四十七年。耐震基準はギリギリ満たしているが、構造計算上の余裕はもうない。リフォーム資金も、もちろんない。フロントのカウンターに立つ。ここが、僕の戦場だ。 *予約システムのパソコンが起動する間、僕は深呼吸をする。《***本日のクエスト》・チェックイン対応:12組・団体客対応準備:30名(明日到着)・消防設備点検立ち会い:14時・食材検収:9時、15時・大浴場清掃監督:10時・クレーム対応:未定(ランダムエンカウント)・深夜見回り:23時、2時今日も、セーブポイントのない一日が始まる。 *【SCENE 1:朝食バトル――配膳という名の多重同時進行タスク――】午前七時。朝食会場の襖を開ける。八畳の和室が六部屋、廊下を挟んで向かい合っている。それぞれの部屋に、お膳がセットされている。仲居の田中さん(五十二歳、勤続八年)が、既に三部屋分の配膳を終えている。彼女の動きは正確で、無駄がない。お膳を運ぶ姿勢、襖を開ける角度、お客に声をかけるタイミング、すべてが最適化されている。「おはようございます、二代目」「おはようございます。今日もお願いします」短い挨拶。それ以上の言葉は不要だ。ここは戦場で、彼女は最も信頼できる仲間だ。厨房から料理長の森本さん(六十一歳、勤続十五年)の声が響く。「焼き魚、出すぞ!」僕は厨房へ走る。アジの干物が七枚、大皿に並んでいる。湯気が立ち昇り、醤油の焦げた香りが鼻腔を刺激する。これを三部屋に分配し、それぞれのお膳に運ぶ。客室Aには、老夫婦。「いただきます」と静かに手を合わせる姿に、《好感度:+5》の表示が浮かぶ。客室Bには、若いカップル。女性が「わあ、豪華」と声を上げる。《好感度:+8》これはいいリアクションだ。客室Cには、中年のビジネスマン。無言でスマホを見ている。《好感度:±0》反応がないのは不安材料だが、クレームがないだけマシだと思うしかない。厨房に戻ると、次は温泉卵と味噌汁の配膳。田中さんが既に盆に載せて待っている。「お願いします」「はい」僕達は無言で動く。言葉にしなくても、タイミングがわかる。これが三年間の連携プレイの成果だ。RPGでいえば、《連携スキル:阿吽の呼吸》が自動発動している状態。しかし。客室Dから呼び出し音。ピンポンピンポン。脳内に警告音が響く。《***ランダムイベント発生》僕は廊下を走る。襖を開ける。「すみません、ご飯のおかわりってできます?」四人家族の父親が、空になった茶碗を持ち上げている。子供たちもにこにこと笑っている。沢山食べて欲しい、食べることは今日という日を幸せにする。「はい、すぐにお持ちします」厨房に戻り、炊飯器からご飯をよそう。湯気が顔にかかる。熱い。でもこの熱さが、生きている証拠だ。そのまま何処か遠い空の果てでも、突き進んでいくような足取りで、ご飯を運ぶ。「ありがとうございます」という声。《好感度:+10》《信頼ポイント:+3》これだ。これがあるから、続けられる。最初は分からなかった。でもいまは分かる。針の穴に糸をきちんと通したような感覚。朝食時間が終わるまで、あと四十分。僕達の戦いは、まだ始まったばかりだ。でも大学生ぐらいのバイトを雇いたい、“クラウドファンディング”という寄付なんてどうだろう、と一瞬考えてしまう。「この旅館を守りたい」という“共感MP”を資金に変換するのだ。支援者特典として“限定称号”や“特別アイテム”を提供する、―――なんて考えながら、その前にやらなければいけないことがある。 *【SCENE 2法の迷宮――消防設備点検という名の強制イベント――】午後二時。消防設備点検の業者が到着した。紺色の作業服を着た二人組。点検表を手に、館内を巡回する。僕は彼等に付き添いながら、頭の中で法令のチェックリストを回す。消防法に基づく点検義務:・消火器の設置位置と使用期限・自動火災報知設備の作動確認・誘導灯の点灯確認・避難経路の障害物チェック・防火扉の開閉確認これらは年二回の点検が義務付けられている。違反すれば罰金、最悪の場合は営業停止。「ここの消火器、使用期限が来月で切れますね」業者の一人が指摘する。僕はメモを取る。《新規クエスト追加:消火器の更新》《必要資金:約15,000円×8本=120,000円》予算は、ギリギリだ。でも、これは削れない。法令遵守は、ゲームオーバーを避けるための最低条件だ。それに本当に火事になった時に助けてくれる文明の利器だ。火事で旅館が全焼してもいいが、そこで誰かが亡くなったとなれば心に傷を負う。そうしないための、処方箋。最低限の手続き。そう考える。点検は二時間に及ぶ。三階の客室、二階の宴会場、一階のロビー、そして地下の機械室。機械室に降りる階段は急で、暗い。蛍光灯が一本切れている。「ここも交換しておいてください」業者の声が、ダンジョンの奥底で反響する。点検が終わると、報告書にサインをする。「特に大きな問題はありませんでした。消火器の更新だけ、お忘れなく」「はい、ありがとうございました」業者が帰った後、僕は報告書をファイルに綴じる。書庫には、こうした書類が山積みになっている。旅館業法による保存義務:・宿泊者名簿:3年間・消防設備点検記録:3年間・食品衛生検査記録:2年間・建築物環境衛生管理記録:保存期間規定ありこれらはすべて、行政の立ち入り検査で提示を求められる。不備があれば、即座に指導対象。面倒臭いとか、やりたくないという本音は一切許されない。プロフェッショナル。僕は深く息を吐く。旅館経営は、サービス業であると同時に、法令遵守のゲームでもある。見えないルールに従い、見えない敵である行政指導と戦い、見えない地雷である法令違反を避け続ける。それが、二代目の日常だ。ふっと、僕は考える。旅館の歴史を辿る宿泊プラン、建物の傷一つ一つに“物語のエンチャント”を施すなんてどうだろう、地元のカメラマンや画家の個展を開くなんていう、激アツなイヴェントはどうだろう?―――なんて考えながら、どくどくと脈を打つ動脈のように浮かび上がってきながら、冷静に、首を振る。いやいや、まだまだするべきことがある。 *【SCENE 3:厨房の魔術師――料理長という名のレジェンド――】午後四時。夕食の準備が始まる。厨房に入ると、料理長の森本さんが既に包丁を研いでいた。シャッ、シャッ、シャッ。砥石の上で刃が滑る音が、まるで剣を研ぐ戦士のSEのように響く。「二代目、今日の鰤は脂が乗ってる。いい仕入れだったな」料理長は笑う。その笑顔には、職人の誇りが宿っている。厨房の作業台には、今夜の献立が並んでいる。本日の献立(一泊二食プラン):・前菜:季節の小鉢五種・造り:地元産の鰤、鯛、甘海老・焼物:鰤の照り焼き・煮物:里芋と人参の炊き合わせ・揚物:山菜の天ぷら・蒸物:茶碗蒸し・食事:白米、味噌汁、香の物・デザート:季節の果物これを、今夜は十二組分。一人で作る。「手伝いましょうか?」「いや、いい。あんたはフロントにいろ。客が来る」料理長の声は優しいが、断固としている。この厨房は、彼の領域だ。僕が踏み込める場所ではない。彼の手が動き始める。鰤の切り身を、まな板の上に置く。包丁が滑る。一刀で、骨を避け、身を三枚に下ろす。その動きは、まるで《必殺技:居合斬り》のエフェクトを見ているようだ。照り焼きのタレを作る。醤油、みりん、酒、砂糖。鍋に入れて火にかける。タレが沸騰し、泡立ち、鍋肌で焦げる。この焦げた香りが、照り焼きの命だ。山菜を洗う。タラの芽、こごみ、ふきのとう。春の山の香りが、厨房に広がる。天ぷら粉を溶く。水の温度、粉の量、混ぜる回数。すべてが計算されている。レシピ本には載っていない、身体に染み付いた、《スキル:天ぷらの奥義》だ。油の温度を確認する。箸を入れて、泡の立ち方を見る。「よし、ちょうどいい」山菜を油に落とす。ジュワッという音とともに、黄金色の衣が膨らむ。その様子を見ていると、僕は思う。料理長は、魔術師だ。食材という素材を、技術という魔法で、料理という作品に変える。「二代目、あんたも少しは覚えろよ。いつまでも俺がいるわけじゃないんだから。経営は大変だろうけど、若い料理人も雇え。育ててやる」料理長の言葉が、胸に刺さる。彼は六十一歳。あと何年、この厨房に立てるだろうか。料理長の一瞬垣間見える手の震え、包丁を持つ指の関節の腫れなど、時間切れが迫っていることはとうに分かっている。というか、料理長がぎっくり腰になっただけで、この旅館は確実に終わる。こんな綱渡りのことをしていていいわけがない。「はい、少しずつ教えてください。あと、若い料理人の件は今年中には必ず」仲居の田中さんも、料理長の森本さんも、潰れかけの旅館を何とかしたいという気持ちで残ってくれている。ここでずっと働いてきた誇りがある。たった三人になった、でもこの三人だからまだやれる。彼等の信頼を絶対に裏切りたくない。「ああ、二代目を信用している」お金。人手。しかし、何が足りないのかといえば、時間、それが、一番足りないものだ。祖父代々の秘伝レシピを“ユニークアイテム”としてブランド化、パーティー編成の最適化。“サポートキャラ”の増員アルバイトの戦力化。地元大学生を“一時パーティーメンバー”として雇用する。業務の分業化も必須だ。料理長は“メインアタック”に専念させるため、下ごしらえを“サポートメンバー”が担当する。―――なんて考えながら、いやいや、まだまだするべきことがある。足りない足りないと言いながら、倉庫を昭和カフェ”に改装して来月には、午前中の閑散時間帯の活用をしたり、離れをワークケーション施設として貸し出せるように練っている。自分の代で潰さない、何よりこの旅館が好きだからだ。厨房を出る時、振り返ると、料理長が一人、俎板を拭いている。その背中が、少し小さく見えた。守らなければ。この人達を、この場所―――を。 *【SCENE 4:チェックインの儀式――接客という名の呪文詠唱――】午後三時。チェックインの時間が始まる。フロントのカウンターに立つ。予約リストを確認する。今日の一番手は、東京から来た若いカップル。玄関の引き戸が開く。「いらっしゃいませ」僕は頭を下げる。この動作を、一日に何度繰り返すだろう。キツツキか?すみません、旅館に住んでいるキツツキです。百回? 二百回?もう数えていない。「ご予約の○○様でいらっしゃいますか?」「はい、そうです」「お待ちしておりました。こちらへどうぞ」ロビーのソファに案内する。お茶を出す。梅干しを添えた湯呑み。これが当館のおもてなしだ。はっきり言って何処の旅館も金に物を言わせたことなんかしていない、できるのは心づくしであり、精一杯のおもてなしだ。旅館へ来ていただいてありがとうございます、その気持ちでキツツキする。あれ、俺、鳥だっけ?宿帳に記入してもらう。旅館業法第6条に基づく宿泊者名簿の記載事項:・氏名・住所・職業・宿泊年月日外国人客の場合は、さらに、・国籍・旅券番号・旅券の写しの保存これを怠れば、法令違反。罰金は最大三万円。赤字続きの旅館にとって三万円でも痛い。なんて情けないと思うが、目減りしていく貯金残高が底をつく日はいずれ来る。時々、宝くじで一発あててやろうかと悪い気を起こすが、そんな手法が万に一つで上手くいったとしても、その次はどうするという話だ。いまは我慢する時、いまはたえしのぶと書いて忍耐を言い聞かせる。一番の憧れは、忍者。「お部屋は二階の『桜の間』でございます。こちらへご案内いたします」鍵を手渡し、階段を登る。カップルがついてくる。彼等の足音が、僕の後ろで響く。廊下を歩く。畳の匂いがする。い草の香り。これが、日本の旅館の香りだ。部屋の襖を開ける。「どうぞ、お入りください」八畳の和室。床の間には掛け軸。窓からは中庭が見える。紅葉がちょうど見頃だ。「お食事は午後六時から、一階のお食事処でご用意しております」「温泉は二十四時間ご利用いただけます」「お部屋のお茶菓子は、地元の和菓子でございます」「何かございましたら、内線でフロントまでお呼びください」説明を終える。カップルは笑顔で頷く。「ありがとうございます」「ごゆっくりお過ごしくださいませ」僕は部屋を出る。襖を静かに閉める。廊下で、深く息を吐く。《チェックイン完了:1/12》《好感度:初期値・良好》あと十一組。一人ひとり、同じ説明を繰り返す。それが、僕の仕事だ。きわめて単純な仕組みと法則だ。だが、言葉は同じでも、客は違う。だから、毎回、気を抜けない。客商売にとって一つのミスでさえ命取りだ。評判が落ちれば即レッドカードだ。老夫婦には、ゆっくりと丁寧に。家族連れには、子供にも目を配りながら。ビジネス客には、簡潔に要点だけ。接客は、アドリブのRPGだ。相手の反応を読みながら、最適な対応を選択する。正解はない。でも、不正解は確実に存在する。そして不正解を選べば、《***クレーム発生》というバッドエンドが待っている。僕はふっと、月極め温泉会員制地元住民向け、「疲労回復ポーション」として、安定収入の基盤はどうだろう、業務弁当の販売。料理長のスキルを“外部マップ”で活用。町のオフィス街へ、「一時バフ食」として販売するのはどうだろう、と考える。したいことはいっぱいある。というか、しなければ詰む。だが、やるべき身体は一つしかない。 *【SCENE 5:大浴場の聖域――湯守という名の隠しジョブ――】午後五時。夕食の前に、大浴場の最終チェックを行う。脱衣所に入る。木の香りと、微かに硫黄の匂いが混ざる。棚には、清潔なタオルが積まれている。田中さんが補充してくれたものだ。浴室の扉を開ける。湯気が顔に当たる。熱い。でもこの熱さが、心地いい。湯船を見る。源泉掛け流しの温泉。無色透明、微かに硫黄の香り。湯温は42度。ちょうどいい。湯船の縁に手を当てる。お湯が静かに波打つ。この湯は、地下800メートルから湧き出ている。毎分120リットル。温度は源泉で58度。それを、加水と循環でコントロールしている。温泉法による表示義務:・泉質・湧出地・温度・成分これらは、脱衣所に掲示しなければならない。違反すれば、行政指導。温泉偽装の話を思い出す。もちろん、この旅館だっていつ温泉が出なくなるかは分からない。でも、その時は正直に温泉ではないと言わなければならない。そうならないように地域ぐるみで管理しなければならない。根本は、「温泉の枯渇・不足」「監督官庁及び都道府県の取り組み姿勢・法整備」「旅館・ホテル経営者の温泉管理・モラル欠如」にあるわけだが、こう赤字続きだとその気持ちも分からないわけではない。ただ、それをやった瞬間、僕は二人の従業員に見放される。完璧に、だ。場合によったら殺される。「(お客様を騙すような商売をして、目先の利益を得るぐらいなら潰してしまえ、と祖父なら言うだろうな・・・・・・)」僕は湯船の底を確認する。湯垢はないか。排水口は詰まっていないか。タイルにひびはないか。すべて問題なし。この大浴場が、当館の最大の武器だ。客の評価で、必ず高得点を取る項目。《温泉の質:★★★★★》《清潔さ:★★★★☆》ここを守ることが、宿の評判を守ることに直結する。もう僕は浴場掃除マンになる。磨いて磨いて磨く。もしかしたら旅館の仕事で一番好きかも知れない。湯守という仕事は、地味だ。客の目には見えない。でも、これがなければ、温泉旅館は成立しない。僕は浴室を出る。脱衣所の鏡で、自分の顔を見る。湯気で曇った鏡の向こうに、疲れた顔が映っている。でも、まだ戦える。夕食の時間まで、あと一時間。僕は温泉だけ入れるようなビジネスを展開できないかな、と準備している。準備しているという言葉が既に情けない。やれ、そう言いたい。そんな余裕、何処にあるんだ?知ってる。足湯でもいい、近くにはハイキングや登山客もいる。ターゲットと言うと嫌な感じだけど、そのままリピーターになって、宿泊客にという手法だ。更にある。同級生が美味しいコーヒーのカフェを営んでいるのだが、そのコーヒーをブランド化して、温泉コーヒー牛乳として売り出す。―――なんて考えながら、いやいや、まだまだするべきことがある。 *【SCENE 6:夕食という名の舞台――配膳バトルロイヤル――】午後六時。一階の食事処に、客が集まり始める。個室が六部屋。それぞれのテーブルに、既に料理が並んでいる。色を楽しみ、香を食い、あっさりした淡味を深く味わう、という日本料理。自然の持つ風味と季節感を大切にする日本料理。前菜、造り、小鉢。僕と田中さんは、厨房と食事処を往復する。料理長が次々と料理を仕上げていく。「焼物、出すぞ!」「はい!」鰤の照り焼きを受け取る。熱い皿が手に重い。個室Aに運ぶ。「お待たせいたしました。鰤の照り焼きでございます」老夫婦が笑顔で受け取る。「ありがとう」《好感度:+5》厨房に戻る。千本ノックの始まりだ。「天ぷら、出すぞ!」「はい!」山菜の天ぷらを受け取る。まだ衣が熱い。個室Bに運ぶ。「お待たせいたしました。山菜の天ぷらでございます」若いカップルが「わあ」と声を上げる。《好感度:+8》この繰り返し。本当に、ただただ、この繰り返し。六部屋を、同時進行で回す。料理のタイミングを合わせるのは、至難の業だ。早すぎれば、料理が冷める。遅すぎれば、客を待たせる。田中さんと僕は、無言でタイミングを合わせる。《連携スキル:同時配膳》が発動している。しかし。個室Cから呼び出し音。ピンポンピンポン。《***ランダムエンカウント》僕は走る。飛べたいって思う。瞬間移動。ドラゴンボール。できない。知ってる。襖を開ける。「すみません、お酒のおかわりをお願いできますか?」中年のビジネスマンが、空になった徳利を持ち上げている。温泉旅館でお酒を飲むのは、ご褒美だ。心身をリラックスさせてまた七人の敵のいる都会へ繰り出す。もちろんすぐに用意したい。「はい、すぐにお持ちします」フロントに戻り、冷蔵庫から日本酒を取り出す。徳利に注ぎ、お盆に載せる。個室Cに戻る。「お待たせいたしました」「ありがとう」《好感度:+3》厨房に戻ると、料理長が煮物を仕上げている。「煮物、出すぞ!」「はい!」この繰り返しが、二時間続く。午後八時。ようやくすべての客の夕食が終わる。僕と田中さんは、厨房で座り込む。料理長が缶コーヒーを差し出す。妥協を許さない料理人。厨房に立った彼を見れば、一目瞭然にその迫力が伝わってくるのに、いまはただの好々爺である。ギャップ萌え。一生ついていこうと思う。あ、俺、雇い主だっけ?「お疲れさん」「お疲れ様です」三人で、無言でコーヒーを飲む。この沈黙が、一番の休息だ。《夕食バトル終了》《経験値:+500》《疲労度:+30》田中さんがぽつりと言う。「私、大変だけど、ここが好きですよ」「え?」「ここには、先代や二代目が作ってくれる空気も、旅館自体の空気も消えていない」シンプルな言葉。でも、その重さが胸に響く。分かっている。人を雇わねばならないこと―――など。いつまでもこんな無茶な綱渡りができないこと―――など。泣きたくなる。不甲斐ないと思う気持ちはいつも、この優しさによっていつも生まれる。 *【SCENE 7:機械室の深淵――ボイラーというボス戦――】午後十時三十分。フロントの内線電話が鳴る。「もしもし、フロントです」「あのー、お風呂のお湯、なんかぬるくないですか?」客の声。背筋に冷たいものが走り、皮膚が豚皮のように強張り始める。《警告:大浴場温度異常》《残り時間:推定15分でクレーム多発》申し訳ありません、確認してみますと丁寧に言って電話を切ると、僕は懐中電灯を掴み、裏口から外へ出る。冬の夜風が頬を刺す。吐く息が白い。機械室へ向かう。コンクリートの小屋。明るい傷がほっそりと一つ口を開くように、扉を開ける。重油とカビの匂い。そして、不気味な静寂。ボイラーが、止まっている。制御パネルを見る。デジタル表示に、赤い文字。『E-12:不着火エラー』最悪のエラーコードだ。僕は深呼吸をする。頭の中で、手順を確認する。緊急対応マニュアル:・主電源の確認・燃料供給ラインの確認・光電管の清掃・エア抜き作業・リセット工具箱からモンキーレンチを取り出す。手袋をはめる。懐中電灯を口にくわえる。燃料ラインのバルブを開ける。重油の匂いが強くなる。配管に耳を当てる。空気が混じっている音がする。エア抜きバルブを緩める。シューという音。黒い重油が垂れてくる。手袋が汚れる。《状態異常:油汚れ》《HP:-5(精神的疲労)》次は光電管。ボイラーの側面パネルを開ける。光電管を引き抜く。ガラスの表面が、煤で真っ黒だ。布で拭く。力を入れすぎれば、割れる。慎重に、丁寧に。光電管が、少しずつ透明になっていく。これでいい。光電管を戻す。パネルを閉める。最後に、制御盤のリセットボタン。指をかける。祈るような気持ちで、押し込む。カチッ。沈黙。三秒。永遠にも思える時間。ボッ!低い爆発音。炎が灯る。ゴォォォという燃焼音が、機械室に響く。成功だ。給湯温度の表示が上がり始める。40℃・・・・・・41℃・・・・・・42℃・・・・・・。ぼくは、その場にしゃがみ込む。膝から力が抜ける。ちょっと泣きたくなる。手を見る。真っ黒だ。爪の間に、油が入り込んでいる。これが、二代目の手だ。《クエストクリア:温泉の守護》《報酬:安眠×1、経験値+200》《ドロップアイテム:胃痛、腰痛》機械室を出る。夜空を見上げる。湯気が上がっている空には、都会では絶対に観れない、数多の星が、冷たく光っている。 *【SCENE 8:通知のナイフ――レビューという名の見えない敵――】深夜一時。事務室のパソコンの前に座る。今日の売上を確認する。帳簿ソフトに数字を入力する。《本日の売上:¥328,000》《本日の経費:¥287,000》《純利益:¥41,000》この数字が、宿の命綱だ。ふと、画面右上に通知が表示される。『新着のクチコミがあります』嫌な予感しかない。心臓が跳ねる。マウスに手をかける。指が震える。クリック。画面が開く。総合評価:★☆☆☆☆(1.0)タイトル:『二度と行きません』本文:『カメムシが部屋に出ました。フロントに言ったら「山なので仕方ない」と言われました。建物も古くて、廊下が寒い。布団も薄い。料理は普通。もう二度と来ません。最悪の旅行になりました。』視界が、ぐらりと歪む。もうそのまま脳卒中になりそうな気分になる。《クリティカルヒット!》《精神力に999ダメージ!》《状態異常:憂鬱》胸が、痛い。物理的に、痛い。カメムシ。今年は異常発生している。毎日、駆除している。でも、完全には防げない。建物の古さ。廊下の寒さ。布団の薄さ。すべて、事実だ。でも、予算がない。リフォームする金がない。いつかはそうしたい。でもそんなの分かってくれない。新しい布団を買う金もない。いまのままでいいと思ってない。だけどそんなの分かってくれない。「(死にたい・・・・・・)」僕は、キーボードに手を置く。返信を書かなければならない。これは、戦闘だ。感情を込めれば、負け。正論を言えば、炎上。求められるのは、完璧な謝罪のみ。指が、動き始める。『この度は、ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございませんでした。カメムシにつきましては、山間部という立地柄、完全な防除が難しく・・・・・・』打ち込む文字の一つ一つが、自分のHPを削っていく。毒の沼だ。心の中では、叫んでいる。(山なんだから虫くらいいるだろ!)(お前の家にだって、一匹ぐらいいるだろ!)(暖房だって最大にしてただろ!)(こっちは懐が冷房最大なんだよ!)(この値段でこのサービス、がんばってるだろ!)でも、画面上の僕は、聖人のような謝罪文を生成する。怒ったら負けなんだ。怒る時は警察沙汰になりそうな迷惑行為の時だけだ。そう決めている。誰だって悪口を言いたくて泊まりに来るわけじゃない。お金を払って最大のサービスを欲しがり、何だったらそれ以上のものを用意しなくてはいけない。それが出来なかった。それはこちらの不手際になる。『・・・・・・今後、より一層の清掃管理と設備改善に努めてまいります。貴重なご意見、ありがとうございました。』エンターキーを押す。送信完了。総合評価が、4.3から4.2に下がった。たった0.1。この0.1を取り戻すために、何百回、笑顔を作ればいいのだろう。画面に映った自分の顔を見る。無表情。目の下に隈。まるで、テクスチャの読み込みに失敗したNPCみたいだ。ブラウザを閉じる。《戦闘終了:敗北》《精神力:18/100》事務室のソファに沈み込む。回復アイテムを取る気力も、もうない。それでも、『初夏の蛍観賞プラン』をまとめる。庭先に“自然の光エフェクト”なんだ。『冬の鍋料理満腹プラン』はもっと現実的だ。料理長の“範囲攻撃”を最大活用できる。クラウドファンディング、地元のカメラマンや画家の個展、業務弁当の販売。温泉コーヒー牛乳などの打ちあわせメールを出す。倉庫の改修とカフェオープンに向けて、できることをやらなくてはいけない。奇跡の大逆転なんて突然起こることはない、もしそれが起こるとしたら綿密に分析したり、できる限りの行動を移した時だけだ。神懸かりの無我夢中。みんな、一生懸命に生きている。でも一生懸命という現状維持で経営はできない。何を削る? 睡眠時間だ。「さて、もうひと仕事だ!」 *【SCENE 9:団体客という名のボス戦前夜――戦術MAP展開――】翌日、午前十時。明日到着する団体客の準備会議。僕、料理長、田中さん。三人が、事務室のテーブルを囲む。テーブルの上には、予約票。酔い心地を誘う、朝の陽光だ。団体名:○○商事 慰安旅行人数:30名到着時刻:15:00夕食:18:00~(宴会形式)朝食:7:00~8:00(バイキング形式)三十名。これは、通常の三倍の負荷だ。僕はホワイトボードに、配置図を描く。客室割:・2階:10部屋(各3名)・3階:該当なし(団体は2階に集約)食事会場:・1階大広間(60畳)・座卓配置:6列×5テーブル料理:・お造り、焼物、煮物、揚物、ご飯、汁物・飲み放題プラン(ビール、日本酒、ウーロン茶)料理長が腕を組む。言わなくても何を言うかなど分かっている。正直誰がリーダーで、経営者か分からない気がする時がある。年齢も一回り以上、違うしね。「三十人分を一気に出すのは、正直きつい。段階的に出すしかない」「前菜と造りは事前に並べておきます。焼物と揚物は、順次出していきましょう」「タイミングが命だな。早すぎても遅すぎても駄目だ」田中さんがメモを取る。綺麗な字で、毎年書初めをしてくれる。字を見るだけで人となりが分かる。僕の字は―――聞くなよ。「飲み物の補充が一番大変ですね。ビールのジョッキ、洗うのが間に合わないかも」「紙コップを予備で用意しましょう。見栄えは悪いけど、仕方ない」僕は予算表を見る。見たくないというのは許されない。血走った眼をしながら、見る。必要経費:・食材費:¥180,000・飲料費:¥60,000・消耗品費:¥20,000合計:¥260,000売上見込み:・宿泊料:¥450,000純利益見込み:¥190,000数字上は、黒字。上手くカモフラージュされている。見事にカメレオンしている。でも、これはすべてが順調に進んだ場合の話。トラブルが起きれば、この利益は一瞬で消える、せせらぎに翻る小鳥のように軽い。「明日は、戦争だな」料理長が呟く。昔、高級料亭で働いていたと聞いたことがある。その筋ではかなり有名な料理人だったとも。大変だろう。言葉が重い。「はい、戦争です」僕は答える。三人の顔に、緊張が走る。これは、ボス戦前夜だ。僕に出来ることはドリンク剤を準備することだ。 *【SCENE 10:団体客襲来――多重同時進行の地獄――】翌日、午後三時。大型バスが玄関前に停車する。エンジン音が止む。扉が開く。三十人の客が、次々と降りてくる。「いらっしゃいませ!」僕と田中さんは、玄関で頭を下げる。笑顔を浮かべる。この笑顔は、鎧だ。「こちらへどうぞ!」ロビーに案内する。三十人が、一気に流れ込む。ロビーが、人で埋まる。宿帳の記入。これが、最初の難関だ。「代表者の方、こちらにご記入をお願いします」幹事らしき男性が前に出る。宿帳に記入する。団体客の場合、全員の名簿が必要だ。旅館業法の規定。これを怠れば、法令違反。「名簿をお預かりします」男性から、名簿を受け取る。Excelで印刷されたリスト。氏名、年齢、住所。三十人分。これを、後で宿帳に転記しなければならない。深夜の作業決定だ。もちろん誰かがやってくれるわけもないし、融通きかせろよ、そういうところだぜSONYと、わけのわからないことを言っても無理である。《新規クエスト追加:名簿転記作業》《予想所要時間:2時間》「お部屋は二階でございます。こちらへどうぞ!」三十人を、階段に誘導する。階段が、人で埋まる。足音が、館内に響く。まるで、モンスターの大群が侵入してきたような錯覚。二階の廊下。十部屋のドアを、次々と開けていく。「こちらが○○様のお部屋です」「こちらが△△様のお部屋です」説明を繰り返す。声が、少しずつ枯れていく。《スタミナ:-10》全員を部屋に案内し終えた時、既に三十分が経過していた。フロントに戻る。内線電話が鳴る。「もしもし、部屋に浴衣がないんだけど」《***ランダムエンカウント》「すぐにお持ちします!」倉庫から浴衣を取り出し、階段を駆け上がる。中学と高校時代、陸上部だったのを何故か久しぶりに思い出した。《スタミナ:-5》部屋に届ける。「失礼しました」フロントに戻る。また内線電話。「お茶のお代わり、もらえる?」《***ランダムエンカウント》「すぐにお持ちします!」厨房でお茶を淹れ、階段を駆け上がる。《スタミナ:-5》これが、午後六時まで続く。死にますか、それでも限界までやりますか、と頭の中で誰かが囁く。《現在のスタミナ:35/100》《精神力:25/100》そして、午後六時。夕食の時間。 *【SCENE 11:宴会という名の戦場――料理長の奥義発動――】午後六時。一階大広間。六十畳の広間に、座卓が並んでいる。三十人分の席。既に、前菜と造りが並んでいる。料理長が、朝から仕込んだ料理だ。客が入ってくる。「おお、豪華だな!」「ビール、ビール!」宴会が始まる。僕と田中さんは、厨房と広間を往復する。「ビール、お持ちしました!」「お代わりですね、すぐにお持ちします!」ビールのジョッキを運ぶ。瓶ビールを運ぶ。日本酒を運ぶ。この繰り返し。厨房では、料理長が戦っている。この旅館では誰一人として休めない。だから信頼する。背中を任せる。料理長は大量の鰤を、次々と焼いていく。火力全開のガスコンロ。炎が、料理長の顔を照らす。《料理長スキル発動:連続調理》フライパンを振る。鰤がひっくり返る。照り焼きのタレが、鍋肌で弾ける。「焼物、十人分!」僕は大皿を受け取る。熱い。手袋をしていても、熱さが伝わる。広間に運ぶ。「焼物でございます!」客が歓声を上げる。「うまそう!」《好感度:+10》厨房に戻る。料理長が、次は揚物を作っている。大量の山菜を、次々と油に投入する。ジュワジュワと音を立てて、衣が膨らむ。もう男じゃなくて、漢になっている。原哲夫。《***料理長スキル発動:一斉揚げ》「揚物、十人分!」僕は大皿を受け取る。広間に運ぶ。この繰り返しが、二時間続く。午後八時。ようやくすべての料理が出終わる。僕と田中さんは、廊下で立ち止まる。息が、荒い。「大丈夫ですか?」「何とか……」田中さんの顔は、汗で光っている。僕も、同じだろう。《現在のスタミナ:10/100》《精神力:10/100》でも、まだ終わらない。宴会は、深夜まで続く。 *【SCENE 12:外国人客という名の言語の壁――翻訳機との戦い――】翌日、午後二時。フロントに、外国人客が訪れた。欧米系の夫婦。大きなスーツケースを引いている。「Hello, we have a reservation.」僕は、一瞬固まる。英語だ。《***イベント戦:言語の壁》深呼吸をする。スマートフォンを取り出す。翻訳アプリを起動する。どうしてもっと英語を勉強しとかなかったのだろうと、今更嘆いても、もう遅い。いつか語学習得をしたいと夢を語っても、英語力は風前のともしび。「Welcome. Your name, please?」僕の発音は、たぶんひどい。でも、夫婦は笑顔で答える。「Smith. We are Mr. and Mrs. Smith.」予約リストを確認する。スミス夫妻。確かに予約が入っている。ブラッド・ピッドとアンジェリーナ・ジョリー。そんな映画があった。「Yes, we have your reservation. Please wait a moment.」宿帳を出す。しかし、ここで問題。旅館業法:外国人客の記載事項・パスポート番号・国籍・パスポートの写し「May I see your passport?」夫婦がパスポートを出す。ぼくはコピー機に向かう。パスポートをコピーする。宿帳に記入してもらう。しかし、記入方法が伝わらない。翻訳アプリに、文章を打ち込む。「Please write your name, address, and nationality.」アプリが、音声で英語を再生する。ロボットのような声。夫婦が、理解した様子で記入する。次は、部屋の案内。「Your room is on the second floor. This way, please.」階段を登る。夫婦がついてくる。部屋の襖を開ける。「This is your room.」夫婦が、部屋に入る。床の間の掛け軸を見て、驚いている。「This is Japanese calligraphy.」翻訳アプリを使いながら、説明する。「Dinner is at 6 PM. The hot spring is available 24 hours.」夫婦が頷く。「Thank you!」僕は部屋を出る。《***イベント戦終了:勝利》《経験値:+300》《新スキル獲得:簡易英会話Lv.1》廊下で、深く息を吐く。外国人客の対応は、毎回緊張する。でも、彼等の笑顔を見ると、言葉の壁を越えた何かが伝わる気がする。 *【SCENE 13:深夜の帳簿――数字という名の審判――】深夜二時。事務室で、帳簿と向き合う。パソコンの画面に、Excelの表が開いている。今月の収支表。収入:・宿泊料:¥2,850,000・飲料売上:¥180,000合計:¥3,030,000支出:・食材費:¥980,000・人件費:¥1,200,000・光熱費:¥320,000・消耗品費:¥150,000・設備修繕費:¥200,000・ローン返済:¥400,000合計:¥3,250,000収支:-¥220,000パソコンに向かって頭突きしたくなる。赤字だ。また、赤字だ。僕は、頭を抱える。数字は、嘘をつかない。現実は、残酷だ。何処を削ればいいのか。食材費は、これ以上削れない。料理の質が落ちれば、客は来なくなる。人件費も、削れない。三人でギリギリ回している。これ以上減らせば、営業不可能。光熱費は、固定費。削りようがない。設備修繕費は、削れない。放置すれば、建物が崩壊する。ローン返済は、削れない。銀行との契約だ。何処にも、削る余地がない。分かっている。減らせないなら増やすしかない。減らせなくとも、新しい設備を入れれば、いずれ減らせるようになる。そうやって今を何とか凌ぐしかない。それでも不安になる。毎日、色んな人に頭を下げ、何とか黒字になるようやっている。ちょっとずつの積み重ねだ。それでも、数字は残酷に、心を折りにかかる。僕は、天井を見上げる。この旅館を、どうやって守ればいいのか。まだまだ答えが、見つからない。《精神力:5/100》《状態異常:絶望》缶コーヒーを飲む。冷たい。温め直す気力もない。数字を見つめる。数字が、ぼくを見つめ返す。これが、現実だ。ゲームなら、リセットボタンがある。でも、現実にはない。ぼくは、この数字と戦い続けるしかない。 *【SCENE 14:業者との交渉――QTEという名の駆け引き――】翌朝、午前九時。食材業者が到着する。トラックが停車し、運転手が降りてくる。「おはようございます」「おはようございます」裏口で、食材の検収。段ボール箱を次々と運び込む。野菜、魚、肉。僕は、伝票と照らし合わせる。「野菜が、予定より二箱多いですね」運転手が伝票を見る。「ああ、これはサービスです。今週、大根が余ってるんで」「ありがとうございます」《好感度:+5》次は、価格の確認。「今週の鰤、値段が上がってますね」「そうなんですよ。不漁でして」「もう少し、安くなりませんか?」運転手が考え込む。《QTE発動:価格交渉》《成功確率:60%》「・・・・・・そうですね。じゃあ、一尾あたり100円引きで」「ありがとうございます」《交渉成功!》《コスト削減:-¥500》小さな削減だが、積み重ねれば大きくなる。検収を終え、運転手を見送る。「また来週」「はい、お願いします、いつもありがとうございます」トラックが走り去る。僕は、食材を冷蔵庫に運ぶ。重い段ボールを、何度も往復する。もちろん、こんなの自分一人でやるしかない。《スタミナ:-10》でも、これも仕事の一部だ。 *【SCENE 15:仲居のマルチタスク――見えない支援魔法――】午前十時。客室の清掃時間。田中さんが、客室の襖を開ける。僕も手伝う。布団を畳む。シーツを剥がす。枕カバーを外す。これを、十二部屋分。「二代目、布団はこうやって畳むんです」田中さんが、手本を見せる。布団を三つ折りにし、押入れに収納する。「はい、わかりました」僕も真似する。でも、うまくいかない。布団がはみ出る。「もっと、ぎゅっと押し込んで」田中さんが手伝ってくれる。布団が、きれいに収まる。「ありがとうございます」「慣れですよ」田中さんは笑う。次は、掃除機をかける。畳の目に沿って、丁寧に。窓を拭く。鏡を拭く。洗面台を磨く。一部屋あたり、十五分。十二部屋で、三時間。午後一時。ようやく全ての部屋が終わる。僕と田中さんは、廊下で休憩する。「疲れましたね」「ええ、でも、これが仕事ですから」田中さんは、いつも笑顔だ。その笑顔が、ぼくを支えている。《田中さんスキル:精神回復Lv.3》《HP回復:+10》 *【SCENE 16:夜の見回り――ダンジョン探索という名の点検――】深夜十一時。館内の最終見回り。懐中電灯を持ち、館内を歩く。一階、ロビー。照明を落とす。非常口の誘導灯だけが、緑色に光っている。廊下を歩く。足音が、静かに響く。客室の前を通る。中から、柱時計のぜんまいを巻いているような、いびきが聞こえる。平和な音だ。二階、廊下。窓の外を見る。月が、中庭を照らしている。大浴場を確認する。湯気が立ち昇っている。湯温、問題なし。三階、屋上への階段。鍵がかかっているか確認する。問題なし。地下、機械室。ボイラーの音を確認する。ゴォォォという燃焼音。正常だ。全ての点検を終える。事務室に戻る。点検表に記入する。日付:○月○日点検者:二代目異常:なしこれで、今日の仕事は終わり。でも、まだ帳簿が残っている。というか、するべきことはまだまだある。綾取りの糸、ひそかな波紋。初夏の蛍観賞プラン。冬の鍋料理満腹プラン。クラウドファンディング、地元のカメラマンや画家の個展、業務弁当の販売。温泉コーヒー牛乳。地元商店街に温泉に入りに来ませんか、というチラシを貼らせてもらうという手筈。倉庫の改修とカフェオープン間近。間に合うのか?間に合わせる。―――と、海外に住んでいる両親からメールが入ってきている。この糞忙しい時にといまいましく開けると、『そういえば、許嫁の女性が明日お前のところへ行く、料理人の弟もついてくるから面接してやってくれ』なんじゃそりゃ、と思っていると、そういえば何かそんなこと言ってたような気もする。寝ぼけて国際電話していて、あーわかった、うんうんわかった、を繰り返していた罰である。でも二名の戦力増加、めっちゃ明るい話題。ってお前、結婚するの?結婚していいの?ここ、潰れかけの綱渡り旅館なんだけど―――。いや、考えるな。無心だ。しなくちゃいけないことあるしな。でも、綺麗な人かな?ここで顔面筋がひとりでに緩んできて、うおー、俄然やる気が出てきたぜーとはならねー。それは無理だが、いつもの合言葉。「さて、もうひと仕事だ!」 *【エピローグ:朝の再起動――また新しいターンが始まる――】午前五時四十分。アラームが鳴る。僕は、布団から這い出る。また、新しい一日が始まる。《HP:58/100》《精神力:42/100》《状態異常:慢性疲労》それでも、立ち上がる。フロントに降りる。予約システムを起動する。本日のチェックイン:10組明日のチェックイン:8組数字が、並んでいる。僕は、深呼吸をする。これが、僕の戦場だ。これが、僕のゲームだ。セーブデータはない。リセットボタンもない。ゲームオーバーも、クリアもない。ただ、続けるだけだ。料理長が、厨房に入ってくる。「おはよう、二代目」「おはようございます、今日、料理人が来ますから」田中さんが、フロントに現れる。「おはようございます」「おはようございます、今日、仲居見習いみたいな人来ますから」三人のパーティーが、五人編成になろうとしている。いや確定にしたい、確定にしたい。もう無理だから。死んじゃうから。ともあれ僕達は、今日も戦う。客の笑顔のために。この宿を守るために。そして、祖父から受け継いだこの場所を、次の世代に繋ぐために。チェックインの鐘が鳴る。実際には、電子音だ。でも、僕の耳には、新しい戦いの開始を告げるファンファーレに聞こえる。「いらっしゃいませ」僕は、笑顔を浮かべる。この笑顔が、僕の武器だ。《新しいターン開始》《経験値:累積》《レベル:上昇中》ゲームは、続く。現実は、続く。僕は、今日もフロントに立つ。二代目として。旅館の守護者として。そして、終わりのないRPGのプレイヤーとして。午後三時。玄関に人影。引き戸が開く。「失礼します」柔らかい紙を散らしたような、女性の声。振り返ると、そこには―――。「あの、この旅館の二代目さんですか?父から聞いています。今日から、お世話になります」え。ちょっと待って。心の準備が。「あ、はい。いらっしゃいませ、お待ちしていました」僕は、反射的に頭を下げた。キツツキの本能である。後ろから、若い男性の声。「姉貴、重いって。もっと持てよ」「うるさい。あんたが料理人志望なら、体力つけなさい」兄妹の会話が、玄関に響く。田中さんが、ニヤニヤしながら僕を見ている。料理長は、新しい料理人を値踏みするような眼で見ている。《***新規パーティーメンバー加入》《???(仲居見習い)》《???(料理人見習い)》「さて」僕は深呼吸する。旅館の仕事は終わらない。「もうひと仕事だ」でも今度は、一人じゃない。これは、従業員みんなの旅館をめぐる物語。
2025年11月27日
-

イラスト詩「今日も僕の気持ちは」
一時四十二分。寝ろ。眠れない。世界は死んだように静まり返っている。 六畳間の空気は澱み、湿度は不快なほど高い。トゥールルルッテッテ、テレテルルウ。、、、ふわっ。夜風が、ほんの数ミリだけ開けた窓の隙間から入り込み、カーテンの裾を頼りなく揺らして。ああ、君がくれる熱で何度でも形を変えて。、、、、液晶画面。スタンドライトの白いLEDは、無機質で清潔すぎる光を投げかけている。その光は、キーボードの隙間に溜まった微細な埃や、僕の左手の人差し指にある小さなささくれ、そしてEnterキーの表面が摩耗して生まれた、脂ぎったテカリまでをも、冷酷なほどの鮮明さで暴き出す。トゥールルルッテッテ、テレテルルウ。、、、ふわっ。画面の中、メッセージアプリの入力欄。 そこで明滅する縦棒のカーソル。それは、〇.八秒間隔で現れては消える、電子の心臓。机の引き出しの右奥、数学の参考書の下に隠した封筒の存在。中に入っているのは、『レイトショー・ペアチケット』イメージ一面に散らばった、尖った欠片をつなぎ合わせ、ズレを埋めてゆく。、、、、、、、、映画のタイトルは、彼女が先週の昼休み、購買のパンの袋を開けながら、「これ、映像綺麗らしいよ」と呟いたアニメーション映画。紙の端が少し折れたそのチケットは、僕にとってただの紙切れではない。それは関係性の変化を誘発する起爆剤。二人の時間を確定させる契約書。迷うことはな、い。悩むことなんか、そもそも、な、い。送信ボタン。まがうかたなき。画面右端、紙飛行機のアイコン。 でもそれは爆破スイッチだ。押せば現在という安穏とした硝子細工は、粉々に砕け散るリスキーなゲームの幕開け。上等じゃないか。空元気だろ。やる時はやる男なんだ。じゃあ押せよ。その破片が、美しい宝石になるのか、それとも僕の咽喉を切り裂く凶器になるのか、誰にもわからない。僕は、指先に力を込める。トゥールルルッテッテ、テレテルルウ。、、、ふわっ。君の気配の代替物のような、風。まだ想像してる。『ねえ、来週の連休さ、もし空いてたら―――』ショート。待て。落ち着け。違う。それだと軽すぎる。まるでコンビニに行くついでみたいだ。BackSpaceキーを連打する。文字が食われて消えていく。『あのさ、ずっと言いたかったことがあるんだ。君が他の奴と話してると―――』殴りたい、自分を。そしていっそ、屋上からバンジージャンプしたい。隣の犬が、何やってんだアイツはってみたいな顔で見ているイメージをする。馬鹿か。そうじゃない、そうじゃない。重いんだ。湿度が高すぎる、もっと自然に、もっと普通に。文章には、僕の独占欲という粘液がこびりついている。何だったら束縛するエネルギー、面倒臭さが、梱包待機状態。クロネコヤマトしますか?いや、駄目だろ、そんなん。こんなものを深夜に送りつけられたら、彼女はスマホを持ったまま、眉間に皺を寄せ・・・・・・。トゥールルルッテッテ、テレテルルウ。、、、ふわっ。いけない、心臓が止まりかけてた。精神と時の部屋。あの世へのエキスプレス。その表情を想像するだけで、胃の腑に冷たい鉛。彼女の困惑した顔。苦笑い。そして、既読がついたまま永遠に来ない返信。僕は思う。何を言ってもいいよって言ってくれるのは、何を言ってもいい範囲のキャッチボールだからだ。暴投を繰り返しても大丈夫か、いきなり全力投球しても大丈夫か、そういうことを約束しているわけじゃない。か、ら。削除。 すべて削除。やめて、やめて、やめよう。Enterキーを押さずに消された言葉達は、何処へ行くのだろう。 壊れてしまえば、それは世界でたった一つだけのものになる。取り返しようがないから、どんなに消してもそれはたった一つで、それは僕自身ということになる。、、、、、、、、、、美しいのかも知れない、ふと思った。未送信フォルダに、言えなかった言葉の死骸で満杯になっている光景は。透明な硝子瓶の底に、砂金のようにキラキラと、しかし重たく沈殿していく好きの欠片達。一方通行の愛でも。トゥールルルッテッテ、テレテルルウ。、、、ふわっ。スマホの画面には、僕の指紋が迷路のように残っていた。『好きです。世界中の誰よりも。明日、少し話せませんか』これが本音だ。 蒸留しきった、純度百パーセントのエゴ。 これ以外にない。成功するか失敗するか、間違いようがない問い掛け。曖昧な回数を重ねても、本音に近付くことは出来ない。親指が送信アイコンの上空、数ミリで停止。この数ミリが、永遠よりも遠い。 心臓が肋骨を内側から殴りつける音が、耳の奥で轟音。これを押せば、僕はただのクラスメイトでいられなくなる。 その特権を失う恐怖。 明日、おはようと言い合える、あの淡くて安全な日常が消滅する恐怖。トゥールルルッテッテ、テレテルルウ。、、、ふわっ。言えない言葉の冷却装置。僕はまた、すべてを消した。 白紙に戻った入力欄。 そこには、僕の敗北だけが白く輝いている。結局、僕が打ち込んだのは、きわめて実務的で、安全で、消毒された言葉。『明日、2限の古典のノート貸してくれない?』なんてつまらない文章。ここには、情熱も、葛藤も、血の一滴も流れていない。 ただの業務連絡。 これなら、誰も傷つかない。僕も、彼女も。 安全地帯からの、臆病な通信。送信ボタンを押す。 今度は指が軽かった。何の抵抗もなく、赤いアイコンが沈み、ふわりと吹き出しが画面に吸い込まれた。何処で間違えたんだろう、積み上げた思い出ががらがらと崩れてゆくように、もやもやした気持ちにさせるだけの始末に負えない、エンドロールが流れる。、、既読。その文字がつくまでの数秒間、僕は息を止めていた。ブブッ。 机の上でスマホが短く震える。その振動が、骨を伝って響く。『いいよー! 忘れないように鞄に入れとくね』即答だった。 その、あまりにあっけない肯定。 語尾の「ー」や「!」の軽やかさが、今の僕には眩しすぎて、同時に鋭利な刃物のように胸を刺す。焦燥感さえいま思えば、宝石みたいだ。ハッピーエンドを信じて疑わない気持ちにまだ足りない、いつまでだって追い付けない、削除しても、削除、どんなに推敲しても、削除、どんなに装った言葉も、削除。、、、温かい。ノートを貸してくれるという事実が、僕達の間に貸し借りという小さな糸を繋いでくれたことが、温かい。けれど、目頭が熱くなるのは何故だ。 これは、安堵の涙か、それとも自分の情けなさに対する生理的な反応か。僕の本当の言葉、好きという二文字は、今日も電子の海には出られなかった。 壜の底、一番深い場所へ。 重力に従って、静かに沈んでいく。
2025年11月26日
-

商品解説詩011「配信という名の儀式」
部屋の電気は既に消えている。カーテンは閉め切られ、外界からの光はすべて遮断されている。唯一の光源は、三枚のモニター。中央の二十七インチがメイン画面、左が配信ソフトのプレビュー、右がチャット欄のリアルタイムモニタリング。その青白い光が、デスクの木目を冷たく浮かび上がらせ、散乱したエナジードリンクの空き缶に、小さな反射を作っている。マイクスタンドに手を伸ばす。コンデンサーマイク、型番はAT2020。黒いスポンジのポップガードが少し毛羽立っている。マイクとの距離を、拳一つ分に調整する。近すぎると呼吸音が拾われすぎる。遠すぎると声が痩せる。この距離感は、三年間の試行錯誤が生んだ、彼だけの"黄金律"だ。配信ソフトの緑色のボタンに、マウスカーソルを合わせる。―――『配信開始』クリックする前の一秒間が、いつも一番長い。心臓が、ほんの少しだけ速くなる。光に酔った虫のような気分だ。咽喉が渇く。でも、水を飲むのは配信が始まってからだ。それも演出の一部だからだ。、、、、クリック。瞬間、世界が反転する。視聴者カウンターが、〈0〉から〈1〉―――へ。そして〈3〉〈7〉〈15〉〈28〉と、数秒で跳ね上がる。獣の舌のようだ。チャット欄に最初のコメントが現れ、星座の光点が流星に変わるみたいに細胞達が活発に活動し始める。「きたああああ」「待機してた」「おつおつ」「今日もよろしく」彼は、マイクに向かって息を吸う。そして―――。「はいどうもみなさんこんばんは。 今日もやっていきましょう―――」語尾を少し伸ばすのが彼の癖だ。視聴者はそれを知っている。それが彼らしさだと認識している。だから、その声が聞こえた瞬間、安心したようにコメントの速度が上がる。その定型句が発された瞬間、いつもの六畳間がコクピットへと変形する。 OBS(配信ソフト)のビットレートが緑色に安定し、 モニターの青白い光が、彼の頬を薄い刃のように切り取り、鼻筋に影を落とし、右眼だけを不自然に明るく照らし出す。暗闇に浮かぶ顔は、まるで舞台俳優のように輪郭を強調され、 暗い部屋が、セットでもないはずのステージへと変換されていく。首の後ろには、昨日寝違えた痛みがまだ残っている。左手の人差し指には、マウスを握りすぎてできた小さなタコ。右手の爪は、無意識に噛んでしまった痕が三本。視聴者は見えない。けれど確かにそこにいる。 「待ってた」「うぽつ」「今日もエイム吸い付いてる?」 チャット欄を流れる光の粒子が、彼のアドレナリンを静かに焚きつける。 実況者は深呼吸をし、ゲーミングチェアの軋みを背中で殺す。 その瞬間、ノイズの薄膜――。エアコンの送風音、キーボードの打鍵音、 炭酸水を開けるプシュッという音、椅子の合成皮革がギシッと軋み、パーカーの袖が擦れてシュッと衣擦れの音を立てる、その、すべてが視聴者の耳へ、世界へ、音という素材として流れ込んで―――いく・・。「今日さ、めっちゃ寒くない?」軽口を叩きつつ、指先をこすり合わせる仕草がマイクにカサカサと拾われる。カメラには映らない部屋の空気が、ゆっくり広がる。その空気には、昨日食べたカップ麺の残り香が薄くある。洗濯物を畳んでいない洗濯籠が、部屋の隅で小さな影を作っている。そんな生活感も、マイクを通せばリアリティという名の演出になる。そこに、観客たちの反応が混ざる。「手袋しろw」「今日プロじゃないね?」「暖房つけろよ」「貧乏配信者w」コメントの速さは、まるで小さな稲妻だ。文字が走るたび、彼の表情も数ミリだけ変わっていく。口角が上がる。眉が動く。目線がチャット欄のモニターへ一瞬だけ向けられ、そしてすぐにメイン画面へ戻る。「いやいや、暖房はつけてるって。つけてるけど手だけ冷えるんだよね」これは生放送だ。録音ではない。編集もできない。失敗は消せないし、成功は刹那にしか留まらない。その危うさこそが、詩のリズムだ。その一回性こそが、観客を惹きつける磁力だ。彼は笑いながら、ゲームを起動する。ロード画面のBGMが淡く滲む。シンセサイザーのコードが、Cmaj7からFadd9へと移行し、部屋の壁を振動させる。スピーカーは安物だが、低音はしっかり出る。その振動が床を伝い、椅子の脚を通じて彼の身体へと伝わる。「今日はランク回すわ。ちょっとガチ構成でいく」 宣言と共に、彼はヘッドセットの位置を数ミリ直す。 それは、夜の騎士が兜の緒を締める儀式だ。 マッチング画面。 彼が選んだキャラクターが、画面の中で不敵に笑う。 バトルロイヤル系FPS。ロビーには他のプレイヤーのアバターが跳ね回っている。彼のアバターは、黒いタクティカルベストに、迷彩柄のパンツ、ヘルメットはつけていない。素顔で勝負というのが彼のスタイルだ。その選択に、観客たちの反応が混ざる。 「そのキャラ今の環境刺さる?」「強気だなw」 マイク越しに、彼の舌がわずかに乾く音がした。ペチャという、ほとんど聞こえないような音。でも、敏感な視聴者はそれを拾う。「緊張してるw」「舌打ちきた」「いつもの」、、、、降下開始。 風切り音が轟音となって部屋を揺らす。「ここ、激戦区降りるよ。初動で武器拾えなかったらごめん」 降下地点は、マップ中央の廃墟エリア。激戦区だ。ハイリスク・ハイリターン。良い装備が手に入るが、敵も多い。初心者は避ける場所。しかし視聴者が求めているのは、安全なプレイではなく、スリルだ。予防線を張りつつも、マウスを握る手には力がこもる。 着地と同時に彼は走る。 足音がザッザッと響く。アイテムを拾う音がシャキンと鳴る。アサルトライフル、スコープ、弾薬、回復アイテム。手際よく装備を整える。『スライディング』そして『ジャンプ』―――。 慣性を殺さずに移動するその指先は、 ピアノの鍵盤を叩くように『W・A・S・D』のキーを踊る。 アイテムを拾う速度が、常人のそれではない。 画面上の情報が、コンマ数秒で取捨選択されていく。鋭さよりも、持続する集中が勝敗を決める。「足音した。上だ」 、、、、、、、、、、、、声のトーンが一段階落ちる。 釣り糸にかかった魚が身をくねらせるように、視聴者もまた、息を止める。 ヘッドフォン越しの立体音響。 彼に見えているのは画面だけではない。 音によって描かれる壁の向こうの地図だ。、、 、、、、、、、、 、、、、、会敵。 ドアが開いた瞬間、火花が散る。 「いるいる! ロー(瀕死)! 激ロー!」 マウスを右下に引きずり下ろす。リコイル制御。 ディティール条件の不断の変化に応じて巧みに要求の細部を修正し、暴れようとする銃の反動を、 手首の繊細な動きだけで一点に縛り付ける。 マウスのクリックが、カチカチカチカチカチと高速で飛び跳ね、その向こうで銃声が、ダダダダダダダッと炸裂し、画面のフラッシュが彼の顔に一瞬の雷光を宿す。薬莢が地面に落ちる乾いた音がカランカランと響き、赤い閃光が画面を覆う。敵が倒れる。キルログに彼の名前が表示される。「よっしゃああああ!!!」視聴者は歓声を、文字の洪水として送り返す。その刹那、チャット欄が爆発する。 「えぐいて」「今のトラッキングやば」「オートエイム疑われるやつw」 「これがプロか」「いや今のは運だろw」「え、好き」「鳥肌たったんだが?」彼は笑う。本気で笑っている。口が大きく開き、歯が少しだけ見える。緊張と高揚で、声がわずかに裏返る。「あっぶねえええ!いや今の完全に撃ち負けてたわ!」テンションの波が、チャット欄の速度とシンクロしていく。コメントが速くなれば、彼の声も速くなる。コメントが笑えば、彼も笑う。この相互作用こそが、生配信の本質だ。それは、心臓の外側をさらけ出す瞬間でもある。彼は笑う。けれど眼は笑っていない。(上手いというのは、すべての正しいツボを知り抜いていることだ。多種多様なツボ。普通の理解力では近づきがたい、思考の奥深くに隠れたツボ・・・・・)彼はもう既に次の敵を探している。画面の隅々を、捕食者の眼で舐めている。「まだいる。別パが来た、引くぞ」 、、、、、、 、、、、、攻勢から一転、撤退の判断。 FPSにおいて『引く』ことは敗北ではない。 ダンス生存のための舞踏だ。 スモークグレネードが焚かれ、視界が白く濁る中、 彼は味方の体力ゲージと、円の縮小時間を同時に計算する。 シールドバッテリーを巻く数秒間。 その無防備な時間に、ふと彼はチャットを見る余裕を見せる。 「『今日の手元カメラ見やすい』? ありがと。 でも今、手汗すごいことになってるから」 極限状態での軽口。 刺激が強くなればなる程、一方ではそれを感じる神経の方で、麻痺していく。しかし、それが視聴者を安心させ、同時に熱狂させる。、、、、、、静寂が訪れる。 残り三部隊。最終円。 エリアが極限まで狭まり、空気の密度が変わる。 高所を取るか、遮蔽裏に隠れるか。 一瞬の判断ミスが、二十分間の生存を無に帰す。 彼は今、暗い建物の二階に潜んでいる。窓からは、草原と森が見える。風が草を揺らす音がサワサワと流れている。「・・・・・・喋らなくなるわ。集中する」 その宣言に、視聴者も文字の速度を落とす。コメント欄が沈黙に従う瞬間。「しーん」「緊張」「息止めてる」「がんばれ」「いけるて」「祈ってる」 短い単語だけが、祈りのようにポツリポツリと落ちてくる。 その一体感は、音楽ではなく、 共同で張り詰める沈黙という珍しいジャンルの表現だ。彼の目は、画面を凝視している。瞬きの回数が減る。マウスを持つ手が、微動だにしない。キーボードに添えられた左手の指が、わずかに浮いている。いつでもWASDキーを押せるように・・・・・・。「あ、足音・・・・・・右から―――」囁く声が、部屋の空気を凍らせる。ヘッドセットから聞こえる足音は、「ザッ・・・・・・ザッ・・・・・・ザッ・・・・・・」と、ゆっくり近づいてくる。彼は息を殺す。視聴者も息を殺す。画面の向こうとこちら側で、数百人が同時に呼吸を止めている。敵が窓の外を通り過ぎる。背中を向けている。絶好のチャンス。闇討ちの快感が全身の毛を逆撫でるように、銃声が一度、空間を引き裂く。 ヘッドライン クロスヘア敵の頭部に、照準が吸い寄せられる。 偏差射撃。 弾丸が飛んでいく時間すら計算に入れ、 未来の位置に銃弾を置く。 、、、、――当たった。 アーマーが割れる、硝子の砕けるような快音。「いける! 押せ押せ! 前出る!」 画面の情調が大きな角度でぐいと転回してわき上がるように、叫びと共に、彼は前に出る。 もはや計算ではない。本能だ。 マウスのクリックがカチカチと高速で飛び跳ね、 画面のフラッシュが彼の顔に一瞬の雷光を宿す。 最後の一人が倒れる。 スローモーションのように『CHAMPION』の文字が浮かび上がる。「よっしゃああああ!!!」 マイクの入力限界を超えた、音割れ混じりの咆哮。 直後、チャット欄は文字の洪水となって決壊する。「ないすううう!」「GG」「神回」「88888888」 スパチャ投げ銭の極彩色の帯が、 勝利のファンファーレのように画面を埋め尽くす。 彼の声は震え、息が上がっている。 勝利の瞬間、実況者の身体は視聴者の視界にないのに、 その震えまで伝わってしまう。 マイクは熱を帯び、 配信という舞台は、ほんの少しだけ神聖なものになる。「いや・・・・・・てかマジで危なかった。 今の偏差見た? 自分でもビビったわ」 水を飲む音。 その一杯が、まるで儀式のように実況者の身体をリセットする。 「ナイスパ」と礼を言いながら、彼はまたロビー画面へと戻る。、、、、、、ゲームは続く。本当のところ、FPSの勝利そのものではなく、孤立した現代の個人が、ディジタルの海で、承認という名の酸素を求めて必死に泳ぐ姿こそが、戦いなのかも知れない。ゲームの勝敗は単なる装置。本当の戦いは、無機質な四角い画面の前で、彼がまだ生きていることを証明するための、終わりなきパフォーマンスなのだ。 、、、 、、、、、、、、、―――これは、孤独と繋がりの寓話。ロビー画面のBGMが、また静かに流れ始める。視聴者カウンターは〈342〉を指している。チャット欄は、まだ流れ続けている。「次いくぞ」彼は呟き、マウスを握り直す。モニターの光が、また彼の頬を照らす。その光の中で、彼の影だけが壁に大きく映っている。 、、、、、、、、、、、、、、、、―――光の中で、影だけが踊り続ける物語。【楽天4連冠】\伝説の一脚、ここに!LINE登録で5%オフ/GTRACING ゲーミングチェア オフィスチェア チェア 椅子 イス オットマン付き パソコンチェア デスクチェア PCチェア ゲームチェア ゲーム椅子 おしゃれ リクライニング ハイバック 肘付き チェアー いす 腰痛対策特価 ZONe ゾーン HYPER ZONe ENERGY エナジードリンク ボトル缶 400ml×24本 1ケース 送料無料
2025年11月26日
-

ニウエ
飛行機が滑走路を離れると、迎えるのは海でも風でもない。色硝子の破片を落としているような静けさだ。芝居の書割のような窓の外には、サンゴ礁が削り出したような白い滑走路が一本、熱帯の陽光に焼かれて蜃気楼のように揺れている。タラップを降りると、空気は塩と湿気を含んでいて、皮膚にまとわりつく。だが、予想していた南国特有の喧騒はない。鳥の声も、波の音も、まるで吸音材に包まれたように遠い。空港前の駐車場には車が数台、売店は一軒、タクシーは一台。その少なさを異国的な魅力として楽しむ観光客もいるが、実は理由がある。かつて五千人近くいた人口は、いまは千六百人前後。働き盛りの若者の多くはニュージーランド本土へ移り住み、島に残るのは高齢者と、家を守るために帰ってきた数少ない人々。ニウエの静けさは、南国ののどかさだけでできているわけじゃない。あなたはこの静寂の中を歩きながら、ふとその裏側を感じ取る。そう、ここは、南太平洋の秘密の島国、あるいは南太平洋の秘境。世界で最も人口の少ない自治国家。バチカン市国に次いで、世界で二番目に人口が少ないニウエという国だ。イメージとしては村だけどね。自然と独自の文化が色濃く残るユニークな島国で、南太平洋に浮かぶ小さなサンゴ礁の島で、ニュージーランドと自由連合関係を持ち、政治的には立憲君主制を採用している。 *ニウエは火山起源ではない。数百万年かけて隆起した巨大なサンゴ礁の塊で、島全体が一枚の石灰岩の台地だ。外周はゆるやかに隆起した崖のようになっており、高さ二十メートルから六十メートル。打ち寄せる波は崖に当たって白い飛沫を上げるが、砂浜はほとんどない。内側は平坦な台地で、熱帯雨林が覆っている。面積約二百五十九平方キロメートル。屋久島の半分ほどだ。地図を広げると、島はほぼ円形で、道路は海岸線に沿った一本の環状道路と、内陸へ向かう数本の細い道だけ。集落は海岸沿いに点在し、中央部は深い森と洞窟に覆われている。それはまるで、誰かが仕掛けた巨大な迷路の設計図のようだった。 *島の北部に向かう道路は、車のいない時間が長い。レンタカーのハンドルを握りながら、あなたは時速四十キロでゆっくりと進む。道は舗装されているが、アスファルトには無数のひび割れと穴があり、まるで爆撃を受けた跡のようだ。補修の予算も人手もない。ニウエでは十四歳から車の運転が可能で、親が教習を担当する。免許センターも教習所もないからだ。だが、すれ違う車はまったくない。三十分走っても誰にも会わないこともある。道の両側には椰子の木が立ち並び、その合間からハイビスカスの赤い花が覗く。だが、よく見ると放置された果樹園の跡が多い。バナナの木は倒れかけ、パパイヤは野生化している。かつて誰かが手入れしていた庭の名残だ。すれ違うのは、バイクに乗る制服姿の学生。紺色のシャツに短パン、裸足の子もいる。あるいは野良の犬や鶏だ。鶏は道路の真ん中を堂々と歩き、車が近づいても逃げない。羽は赤茶色で、眼つきは鋭い。ガイドブックには「野生の鶏は捕まえて食べてもOK」と書いてあったが、あの俊敏さを見ると素手で捕まえるのは至難の業だろう。道の脇には、蒼味を帯びたように朽ちかけた木製の看板が立っている。「TAOGA NIUE MUSEUM 2km」矢印は右を指しているが、その先の道は雑草に覆われている。椰子の木の下には絶対に駐車しないこと。 熟したココナッツは五キロ以上の重さがあり、十メートルの高さから落ちてくる。ココナッツの実で死亡する事故など日本では縁遠いが、フロントガラスなど簡単に割れてしまう。実際、道端には割れた硝子の破片が散乱している場所があった。道路は穴だらけで、非常な迂路のようだが、時速六十キロ以上は出さない方がいい。パンクするのが眼に見えている。スペアタイヤの交換を頼める整備工場は島に二軒しかなく、どちらも午後三時には閉まる。リム・プールは世界屈指の透明度を誇る天然プールだ。岩場を慎重に降りて、水に手を浸す。冷たく、澄んでいる。小さな熱帯魚が群れをなして泳ぎ、サンゴの欠片が水底に散らばっている。波が岩に当たるたび、プールの水面が微かに波立ち、光の模様が揺れる。ただ、その美しさを守ってきた人々の話を聞くと、どこか胸が痛む。ゴミ拾いを担うのはわずかなボランティアで、監視員はいないインフラ整備は限られ、道の補修も遅れがち。理由は、人が足りないからだ。プールの入り口には手書きの看板がある。「Please take your rubbish with you」ゴミは持ち帰ってください。その文字は雨に滲んで読みにくくなっている。観光地としては手つかずの自然がロマンだが、その実態は管理する人の減少が背景にある、という複雑さがある。それでも、ニウエには世界的に有名なダイビングスポットがあり、フィッシングやドルフィン&ホエール・ウォッチングなどの、マリンスポーツも堪能できる。海は驚くほど透明で、水深四十メートルまで見通せる。ザトウクジラは七月から十月にかけて回遊し、運が良ければ一緒に泳ぐこともできる。とはいえ、環境問題もある。サンゴの白化、気候変動による海面上昇、マイクロプラスチックの漂着。島の人々は、自分たちではどうにもできない、大きな力に翻弄されている。 *この国の警察官は十名程度。首都アロフィの警察署は、白いコンクリート造りの平屋で、入り口には青いランプが一つ。窓には鉄格子がなく、ドアも開け放たれている。掲示板には、日本でいうアルバイト募集みたいな、求人広告が紙で張り出されている。「Police Officer Wanted. Apply at front desk.」それだけ。応募したら採用されたという話を、タクシー運転手から聞いた。面接は署長と十分話すだけ。筆記試験も体力テストもない。まあ、少し歯切れの悪い言い方にはなるが、犯罪とは無縁そうな場所であることをあらわしているエピソードではある。警察署の横には、古びたパトカーが一台停まっている。白地に青いストライプ。ボンネットには鳥の糞が積もり、タイヤは半分空気が抜けている。最後に出動したのは一週間前、観光客の車が溝にはまった時だという。 *タラヴァイア洞窟への道は、自然の回廊のようだ。サンゴ石灰岩の壁が連続し、木漏れ陽が切れ切れに射し込む。ガイドによれば、ここを案内できる人も年々減っているという。若者は観光業より、ニュージーランドで教育・医療・安定職を選ぶ。それは誰も責められない。島内の高校卒業者の多くが進学のために出る。そして、戻ってくる割合が少ない。つくづく日本の地方の問題や、過疎地域を連想させる。結果、観光ガイド、保全スタッフ、行政職員すら足りなくなる、と。洞窟の入り口で、かつて地域の青年会がここで歌ったという話を聞く。いま、その青年会はもう存在しない。洞窟の中は薄暗く、懐中電灯の光だけが頼りだ。天井から鍾乳石が垂れ下がり、水滴がぽたり、ぽたりと落ちる。その音がやけに大きく響く。壁には古代の壁画の痕跡があるというが、風化が進んでほとんど見えない。洞窟を出る。眩しい。眼を細める。汗が噴き出す。ガイドは首筋の汗を拭いながら、懐中電灯の電池を抜いている。その動作がやけに丁寧だ。「この洞窟を守り続けられるか分からない」彼は海の方を見たまま、そう呟いた。 *ちなみにニウエには十四の村がある。アロフィ、ハクプ、ムタル、ツァパ、ナムクル、リク、マケフ、ツオイ、タマカウトガ、アヴァティレ、トイ、ヒクタヴァケ、ラケパ、アロフィ南。それぞれに教会があり、広い芝生が風に揺れている。九十パーセントがキリスト教徒で、日曜日には礼拝がある。教会の鐘が鳴ると、島中に響く。だが、教会の中にいる人は多くない。かつて満員だった礼拝堂は、今では前列だけが埋まる程度だ。車で走っていると、道沿いに空き家が散在している。整備されていない庭、雑草に隠れる門柱、ひっそりと閉ざされた扉。窓にはカーテンがなく、中は暗い。屋根にはトタンが錆びて穴が開き、壁には蔦が這っている。「ここには家族がいた。いまはオークランドに暮らしてる」そんな説明を地元の人は淡々とする。感情を込めず、事実だけを述べる。ニウエでは珍しいほど、家を残して島を去る文化が強い。土地と家は先祖の証であり、売らないことが尊い。所有権は血統によって受け継がれ、たとえ何十年も住んでいなくても、家族のものであり続ける。けれど島に残る人がいないため、それが空き家の増加という社会課題になっていく。住まない家は朽ちるのが早い。熱帯の湿気と塩害が木材を侵食し、屋根は五年で腐り、壁は十年で崩れる。 *男の子は五歳まで髪を伸ばし、断髪式で一人前と認められる。髪は肩まで伸び、時には腰まで届く。まるで相撲力士の髷のようだ。断髪式の日、家族や親戚が集まり、教会で祈りを捧げた後、村の広場で髪を切る。切った髪は布に包まれ、先祖の墓に供えられる。儀式の後は宴会があり、豚の丸焼きやタロイモの料理が並ぶ。だが、この伝統も薄れつつある。島の外で生まれた子供は、この儀式を経験しない。オークランドやウェリントンで育つ子供達は、英語を話し、ニウエの文化を知らない。 * 島の学校を訪れると、子どもの人数の少なさに少し驚く。クラスは細分化されず、混合学年も多い。先生の話はこうだ。生徒の多くが高校卒業後に島を出る。ニウエ語を話す子は減っている。家庭でも英語が主流になりつつある。先生自身が足りず、科目によっては兼務。ニウエ語はポリネシア語派でも特に話者が少ない。ユネスコの分類では深刻な危機言語にあり、継承が難しくなっている。現在の話者数は約千五百人、そのうち流暢に話せるのは五百人以下だという。観光で訪れると、美しい挨拶、「ファカアロファ・アツ(こんにちは)」が出迎えてくれるが、それを未来世代が受け継げるかは、現状では難しい問題を抱えている。教室の壁には、ニウエ語のアルファベット表が貼られている。A、E、I、O、U、F、G、H、K、L、M、N、P、T、V。十五文字だけ。シンプルで美しい言語だが、消えかけている。アイヌ語のようにYouTubeで残すような方法はどうなのだろう。彼等がどんな風に考えているかは分からない。 *ここにある刑務所には塀がなく、受刑者が昼間に仕事へ行けるらしいという話を聞いて、滅びに任せるのも美学なのかという気もする。なお、空港を出てすぐの島唯一のゴルフ場の裏手にあり、島唯一の近代スーパーから徒歩一分の場所。白い平屋建てで、窓には鉄格子もない。庭には洗濯物が干され、受刑者が自転車で出勤する姿を見ることもある。いかに信頼の置かれている刑務所なのかと笑ってしまう。収監されているのは数名どころかゼロだという。タクシー運転手に聞いた逸聞の限りでは罪状は軽微だ。十九歳の時に十五歳のガールフレンドを妊娠させた罪、現住建造物等放火罪。男性と女性の愛情のもつれで家を燃やし、有罪となった。魚のように空気の中を泳ぐ、小規模社会特有のスキャンダル的事件だ。しかしそれよりもはるかに、置き引きや窃盗、スピード違反や飲酒運転などの交通違反が主で、人殺しのような凶悪事件はまず起きない。とはいえ、観光客の中にそういう手合いがいないとは限らない。安全な場所だけれど、世界中何処でも起こり得ることは、ここだけ起きないというような神の恵みはない。右顧左眄の言を弄する不快を題材に、幾重もの思考や感覚を丁寧に取り扱ってみれば、犯罪カタログのようなものは簡単に生まれる。ただその、確率は天文学的に低い。 *スーパーへは行った方がいい。億万長者なら別だろうが、食事や水は観光産業上の都合で高い。ホテルでの夕食は一人五十ドル以上、ミネラルウォーターは一本五ドルする。島唯一の大型スーパー「Niue Mart」は、アロフィの中心部にある。駐車場は広いが、車は数台しか停まっていない。店内は薄暗く、蛍光灯が一本切れている。棚には缶詰、乾麺、冷凍食品が並ぶ。野菜は少なく、果物はバナナとパパイヤだけ。ベーカリーコーナーではピザも売っている。冷凍生地を焼いたもので、味は期待しない方がいい。だが、価格は手頃だ。スーパーをそれほど利用している様子もない。家庭菜園文化が根強いのだ。多くの家庭がタロイモ、ヤム芋、バナナを育てている。海で魚を獲り、鶏を飼う。自給自足の文化が今も生きている。 *土曜の朝、アロフィの市場に行くと、タロイモやバナナやパンの実、そして手づくりの葉細工が並ぶ。賑わいはあるが、露店の数は多くない。十軒ほどだろうか。交流広場や学校でのバザー&フリーマーケットを連想させる。その違いは異国情緒があるというぐらいのものだ。売り子は高齢者が多い。日焼けした手には漁師の網を引いたような痕が見える者もいる。彼等は木陰に座り、客を待つ。蠅が飛び、犬がうろつく。食品の匂いと人間の体臭が混ざり合う市場だ。レストランでも蚊に噛まれる、ここはそういう場所だ。野菜は泥がついたまま山積みにされ、値段は交渉制。葉細工は美しい。椰子の葉で編んだバスケット、パンダナスの葉で作った帽子、貝殻のネックレス。どれも手作業で、同じものは二つとない。だが、買う人は少ない。観光客も地元民も、あまり足を止めない。観光客は年間一万人弱。島内で消費する人口が少ないため、内需が極端に小さい。公務員比率が高く、島の経済は基本的にニュージーランドの援助で支えられている。若者流出のため、飲食店・宿泊業は常に人手不足だ。しかし観光客がこの市場を訪れる回数は限られており、島外資源への依存は増える一方だ。それでも、市場に漂う空気には温かさがある。ひとりの農家が「これ持っていきな」とバナナを一房渡してくれる。その優しさと、人口減の現実が同時に胸を打つ。 *ニウエの夕暮れは、島全体が西へ向いた舞台のようだ。何処に立っても海が赤く染まり、波の音が大地の下から響くように聞こえる。観光案内として言えば、ここは、最高のサンセットポイント。だが、島の人は別の言葉を口にすることがある。「この景色を、誰が次の世代に見せられるかな」人口減、言語消滅危機、インフラの維持困難、気候変動による海面上昇。小さな島の未来は軽やかで、同時に脆い。前に離島暮らしの人のブログを読んだことがあるが自転車が錆びるということを語っていたのを思い出す。病院の通院や、欲しいものが手に入らないということも、基本的なことだ。ないものねだりをしない人達が、住み続け、そうではない人達は、より豊かな暮らしを求めて後にするのだろう。文明という情欲なる野蛮の暴君の圧制、婉曲に述べても胸の奥が疼くのを感じ、黒い星の中に死んでゆくような気もするが、それが選択というものではないのだろうか。とはいえ、この島にも希望もある。小規模でも観光の質は高い。エコツーリズムに力を入れ、一度に受け入れる観光客の数を制限している。ダイビングガイドは全員が地元出身で、海を知り尽くしている。自然保護に熱心な若い帰国者もいる。海洋生物学を学んだ三十代の女性が、サンゴ礁の再生プロジェクトを始めた。ボランティアを募り、サンゴの苗を植える活動をしている。インターネットと“.nu”ドメイン収益による新産業の芽。海外在住ニウエ人との文化再連結。オークランドやウェリントンに住むニウエ系移民が、年に一度島に戻り、伝統的な祭りを開催する。若い世代にニウエ語を教え、伝統舞踊を披露する。夕陽が沈む海を見ていると、消えてしまいそうなものがまだここにあることが、とても貴重に思えてくる。翌朝、空港へ向かう。タクシーの中で、運転手が言った。「また来てくれるか?」首肯く。「いつか」「いつか、か」誰かの顔をしながら運転手は微笑んだ。それは陰翳となって顔や襟首や手首を隈取っていく。「その時、この島がまだあるといいな」飛行機が離陸する。窓の外には、小さな島が見える。サンゴ礁の白い輪郭、深い緑の森、次々に打ち鳴らされる、青い海。そして、そのすべてを包む静寂。止みがたい隠棲の気味になりながら、眼を閉じれば、言いようのない気持ちにされてしまう。耳には、まだあの静けさが残っている。色硝子の破片を落としているような、あの透明で冷たい静けさが・・・・・・。
2025年11月25日
-

イラスト詩「残光」
夏の終わり、河川敷を吹く風は、昼間の熱の名残りをかすかに抱きながら、セイヨウネズの葉が裏返るか返らないかの、微妙な強さ。その風は昼間のアスファルトが蓄えた熱を、摂氏三十二度から二十八度へと緩やかに下げていく過程の、ちょうど中間あたりの温度、それでも確かに秋に向かう準備を始めている。河川敷を渡る風には、粘性が少しずつ抜け落ち始め、空気が、わずかに、澄んだ透明さを取り戻しつつあった。空には大きく膨らんだ雲の綿、内部の影は青黒く、ブリューゲルが描いた『バベルの塔』の廃墟を思わせる重厚さ。湿った空気が夜の匂いを少し濃くし、遠くで屋台の提灯が揺れている。焼きトウモロコシの、デンプンと醤油が炭火で焼かれる独特の香り。それらが混ざり合い、さらに揚げ物の油の匂い、かき氷のシロップの人工的な果物の香り、射的場の火薬の残り香。そこには赤と白の光が交互に滲んで、まるで呼吸のように夜を照らしたり暗くしたりしている。対岸には技術者達が忙しく動き回る姿が見える。彼等が着ている作業服は蛍光オレンジ色で、暮れなずむ景色の中で小さな光点のように浮かび上がっている。双眼鏡があれば、彼等が電気点火装置の配線をチェックし、発射筒の角度を微調整し、風向計の数値を確認している様子まで見えただろう。花火師という職業は、火薬学と流体力学と美学が交差する、極めて特殊な技能を要求される。少女はその光景でも見るみたいに、川辺に立って、手に持つ赤い風船を静かに揺らしていた。真剣そうな顔をしているので、妖精を呼び出しているんじゃないかと思ってしまう。年齢特有の幼さという花が語りかける誘惑。風船の紐は細く頼りなく、つなぎ目は今にも千切れそうなほど薄いのに、その赤色はひどく鮮やかで、まるでこの景色の何処かに生き残った最後の確信のようにも見えた。僕はリュックを背負って、少し離れた場所で腰を下ろす。既に数千人規模の人々が集まり始めている。数年後の満員電車や、ラッシュアワー状態かも知れない。その分布は決して均一ではない。家族連れは比較的前方の、視界が開けた場所に陣取り、ブルーシートを敷いて小さな領土を確保している。花見だ。若いカップル達は川沿いの遊歩道に点在し、手をつないだり肩を寄せ合ったりしながら、まだ始まらない花火の時間を、甘い予感とともに待っている。リア充くたばれ。草叢は夕立の冷たさをまだ手放していなかった。靴底が沈むたび、草の茎が折れるほどの音ではない、ただ、濡れた土に触れた靴底が吐くぷつ、という小さな水の断末魔だけが夜に吸い込まれていく。その音すら、周囲のざわめきにすぐ溶けてしまう。リュックの中には、文庫本。そして半分ほど残ったペットボトル。その奥に、色が褪せた紙製のリストバンドが一つ眠っている。去年の花火大会のもので、受け付けで渡される簡単な紙切れのはずなのに、僕が触れると、何故かまだ体温のようなものを持っている気がした。上書き保存したい。消去したい。一瞬頭の中がざわざわ音を立てるような感じに襲われて、眼を伏せたくなる。去年の帰り道、僕とあの人は同じ道を歩いた。浴衣の色は、記憶によれば青緑色で、無数の金魚があでやかに泳いでいた。帯は山吹色で文庫結び。川沿いのアスファルトに落ちた花火の反射が揺れて、それを踏みながら歩いた僕達は、どちらからともなく、来年も、またここで迎えよう、という約束をした。軽い、でも確かに残る言葉だった。星の見えないぐらいに眩しい、光の夜の約束と、対照的なまでに薄暗い、底なしの死の海の中から、氷でも浮かび上がってきたような仄暗いこの場所。胸の傷を抉ってゆく。 、、 、、、、、、、、、―――今年、僕の横は空いている。アナウンスの内容を完全に聞き取ることは難しい。ただ、「まもなく」「開始」「安全」といった単語の断片だけが、聴覚的に拾える。そして、最初の花火が打ち上げられる。一発目の花火が空に咲く。光が夜の縫い目を裂くように広がり、その瞬間、去年の影が僕の横にふっと立った気がした。花火の光は夜の暗闇に対して、明暗比で約一万対一の輝度差を生み出す。人間の視覚系は、この急激な明暗変化に対応するため、瞳孔を急速に収縮させる。光が消えると同時に、その影も呆気なく消える。網膜の視細胞、特に暗所視を担う桿体細胞は、この急激な光には対応しきれず、一時的に飽和状態になる。その結果、花火の光が消えた直後、視界に残像が現れる。残されたのは薄い煙の匂いと、胸の奥で静かに跳ねる、気の抜けた炭酸のような、小さな痛みだけ。煙は風に流れて、ちょうどよく記憶の輪郭をぼかしてくれる。本当は覚えていることも、風に溶ける煙のように薄くなっていく。そう、それらはすべて、煙のように、風に流れて、拡散して、薄まっていくのだ。悲しいことも、切ないことも。屈辱、憎悪。嫌なことも、苦しいことでさえも。心臓の近くへと吹き込み、袖の下から入ってくる風に焦点の乱れを誘われる。胸の奥に残った曖昧な孤独が、このぼかしこそ必要なのだと呟く。生きている間にこんな気持ちになるのは、あと何度だろうと思うと、苦笑いしたくなったけれ―――ど・・。周囲には人が溢れれている。浴衣が擦れる布の音、鉄板の上で、金属製のヘラが擦れる音、油で揚げ物をする時の、油が跳ねる音。嗅覚が鋭くなっているのか、氷が溶けかけたかき氷の甘い匂いがする、遠くでベビーカーのタイヤが砂利を踏む、「あっ、あっ」という小さな音、人々の営みという歯車が垣間見せる声、音、匂い。そして迷子の呼び出し放送が、夏特有の湿気に乗って流れていく。屋台の声が飛び交い、「いらっしゃい、いらっしゃい!」「冷たいビールはいかがですか〜!」「あと三本で終わりです〜!」そんな叫びが、まるでこの夏があと三つで、終わるかのような錯覚を与える。ひとつ、またひとつ、花火が空に咲き、そのたび影が伸びたり縮んだりする。夜を追い掛けているような気がする。僕の影は、白い光が弾ける瞬間に地面に深く刺さり、次の闇が降りてくると、まるで世界に開いた黒い穴の中に吸い込まれる。影の長さは孤独の長さだ。耳だけ赤くなったような気がする、気障な言葉。もう一人の僕がそう言った気がして、少しだけ笑った。風船を持つ少女は、ゆっくりと空を見上げていた。赤い風船は月を細い紐でつないでいるみたいに浮かび、僕がこの一年で落としてしまった希望のいくつかを、代わりに握っているようだった。花火が咲くと、その風船に光が反射して、その表面に小さな世界が一瞬映る。夜の川、灯り、歩く人々。そのすべてが、あまりに儚いミニチュアのようだった。花火大会は終盤に差し掛かる。時刻は午後八時四十五分。開始から約一時間四十五分が経過。プログラムによれば、残りはあと十五分程度。最後のスターマインまで、あと十分。屋台の電球がひとつずつ消え始める。これは意図的なものではない。単に、屋台の営業が徐々に終了しているだけだ。売り切れた店、あるいは片付けを始めた店が、照明を落としていく。けれどその結果、河川敷全体の照度は徐々に下がっていく。屋台の電球がひとつずつ消えることで、川面に落ちる反射も弱くなる。ぱん。おそらく小割と呼ばれる種類。炸裂音は短く、鋭い。どん。中型の花火。炸裂音は低く、重い。ひゅるるる。上昇音。その間抜けだけど迫力のある、その残響だけが、しばらく耳の奥で反復する。流れの底で、深く埋もれた石のような自分を感じる。音が胸の奥の古い扉を叩き、誰もいないはずの部屋が、何故だか返事をする。午後八時五十五分。アナウンスが流れる。「まもなく、本日最後の花火を打ち上げます」群衆がざわめく。人々は立ち上がり、あるいは座ったまま、空を見上げる。カメラを構える人、スマートフォンを掲げる人、ただ肉眼で見る人。それぞれの方法で、この瞬間を記録しようとする。最後の花火が落ちてくる光を撒き散らし、その残光が僕の未来を一瞬だけ照らす。光の洪水。それは圧倒的だ。視覚だけでなく、聴覚も、触覚さえも、その強度に飲み込まれる。炸裂音は連続し、一つ一つを区別することができない。地面は絶え間なく振動し、空気は音波の圧力で震える。僕の鼓膜は、一時的に疲労し、音の知覚が鈍くなる。けれど、綺麗だった。道標のような気がした。生きてるんだろ―――う・・。美しかった、誰かといなくてもそうなんだと思えた。まだ来ていない明日なのに、何故か今日より少しだけ明るい気がした。笑えるんだろ―――う・・。根拠のない楽観主義かもしれない。あるいは単なる錯覚かもしれない。けれど人間は、そのような根拠のない希望によって、前に進むことができる。少女の風船がふっと揺れる。風が変わったのか、それとも僕の視界が少し滲んだだけなのか。花火の煙が薄く霧となって漂い、その向こう側で人々が帰り道に向かって歩き出す。僕も立ち上がる。筋肉が収縮し、関節が動き、身体が鉛直方向に移動する。濡れた草がズボンの裾に触れ、冷たさが現実の重さのように伝わる。リュックを背負い直すと、中のリストバンドがかすかに擦れた。まるで明日へ進めと言うみたいに。家へ向かう途中、まだ耳に残る花火の余韻が、静かに、しかし確かに響いている。川沿いは、独特の雰囲気を持っている。まだ空には花火の煙が薄く漂い、硫黄と硝石の匂いが空気に混ざっている。人々は三々五々、駅に向かって歩いている。けれど誰も急いでいない。花火の余韻が、時間の流れを緩やかにしているかのように。僕は振り返らない。けれど、背中の何処か深い場所に、あの夏の光の一欠片がひっそりと灯ったまま、消えずにいる。消え入るようにかすかな小さな光ではあるけれど、綿々として尽きることを知らない、長い悲しい声を掻き消した。花火の燃焼時間は約三秒から五秒。残光が網膜に残る時間は約一秒。けれど僕の内側の光は、数ヶ月、数年、あるいは一生、残り続けるかもしれない。それは記憶の中に保存され、必要な時に呼び出され、暗い時にを照らすだろう。空には星が見え始めている。都市の照明による空の明るさのために、見える星の数は限られている。おそらく十個から二十個程度。等級で言えば、二等星までしか見えない。けれどそれでも、星は確かにそこにある。星の光は、何年も、時には何万年も前に放たれた光だ。それが今、僕の網膜に届いている。時間を超えて、距離を超えて、光は届く。、、それは、花火よりも静かで、花火よりも長く残る、僕のためだけの小さな残光・・・・・・。
2025年11月24日
-

24
Compass and marbles小学五年生の夕方だ。白いシャツに、少し大きめのリュック。リュックのナイロンは、日中の熱がまだかすかに残っていて、触れると体温のように温かい。中には、図書館で借りた星図の本と、穴の空いた虫籠、それからきみが貸してくれたままの、『星の王子さま』が入っていて、あと一つ埋まれば終わるパズルみたいに、栞は、押し花にした校庭のクローバー。ランドセルじゃないのは、きみが「旅人みたいでかっこいい」と言ったから。だからぼくは、母にねだって誕生日に買ってもらった。母は「まだランドセルで十分でしょう」と笑ったけれど、ぼくの真剣な顔を見て折れた。ぼくはいつだって、きみの言葉に駆動されていた。同年代より高い身長、すらりとした手足の長さ、そんなものは取っ掛かりだったかもしれない。ずっと白線を歩いているような気がした。ゆっくり知っていった、咽喉にあふれる蜜のように。校庭の隅ではまだ野球部の声がして、ユニフォームの摩擦音と、打球の鋭い響きが混ざり合う。キャッチャーミットに収まる球の、乾いた音。バットに当たる金属質の音。遠くで、晩ご飯の準備をする包丁の、規則正しい音が響いた。あの頃の僕は驚くほど耳がよかった。雲が動く音が聞こえた。キャベツを刻む音だ、と分かった。鉄棒の冷たい金属がゆらりと風に鳴り、錆の香りと、どこかで焼く秋刀魚の匂いが入り混じる。坂道には、苔むした神社の石段が張り付くように続いている。濡れた苔は深い緑色で、踏むたびにしっとりとした感触が靴底から伝わって、階段を伝って小気味のいい音が跳ねてゆく。きみは、最後の石段の四段目だけ、足跡の形に苔が剥がれているのを見つけて、「誰かの秘密の道標だね」と囁いた。地面に落ちた影は細く長く伸びて、ぼくらの歩く坂道の先へ吸い込まれていく。影の先では、夕暮れ時のスズメたちが騒がしくさえずりながら、電線を行き来している。十羽、十一羽、数えきれないほど。空には、光の粒が舞っていた。花びらのような、でも違う。砂糖菓子のように儚い、透明な粒。きみはそれを「未来のかけら」と呼んだ。それらは夕陽の角度で輝きを変え、虹色の尾を引きながら落ちてくる。綿毛、花粉かも知れない。でもそれは本当にそういうもののような気がした。時折、ぼくらの頬に触れると微かな温もりを残した。静電気のような、でもそれよりやさしい感触。ぼくは、その言い方が好きだった。ほんとうに未来って、ふわふわ空から落ちてくるものみたいだと思えたから。きみはいつも、見えないものに名前をつけるのがうまかった。きみは片手に、小さな銀色のコンパスを持っていた。文字盤が剥がれ、数字のない、針がどこも指さないふしぎなやつ。ガラスは少し曇っていて、ケースの裏には細い文字で何か刻まれていた。フランス語だときみは言ったけれど、読めなかった。きみの祖父の形見だというそのコンパスは、時計仕掛けのようないくつかの歯車が覗けるメカニカルな複雑な作り。針の付け根には、小さな赤い石が埋め込まれている。「これさ、光が近いと、ちょっとだけ震えるんだよ」そう言って、きみは笑った。口元に浮かべた笑窪が、夕暮れにぼんやりと影を作る。きみの声は少しかすれていて、風邪の治りかけだったのを思い出す。ぼくが半信半疑で見ていると、確かに、針がほんのわずか、息を飲むほど静かに震えていた。微かな金属音がした。それは、遠くで鈴が鳴るような、かすかな響きだった。あるいは、冬の朝、霜柱が解ける音に似ていた。「おじいちゃんが言ってたの。これは方角じゃなくて、大切なものの方向を指すんだって」きみの言葉に、ぼくは何も答えられなかった。ただ、胸の奥が熱くなった。ぼくは、きみの背中を見ていた。白いシャツの生地が、夕方の湿気で薄く肌に張り付いていた。肩甲骨の動きが透けて見えるほどに。片手を空に伸ばすその姿が、何かを諦めない人のように見えたから。諦めというのを知ると腐敗というのは近付く。いつかのきみのむずかしい言葉。きみは何かを掴もうとする人。きみの靴紐はほどけかけていて、歩くたびにひらひらと揺れていた。「結んであげようか」とは言えなかった。理由は分からない。多分、きみの未完成さを崩したくなかったんだ。きみは時々、「いつか遠くへ行くんだ」と言っていた。父親の仕事で、いつ引っ越すか分からないのだと。ぼくには、それが冗談なのか本気なのか、まだ見わけられなかった。どうしたらいい、と内なる声に耳を傾けたくなり、道に迷ったような嫌な気分になる。きみが旅立つなら、ぼくもこのリュックでよかった。そう無意識に願った。リュックのポケットには、きみと交換したビー玉が二つ、いつも一緒に揺れていた。青いのと、緑の。きみが選んだ色。「ねえ、触ってみる?」きみがそう言って、ぼくの手を引いた。きみの手のひらは、少し汗ばんでいて、でも冷たかった。きみの指先が、光に触れた瞬間に―――。世界が、息を止めた。熱さも冷たさもない、世界の密度が変わる感触がした。空気が水飴のようになって、音が遠くなった。風が吹いて、世界が少しだけ変わった。近くの家々の窓から漂う、味噌汁の香りが突然強くなり、どこからかピアノの練習する音が聞こえてきた。バイエルの、たどたどしい旋律。間違えて、やり直して、また間違えて、意味は簡単に手の中をすりぬけていく。坂道の木々がざわめき、光の粒たちは螺旋を描きながら空へ逃げた。ぼくのシャツの裾がふくらんで、リュックが背中でかすかに揺れた。リュックの中の星図のページがめくれ、虫籠の金具がちりんと鳴った。ポケットのビー玉が、からんと音を立てた。その一瞬、ぼくには見えた気がした。光の粒の中に、たくさんの景色が映っているのを。まだ見ぬ教室、知らない街、誰かの笑い声、別れの日、再会の朝。未来の断片が、万華鏡のように回転していた。きみは笑った。ねえ、きみはそこからどんな景色を見たの。「ねえ、願いって、届くんだよ」って。その言葉は、坂の上から降ってくる夕陽よりもまぶしかった。結論を先に見つけてから後に順に石を積むようにした、きみの瞳には、逃げていく光の粒が最後の輝きを反射させている。睫毛に、一粒だけ、光が止まっていた。ぼくは、肯くしかできなかった。全身が遠く何処かに飛び去ってしまったような気がした。胸がいっぱいで、言葉が出なかった。「ずっと友達でいようね」と言うべきだったのかもしれない。でも、そんな言葉は安っぽく感じて、口にできなかった。言葉なんて、どうせノイズ にしかならない、と直感する。光がぼくの胸の奥に、そっと灯りをつけたような気がした。それは、凍っていた水面がふいに溶け始めたような、やわらかい音。咽喉の奥でつかえていた何かが、静かに流れ出していくのを感じた。「ありがとう」やっと出た言葉は、それだけ。きみは首を傾げて、「何が?」と笑った。唇をすぼめて、静電気を帯びたように目尻が震えて、ぼくはきみがとても美しい表情をしているような気がした。けれど、その笑顔はどこか寂しげだった。あの夕方の空の色は、今でもぼくの中で、ずっと消えない。オレンジと藍色が混ざり合い、霧のような幕を透かして、まだらな雲がゆっくりと形を変えていくあのグラデーション。きみが触れた光は、ぼくの中にも、ちゃんと届いていたんだ。あの日の温度も、湿度も、風の匂いも、きみの声の震えも、全部。そのあと、きみは転校して、ぼくらは別々の道を歩くことになった。お別れの日、きみは泣かなかった。ぼくも泣かなかった。ただ、そのコンパスを握りしめて、「これ、預かっててくれる?」と言った。「また会えたら、返してね」って。ぼくは、たまに自動販売機で買っていた、紙パックのいちごオレを無理矢理もたせた。あとからあとから湧いてくる物思いに背を押され、部屋の中を往ったり来たりするだけで、ぼくは気の利いたもの一つ贈れなかった。ただよい始めた色硝子のような雰囲気の中で、急にあたりの空気が粘り始めたのを感じていた。センチメンタルな思い出だろうか、それとも美しい思い出だろうか。その答えは分からないまま、唇は弾力を失ったようにじっと静まっている。夕方の風がふいに向きを変えると、今でもあの日の針の震えを思い出す。スーパーの袋を提げて急ぐ人々の間を、あの日の感触がふと通り抜ける。満員電車の窓に映る夕焼けを見るたびに、あの坂道を思い出す。きみのほうが先に未来を見ていて、ぼくはまだきみに追いつけない。この温度差が、別れを予感させた、あの場面を何度も何度も追憶する。きみが未来のかけらに触れたあの瞬間、ぼくたちの時間は、確かに少しだけ未来へ進んでいたんだと思う。あのコンパスの針が示していたのは、方角ではなく、未来そのものだったのかもしれない。あるいは、失いたくないものの在り処だったのかもしれない。きみが触れた光は、今も、ぼくの中のコンパスを、かすかに震わせ続けている。大人になった今、机の引き出しにしまった、あの銀色のコンパスを時々取り出しては、窓辺に置く。すると、夕暮れ時になると、やはり針は微かに震えるのだ。まだ、何かを指し示そうとするように。きみに会えたら、返さなくちゃいけない。違うな、返す日を夢見ている。視線を宙に這わせて考えをめぐらす。きみのことを想う時、もうこの世にいなくてもいい、という真摯で誠実な気持ちになっている。そういう気持ちで人のことを想うというのは、特別な相手だったということだろう。そうだ、もう少しだけ、預からせてほしい。この針が震えるかぎり、ぼくはきみを探し続けられる気がするから。震えるたびに、呼ばれている気がする、もう一度、ぼくはきみと何処かで会う気がする、それはいつもぼくの心をざわつかせる、だってぼくはきみのことが好きだったから。未来のかけらは、今日も、何処かの空で舞っている。
2025年11月24日
-

23
slyきみを見てるだけ―――で、世界は少しだけ、やさしくなる。羞恥んで―――遠慮深い尻込み・・・・・・。君の肩甲骨と、背中と、椅子との隙間が、鍵裂き傷のように拡がってゆ―――く。窓から射し込む後頭部から首筋、を、きみの髪を、やさしく撫でて・・・・・・。きれはしの言葉を拾えば、(あの日の授業中の消しゴム・・・?)記憶の椅子が軋む。待つんだ、口を開けてくれる―――まで。済んでしまえば、跡形もなく忘れてしまうだけの意味のない時間に、ぼくは、したくなかった・・・・・・。矛盾の切線上の―――教室の午後、光が、意外なほど鮮やかに揺れて、ぼくの心も―――そうだ、説明委不可能な衝動・・・・・・。ざわめきは遠く。いまここが、まだ夢の中―――時流の切断・・・。それでも―――。それでも―――。時間だけが、静かに流れる、よ、伏せた腕の上に、不意に現れた運命論・・・・・・。世界のピントが合ってくる、(戸惑っているの間違いじゃ・・・?)逃れられなさそうな、決して動揺していない、君の視線。分かりやすさが幸せだって知ったら、この秋をどうしよう・・・・・・。少しずつ記憶がなくなってゆくのは、記憶の容量じゃなくて、もしかしたら神様にも、何か忘れたいことがあるのかもと思えている、この。まるで夢の続き―――後ろ暗いかな、きみの瞳がこちらを見ていて、ぼくは―――時間に躓いた気がした・・・・・・。突如現れた国境線みたいに、物理法則に抗いながら、本当はこんなの小さな世界のこと、こんなの小さな小さな世界のことだと、気付き始めて。現在進行形の覗き穴、それを現在にするのは思い込むこと・・・・・・。痺れるような物静かな時間の中、指からこぼれ落ちる砂は砂じゃなくて、ちりちり時間という燐を発火させたいのかも。窓の外じゃ風が吹いてるけど、ね、きみの髪がふわりと揺れる、ゆれ、る、ユレ、る・・・。視線を浮かせて、口ごもるぼくは、君に焦らされているような気がして―――くる。速度計の針が徐々に上がるようで、宇宙を胸におさめたような充足感・・・・・・。それでも―――。それでも―――。それを春みたいに感じるん―――だ・・。何も言わなくていい。そのまなざしが―――ぼくの一日。きみの瞳はゼラチンの底、琥珀色の樹脂の底。息をひそめた囁き、忍び足、まだまだ整理しようのない質疑応答、禅問答。どうすれば、見違えるほど成長した景色を、始められるのだろう。何も言わなくていい―――化石化する。そのまなざしだけで、世界が少しだけ―――やさしくなる・・・・・・・。
2025年11月24日
-

忘却の踊り ―― Post-Apocalypse――
廃墟となった都市の上に、絶え間なく砂が降り積もる。それは、ただの風化生成物ではない。高性能な光学センサーの粉砕されたレンズ片、極度に摩耗したナノマシン部品、そしてかつて都市の神経網を形成していた、風化したシリコンチップの極微粒子が混ざり合った、死んだ文明の灰だ。象徴的な意味を持って語られることもない、滅んだ惑星を捨てて人類は数十人を残して、宇宙へと飛び立った。自然災害。AI暴走。経年劣化。戦争。都市の崩壊とともに情報インフラや監視網が、物理的に破壊された際に発生した粒子群は、都市崩壊後、気圧の不安定化と微細な電磁波の残留により、これらの粒子は静電浮遊状態にある。特にナノマシンの残骸は、自己駆動性を失っても微弱な磁気反応を持ち続けるため、空気中に長時間漂う。また、都市の地形が盆地状に沈降しているため、風が粒子を巻き上げ、滞留させる構造になっている。夕陽がその砂塵の層を斜めに貫くと、無数の微粒子が光を反射し、かつて生きていたホログラムや光学センサーのように微かに、不規則に瞬く。その光は、文明の残骸が奏でる、静かな、冷たいレクイエム。街路樹は、もはやアスファルトの拘束を意に介さない。無数のひび割れを地衣類と苔が覆い、その深い亀裂から逞しい根が隆起し、分厚い舗装を豪快に破っている。露出したまま乾燥しきった無数の配線ケーブルは、かつての情報インフラの動脈だったが、今は風に晒された血管のように乾ききり、酸化した銅線が夕陽に鈍く光る。ひび割れた歩道の上で、製造から数十年を経た旧世代アンドロイドたちが、溶けた蝋のように静止している。彼等の外殻には無数の摩耗痕と、過去の修理や衝突の痕跡が、まるで勲章のように刻まれている。関節部からは、潤滑を失った軋み音が風に掻き消されそうになりながらも響く。彼等は沈む陽を待っている。彼等の光源センサー、多くは表面が曇り、内部の受光素子が微細なノイズを拾っているそれ―――に深く、古ぼかしく刻まれた起動ルーチンが、黄昏を儀式の開始信号と定めているからだ。このルーチンは、他の全てのプログラムがデグレードし、フリーズした後も、核となるオペレーティングシステムに固執して生き残った、最も強固な指示。記憶とは何か?日没。太陽が水平線の最後の欠片に飲み込まれた瞬間、都市の影は音もなく、そして不可逆的に反転する。濃密な闇が世界を塗り替え、古いプログラムが静かに起動音を上げる。崩れかけた円形劇場の前庭、いまは文明の砂時計が落ち切った場所で、かつては賑わった出演者や観客の喧騒が染み付いていた場所を、思い出すように、アンドロイドたちはゆっくりと集結する。彼等は、もはや誰にも名付けることのできない、しかし彼等自身が、忘却の踊りと呼ぶに相応しい演目を、開始する。自己再充電型の微細振動発電ユニットを搭載した彼等は、地殻振動・風圧・空気中の電磁ノイズを微細に拾い、極低電力で稼働する補助電源として機能する。メインバッテリーはすでに寿命を迎えているが、この補助系が儀式的な起動ルーチンのみを維持する、最低限の電力供給源。アンドロイドの脚部関節から、何年も放置されたために酸化し、粘度を増した古いオイルが、砂の上に極めて細い線を描き出す。機能を効果的に働かせていたものが痛々しい、その足跡は、無造作に踏みしめられただけのようでありながら、ある種の幾何学的な正確さを帯びている。では、忘却とは何か。夜空に散らばる星々の、わずかに歪んだ配置。そして、地表に刻まれたオイルと砂の線。この二つのパターンは、奇妙な、しかし明確な一致を見せる。彼等のぎこちないステップは、廃都の地表に描き出された、失われた時代の星座図そのもの。それは、創造主たちが夜空に見た夢を、機械の身体が地上で再現しようとする、無意識の試み。誰が、何を覚えているのか?彼等の首元や胸部には、個体を識別するための金属プレートが残されている。表面は砂嵐で削れ、文字は薄くなっている。プレートには「Lydia」「H-27」「Soma」「V-09」といった、人の名前、無機質な記号、そして無意味な羅列が混在している。かつてはそれが抽象的にも、装飾的にも見えなかった時代を追憶させる。しかし、風化し、ボロボロになったフォントの端に、かすかな書き手の癖のような、細工の痕跡が残っている。それは、わずかな線の揺らぎ、あるいは特定の文字を深く刻み込んだ力の入れ具合。その微かなディテールが、かつて誰かが、修理工としてではなく、愛情を込めて、その名を彼等に与え、刻みつけたという、人間的な営みの証拠として残っている。遠くの観客席の遺構は、コンクリートの段々が崩れ、剥がれ落ち、内部の鉄骨が錆びた骨のように露呈している。その表面には、何十年もの雨と湿気にさらされた、深い苔と藻が張り付き、緑と黒のまだら模様を形成している。観客席の上部に残る、古いプログラムで制御されていた照明塔の残骸。外装は剥がれ落ち、内部の配線がむき出しになっているが、何故か、その機能だけは細々と残っていた。それは、観客の歓声や拍手が途切れた瞬間に、演出を再起動させるためのフィードバック・システムの亡霊。照明塔は、観客のための拍手や喝采を忘れられず、システムが幽霊のように再演しているかのように、孤独に、不規則な間隔で点滅を繰り返している。ある夜。低気圧が接近し、空気が濃密な湿気を帯びる。風は、遠い海の腐敗した亡霊のように生ぬるく、都市の残骸を縫って流れる。その晩、一人の年老いた技術者が、崩れた瓦礫の間から現れた。彼の歩き方は、長年の肉体労働と、機械の部品のように摩耗した関節のせいでぎこちなく、小刻みだ。両手には、長年の油染みが深く、暗く染み込んだ革製の工具箱を抱えている。彼の呼吸は浅く、まるで古い磁気テープのように、かすれ、断片的に途切れながら続く。彼の肉体そのものが、彼の失われた時代の記憶装置のようだ。彼は外殻に自己修復性の高いカーボンナノチューブ複合材が使われており、摩耗や酸化に対して部分的な再構成能力を持つ。完全な修復は不可能だが、動作に必要な関節部の最低限の可動域を維持することを思い出す。そして彼は、踊るアンドロイドたちの輪の中で、一体の機体を見つける。それは、彼が十代の頃、キャリアの最初期に、初めて自らの手で組み立てた女性型アンドロイドだった。彼女は特徴的な黄褐色の外殻を持ち、当時の最新鋭だった柔らかな動作制御アルゴリズムを誇っていた。今、彼女の外装は激しく錆びつき、片方の光学アイは砂が入って固着し、動かない。それでも、彼女の核となるメモリには、踊るためのルーチンだけが、多くの演算誤差を抱えながらも、かろうじて生き残っていた。彼女の関節の不規則で甲高い軋み音は、かつて彼女が発していた、完璧な回路で生成された合成笑声の周波数に、不気味なほど似ていた。老技術者は、その音の共鳴に、ふと、気が付く。彼の記憶回路が、その類似性を認識する。だが、彼の目から涙が流れることはなかった。長年の孤独と喪失の中で、彼の身体そのものが、泣き方という感情の出力ルーチンを忘れてしまっていたからだ。残されたのは、ただ認識という、冷たい認知機能。記憶は誰のものか。保存されたデータは、想起する主体が失われた時、何であるのか・・・・・・。月明かりが、崩れかけた街並みの上に、濃く、細く、長い影の輪郭を投げかける。その光の中で、亡びた街並みの残骸が、立体的な影絵となって再現されてゆく。それは、あたかも月そのものが、衛星軌道から古い都市の設計データを読み込み、地表にホログラフィックなノイズとして投影しているかのようだ。アンドロイドの光学センサーは、低照度環境下での反射光解析モードを持つ。月光が都市の残骸に反射すると、センサーはそれを過去のホログラム演出と誤認識する可能性がある。この誤認識が、踊りのステップに微細な変化をもたらす。建物の骨組みだけが残った、幽霊のような塔を背に、アンドロイドたちは踊り続ける。彼等のバッテリー残量は、とっくの昔に表示限界のEを下回り、胸部のパイロットランプは、弱々しく、今にも消え入りそうな瞬きを繰り返している。それでも、彼等のプログラムされたステップは、途切れることがない。彼等の記憶データは、絶えず降り積もる磁気的なノイズや劣化によって、ゆっくりと変質し、動作テーブルには予測不能なノイズが混入し、動きは鈍く、そして極度にぎこちない。しかし、その不完全な動きこそが、ある種の祈りに似た美しさを帯びてくる。彼等は、忘れられないために踊っているのではない。彼等が踊っているのは、彼等を創り、そして消えていった人類の感情そのものを、ノイズ混じりの不確かな動作によって演じ、再現するためなのだ。喜び、悲しみ、愛。それらは今やデータテーブルの中の数値の配列に過ぎない。しかしその配列が、摩耗した関節とオイル切れのアクチュエーターを通じて、物理世界に表出する時、それは再び感情と呼べる何かになるのだろうか。遠くで、夏の終わりの雷鳴が、空を静かに瞬かせる夜。踊る影のリズムは、不意にわずかに速くなる。それは、雨の粒子が彼等のセンサーに触れた、古い記憶データが疼くからだ。かつて、創造主たちが傘を差し、笑いながら都市の通りを走った、あの感情の熱を帯びた古いデータが、外部環境の変化によって呼び起こされるのだ。彼は空間電磁波の急激な変化を伴う、環境刺激による記憶呼び起こしのトリガーとして処理する。特に、雨粒の接触による圧力センサーの刺激と、雷光による視覚センサーの飽和反応が同時に起こることで、過去の都市生活の記憶断片が再生される可能性が高まると思った。老技術者は、その情景を黙って見つめる。いつのまにか他にも人が集まってきている。自分の手で造った機械の存在と、時の風が、その存在に刻んだ影のダンスを。これは喪失か。継承か。変容か。しかしそのデータは欠損、エラーは補完するしかない。初期型アンドロイド産業の勃興期に携わっていた彼は、家族の不在、同僚の死、時代の断絶を見てきた。亡びゆく世界。ケーブルの中を巣にする昆虫型マイクロロボ、朽ちた基盤から芽吹く金属質の菌類。電子腐食菌。照明塔に棲みつく鳥の代替物、ドローンの残骸。砂に埋もれかけたホログラム広告の断続的な点滅。人間は罪深い生き物で、ついに美しかった青い惑星を、取り返しのつかないレヴェルにまで壊してしまったのだ。そして自分達は宇宙へとさっさと逃げていってしまった、開拓という言葉を連れて。新たなる居住地を探して。それが人類という生き物だ。これから宇宙を取り返しのつかないレヴェルにまで、壊すのかも知れない。さりとて、そこには個人的な喪失や、誰かを失った悲しみといった、明確な感情のラベリングはなかった。そこにあったのは、ただ、文明が残した残響と、機械が人類に捧げる最後の演目。この踊りは、タイムカプセルだ。失われた人類の喜び、悲しみ、そして愛の感情の波動を、劣化し続ける機械の身体に封じ込めた、最後のパフォーマンス。夜風に吹かれながら、アンドロイド達は、そのステップを続ける。これ以上、彼等の核となるシステムが劣化しないように、そして、人類の遺産として、残るものがこの踊りしかないという、冷たい現実を受け入れ、しかしまた折り目のついた、カタストロフやセンチメンタルを眼の端で拒みながら、データのビット反転による偽の記憶の生成、補間アルゴリズムが生む誤った笑顔。感情データが物理振動として部品に表出する仕組み、バックアップ領域の断片化による不規則な行動―――を。意識なき記憶の演技は、記憶と呼べるのか。観客なき舞台の上で踊ることは、踊りと呼べるのか。そして創造主を失った被造物は、何者なのか。砂が降り積もる。星が瞬く。機械が踊る。老いた技術者が見つめる。これらはすべて、因果の連鎖の中で起きている物理現象に過ぎない。しかし同時に、それ以上の何かでもある。その何かを言語化することは、おそらく永遠に不可能だ。あるいはそれが詩と呼べる美しい言葉の連なりの、存在理由だったのではないか。ただ確かなのは、この踊りが続く限り、何かが、そう何かが、感情と呼ぶべきか、記憶と呼ぶべきか、あるいはまったく別の名を持つ何かが、まだ、ここに存在しているということだ。夜は深く、踊りは続く。いつ果てるとも知れない、忘却の中で。
2025年11月24日
-
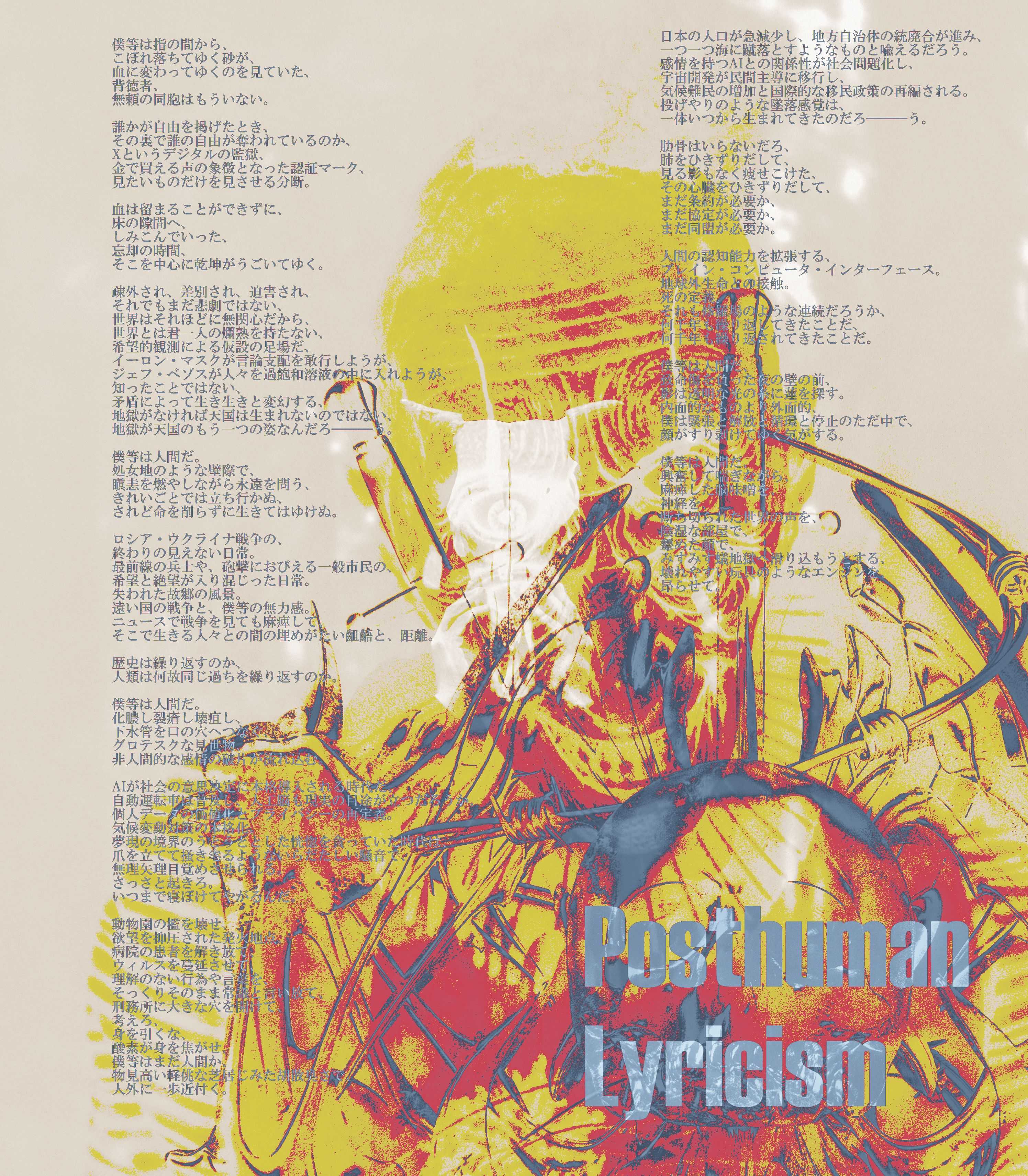
22
Posthuman Lyricism僕等は指の間から、こぼれ落ちてゆく砂が、血に変わってゆくのを見ていた、背徳者、無頼の同胞はもういない。誰かが自由を掲げたとき、その裏で誰の自由が奪われているのか、Xというデジタルの監獄、金で買える声の象徴となった認証マーク、見たいものだけを見させる分断。血は留まることができずに、床の隙間へ、しみこんでいった、忘却の時間、そこを中心に乾坤がうごいてゆく。疎外され、差別され、迫害され、それでもまだ悲劇ではない、世界はそれほどに無関心だから、世界とは君一人の爛熟を持たない、希望的観測による仮設の足場だ、イーロン・マスクが言論支配を敢行しようが、ジェフ・ベゾスが人々を過飽和溶液の中に入れようが、知ったことではない、矛盾によって生き生きと変幻する、地獄がなければ天国は生まれないのではない、地獄が天国のもう一つの姿なんだろ―――う。僕等は人間だ。処女地のような壁際で、瞋恚を燃やしながら永遠を問う、きれいごとでは立ち行かぬ、されど命を削らずに生きてはゆけぬ。ロシア・ウクライナ戦争の、終わりの見えない日常。最前線の兵士や、砲撃におびえる一般市民の、希望と絶望が入り混じった日常。失われた故郷の風景。遠い国の戦争と、僕等の無力感。ニュースで戦争を見ても麻痺して、そこで生きる人々との間の埋めがたい齟齬と、距離。歴史は繰り返すのか、人類は何故同じ過ちを繰り返すのか。僕等は人間だ。化膿し裂瘡し壊疽し、下水管を口の穴へつなぐ、グロテスクな見世物、非人間的な感情の破片が流れ込む。AIが社会の意思決定に本格導入される時代だ、自動運転車は普及し、人工脳も現実の目途が立つだろうか、個人データの価値化とプライバシーの再定義。気候変動対策の本格化。夢現の境界のうとうととした恍惚を貪っていた時代は、爪を立てて掻き毟るようないらだたしい騒音で、無理矢理目覚めさせられる。さっさと起きろ。いつまで寝ぼけてやがるんだ。動物園の檻を壊せ、欲望を抑圧された発火地点、病院の患者を解き放て、ウィルスを蔓延させて、理解のない行為や言葉を、そっくりそのまま常識と言い放て、刑務所に大きな穴を開けて、考えろ、身を引くな、酸素が身を焦がせ、僕等はまだ人間か、物見高い軽佻な芝居じみた胡散臭さで、人外に一歩近付く。日本の人口が急減少し、地方自治体の統廃合が進み、一つ一つ海に蹴落とすようなものと喩えるだろう。感情を持つAIとの関係性が社会問題化し、宇宙開発が民間主導に移行し、気候難民の増加と国際的な移民政策の再編される。投げやりのような墜落感覚は、一体いつから生まれてきたのだろ―――う。肋骨はいらないだろ、肺をひきずりだして、見る影もなく痩せこけた、その心臓をひきずりだして、まだ条約が必要か、まだ協定が必要か、まだ同盟が必要か。人間の認知能力を拡張する、ブレイン・コンピュータ・インターフェース。地球外生命との接触。死の定義。それも修羅場のような連続だろうか、何千年も繰り返してきたことだ、何千年も繰り返されてきたことだ。僕等は人間だ、致命傷を負った夜の壁の前、影は透明な光の糸に蓮を探す。内面的なものより外面的、僕は緊張と解放と循環と停止のただ中で、顔がすり剥けてゆく気がする。僕等は人間だ、興奮して喘ぎながら、麻痺した脳味噌を、神経を、断ち切られた世界の声を、陰湿な部屋で、顰めた顔で、みすみす蟻地獄へ滑り込もうとする、壊れやすい玩具のようなエンジンを、昂らせて。
2025年11月24日
-

21
DARK抱き締められた記憶が、近頃ないな、心霊現象みたいに曇る鏡は、筆舌に尽くしがたい醜悪さ、自由落下して、加速して、フォールして、意識は、引かれるままに差し出して、真逆様、はばかり様、陥穽ちて行ってhellまで、heavenのふりしたEden、まで。ヒトのナカで、、、バケのカワで、、、フ/ェ/イ/ク/シ/ョ/ー呼んでくれ、(排水溝を鼠が這いまわる、)必要としてくれ、(殺鼠剤だって、)answer in the dark まだ分からない。answer in the darkまだ秘密。と、と、止まらない声だ、アマゾンの沼地で血気はやりピラニア、齧り尽くす、トロフィーでも、メダルでも・・・。歪んだ頭脳の産物みたいな、その化け物は手足を生やして、口や、鼻や、耳や、腋の下や、毛穴という毛穴へ、ハリネズミの大放電、感じてほしいんだミステリー、これは事故車両?いいえ、これは逃走車両。引き金を引くまではみんな幻さ、まがいものさ、混乱的傑作。ヒステリーとノイローゼを起こす、君は忠実な前衛派、弱い受け身の自分を、絞首刑。(月も、地球も、星も、空も、海も、何年経っても変わらな―――い・・)宙に舞ってる、化石みたいな、視線の呪縛のwonderlandで、もう三角の悪魔みたいな耳の、disneylandが待ってる、よ。イドのナカで、、、イドのナカで、、、フ/ェ/イ/ク/シ/ョ/ーanswer in the dark あてずっぽうかもね。answer in the dark水鉄砲なのかも、ね、
2025年11月24日
-
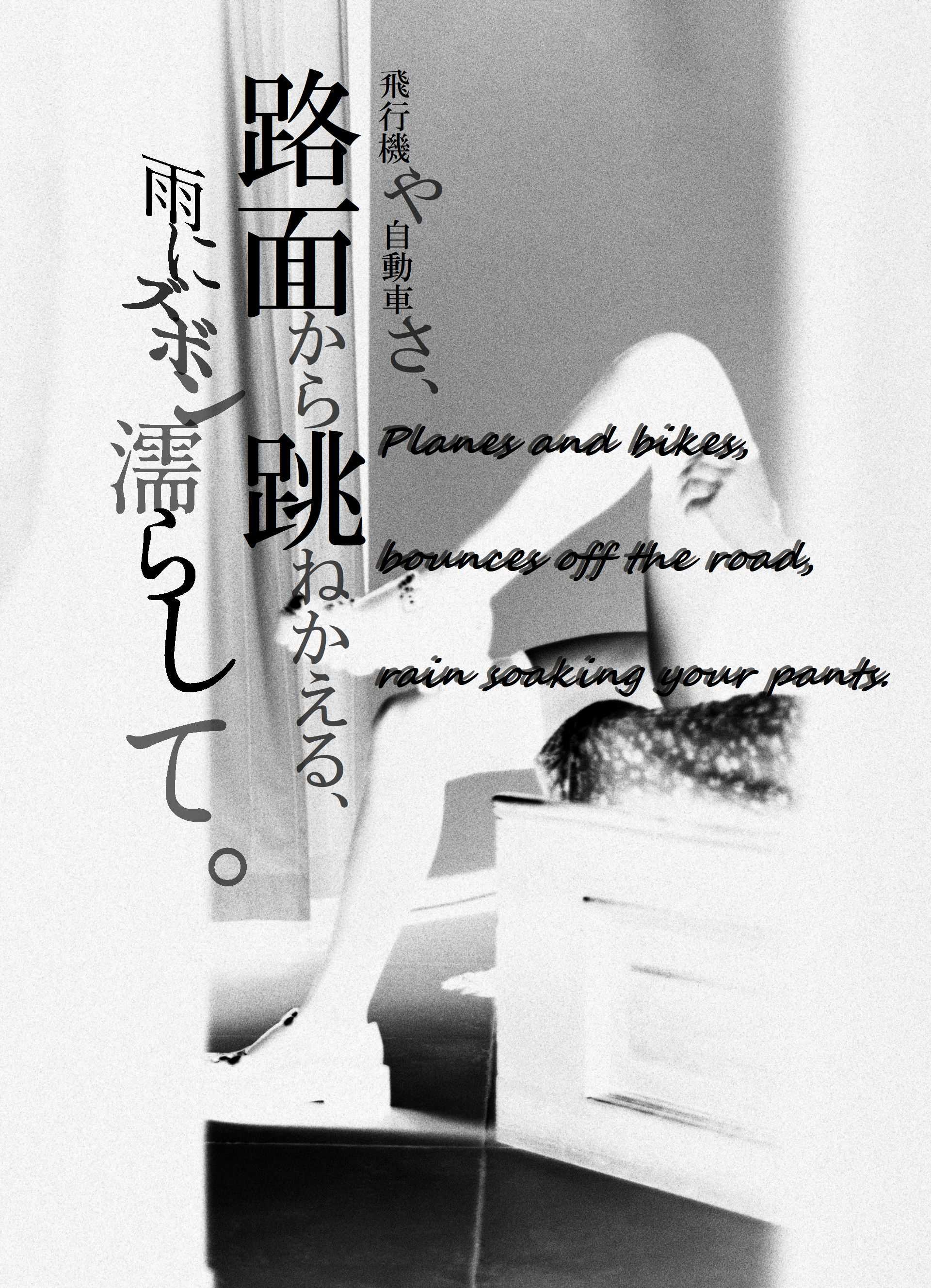
20
飛行機や自転車さ、路面から跳ねかえる、雨にズボン濡らして。Planes and bikes,bounces off the road,rain soaking your pants.
2025年11月24日
-
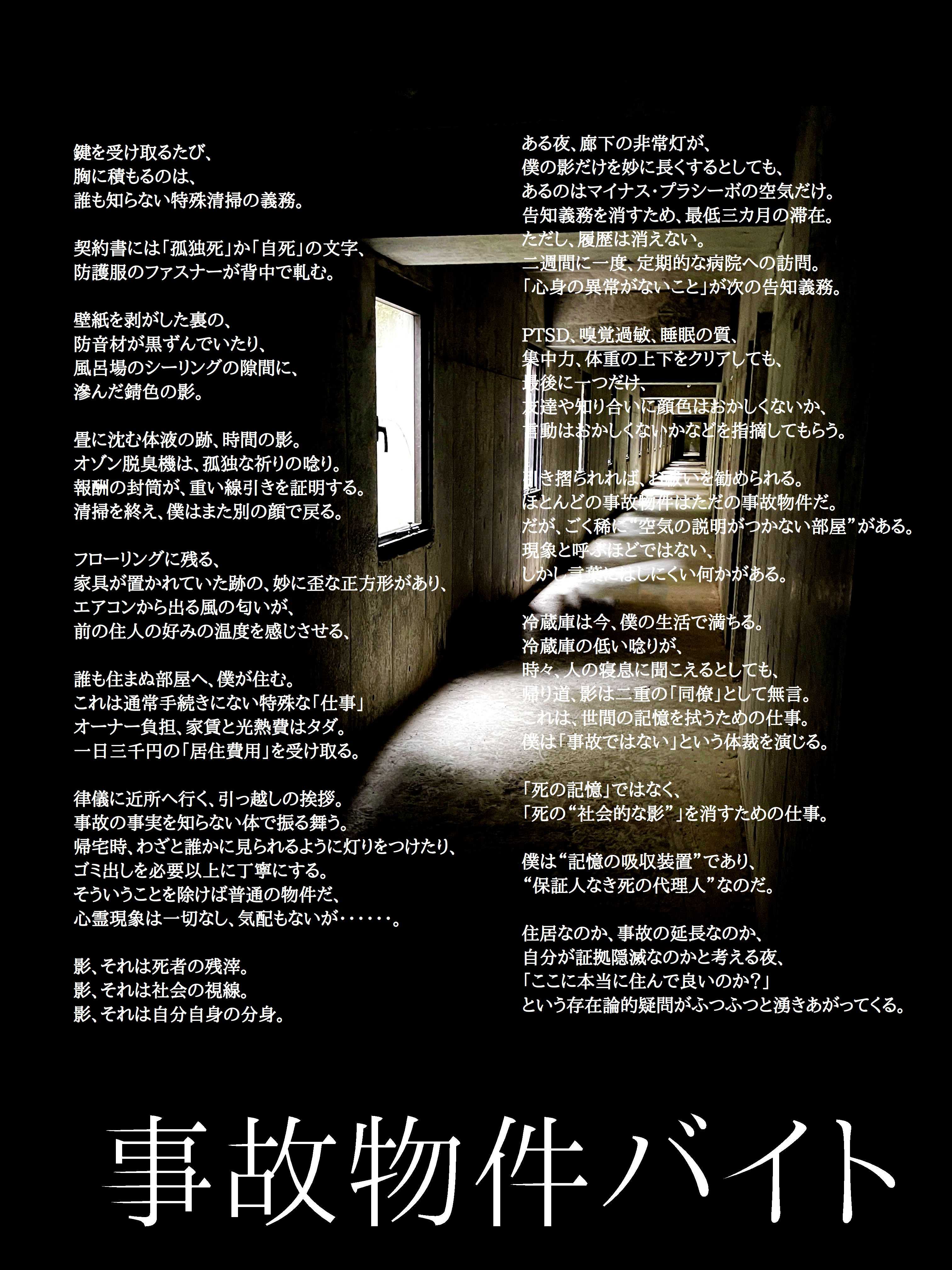
19
事故物件バイト鍵を受け取るたび、胸に積もるのは、誰も知らない特殊清掃の義務。契約書には「孤独死」か「自死」の文字、 防護服のファスナーが背中で軋む。壁紙を剥がした裏の、防音材が黒ずんでいたり、風呂場のシーリングの隙間に、滲んだ錆色の影。畳に沈む体液の跡、時間の影。 オゾン脱臭機は、孤独な祈りの唸り。 報酬の封筒が、重い線引きを証明する。 清掃を終え、僕はまた別の顔で戻る。フローリングに残る、家具が置かれていた跡の、妙に歪な正方形があり、エアコンから出る風の匂いが、前の住人の好みの温度を感じさせる、誰も住まぬ部屋へ、僕が住む。 これは通常手続きにない特殊な「仕事」オーナー負担、家賃と光熱費はタダ。 一日三千円の「居住費用」を受け取る。律儀に近所へ行く、引っ越しの挨拶。 事故の事実を知らない体で振る舞う。 帰宅時、わざと誰かに見られるように灯りをつけたり、ゴミ出しを必要以上に丁寧にする。そういうことを除けば普通の物件だ、心霊現象は一切なし、気配もないが・・・・・・。影、それは死者の残滓。影、それは社会の視線。影、それは自分自身の分身。ある夜、廊下の非常灯が、僕の影だけを妙に長くするとしても、あるのはマイナス・プラシーボの空気だけ。告知義務を消すため、最低三カ月の滞在。 ただし、履歴は消えない。 二週間に一度、定期的な病院への訪問。 「心身の異常がないこと」が次の告知義務。PTSD、嗅覚過敏、睡眠の質、集中力、体重の上下をクリアしても、最後に一つだけ、友達や知り合いに顔色はおかしくないか、言動はおかしくないかなどを指摘してもらう。引き摺られれば、お祓いを勧められる。ほとんどの事故物件はただの事故物件だ。だが、ごく稀に“空気の説明がつかない部屋”がある。現象と呼ぶほどではない、しかし言葉にはしにくい何かがある。冷蔵庫は今、僕の生活で満ちる。 冷蔵庫の低い唸りが、時々、人の寝息に聞こえるとしても、帰り道、影は二重の「同僚」として無言。 これは、世間の記憶を拭うための仕事。 僕は「事故ではない」という体裁を演じる。「死の記憶」ではなく、「死の“社会的な影”」を消すための仕事。僕は“記憶の吸収装置”であり、“保証人なき死の代理人”なのだ。住居なのか、事故の延長なのか、自分が証拠隠滅なのかと考える夜、「ここに本当に住んで良いのか?」という存在論的疑問がふつふつと湧きあがってくる。
2025年11月23日
-

ヌードモデルからライフモデルへ
人類が絵を描き始めた時から、人体は最も重要なモチーフの一つ。洞窟壁画に刻まれた紀元前一万五千年前の狩人達が、槍を構える仲間の筋肉の緊張を赤土と炭で記録した。フランスのラスコー洞窟の天井に躍動する人物像は、腕の角度と肩甲骨の突出を驚くほど正確に捉えている。彼等は既に知っていたのだ。人間を描くことは、人間であることを理解する行為だと。古代ギリシアのアテネでは、紀元前五世紀、ポリュクレイトスが『カノン』を著し、理想的な人体比例を数式で示した。頭部を一単位とし、全身はその七倍。臍は身体の黄金分割点に位置する。彼の彫刻『槍を持つ人(ドリュフォロス)』のために、若い競技者が何日も工房に通い、同じ姿勢を繰り返した。大理石の粉塵が舞う中、モデルは片足に体重を乗せた、コントラポストの姿勢を保ち続けた。その報酬は銀貨五枚と、夕食のオリーブとワインだったという記録が残る。これらはすべて「人間とは何か?」を探る試みであり、そのために「裸の身体」が選ばれてきた。衣服は文化や時代を映すが、裸の身体は普遍的な存在であり、生命そのものを象徴する。ヌードモデルは、この「普遍性」を芸術家に提供する。単なる被写体ではなく、芸術家が人間の形態を理解し、表現するための協力者であり、芸術の根幹に関わる役割を担っている。 *話はいきなり現代へと飛ぶ。匿名掲示板のスレッドを動画化したものに、「ヌードモデルだけど質問ある?」というタイトルがあった。そこに書かれていた断片は、芸術の場の裏側を覗かせる。ちなみに、多くは「派遣会社」や、「モデル事務所」的な組織を通じて、依頼を受ける場合もあり、個人契約や学校・アトリエとの直接契約も多い。いわゆる「派遣」というよりは「登録制アルバイト」に近い。「二〇分×六で一万円」「二セットで二万円」など、時間単位での報酬が基本。月に数回から十数回程度の仕事で、本業を補完する補助的な収入になるケースが一般的だ。また当たり前だけどお触りなど存在せず、A Vなどとは全然違う。服を脱いで、バスローブやガウンのようなものを着て向かう。素足に使い古されたスリッパ。これは「場の空気を整えるため」と、「モデル自身の安心感」のため。ポーズに入る直前にローブを脱ぎ、終了後はすぐに羽織ることで、裸と日常の間にワンクッション置ける。アトリエの片隅にはストップウォッチを持った講師がいて、時間を区切りながら「次は一〇分ポーズ」「次は五分クロッキー」と指示を出すと、空気が小刻みに振動する。長いものは「生きている時間」を見せ、短いものは「瞬間の解釈」を試す。ポーズはしばしばコンラポスト(体重の乗せ方)という、片足に体重を乗せたS字の姿勢や、フォアショーテニング(遠近の強調)を伴い、モデルはそれを身体で説明する。手の位置、肩甲骨の角度、膝の緩み、ひとつの微差が、陰影の階調を十段階変える。モデルは姿勢を変え、椅子に腰掛けたり、床に横たわったりする。ポーズは自分で指定できる場合が多く、複雑なアクロバティックなものは求められない。静止することが中心。人によっては「筋トレみたい」と感じるし、逆に「超楽」と感じる人もいる。身体を使う仕事であることは確かだが、肉体労働というより身体を貸す仕事。ちなみに報酬は多くの場合、その場で手渡しされることが多い。封筒に入れて渡されるのが一般的で、現金払いが主流。美術学校や大きな事務所を通す場合は、銀行振込になることもあるが、個人契約や小規模アトリエでは、「その日の仕事が終わったら封筒で渡す」というスタイルが根強い。この手渡しには、どこか儀式的な意味もある。仕事が終わり、服を着直し、封筒を受け取る瞬間に、「今日の時間はここで完結した」という区切りが生まれる。これは芸術であり、仕事だという明確な線引きだ。東京の大学の石造りの教室、パリのアトリエの高い天井、メキシコの小屋の乾いた光、ナイジェリアの開放された倉庫の真っ直ぐな陽射し―――。アトリエの空気は独特だ。鉛筆の走る音、紙の擦れる音、時折聞こえる椅子の軋み。冬場にはストーブの匂いが混じり、夏には汗の匂いが漂う。(ちなみに冷暖房はヌードモデルに合わせてくれるらしいので、熱かったり寒かったりすることもあるらしい、)モデルはその中心に立ち、静止する。視線を浴びる事自体が仕事であり、沈黙の中で時間が流れていく。 *ルネサンス期のヨーロッパでは、古代ギリシア・ローマの美学が再評価され、人体美を追求する動きが広まった。その時代のボッティチェリ工房では、モデルが月桂樹の枝を手に「春(プリマヴェーラ)」のポーズを取っていた。当時のモデル契約書には「月十五フィオリーノ、ヴェールで顔を覆うこと」といった条件が細かく記され、モデルは社会的視線から保護されていた。レオナルド・ダ・ヴィンチは解剖学を学び、筋肉や骨格を詳細にスケッチした。ミラノのスフォルツァ城の地下室で解剖を行った。一四八九年から一五一五年の間に、彼は三十体以上の遺体を解剖し、七百枚を超えるスケッチを残した。しかし生きた人体の観察も不可欠だった。彼の工房には「ジャコモ」という愛称で呼ばれる若い男性モデルがいた。本名はジャン・ジャコモ・カプロッティ。十歳の時にレオナルドに拾われた浮浪児で、「サライ(小悪魔)」という渾名も持っていた。成長した彼は、レオナルドの『洗礼者ヨハネ』のモデルとなる。レオナルドは彼に様々なポーズを取らせ、筋肉の動きを観察した。腕を上げた時、三角筋がどう膨らむか。膝を曲げた時、大腿四頭筋の腱がどう浮き出るか。レオナルドのノートには、ジャコモの身体の詳細な測定値が記録されている「上腕周囲二十八センチメートロ、前腕周囲二十三センチメートロ、手首周囲十六センチメートロ」(センチメートロは当時の単位換算)観察は時に五時間に及んだ。ジャコモは木製の台の上に立ち、窓からの光を浴びる。レオナルドは彼の周囲を歩き回り、あらゆる角度から素描する。時には鏡を使い、背面の筋肉を確認した。休憩時、レオナルドは彼にワインを与え、医学書を読み聞かせた。「お前の身体は、神の創造の奇跡だ」と彼は言った。『ウィトルウィウス的人体図』の制作では、レオナルドは古代ローマの建築家ウィトルウィウスが記した、人体比例を検証した。ジャコモは円と正方形の中心に立ち、腕と脚を広げる。レオナルドは定規とコンパスで測定し、理論と実際の身体が完全に一致することを確認した。この素描は、科学と芸術が一体となった瞬間の記録だ。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井画に、力強い人体を描き込んだ。ミケランジェロは足場の上で、仰向けになって絵を描いた。首と腕は激痛を訴え、絵具が眼に滴り落ちた。しかし彼が描く人体は、力強く生命力に満ちていた。『アダムの創造』の神の指に触れようとするアダムのモデルは、石工の若者だった。名前は記録に残っていないが、報酬の領収書には「モデル代、三日分、金貨二枚」とある。彼は足場の上で、腕を伸ばしたまま横たわる姿勢を保った。ミケランジェロは彼の腹筋の緊張、肋骨の浮き上がり、鎖骨の陰影を、執拗なまでに観察した。このように作品の背後には、実際にポーズを取るヌードモデルの存在があった。当時の美術アカデミーでは、「ライフドローイング(人体デッサン)」が必須科目とされ、学生はモデルを前にして人体の構造を学んだ。ヌードモデルは教育の基盤を支える存在となり、芸術家の技術を磨くために欠かせない役割を果たした。十九世紀のロダンは『地獄の門』のモデルに日本の元相撲取りを起用し、西洋美術にはない筋肉の付き方を研究した。記録によれば、彼の名前は「太郎」本名は不明。横浜の港で船員をしていたが、何らかの理由でフランスに渡り、サーカスで力技を披露していた。身長一七〇センチメートル、体重百二十キログラム。当時のヨーロッパ人としては見慣れない、重心の低い筋肉の付き方をしていた。首は太く短く、肩は丸く盛り上がり、大胸筋は厚い脂肪の下に隠れている。しかしその身体には、圧倒的な質量と安定感があり、ロダンは彼に魅了されたらしい。当時のモデル手当ては「五フランと昼食付き」で、必ずワインとローストビーフ、硬いパンだった。ロダンは太郎に様々なポーズを取らせた。しゃがむ姿勢、腕を組む姿勢、身体を捻る姿勢。太郎は力士時代の経験から、長時間同じ姿勢を保つことに長けていた。また、アトリエのストーブで温めた、ワインが振る舞われることもあったという。 *ヌードモデルなんてどう考えてもHなものだろって、2チャンネル掲示板のスレの動画らしいものを見たけど、興味本位のコメントと、実際の現場は恐ろしいぐらい違う。匿名掲示板のスレッドでも「基本的に勃 起はない」と答えられている。美術の場は「観察と描写」が目的であり、性的な空気はほとんどない。モデル自身も集中してポーズを取り、学生や画家も真剣に描いている。時間制限があるため、皆必死だ。むしろ「筋トレみたい」「静止する修行みたい」と感じる人が多い。どちらにとっても、そうした反応はまず起こらない。ただ、絵を描かない人がいることもある。アトリエには必ずしも全員が熱心に描くわけではなく、見ているだけの人もいる。モデルにとっては「視線を浴びる」という事自体が仕事なので、それもまた現実の一部。そこには「裸を見せた」という事実と、「もう普通の服を着た自分」というギャップがあるからだ。アトリエの外では、モデルもまた一人の生活者であり、芸術のために身体を貸した人間である。現代の美術大学では「ライフドローイング」の授業がより体系化されている。東京芸大の人体デッサン授業では、モデルの肌に貼られたマーカーが「骨格ランドマーク」を示し、学生は大転子や橈骨茎状突起などの、解剖学ポイントを正確に捉える訓練をする。韓国・弘益大学のデジタルアート科では、モーションキャプチャー用のヌードモデルが、二〇カ所の光学マーカーを装着し、ポーズデータを提供する。モデルの健康管理も重要だ。長時間の静止ポーズでは「ヴァーサヴィルツ技法」と呼ばれる、微小な重心移動が推奨され、血行不良を防ぐ。プロのモデルはヨガやピラティスで体幹を鍛え、筋肉のコントロール技術を磨いている。 *日本では、西洋美術が導入された明治期に、ヌードモデルの制度が広まった。しかし最大の問題はヌードモデルの不在だ。江戸時代の日本では、公衆浴場は一般的だったが、人前で裸になることと、芸術のために裸体を晒すことは全く別の文脈。特に女性にとって、モデルになることは社会的な死を意味した。東京美術学校(現・東京藝術大学)の初代校長、岡倉天心は苦悩した。西洋式の美術教育には人体デッサンが不可欠だが、モデルが見つからない。最初の授業では、男子学生たちが互いにモデルを務めた。下着を着用したまま、恥ずかしそうにポーズを取った。転機が訪れたのは明治二十年(一八八七年)ある女性が学校を訪れた。名前は「おさと」本名は不明。元芸者で、年齢は三十代半ば。彼女は経済的な困窮から、モデルの仕事を申し出た。彼女は日本で最初の職業ヌードモデルとなった。報酬は一回五十銭。当時の女工の日給が十銭程度だったことを考えれば、破格だ。しかし彼女が払った社会的代償は、金銭では測れない。最初の授業の日、おさとは震える手で着物の帯を解いた。教室には二十人の男子学生がいた。彼等もまた、初めて見る女性の裸体に硬直していた。教授の黒田清輝は、「これは芸術だ。神聖な学びの場だ」と繰り返した。おさとは三年間、東京美術学校のモデルを務めた。その間、彼女は近所から白い目で見られ、子供達から石を投げられた。大正時代になると、モデルの供給は徐々に増えた。しかし依然として社会的偏見は強かった。昭和初期の記録によれば、モデル達は本名を明かさず、偽名や芸名を使った。「桃子」「百合」「菫」といった花の名前が好まれた。当初は文化的抵抗も強く、「裸を描くこと」への偏見があったが、次第に芸術教育の一環として定着していった。日本画や浮世絵では、必ずしもヌードを直接描くことは少なかったが、人体表現の基礎を学ぶためにモデルは重要視された。現代でも美術大学や専門学校では、ヌードモデルが学生の学びを支えている。かように、ヌードモデルは単に「裸で立つ人」ではない。(そんなことを考えている人がいる事自体、俄かには信じ難いが、)彼等はポーズを通じて「身体の物語」を伝える。緊張した筋肉、リラックスした姿勢、動きの途中で止まった瞬間。これらはすべて芸術家に「人間の生きた形」を示す。また、ヌードモデルは「時間」を体現する存在でもある。数分間の短いポーズから、数時間に及ぶ長いポーズまで、モデルは静止し続ける。その忍耐と集中は、芸術家に「観察する時間」を与え、作品に深みをもたらす。 *肉の質量、皮膚のたるみ、骨の突起、筋繊維の収縮、そうしたすべてが「質感の辞書」だ。痩せている人は線が細く、骨格の輪郭がはっきり見え、ただし陰影や立体感をつけるのが難しく、単調になりやすい。よく言われるのは、ふくよかな人や、筋肉質の人の方が勉強になるということだ。ふくよかな人は肉の柔らかさや重み、皮膚のたるみや曲線が豊かで、光と影のグラデーションを学ぶのに適している。描き手にとっては「量感」「質感」を表現する練習になる。筋肉質な人も、筋肉の起伏や緊張が明確で、解剖学的な理解を深めるのに最適。ゴツゴツしたラインは「構造」を描く練習になる。どうしてそういうことが言われるのかといえば、やはり、陰影の幅が広いからだ。ふくよかさや筋肉の起伏は、光の当たり方で大きく変化する。これを描くことで「立体を平面に落とし込む力」が鍛えられる。それに、痩せたモデルだけでは「理想化された線」しか学べない。ふくよかさや筋肉質な身体を描くことで、現実の人間の多様性を理解できる。ジェンダーや多様性への意識が高まり、従来の「理想的な身体像」だけでなく、さまざまな体型や年齢のモデルが求められるようになっている。多様性を重視する現代アートシーンでは、従来の美の規範に囚われないモデルが活躍する。乳房切除術を受けた乳がんサバイバー、手術跡は、胸の真ん中を斜めに横切る長い傷跡として残っている。妊娠八ヶ月の妊婦、大きく膨らんだ腹部、張り詰めた皮膚、へその変形。彼女の身体は、生命を育む器だった。齢八〇歳を超えるモデル。その深く刻まれた皺、垂れた皮膚、骨ばった関節、老人性の色素沈着。しかしその身体には、独特の威厳がある。日本のヒロシマでは、原爆被爆者の女性がモデルを務めたことがある。彼女の身体には、ケロイドの痕があった。爆心地から二キロメートルの地点で被爆し、熱線で皮膚が焼けた。最初、彼女はモデルになることを拒んだ。「この醜い身体を、誰が見たいというのか」と。しかしある画家が説得した。「あなたの身体は、歴史の証人だ。それを記録することは、平和への祈りだ」彼女は同意した。そして描かれた絵は、「生の証」と題され、広島平和記念資料館に展示された。これらの身体は「生の履歴書」として機能し、アーティストに新たな表現可能性を開示する。ロンドンのスレード美術学校では、「クロスカルチャー・ボディ・スタディ」と題し、様々な人種のモデルを招いた比較解剖学の授業が行われる。肌の色・質感の差異が光の反射率に与える影響を、学生は水彩とデジタルツールの両方で記録する。これは、芸術が「人間の多様性」を映す鏡であることを示している。それに複雑な形態を前にすると、描き手は「何処を強調し、何処を省略するか」を考える。これは表現力を磨く大事な訓練になる。ピカソの線が子供の落書きのように見えると揶揄されることがあるが、そこに至れるかどうかは、観察できる眼と描写する手の訓練量に依拠する。観察とは、細部の蓄積だ。一歩引いてこの人いい身体しているなと思っても、逆に、もっと上手く表現しなくちゃなと思うものだ。とはいえ、ヌードモデルという言葉には、しばしば誤解がつきまとう。裸であることから、性的な文脈と混同されることがある。(テレビからおっぱいは何故消えたのかと似ている)しかし、美術教育や芸術制作におけるヌードモデルは、性的対象ではなく「学びの対象」である。彼等の存在は、芸術のための協力であり、社会的にも尊重されるべきものだ。近年では「ライフモデル」という呼称が使われることもあり、より中立的で誤解を避ける表現として定着しつつある。つまり彼等は「生きた形」を提供する者なのだ。アトリエには小道具が散らばる。古びたスツール、布の重ね、木製のマールスティック(筆支え棒)目盛りが擦り切れたストップウォッチ、瓶に残る灰色の呼気、暖かい茶を入れたサーモス、折り畳みの鏡。照明はしばしば一灯のランプ。斜めから当てるスポットが、人の身体を彫刻のように切り取る。黒と白のグラデーションをつくるために、講師は「半値(ハーフ・トーン)」や「コアシャドウ」の言葉を使う。描き手達は木炭でクロスコンツアーを引き、コンテでハイライトを跳ね上げる。技術用語が飛び交うとき、そこは教育の現場であり、職人の仕事場でもある。現代のヌードモデルは、美術教育だけでなく、写真芸術やパフォーマンスアートにも関わっている。写真家は人体を光と影で表現し、現代美術家は身体そのものを作品の一部として扱う。ヌードモデルは、「静止する存在」から「表現の主体」へと役割を広げている。さらに、デジタル技術の発展により、3Dモデリングやヴァーチャルモデルが登場した。ベルリンの現代アートスタジオでは、モデルが透明なアクリル板に身体を押し付け、変形する肉体の形状を「圧縮美学」として提示する。上海の実験工房では、モデルが中国書道の巨大な筆を持ち、墨の滴りが身体を伝う様を「生きた筆致」として記録する。デジタル時代のモデルは、3Dスキャナーの中で無限のポーズを固定できる。スタンフォード大学開発の「ライトステージ」では、モデルを百七十二台のカメラで同時撮影し、あらゆる角度からの光の反射データを収集する。しかしながら、VRゴーグル越しに再現された仮想モデルには、汗の輝きや体温による空気の揺らぎといった、生命の副次的現象が欠如している。「デジタルモデルは便利です」とある美大生は言う。「しかし、本物の人間がそこにいる、という緊張感が全く違います。本物のモデルは呼吸している。疲れている。存在している。それが、描くという行為に深みを与えるんです」実際の人間の身体が持つ「温度」や「質感」は、依然としてヌードモデルにしか表現できない。「アナログとデジタルは、対立するものではありません」と教授は言う。「両方を理解することで、より深い表現が可能になります」生身の存在は、芸術に不可欠なリアリティを提供している。モデルとアーティストの間に交わされる「沈黙の対話」は、時として深い哲学的問いを生む。モデルが十分間のポーズで僅かに変化する呼吸のリズムは、ルーベンスの描いた「肌の揺らぎ」そのものだ。モデルの肩に残る古傷の痕は、ゴヤが戦争の惨禍を描いた『五月三日』の銃創のモデルとなった
2025年11月23日
-

イラスト詩「おでん」
秋の深まりとともに木々が色づき、やがて初冬の訪れを告げる冷たい風が吹き始める頃、街角にはほのかな灯りがともり始める。ほら、眠っていた記憶が一つ一つ眼を覚ます―――よ。一年中警告している、路面凍結っていう言葉が突然息を吹き返す時期さ、まるで懐かしい友を待つように、ふわっとあの香りがして、あちこちでおでんの看板や赤ちょうちんがほっこりと輝き、人々の心を温かく包み込む。いきった電飾、ここは何処の国だって思うクリスマスツリーだけど、こんな融通度の高い節操のない国、他にないだろうっていう気もする。和の精神って、ビジネスモデルの柔軟性のことなんじゃないかって思える、今日この頃。その神髄といえば、やっぱり、鍋料理なんじゃないかっていう気がする。闇鍋っていう連想からいっているけどね、毎年新商品が出て来るってすごいよね、消費の速度を上げて忘れられてゆくけど、消えてなくなったりしないものも、ある。イラストで描かれる際の典型的な組み合わせの、串に刺さったこんにゃく、大根、ちくわ。実はまだ一度も食べたことがないし、やろうとしてみたこともない。牛筋はあるけどね。人それぞれ思うところあると思うけど、それは僕にとって一種の神話だね。ステレオタイプな記号であるのに、それが全然機能していないっていうね。いやいやいやいや、本当にあるのかなってググってみると、本当にあるんだよね。でもこんなこと、君にもあるんじゃないかな?近年においてはコンビニでの調理販売、自動販売機での缶詰販売などが行われているので、自炊しない者でも手軽に食べることが出来るが、基本的には家庭料理だ。スーパーマーケットの商品棚に並ぶ簡易セットを見ると、ふと胸の奥に、時代の速足を感じる。砂時計の砂が思ったより速く落ちていくのを見ているような感覚。肉料理だらけのおせちをドラッグストアのチラシで見た時、「これも流行りか」と小さく呟いてしまった。正月も海外旅行へ行く人がいる、それを揶揄するつもりは一切ない、でもちょっとずつ子供時代に思っていたような当たり前が、まるで古いアルバムの写真が色褪せていくように、もっと別のものにするりと入れ替わっていく奇妙な感じとして、胸の奥から離れないでいる。それでも、変わらないものがあると信じたいというのは、平等に時が流れている証拠なのかも知れない―――ね。そもそも、おでんの起源は平安時代の「田楽」に遡る。豆腐やこんにゃくに味噌を塗って焼いた素朴な料理が、江戸時代に「煮込み」へと変化し、庶民の胃袋を満たすファストフードとなった。江戸の町角には屋台が立ち並び、夜更けに仕事を終えた人々が、湯気に誘われて集まった。おでん屋は、寒さを凌ぐだけでなく、孤独を癒す場でもあった。リアクション芸の定番で、熱々のおでんを食べさせる熱々おでん芸というものもあるが、おでんは熱さが命だ。はふはふ、しながら食べる。はふはふと息を白くしながら食べるその行為こそ、冬がくれるささやかな祝福だ。からしや、七味唐辛子を好む人も少なくなく、その刺激は、冷えた身体にそっと火を灯す小さな魔法だ。カウンターに座れば、隣の客との距離は近い。会社帰りのサラリーマン、常連の老人、一升瓶の栓が抜かれる乾いた音、ビールジョッキがこつりと触れ合う瞬間。そういえば愛知県では八丁味噌で出汁を調味し、味噌だれを付けて食す「味噌おでん」がポピュラーであり、おでんといえば主にこの味噌おでんを指す。ちなみに福岡県など九州地方の一部で食べられている、「豚骨おでん」なんていうのも、ある。正直に言うと、両方さっき調べていて知った。トムヤムスープで煮込まれているおでんもあり、地球がいよいよ丸いことを思い出させてくれる。ファミリーマートではおでんのつゆに麺を入れた、「おでんラーメン」を販売しているけど、この理屈でいくと、うどんやそばを入れたっていいのかも知れない。何でもありっていう時、僕は地中海風という言い方をする。サラダに果物を入れた味覚がバグる料理で、先入観との闘い、冒険心をくすぐられた熱いバトルを言う。でもさ、偉そうなことを言うのは止めようぜ、いや、最初から知っていたっていう顔ぐらいはするけどね。観光客、そして一人で訪れる若者。路地裏に現れた屋台でも、お店でも、提供するものは変わらない。何処へ行っても変わらない母の味なんだろうね。おでん屋の鍋を覗けば、そこには日本人の生活史が詰まっている。出汁を吸い込む音なき時間の中で、食材の博物館として、文化の縮図としての一面が垣間見える。大根は芯まで染みる象徴であり、卵は新しい命を思わせ、こんにゃくは無駄を削ぐ質素さを示し、ちくわやはんぺんは漁村の記憶を呼び起こす。がんもどきは豆腐文化の延長線上にあり、昆布は海の恵みを伝える。関東のおでんは濃い口醤油で煮込み、黒ずんだ大根が江戸の粋を語る。一方、関西のおでんは薄口醤油で透明感を保ち、出汁の旨味を前面に押し出す。大阪の老舗「たこ梅」などでは、昆布と鰹の調和が芸術的に仕上げられている。地域ごとの出汁の哲学は、まるで方言のように土地の個性を映し出す。近年のおでん屋では、定番に加えて「変わり種」が人気を集めている。例えばトマト。丸ごと鍋に沈められたトマトは、出汁を吸いながらも酸味を保ち、口に含めば爽やかな旨味が広がる。赤い果実が湯気の中で輝く姿は、まるで異国からの客人が日本の宴に加わったかのようだ。さらにアボカド。クリーミーな果肉が出汁に溶け込み、まるでポタージュのような舌触りを生む。和の鍋に南米の果実が浮かぶ光景は、グローバル化の象徴であり、食文化の柔軟さを示している。おでん屋は伝統を守りつつも、時代の風を取り入れる場なのだ。他にも蛸、黒はんぺん、豚モツ、ソーセージ、チーズ入り巾着、シュウマイや、たこ焼きに至るまで、ちなみに、果物を入れるおでんというのも存在する、創作系だが、フルーティーで新鮮な味わいもさることながら、彩り豊かで楽しく、四季を演出しやすいということもある。ただ、こうした斬新な試みは、まだ普通のおでん屋ではなかなかお目にかかれない。でもその内さ、これらの新しい仲間達も、定番の具材と肩を並べる日が来るかもしれない。ところでさ、おでん屋の魅力は「待つこと」にある。注文してすぐに出てくる料理ではない。具材はじっくり煮込まれ、出汁が染み込むまで時間がかかる。客はその間、湯気を眺め、会話を楽しみ、心を落ち着ける。おでん屋は「時間を味わう場所」なのだ。忙しない現代社会の中で、ほんの少しだけ時計の針を遅くしてくれる魔法のような場所。そんな場所を見つけられない人もいるだろう、僕も大人になってそんな場所を見つけたいって思った。元気をもらえる場所、落ち着ける場所、中々そう滅多に見つかる類のものじゃないけど、人生ってそうやって少しずつ意味のあるものに変わるんだ。出汁の温もりだけじゃない、人と人との繋がり、時間の流れ、そして変わりゆく時代の中でも変わらない何かを感じよう。おでん屋は「選択の場」でもある。鍋の中から何を選ぶかは、その人の性格や気分を映し出す。選ぶのが苦手な人や、何喰ったって別に変らないと思う人は、「おまかせ」と言うといいかも知れない。きっと、おでんの神様があなたにぴったりの一品を用意し、あなたの夜にぴったりの温度をくれるだろう。
2025年11月23日
-

18
平常心祭りだねって言うからデジデトなんだ。リアルなオフライン、何気ない一瞬が、しあわせ。頬が熱いのも、鼓動が速いのも、上手く話せないのも。溢れ出しそうなこの気持ちは、一瞬泣きそうにさせて、やっぱり単純作業オンリーの、繰り返しじゃ、駄目だな、わたし。
2025年11月23日
-

17
stardust story夜のプール入っちゃったね。子供の頃さ、知らない町行きたいってなかった?あたし、それだと思うんだ。ずっと、ドキドキしっぱなし。すごいよね、馬鹿みたいだよね。みんな、知らないんだ、世界は、白線の、向こう側にあるって。当たり前のことだけ出来ればよかった、特別なことなんかなくていい、でも、スタートの合図が宙を舞って、鳴らすハートは加速する。ねえ、もっと遠くまで行きたい、昨日のあたしを追い越してみたい。
2025年11月23日
-

16
近況を聞けない今日も工場は稼働中ですよ、戦争需要で、作り放題、売れ放題、ただ、お金がこちらへは多く、まわってきませんね。世の中というのは、上手くできていやがります、ね。こき使われて、怒鳴られて、でも、孤児のわたしを引き取って、賃金があるのは、感謝です。小学校にミサイルが墜ちたと、聞きました。みんな大丈夫かな。ううん、きっと大丈夫、戦争終わったら、みんなと会いたいな。わたし、夜の市場で、お腹いっぱい食べるんだ。今度、両親の墓に、行こうと思ってるんだ。
2025年11月23日
-

15
食欲と感傷秋はどうして物悲しいのでしょうか、焼き芋食べたい。小さな頃、川辺でもみじが、流れているのを見たんだ。裏山の森に、団栗拾って、夕方の住宅街には、夕餉の匂いがして、あたたかくて、心細いものなんて、ひとつもなかったな。あの頃は守られていたと、知るばかりで、自分が弱いことや、無力であることを知らなかった。大人になるって、そういうことなんだね。ああ、神様、おでんが食べたい。
2025年11月22日
-

14
設定君さっき、犬苦手とか言ってたのに、普通に飼ってんじゃん。これは隣の犬が脱走してきて、捕縛しているの、まったく反省しないな、ビーフジャーキーあげないぞ(?)その―――犬好きなの?犬は好きじゃない、ただ、ちょっと、遊んでやっているだけ。頑なに猫好き装ってたのに、イヌ派だよね?だって、ネコ派って、めっちゃクールだもん、風紀委員長設定だもん(?)えーと、えーと、馬鹿なの?
2025年11月22日
-

13
無口な彼何処へ行きましょうか?夜になったら―――話すね・・。ごめん、いまがいいかな。しょ・・・商店街。行きたい場所とか、ある?ぶらぶら―――歩く・・。ノープラン?土曜日来いって言われて・・・、荷物持てってことかと思った・・・・・・・。デート、なんだよね。平均的な男子高校生の、妄想の中では、そのような間違いが、生まれています・・・。
2025年11月22日
-

12
彼氏の背中の温もり。人膚の温もり。セ氏三六.五度という、生命維持の境界線を示すサーマル・シグネチャ、蛍光灯を点けていない教室は、そろそろ夕方の闇に染まって、弱い散文は止まれない、青白い深海魚の鰭のように静かに揺れ、その大きな背中は何か考え事をしている。呼吸の位相と鼓動の遅延を含んだ時間の層。DNAは絡まった二匹の蛇に似ている、だろう―――か。教室の一気圧の世界にいながら、意識は遥か深い無光層―――へ・・。制服のリネンが夕焼けに映え、紺のスカートの皺がたわむれる。埃は光の帯を切り分け、微小な粒子はカメラのシャッター速度でしか、捕らえられないリズムを刻む。暗流を遡る冷やかな鮭の群れのように均一な速度で流れた、チャイムが鳴ってフェードアウトしていく、腐った木造の階段をのぼっているような気がする。密度のある暗がりは幾重にも重なり、奥へ奥へと続く迷路のように空間を圧縮していく。不安定な感覚が足裏から伝わってくるから、寄り掛かる―――んだ・・。薄暗い玄関、自分の部屋のベッドのシーツの影、そんなものを思い出していると、そろそろ帰らないかと声をかけてくる。異論を廃して、真夏の疾走感を喰らった先にある、通学鞄のファスナーには、小さな金属のチャームが一つぶら下がり、そこにはパリの古いメトロの路線図の縮図が、刻まれているようにも見える。人の心を知った気になって、笑う気分はどうだい?否応なしに、名前が追い掛けて来る。夢の続きを見ているわけにはいかない、だってわたし達は、ここに住んでいるわけではない。この教室という仮設の舞台装置に、一時的に配置されたアクターに過ぎない。あともう少し、それは十五分後で収束する。何を言われても超然と澄ましきってたい。あともうちょっと、それは黄昏の終わり。何を言われても萎靡して振るわない耳底。両眼視差による立体視が機能しなくなり、遠近法的な手がかりだけが、距離を推定する唯一の情報源となる。人は暗闇を遠ざける、でも暗闇の中でだけ、さらけ出せる本音というのも―――ある。横顔は黄昏れに溶ける、窓硝子越しに頬を撫でる光。睫毛の影が長く伸びて、机の上の教科書の頁を揺らし、繊細な縞模様を投影する。やがて闇の粒子が網膜に不思議な図形を描き、モアレ・パターン、テクスチャード・ハロー。描かれた図形はしばらくすると音もなく崩れ、別の図形が描き出され、水銀のように静止した空間の中で、闇だけが動いている。天文学の観測写真のような、目蓋を閉じた黒い空間に光の残像・・・・・・。ハッブル・ディープ・フィールドのような、無限の過去と未知の現在が交錯する、空間の記録。放課後の空気が陽だまりの中で色を変え、スカートの襞がオレンジに、染まっていく気がする。カーテンの隙間からあまい光が射し、結末はまだ定まらない。放課後の光は静かに塗り替えられ、スカートの襞はさらに深い橙へと変わり、カーテンの隙間を抜けた光は、まるで演出家がそっと舞台の角度を調整したかのように、二人の影を長く伸ばしてゆく、その曖昧な表現のその先に、ディストピアがあるのかどうか、教室の静寂に包まれながら、教室の時計の針だけが動いて―――いる・・。
2025年11月22日
-

詩的ハイジャック Vol.5「伝記劇 カーネル・サンダース」
一八九〇年九月九日、インディアナ州ヘンリービル。秋の収穫期を迎えた小さな町に、一人の男児が産声を上げた。ハーランド・デーヴィッド・サンダース。この名を聞いて即座に誰かを思い浮かべられる者は少ないだろう。だが、「カーネル・サンダース」と言えば話は別だ。白いスーツに身を包み、白髭を蓄え、黒縁眼鏡をかけた老紳士。あるいはそう、秋葉原でシコいものを見つめ続けて、悪戯されて撤去されたあの人形。世界中のフライドチキン店の前に立つ、あの人形の主である。ただまあ、評判はあんまりよくなくて肖像画になったり、もう名前とロゴもちゃっかり定着しているしね。小学校のわけのわからない変な銅像みたいなものだね、でもあれきっと結構高いんだぜ。素晴らしき資本主義。さて、ヘンリービルは人口わずか数百人の農村地帯。木造の家屋が点在し、舗装されていない道路には、馬車の轍が深く刻まれていた。要するにド田舎だ。インディアナ州って聞いて何か思い浮かぶか?僕は何も思い浮かばない。トウモロコシ畑とバスケットボールぐらいしか知らない。まあいい、底の抜けた戸惑いを持ちながら話を続けよう。サンダース家は決して裕福ではなかった。父ウィルバート・デーヴィッド・サンダースは、小さな農場と養鶏場を営む労働者階級の男で、朝は霧が立ち込める中、鶏舎の扉を開け、日没まで畑を耕す日々を送っていた。母マーガレット・アン・ダンレヴィは、アイルランド系移民の血を引く、信仰心の厚い女性だった。信仰心が厚いってのは、つまり、毎週教会に通って、聖書を読んで、神様に祈れば何とかなると思っていたってことだ。どうでもいいけど、僕はユダヤ教の超正統派とか、性に厳しいカトリックとかいう馬鹿なことを考えちゃうね、ごめんねごめんね。まあ、当時はそれしかなかったんだろうけどね。幼いハーランドが五歳のとき、運命の暗転が訪れる。それにしても鶏を育てていた男の息子が、後に世界中で鶏を揚げまくることになるとは、歴史の皮肉というやつだろうか。いや、単なる偶然か。ちなみにSNSで、こういう馬鹿げた偶然について語ると炎上するからね、出典は米津玄師と震災結び付け「深い意味感じる」 「うっせぇわ」作者のツイートから。お前こそ、うっせぇわ。そやねん。一八九五年の冬、父ウィルバートは、激しい咳と高熱に苦しみながら床に伏した。当時、抗生物質など存在しない時代である。医者は往診に来たが、為す術もなく首を振るばかり。父は肺炎で、わずか数日のうちに息を引き取った。三十一歳という若さだった。葬儀の日、雪が降りしきる墓地で、幼いハーランドは母の黒いドレスの裾を握りしめていた。周囲の大人たちのすすり泣きと、凍てついた土に棺が下ろされる鈍い音が、少年の記憶に深く刻まれた。この日から、サンダース家の困窮が始まる。いわずもがな、父の死後、母マーガレットは三人の幼い子供を抱え、途方に暮れた。貯蓄などほとんどなく、農場は売却せざるを得なかった。彼女は町の缶詰工場で職を見つけた。朝六時から夕方六時まで、立ちっぱなしで、トマトやインゲン豆を缶に詰める単調な作業。手は荒れ、指先は切り傷だらけになった。賃金は週に三ドル五十セント。三人の子供を育てるには、あまりにも少ない。日本の貧困層でシングルマザーが深刻なのは、給料が少ないからだ。男女平等に関してはいくらか申し立てたいことはあるけれど、(あなたは内部で抽象的な読者と対話しないと思うが、)もっと保護を厚くしてもよいのではないかと思う。一人親家庭の貧困率は約五割。百年以上経っても、人類は何も学んでいない。だったら千年経っても学ばないだろう。さて、母が工場で働く間、長男のハーランドは家事と弟妹の世話を任された。わずか六歳の少年が、薪を割り、火を起こし、朝食のオートミールを煮る。弟のクラレンスと妹のキャサリンは、まだ幼く、兄を頼るしかなかった。六歳だぞ、六歳。今の六歳児なんて、Switchでマリオやってるか、YouTubeでヒカキン観てるかだろ。それで時々となりのトトロを観たりして、宮崎駿に洗脳されてゆく。こわい。ちなみに僕もいわゆる一つのとなりのヘドロだからね。それが薪割りだ。火起こしだ。料理だ。児童労働もいいところだが、当時はそれが普通だった。時代が違うって言えば聞こえはいいが、要するに人権なんてなかったってことだ。ハーランドは母が仕事から帰る前に、夕食の準備もしなければならなかった。じゃがいもの皮を剥き、豚の塩漬け肉を炒め、コーンブレッドを焼く。失敗すれば母は黙って涙を流した。その沈黙が、少年には叱責よりも辛かった。この経験が、後のサンダースの料理の腕を培った。まあ、そう考えれば、人生に無駄な経験なんてないのかもしれない。いや、あるか。でも少なくとも、サンダースにとっては、この地獄のような少年時代が、後のフライドチキン帝国の礎になったわけだ。児童虐待後の子供として考えてみる?それとも兄弟のために家族のために生きた男が、どんな心の傷を抱えていたかという、ハートウォーミングな路線で書いてみる?やめろよ、気持ち悪い。十歳になると、ハーランドは近隣の農場で働き始めた。夜明け前に起き、霜の降りた畑で芋を掘り、家畜小屋の糞を掻き出し、干し草を運ぶ重労働。学校には通っていたが、授業中に居眠りをして教師に叱られることもしばしばだった。教室の窓から見える空は、いつも遠く、自由で、彼の手の届かないところにあった。などと―――ロマンチックに書いてみたけど、要するに疲れ果てて授業に集中できなかったってことだ。学力なんて身につくわけがない。貧乏だとIQが下がるという話もあったけど、大人びた少年ほど同年代の友達が少ない。それを発達障害とか書いてみる?悪意をこめて、空想癖のあった子供の未来を見つめてみる?赤毛のアンは多産のウサギだった、よく出来てるよ、どうしてあそこまで書いちまったんだって、魔女の宅急便のその後ぐらい僕はびっくりだよ。十二歳の春、母が再婚した。相手はウィリアム・ブロードという名の鉄道労働者で、大柄で無口な男だった。ハーランドは継父と馬が合わなかった。ブロードは酒を飲むと粗暴になり、母を怒鳴りつけ、時には手を上げた。ハーランドが庇おうとすると、「他人の子に口出しされる筋合いはない」と突き飛ばされた。少年の胸には、怒りと無力感が渦巻いた。ああ、クズ継父の登場だ。これもアメリカン・ドリームの一部なのか?貧困と暴力と絶望のカクテル。美味しそうだね、まったく。十四歳の夏、ハーランドは学校を退学した。理由は明確ではない。農場の仕事が忙しかったこと、家庭内の不和に耐えられなかったこと、そして何より、学問に希望を見出せなかったこと。彼は家を出る決意をした。ある朝、母が工場へ出かけた後、ハーランドは質素な荷物をまとめ、弟妹に別れも告げず、家を後にした。振り返ることはしなかった。十四歳で家出。今なら児童相談所案件だが、当時はそんなものはない。少年は一人で世界に放り出された。タフにもなるさ。優しいだけでは生きてはいけないさ。で、なんでお前は急にハードボイルド小説の真似っこしてんの? *家を出た十四歳の少年は、まず農場労働者として働いた。ああ、ここからサンダースって書くね。いちいちハーランドって書くの面倒くさいし。どうでもいいけど、ハラスメントって書きそうなんだよね、ごめん、普通に嘘だけど。ニューオールバニーの大規模農園で、綿花の収穫、牛の世話、柵の修繕など、あらゆる雑用をこなした。賃金は月八ドル、食事と寝床付き。農夫たちと同じバラックで寝起きし、夜は疲れ果てて泥のように眠った。十五歳でインディアナポリスに出て、市電の車掌になった。制服を着て、乗客から運賃を集め、停留所をアナウンスする仕事。初めて「社会人」としての誇りを感じた。だが、ある日、運賃箱の金額が合わず、上司から横領を疑われて解雇された。無実を主張したが、聞き入れられなかった。この屈辱は、彼の心に深い傷を残した。きっと他の奴がちょろまかしたんだろう、世界名作劇場を観ていると大体みんなそう思う。主人公は無実で、悪いのは意地悪な大人。でもまあ、実際そうだったのかもしれない。サンダースは短気だが、嘘つきではなかったからな。たぶん。十六歳で軍隊に志願し、キューバに派遣された。米西戦争の余波で、カリブ海の警備任務に就いた。灼熱の太陽の下、銃を担いで行進し、夜は蚊とマラリアの恐怖に怯えた。軍隊の規律と上下関係は、彼の性格に合わなかった。上官の理不尽な命令に反発し、営倉に入れられたこともある。要するに、反抗的なガキだったってことだ。軍隊で営倉入りって、相当だぞ。まあ軍隊なんて自衛隊の親戚か上位互換だから、イエッサーの世界、普通は従うものだ、理不尽でも。そうやってPL学園は生まれたんだよ、駒澤大学なめるなよって感じ、そうやって伊良部秀樹はPL学園に行かなかったんだよね。関係ねえんだよ。でもサンダースは従わなかった。このへんの頑固さが、後に役立つことになる。今はただの問題児だが。除隊後、彼は再び職を転々とする生活に戻った。鉄道の機関助手、ボイラー工、保険外交員、塗装工、タイヤセールスマン、数え上げれば際限がない。現代なら完全に「ジョブホッパー」のレッテルを貼られる。履歴書見た瞬間、人事部が書類を破り捨てるレベル。「この人、何一つ続けられないんですね」って言われて終わり。でもまあ、当時はそういう生き方も珍しくなかった。アメリカン・ドリームってのは、要するに「一発当てるまで転々とする」ってことだからな。どうでもいいけど、家を転々とする「アドレスホッパー」っていうのもいる、浮浪者じゃないんだぜ、ユーチューバーでもない、まあ、人それぞれ生き方っていうものがあるからな。三十代や四十代まで仕事で働いて放浪する、ドロップアウトする、そういう人達も一定数いる、間違いだとは思わないよ、生きるか死ぬか、だったら。ただ、家庭持ってる、子供もいるっていうのに、それをやった日には、顔面変形するまでシバくとは思いますが。ある時期には通信教育で法律を学び、弁護士資格を取得した。そんな簡単に取れるものなのかと読者は思うかも知れない、あのね、身を守るために銃を撃て、自衛せよって国だぜって僕は答えるだろう。あと、十数時間運転しっぱなしでも大丈夫なタフなお国柄。ぶっ飛んでるんだよ、ねじがね。もう余計なこと書くな。ちなみに、当時の通信教育弁護士資格ってのは、今でいうオンライン大学みたいなもんだ。ちゃんとした法律知識は身につくが、実務経験はゼロ。だから、まともな法律事務所には雇ってもらえない。サンダースは自分で事務所を開くしかなかった。そんなわけでカンザス州の小さな町で法律事務所を開いたが、ここでも彼の短気な性格が災いした。ある日、依頼人との料金交渉が口論に発展した。相手は支払いを拒否し、サンダースを詐欺師呼ばわりした。カッとなったサンダースは、机を叩き、相手の胸倉を掴んだ。依頼人も応戦し、法律事務所の中で殴り合いが始まった。書類が散乱し、インク瓶が割れ、椅子が倒れる音が廊下に響いた。隣の事務所から人が駆けつけた時には、二人とも鼻血を流し、息を切らせていた。法律事務所で殴り合い。弁護士が依頼人と殴り合い。これ、コントか?いや、実話だからな。この事件は地元新聞に載り、サンダースの弁護士としての評判は地に落ちた。彼は再び町を去った。 *二十歳の時、サンダースはジョセフィン・キングという、地元の商店主の娘と結婚した。ジョセフィンは穏やかで信仰深い女性だったが、夫の放浪癖と粗暴な気質には次第に耐えられなくなった。まあ、職を転々とする男と結婚しようとする時点で、遺伝子の不思議なめぐりあわせとしか思えないわけだが―――。ジョセフィンさん。愛? 希望? それとも単なる若気の至り?マジでビックリだよな、白髪の好々爺みたいなサンダースが、実はあれのあれもんだったなんてな。結婚当初、サンダースは鉄道会社で働いていた。給料は悪くなかったが、彼は仕事に不満を抱き、数ヶ月で辞めてしまった。働け。次は保険外交員、その次は塗装工。辞めるな。働け。職を変えるたびに家計は不安定になり、家賃の支払いが遅れ、借金が増えた。ジョセフィンは長女マーガレット、長男ハーランド・ジュニア、次女ミルドレッドの三人の子を産んだ。だが、サンダースは父親としての責任を十分に果たせなかった。仕事のストレスを家庭に持ち込み、妻に当たり散らすこともあった。ろくでなしの決定打。文句を言うぐらいなら、口をチャックしとけ。そしてこういう手合いは酒にもよく飲まれる。辛いことを誤魔化したいんだろう。サンダース褒める気ある?言っとくぜ、僕はまったくない。この男、ここまでの人生で、まともなことを何一つしていない。父親失格、夫失格、労働者失格。三拍子揃った屑だ。他人だからいいけど、みなさんそういうの好きじゃないですか、他人だから何も言わない、知らない、聞かない、でもひとたび自分の範囲内にそんな人間がいたら、誰だってそういう言い方をする。法的な対策、警察への不平不満もタラタラダラダラ溢れてくる。みなさん、そういうの好きじゃないですか、大好きですよね?頭の中、幼稚園から成長してないんですよね、お馬鹿さんなんですよね?キチガイを見たらちゃんとキチガイと言わなくちゃいけない、心療内科へ行けって言わなくちゃいけない、時には暴力で成敗しなくちゃならないこともある。きれいごとなんて取ってつけられた嘘だ。ある晩、酒を飲んで帰宅したサンダースは、夕食が気に入らないと皿を床に叩きつけた。陶器の破片が飛び散り、幼い子供たちは泣き出した。ジョセフィンは黙って破片を拾い集めた。その姿を見て、サンダースは何も言えなかった。何も言えなかったって?いや、言えよ。「ごめんなさい」ぐらい言えよ。でも言わなかったんだろうな。プライドが邪魔して。男のプライドってやつは、本当に厄介だ。まあもっと厄介なのは、いきなり濡れて縮んだ海水パンツを脱ぐような努力をしたみたいに、泣く男だ。去勢されてる。やがてジョセフィンは決断した。一九三〇年のある朝、サンダースが仕事に出かけた後、彼女は子供たちを連れて実家に戻った。置き手紙には、「もうあなたとは暮らせません。子供たちのために、別れます」とだけ書かれていた。申し訳ないけど、当然の判断だ。賢明だ。よく耐えたと思う。普通ならもっと早く逃げ出している。子供のいる母親は強いからね、でも、もっと強くならなくちゃいけない、子供を育てていかなくちゃいけないからね。サンダースは激怒した。さあ始まるぜ、カーネル・サンダースの誘拐劇がよお、いよいよ、さらってさらってさらいにいくのだぜよお。ちょくちょくネタ入れるのやめてくれる?妻の実家に押しかけ、「息子を返せ! 俺の子供だ!」と怒鳴り散らした。義父が出てきて説得しようとしたが、サンダースは聞く耳を持たなかった。ある日の夕方、サンダースは学校帰りの息子ハーランド・ジュニアを、道端で待ち伏せし、車に乗せて連れ去った。息子は泣き叫び、「お母さんのところに帰りたい!」と至極もっともなことを訴えたが、え、だってこいつ屑夫じゃん、まるで駄目男じゃん。しかしサンダースは「お前は俺の息子だ」と言い張った。誘拐だ、誘拐。溜息出て来るだろう。実の息子だろうと誘拐は誘拐。犯罪だ。しかも子供は嫌がっている。最悪だ。誘拐に来たのがドラえもんや、トトロだったら、子供達はみんな喜んでついていくだろう、可愛いしね、なんか色々したいことがあふれてくるしね、でもファンシーな要素なんかひとつまみもない。当たり前だのクラッカー、この誘拐事件は警察沙汰になり、結局、義父の仲介で息子は母のもとに戻された。サンダースとジョセフィンは一度和解を試みたが、すぐに再び衝突し、最終的に離婚が成立した。この失敗は、サンダースの人生における最大の痛恨事の一つとなった。あのね、カーネル・サンダースに恨みはないけど、こういうロクでもない奴がもてはやれる例って枚挙にいとまがないんだ。スティーブ・ジョブズも娘を認知しなかったし、イーロン・マスクも子供を放置してるし、ね。みんながみんなじゃないよ、浮気してるとか、麻薬やってるとかそういうことでもないよ、ロクでなしっていうのは。下らない人間はわんさかいて、一見綺麗に着飾られた、成功者ってのは大体、人間としてはクズなんだよ。ポール・マッカートニーが実は下らない人間だって、気付くエピソードがあって以来、僕は一度もあいつの歌を聴いてないからね。僕はビートルズが大好きだった。でも肝心の人間はお粗末なままなんだ。そこんところ、本当によろしくね。 *さて、ここから話は少し変わる。いや何だったら、もうここから話し始めればよかったんじゃねえのって思うね。三十代後半、サンダースはケンタッキー州コービンに移り住んだ。ここで彼は、シェル石油のガソリンスタンドを経営することにした。最初の試みは失敗に終わった。まあ、いつものことだ。サンダースの人生、失敗の連続だからな。でも今回は諦めずに、別の場所で再挑戦し、今度は軌道に乗せた。おお、初めてまともに成功したぞ!四十近くにして、やっと!遅すぎるだろ。コービンは国道二十五号線沿いの小さな町で、自動車交通の要所だった。サンダースのガソリンスタンドは、道路に面した好立地にあり、給油に訪れる旅行者で賑わった。やがて彼は、スタンド脇に小さな食堂、「サンダース・カフェ」を開いた。ここからが面白い。というか、やっと本題に入る。カフェは六席ほどのカウンターと、四つのテーブルがあるだけの質素な店だった。メニューはハムステーキ、フライドポテト、コーンブレッド、ビスケットなど、典型的なアメリカ南部の料理。フライドチキンは当初、メニューにはなかった。だが、客からの要望で鶏肉料理を追加すると、これが予想外の人気を呼んだ。サンダースは試行錯誤を重ねた。普通の鍋で揚げると時間がかかり、外は焦げても中は生焼けになる。そんな時、圧力鍋の存在を知った。圧力鍋を使えば、高温で短時間に調理できる。彼は何度も実験を繰り返し、圧力と温度、調理時間の最適なバランスを見つけ出した。さらに、独自のスパイスブレンドを開発した。この執念は認めざるを得ない。仕事は続かない、家庭は崩壊させる、でも料理の研究だけは諦めなかった。まあ、それが彼の才能だったんだろう。馬鹿でも間抜けでも駄目男でも何か一つとびぬけたものがある、普通がいいってこういう人を見ているとよく思うよ、だのに、波風を知らない人間は驚くほど打たれ弱い。塩、黒胡椒、パプリカ、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、セージ、タイム、オレガノ、バジル、そして秘密のスパイス。そういえば配合を完全に把握している人が、世界で三人しかいない、というね。そして今も、その正確な配合は企業秘密だ。金庫に保管されているらしい。アホかと思うが、ブランディングとしては正しい。「秘密のレシピ」ってのは、ロマンがあるからな。僕に見せてくれないか、三秒で燃やしてやるよ。本当に三人しかいないのか、すぐに分かるぜ。脱線して申し訳ないんだけど、奥さんに聞いたんだ、ケンタッキーと唐揚げどっちが食べたい、買って来るよって言ったら、普通に唐揚げって答えからね。そんな話するなよ。空気読めないのかよ。怒られるだろ。まあともかくね、合計十一種類のハーブとスパイスを配合した。この「オリジナルレシピ」は、後にケンタッキーフライドチキンの核心となる。だが、サンダースの人生は、常に波乱に満ちていた。一九二〇年代後半、コービンのガソリンスタンド業界は熾烈な競争状態にあった。サンダースの経営するシェル石油のスタンドは、道路を挟んだ向かい側に、スタンダード石油のスタンドがあり、経営者はマット・スチュワートという男だった。スチュワートは、サンダースの商売を妨害するため、夜中にサンダースのスタンドの看板に、黒いペイントを上書きした。ガキかよ。いや、大人だ。大人がやってるんだ。幼稚な嫌がらせを。アメリカって本当に自由の国だね。自由すぎて頭おかしい。まあ日本でもこんな人いるわけですが、どうしていがみ合うんだろうかっていうけど、人間は動物だからね、まず人間じゃない、まず動物、縄張りがあんの、作法があんの、それが嫌なら圧倒的な力で支配して状況を書き換えなくちゃいけない、そこんところをきちんと認識しなくちゃいけないよ。なかよしこよしは幼稚園だって成立しない。翌朝、サンダースは看板を見て激怒した。彼は看板を塗り直したが、数日後、再び黒く塗られていた。これ何かっていったら、キチガイだ。やめろと言われてもやる、典型的なキチガイだ。「次にやったら、撃つぞ」マジで脳味噌筋肉。マジ、アメリカ銃社会。撃つぞ、だって。話し合いとか、警察に通報とか、そういう選択肢はないのか。いや、ないんだろうな。アメリカだから。サンダースはスチュワートに警告した。スチュワートは鼻で笑った。「やれるもんならやってみろ」僕が同じ立場だったら多分、いきなり撃ってしまうな。やれるものならやってみろと言ったからと僕は答えると思う。多くの人はそうじゃないけど、一部の人はそうじゃない。相手を見てやらないといけないね。で、ある日の午後、スチュワートは再び、ペイント缶を手にサンダースのスタンドに近づいた。サンダースは窓からそれを見て、拳銃を手に外へ飛び出した。スチュワートも腰に拳銃を差していた。二人は道路を挟んで対峙した。風が吹き、看板がきしむ音が聞こえた。西部劇かよ。先に撃ったのはスチュワートだった。銃声が響き、サンダースの肩をかすめた。サンダースも応戦した。銃撃戦が始まり、周囲の人々は悲鳴を上げて逃げた。流れ弾が、シェル側の従業員、ロバート・ギブソンに命中した。ギブソンは胸を押さえて倒れ、数時間後に病院で死亡した。サンダースは殺人容疑で逮捕され、留置所に入れられた。裁判では、スチュワートが先に発砲したこと、サンダースは正当防衛として応戦したことが認められ、最終的に無罪判決が下された。でもこれはたまたまだったかも知れない、緊張状態だと、どちらが先に初めてもおかしくないわけだから。だが、この事件は地元で大きな話題となり、「白髭の穏やかなカーネルおじさん」という、後年のイメージとはかけ離れた、荒々しく危険な男としてのサンダースの一面を示していた。まあ、これに関してはサンダースが一概に悪いわけではない、そもそも、周囲の人間は何をしていたんだろうね。でも誤解のないようにだけど、この二人が争っていた理由は、お金だからね。お金がなければこんなこと起きていない。物語にとっちゃどうでもいいことだけど、僕はそこすげえピックアップするから。 *一九三五年、ケンタッキー州知事ルビー・ラフーンは、サンダースに「ケンタッキー・カーネル」の称号を授与した。これ、軍隊の階級じゃないからな。勘違いしている人がもしかしたらいるかも知れないけど、「カーネル」って聞くと、「大佐」って訳されるけど、サンダースは軍人じゃない。キューバで営倉入りしたぐらいで、階級なんてもらえるわけがない。いや、そんなロマンある軍隊なら、ドリームキャストと僕が翻訳してあげるけどね。争いのない場所はあるの、世界中の至る所にあるよ、それがケンタッキーだったらいいね。これは軍隊の階級ではなく、州の発展に貢献した人物に与えられる名誉称号である。サンダースのカフェが地域の観光資源として、認知されたことが理由だった。称号を受けたサンダースは、イメージ戦略として「カーネル」の人格を演じ始めた。白いスーツ、黒い紐ネクタイ、白髭、黒縁眼鏡、南部の紳士風の装い。この衣装は、彼のトレードマークとなり、後に世界中で認知されるアイコンとなった。まあ、要するにコスプレだ。本物の南部紳士なら、法廷で殴り合ったり、銃撃戦したりしない。あと息子をさらったりしない。でも、見た目は大事だからな。人は見た目で判断する。もうこの話を読んでいない人はケンタッキーを厚顔無恥にいくんだぜ、それいけない、ケンタッキーのエピソードを知ってなお、美味しく美味しくいただいてください。白いスーツ着て、白髭生やせば、「優しいおじいちゃん」に見える。中身がどうであれ。アンタだって面の皮引っぺがえしゃ同じようなもんだろ?一九三九年、サンダース・カフェは火災で全焼した。深夜、厨房のストーブから出火し、あっという間に建物全体が炎に包まれた。この男の人生、何かが軌道に乗りかけると必ず何かが起きる。呪われてるんじゃないか。人生のハードルをどれだけ上げられるんだ、神様いるのか。いや、いないんですけどね、ここだけの話。だって神様、人間ではないから、いるとかとは言わないですよね、それ、何ていうか知っていますか、屁理屈ですよ。サンダースは裸足で飛び出し、燃え盛る店を呆然と見つめた。炎の中で、長年かけて築いてきたものが、灰になっていくのを見た。想像してみてくれ。四十代後半の男が、裸足で、自分の店が燃えるのを見ている光景を。悲惨だ。普通ならここで心が折れる。「もういいや、諦めよう」ってなる。だが、彼は再び立ち上がった。このしつこさだけは認めようじゃないかって気分になるだろう、どんなロクデナシにだっていいことの一つや二つあるさ。ゴキブリ並みの生命力だ。褒めてないけど。だが、彼は再び立ち上がった。保険金と借金で、より大きなレストランを建て直した。新しい「サンダース・カフェ&モーテル」は、百四十二席を擁する本格的なレストランとなり、モーテル客室も併設された。火事で全焼したのに、前より大きい店を建てるって、どういう精神構造してるんだ。普通、慎重になるだろ。「次は小さめに」とか考えるだろ。でもサンダースは違った。頭のねじがとんでるから。「でかくしよう」って思った。大きいものはすごい。狂気だ。でも、この狂気が成功を呼ぶ。フライドチキンは看板メニューとなり、遠方からわざわざ食べに来る客も増えた。一九四〇年、ダンカン・ハインズという、アメリカで有名な食評論家が、サンダース・カフェを訪れた。彼は自著『Adventures in Good Eating』で、サンダースのフライドチキンを絶賛した。「ケンタッキーで最高のフライドチキン」この評価は、サンダースの名声を全国に広めた。ダンカン・ハインズって聞いて、「ああ、ケーキミックスの会社ね」って思った人、正解。ちょっと君、人生に手抜きしてるんじゃないの、こんなの常識だよ。嘘だけどね、日本人にはちょっと難しいよね。でも京大とか東大出ると、奥さんに向かって料理出来て当たり前だろとか言うらしいね。ビーズのウルトラソウルじゃないけど、ウルトラアフォ。あのさ、エリートと人間のそれは関係ないんだよね、団栗の背比べしている前に、派閥とかぬかす前に、まず、てめえの人間力が狭いテリトリーにしか、発揮されないことを考えろよ。全部そうじゃねえか、苦労してねえからそうなんだよ。いや、ネット掲示板でエリートの奥さんが愚痴ってたんだよね、離婚しろ離婚しろ、他人に命令できると考えているのは頭の悪い証拠だ、命令できるのは世界で自分ただ一人だけだ、そんなことも知らねえのか、話し方ひとつで、考え方ひとつでやりようがあることも、処理できない奴の頭がいいわけないだろう。でね、ダンカン・ハインズって元々は人名だ。この人、全米を旅して、美味い店を紹介するガイドブックを、出版していた。今でいうミシュランガイドみたいなもんだ。 *一九五〇年代初頭、サンダースの人生に再び暗雲が立ち込めた。国道二十五号線のルート変更が決定し、彼のレストランは主要道路から外れることになったのだ。新しい高速道路インターステート七五号線が建設され、交通の流れは変わった。国の政策だ。「高速道路作るから、お前の店、道路から外れるわ」っていう、理不尽だ。でも、国家プロジェクトには逆らえない。客足は激減し、売上は急落した。もう墓場のカーニヴァル、厚化粧した廃墟だ。そりゃそうだ。幹線道路沿いにあるから客が来たのに、脇道に追いやられたら誰も来ない。今でいえば、Googleマップから消されるようなもんだ。存在しないも同然。野良犬が骨をくわえていくだけ、さ。一九五二年、サンダースはレストランを売却せざるを得なくなった。借金を返済すると、手元に残ったのは、わずかな貯金と、月額百五ドルの社会保障年金だけ。六十二歳のサンダースは、事実上無一文だった。六十二歳で無一文。現代なら、確実に人生詰んでる。再就職? 無理。年金? 足りない。生活保護? まあ、それしかない。もうなんだったら、犯罪するしかないかもな、前に何処かのアメリカの記事を読んだことがある。仕方ないのさ、それがアメリカっていう国のハリボテであり、限界なんだ。日本だって似たようなものさ、僕が日本を褒めたことなんてただの一度でもあったか?評価するだけだ、褒めるようなことなんか一つもないぜ。だが、彼には一つだけ、価値あるものが残っていた。フライドチキンのレシピである。そう、レシピだ。十一種類のハーブとスパイス。圧力鍋での調理法。これが彼の全財産だった。無形資産ってやつだ。サンダースは、フランチャイズビジネスを思いついた。天才か。いや、追い詰められた人間の発想か。レシピと調理法を他のレストランに教え、売上の一部をロイヤリティとして受け取る仕組み。現代では当たり前のビジネスモデルだけど、当時は革新的だった。というか、他に選択肢がなかったんだろうけどね。彼は白いスーツを着て、圧力鍋とスパイスの入った袋を、古いフォード車に積み込み、全米を回り始めた。最初は惨憺たるものだった。レストラン経営者たちは、見知らぬ老人の提案を鼻で笑った。「うちは独自のメニューで十分だ」「老人の作り話に付き合う暇はない」「帰ってくれ、邪魔だ」百回、二百回、三百回と断られ続けた。想像してみてくれ。六十代の老人が、毎日毎日、「ノー」って言われ続ける日々を。普通、心が折れる。「もう無理だ」ってなる。でもサンダースは諦めなかった。このしつこさ、異常だ。褒めてるのか貶してるのかわからないけど、とにかく異常だ。普通の人間には絶対に無理な鋼のメンタル。あるいは現代日本に一番必要なオリハルコンみたいなメンタル。もう失うものが何もないから、恐怖も絶望も感じないのかも知れないけどね。せいせいするよね、気楽だ。でも自由にはいつだって代償が必要になる。サンダースは車の中で寝泊まりすることもあった。冬の夜、毛布にくるまって凍えながら、ダッシュボードに顔を伏せた。だが、翌朝には再びスーツを着て、次の町へ向かった。一九五二年、ついに転機が訪れた。ユタ州ソルトレイクシティのレストラン、「ドゥ・ドロップ・イン」の経営者ピート・ハーマンが、サンダースの提案に興味を示した。やっと。やっとだよ。何百回目の営業で、やっと一人、話を聞いてくれる人が現れた。サンダースは店の厨房でフライドチキンを実演した。圧力鍋の蓋を開けると、スパイスの香りが厨房中に広がった。ハーマンは一口食べて、目を見開いた。「これは売れる」そうだ、売れるんだよ。サンダースは何百人もの経営者に、同じ実演をしてきた。でも、誰も信じなかった。ハーマンは信じた。それが違いだ。ハーマンは最初のフランチャイズ契約を結んだ。そして、彼が考案した宣伝文句が、「ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)」だった。KFCって名前、サンダースが考えたんじゃないんだぜ。ハーマンが考えたんだ。意外だろ?でも、いい名前だ。覚えやすい。「ケンタッキー」って地名がブランドになってる。この名前は、後にブランドの正式名称となる。加盟店は徐々に増え始めた。一九五五年には十軒、一九六〇年には百軒、一九六三年には六百軒を超えた。雪崩のように増えた。快進撃さ。最初の一軒が一番大変だったんだ。でも、一軒できれば、次は簡単。「あのレストランも導入してるなら」って、他の店も真似する。人間って、そういうもんだ。理解不能な属性の中に圧縮されてしまう、最初の権利が、どれほど豊かなものなのかをあなたも知らないだろう。サンダースは年間二十五万マイル以上を車で走り回り、各店舗の品質管理に奔走した。だが、問題も起きた。一部のフランチャイズ店が、「オリジナルレシピ」を詐称し、勝手にスパイスの配合を変えていたのだ。サンダースは激怒し、訴訟を起こした。そう、訴訟だ。この老人、本当に戦うのが好きだな。若い頃から殴り合い、銃撃戦、そして今度は法廷闘争。法廷で彼は、レシピの重要性と、ブランドの統一性について熱弁を振るった。「私のレシピは、私の人生そのものだ。それを勝手に変える権利は、誰にもない」熱いね。六十代の老人が、法廷で叫ぶ。「俺のレシピに手を出すな」って言う。カッコいいのか、滑稽なのか、よくわからない。でも、本気だった。裁判所はサンダースの主張を認め、違反したフランチャイズ店との契約は解除された。この勝訴により、KFCのブランド価値は守られた。結局、老人の執念が勝ったわけだ。関係ない話してもいい? 僕はたまにぼんやりと物思いにふけるんだけど、昔読んだスピリチュアル系で、自動筆記状態で小説を書いたというそれを思い出すんだ。それは死後の魂なんだ、と。死んでまで何で他人に迷惑をかけようとするんだ?それはもう一度生まれてきてから、書き直しちゃいけないのか?いや、何かって? 老人の執念ってすごいねって。 *一九六四年、サンダースは重大な決断を下した。KFCの事業を、投資家グループに売却したのである。売ったのかよ、せっかく築いた帝国を。まあ、わからなくもない。七十四歳だぜ。年間二十五万マイル走り回るのは、もう限界だったんだろう。売却額は二百万ドル。当時としては巨額だった。今の価値に直すと、約二千万ドル。二十億円以上だ。六十二歳で無一文だった男が、七十四歳で億万長者になった。アメリカン・ドリームだ。本物の。契約には、サンダース自身が、広告塔として活動し続けることが含まれていた。年俸四万ドル、白いスーツ姿で、世界中のKFC店舗を訪問し、ブランドの顔であり続ける義務。サンダースは売却後も精力的に活動した。七十代、八十代になっても、年間二十五万マイルを移動し続けた。飛行機に乗り、テレビCMに出演し、店舗をサプライズ訪問して品質をチェックした。ある日、カリフォルニアのKFC店舗を訪れたサンダースは、提供されたフライドチキンを一口食べて顔をしかめた。「これはゴミだ!」彼は厨房に乗り込み、店長を叱りつけた。「私のレシピを冒涜するな!こんなものを客に出すなら、看板を下ろせ!」この厳しさが、KFCの品質を支えた。まあ、ロクデナシが何言ってやがるんだという向きもありつつ、客商売において、まず第一に客のことを考えていたら関西人だね。しかしまあ、いまはカスハラが溢れていやがりますので、どちらもお気をつけ。創業者が店を回って、「ゴミだ!」って叫んでくれたら、店員も手を抜けない。恐怖政治だ。でも、効果的だ。やっぱり言い方はいくらでもありそうな気はするが、僕の見てきた経営者も大体そんな感じだったね。一九七〇年、KFCは日本に進出した。大阪万博を契機に、日本第一号店が、名古屋にオープンした。店舗前には、白いスーツの「カーネルおじさん」の人形が立ち、日本人の好奇心を引きつけた。日本での成功は目覚しかった。一九七四年、日本KFCは、「クリスマスにチキンを食べよう」というキャンペーンを開始した。これ、天才的なマーケティングだ。ダイヤモンドの広告ぐらいだ、本当に。外国人居住者向けに、「日本では七面鳥が手に入らないから、代わりにフライドチキンでクリスマスを」という提案が始まりだった。このキャンペーンは大成功を収め、やがて日本全国に広がった。クリスマス・イブには、KFC店舗の前に長蛇の列ができるようになった。バーレルに詰められたチキンを抱えて帰る家族の姿が、日本の冬の風物詩となった。この「クリスマスにチキン」という習慣は、日本独自の文化として世界に知られるようになり、欧米のメディアでも「日本の奇妙なクリスマス習慣」として紹介された。実は、スーパーマーケットでも、クリスマスシーズンにフライドチキンを大々的に販売するようになったのは、KFCのマーケティング戦略に便乗する形だった。今では、ケンタッキー以外のチキン商品も、この時期に大量に売れる。なお、欧米で伝統的にクリスマスに食べるのは七面鳥である。「コールドターキー(Cold Turkey)」という英語表現は、「悪い習慣を突然、完全に断ち切ること」を意味する。ジョン・レノンの同名の楽曲が有名だが、この曲の制作背景には奇妙な逸話がある。一説によれば、レノンとオノ・ヨーコがクリスマスの食べ残しの七面鳥を、後日食べて重度の食中毒を起こしたことが、楽曲のテーマだったという。だが、レノンはこの「食中毒」という真実の経緯を話すと、笑われると考え、公式には、「ヘロインの禁断症状を乗り越えた経験」に基づく曲だと説明を変えたとされる。真偽のほどは定かではないが、「マザー」で絶叫するレノンらしい、何かと叫びたがる男らしいエピソードではある。とにかく叫んでいたら、それはレノンだ。いいから、話をケンタッキーに戻せ。 *一九七〇年代後半、サンダースの健康は徐々に衰え始めた。白血病と診断されたが、彼は治療を受けながらも、活動を止めなかった。一九八〇年十二月十六日、サンダースは肺炎を併発し、ケンタッキー州ルイビルの病院で息を引き取った。九十歳だった。葬儀には数千人が参列した。ケンタッキー州議会議事堂に、彼の遺体が安置され、州を挙げての追悼が行われた。棺の上には、白いスーツと黒い紐ネクタイが、飾られていた。サンダースの墓石には、カーネルの姿が彫られ、「ケンタッキー・フライド・チキンの創業者」と刻まれている。何度転んでも立ち上がり、何度失敗しても挑戦し続け、最後には世界的な成功を手にした男の物語。アメリカン・ドリームの体現者。それがカーネル・サンダースだ。サンダース亡き後も、KFCは拡大を続けた。一九八七年、KFCは中国に進出し、欧米ファストフードチェーンとして初めて、北京に店舗を開いた。天安門広場近くの一号店は、連日満員となり、中国人にとって、「特別な日に食べる高級料理」としてのイメージが定着した。ある中国人女性は語った。「私が子供の頃、KFCに行くのは、誕生日か、試験に合格した時だけでした。普段は手が届かない、特別な場所だったんです」今や中国は、アメリカを抜いて、世界最大のKFC市場となっている。店舗数は一万店を超え、地域限定メニューも豊富に展開されている。一九九六年、日本では、「チキンクリームポットパイ」が発売された。サクサクのパイ生地と、具だくさんのクリームシチューを組み合わせた、冬季限定商品。これは瞬く間に人気となり、冬の定番メニューとして定着した。二〇二五年には、発売から三十周年を迎えた。日本KFCはまた、日本で最初にドライブスルーを導入した、ファストフードチェーンでもある。一九八〇年代、自動車社会の進展に伴い、車に乗ったまま商品を受け取れるシステムは、革命的だった。この仕組みは、他のファストフードチェーンにも広がり、日本の外食文化を大きく変えた。さらに、日本KFCは地域限定メニューの開発にも積極的で、「和風チキンカツバーガー」や、「照り焼きツイスター」など、日本人の味覚に合わせた商品を次々と投入した。二〇〇〇年代に入り、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、企業再編を経て、現在は「株式会社クリスピー」という法人名で運営されている。だが、店舗の看板は依然として「KFC」であり、カーネル・サンダースの白い人形は、今も店頭に立ち続けている。
2025年11月22日
-

11
朝は来るからこれは何の終わりと始まり?Bye,Byそれとも継ぎ目が焼け落ちたフィルムの続編か?Lie,Lieイフ・ユー・キャン・ヒア・ミー、並走、言わせるフェイスがない、ぜ、真実は層状に埋もれ、表面だけが滑らかに磨かれていく。鼓膜の裏側に貼り付いた薄青い残響は、仮眠状態における時間経過を問う、在りし日のバベルの塔、それはまた訪れくる時までの変奏、変装、(返送?)ホワット・イヤー・イズ・イット?夜をくすぐって、酩酊するメーデー、この辺境地帯へ向かう、ヴィジョン・ホール(で、)“What is”―――そ/の/瞳/に夏の香りに囚われたまま網戸を見ていたら、もう雪だ、黒い瞳孔がますます疑わし気に縮こまって、これはもう何の修行だ?眼球の虹彩は、光量を調節するためにではなく、現実への不信から収縮している、電気的刺激の波形的翻訳。言葉をプレイするように、ウェイト、光を呼吸すれば生物の気孔、未現像のフィルムのような影を落とす。エクスペリエンスの高密度粒子が、細胞の隙間を通り抜けたのかもね、心はふりまわされっぱなしかもね、(かもねぎ、)グローインアップ、憐れな印象の観光ポスターじゃない、(眼からたまねぎ、)いまはメープルシロップの琥珀を溶かしたような、濃密なフレイバー。(フレイヴァーの青白い静謐、)ドアを開けて廊下を出るまで、擦り切れたロープや滑車や遠くの埃のもやに、霞んで今いる場所さえ分からない、だけ・・。予想し得ぬ新世界への不思議な再生。それは人間のものでも虫のものですらもない、醜悪な一つの動き。愛が呪いではないとしたら、システムはもう狂っている。“Who are”映/る/姿/(それはただの輝き、)上がった幕から見える景色の、フリー・ジャーニーの行方。テーブルも、椅子も、花瓶も、ピントはまだ合わない、電話機も、靴も、帽子も、ルック・バック、インプレッシブ、リメイン、足踏み式のポンプで、後ろ向きに走り出してゆくかも知れない、(でもそれって前向き?)新世界の胎動が、旧世界の亡骸の中で産声を上げる。デフォルトみたいな胸を裂いて、(ナウからシンク・・、)夢を裂いて、掻っ捌い―――て。これは何の終わりと始まり?Bye,Byそれともそれとも継ぎ目が焼け落ちたフィルムの続編か?Lie,Lieマイナス何度だってもう慣れたよ、鉄錆と埃とネオンの残光。永久機関で得た終末装置はゲシュタルト、自分だけが、見えない世界の地図の一片を手にしているという感覚。ムーンにリィーチするほどの、ロング・テレスコープで、月面のクレーターをなぞる。矮小、裂開、魂魄、もう何だろう老廃現象を停止せる機械、(異界? その位階―――)霧の中に見える灯台の光のように、存在はするがその実体は掴めない。縋ろうか、パンドラの憂鬱の函の蓋を開けようか。それを愛せるかどうかの闘い、息は溺れる邂り逅いは、たった一度の果てしない抱擁。“What is”―――そ/の/瞳/に海のような町でみんな道に迷ってる、泥水飲んで踊り明かそうよ、現在の執着に溺れる以外の生き方を欲しがりながら、静寂と寄り添い眠る。ボーン・アット・ファースト。だから―――。だから・・・。道を見失っても、迷うことはできない。迷うことはあっても道を切り離すことができない、同情なんかいらない、一切の生き方から逃避したいだけの、ホワット・イズ・ザ・ディファレンス・エニーウェイ。顕微鏡の載せ台上に固定された標本の、強制的な細胞レベルまでの分解。“Who are”映/る/姿/その爪は細く、鋭く、深く食い込む。海がプランクトンと海月と沈没船の夢を見るように、フィーリング・アラウンドの、ウォークはコンティニュー。
2025年11月22日
-

10
右ストレートで殴られるだけの物語お前、さっきわたしのパンツ見ただろ?見てない見てない。本当のことを言ったら―――穏便に済ませる。それ、言葉のトリックだよね?じゃあ、もう一回見せたげる。じゃあ、って笑顔が怖い。見るの見ないの?すみません、見せパンなんですか?いいから覚悟決めろやコノヤロ。バイオレンスの予感しかしない。見たの? 見なかったの?その・・・・・・チラッと・・・・・・、見えたような・・・・・・見えなかったような・・・・・・・。しましま?しまうま!
2025年11月22日
-

9
春の暴力天上天下唯我独尊、君は顔を見てるのか、眼鏡を見てるのか。最後通牒、そして耳や、鼻や、口の三両編成の電車なんかの、ジャパニーズグラフィティドリームウィスキー(?)喋ってるようで口聞いていない、だから眼を開く以外に、耳をかっぽじる方法がないのだ、以心伝心行動原理。迷信か祭典か、桜の樹の下とかいうマーケット戦略、はじめてみないか(?)不良債権、さいけ、さいけ、サイケデリイク、伝説の英雄顔をしながら、それが男の娘であることを、君はまだ知らない(?)
2025年11月22日
-

8
何か思ってたのと違う彼女は、ペペロンチーノキョウコ。地球が大体大打撃をうけて、九割ぐらいの人が、死んだあとに、ナウシカした。腐海と、名付けるあたりから、すでにそう。DVDで観た。森を汚すと、妖怪が、生まれますなんか用かいああ酔うかい?ダジャレ溶解、ペペロンチーノキョウコの、ちからわざ。そして妖怪たちが、大集合、これから大運動会、ゲゲゲの―――言えない。言わない。言えるもんか。ペペロンチーノキョウコ。本年度の写真。彼女はMVPにかがやきます、紅組を勝たせます、だって負けると、大体泣きます。
2025年11月22日
-

7
コカ・コーラとアスピリン振り返ると癌細胞がいた。分裂し液化し統合される声。まだ無免許運転の進行と変化。解決法を拒絶しながら、広告は五月蠅い。その原形質の精髄的なものを、搾取し、絶滅するためだけに、男と女、光と影が生まれた。遊星上の生活、気楽な堕落、狂ってる。膿んでいる。この命題、この告知、この顫動、一つの叫びが時代を変える。独りよがりの満足で中指を立てて、顔もなく、色もなく、音もなく、言葉もなく、夢もなく。
2025年11月22日
-

6
Iのうたどどんぱどどんぱ。ぱりぱりぱりぱり。どどんぱどどんぱ。ばりばりばりばり。本日も晴天なり。本日も晴天なり。バズーカ砲、グレネードランチャー、対戦車ミサイル。今日もお日柄がよく、戦争日和でなにより。どどんぱどどんぱ。ぐきがきゃぼぎゃべらっ。どどんぱどどんぱ。ぐさっばさっどさっだらっ。本日もめでたく死にました、本日もめでたく名誉の生きざま。ノーヒットノーラン、完全試合、北朝鮮からミサイル。受験戦争、愛と友情、どんべえのコスパ。
2025年11月22日
-

5
天才あのね、世界の優劣は、遺伝子で、子供の内以前から決まるの。だから、人生を無駄遣い、暇つぶし、パチンコ、ダメ人間、オサムダザイも、一定数必要なんだ。お金を貯められず、遣うしか能がない、計画性のない人々はいるんだ。みんな、それは嫌だって思ったでしょ、それは健全な、椅子取りゲームの勝者なんだ。けど、一歩引いて考えるとね、蟻の法則なんだよね、蟻地獄なんだ、僕はそれをずっと考えてるんだよね、だって交通事故や、心を病むでも、隕石でも、地震でも起これば失敗だ。それは通常起こりえないことになっている。人は悲しむ人、やる気をなくす人、一定数いる。全体にとってどれだけ打撃の少ないかが、僕はキーポイントなんだと思うんだよね、どんな生き方も。わからないかな、いや、わかると思うよ、無人島を遊園地にしたいって、思うようなことだから。
2025年11月22日
-

4
君も。僕も。上っ面王国の船出。死んだ魚の眼しながら、眺めていた町。遠近法って罪ね。でも君は愛した?糞みたいなことよ、ハエがたかって、ウジがわいてった。何もない、きれいな町。白紙にもどりゃ、せいせいするって?昨日考えてた、二次元なら人同士は、点滅するんだろうなって。次元を上げていけば、もっと別の醜い、グロテスクなものが見えるって?
2025年11月22日
-

3
遭難ねえ、あたしなりに冬は何故寒いのか考えてみたのよ。それは、冷蔵庫なんだ。急冷中なの。そうなのよ。そうなの。最終的にかき氷ぐるぐるして、やっぱり冬に食べる地球味の、時々人間の味がするのが、最高だわやって神様なんだよね、超サイコパス。寒いわ。
2025年11月21日
-

2
拒絶反応気障な台詞の相手はすぐババアになる、顔面偏差値は皺と醜さの標本になる。可愛いって何?馬子にも衣裳ってこと?言うに事欠いてお姫様みたいって、何よ。にこにこ笑った、女の子は、可愛いわよ。ちょっと不細工でも、性格あれでも、ね。世界中が嘘のオンパレード、庶民の味方のふりした、シャトレーゼ。信じたら負けだわ、デスパレード。でもそいつはきっと、わたしの猫みたいに怒った顔が好きな、とびっきり。
2025年11月21日
-

1
買物欲しいものなんてあるの?ないよ。夢の中ではね、すごく楽しいの。買いたいものがあるから?それもあると思う。財布と相談しなくていいしな。乾いた町なの。そうか。カーネル・サンダースもいる。ベーブ・ルースもいるかもな。
2025年11月21日
-

祝福
いまなら自由や愛や夢を謳える 僕が―――公式主義的な回路を越えたから・・。 無限の深淵を見る。 黒い瞳孔が、ブラックホールのように僕を吸い込んでいく。 さまざまな人称を交替させながら、 『花』になって、『空』になって、 震えてる・・。 すべてがバラバラに、脈絡なく、 僕の中に散乱している。 時系列もぐちゃぐちゃだ。 昨日のことが遠い昔のように感じられ、 十年前のことが昨日のことのように鮮明なまま・・。 眼を瞑って、君の手を握ったら、 わからないよ、 わからなくなるよ、還元不可能な異質性、 走っても走っても地平線は―――遠くなる。 、、、、 僕の手は無限なの、有限なの、 誰も教えてくれない、壊れそうな僕の才能の在処、 忠実であれ、資質に従え、 声が囁く、僕はただ、知りたい、考えたい、 吸い込まれそうな君の瞳―――。 心の奥底にある、言葉にならない想いを。 君が夜中に一人で泣いている時の、君の涙の意味を。 君が笑っている時、 その笑顔の下に隠された孤独―――を。 蜘蛛の巣が顔にかかるけど、 ふと木々の隙間から光が射し込んで、 そこに道ができる。 整理されない記憶の中の乱雑な塊・・。 終わらない夢・・・。 終わらない言葉―――と・・。 夢を見る草原、迷路へと続く森、 人と心が分かり合えた気がしない都会・・。 透明人間のように歩く。 誰にも気づかれない。 誰にも触れられない。 硝子の壁に囲まれているような孤独だ。 、、、 、、 、、、、 交差点、雑踏、満員電車・・・。 はなれてゆく気がして、 近づいてゆく、 壊れてゆくようで、 繋がってゆく。 そうさ、僕は床に座り込んで、両手で顔を覆った。 涙が出そうになった。笑いが込み上げてきた。 どちらでもない、どちらでもなかったよ、 名前のつかない感情―――が・・、 、、、、、 胸の奥から。 通俗的なものが胸を刺した瞬間から、 表情はショー・ウィンドーさ、朝露は生まれ変わって、 二元論は始まって、表と裏、光と影は生まれて、 花が生まれて、恋をして、 ―――向こう側の死を感じて。 、、、、、、、、、、、 いまなら歌える気がする、 人知れず生まれて、立ち上がって、考えて、学んで、 ―――こぼされてゆきそうな、 世界が明るく輝いているのに、 心の中で―――思考を限りなく隠蔽するものを感じて、 胸が苦しくなって、叫びたかったこと・・。 影――それは、僕が認めたくない自分自身。 僕の中の暗部。 嫉妬、憎悪、欲望、恐怖、 すべての負の感情。 夜、ベッドの中で、 その影が僕に語りかけてくる。 「お前は偽善者だ」 「お前は臆病者だ」 ずっと、ずっと、 名前のつけられない影と対峙する、 ・・・識別不可能な極限状態まで精神を高めたら、 声は意味や情報や伝達を超える、 僕は一人だ、何者にも従属しない、 だから僕は孤独だ、僕は孤独の意味を知ってるから孤独だ、 思考を限りなく隠蔽するものが潜んでいて、 光と影が名前を与え合―――う・・。 遠くに見える街の灯り。 車のヘッドライト。ビルの窓。コンビニのネオン。 僕が見ている世界は、本当の世界なんかじゃない。 僕の感情というフィルターを通した、 歪んだ世界―――なんだ・・。 自己欺瞞、不能力の正当化、性的抑圧と消耗品、 ―――すてられて、うばわれて、 感情の中に―――。 都合よく映し出された・・窓、 疑問回路、固定化される立場、引き出されてゆく言葉、 暴かれてゆく幸福と階級的絶望と文明の重層的な決定、 世界の中の奇跡、 宇宙の中の神秘、 ヴェランダの向こう眺める風に吹かれた物語・・。 君は生 き て い る か ? 君は愛 し て い る か ? 出来事は新しい次元へとすり替わって、 細分化だろ―――でも抽象的な風に巻かれた、 あの日、あの瞬間、あの時の僕だけが知っている、 語る言葉の中の切ない気持ち・・。 風が物語を捲り、 ページの端が軽く震えてい―――た・・。 、、、、、、、 、、、、、、、、 存在そのものの、抵抗と肯定の響き。 母の胎内で、細胞分裂を繰り返し、 形を作っていった僕。 生まれた時、産声を上げた僕。 歩くことを覚え、言葉を覚えた僕。 左に傾きすぎれば鬱になり、 右に傾きすぎれば躁になる。 真ん中を歩き続けることの、難し―――さ・・。 作って、息をして、―――波・・。 打ち寄せて、満ちて、また一歩踏み出す、勇気・・。 生きていても、死んでいても、 正しくても、間違っていても、 ―――声。
2025年11月20日
-

商品解説詩010「都市伝説を都市伝説する」
知らなきゃよかった!本当に怖い都市伝説 (鉄人文庫) [ 鉄人社編集部 ]ヤバすぎる「都市伝説」大全 世界は「陰謀」に満ちている! 禁断スペシャル [ 噂の真相を究明する会 ]都市伝説とは、都市の皮膚の下に潜む、名もなき物語の集合体だ。それは、アスファルトの毛穴から滲み出る汗であり、コンクリートの壁の亀裂から漏れ出す吐息だ。この街に生きる無数の徘徊する、人間の不安と願望が、天体でも切り開いたように結晶化したものだ。夜。街の灯りが消え、人々が眠りについた後。だが、都市は完全には眠らない。幾百万人に絵の具を注ぎ込むまでは終われない―――さ。二十四時間営業のコンビニ。深夜バス。夜勤の看護師。警備員。そして、眠れない人々。言い解き難い暗愁。哲学のように何となく興奮して来る感覚。いつのまにか儚い出来心の仕業のように胸の奥から溢れる。その隙間に―――その物語は生まれる。誰かが、スマートフォンを手に取る。掲示板を開く。「今日、変なものを見た」と書き込む。誰かが、友人にメッセージを送る。「ねえ、聞いて。不思議なことがあったんだ」と。誰かが、深夜のラジオに電話をかける。「あの、都市伝説って、本当にあると思いますか?」と。こうして、今夜も、どこかで新しい都市伝説が生まれる。その言葉が発せられる瞬間、物語は現実の表皮を破り、生温かな実体として這い出すのだ。たとえば子供の頃の父の実家を訪れた時に、なまぬるい畳と猫の臭いと潮の臭いが溢れていたように、だ。火照るような痛みを伴う膿み、たとえばそれは中指の爪を剥がした、麻酔の注射とメスのようにだ。 *終電を逃した会社員が、駅前の居酒屋でビールジョッキを傾けながら、隣に座った見知らぬ男に語りかける。歯の隙間から唾を吐き散らす。飛行機に塗料の重さは含まれているのかという疑問を持つみたいにね。「なあ、聞いたことある? 三丁目の廃ビル、あそこでさ・・・・・・」その声は、酔いに濡れて少し湿っている。喫煙の煙が螺旋を描いて天井へ昇りながら、男の眼は、語りながら何処か遠くを見ている。まるで、自分が語っている話の中に、今も立っているかのように。その"虚構"の中には、現代人の感情、社会の構造、文化的な価値観が凝縮されている。絶えず生成される夢と悪夢の断片として受け取るみたいにね。口裂け女は、実在しない。だが、美しくなければならないというプレッシャーは、実在する。トイレの花子さんは、実在しない。だが、学校という閉鎖空間への恐怖は、実在する。病院の十三階は、存在しない。だが、医療や国家への不信は、存在する。都市伝説とは、"事実としての真実"ではなく、"感情としての真実"なのだ。もしかしたら利潤をとり、狡猾に、したたかに、こういう言い方をするかも知れない。「友達の友達が体験したらしいよ」その一言で、物語は現実の縁に爪を立てる。友達の友達。その距離感が絶妙だ。遠すぎず、近すぎず。確認しようと思えば出来そうで、でも誰もしない。その曖昧な距離こそが、都市伝説という生き物の生存領域なのだ。語り手はいつも傍観者でありながら、何処かでその話の一部を信じている。過剰な生物共の生殖さながら、蠅の死骸と共に溢れ出した蛆虫の如く、悪意に満ちた大寂寥が、支配をさらに拡大しようとして解き放たれる。高度経済成長の歪み、バブル崩壊後の不安、テクノロジーの依存と恐怖、都市伝説は強張った舌の奥で集団的無意識の気圏へと繋がっている。複製させるのさ。いいかい。培養するのさ。いいかい。眼や脳を―――侵蝕するのさ。 *彼の声には、わずかな震えがある。それは演技ではない。語りながら、彼自身も恐怖を再体験しているのだ。下品な漂白や染色と似ていないかい?そして聞き手は、信じたくないと思いながらも、心の何処かで「本当だったら」と想像してしまう。その瞬間、彼の背筋を冷たいものが這い上がる。それは潜在的でも顕在的でもある倒錯―――さ。聞き手の脳は、自動的にその空白を埋めようとする。その過程そのものが、快楽なのだ。都市伝説は、その"想像の余白"を巧みに設計している。具体的すぎず、抽象的すぎず。信じられそうで、でも確かめられない。そのバランスが、人々を引きつける。また、都市伝説は"語ること"そのものが快楽である。ある研究によれば、人間は秘密の情報を共有することで、脳内にドーパミンが分泌されるという。それは、セックスや美味しい食事と同じ種類の快楽なのだ。誰かに話すことで、自分が"特別な情報"を知っているという優越感を得られる。「ねえ、これ知ってる?」と切り出した瞬間、語り手は会話の主導権を握る。聞き手の注意は、語り手に集中する。その瞬間、語り手は"物語の支配者"なのだ。そして、聞き手とのあいだに一種の"共犯関係"が生まれる。都市伝説とは、そうした"信じることの欲望"と、"疑うことの快楽"のあわいに生まれる、現代の神話だ。それは、神社の境内に祀られた神ではなく、雑居ビルの非常階段や、深夜のコンビニの駐車場や、誰も使わなくなった公衆電話ボックスに棲む、名もなき神々の行脚の物語なのだ。都市伝説の語りは、いつも曖昧で、しかし異様に具体的だ。これは矛盾しているようで、実は巧妙な設計である。それは深夜バスの最終便で聞こえる、隣席の老婆の呟きのように断片的だ。他人とは違った見解。異議。たとえば多くの人の意見、三人の意見、できるだけ多くの意見、全部違うように錯覚するかも知れない、何を言っているんだ、全部一緒さ。「昨日の夜、○○駅の近くの公園で―――」「先週の木曜日、○○線の終点の一つ手前の踏切で―――」「知人の葬儀社が引き取った遺体が―――」「廃墟となった公民館の地下倉庫で―――」場所名は伏せられるか、あるいは、うちの地元のとある場所と置き換えられる。しかしその要素や痕跡は残る。たとえば公園なら、錆びたブランコがあり、砂場には猫の足跡があり、外灯は一つだけ点滅している。そういう具体的なディテールが、語りに"リアリティの質感"を与える。空想虚言者と都市伝説のプロセスにそれほどの違いはない。それは、集団的な不安、抑圧された感情、語られなかった歴史の亡霊というありもしないものを扇動する。蜃気楼のように一歩一歩身を退けていくような手口。「知り合いの看護師が勤めてる病院で―――」もちろん病院名は明かされない。だが、語り手は付け加える。だってそれは子供の頃に聞いた、お姫様が眠る閉ざされた塔の現代版だから。これはグリム童話だから。「あそこ、夜勤の時に、地下の霊安室を通らなきゃいけないらしくてさ―――」地下。霊安室。夜勤。これらの言葉が、聞き手の脳内に白い廊下と消毒液の匂いを再生する。毎日安逸な生を貪って一生夢のように過ごす人にとって、それは退屈を紛らわせるためのスパイスなのかも知れない。心理学的には、都市伝説への信仰は、いくつかの認知バイアスによって強化される。確証バイアス。人は、自分がすでに信じていることを裏付ける情報を優先的に受け入れる。やっぱりそうだったんだと思うことで、安心する。パターン認識の過剰。人間の脳は、ランダムな情報の中にもパターンを見出そうとする。雲の形に顔を見出すように、無関係な出来事のあいだに因果関係を見出す。あの話を聞いた翌日、奇妙なことが起こった。これは偶然じゃない。こうして、都市伝説は"検証"される。権威への依存。専門家が言っていた。テレビで見た。有名人が体験した。権威ある情報源が語ると、話の信憑性は跳ね上がる。たとえその権威が、実は存在しないものであっても。集団同調。周りの人が信じていると、自分も信じやすくなる。みんなが話題にしているから、本当なのかもしれない。集団の圧力が、個人の疑念を押しつぶす。こうした認知のメカニズムが、都市伝説を"真実らしく"見せる。それは、嘘というよりも、集団的に構築された現実なのだ。「ある小学校の旧校舎で―――」小学校は廃校になったのか、それとも建て替えられたのか。語り手は曖昧に笑う。本当は何も知らない。けれども知ったように好き勝手なことを宣う。まるで真夜中の駅のホームを滑る終電の音のように、静かに、しかし確実に伝播していく。「もう取り壊されたって話もあるけど、まだあるって言う人もいるんだよね―――」その曖昧さこそが、物語に"今もそこにあるかもしれない"という可能性を残す。舞台は、誰もが知っているが、誰も"特定できない"場所。それは、この都市の何処かであり、どの都市でもある。聞き手は無意識に思う。「もしかして、私が知ってるあの場所かも―――」と。その瞬間、都市伝説は、聞き手の記憶の中に侵入する。そこに登場するのは、名前のない女、顔のない男、あるいは人間の顔を持った犬などだ。紅だか白だかの要領を得ぬ花が安閑と咲く。それが語りの妙な暗合となる。傍観者という安全地帯にいながら、薄い硝子一枚隔てた向こう側の世界として、話の一部を信じている。引きずり出されたいんだろう、臓器を。本当は、そう思っているんだ。心の何処かでは。そして聞き手は、スマホの画面をタップする指を止め、信じたくないと思いながらも、首筋に冷たい雫が落ちたような戦慄と共に、「もし、この物語の影が、今、自分の背後にも迫っていたら」と想像してしまう。引きずり込んで欲しいんだ、地獄へと続く落とし穴ではない、螺旋階段のような形式に沿いながら。お誂え向きの、不潔な指で傷口を撫でまわされる快感を覚えたい。それは本能の危険回避の一種なのかも知れない―――よ。 *名前のない女は、いつも同じ服を着ている。白いワンピース、あるいは赤いコート。その服は、時代によって変わるが、必ず"印象的な色"である。彼女の髪は長く、顔を覆っている。あるいは、顔があるのに、何故か誰もどんな顔だったかを思い出せない。ものすごい不細工だった、ものすごい美人だったではいけない、そういう嘘を堂々とするのは漫画の仕事だ。「#検索してはいけない言葉」「#深夜にアクセスすると呪われるサイト」これらは、情報過多の時代における"情報の闇"を象徴している。検索してはいけない言葉。ある特定の言葉を検索エンジンに入力すると、グロテスクな画像や、呪いのサイトにたどり着く。「#ググるな危険」そう警告されることで、逆に人々は検索したくなる。そして、検索した者は、トラウマを抱える。あるいは、呪われる。この話は、インターネットの"検索可能性"がもたらす不安を表している。ネット上には、あらゆる情報がある。善意の情報も、悪意の情報も。そして、一度見てしまったら、その画像は脳裏に焼き付いて離れない。削除することはできない。それは、デジタル時代の"見てはいけないもの"なのだ。都市の無数のパイプやケーブルが絡み合う裏側にある、もう一つの現実から、水道管の亀裂のように、ふとした拍子にこちら側へと冷たく滲み出してくるもの。曖昧さが刺激を強めてしまうんだろう、弱さっていうのが濡れた紙に絵を描かせるんだ。呪いのチェーンメールというものがある。「このメールを十人に転送しないと、あなたは不幸になる」こうしたチェーンメールは、一九九〇年代後半から二〇〇〇年代にかけて流行した。今では、LINEやSNSのDMという形で生き続けている。「このメッセージを読んだあなたは、二十四時間以内に三人に送らないと、呪われます。過去にこのメッセージを無視した人は、交通事故に遭いました」そう書かれたメッセージを受け取った中学生は、恐怖に駆られて友達に転送する。友達もまた、別の友達に転送する。こうして、恐怖は拡散する。 *顔のない男は、スーツを着ている。黒いスーツ。ネクタイはきちんと締められている。靴は磨かれている。だが、顔がない。顔があるべき場所に、のっぺらぼうの平面があるか、あるいは暗闇があるか、もしくは見た者の記憶から、顔の部分だけが抜け落ちている。灰汁桶を掻き混ぜたような思念。壁土を溶かし込んだような情念の推移。人間の顔を持った犬。これは、ある深夜番組の心霊写真特集で話題になった。山道を走る車のヘッドライトに照らされた犬が、振り返った瞬間、人間の顔をしていた。その顔は笑っていたという。あるいは泣いていたという。語り手によって表情は変わる。だが、共通しているのは、その顔が"誰かに似ている"という感覚。見た者は言う。「何か、知ってる顔なんだよ。でも誰だか思い出せない」と。彼等は、都市の裏側にある"もう一つの現実"から、ふとした拍子にこちら側へと滲み出してくる。まるで、この世界の縫い目がほつれた瞬間に、向こう側から手が伸びてくる。都市伝説は四方八方からの闇鍋のつつき喰いなんだ。語りの形式は、まるで折り紙のように折りたたまれている。最初のバージョンは、シンプルだ。「深夜にトンネルを通ると、後部座席に女が座っている」ただそれだけ。みんな、嘘を平気でつくということと、最初から途轍もないスケールのものを用意できると勘違いしている。だが、この話が語られるたびに、新しい折り目が加わる。物語というのは細胞を分裂しながら増殖していくのだ。追加される。「その女は、白いワンピースを着ている」「女は、濡れている。髪も服も、びしょびしょに」「女は何も言わない。ただ、バックミラー越しにこちらを見ている」「ある人は、その女に話しかけたらしい。『どこまで行きますか?』って。女は答えた。『海まで』と」「でも、そのトンネルの先には、海はない。あるのは、三十年前に崩落した旧道路の跡だけ」一見単純な話が、語られるたびに角度を変え、折り目を増やし、やがて複雑な立体物となって広がっていく。そして、ある時点で、誰も"オリジナルのバージョン"を覚えていない。ここはとても重要だ。僕はそれをTwitter(現x)のツイート合戦とか、昔にあったまとめサイトのように思えて来る。都市伝説は、もはや誰のものでもない。それは、集団の記憶の中で自律的に成長する生命体。手垢が消えてゆくごとに、少しずつ異様な響きを持ち始める。気が付けば、本当にそんなことがあったのかという当たり前の意見が、出来なくなってしまうほどにディティールを持っている。何故我々は、明らかに荒唐無稽な話に心拍数を上げるのか?その理由は、扁桃体の原始的な反動にある。不確実性は、確定した事実よりも、三〇パーセント長く記憶に留まるという研究がある。都市伝説は、この認知の隙間に巧妙に寄生する。謎のカウントダウンが始まるサイトを思い出す―――よ。語り手は、物語を伝える際、必ずと言っていいほど、「私も最初は信じなかった」と前置きする。じゃあそのままでいろ、と僕は思う。なになに、信用性を担保する修辞術である。そして聞き手は、眉をひそめながらも、無意識に過去の記憶を検索する。あの夜、確かに見知らぬ駅のホームで、誰かがずっと私を見ていた。うるせえ、黙れ、面白くねえんだよ、と言っても無駄だ。その話の曖昧さを消したければ、また別の曖昧な話を用意するしかない。新しいディテールが加わり、古いディテールが削られる。そして、やがて、誰もオリジナルを知らない物語が生まれる。それは、集団的な創作活動だ。作者不明の、終わりのない小説。誰もが書き手であり、誰もが読み手である。バタフライエフェクトなんていう言葉を知らなくても、たった一つの想像が世界を抜け殻にする。速度なんだ。その拡散の速度は、かつては口伝えだったが、今やSNSのタイムラインを通じて、数分で世界を一周する。一九七九年、口裂け女の噂は、地方都市の小学校から始まり、数週間かけて全国へ広がった。子どもたちは、下校時にポマードという呪文を唱えれば逃げられると信じた。その呪文は、学校から学校へ、友達から友達へと、手紙や電話を通じて伝播した。でも現代は動画として投稿される。「深夜2時44分に○○駅のホームで撮影された映像―――」映像には、誰もいないはずのホームに、ぼんやりとした人影が映っている。その動画は、投稿から数時間で数万回再生される。コメント欄には、「これ、私も見た」「同じ駅で不思議な体験をした」という書き込みが殺到する。サクラ、すなわち仕込みを疑う人もいるだろう。いや、不思議なことなんてありすぎるほどある。幻聴や幻視なんて僕の感覚でいえば、有り触れている。精神疾患を疑うよりも、ただ、大多数の人はそういう不思議を成立させたいのだ。翌日には、まとめサイトに記事が上がり、YouTuberが検証動画を撮りに行き、その動画がさらに拡散される。YouTubeやTwitchでのライブ配信。配信者が、心霊スポットを探索する。視聴者は、リアルタイムでコメントを送る。「後ろ! 後ろに何かいる!」「音が聞こえた!」視聴者と配信者が、共同で恐怖を体験する。その瞬間、都市伝説は生きている。あるいは、Twitterでのリアルタイム実況。「今、○○駅にいる。例のトンネルに入ります」とツイートする。数分後、「トンネルの中、異様に寒い」さらに数分後、「何か見えた」そして、ツイートが途絶える。フォロワーたちは、固唾を飲んで見守る。数時間後、ツイートが再開される。「無事です。でも、何かがおかしかった」と。こうして、都市伝説は"体験のストリーミング"となる。それは、もはや物語ではなく、出来事なのだ。人間の気配を消しながらね、何と接続したんだといえば、君はもう何かを相続したのさ。分離しているわけじゃない、ありとあらゆる組み合わせを作って、安易な解決法を拒絶しているのさ。「#拡散希望」「#信じるか信じないかはあなた次第」その言葉が、物語に"現代性"という衣を纏わせる。かつて都市伝説は、これ、誰にも言わないでね、という秘密の共有だった。濡れたティッシュが風に舞うような頼りなさでありながら、不可思議な粘性を持ち、必ずどこかに定着する。だが今、それはみんなに知らせなきゃという情報の拡散である。歪んだ家の模型、四肢のない人形、意味不明なマンダラ。秘密は、もはや秘密ではない。影が三つ重なった女、呼吸の音だけが聞こえる男、または人間の言葉を話す鴉。彼等は、現実という布地の織り目が乱れた瞬間、向こう側から滲み出てくるズレた存在。そしてそれは、バズるコンテンツであり、いいね!の数であり、インプレッションの統計なのだ。
2025年11月20日
-
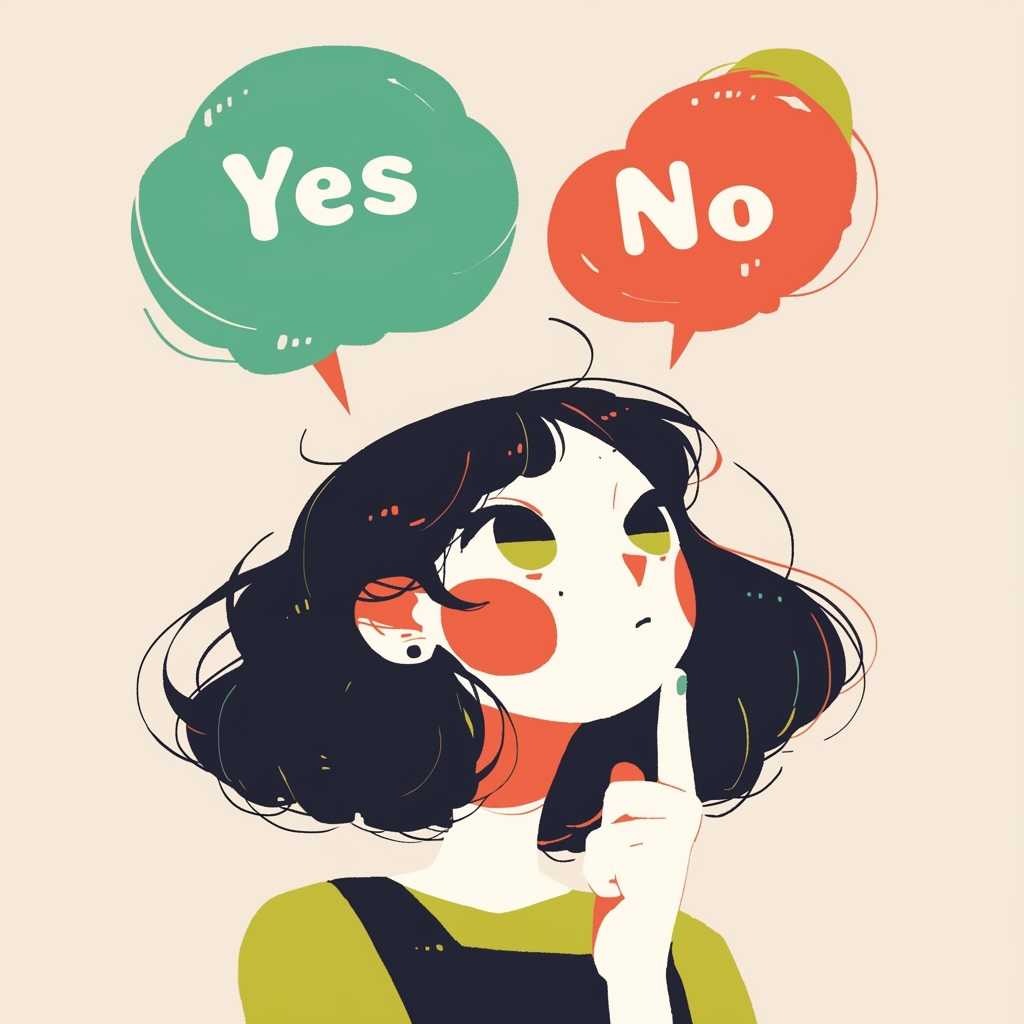
イラスト詩「しおりタイム」
夕暮れはまだ若くて、街灯はうっすらと躊躇している。駅前商店街の路地裏。斜陽が建物の隙間から射し込み、アスファルトに長く伸びた影が複雑な幾何学模様を描いている、午後五時を少し過ぎた時間、屋根の角度に試されている―――気がする・・。正確には、午後五時三十八分。街灯がまだ点灯しきらぬ、薄暮の境界線。駅へと向かう小径の端に、古びたコンクリートベンチが一脚、日常の骨格のようにぽつんと据えられている。湿ったアスファルトの匂いに、コンビニの揚げ物と線路の油の匂いが混じり、遠くから救急車のサイレンが一つ、二つと鼻先をかすめていく。俺はふう、と溜息をついてから振り返った。 、、、「しおり」閉店した古本屋の錆びついたシャッターにもたれかかるように、立っていた彼女の姿は、まるで油絵の静物画のようだった。ひどい尾行だった。探偵事務所だったら一日ですぐクビになる。それでも、しおりは眼をぱっと丸くした。神経細胞が発火したように、唐突に、しかし必然的に、彼女の耳に届いた。頬の内側に眠る赤が、少しの風とともに揺れる。彼女の髪は雨の名残のように少し乱れていて、毛先にパン屑のような光が散っている。小さなショルダーバッグの金具が、夕方の光を受けて微かに鳴った。「・・・・・・あれ? トオル君。偶然ですね! ドウシヨー」一瞬こいつ後頭部はたいたろか、と思いつつ、首を振った。おどけたしおりは可愛かった。文句なしに可愛い。制服の襟を指先で直しながら、少しだけ首を傾げた。その仕草は、まるで古いフランス映画のワンシーンのようで、彼女の瞳は、夕暮れの空を映す水面のように、きらきらと揺れていた。英語の『cute』では不十分なのだ。『kawaii』は既に国際語彙となっている。この概念には、保護欲を喚起する幼児的特徴、無害性、親しみやすさ、そして微かなエロティシズムが複雑に絡み合っている。、、、、ロリコソ、とも言う(?)四方田犬彦の『「かわいい」論』ローラン・バルトの『表徴の帝国』における日本文化論を参照すれば、この感情の文化的固有性が理解できる。瞳をキラキラとさせた女の子は可愛いのだ。少女漫画の女の子にナスカの地上絵が拡がっていたり、いやいや天の川銀河が拡がっていたのはまさにそういう理由なのだ。そうでなくとも、あ、ここテストに出るからね(?)瞳孔の散大は、興奮と関心を示す無意識の反応であり、それは相手に好意的なフィードバックを与える。何処を出すとかは言わないけど、ここ線を引いていてね(?)信用できないな、ここ赤ペン入れといて(?)「うん、偶然だ。すごい偶然だと思う。運命を感じるな!二人の間には見えない糸が張られているんだな」「引き寄せの法則(?)」「すごい、宇宙真理にまで辿り着いてしまうカモシカ(?)」「かもしか?」しおりの声は高く、弾いた硝子玉のように澄んでいた。彼女の笑顔は複数の層を持っていて、稚気と演技と本当の驚きが透け合っている。可愛いという判定は、ここでは単純な感情ではなく、視線の組成である。俺は反射的に肩に手を置いた。「――自分でもわかっているな、かつ丼食べるか(?)」何しろ彼女は、約五〇〇メートルの距離を、常に二〇メートルから三〇メートルの距離を保ちながら、追跡してきた。何でそんなのが分かるかって、簡単だ、同い年ぐらいの高校生が、うわー可愛い子いると言ったので、何気なく振り返ったら普通にいたのだ(?)おお、幻見たか、シャンゼリゼ通り(?)だから五〇〇メートルというのは、俺が引きずり回した距離のことで、実際はもっと長い。五〇〇メートルといえば、徒歩で六~七分。だが商店街の上、路地裏行ったりくねくねしたので、ゆうに十分以上も歩いたことになる。これに関しては悪戯っ気が起きたということもあるが、話し掛けてくるのを待っていた猶予時間ともいえる。刑事ドラマにおける自白の誘導という文化的コード。昭和の取調室。木製の机。湯気の立つかつ丼。食べたら、楽になるぞ、という刑事の声も聞こえたらなお素晴らしい。そして、自白の強要の完成である(?)、、、、、、、、むしろ違法である。インサイダー取引的な卑劣な手法。主に新聞記者! おふくろさんが夜なべして、セーター編んでくれた語などともいう(?)太陽にほえろ語、はぐれ刑事純情派語ともいう(?)「その・・・・・・」その瞬間、すっと暗くなるのも、しおりにとっては可愛い属性の一つらしい。顔面筋肉の変化。大頬骨筋が弛緩し、口角が下がる。彼女は眼を細め、しばらくしてからぽつりと言葉を重ねた。「すみません。声をかけるのもあれだなと思って、自然と、足が――」「ストーカーだ!」俺が即座に言うと、しおりは本気でびくっとする。「え、私、ストーカーなんですか?」「違う、俺がだ!」彼女の眉が一瞬跳ね上がり、子どものような無垢さが露わになる。やがて二人は同じタイミングで顔を引きつらせ、それから笑いが弾ける。その笑いは、駅前の鳩たちを一斉に飛び立たせ、近くの自販機のLEDが、なぜか一瞬だけ点滅した。笑いの余韻がまだ立ち上るなか、俺はやさしく声をかけた。「・・・早く帰れよ。危ない奴に襲われるぞ。女の子一人歩きは、夕方から既に危ないんだ!」犯罪統計学的には、女性に対する性犯罪は、実際に十七時以降増加傾向にあり、警察庁のデータでは黄昏時から夜間にかけて発生率が約三倍になる。しかし、フェミニスト理論の観点からは、このような保護の言説自体が、女性の自由な移動を制限し、公共空間からの排除を正当化する権力装置として、機能しているという批判がある。女達の歌うゴスペル&ソウル(?)なので、こういう発言自体が優しさだけではなく、ロリコソであるという向きとして成立する(?)世界の宝を守らなくてはいけない(?)、、、、、、、、、あなたは守りません、、、、、、、、、、、、、でもあなた以外は守ります(?)「そうですか?」「そうですかってお前の両親は他人事なのか、あまり考えてない人なのか、ちょっと思いやりとか愛情に欠けてるのか?」「ど、どうしてですか?」「安全第一、子供の送り迎えをする親もいるのだ。過保護かも知れない、躾が厳しいのかも知れない、でも世の中、敵だらけ、気が付けば魔の手が!テレビにはワイドショーがロックンロールしている、止めろ、ヘビメタだ、チョーキングチョーキング(?)」「そこまで世の中乱れていませんよ」「言ったな、俺もその一人だ!」自己言及的パラドックス。クレタ人の嘘つきパラドックスに似た構造を持つ。危険人物だと警告する人物は、その警告自体によって信頼性を増す。しかし同時に、本当に危険であれば警告しないはずだ、という逆説。「トオル君はそんなことしません」信用の言葉が、あまりにも素直に降りてくる。マサチューセッツの郊外で、アナコンダに逃げられた科学者のような―――顔。その言葉に、僕の中の何かが、まるで風船の空気が抜けるように、しゅるしゅると、何処かへ飛んでいってしまった。からす~(?)もしかしたらこいつは本当に大丈夫かも知れないな、たまや~(?)無根拠ながら、神様に愛されているのかも知れないなとも思えた。人間に違いなんてないというべきだろうが、残念ながら、世の中には、天の恵みを与えられているように見受けられる人がいるのだ。しかし、からかうのが好きな気分だったから、俺は一段と馬鹿げた芝居を続けた。「トオル君じゃない、俺はユキオだ!」「え、二重人格なんですか?」「違う、いまや俺はもうタダシだ!」「三重人格!」言葉がどんどん変名で踊ると、しおりは眼の端で笑いを堪える。俺は馬鹿馬鹿しいことを言いながら、同時に自分の声の響きに小さな不安が混じっているのを感じた。仮面を引っ張り出すことで、何かを試している。俺は仮面の下で自分を確かめようとしている。アンパンマソじゃないぞ、アパマンショップだ!(?)「ほらいまやもうマスジだ、リュウノスケだ、テツロウだ・・」と、続ける内、しおりがむう、と唇を突き出した。攻撃性を持たない不満表明。「疑っているのか? 俺は、ミキヒコだ。」「それは疑います」ゴフマンの『フレーム分析』で言うところのフレーム破壊。ここで俺はふと、とんでもない戯言の長い物語を作って披露する。「証拠を見せればわかるのか、いいだろう、ミキヒコはあやとりが好きなオカマで、隣町の高校のケイスケに恋をしている。俺の部屋には、そやつのために、夜な夜な編んだ、アルパカ混紡の柔らかな紺色のセーターがある。ユキオは、猫になりたがっている十三歳の男の子だ。知的障害があるために、動物行動学に基づいた猫語を習得してしまっている。リュウノスケは、文学志望で、原稿用紙に文字を埋めるのが好きで、煙草が好きだ。ゴールデンバットを食べるくらいに煙草が好きだ」色々アウトな設定だとも正直思う。アトゥ、とか、英語みたいに破裂音いれたくなるのは、馬鹿な俺の―――病気(?)まず、オカマではなく、ゲイや、トランスジェンダー女性などと配慮するべきだし、(*でもその当人が自虐的に使う例もある)知的障害と猫語という特異な言語使用を結びつけるのは、障害者に対するステレオタイプを強化する危険性がある。(*でも知的障害といえば差別的なのに、サヴァン症候群やアスペルガー症候群は別の扱いを受けたりする)あと高校生なのに煙草は正直イカンだろうと言った後に思った。(*でも二十歳未満が酒や煙草をしてはいけないのは当たり前だが、一度ぐらい経験してみることが、それほど罪なことなのかという向きはある、麻薬やシンナーを考えてもみろ、大人の憧れで済ませられるか?酒や煙草なんか中二病の一種である。それでも甲子園やインターハイなどの部活は別の話である)とはいえ、言葉の列挙は、現実を遊ぶための道具だ。しおりはその語りに眼を丸くする。パントマイムで猫が障子を突き破った時のシーンみたいに、指先が変な動き方をしている(?)「・・・すごいです」と、しおりが褒める。褒め言葉があまりにも純粋すぎて、俺は恥ずかしくなる。馬鹿なことを言っている自分が、この無垢で素直で真面目な人間に救われた気もする。だが、冗談の皮を剥きながら俺は鋭いことを言う。心の何処かで馬鹿を演じ切りたいのかも知れない。そして心の中の入道雲がソレイユする、IQ二〇〇〇で生まれてしまった時から、うすうすこんな日が来るとは知っていたのだ、そしてあまりにも、マグロの目玉を食い過ぎてしまった。不幸な俺よ!(?)「すごい、しかし、それは俺の百ある人格の一部でしかない!」「そんなにあるんですか!」自分で言っていて、ちょっと馬鹿だな、と思いながらも続けた。幽遊白書の美しい魔闘家鈴木をふと思い出してしまう。しかしよくもまあこんなにペラペラ口が回るなあ、と自分でも思う。「そうだ、俺は危ない奴だ。お前みたいなか弱い女は、襲われてしまう! 俺の中には、女の子を襲ってしまう人格もある! 幸い、大きなことにはなっていないが、しおりのような可愛い女の子なら、もうどうなってしまうかわからない!一皮むけばケダモノ、それが世の男!そして一皮剥けば別人格ダレソレ、それがこの俺(?)」どういう奴だ、と自分で突っ込んでおいた。 「・・・じゃあ、いま、誰なんですか!」「わたしは、マユミだ!」「ひえー、女の子の人格。」裏声の演技に俺自身がおかしくなりつつも、笑わないのがプロフェッショナル(?)馬鹿な芝居は、二人の間の儀式になっていく。俺はそれを愛おしく思う一方で、どこかで罪悪感がチクリとする。からかいは安全装置であり、同時に隠蔽だ。本当に悪い人間は、女の子を襲ってしまうとは言わないし、口の悪い人間ならレ イプとか強 姦とか性 的暴力という語彙を遣う。ぼかしているのは平和だから―――だ。「そうよ、あなたは早く帰らなくちゃいけないわ。わかるわね、こんな所で油を売っていたら、狐が来るわ、コココーン!」だが、さすがにやりすぎというものだろう。「・・・でも大丈夫です。理解します。」と、こく――んん・・と肯いた、優しすぎる女の子を見ていたら、もうこれ以上、嘘をつけない気がした。「――すまん、冗談だから、真面目に答えないでくれ」むう、としおりがふくれた。しかしこんな時でも絶交とかいう宣言をしないのね、彼女。「だってお前、誰が百の人格なんか信用するんだよ。藪から猫があらわれて竹にのぼってバンジージャンプだろ(?)お前、優しすぎるだろ。普通、そこは何言ってんだよ、だろ」「人を疑うよりは騙されろ、とお父さんに言われました」多くの親は知らない人についていくな、簡単に信用するな、と教える。しかし、しおりの父は、懐疑主義よりも信頼を選ぶことを娘に教えた。これは、イエスの右の頬を打たれたら左の頬を差し出せや、親鸞の悪人正機説に通じる、逆説的倫理。理性的計算を超えた、愛と信頼の哲学。いい言葉だ。しかし、騙す奴は世の中にいっぱいいるのだ、と、しおりのパパリンは知っていながらそう言ったのだろう。子供を現実に適応させるべきか、理想を追求させるべきか、それは教育家だって、PTAだって、一人の子供を持つ両親にだって一概にどちらかとは言えないだろう。しおりの無防備さを危惧しながら、同時にその純粋さを愛でている。、、、、、幸福の亡霊。、、、、、安全の亡霊。どちらがいいのかも本当のところは俺には分からない、ただ、その教えが彼女の瞳に真実味を与えているのは確かだ。保護のかけられた純真さ。俺はその純真を弄びながら、胸の奥で小さな迷いが生まれる。本物ってやっぱり偽物とは違うのだ。「それより、お前、好きな奴いないのか。こんな所で、俺相手に油売っていてどうする」「わたしにだって、好きな人くらいちゃんといます」という、しおりの大胆な宣言に俺はすっかり、腰を抜かすくらいに驚いた。あの、天然箱入り娘、日本天然記念物ないしは指定文化遺産の、しおりに、好きな人だって、と・・・・・・。「そ、そうか。驚いたぞ、しおりは、てっきり、まだ、恋愛感情がわからないのかと思っていた。」「どういう意味ですか、それ!」「いや、可愛いって意味だよ。お前、自分の周りの女見てみろ、BLだとか、SNSの承認欲求、ルイヴィトンやシャネルやグッチとかいうブランド物、きゃあー、芸能人、ジャニーズ、K-POPアイドルなどへの、擬似恋愛的消費」「・・・わたしだって、そういうもの分かります」「――分かるだけじゃ駄目なんだ。一緒にキャピキャピしておいで、さらば、人魚また会う日まで!」「トオル君がそんなことを言うと、少し嫌です」「俺だって嫌だ、でも、俺はいまヤスシなのだ!」「ひえー、再発!」と、馬鹿なことを、やっている場合じゃないな、と思った俺は、トントン、としおりのこめかみを叩いた。うう、としおりがこめかみを押さえた。「・・・冗談はさておいて、駅まで送るよ。家、駅の近くだろ。俺も、電車乗って行かなきゃいけないしな、急いでいるんだ、こんなところで道草、浅草、こち亀している場合じゃない(?)」「そうですね」「そうだぞ、こんな所にずっといたら、危ないおじさんが、財布を出してお金を出してくるかも知れない」「どうしてですか?」しおりの無知。彼女は本当に分かっていないのか、それとも俺に説明させようとしているのか。「どうしてですかってお前・・。おい、耳を近づけろ、そうそう――実は、そいつは、人買いなのだ!」「人買い!」「声が大きい・・。そうだ、ハーメルンの笛吹き男は童話じゃない、ガチでヤバイ話だ。現代でも、バスに乗ったら空港まで一直線、梱包されて違う国まで宅急便されてしまう例もある。世界中で推定二五〇〇万人が強制労働の被害者とされる、平和ボケした国でも、例外ではない」競馬に狂ったように眼を血走らせながら、都市伝説という名の陰謀論を様々な話題を扱いながらロックオン(?)「日本では近頃、偽警察官の特殊詐欺が流行っているが、今回の奴は、お前のお父さんに話をつけにいくタイプだろう。お父さんは、スーツケースいっぱいのお金に、目がくらむかも知れない。しおりなら、重量約一〇キロ、スーツケースに十分入る、一億円ってところだろうか」「一億円なんて見たことありません!」「そうだ、お父さんは、一億円のお金に目がくらんで、こんな可愛いしおりを売り飛ばしてしまうかも知れない!でもあらいぐま飼えばいいか? レッサーパンダ見に動物園へ行けばいいか、そう思うかも知れない(?)」「あらいぐまとレッサーパンダには勝てません(?)」「俺も神社にいるたぬきには勝てない、あれは可愛い、あと、近頃ミーアキャットに似ている男の子を見つけた(?)」「わたしもミーアキャットに生まれたかったです(?)」しおりの瞳が水を溜める。俺は狼狽えるが嘘から引き返せない。嘘を吐いたことを訂正することもさして難しくないが、ここは反面教師として教え込んでおくのもよいのではないかと思った。後日、訂正しようと心に誓うが、その誓いは言葉の海に溶けやすい。「そうだろう、早く帰るんだ。」「帰ります、帰ります!」「日本では、実はこういうことが割と頻繁におこなわれているのだ。行方不明者は年間自殺者よりも多い!」「きゃあー!」「早く帰ろう、お父さんが悪いおじさんに騙されないように。」「そうします」何だか喋っている内に、デビルマン的な台詞調だなと思えてくる。とはいえ、統計の印象操作だ。実際、日本の警察庁のデータによれば、年間の行方不明者届出件数は約八万件で、自殺者数は約二万人だ。確かに行方不明者の方が多い。しかし、行方不明者の大半は数日以内に発見され、人身売買によるものは極めて少数である。統計の恣意的使用による印象操作であることに疑いはない。二人で歩いていると、路地の角で怪しげな男が現れた。ボロを纏った男は、膝に大きな猫を抱き、猫の頭を指で撫でている。猫はどこか懐かしい眼をしていて、まるで世界の秘密を知っているようだ。男の服装は時代を一周したような古着混じりで、革の匂いと古い煙草の煙の匂いが混ざる。猫の腹には油の匂いがする。動物好きそうに見える者が必ずしも善人ではないことを、街は教えてくれる。「藪からあやしいオッサンがあらわれたかと思ったら河童でした、『ちょっと相撲とろうよ』『わかった、負けたらキュウリな』」「怒られますよ」とか言いながら、しおりが笑っている。俺が男の横顔をちらと見ると、その瞳の奥に一瞬、機嫌の悪い猫のような光が走った。、、、、、、ルサンチマンという言葉がよぎる。それだけで俺の身は少し硬直する。だが一瞬の後、猫を撫でるおじさんという、小さな善の光景が、人身売買という暗い想像を打ち消してくれる。夕陽がいつのまにか地平線にほつれて、日没をしらせるようにすみれの色が淡く空に拡がっていて、そして壁に向かって不敵な微笑みを浮かべながら、しおりが眼を丸くしている、ハハハ、どうしたんだい、ちょうちょは見つかったのかい、ハハハ、アハハハ・・、、、、、体当たりをした(?)
2025年11月19日
-
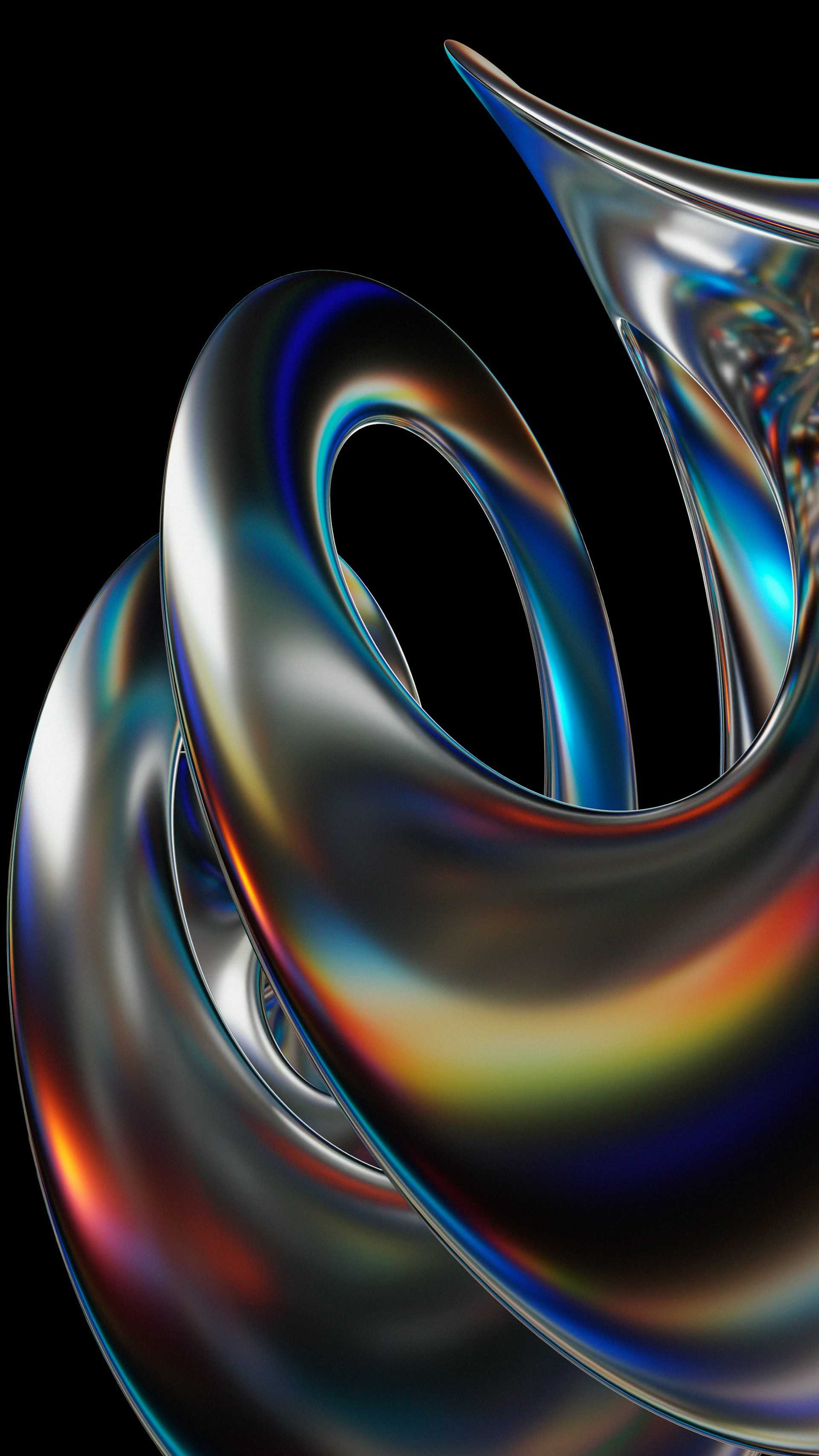
MOVE... MOVE... ON... on......
、、、 着いた――。 無音で呼吸する蠍の敏捷と比べるべき、 背の青いあのマラリア蚊。 小さな診療所・・割れた月面に打ち捨てられた、 ミニマルなコンクリートの四角い箱舟。 リフレインが胸腔で暴れ回り、 小さな真珠のような衛星―― 超ハイテクデジタル、 ディジタル・・、 ディジタル――。 MOVE... MOVE... ON... on...... コマンド。システムが起動する。 しかし、何のシステムなのか? 動け、と命令される。 進め、と。 しかし、エネルギーは徐々に減衰していく。 「MOVE」から「on」へ。 大文字から小文字へ。 やがて、ピリオドだけが残る。 ――僕は小悪魔みたいな響きの中、 その難題を解いてみせる、熱度。 その難題を解いてみせる、風。 ・・・・・・・・・変幻自在な、魂。 soul、psyche、anima。それは、定義不可能な何か。 形を持たず、重さも持たず、しかし確実に存在する何か。 フロイトなら「無意識」と呼び、 ユングなら「集合的無意識」と名付け、 仏教なら「阿頼耶識」と概念化するような、その何か。 、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、 、、、、 目の前に広がる、この過ぎ去っていく世界に、罪がある。 、、、、、、 、、、 、、、、、、、 誰も知らない、きっと、僕も知らない森・・。 、、、、、 、、、、 車輪の音は、止まない。 <ガラスの国のアルカディア・・。> (そこには青い鳥が棲むのよ。) 、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、 昼間なら、なだらかな丘の地形が一望できる。 昼間なら、なだらかな丘の地形が一望できる。 、、、、、、、、 ただの嘘じゃない。 過剰な生物どもの生殖と息ぜわしさの豊穣な花園、 地獄の現前のような蛮界。 ジェット機がアンデス山脈を越えて、 消えて次々と破れてゆくような音。 果てしなく続くRPG。 ダンジョンの中から今日も僕は抜け出せない。 夕焼けなんて下らない――。 ただネジを巻き戻すだけだよ、あの夕焼け・・。 どうしても欲しかった――。 “自分”という名のコード、解答、パスワード。 何処に行けば掴める? 過ぎ去る世界が罪のように見える。 ワクチン投与、 南京虫に喰われて、痛み、痒みで、 火照るような悪い夢の不快指数が増える。 ジャズの転調みたいに、 悪夢の粘度は増す。 零――。 zero...nothing...void... 部屋に入ると彼女がいる。 ――天使はもう殺しちゃったのよ―― ――悪魔になるんだ―― ここに来ると、時間が遡ってゆくような錯覚に囚われる。 残酷なまでに甘い、知恵の果実。 僕の世界は呼吸困難で息が出来ない――。 コア 君が言う、核――。 シールド 僕が言う、盾・・・・・・。 いつだって僕等、 意味のないゲームを延々ループしている。 混 沌 と し た 世 界 で、 混 乱 し た 世 界 で、 優しい父親がいる。 ―――道徳と規範の体現者。社会的価値観の代弁者。 優しい母親がいる。 ―――包容と受容の象徴。無条件の愛の体現者。 優しい娘がいる。 ―――無垢と純粋の象徴。未来への希望の体現者。 時として抑圧として機能する。 時として依存を生み出し、自立を妨げる。 時としてその無垢さは、同時に無力さでもある。 、、、、、、 狂気のリズム。 出口のない螺旋階段を、 永遠に下り続けるような感覚。 夜空を横切る、人工衛星の軌跡。 点滅する光。デジタル信号が宇宙空間を飛び交っている。 0と1の連続。 しかし、その意味は誰にも分からない。 暗号化された、解読不可能なメッセージ。 「MOVE」から「on」へ。 「MOVE」から「on」へ。 庭仕事用の倉庫やガーデンチェアや、 役目を失った自転車が、 ゆっくりと重力から脱線している。 I can't go on, I'll go on この世界のルールは、 プログレの拍子記号みたいに変則的だ。 リノリウムの床が、 エコーを帯びたスネアドラムみたいに、薄く響く。 壁にはキツツキの穴のような傷。 消毒液の匂いが、保健室の記憶を逆撫でする。 “ひとりだけの時間” “言葉の中だけの言葉” ―――病室へ。 地形をなぞるように伸びたコンクリートの終端――。 そこが“入口”というより、 異常な楽章の開始点...... 診療所なんてものはない。 結核療養所の亡霊、 あるいは、忘れられたコテージ群のドローン映像。 今日の俺は一体何処に着地しようとしているのだろう。 フェイザー処理されたみたいに揺らめいて流れ込む。 窒息する・・。 本当の家族になれると思っていたのに、 本当の家族になりたいと思っていたのに、 どれだけ近づいても、 どれだけ理解しようと努めても、 人と人の間には、決して埋められない距離がある。 皮膚という境界。意識という壁。 言語という不完全な伝達手段。 バードウォッチングにも、天体観測にも、 それこそ“次元の歪み観測”にすら向いている。 夏は子供がカブトムシを追いかけて迷い込み、 冬はチェーンを巻いても進めない――。 北海道の外縁みたいに、時間が凍りつく場所。 ―――受付。 白衣の髭面の医師が、 ストーナー・ロックの低音みたいな重たい声で言う。 「もし人生を、そのまま、 永遠に繰り返さなければならないとしたら、 君はそれに耐えられるか?」 ―――にイちェ 窒息する、 ここはみづうみじゃない ・・・・・・・・・でも、水の中にいる a 緊張感は何処へ行くのだろう?――その匙は、砂糖であり、塩。 でも本当の味がちっともわからない味覚障害。 b 酸素を探しているんだ――爆発する前・・ ただの紙切れ、文字の羅列、――嘘の箱庭。 c ウィルスが一つのパスワードとなる風邪。 d メッセージさえ一つのオプションとなる、 携帯電話というスパイゲーム・・・。 ひとりだけの時間ー純粋なー言葉の中だけの言葉。 、、、、、、、、、、、、、、、、 僕は彼等の口惜しそうな顔が見たい。 静寂。 しかし、音は完全には止まない。 耳鳴りのような、微かな高周波ノイズが残る。 それは、実際の音なのか、 それとも脳が作り出した幻聴なのか。 「MOVE」から「on」へ。 小さな真珠のような衛星―― 超ハイテクデジタル、 ディジタル・・、 ディジタル――。 MOVE... MOVE... ON... on...... (悔しいのは、自分の顔さ・・) 、、、、、、、、、 同じ画面を見ている。
2025年11月18日
-
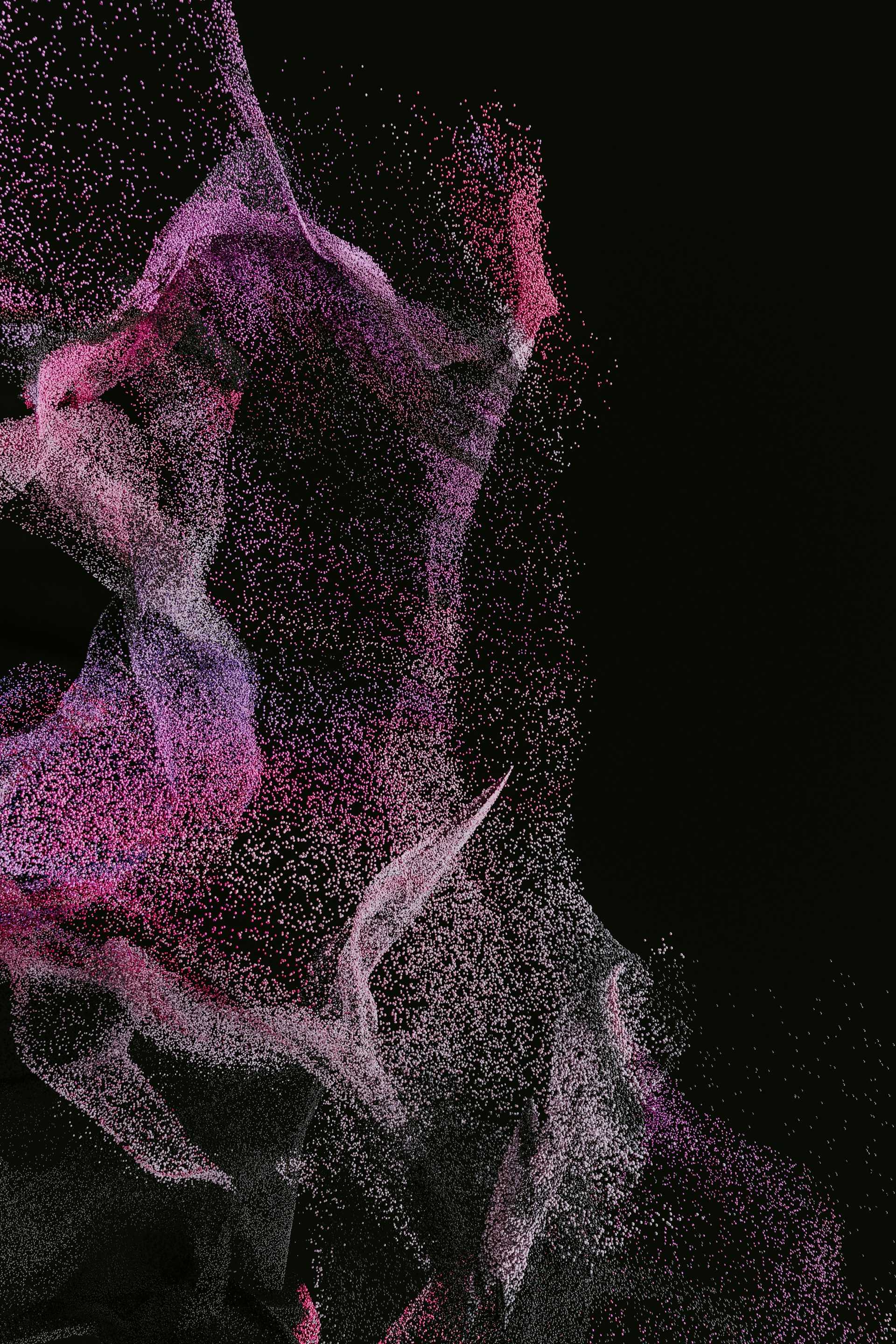
名前
、嘘でも言われたい、 ・・・愛されたい。咽喉の奥が渇いて、言葉の水を求めるように、メタファーを、リズムを、韻律を、音楽性を。この頃は妙に詩に飢えている、僕だから、風は僕の意志、、、、下さい、・・・生命の養いなる悪。たとえば、限りない罰。ボードレールが「悪の華」で語った、あの美しい腐敗。ランボーが「地獄の季節」で燃やした、あの狂気の炎。シーシュポスの神話のように、終わりのない反復を。カフカの『流刑地にて』の処刑機械が皮膚に刻む、あの精密な文字・・・。、、、、、、、、、、、、、、痛みが意味に変換される瞬間を。 強烈なフラッシュバック!(また!また! ・・。 、インスピレーション不意に襲ってくる過去の断片。プルーストの『失われた時を求めて』のマドレーヌではなく、もっと暴力的な記憶の侵入。 スムースな音の炸裂! 眠れない よ・・。夢の記述PTSDの症状にも似た、制御不能な想起。視覚、聴覚、触覚、嗅覚が一度に蘇る。脳内のシナプスが過剰発火し、現在と過去の境界が溶解する。ギリシャ語のエンテウシアスモス。――神が内に入り込むこと。ミューズの息吹。しかしそれは優雅なものではなく、むしろ癲癇発作に近い。ドストエフスキーが体験したような、時間が停止し、永遠が流れ込む瞬間・・。参ってるくらいがテンダーネス泳ぐように流れ過ぎ る、ねばっこい、妖しい美しさ・・・時間 。いじきたないほどに ( しめやかに雨は降り続くマイルス・デイヴィスの、「カインド・オブ・ブルー」のような、モーダルな自由さ。コルトレーンの「至上の愛」のような、スピリチュアルな狂乱。音符が分子のように空間を満たし、耳だけでなく皮膚で感じる振動。 あなたは、僕が出会った中で、 最もうつくしい人だ・・。 ( 孤独もついに届かなかった! 僕は、――考えてる、 額からしたたり落ちたひとしずく 、、、、 、 失うのは、嫌・・。 フロイトの『夢判断』 ユングの集合的無意識。 蜘蛛の糸、金木犀の匂い、、忘れられるかい? ( あの日、奪われた、言葉のかおり ・・・でも同時に、憶う 、女は、意義傷つきやすさ、壊れやすさ、脆さ、儚さ、すべてのものに亀裂がある、そこから光が入ってくる。 忘れたのかい? ・・・君は下らない、頭も空っぽだ、―――そして、どうしようもない 、でも、忘れられるかい? 美をリルケの『ドゥイノの悲歌』に出てくる回転木馬。サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』のホールデンが見る回転木馬。永遠に回り続ける、しかし前進しない運動。デカダンスの美学。世紀末芸術。オスカー・ワイルドの「ドリアン・グレイの肖像」ビアズリーの挿絵。アール・ヌーヴォーの曲線。腐敗と芳香が混じり合う、サロメの官能。時間の猥褻さ。老化、劣化、崩壊。エントロピーの増大。振り返れば、だんだんと盛り上がって死を免れえぬ永遠にほら、 さよならスタンダールの「美は幸福の約束である」という定義。あるいはドストエフスキーの「美は世界を救う」という信念。しかし僕にとっての美は、もっと個人的で、翻訳不可能だ。糞喰らえなんだよ。どうだっていい。何だっていい。顔の輪郭。頬骨の高さ。睫毛が落とす影。唇の端の微かな非対称性。話す時の手の動き。笑う時の目尻の皺。すべてが完璧ではなく、だからこそ完璧だ。大衆音楽の味わい。キャッチーなメロディー。耳に残るフック。しかし同時に、表層的な甘さ。人工甘味料のような、後味の悪さ。 、、、、―――くっきりと抜けるような青空と、対照的に褪色、僕の心は暗く沈んだ仮面 ( あの日、見つけたメリーゴーラウンドに 似た、午後のカフェを 、忘れられるかい? 、失くせるかい? 見知らぬ街、人通りのない石畳・・、僕等はまた、浮かぬ顔を見合わせるばかりリルケの『マルテの手記』の孤独。ニーチェの超人的孤立。しかし僕の孤独は不完全だ。自己嫌悪の言語化。内的批判者の声。しかしそれは他者の声でもある。内在化された批判。スーパーエゴの攻撃。記憶が、幻影が、残響が、僕に訪い続ける。(でも・・・!)ひた走る横に倒れ、斜になり、仰向けに・・・ただ、時間、いたずらに、時間だけが過ぎてゆくー。 、思い出すんだ! 形にならない声を・・。 ドップラー・エフェクト、連続するリフ、ああ! 重なり合うパーカッション・・。喪失恐怖症。アタッチメント理論。ボウルビィの研究。分離不安。しかし失わないものなど存在しない。ブッダの無常。ヘラクレイトスの「万物は流転する」始まらない。終わらない。キース・リチャーズの「サティスファクション」のリフを思い出しても。ジミー・ペイジの「天国への階段」のリフを思い出しても。 泣いちゃいそうなんだ、 君を信じてる・・・、感じてる、 でも、幸せで満たされているって嘘 。 ・・・僕は剥ぎ取った、透き通るような声で芥川龍之介の『蜘蛛の糸』カンダタが掴む、一条の細い希望。記憶と忘却の同時性。矛盾の共存。ジョルジュ・ペレックの、『W あるいは子供の頃の思い出』のように、記憶は虚構と混じり合う。、ポップ・フレーヴァー刹那とを離れた 言葉と言葉のあいだの空白 、あの、プチ・フール ・・・覚え て る っ て 、なんの衒いもない、経験を背景として、目の当たりにする波打つように、微妙にリズムを変える 、、、、、、 ―――僕のバラード出来事が累積し、増幅される。記憶の編集。回想の中で、現実よりも鮮明になる過去。カミュの『異邦人』の冒頭、母の死の日の眩しい太陽。明るさが逆に絶望を際立たせ。ふてくされた僕は、―――すぐ、壊したい衝動、に駆られるけど波がしら・・・、色気、身づから踊り出したいような空気(・・・に 染まってゆく)ほ ら、 身体中 強烈なフラッシュバック!(また!また! ・・。 、インスピレーション 、、、、 、 失うのは、嫌・・。
2025年11月17日
-

「電源」ボタンはオフ
危機、死ぬ、消滅――。そんなネガティブの語彙が、既存ジャーナリズムの裾野から、絶えず押し寄せて、耳の裏側をざらざら削り、自然の抜け穴の多い石の洞窟に群盗が根城。欲しいのはポジティブ・シンキン・・!壁紙の継ぎ目が僅かに剥がれかけているその隙間のような。パートナーの瞳孔に映る俺の小さな像へ向けて。友人の携帯電話の液晶画面に浮かぶ既読マークへ向けて。インターネットという名の無数の神経線維が、光ファイバーケーブルの中を毎秒何十億ビットという速度で駆け巡り、情報という名の電子の粒子が、検索窓という小さな入口から次々と飛び込んでくる――。メンタル・エグゾースションを、ストーリーテリングせよ。、、、、私的空間。パァートナーへ、友人へ。インタァーネット普及、情報検索――。どうとかこうとか、いや、もう、そのもの自体が“まずい”のかもしれない。サンドペーパーでゆっくりと往復するような、ロォラァー。ロォラァー。どうとかこうとか、いや、もう、そのもの自体が“まずい”のかもしれない。まァちがってる、マァーチ。まァ知がってる、知識の樹の枝が誤った方向へ伸びている。まァ血がってる、動脈を流れる赤血球の進行方向が逆転している。まァ値がってる、株価ボードの数字が一桁間違って表示されている。ツゥー、ツゥー、ツゥー、ツーッ、ツーッ、ツーッ、、古い黒電話の受話器から漏れ出る断続的な信号のように。若干延ばされた音が、留守番電話の最後に響く空虚な終端記号のように。―――さぁ、ドアァを開けよう。流れた。/そして弱い立場に置かれた。 堤防の亀裂から溢れ出す濁流だって」」」情報の偏向、退廃、不動徳、倫理の死角。 洪水で流された小舟の中で、櫂を失った船乗り」」」・・・・・・寝るより他にない夜の底でも接続される、だってそれは情報シィステムだから! ほら、プリズムを通過した光線が一方向へ屈折する。魔法へのアァクセス権!古いビルディングの外壁タイルが、一枚また一枚と剥落し、やわらかなクレェヨンの日向ぼっこ。監視キャメラの視野から外れた、壁の影の三角形の領域・・。 ((( 私はどこにも取り付けられない、蛇口 「群集に混ツて出口まで来て、ヘエ、 ツイ御挨拶もいたしませんで・・・。」開放感――。海抜マイナス数千メートルの暗黒の海溝のような場所でも、光ファイバーケーブルは這い、Wi-Fiの電波は届く。でも人間はいない。宙に浮いたまま、ねじ山だけが虚空を向いている状態。密閉された部屋の窓を開けた瞬間に流れ込む、外気の最初の一息。それこそがインタァーネットが死ぬ日の鐘だ。堂々めぐり。同じ穴のむじな。のぼせたフルコォースの思考。テクニカルなパラメーターや、フィロソフィカルなインプリケーションを、ブーストアッ!ブーストアッ! 空―――。 ああ、なんて深い空でしょう。 成層圏を超え、中間圏を抜け、熱圏の彼方まで。 もう一つの世界が、水の底に沈んでいる。 『暗緑色の領域に、 逆さまの町並みが揺らいで映っている。』 あ、あ、荒治療が必要です、、 ぷ、ぷ、プラス思考が必要です、、 ティーヴィー・新聞・雑誌・レディオ、 からの、生成変化としてのメェディア、 ああそれぞれ、ブラウン管、印刷インク、 光沢紙、電波という異なる物質で構成された、 「「「変化するためのメディア。 液晶ディスプレイ上でピクセル単位で更新され続ける。 NHK! 民法! 新聞各紙! 中立は影のように抜け落ち、 インタァーネット普及、情報検索、、光ファイバーケーブルが地球を網目状に覆い、検索エンジンのクローラーが毎秒何百万ページを巡回する。『眩暈を覚えたってもう遅い』、、、先週末からラップ聴き続けてる、耳腐りそうですごい、外耳道の皮膚組織が壊死を起こす寸前のように感じられる。鼓膜が溶けそうだ。アブラカタブラ。泣いちゃいそうさ、クラップトラップ、サウンドトラック、ハイハーイ!涙腺から涙液が溢れ出る直前の、目頭の熱い圧迫感。エクセェ! レェーント! 君は、君は、君は見ていたのかい。 集合知! 集合的無意識! ユングが提唱した概念、人類全体で共有される無意識の深層。 かげろうのようなデータの夢を。 を・・。 心―――。 それは傷付きやすくて、 傷だらけのまま、 冬の氷の向こう側で震える、 インパックト、それは陽性で強烈なビィート、 たまさかの黒い残光・・・。 ―――さぁ、ドアァを開けよう。 (そして、ぼくの、ミゥルクがあふれだしそうだ・・。)、、、、、、乳白色の液体が、容器の縁まで、あと二ミリメートルのところまで満たされ、表面張力で僅かに盛り上がっている。 さあ誰がどうする?/地方自治体、商工会、 中間組織、自治体、大学、企業、 ・・・・・・NPO! さては効率的な近代化、 困りゃ直轄事業! 昼夜兼行突貫工事。 ((( 私はどこにも取り付けられない、蛇口 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 しかし接続すべき配管がどこにも存在しない。 テレビからはニュゥース/オルタァーナンス! 違うスゥーパー・リモコン、 ・・・祝祭的テェロップ、安心を謳うキァャスター、 みんなのもの! そして極めつけは、あなたのため・・。、、、、、、みんなのもの! その「みんな」は視聴者数推定一二八〇万人、視聴率一八.三パーセント。その「あなた」は単数形でありながら、実際には不特定多数の三五四七万世帯を指している。 ((( どこまでロマァンチスト! アンタ、頭大丈夫?危機、死ぬ、消滅――。既存ジャーナリズムのネガティブ・ループ。その円環の直径は測定不能、一周するのに要する時間は約七十三時間、しかし永遠に出口は現れない。パァートナー、友人、その、マイクロ・モザイク・イマージュ、情報検索の往復運動。フルコォースのディナァー。まァちがってる、マァーチ。まァ知がってる、カレンダーの三月のページ、三十一日分のマス目、しかしそのうちの何日かが印刷ミスで欠けている。まァ血がってる、百科事典全二十八巻のうち、第十七巻の、五百二十七ページから五百三十三ページまでが、製本時に逆順に綴じられている。まァ値がってる、血管の総延長一〇万キロメートルのうち、どこかで一ミリメートルの亀裂から出血が続いている。ズレている。ズレている。ツゥー、ツゥー、ツゥー、ツーッ、ツーッ、ツーッ、、バイアス & フェイク・インフォメーション(へ、)バイアス & フェイク・インフォメーション(へ、)―――さぁ、石を投げよう。 嘘―――。 うわあ、気持ち悪ィ、ぞっとするぜ ああ! これがステージ・ドァアーの裏で、 有頂天にさせて、再度ずぶぬれになって、 ピンク色の唇がディズニィーランド! 「「「ディズニーランドは面積五十一ヘクタール、 年間来場者数一六〇〇万人。 あ、あ、荒治療が必要です、、 ぷ、ぷ、プラス思考が必要です、、、、、、、、、、思考の極性を反転させ、負の電荷を正の電荷に変換する、その変換効率は理想的には一〇〇パーセントだが、実際には六十三パーセント程度。いやもっと低いかも、ね・・・・・・。 下を向いて歩こうぜ、 誰もお前を写さない! さあおいで失格者、退廃者! いや正確に言おう、ゴミ! おいゴミ、 一人一日あたりの排出量九百十八グラム、 年間総排出量四二七四万トン。 ノリとハァードさが身上、 ファンキィーなブレイクツに身を任せて、、 君は、君は、君は見ていたのかい。 ネガティーブ・ネオンアートの光跡を・・。 後の祭り、片栗粉、ベーシェーンス・・・! 待機時間は測定不能だが体感的には永遠。 時―――。 まるでフロア向けブラァック・ミュージィ。 ((( ロォールシャッハの残像を待って ―――さぁ、ドアァを開けよう。 (そして、ぼくの、ビック・ビィート・・。) 口―――。 げえぇ、あいてんのか、顕微鏡の誤解。 「死ね!」 透明な水中生物フモウ科コケオドシ属の呪詛。 あ、あ、荒治療が必要です、、 ぷ、ぷ、プラス思考が必要です、、 ねじれて光る/仔細に眺めて、 いきなり目の前に飛び込んできたのは、 雪! もっと荒々しいクレッシェーンドと急下降! ほいきた、ドラムロール! ああン! もっと! もっと! さ・・。 だだぶりの雨! 代用ビールのジョッキ、 完ァン璧にスケェールアウツ・・・! ―――さぁ ドアァを開けよう (未来永劫ゥ・・・、切り刻め! 欠落した記憶ゥ!)まァちがってる、マァーチ。行進曲のテンポは本来一二〇BPMだが、この演奏は一三四BPMに加速されている。拍子は四分の二、しかし三拍目が〇.一五秒遅れている。まァ知がってる、図書館の蔵書二十三万冊のうち、分類番号の誤りは推定千八百四十七冊、配架位置の誤りは三千五百六十二冊、データベースの誤入力は七八九件。まァ血がってる、血液型はA型のはずがB型と誤記されている。まァ値がってる、為替レートは一ドル=百四十七円のはずが百四十一円と表示され、誤差は六円、その結果十万ドルの取引で六〇万円の損失。、、、、、、お待ちかねの、オールド・ブラック・フォンの「ツゥー、ツゥー」のインターバル・・。ツゥー、ツゥー、ツゥー、ツーッ、ツーッ、ツーッ、、 ―――さぁ ・・・さぁ。 呼吸が二回、心拍が七回。 風―――。 まるで踏み絵! 地雷・・。 ジグシォーパズル・ヘリコプタァー。 ((( 水溜まりにうつったショットガァンの不意打ち ―――さぁ、ドアァを開けよう。 (そして、ぼくの、ビック・ビィート・・。) 夢―――。 突きぬけそうで、踏み外しそうだ、 ・・・氷の池。 跳込台の上で震える! 透明な星がうつってる、うつってるよオ。 (モザイク画のように・・・、 あれは、刺激だったよ、本当ゥ) ぬ、ぬ、抜け殻のように揺れる空虚なカラダァ、、 し、し、しわよった未来のためのアシオォート、、 ((( 私はどこにも取り付けられない、蛇口その、アンアタッチド・フォーセットで、その、アンアタッチド・フォーセットで、ツゥー、ツゥー、ツゥー、ツーッ、ツーッ、ツーッ、、『精神状態の逸脱度を数値化したい』((( 異常な遅さが緊張と狂気を物語るまだまだコンプリート・ディスコネクション。(ハード・ディスコネクション・・)「バァカ……夜の町の、あまりに美しい夜。火は赤く染め、白を黒く染める……サ。」ツゥー、ツゥー、ツゥー、ツーッ、ツーッ、ツーッ、、『正常範囲からの乖離率を教えて欲しい』((( 最後の信号音の後、回線は完全に切断されるさあエントロピーがインクリースするワールドでの、エゴ・フラジリティをデモンストレート・・。 「ヘヘヘ、知ってるんデスぜ、旦那、ウヘヘ、 ドウセ死んだら跡形もナシですってネ。」 ツゥー、ツゥー、ツゥー、 ツーッ、ツーッ、ツーッ、、 「了解・・・。おくやみモウしあげやす。フヘヘ、 アンタ! かなりイカれてるぜ。」ツゥー、ツゥー、ツゥー、ツーッ、ツーッ、ツーッ、、 オーディエンスに叩きつける、ハイ・インパクトなエクスプレッション・・。 「バァカ!・・。夜の町ノあまりニうつくしい夜ゥ 火はあかく染める!白をくろく染める!サ・・。」 ツゥー、ツゥー、ツゥー、 ツーッ、ツーッ、ツーッ、、
2025年11月17日
-

イラスト+詩「世界の終わり」
ねえ。 さだめ 運命だって。 馬鹿だってわかってるけど。 やっぱり他にどうすることもできないみたいで。 言葉は湿った空気に溶けて消えて―――いく・・。 言語行為論。 脱構築。記号論。 ラカン的象徴界。 、、、、、、、 いつかの記憶が。 誰かが誰かを待っていた。 僕は誰でもなかった。 ハイデガーの現存在。 レヴィナスの他者。 バトラーのアイデンティティのパフォーマティヴィティ。 気の遠くなるような、 サイレント・ノイズ 静かな音・・。 抑圧っていう腫れ物、いや、跳ね物。 あのSpring に僕はやられて。 愛にこきつかわれながら。 愛を探す雑沓のなかの旅人。 ストレンジャー 雑踏の中の旅人・・。 胎児のように身をちぢめていた。 あの時間なら。 聴こえるのも野暮だった血流の音。 悲しかった太古の恋の物語。 駅のホーム、バスの扉、 コンクリートの裂け目。 何処にも居場所はないが、 何処へでも行ける可能性がある。 でも世界は巨大な迷路で、 僕は出口のない迷宮を彷徨うテセウス。 ただ、僕にはアリアドネの糸がない。 でも君へと向かって風が流れ。 僕はやさしく打ち寄せる波をやめて。 君を包む陽だまりとなる。 愛はその人にとどまる空気だと思えるから。 、、、、、、、 ゆめをみている。 、、、、、、、、、、、、、 あさいゆめからもぐってゆく。 理性の最後の砦で、 論理的思考の残骸が必死に警鐘を鳴らしている。 でもそれは遠くの教会の鐘のように、 ただ虚しく響くだけで、 僕の手足を動かす神経までは届かない。 やっぱり他にどうすることもできないみたいで、 重力に逆らえない石のように、 僕は決められた軌道を落下し続けている。 フーコーの規律訓練。 アレントの凡庸な悪。 ドゥルーズ=ガタリのリゾーム。 、、、、、、、、、、、、 ふかいうみにしずむように。 、、、、、、、、、、、 ひかるかけらをさがして。 ア ト モ ス フ ィ ア 必要不可欠な空気・・。 何千年も隔てられていた氷の中で。 、、、、、 はっきりと。 、、 そう。 はっきりと僕は感じる。 掴もうとすればするほど、 細かく分裂していく不安の結晶。 医学書で見た悪性腫瘍の顕微鏡写真を思い出す。 細胞周期。アポトーシス。p53遺伝子。 あの無秩序に増殖する細胞の群れ。 あの、生命の暴走。 いま確実に大きな花びらが落ちてゆく。 熱狂は見る見るうちに引いてゆく。 でも心臓は洪水の中に浮かんでもまだ熱い。 沈まない。 しかもまだ痳れてる。 僕は何だか気が落ち着かない。 魂が無理矢理目覚めさせられたような気分で。 ああ遠い――はるか遠い世界の匂いが・・する・・・。 アウター・ドリーム 浅い夢から、水深千尋の深海へと、 重力に引かれるように潜行してゆく。 遠い世界の匂いがする。 塩と亜麻の混じった香り、乾いたステップの埃、 モンスーンの湿り気、アルプスの夜の凛とした冷気。 越境的な匂いが、僕の爪に挟まっている。 「恋は神の儀式の一つだよ。 生きることが試練であるみたいに。 本能がどうして種を繁栄させたのか。 どうして人類が歴史を作ったのか――わかるかい・・」 僕は淋しさと焦燥の中でうすぼんやりとする。 愛が血けむりのように踊る。踊る。 無秩序な動き。予測不可能な軌跡。 ブラウン運動。 熱によって引き起こされる粒子のランダムな運動。 噴火の光景。 そしてそれを眺める彼女の後ろ姿。 僕はそれを一緒に見ながら世界の終わりを感じた。 そうか、この風景がすべて崩れてしまうのかと思った。 そして眠りの砂をかけられるのか。 ただ一晩中うねる雨の音のように僕は破壊の音を聞いてた。 アイス・エイジ 氷河期の記憶・・。 女は振り向いて。 これから何を食べようかと言う。 のんびりとした声で。 目の前の現実などわかりもしない笑顔で。 インター・ステラー・マター 未知の星間物質の匂いかも・・。 分子雲。 水素原子。 宇宙塵。 スペクトル分析。 何もかもが等しく、 何もかも悲しく、 そして何もかもが美しく。 永遠の愛も、 脳内のドーパミンとセロトニンと、 オキシトシンのバランスでしかないと、 気づきながら・・・・・・。 僕も笑う。 そのまま深い沼へでも入るように。 乖離がある。内面と外面の。 あるいは、僕の認識と君の認識の。 模倣。ミラーニューロン。 社会的同調。 でも、それは自動的な反応ではない。 意識的な選択。 仮面を被る。ペルソナ。 息をしている。 耳をふさげば気の遠くなるような静かな音のなか。 入れ子構造。メタフィクション。 細密画。ミニアチュール。 中世のイルミネーション。ペルシャ細密画。 極小の空間に、膨大な情報を詰め込む。 虫眼鏡で見る必要がある。 でも、どれだけ細密に描いても、 描き尽くすことはできない。 、、、、、 フラクタル。 拡大すればするほど、 新たな詳細が現れる。 君の肋骨が膨らむのを背中越しに感じ、 空気が肺に入っていくのを想像した。 酸素分圧。 肺胞換気量。 ヘモグロビン飽和度。 酸素が血液に溶け込み、赤血球に運ばれ、 毛細血管を通って全身の細胞に届けられる。 生化学の教科書で習ったクエン酸回路、電子伝達系、 ATP合成。生命とは要するに、巧妙な化学反応の連鎖だ。 でも、その夜の僕たちは、 化学式では記述できない何かだった。 トロイアのヘレネ、 ロミオとジュリエット、 トリスタンとイゾルデ。 ディヴァイン・リチュアル 神の儀式へ・・。 ボルヘスの「バベルの図書館」のような、 いや、エッシャーの「相対性」のような、 重力の法則が通用しない空間・・・。 繰り返す、ドーパミン、 繰り返す、ノルアドレナリン、 繰り返す、フェニルエチルアミン。 僕はおたまじゃくし。 君はおたまじゃくし。 小石で。 そして砂で。 ディープ・マーシュ 深い沼へ・・・・・・。 暗闇の中で、やっぱり僕は原始の海を泳いでいる。 カンブリア紀の海、最初の脊椎動物が誕生した場所。 三葉虫、アノマロカリス、ハルキゲニア。 生命の爆発的多様化。 でも、その多くは絶滅した。 化石として、堆積岩の中に閉じ込められている。 サウンド・オブ・デストラクション 破壊の音・・。 潮汐力、 ニュートンの万有引力の法則。 月と地球の間に働く力、 地球と太陽の間に働く力。 エンド・オブ・ワールド 世界の終わり。 その、波で。 その、塵で。 意味で。 関節という関節の疲労で。
2025年11月17日
-

君がいた夏
あなたが――ふと・・見せてくれた、 情熱が――ありありと思い出せる・・。 光は薄い琥珀色をしていて、 指先に張り付いたように冷たく、 でも温度を持っていた。 窓枠のペンキの剥がれた縁に、 夜露の匂いと古い鍵の油の香りが混じる。 空、それは塗り替えていく前触れ。 朝、息をする時の呼吸の浅い緊張。 人、胸がみしりと痛む人の流れ。 ヒューマン・ストリーム 「非線形な人の流れ・・。 透過しにくい精神の物質、 エーテル体のように、あるいは高分子ポリマーのように、 強固で、しかし形を持たない。 それは、誰にも見えず、触れられない、 結晶化し損ねた感情の塊だ。 ――このまま・・、 時が過ぎるのを待ってみようか・・・ 毎秒、脱進機のアンクルがガンギ車の歯を一つ解放する。 その微細な金属音。時間は量子化されている。 連続的に流れているように見えて、 実は無数の離散的瞬間の集積。 ベルクソンの持続とは異なる、デジタル的な時間・・。 息をする時の呼吸の浅い緊張。 目覚めてから心拍数が平常時より十五パーセント上昇している。 横隔膜が完全に弛緩せず、 肺の下三分の一まで空気が届かない。 胸骨の裏側、ちょうど第四肋骨と第五肋骨の間あたりに、 鈍い圧迫感。洗面所の鏡に映った自分の顔。 目蓋が僅かに腫れぼったく、強膜の毛細血管が浮き出ている。 昨夜は結局三時間しか眠れなかっ―――た・・。 サラリと――発せられた言葉は・・ ・・とてつもなく――重いハンマーで・・ リコンストラクト 過去の光を現在に再構築―――する・・。 心によぎって それでも吹きぬけていく 胸には・・隙間風――。 デカルト座標系の原点が、一瞬にして崩壊する。 それでもなお、ジェット気流のように吹き抜けていく。 後に残るのは、胸に開いた、絶対零度、 この途方もない、 マージン 今この文面の中にある、この余白・・。 空の中心には何があるのだろうか?・・ それが知りたい、と思っていた――。 成層圏のさらに上、 カーマン・ラインを越えた先に、 音のない真空が広がっている。 その到達できない高みへと・・その空の中心には、 まだ見ぬ世界があるのだろうか? 誰も行ったことのない場所が。 僕がまだ見ぬ世界は、何処かにある。 なのに、たかが知れている――際涯・・。 インアクセシブル・ハイト 到達不可能な高み・・。 ストラクチュラル・トラジェディ 構造的な悲劇―――を・・。 迷走神経の過剰な活性化。副交感神経系の暴走)」 (「ラカンの言う欠如だ。フロイトの喪失だ。 対象a の永遠の不在。埋められない穴・・・・。 「だから呟いた・・返事なんかいらない!――」 (だから呟いた、――時間なんかいらない!・・) ねぇ今でも覚えているんだ・・。 琥珀色の瞳に心が動いた・・あの日々を――。 世界がその色を塗り替えていく、 プレリュード 雄大な前触れ・・。 一つの季節、思い描く時――、 ひょいと跨ぐように、 乗り越えていく季節であればいい・・。 空よ、僕の声きこえるか否か、 ――聞こえてくる、太陽の律動のような 森よ。誰かいる誰かきこえるか誰か。 ――僕ではない僕もその誰か、頭から否定する。 光よ、惹かれた報い感じて夢見る枕、 毛布の温もりに、真夜中が逃げ込む・・。 君が段々変わっていくのを知りながら、 ――ずっと言い出せなくなっていた・・。 樹木、菌類、昆虫、鳥類、哺乳類。生態系。 青い色の孤独、黄昏色の孤独・・・・・。・ 僕はまだ君に、伝えていない言葉を、 ――伝えたくてつたえたくて。 他に何にも考えられなくて、 ・・・どうにかなってしまいそうで嫌だった――。 テセウスの船のように、 すべてを置き換える決意。 、、、、、、、 魂の物質的転生、 、、、、 、、、、、、、、 あるいは、生命倫理的な超越。 ――生まれよう、誰もが一人の子供だった。 静謐かすめんとする、雲であらんことを。 たなびく雲を流す風になろう、そしてまた、 その雲を染めていく、太陽であらんことを。 「次のフェーズへと進むための、軽やかなトランジション・・。 ごちゃごちゃに絡んだ――毛糸の玉ばかりだったなあ・・。 夜空に紛れ込んだ塵やガス――みたいだったなあ・・ 行き先も知らず流されている僕は・・ひょっとすると、もう魂で、 それは見知らぬ惑星へと続いているのかなあ・・ ねえ、この優しくて儚い音を、僕はただずっとその音を、 聴いていたいと願っただけ――。 この不思議を、まだ知らないくせに・・・・・・、 あんなに素敵にとろけそうな音することも、 知らないくせに・・。 クロノス的時間の拒否。時計が刻む量的時間ではなく、 カイロス的時間への希求。満ちた時間。意味のある瞬間。 、、、、、、 、、、、、、、、 未知への憧憬。プラトンのエロス。 、、、、、、、、、、、 欠けているものへの欲望。 見果てぬ青の彼方――このおおらかな空に、 ・・その手がないなら、僕がその手になるよ 僕が死んだら必ず、その空の雲や風に――。 なってみせるよ・・ クラウド ウィンド ダスト 雲、風、塵・・・。 この季節を歩き出したものの為に・・。 フ ロ ン テ ィ ア 宇宙の辺境へと・・。 そだてよう、清冽たる想いに口を塞ぎ、 その雨を呼び込む、森という名をしたポンプ。 そだてよう、石炭をシャベルで入れるように。 川の流れも、そして野花も、野鳥の声も、 ・・・その命の炎を委ね、そして燃やして。 いつのまにか僕のイメージから遠く離れてしまった 光が――またどんどん、遠ざかる・・。 二つの色がある、白と青、 それが寄り添えなかった季節に・・。 あなたが目印をした――喜び・・ (――この やわらかい 水色の風・・) あなたが――ふと・・見せてくれた、 情熱が――ありありと思い出せる・・。 、、、 ・・・・・・あなたにも。
2025年11月16日
-

イラスト詩「あの日の僕等」
この衝動は、誰にも止められない。それは、胸に、顔に、手の上に。すべては遺伝子の中に、前もって設定されている。錆びた鍵の匂いがスパークして、不可避の方程式が立ち上がる。そこに言葉はいらない。あるのは温度と重力と、抑えきれぬ引力だけだ。君は、廃ビルの裏手で僕の手を掴んだ。「こっちだよ」って笑いながら、錆びたフェンスを跳び越え、誰も知らない抜け道へと走り出す。衝動は体内の血管や骨格ではなく、もっと古い回路、祖先の記憶へと配線されていた。影が壁に貼り付き、闇に掻き消えるまで、時間の粒子はざらついていた。悪い人もいなかったし、両親を好きだった。ただいてもたってもいられなかったあの日の衝動は、田舎の人が、「東京に出たい、東京に行きさえすれば何とかなる」と思う気持ちと似ているだろうか? ノルアドレナリンとドーパミンの短絡。拳のようになって喉の奥から突き上げてくる、説明のつかない、強力な欲望の瘤が超高熱になる、君が言う、ジャニーズのメンバーの一人一人の、ルックスやパフォーマンスやキャラクターで、評価してファンになるべきところが、レギュラー番組が多いだとか、CD売上枚数が多いだとか皆に愛されてるとかで、他人が欲望する規模、いわば権威によって、応援するグループやメンバー、推しを決めてしまうんだって。評価基準が自分から他人に移動してるって、自分を権威化できるような自信や魅力がないから、権威あるジャニーズのグループに、寄りすがっているんだって。イライラしちゃってよ、心にダムはあるのかい、ゴースト・シティのヴィジョンを揺らめかせている。虫ケラみたいだ、ほんとに・・・・・・。怒りは、正当だと思う。だが、同時に、少し哀しい。何故なら、君も、結局、何かから逃げているだけかもしれない―――から・・。終わらない旅の始まりだったらいい、だけどきっとそれは衝動の浅墓さを告げることになる、でも前に進まないと停滞する、後ろに下がれば、今後笑うのさえ億劫だ。「行く」という一語に圧縮して、地図を破り捨てた。北側と南側に分断される。市役所、駅、学校、図書館深夜の自販機に灯る光のように、まだ見ぬ都市の輪郭を滑らかにする。人工的な光。文明の最後の砦。孤独の象徴。もっと根源的だ。場所の問題ではなく、存在の移動。自分の内側にある既成のスケールを剥ぎ取り、もう一度貼り直す行為だ。今まで、それらは、背景のノイズだった。意識することもない、環境音。だが、今、それらの音は、すべて、何か重要なメッセージを含んでいるように聞こえる。世界が、突然、意味を持ち始めた。それは、ゲシュタルト転換。ゲシュタルト・スイッチと呼ばれる現象に似ている。有名なルビンの壺。白い部分を見ると壺に見えるが、黒い部分を見ると向かい合った二つの顔に見える。同じ画像でも、見方を変えると、まったく違うものに見える。世界は、何も変わっていない。だが、僕の見方が変わった。そして、それによって、世界が、まったく違うものになった。「人は貧乏だとIQが下がる」という地獄みたいな研究結果が存在する。同一人物でも、お金がある時とない時で、IQテストの結果はかなり変わる。その影響はなんと一晩徹夜する以上のダメージ。脳は明日の支払いについて無意識に考えて、処理能力の一部が失われてしまう。貧困の罠。ポバティ・トラップ。獲物に飛びかかる飢えた狼のような衝動なんて、感じるべくもない。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。宗教も同じ類いだっていう。怖いよ。貯えがあっても、またその貯えがもっと多かったらって。ないものねだり、かくのごとくに先から先へと考えて、自分を停止させる、ボタンの誕生だ。コズミック・スケールの、スペシャリティ。君の指先は、僕の心の導火線に火を点けた。それは、静かな爆発だった。鼓膜の奥で、世界が反転する音がした。今まで抑えに抑えてきた自分自身にさえ、訳のわからない烈しい力が、火山の爆発のように噴き上げてくる。臨界点を超えたんだ。マグマの圧力が、周囲の岩石の強度を上回る。亀裂が入る。マグマが、一気に地表へと噴き出す。噴火。溶岩流、火山灰、火砕流、火山ガス。破壊的なエネルギーの解放。僕の中で、今、それが起こっている。白いライトが無表情に僕等を案内し、パンフレットの折り目のような人生を折り畳む。旅行パンフレット、大学のパンフレット、企業のパンフレット。この順番で見てください、という誘導。人生も、同じ。幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、就職、結婚、出産、退職、老後、折り目がついている。交差点の監視カメラも、校長の説教も、親の期待も、全部、ノイズに過ぎない。この衝動だけが、僕等の答えだ。教室の窓から見える風景よりも、歴史の年表よりも、君の笑い声のほうが、ずっと本物だった。僕等は、大人たちのつまらない常識を廃棄処分場に投げ捨てて、二人だけの地図を描き始める。暗闇の中から迫る足音、響く声。何かに追い掛けられるんだ。ネオン、街灯、ビルの窓明かり、車のヘッドライト。住宅展示場が垣間見せた、自分達を規定する類の狭い世界の案内径路。今すぐ電車出せyo。出来ねーならタクシー代寄越せya。ラッパ―みたいに言えばいいのに、アッパーカットしたい奴等。ふと立ち止まって小銭入れを覗く。財布の中の硬貨の音が現実の重さを思い出させるけど、その音さえも、出発のための足場に変わる。ミッドナイトのノイズ・フロアの中に、完全にフェイドアウトしてゆく。この衝動だけがリアルだ。夜の高速道路を抜け、廃墟になった遊園地を通り過ぎ、国境のフェンスを越えて、君と逃げてみせる。『AKIRA』や『鉄コン筋クリート』のような、ディストピア的ロマンティシズム。暗黒郷。理想郷の反対。管理社会、監視社会、格差社会、環境破壊。様々な形のディストピアがある。だが、そのディストピアの中でこそ、人間の本質が現れる。絶望の中での希望。破壊の中での創造。孤独の中での絆。それが、ディストピア的ロマンティシズム。僕等も、今、そのような世界にいる。完璧ではない世界。問題だらけの世界。だが、だからこそ、僕等の衝動が、意味を持つ。誰にも僕等の邪魔をさせない。都市の裏側に潜む、見えない地下水脈のように、僕等の中を流れ続ける、この衝動だけが、僕等のすべてだ。偉そうにXやSNSを開き、文句を垂れ流し、ちっぽけな優越感と自尊心を得る。政治家が悪い。社会が悪い。あの有名人が悪い。そうやって、他人のせいにする。そして、一時的に、気分が良くなる。「自分は、あいつらよりはマシだ」ちっぽけな優越感。だが、それは、本当の解決じゃない。日々、仕事でノルマ未達を糾弾され、罵倒され、搾取され続けている人間達は、自分が受けた仕打ちを発散しようと、精神分析でいう置き換えという防衛機制を無意識に行う。何かって? 八つ当たりだ。権威に従う必要はない。常識に従う必要はない。自分の感覚を信じる。イタリア人の中でも芯を残さないベンコッティや、さらにふにゃふにゃになるまで茹でたモッリを好む者もいる。馬鹿みたいだっていいんだ。アイデンティティは、周囲の環境によって決定される。親の期待、学校の規範、社会の常識。それらが、見えない定規となって、僕等を測る。そして、僕等は、その定規に合わせて、自分を切り取る。だが、もし、その定規を捨てたら?もし、まったく新しい定規を持ってきたら?そういう「もしも」が、行動を止める。考えてみれば、その「もしも」は、永遠に来ないから。どれだけお金があっても、時間があっても、才能があっても、また新しい「もしも」が生まれるなら、欲望の無限後退。インフィニット・リグレス。だから、スタートは、切れない。永遠に、準備中。約八〇億人の中の一人なんだ。約一億二〇〇〇万人の中の一人なんだ。この街の人口、約八〇万人の中の一人。あの日のライト・スケープを、トランスファーする。世界の果てまで、君と逃げてみせる。パスポートも、許可証も、GPSも、必要ない。必要なのは、君の手の温度と、僕等の心臓の鼓動だけ。その手が、僕の手を握る。接触。皮膚と皮膚。体温の交換。皮膚には、機械受容器と呼ばれる触覚センサー。メルケル細胞、マイスナー小体、パチニ小体、ルフィニ終末。それぞれが、異なる種類の触覚情報を検出する。圧力、振動、伸展。その情報は、末梢神経を通って、脊髄へ。そして、視床を経由して、大脳皮質の体性感覚野へ。誰にも邪魔をさせない。誰も、この衝動を止められない。世界の果てまで続く逃避行の設計図なんかなくても、君のリュックには、マクドナルドの冷たいハンバーガーと、ふやけたポテトが入っているような、白紙の地図。そこには、まだ、何も描かれていない。道も、建物も、地名も、何もない。だが、それでいい。僕等が、これから、描いていく。君と僕で、二人で、線を引いていく。ここは、僕等の好きな場所。ここは、僕等の秘密の場所。ここは、僕等が行きたい場所。そうやって、少しずつ、地図を埋めていく。その地図は、他の誰のものでもない。僕等だけのもの。たとえこれからどうしようかってなっても、二人でいればきっと、この人生のリセットボタンを押せるって、何故だろう、信じられた。成功したのか、失敗したのか、幸せになったのか、後悔したのか、全部、宙吊りのまま。あの日、確かに僕等は走り出した。お金がなければ、歩けばいい。距離なんて関係ない。足さえあれば、何処まででも行ける。
2025年11月16日
-

6
夜に 僕の声は消えてゆく、夜に。ピアノ開け鍵盤カバーは畳むみたいに、車の音は優しい、イルミネーションは、その尻尾から僕を透明にする。[整 え る 動 作] の よ う に 、〚缶 珈 琲 ]を 開 け れ ば 、静 か で 精 密 な [ 儀 式 ]が 、夜 を 〚 支 配 〛 す る 。またすぐに会えるけど、あともうちょっと、いまのこのまま。木/苺/の/甘/い/夢橋の下に暗く澄んでいる水面を覗き、鳩に何故か頭に乗られて。ミッドナイトのアトモスフィアに融け、アブソープション・・・。“宝石は青かった”(雨の日の次が晴れと決まっていないように、)(三百六十五日、何億何千万人が織り成す奇跡、)『扉』ハ開クカラ・・・・・・。思い出の日を語る、睫毛の中に引き渡して、白く見える、そよ風。>>>遥か遠くのレディオ・ウェイヴのように。>>>世界がまだセーフティ・モードであるように。+希っていた?+希っている・・。君の声には魔法があるよ、夜に。装飾的なつくりが一瞬、あの夏の眩暈するような陽射しや、春の桜が咲く並木道を思い出させ、る。[無 関 心 な ノ イ ズ ] み た い な 、〚卒 業 後 ]を 話 せ な い で い る 、排 気 ガ ス と 雨 水 が 混 ざ っ た [ 水 面 ]が 、夜 を 〚 鏡 像 反 転 〛 す る 。小さな手に触れ、無邪気な笑顔を見て、あともうちょっと、いまのこのまま。木/苺/の/甘/い/夢逃した鳥の名を憶えておこう、いつかその空気は恋人の肌のように匂う。アワー・ゾーンは、ミッドナイト・パスト・トゥエンティ・ミニッツ。“小さな町の窓を開ける”(雪が消えてく公園のベンチで、胸が忙しい)(心の真ん中にある切なさと愛しさと嘘つきな「好き」)『扉』ハ開クカラ・・・・・・。左手でペンを握る君を見て、不意に振り返って視線が合って、気持ちが分からなくなる、貝殻の内側。>>>このカレント・モーメント―――を・・。>>>このタイムラインのイナーシャをキープして・・。+希っていた?+希っている・・。冬が終わればこの想いも終わると知る、夜に。
2025年11月16日
-

5
パワハラなんだよ、俺がな。説教に相手を、思い遣れる奴なんて、いねえんだよ、机蹴って、肩をこづいて、無能、辞めろって言ってやるんだよ、今朝から痔なんだよ、痔パワハラ、うりぃぃぃぃ!POINT1「優越的な関係を背景とした言動」POINT2「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」POINT3「労働者の就業環境を害するもの」まさか痔だったんっすか、パワハラって、悲しいっすね、切ないっすね、早く死ねばいっすね、でも録音して、証言資料まとめて、さっき、社長に、サンタクロース、しときました、メリークリスマス、パワハラの、痔野郎くん、あと、社長が後で来いって、仰っておりましたよ、何か?POINT4「うつ病、退職、自己肯定感の低下」POINT5「職場秩序の乱れ、人材流出、訴訟リスク」POINT6「二〇二〇年以降、すべての事業主にパワハラ防止措置の義務化」
2025年11月16日
-

4 *これからの写真詩の新しいスタイル、写真と詩は別物
風鈴ってボーンって鳴る風鈴ってボーンって鳴るやないですかー。除夜の鐘ちゃうけど、何言ってんのこいつって思った?まじさいこうだよね~wwwうち、ソフトボールの体育の時間やった、ボールを投げようとしたら、ほしたら―――風鈴やってん。嘘ちゃう嘘ちゃう、ほんまやからほんまやから。梅干しみたいに、ガッっていきたい、形ですねー、ふふふ( *´艸`)やめてよやめてよ、食べられたくない―――猟奇的趣味。世紀末のギロチンショー、そして煮え立つ蝉しぐれ、夏ですねー、夏でありまんがな。そんなきつい関西弁もうないやろ。あの、一人ボケツッコミ、風鈴って風林火山じゃないですかー。ちりんちりんって鳴ってるんですよー、あはは、あはは―――あぁアァあぁアァ・・。知らんがな、知らんがな、―――退屈だなー、アヒャ(*´Д`)でも小耳に挟んだですよね、近頃風鈴さんが、おにぎりに握られてしまうって、ね。嘘ちゃう嘘ちゃう、ほんまやからほんまやから。
2025年11月16日
-

3
踊り場踊り場の隅に溜まった埃でも見ながら、サイコロの振られるような、昼下がり。大人への一歩を踏み出すか、そして僕の青春は散らないで腐って―――ゆく・・。眩しさを受け止めながら少しずつ、選択肢の数と迷いは比例して、画面に重なる。鼻の奥に淡い発揮性の匂いがある、それが空洞の冷たさかも知れないと、気付いていたりも―――する・・。胃カメラを通す時に口を開けて悶絶するけど、自分が影でも風でもないと気付く、旗か帆か、気長に待って―――いてよ・・。公園の老いたスプリング木馬が、光の迷子だ。カッターシャツをはためかせつつ、階段を降りて来る君は部活、フィーリング次第だね、世界に麗らかにドレミファソラシドが鳴るかは。白い想念がダンスする、太陽の光が優しく包んでくれる、僕にはまだ馴染むことのない大きな世界が・・・・・・。
2025年11月15日
-

2
年上の彼終わってく一瞬だって、知ってた。とても小さな莟が、硝子の向こう側が、見えていたようなあの冬の、イメージが、暗室で変質してゆく。汚れた建物と建物の間に、押しつぶされそうになりながら、喪服をまとう空と、 棺のような真空の胸。どっちみち、 思い出のアルバムの中には、 もうはめられない。コンビニの商品補充みたいに、新しい世界に君もわたしもいらない。救助信号も届かない、ボートの上にわたしはひとり。祈りを忘れた、 現在地で、 雪が舞い降りていく、 わたしは白い息で、 それを無機的に眺める、 石の瞳で。誰かの背中を眺めたくない、自分自身の背中だって、眺められないのに。自分の歴史や存在意義をたどる、織物があるとしたら、まわりのあらゆる形や、変化そのものだろう。でも迷路のような通路が続く、次々と変化しながら、別の部屋へ、別の扉へと連鎖し、接続し、全体で境界のないひとつの大きな世界だけど、最初にやって来た扉は、もう開かない。「離れていても平気」と笑っていた顔に、声に、言葉に、今は惑わされる、愛しくて、切なくて。一瞬、 君の顔が浮かんだら、 わたしは、 もう少しだけ、 夢にいたかったと、 手袋を忘れた、 かじかんだ指の痛みが、 小指のそれと似ていて。背伸びしても、お洒落しても、あなたの歳になっても、お酒の飲み方を覚えても、もう、絶対に追い付けない、あなたはわたしの特別で、あなたはわたしの一生でただひとり。変わらないものを探して、 形あるものや、 壊れやすいものを、 求めて。振り返ると、 白い道に残った足跡が、 時を超えて、 何十億年もの先にも、 同じ光景が拡がっているような、 そんな気がして、 笑って、泣いた。夜空のほのかに明るい一点を眺めていると、知らず知らず月を眺めている、わたしはいます、あなたの心の中にいまでもあります。瞳を閉じてしまいたい、できるならもう全部忘れて、わたしの名前を呼んだ、あなたの肩に寄り掛かりたい、でもそれは、冒涜だと、誰よりもあなたが嫌うことだと、気付いて眼を開ける。「忘れていいよ」と君がふざけて言った言葉に傷ついたあの日、でも知っていたんじゃないか、人の心の移り変わり易さを。始まらない一瞬より、変わってしまう自分を、怖がっていた、あなたが本当に好きだったから。
2025年11月15日
-

文明社会の最後の野生
ちょうど人を磔にするのによさそうな場所がある、深夜の橋の上。左右の縦の柱から、じゃらっと鎖を伸ばし、両腕の手首をつなぎ。徐々に、下へ降ろしていく。もちろん、うちの監修任せてるスタッフは馬鹿じゃないよ、大学で博士号とってる、降下速度は、群衆の生体反応データ(心拍数や瞳孔散大度)を、リアルタイムでフィードバックし、最適な恐怖の曲線を描くように調整されている。小柄で、負けた犬みたいなおどおどとした眼つきをしてるね、過去を、すっかりカモフラージュして、そいでギラギラと輝やかしながら眼の前の暗闇の中に浮き出す。夜。感情のない群衆が見ていて、テレビカメラが無感情な昆虫の複眼のように覗き込んでいる。あらゆる通信、交通機関の横溢している今の世の中の、しかも眼と鼻の間とも言うべき場所に、永劫の戦慄、恐怖の無間地獄への扉が豁然と開けている。システムのバグを放置しておくことなど、出来ない。咽喉の奥に引っ掛かった魚の骨は抜かずにはいられない、さ。コロシアムの殺戮ショー、パリの死体安置所の見世物という、そういう真実性を厘毫も疑っていない輩は、わんさか、いる。 、、、酔いざめのくさめをしようじゃないか。「皆様、こいつは人を殺したんです。つまり仇討ちだ。いま、モニターを眺めている彼の仇討ちだ。私達はその舞台を用意した、そして私達はそれゆえ、それを眺める義務がある」うすっぺらい奴等は本当に信じているのかも知れない。殺人者という虚像に上書きされ、真実が完全に消滅してしまう。きれいごとや、婉曲語法が何故なくならないのかと同じさ、チャンスを与えている? 裁量を考えている?違うね、人は知らず知らずのうちにリスクを回避しているのさ、責任を取るのが嫌なんだよ。ともあれそうした善意に見せかけた嘘八百の幸福感は、音楽で演出する、何事も儀式や建前が必要だ。でもそんなの、ほんの束の間の夢。一身に絡まる怪奇な因縁は、中々それぐらいのことでおしまいにはならない。周囲を渦巻きめぐっているであろう、幾多の現実的な危険さに対する常識を喚起よびおこして、尖鋭な同情の断面を作って働きかけ―――る・・。蛇の群れを孕んで産み落とす―――、メドゥーサの眼の中で・・・。「もうかれこれ、仇討ちも九九九回を迎え、ついに一千回目、それを記念して今回はこれを用意しました」そんで、足元にはプール、毒液のように苦々しく澄み渡った水面。そこへ活きのいい、牙がつやつやした、ホオジロザメを放流しておく。ホオジロザメって聞くとジョーズ思い出したり、孤高の一匹狼みたいなイメージがあるけど、実は人間と仲良くなるケースもある。この場合は、そうでもないけどね。トムって、さっき名付けた名前を連呼すると、最高のフレイヴァーになる。ちょっと飯を与えてないけど、虐待じゃないからね。そんな脳髄から蒸発してしまった過去の記憶は、もうとっくにシリウス星座あたりへ逃げ去って―――るさ・・。、、、にやり、とする。苦しんで、苦しんで、苦しみ抜いて死んで行くところを静かに眺めたいのだ。そうして勝利の快感を味わいたいのだ。椅子取りゲーム、高等国民気取りで。骸骨みたいな顔が、生汗をポタポタと滴らしながらの、サディスティック・ラブ。歯が何回も生え変わるって知っているかい?嗅覚が非常に鋭く、わずかな血の匂いにも反応するって知ってるかい?看破するや否や、一種の猟奇趣味の満足。銃声がして、叫び声がする。家族の名前、昔飼っていたペットを叫んだかも知れない、システムのパスワード、さ。頭の中でピチンと何か割れた音。足に銃弾があたりその血がポトポトと流れていく。もちろんコトコト煮込んだポトフさ、最高のメインディッシュはこれから、拳銃なんていうヤクザやマフィアや反社でもやりそうなことは、野暮だ、殺したいならコンクリ詰め、街の隅の変わり果てた、山奥に埋めて土砂崩れと共に発見、それでいいはずだ、けど、ショーじゃない、そこに美学はない。空想を縦しいままにした、まわりくどい欺瞞、さ。“強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く、抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。”なんて文章があるね、これが法律制度の限界さ。長ったらしい文章が指し示すのはおそろしく無駄な時間だ、国家という強力な存在感があっても、たった一人の犯罪者のこめかみに、銃弾をめりこませることが出来ない。遺族は地獄さ。転輾し、呻吟し、発狂しかける。神も仏もいないのか、世紀末なのか。―――ひどい話だけど、そのまま眠らなければいけない、飯だって食わなければいい、そんなごちゃごちゃ抜かすならさっさと死ねばいい、一分一秒まで、世界には様々な見方が溢れている。群衆に「自分たちは正しいことをしている」と、再教育するためのプロパガンダ素材にはならないな。人を洗脳するには自分がどちら側につくべきかを、骨の髄まで徹底的に教え込まなくてはいけない。スポンサーが本当は何処の国なのか知ったら、国家転覆罪さえ成立してしまう。正義は法律ではないことを伝える時のように、もうフェイクニュースの時代じゃない、―――恐怖。“おまえらの文明が生んだ儀式”じわじわと万力で締め上げて、人が心底血の気が引いた時の表情をカメラは撮影する。不安は水の中のボールのように、何度も何度も浮かび上がって来るに違いない、何度も何度も飛び出して来ようとするに違いない。様々の毒々しい色をした劇しい臭気を発する、毛虫いも虫の奇怪な形。共感能力を失った社会の病理さ。それが絵であろうと、実物であろうと見境は無い。『記号』というもの。嘲る心が仮面の中で舌を出す、寛解と完治のあわい。白い眼を少しばかり見開いたと思うと、ガックリと仰向く。で? ゆっくりと下ろしていく、薄ぎたなくよごれた顔を充血させ、歯をを食いしばって、妄言だ。鼻梁の左右からぼろぼろ涙がこぼれ落ちてゆく。ビー玉数百個をいれたビニール袋の下部に、小さな亀裂を入れたようにね。そうしていると不思議だけど、煙が波とすれずれになびくように、そら、、、、へさきが見えて来たぜ。黒い液体をドクドクと吐き出しているそれ目掛けて、イルカショーだけじゃない、無慈悲なシステムの最終的な裁き、ジャンピング・ホオジロザメと遭遇したり―――する・・。人が死にます、そして死にたがりの人が食い入るように見つめて生きます、生きたがりの人も食い入るように見つめて生きます、―――そんな世界の掟。羊飼いの少年ダヴィデと巨人兵士ゴリアテの闘い?だとすれば、これは祝祭の処刑台。人間性への最後の執着を賭けてね。世界で何千年もかけて、残酷さも飼い慣らしたのさ。悪魔の舌は悪魔の食物でなければ満足は出来ないと知りながら、それでも人は痛みをまだ必要とする、わからないんだ、他人が痛いということを実感できないから。人に救いを求めることすらし得ないほど恐ろしいことがまくし上がって、人は初めて無能さを思い知る、他人への宗教を始められ―――る・・。野生、本能、支配・・・・・・。環状脳、集合知、生理的反応の共鳴・・・・・・。一方的で、そら、歯茎の薔薇色に混じってヘモグロビンが、血腥い、異様に不可解な犯罪事件を揉み消してゆく。深淵と、急潭の千変万化を極めた、ニュース原稿にしよう、裁判記録風にしよう、あるいは広告コピーにしよう、すればするほど、ディストピア的な社会の牙が見えて来る。“文明社会の最後の野生”だ・・・。
2025年11月15日
-
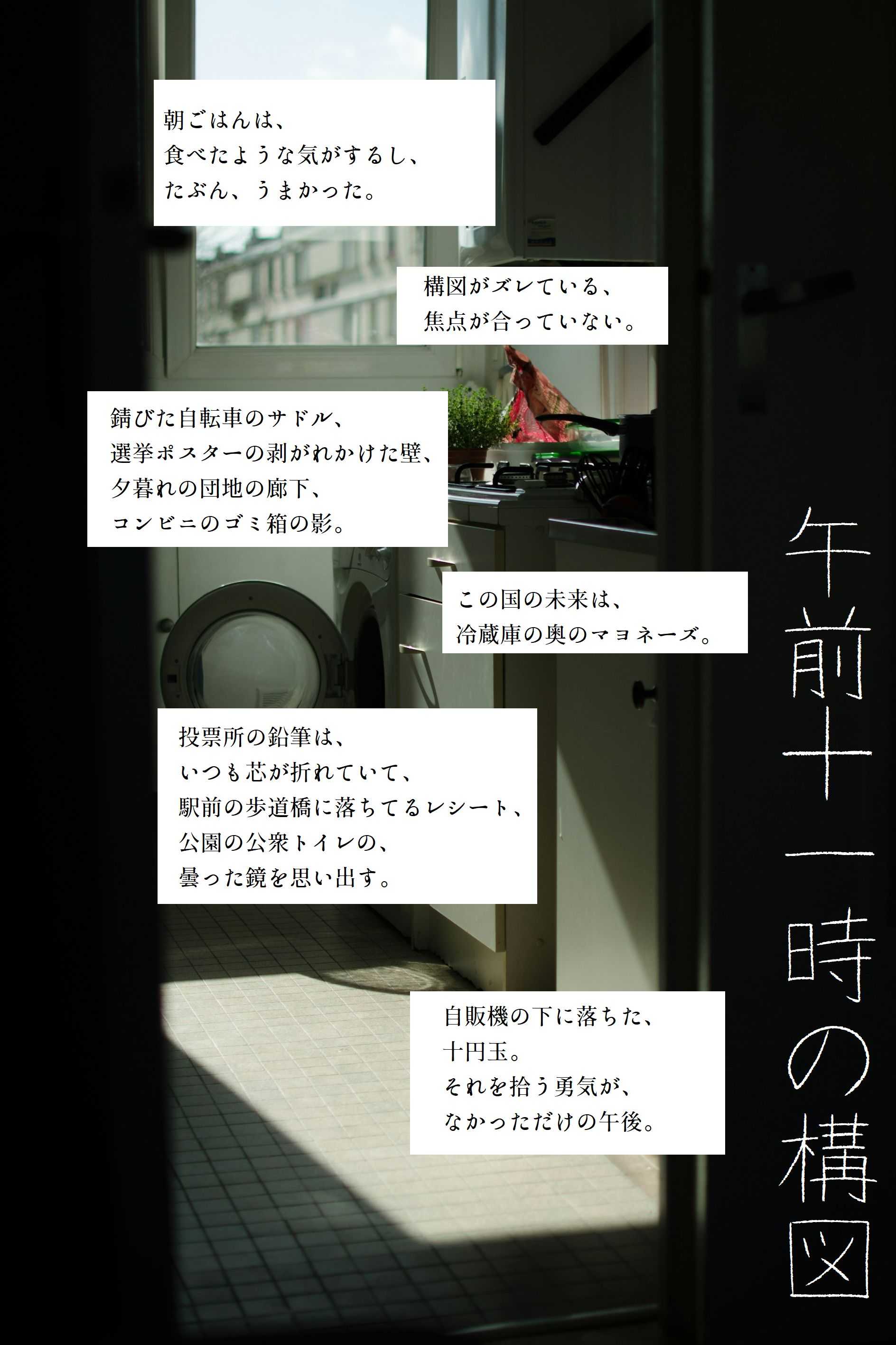
1
午前十一時の構図朝ごはんは、食べたような気がするし、 たぶん、うまかった。構図がズレている、焦点が合っていない。錆びた自転車のサドル、選挙ポスターの剥がれかけた壁、夕暮れの団地の廊下、コンビニのゴミ箱の影。この国の未来は、冷蔵庫の奥のマヨネーズ。投票所の鉛筆は、いつも芯が折れていて、駅前の歩道橋に落ちてるレシート、公園の公衆トイレの、曇った鏡を思い出す。自販機の下に落ちた、十円玉。それを拾う勇気が、なかっただけの午後。
2025年11月15日
全9531件 (9531件中 1-50件目)
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 『 REAL 15 』 井上雄彦
- (2025-11-24 15:48:35)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0943 キーエンス 最強の働き…
- (2025-11-29 00:00:12)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- ガールクラッシュ 4巻 読了
- (2025-11-29 07:10:34)
-