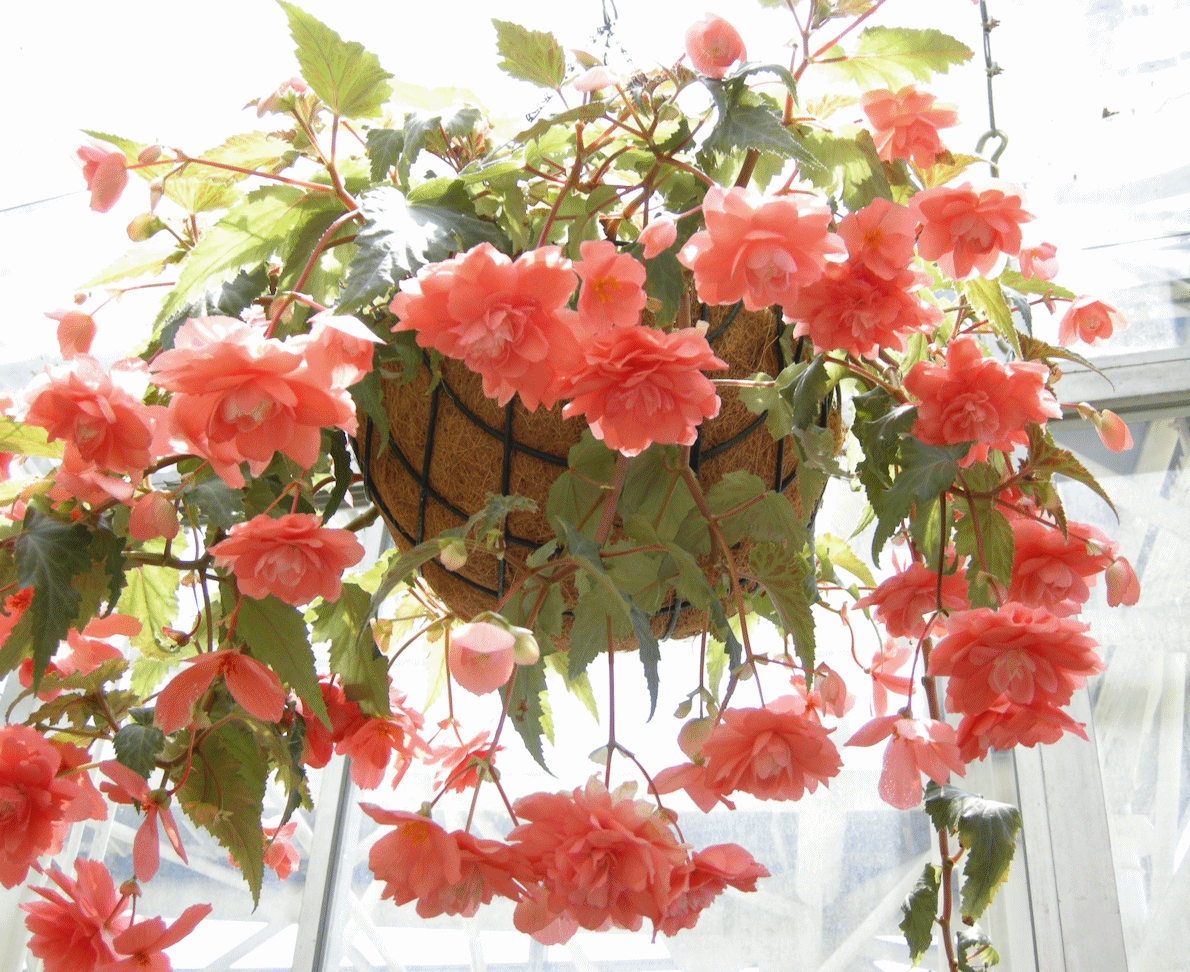-
1

懐紙とかいしきの違い
和菓子をのせている和紙には大きく分けて2種類ある。懐紙(かいし)と掻敷(かいしき)。響きは似ていますが、使い方には違いがあるそうです。昨日のブログで懐紙のことを書きましたが、懐紙は、文字通り懐にしのばせておく紙という意味です。茶道に使われるものというイメージが強いかもしれませんが、ハンカチ、ティッシュ、メモ帳代わりなど、その用途はとても幅広いものなのです。時代劇でもよく見ると着物の襟元に懐紙がはさんであることが多く、懐紙を持つことがたしなみだったことがうかがえます。掻敷は、料理の下に敷くものです。和紙だけでなく、料理を乗せる葉っぱなども掻敷と呼ばれ、一般的には「かいしき」とひらがなで表記されます。天ぷらなどの揚げ物には、よく奉書紙などの紙掻敷が使われます。古くから伝わる風習には、ルールがあるものです。間違った使い方をしてしまうと、せっかくのおもてなしが台無しになってしまいます。和紙に和菓子をのせれば上品に仕上がる、と思いがちですがこれだけではNGです。かいしきには、「吉のかいしき」「凶のかいしき」があります。吉のかいしきは、普段使いや、お祝いのときに、凶のかいしきは、お葬式などで使われるものと区別する必要があります。折り方の違いがあるようです。折り方については詳しい説明がありましたので、興味のある方はご覧ください。かいしき可愛い形のものがありますね。お料理は、目で楽しむもの。懐石料理など、季節によって紅葉が添えてあったり、桜が添えてあったり。日本人の繊細な心使いですね。器もそうですが、こんなかいせきで、季節感を演出してもお洒落ですね。山根式折形 皆敷かいしき 四方紅六寸・二十枚入り 折り形図形入り・肌吉紙使用 【ゆうパケット対応】『てまひま工房 Naturalist もみじ ウッドペーパー 5枚セット 79399』【かいしき ティータイム パーティー ウッド ペーパー テーブル 雑貨 日本製 ヤマコー】【ゆうパケット対応】『てまひま工房 Naturalist さくら ウッドペーパー 5枚セット 79401』【かいしき ティータイム パーティー ウッド ペーパー テーブル 雑貨 日本製 ヤマコー】
2023.02.23
閲覧総数 342
-
2

リサイクル着物のサイズ
リサイクル着物は裄65までなら山ほど出ています。丁度自分達の母のサイズ。身体150センチ代の方でしたら、アンティーク着物も着られ質の良い昔の着物も合うと思います自分は身長は160ですが、一般的な仕立てでは身丈165でもおはしょりはちょっとしかとれない。裄68のトールサイズを探しているので、なかなか巡り合えない。一般的に身体プラス、マイナス5センチなら着付けで何とかなると言われていますが、腰高さん鳩胸さんは生地を沢山必要とするので身体プラス5〜10センチと考えた方が良いと思います。裄のお直し丈のお直し等に出すと、それぞれ1万円はかかります。柄の気に入った物質の良い物ならそれでも買いかなと思いますが。帯も昔の物は短い物もあります。充分吟味して購入して下さいね。
2023.06.19
閲覧総数 120