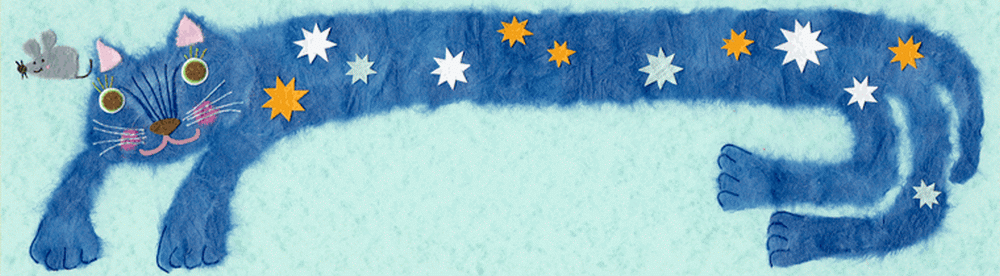PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
コメント新着
カテゴリ: カテゴリ未分類
どもども^^
最近は更新が2週間ぐらいおきになっているね。
日記をコマめに覗いている方々には本当に申し訳ないm(_ _)m
さて、試験もほとんど終わったのでほんと一息ついている
今日この頃です。
順調なら28単位くらいはとれるはず!
これでまた留年ということにはならなそう(笑)
さて、今日の文は申し訳ないことに
つらつらと長くなっちゃいました^^;
思わずだらだらだらだらしてしまったもので。。
(一時は迷惑だから消そうと思ったぐらい。。)
暇な人だけどーぞ^^;
==========================
それにしてもテスト勉強とレポートしてて思ったのですが
インターンやって物事の処理が
むちゃくちゃ早くなったような気がします。
よく大学人の方々で「インターンは学業の邪魔になる!」と
おっしゃる人は少なくないですが、
僕は時にはインターンやるとかえって勉強の仕方を覚えるので
非常にためになると体験者と思いました。
どちらも論理的な正しさが問われている。
つまり、同じような能力が必要だと思うんだよね。
実際にこの前授業でプレゼンがあったんだけど
「思った以上によく調べており、まとまったいいプレゼンだった。
正直驚いた。」
といってもこのときは調べるのもまとめるのも
そこまで時間はかけていない。多分合わせて2,3時間程度。
つまりそこまで情報は集めてない。
このことから考えると、ひょっとして
学問は知識量だけじゃなくて、どういう『考え方』でやるかも
同じ位重要なのではないかと最近思っています。
『考え方』の訓練。読んだ本や聞いた授業から
そこからどのようなポイントが重要なのかを見抜き、
どのような法則があると組み立てるか。
もしくは自分の主張を裏付けるにはどういった情報が
必要だと考え、行動するか。などなど。
個人的には多分こういうのが相当重要では?と思うんだよね。
この『考え方』を教える授業を
大学でもっと増やした方がいいんじゃないかなぁと最近思います。
そしたら知識は利用するだけになるしね。
仮説思考、多面的思考、批判的思考、構造化思考。
すべて学問に応用すると相当有効だと思うんだけどなぁ。
あと、そもそも半分の先生方のプレゼン力はあんまし高くないから
本でなくわざわざ口頭で知識を伝えることが
効果があるとは必ずしも思えない気が最近する。
それだったら、誰かが先生の授業を聞いて
要約してわかりやすくパフォーマンス付けた方が
いいんじゃないかと思うときもある。
初心者用には授業を噛み砕くことが有効では。
だから、よく授業聞いてわかんなくても
友達に聞いたらわかるということがよくおきる。
教授よりも友達の方がけっこう説明できるということ。
もう一つ。教授に質問しやすくない雰囲気があることも
友達>教授になる要因の一つではないかと思う。
ただ、これは大学だけじゃないかな。高校も中学も小学校も。
なんで学校の先生じゃなくて、友達や塾の先生や家庭教師に頼るんだろう。
気持ちはわかるけど物凄く勿体無いような。。
そもそも講義授業を受ける必要はないと思うけど
といっても多分、今の日本の大学のルールだと時間数で
単位分の勉強を計っているから、
授業は当分は先生の『口頭講義』のままなんだろうな。
文科省が易々とそこにメス入れれる気がしない。
でも、そもそも、結果でなくて時間数で計るのは
理に適っていないと思う。アメリカは合理的だから結果で計るので
短期間で大学院の学位が与えられたりもする。
お互いの時間を有効利用する意味でも有効だと思う。
もちろん「授業で座ってしっかり聞く」
というのは、本を読むより耳で聞いたほうが理解できるタイプの人は
3分の1位いることがNLP理論で証明されてるから
まるっきり授業をなくさなくてもいいんだけど、
でも「本派」の人のことも考えてもいいんじゃないかなぁ。
プレゼンと一緒。正確さよりも明確さ。
細かい定義は大筋のポイントを抑えないと
覚えられないし、重要性がわからないはず。
加えて言えば、変な言葉をさも当たり前に使うのはやめて欲しいと
最近感じている。
例えば「相対化」とか「可逆性」とか。
確かにそういう言葉を覚えないと学問の共通語知らないから
日本の中でも海外でも深く学問できなくなるけど
あまりにそういう言葉使いすぎると
ご老人にパソコン教えるのに「ダブルクリック」って
言って混乱させているようなものでは。
むしろ学問の敷居を高くしすぎている気がする。
あとこんなことも時々思ったりする。
この教授は言葉に酔っているのでは、と思うとき。
この前、
「この論文はまるでかのギリシア神話の~~のように・・のアンチテーゼ
としてうんぬんかんぬん」
という文を見たけど、この文に価値があるととても思えない。
本人の自己満足では。
この教授は怖がりなんじゃないか、と思うとき、
「必ずしもこの文は・・の主張を否定はできないが
ある種の可能性として~~について主張できるかもしれないと思う」
とかいう文を見たりするけど、非常にわかりにくい。
正確に伝えたいのはわかる。批判されるからね。
でも学問なんて批判されてナンボだろ。
何だって問題点叩いてつぶすことで完成度が増すわけだし。
そんなん社会人として怖がりに見える。あるいはプライドが高く見える。
せめて場合分けと確率と条件で示して欲しいけどお願いできないかな。
そしたら情報処理できる。
(ex.~のケースの場合、約70%で当たっているはず。
・・・が立証できることが条件、とか)
他にも改善できると思うところはまだまだあるけど、
総括すると、今の教育、特に大学教育は
「コミュニケーション力」不足だと個人的には思う。
学問にはコミュニケーション力はあまり問われなくても
教育にはコミュニケーション力は非常に問われると思う。
僕は教育にはキャリア教育も足りないし、
社会教育や実践教育も足りないと思うけど、
そもそも知識伝えるのにも「コミュニケーション力」が
不足していると思う。
もっともっともっともっともっともっと
わかる授業はできるような気がする。
大学は本当に「知の宝庫」だと思うけど、
だからいい授業できるわけではないのが残念だと思う。
名プレイヤー名監督にあらずと言われているように、
名教授は名教育者じゃないしなぁ。
=========================
・・・とまあ、つらつらとしてしまったわけですよ。
ときどきこういう風にだらだらした長文になって
結局削除、っていうことがあるんだけどね^^;
でも話の続きじゃないけど、教授方が悪いわけでは
全然ないとも僕は思っているんですよ。
教授方も授業をやるためだけに教授やってるわけじゃないし
そもそも大学に行く学生が昔の数%とかから
今は40%になったから、学生のやる気もレベルも落ちてるしね。
他にも個人的には、ITがいろんな面で発達して
娯楽もいろんな面で発達たから
先生方の授業が、TVとか巷の情報に対して
遥かに「つまらなく」見えてしまうのが、すごく重要な変化だと思っている。
昔のTVや漫画が下手だなぁ、面白くないなぁと
思うでしょ。それと同じ。トレンドもあるけど、
何より「伝えること」「見せ方」が飛躍的に変化したし、発達したのは
すごく大きな変化だと思う。
だから今の大学教育の問題は、
時代の変化により、求められる教育が本当にいろんな意味で
変わってしまっているからだと思う。
それは教授の先生方のせいじゃない。
でも、それでも大学教育はよくしていかなきゃ
いけないと絶対思うけどね。
自分は教育は5つのためにやっていると思う。
一つは教育を受ける「本人」のため
二つは「国」のため。国の平和や繁栄は人で決まる
三つは「国際社会」のため。今後グローバリゼーションは
ITの発達のため更に加速。相互依存が高まる。
四つは「本人の子供」のため。直接影響受ける。
そして五つは「本人の孫」のため。
間接的に影響受けるが、それだけでないと思っている
社会階級は実は再生産されている。格差社会が広がる今後、
今の教育が以後の子孫の階級を決める可能性が高い。しかも今後
高齢化社会になる。今の日本政府の動向を見ると、対策しない/できない
可能性が高い。だから社会保障は家族的なつながりがより重要になる。
家の力の差が、人の選択肢に差を産む可能性がより高まると見ている。
国の歴史のどの場面でも教育は重要だと思うけど、
より社会が今後まずます複雑で独自の判断が求められるようになるので、
過去よりも今、今よりも未来、に教育の責任がより高まっていると思う。
今の教育改革が改革でなくなる時代が来ると思う。
それは生ぬるいっていう意味で。
今の程度の変化はむしろ当たり前で、
常に教育は改善され、進化しないとそろそろ間に合わなくなる。
TOYOTAじゃないけど常に「改善」するようでないと。
そしたらお受験とか偏差値とか言ってられなくなる。
メディアは東大とか受験戦争とか昔の時代の見方で今を捉えつつ
ゆとり教育批判とか最近のトピックに現象しか
追えてないけど、根本を見たり、先を見据えないと
時代が求める変化のブレーキになってしまう。
(話の本筋と関係ないけど、政治と教育とメディア。
日本では既存権力ほど変化がのろいと思う。
影響力がでかいんだから責任重大なのに)
でも大学教育の場合、教育の変化は求められても
学部や学科を常に変えるのはまずくなる。
それは現在教育と表裏一体になっている研究は
長期的に取り組んで成果が出る性格があるので、
教育のために教授や研究体制をコロコロ変えることはできない。
となると、答えは教育者と研究者を一部切り離すか、
教育も研究もどちらもがんばるかことが必要だと思う。
アメリカは両方とも実行されている。
このままだと筆が止まらん。。。
とにかく教育は変化が早く求められるのではと
最近思っているんだよね。根本的なのを。
大学教育だけじゃなくて全部。
それを政府がやるかだけど、うーん。悩ましい。
。。。最近は教育について考えすぎなようです。
最近は更新が2週間ぐらいおきになっているね。
日記をコマめに覗いている方々には本当に申し訳ないm(_ _)m
さて、試験もほとんど終わったのでほんと一息ついている
今日この頃です。
順調なら28単位くらいはとれるはず!
これでまた留年ということにはならなそう(笑)
さて、今日の文は申し訳ないことに
つらつらと長くなっちゃいました^^;
思わずだらだらだらだらしてしまったもので。。
(一時は迷惑だから消そうと思ったぐらい。。)
暇な人だけどーぞ^^;
==========================
それにしてもテスト勉強とレポートしてて思ったのですが
インターンやって物事の処理が
むちゃくちゃ早くなったような気がします。
よく大学人の方々で「インターンは学業の邪魔になる!」と
おっしゃる人は少なくないですが、
僕は時にはインターンやるとかえって勉強の仕方を覚えるので
非常にためになると体験者と思いました。
どちらも論理的な正しさが問われている。
つまり、同じような能力が必要だと思うんだよね。
実際にこの前授業でプレゼンがあったんだけど
「思った以上によく調べており、まとまったいいプレゼンだった。
正直驚いた。」
といってもこのときは調べるのもまとめるのも
そこまで時間はかけていない。多分合わせて2,3時間程度。
つまりそこまで情報は集めてない。
このことから考えると、ひょっとして
学問は知識量だけじゃなくて、どういう『考え方』でやるかも
同じ位重要なのではないかと最近思っています。
『考え方』の訓練。読んだ本や聞いた授業から
そこからどのようなポイントが重要なのかを見抜き、
どのような法則があると組み立てるか。
もしくは自分の主張を裏付けるにはどういった情報が
必要だと考え、行動するか。などなど。
個人的には多分こういうのが相当重要では?と思うんだよね。
この『考え方』を教える授業を
大学でもっと増やした方がいいんじゃないかなぁと最近思います。
そしたら知識は利用するだけになるしね。
仮説思考、多面的思考、批判的思考、構造化思考。
すべて学問に応用すると相当有効だと思うんだけどなぁ。
あと、そもそも半分の先生方のプレゼン力はあんまし高くないから
本でなくわざわざ口頭で知識を伝えることが
効果があるとは必ずしも思えない気が最近する。
それだったら、誰かが先生の授業を聞いて
要約してわかりやすくパフォーマンス付けた方が
いいんじゃないかと思うときもある。
初心者用には授業を噛み砕くことが有効では。
だから、よく授業聞いてわかんなくても
友達に聞いたらわかるということがよくおきる。
教授よりも友達の方がけっこう説明できるということ。
もう一つ。教授に質問しやすくない雰囲気があることも
友達>教授になる要因の一つではないかと思う。
ただ、これは大学だけじゃないかな。高校も中学も小学校も。
なんで学校の先生じゃなくて、友達や塾の先生や家庭教師に頼るんだろう。
気持ちはわかるけど物凄く勿体無いような。。
そもそも講義授業を受ける必要はないと思うけど
といっても多分、今の日本の大学のルールだと時間数で
単位分の勉強を計っているから、
授業は当分は先生の『口頭講義』のままなんだろうな。
文科省が易々とそこにメス入れれる気がしない。
でも、そもそも、結果でなくて時間数で計るのは
理に適っていないと思う。アメリカは合理的だから結果で計るので
短期間で大学院の学位が与えられたりもする。
お互いの時間を有効利用する意味でも有効だと思う。
もちろん「授業で座ってしっかり聞く」
というのは、本を読むより耳で聞いたほうが理解できるタイプの人は
3分の1位いることがNLP理論で証明されてるから
まるっきり授業をなくさなくてもいいんだけど、
でも「本派」の人のことも考えてもいいんじゃないかなぁ。
プレゼンと一緒。正確さよりも明確さ。
細かい定義は大筋のポイントを抑えないと
覚えられないし、重要性がわからないはず。
加えて言えば、変な言葉をさも当たり前に使うのはやめて欲しいと
最近感じている。
例えば「相対化」とか「可逆性」とか。
確かにそういう言葉を覚えないと学問の共通語知らないから
日本の中でも海外でも深く学問できなくなるけど
あまりにそういう言葉使いすぎると
ご老人にパソコン教えるのに「ダブルクリック」って
言って混乱させているようなものでは。
むしろ学問の敷居を高くしすぎている気がする。
あとこんなことも時々思ったりする。
この教授は言葉に酔っているのでは、と思うとき。
この前、
「この論文はまるでかのギリシア神話の~~のように・・のアンチテーゼ
としてうんぬんかんぬん」
という文を見たけど、この文に価値があるととても思えない。
本人の自己満足では。
この教授は怖がりなんじゃないか、と思うとき、
「必ずしもこの文は・・の主張を否定はできないが
ある種の可能性として~~について主張できるかもしれないと思う」
とかいう文を見たりするけど、非常にわかりにくい。
正確に伝えたいのはわかる。批判されるからね。
でも学問なんて批判されてナンボだろ。
何だって問題点叩いてつぶすことで完成度が増すわけだし。
そんなん社会人として怖がりに見える。あるいはプライドが高く見える。
せめて場合分けと確率と条件で示して欲しいけどお願いできないかな。
そしたら情報処理できる。
(ex.~のケースの場合、約70%で当たっているはず。
・・・が立証できることが条件、とか)
他にも改善できると思うところはまだまだあるけど、
総括すると、今の教育、特に大学教育は
「コミュニケーション力」不足だと個人的には思う。
学問にはコミュニケーション力はあまり問われなくても
教育にはコミュニケーション力は非常に問われると思う。
僕は教育にはキャリア教育も足りないし、
社会教育や実践教育も足りないと思うけど、
そもそも知識伝えるのにも「コミュニケーション力」が
不足していると思う。
もっともっともっともっともっともっと
わかる授業はできるような気がする。
大学は本当に「知の宝庫」だと思うけど、
だからいい授業できるわけではないのが残念だと思う。
名プレイヤー名監督にあらずと言われているように、
名教授は名教育者じゃないしなぁ。
=========================
・・・とまあ、つらつらとしてしまったわけですよ。
ときどきこういう風にだらだらした長文になって
結局削除、っていうことがあるんだけどね^^;
でも話の続きじゃないけど、教授方が悪いわけでは
全然ないとも僕は思っているんですよ。
教授方も授業をやるためだけに教授やってるわけじゃないし
そもそも大学に行く学生が昔の数%とかから
今は40%になったから、学生のやる気もレベルも落ちてるしね。
他にも個人的には、ITがいろんな面で発達して
娯楽もいろんな面で発達たから
先生方の授業が、TVとか巷の情報に対して
遥かに「つまらなく」見えてしまうのが、すごく重要な変化だと思っている。
昔のTVや漫画が下手だなぁ、面白くないなぁと
思うでしょ。それと同じ。トレンドもあるけど、
何より「伝えること」「見せ方」が飛躍的に変化したし、発達したのは
すごく大きな変化だと思う。
だから今の大学教育の問題は、
時代の変化により、求められる教育が本当にいろんな意味で
変わってしまっているからだと思う。
それは教授の先生方のせいじゃない。
でも、それでも大学教育はよくしていかなきゃ
いけないと絶対思うけどね。
自分は教育は5つのためにやっていると思う。
一つは教育を受ける「本人」のため
二つは「国」のため。国の平和や繁栄は人で決まる
三つは「国際社会」のため。今後グローバリゼーションは
ITの発達のため更に加速。相互依存が高まる。
四つは「本人の子供」のため。直接影響受ける。
そして五つは「本人の孫」のため。
間接的に影響受けるが、それだけでないと思っている
社会階級は実は再生産されている。格差社会が広がる今後、
今の教育が以後の子孫の階級を決める可能性が高い。しかも今後
高齢化社会になる。今の日本政府の動向を見ると、対策しない/できない
可能性が高い。だから社会保障は家族的なつながりがより重要になる。
家の力の差が、人の選択肢に差を産む可能性がより高まると見ている。
国の歴史のどの場面でも教育は重要だと思うけど、
より社会が今後まずます複雑で独自の判断が求められるようになるので、
過去よりも今、今よりも未来、に教育の責任がより高まっていると思う。
今の教育改革が改革でなくなる時代が来ると思う。
それは生ぬるいっていう意味で。
今の程度の変化はむしろ当たり前で、
常に教育は改善され、進化しないとそろそろ間に合わなくなる。
TOYOTAじゃないけど常に「改善」するようでないと。
そしたらお受験とか偏差値とか言ってられなくなる。
メディアは東大とか受験戦争とか昔の時代の見方で今を捉えつつ
ゆとり教育批判とか最近のトピックに現象しか
追えてないけど、根本を見たり、先を見据えないと
時代が求める変化のブレーキになってしまう。
(話の本筋と関係ないけど、政治と教育とメディア。
日本では既存権力ほど変化がのろいと思う。
影響力がでかいんだから責任重大なのに)
でも大学教育の場合、教育の変化は求められても
学部や学科を常に変えるのはまずくなる。
それは現在教育と表裏一体になっている研究は
長期的に取り組んで成果が出る性格があるので、
教育のために教授や研究体制をコロコロ変えることはできない。
となると、答えは教育者と研究者を一部切り離すか、
教育も研究もどちらもがんばるかことが必要だと思う。
アメリカは両方とも実行されている。
このままだと筆が止まらん。。。
とにかく教育は変化が早く求められるのではと
最近思っているんだよね。根本的なのを。
大学教育だけじゃなくて全部。
それを政府がやるかだけど、うーん。悩ましい。
。。。最近は教育について考えすぎなようです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.