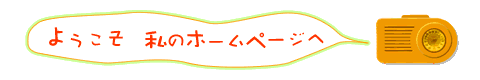全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
「演出」の重要性
musamejiさん 返事おくれてすいません。書き込みありがとうございます。 日本の会社に関する「企業風土」「品」という点に関しては同感です。以前ドイツの大手化学メーカーの仕事を担当してましたが、彼らの社会貢献活動に対する真剣な取り組みには感服しました(彼らはそれのアピール自体も非常に上手ですが。そういう部分は広告代理店さんが日本企業にもアドバイスしてあげたほうがいいのかもしれませんね)。 倫理観の高さがウリの大企業、といわれてもすぐに思いつく会社というのもなかなかないですよね。 利益の大きさだけを追求しているうちはやはり「二流」の域を出ないと思んですが、実際には3面記事に乗るような事件を起こした会社でさえ、サイズがでかい、利益が出ているというだけで「一流」企業と呼ばれてますよね。 結局政治と同じで、社会にガバナンスのチカラがないと出来損ないが大手を振るってしまうということなんですかね。景気が悪いと人心もせちがなく荒むということかもしれませんね。***************** 現実問題としても、例えば業績の急激な悪化など、何らかのピンチのとき、利益の大きさだけをウリにしていた会社の株主は「縁の切れ目」といわんばかりに株を売ってしまいますが、「根強いファン」といった感じの株主のいる会社は意外と株価が持ちこたえます。 これこそ企業ブランド力の有無の差が企業価値として測れるわかりやすい事例だと思います。****************** BSE問題で吉野家D&Cが苦しんでます。「牛丼一筋」にこだわってきたため(さらには米国産に依存しすぎたため)ダメージが大きいと見られがちですが、これほど根強いファンの多い会社もそうそうありませんから、材料の供給が安定してくれば、間違いなく業績は回復すると思うのですが。 でも輸入停止が長引きそうなので、カレーとか焼き鳥とか鮭いくらとかをはじめるとか。個人的には「牛丼一筋」を守り続けて欲しかったような気もするのですが。 こういう局面で競合他社一同供給ストップしているわけですから、牛丼ファンもがっかりしているわけで、ここで一番、無理しても(損失覚悟で)材料をかき集めて牛丼を提供し続ければ、オトコをあげるチャンスだったような気もしたのですが。示し合わせたように各社同様の対応という感じでちょっと面白くないですよね(まあ、私なんかが考えているより事態は深刻なんでしょう)。**************** 私自身の仕事の話についていっても、最近再生企業を支援する上でもIRに関する専門技術も必要な気がしてきています。 あるファンドの人が言っていたのですが、投資を決めてからは、何か事あるごとにプレスリリースにしているとのことでした。どんなに小さいことでも改革が進み、少しづつでも改善していることをこまめにアピールすることが、企業が生き返りつつあることを周囲に印象付ける秘訣とか。(ご当人はそういってませんでしたが、投資先が改革施策について次々とプレスリリースことは同時に再生ファンド自身の業界内プレゼンスを高めることにもつながります。特に新し目のファンドは非常にマスコミにサービス精神があります) そういえばゴーンさんも随分とマスコミ露出してましたよね。「身売り」という負け犬イメージがスポーツカーを売る日産にとって致命的とも思われたのですが、カリスマ経営者と改革集団のイメージをうまく演出し、顧客のロイヤルティと従業員の士気を回復し、再生に結び付けていたのかなと思います。 IRとかブランド価値とかいうと、なんとなく小手先のまやかしっぽい印象を持つ方もおられるかもしれないですが、企業も人の集まり、お客も人間ですから、「演出」も重要な要素だと思います。 そのうち再生ファンドがIRの専門家や広告代理店のやり手をヘッドハンティングするようになるのかなと思ったりします。
2004年01月31日
コメント(0)
-
2003年M&A回顧
例年、一月半ばほどになってくると各調査機関(レコフ社、トムソンファイナンシャル社、証券会社など)のM&A統計が公表されるようになってきます。 M&Aは各企業の戦略達成の「手段」ということもあり、その統計を見ると各企業セクターのその年の共通の課題(例えば国民経済情勢、市場競争環境、規制緩和など)、あるいは企業戦略の流行(?)などが良くわかります。 下っ端の時分はあまりこういったマクロ的な部分には関心がなかったのですが、最近は営業しなければならないですし、たまに講師として人前に立つこともあるので、こういった業界全体の傾向みたいなものも、きちんと「自分なりの分析」を付け加えた上で(クライアントも受講者も怖いくらいレベルが高いかたがおられるので)頭に入れておかなければならない感じです。 また次の「戦略商品」を考える上でも、この手のマクロ分析は必要です。 ほんとは忙しいんですが、折を見てこの手のものも結構時間をとって見るようにしています。************** レコフの年間統計(1月10日に日経新聞でも公表されています)によると、件数ベースでは「グループ外M&A」「グループ内M&A」ともにここ2~3年は安定して推移してます(今年のほうが昨年よりわずかに減少しています)。金額ベースのデータは、各社の自主的プレスリリースによる部分が多いので必ずしも網羅的ではないのですが、集計された数字(公表のあったもののみを集計)で見る限りは、前年に比べて合計額は減少・件数は増加となっており、すなわち1件あたりの金額(平均額)は大きく減少したようです。「ツブが小さくなった」私自身が仕事をしながら、なんとなく感じていたところとやっぱり一致していたようでした(つまり、忙しい割にはちっとも儲からない「貧乏暇なし」の年だったようです)。 昨年までは国際案件(当事者の一方の国籍が海外)が総じて低調だったのですが、今年は「海外企業による日本企業買収」(我々は「アウト=イン」と呼んでます)、特にアメリカ企業によるものは増加に転じていました。 このアウト=インが行われる業種セクターというのは比較的限られていて、証券、その他金融(ノンバンク、ファンド)に集約される傾向があります。実際には小売、サービス、不動産など、様々な業種の日本企業が買収されていますが、ほとんどがリップルウッド、サーベラスなどのファンド、あるいはゴールドマンサックス、モルガンスタンレーなどの証券会社をカマせて取引され、あるいは特別目的会社(SPC、名目的な会社、ファンドの一種です)を組成して投資しているので、統計上そうなるのだと思います(ちなみにリップルウッドの傘下にある新生銀行の買収案件も統計上はアウト=インになっています)。 思い出されるような案件としては、ダイエーの福岡事業、神戸事業はともに米系のファンド、証券会社が落札しています(コロニーキャピタル、モルガンスタンレー)。日本テレコムを買収したのも米系リップルウッドでした。他にもゴールドマンやローンスターなどがゴルフ場やホテルなどの倒産案件を落札しています。破綻生保の草刈場だとか不良債権のバルクセールなどがなくなり、またスリーアイなどの大御所外資ファンドが撤退を決めるなど、なんとなく低調になった感があった一方で、いままであまり耳にしなかったような外資ファンドが1~2件の案件を落とすようなのも結構あったようでした。公の株式市場では外国人投資家の存在感は大きいですが、M&Aの世界に関して言えば、やっぱり預金保険機構とかRCCとかのおかげで、日本企業にも多少は「防御」方法が身についてきてたみたいですね。
2004年01月21日
コメント(0)
-
少数派の株主を「搾り出す」
本日の日経朝刊より「米系ファンドの買収対抗策」ソトーとユシロ化に対する敵対的買収への各社の対抗策が発表されました。同紙にはソトーの公開買付公告も掲載(7面)されています(小さい字でごちょごちょ書いていますが、こちらも一読の価値あると思います。私はスクラップ・ブックしました)。当案件には私はまったく直接タッチしていないのですが、別のクライアントさんとの世間話くらいには出てきそうなので。新聞報道とかでしか情報を知らないのですが、年末あたりからの久々のドラマチックな攻防戦にちょっと注目しておりました。 手法自体は専門書・雑誌など(商事法務とか)でも取り上げられているようなオーソドックスなもの(とはいえ、普通には耳にしない専門用語が飛び交う、結構複雑なもの)ですが、やっぱり実務例として(実際の買付公告などと合わせて)みると、おもしろいです。 このうち個人的に面白いと思ったのは「株式移転」を用いた少数株主追い出し策のストラクチャリングです(詳細は新聞記事ではなく、公告のほうに載っています)。専門的には「スクイーズ・アウト」とかといいます。要は、株を売りたがらない人から無理やり買い取る(その結果、完全な非公開会社となる)ためのM&A手法です。 本来、自分の持ち物を売るかどうかは本人の自由意志によるのが(通常の感覚的にも、憲法上も)原則ですが、商法の世界の株式移転というのを使うと、テコでも株を売らない(つまりその会社の株主総会に居座る)といってた人を半ば強制的に締め出す(「搾り出す」)ことができます。そいう意味では結構斬新な(そんなことが許されるの?的な)ものです(念のため、もちろん商法ないし株式移転は違憲ではありません。商法も真っ向から締め出しの手続として株式移転を用意しているわけではありません。あくまで便法的な「テクニック」です)。 もちろん誰にでもできることではなく、株式移転をするためには商法の決まりにのっとって、その会社の3分の2以上の株(要は議決権)が必要です(厳密には特別決議という多数決条件を満たせばいいので3分の2なくても大丈夫かもしれないのですが、確実に決議を通せる安定多数が、3分の2ということです)。つまり会社の株式の3分の2を押さえていれば、(ジャマなら)残りの3分の1はいつでも強制的に追い出すことができる、ということです(注:わかりやすく書いている関係上、多少語弊もあります。例えば先ほど来「強制的に買い取る」という記述をしていますが、実際は会社をペーパーカンパニーに強制的にすり替えて、その会社を強制的に清算することで、強制的に代金(手切れ金・立退き料)を株主に分配する、という言い方の方が正しいのかもしれません。本当にやるならきちんとした弁護士さんに相談してくださいね)。 ですから、ソトーの場合もまずは3分の2を押さえにかからなければならないのですが、公開会社である関係上、証券取引法の決まりに従って「株式公開買付(TOB)」という手続を踏んでいます(詳しい内情はわからないのですが、現経営陣はすでに40-50%はすでに押さえているそうですので、実質的には残りの20-30%を一般株主から集めればOKということなのでしょう)。ソトー・NIFベンチャーズ陣営は、このTOBという手続で不特定多数の一般株主に一定の値段(市場価格よりかなり高めの値段)で売ってくれるように申し込んだ、というのが今日の報道リリースの内容です。 ちなみにこの案件の場合、米系ファンドのスティールPTRsが、12月に先にTOBで一般株主に対してソトーの株式を売ってくれるように申し入れをしています。またこれに対してソトーの経営陣がそれに応じないように一般株主に求める内容の公告をしています(その辺の応酬もネット上でPDFなどで入手できる公の文書ですので、興味のある方は拝見してみてください)。 株式移転や本ストラクチャーは、図(ポンチ絵)とかもないと文章だけでは説明しづらいですし、かえって難しくなってしまうでしょうから、本日記では詳細を割愛させていただきました(説明べた・エネルギー不足の言い訳です・・・)。でも気に食わない株主を(手切れ金を払えば)合法的に会社から「搾り出す」手段があるというのは、ご記憶の価値があるのではないでしょうか。***************** 個人的に面白いと思った案件なので(業務時間中でしたが)ヤフーファイナンスの各銘柄の掲示板も見てみたのですが、やはり敵対的TOBを仕掛けられるだけあって、個人投資家さんの間でも「株主軽視経営」とか「IR下手」とか結構手厳しい記述が「すでに2,3年前から」されていますね(興味のある方は、特にソトーは早めにどうぞ。上場廃止になったら見れなくなってしまいます)。やはり最近の風潮としては、用もないのに(有益なビジネスアイデアも持たないのに)大量のキャッシュを手元に寝かせているというのは(故意かどうかにかかわらず)「悪」ということみたいですね。これも公開会社ゆえの厳しいコーポレート・ガバナンス、ということなのでしょう。 夕べは公開準備中(目前)の会社の役員をやっている友人と久々に話をしたのですが、彼女いわく、結局公開できる会社というのはそれなりに業績がいいのでキャッシュは潤沢、だから株式公開で新たに資金集めをする必要というのは実際にはない、むしろ変に株式を放出して株主構成をおかしくしないよう、必要最低限の募集・売り出しに抑えるために証券会社と頭をつかっている、とのこと。資金調達の必要がないのに公開するというのは、ちょっと矛盾というか、株式公開の本旨からはずれてるような気がしないでもないのですが、ある意味正解と思います。 実際にはアイデアはすでに枯渇しているのに「もらえる金はもらえる時にもらっとけ」的に、とりあえずで必要以上の大金を市場から集めてしまうと、資金を手元で寝かせることになり、結局株主の批判を浴び、上記2社のような敵対的TOBのターゲットになりかねません(ベンチャー企業でも旧通産省出身のMさんのファンドに攻撃されてしまった事例がありましたよね)。 とりあえず身の丈にあった資金で会社を動かすこととして、公開の目的は「会社の知名度」とか「優秀な人材の募集」とかに絞っておく。本当に必要なお金で、きちんとしたビジネスプランに裏付けられたものなら、別に後からでもタイミングを見計らって市場から増資で調達すればいい(調達できる)ということではないでしょうか。公開時のご祝儀相場でガバッと集めておかないと、先々調達できるかわからないから、とかでは、そもそも公開会社としてその会社の行く末自体に先々不安を感じます。
2004年01月16日
コメント(0)
-
ストック・オプションの会計基準
本日の日経朝刊より「ストックオプション、人件費計上なら過半数見直し」とのこと。ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレスに2000年以降上場した企業へのアンケート結果によれば、企業は人件費として費用計上が義務付けられるのなら、現在採用しているストックオプションの縮小や廃止など制度を見直すと考えているとのこと。 ベンチャー関連の会計トピックとしてはお馴染みの論点です(お馴染みになりすぎて、すでに関心を失っている方もおられるかもしれませんが) 変更賛成派(費用計上賛成派)の掲げる理由としては、「オプションの形をとるとはいえ労働の対価として役員・従業員に経済的価値を付与するものなのだから、給料の一形態すなわち費用と考えるべきだ」という極めて単純明快な理由です。 さらに言えば、ストックオプションで人件費計上を後送りにしている企業のほうが、現金で給料を払っている企業よりも、利益の大きい良い会社に見えるのは、おかしいのではないか(ストックオプションというのは発行企業の損失負担が無限大となりうるリスクの高い戦術である、そのような無謀なものに頼らず現金で優秀な人材に給料を払える会社のほうが本来なら安定した良い会社のはずである、ストックオプションに頼るような不安定な会社が見せかけ上、利益の大きい良い会社になることには問題があるのではないか、投資家に誤った判断をさせることにつながるのではないか)というのがあるのでしょう。 反対派の挙げる理由の主なものとしては、ベンチャーの活性化策として有効な同制度のメリットをなくすことになり、しいては産業の活力を失わせる、というものとか(産業政策上の理由)現在の状況からでは客観的なストックオプションの評価方法というが十分確立していないから、オプション行使前の付与の段階で見積もりで費用を計上するのは困難・時期尚早だ、というもの(技術的理由)でしょう。************** 何らかの粉飾決算事件(例えばエンロン)がおきると、ここぞとばかりに「ついでにストックオプションも見直すべき」との賛成派の声が大きくなり、それをハイテク企業や会計事務所がロビー活動で押し戻すというのが、米国での論争のあり方です。米国の会計基準は自他共に認める世界で最もアグレッシブな会計基準とされているのですが、この論点に関しては非常に歯切れが悪いです(ちなみに会計基準の強い・弱いは、その会計基準が会計理論にどれだけ忠実かということで決まります。日本の会計基準が日に日に米国基準や欧州で盛んな国際会計基準へと収斂されていくのは、日本の会計基準が「理論的に弱い」と攻撃され続けた結果です)。 この問題では「ベンチャー保護・経済の活性化」ということが常に主張されているのですが、先に触れた米国でのロビー活動をやっているのは、実際には現在のベンチャー達ではなく、すでに大企業となったハイテク企業です。固有名詞は避けたいと思いますが、彼ら自身もストックオプションを長年にわたって広範に活用(ある意味乱発)しており、その会計基準の変更には、大企業ゆえに、今あるベンチャー企業以上に多大な影響を被る立場のはずです。 もし費用化が強制されれば、過去に付与したストックオプションについても費用計上すべきという風になるかもしれません。過去長年にわたって乱発してきたストックオプションを一気に費用化しなければならないとなったら、とんでもない金額の赤字計上を余儀なくされることでしょう。 また、ここまで「有利」な会計基準をとっておきながら急に「不利」な会計基準に変更すれば、当然にその企業の業績カーブは下降トレンドを描きます。「成長力」「将来への期待」で人心を掴んできたハイテク企業にとって、実はその「成長神話」がストックオプションの「活用」によって「会計的に作られたもの」だった、ということが露呈されれば、株価にも影響があるでしょう(もしかしたらまたエンロンのときのようなパニックになるかもしれません)。 なにより経営者自身がとんでもない金額のストックオプションを自らに付与しているはずですから、費用化によってそのことが明るみになる、社会の批判の的になる、ということもあるのかもしれません。 上記のような費用化のデメリットは「これから」ストックオプションを活用しようとする企業にとっては別に気にならない論点だと思います。こういった意味ではこの問題は「これからのベンチャー」より「かつてのベンチャー」にとって、より深刻な問題なのだと思います。彼らはさも「後人のため・国家のためにロビー活動をしてあげている」という感じですが、それもなんとなく眉ツバな感じで、「ベンチャー」を大儀・人質にして自分達もストックオプションを費用計上したくないのだと思うのは私だけでしょうか。 実際のところ、たとえ費用計上しても、当該ベンチャー企業が「現金で」給料を払わないことには変わりない(ちょっと難しい言い方をするとキャッシュフロー上はなんらインパクトはない)という意味においては、費用計上が強制されたからといって「人材獲得手段」としてのストックオプションの効果には変わりはないはずです(付与された人材の側にとっては、会社が経理上オプションを費用計上しているからといって当該会社への就職するやめる、なんてことはないですよね)。そのような意味においても反対派は「人材獲得手段」としてではなく(ちょっと厳しい言い方ですが)「経理操作手段」としてのストックオプションの効果を重視してもっぱら反対説と展開している、と言われてしまうのだと思います。 変更賛成派は、別にストックオプション自体を否定しているわけではないのですが、反対派はむしろストックオプション自体の可否の方向へと「上手に」議論をすり替えて、政治問題・産業問題に持ち込んでいるきらいがあります。本来は「費用化やめますか?ストックオプションやめますか?」という2者択一ではないのですが、上記新聞での話のあり方もそんな感じになってますよね。*************** 会計基準の賛否を問う問題というのは、結局のところ企業と投資家とどっちの便益を優先すべきか、というところが本質になります。確かに国民経済上・産業政策上はベンチャーを刺激すべきであることは間違いありません。そのためにはベンチャーに有利に働く諸制度を備えたほうがいいでしょう。ただ政策的に誰かを「有利」に取り計らえば、その反対側で誰かが必ず「不利」に扱われるはずです。不利を被るのは投資家です。 投資家の不利といえば、株で損をすることが先ずあげられますが、それ以外にもあります(むしろこちらのほうがより現実的です)。投資銀行やベンチャーキャピタルはストックオプションの功罪を熟知しており、それを費用化しなければその企業本来の実態がつかめないことはわかっていますから、自ら費用化処理の計算しています。投資判断のためですから当然に企業間比較もするので、場合によっては何10件も計算し、あるいはそれを外部に委託するのかもしません。ここで費やす時間・お金は投資家の被る不利です(会計基準で初めから強制計算されていれば不必要なコストです。ただしここでかかるコストも彼らなりに投資から回収を図りますから、結局はベンチャー自身に「より高い投資利回りの要求」という形で跳ね返ってきているはずです。そういう意味では、ベンチャー自身・投資銀行との関係では、費用化するかどうかで大差はないのかもしれません)。 ここまでの議論でお気づきかもしれませんが、結局一番不利を被るのは、投資家の中でも、専門知識・計算技術・人材・資金力に乏しいノンプロの個人投資家です。投資銀行やベンチャーキャピタルは多少手間を掛かかるとしても、先々大儲けするためですから、それは厭いません。それが彼らの仕事ですし、彼ら自身にコントロールできる範囲なら、むしろ情報の不平等(会計基準の不備)は彼らにとって有利・好都合と考えるでしょう。 そういった手段を持たないノンプロの個人投資家は、何も知らされないままにクズ株に飛びつき、あとあとストックオプションが行使されるに従って株価が下落し、何が原因なのかよくわからないうちに虎の子の投資資金を失うことになるのかもしれません(無論ここで一般投資家をカモっているのはIPO時に売り抜けた創業者であり、投資銀行です。もちろん皆が皆そのような悪意に満ちた人ではないと信じていますが)。************** 「相場は弱肉強食なんだから、プロがノンプロをカモるのは当然のことだ」「ノンプロ投資家だって一儲けしてやろうという色気がもとで火傷するのだから自業自得だ」「ストックオプションは財務諸表に注記されている、よく読まずに株を買うヤツが悪い」「今はルール上は禁止されていないのだから反則技ではない、使って何が悪い」とかいう言い分もあるかも知れません。ある意味正解ですが、結果的には「ノンプロは出て行け」といっているようなものです。 日本ではベンチャーが育ちづらい・活発でないみたいなことが言われていますが、常々私が感じるに、日本人がクリエイティビティに欠けるとか、勇気・行動力がないとか、ということはないと思います。お金ときっかけさえあれば創業に挑戦したいという人・アイデアをただ暖め続けている人は、話の大きい・小さいはあるにせよ、それこそ腐るほどいるのであって、むしろ日本に欠けているものがあるとすれば、リスクの高いベンチャーに投資する人たち、つまりリスク・マネーのほうではないでしょうか(あるいは両者を橋渡しするシステムかもしれません)。 くすぶるアイデアを現実化するにはリスク・マネーが必要>そのためには彼らのためのエクジットの場が整備されることが必要>それがいわゆる新興株式市場なのですが、そこが行き過ぎた弱肉強食で初心者をまったく受け付けないようなものになっては、ベンチャーの育つ土壌全体が育たず、地盤沈下させてしまいます。「ハイリスクを冒したものにハイリターンで報いる」というのがベンチャーの基本ルールですが、多少は弱者に配慮した「ルール改正」もしないとかえってダメということもあるのではないでしょうか。*************** 最後に、ここまで長々書きましたが、私個人はどちらでもいいというのが正直なところです。先ほど若干触れましたが、結局のところキャッシュフロー会計的にはインパクトなしですし(そういう意味でエネルギーを使って議論するほどのことでもないという気がしてますし)、また我々の会社としてはいずれに転んでもあまり商機がありそうにないので。 どちらかというと、議論から見落とされがちな部分について焦点を当ててみたかったと(メディアが反対派の眉ツバにあまりに簡単に乗せられているのに不満を感じていた)いうトコで、やや賛成派の立場から書いたまでです。どっちのほうが「これからの」ベンチャー育成に望ましいのかは私にもよくわかりません。
2004年01月14日
コメント(0)
-
再生企業の「診断」
仕事上、銀行(メイン行)などの要望に応じて、同行の貸付先で業績不振の中小・オーナー系企業を財務分析することがあります。メイン行としての目的は、まずそもそも同社を存続させるか見放すかの判断をするため、あるいは存続させるにしても審査部の審査・監査法人の監査・金融庁の検査に納得してもらえる事業計画(再生計画)を作成する基礎とするため、さらには準メイン行や大口取引先などの他債権者の協力を仰ぐための説得材料とするため、などなどの理由から第三者的立場の調査分析レポートを作成させます。 もちろん同様のレポートを作成するには結構な金額の手数料を取りますから一定規模以上であるとともに、大手企業が取引先などとして関与している場合(大手企業の1次下請け)などに限定しているようです。手数料としては、我々としても決して割のいい仕事ではないのですが、まとまった件数の仕事がもらえるので、スタッフの稼働率維持という目的上は助かる面もありますし、銀行の紹介で大きいM&A案件をえら得る場合もあるので、仕事は請けるようにしています。 再生企業の再建計画を作成するステップとして、よくつかう表現で「診断>応急処置>止血>外科手術>リハビリ」というのがあります。このうちもっとも重要なのは「診断」の段階です。われわれ、仕事をさせてもらう立場としても、もっとも微妙なノウハウが必要とされる部分だと思います。結局、誤った診断で治療方針を誤れば、外科手術をする前に絶命していまったり、場合によっては外科手術が致命傷となりかねないからです(その辺は人間の病気と同じです)。結局のところは診断の段階でも後々の外科手術・リハビリまでのイメージを持ちつつやらなければ、再建のグランドデザインを描くような診断はできませんから、診断をするには結局すべてのプロセスにかかわる知識が要求されるのだと思います。 診断というのは、先に述べたような専門的(経営的・財務的・法律的)な現状分析をすることです。 まず第一にモノはオーナー系の中小企業で、会計監査などを定期的に受けている先ではないのですから、潰れるかどうかの死に物狂いの段階になってくると、まず間違いなく粉飾決算をしています。粉飾決算はウソそのものですから、まずは倫理的に問題があるのでしょうが、それ以上に会社の現状の収益力の把握(過去の趨勢から把握します)の妨げになりますから、これを調整する必要があります。 またこれもよくある事例ですが、2重・3重帳簿をこしらえていて、銀行ごと・取引先ごとに違う決算書を提出し、一部の親密先にだけ本当の決算書を見せているということがあります。これ自体もよく効く話かと思いますが、こと企業再建の場にあっては、このような情報の非対称的な開示は債権者間の疑心暗鬼をうみ、得られる協力を得られなくしますので、(一応)中立な第三者が粉飾を徹底的に洗い出し、債務者・債権者団すべての現状認識・情報量を(できるだけ、少なくとも建前上は)均一共通にしておくべきでしょう。 私の関与した先について言えば、多くのオーナーさんがほんの「一時しのぎ」のつもりで(翌期には元に戻すつもりで)赤字を損益トントンに「修正」したり、棚卸しで商品を「大量に数え間違ったり」します。ある期で利益を増やす粉飾をすれば、将来の期で利益を減らす修正をしなければつじつまが合わなくなるのということはわかっているようなので(わかってなくて粉飾する方も少なくないですが)翌期か翌々期に業績が戻ればとか、あの取引先が仕事を発注してくれればとか、必ず元に戻す、というつもりでやるそうなのですが、実際にはその「賭け」に見放され続けたとうのがバブル崩壊後の10数年間だったようです。 「会社を守るため」「従業員の生活を守るため」「社長なら誰でもやっていること」という気持ちも理解できなくないのですが、繰り返した粉飾決算が積もり積もって、もはや戻し修正のやりようのないような、とんでもない金額の「実質」債務超過になっている場合がほとんどです。もし銀行や取引先にばれたら、融資引き上げ・供給ストップで、会社はもちろんのこと、社長・その家族の持ち物さえ取り上げられてしまうような状況です。社長さんの対応は様々で、言い訳する人・しない人、泣き崩れる人もいれば、やっと告白できてすっきりしたという人もいます。我々・債権者の立場としても同情できる場合とできない場合と様々です。 粉飾のピックアップというのはある意味、前提条件の回復のレベルのことで、もっとも重要なのは会社の事業別分析です。診断の後に「止血」とか「外科手術」が待っているのですが、そのためには会社の事業(製品・顧客)のうち、どれが「流血」原因なのかをきっちり特定する必要があります。いかに不振企業といえ、会社の事業のうちのすべてが「流血」原因ではなく、よい部分と悪い部分が混在しているはずですから、その後の会社のカタチを決めていくためにも、この診断の段階でしっかりと事業別の損益を把握する必要があるのですが、そのような都合のいい資料はできていませんから(そんな分析が日ごろからできるなら、そもそも会社がヒダリ前にはならないでしょうから)一から作ります。作るといっても中小企業ですし、さんざんリストラしまくっているので、社内にそんなマンパワーも残されいないので、結局は外部(会計事務所・法律事務所・コンサル)に頼ることになります。 先ほど来、企業再建を体の病気になぞらえてきましたが、一つ違うところは企業の場合は「風説」によって絶命する場合があるということです。つまり、「あそこは危ない」といううわさが流れると、たとえ実際には別に危なくないにもかかわず、潮が引くように銀行・取引先が我先に手を引き出し、本当に潰れてしまう場合があるということです(人の体の場合には「あの人は病気だ」といううわさが立ったからといって病気が重くなるというのはありません)。従って我々がお手伝いにあがる場合にはその辺の部分にも最新の注意を払います。もちろんターゲットさんもそのような情報統制を張るようなことはしたことないでしょうから、例えば「従業員に対しては我々が○○の職員であり、○○の調査の目的で来たという風に説明してください」とか、そのような部分に関してもアドバイスをするようにします。工業団地のようなところに入っているターゲットなどの場合、あまりスーツ・ネクタイでめがねを掛けたのが大勢で会社に頻繁に出入りすると周りからやはり怪しまれますから、過去の事例ではわざとカジュアルな格好で仕事をしたということもありました。
2004年01月12日
コメント(0)
-
無形資産について
つい先週木曜8日の日経金融新聞に電通の証券アナリストレポートがありましたが、そこでいま同社の取り組みとして紹介されていたのが「広告=投資」ということをクライアントに根付かせることというのがありました。 売上収益が低迷すると企業は費用削減で利益を捻出する策に出ます。その際に彼らが商売とするところの広告活動はまず一番のリストラの標的に成りがちです。ただここで冷静に考えるべきことは継続的な広告宣伝活動により「ブランド価値」という「知的財産」を同時に得ているのであり、広告宣伝は単にお金が出て行くだけの浪費ではない、短期的な景気に左右ざれず、より長期的・戦略的視点に立って広告ないし企業ブランド価値の形成に「投資」をしていくべきだ、ということみたいです(電通の方、違ってたらご指摘ください)。**************** 私はタイトルには「無形資産」としました。これは会計専門用語です。一般に「知財」という場合通常イメージするのは特許技術やブランド価値ですが、「無形資産」はこれよりさらに広い概念で、顧客リストとか、従業員の熟練度とか、立地条件とか、さらには契約上の有利な地位とかも入ります(つまり無形資産>知的財産)。人によっては無形資産を「オフバランス資産」(貸借対照表に載ってこない資産)という風に言う方もいます。 あるところに非常に優秀な企業があると考えてください。それに目をつけた人が同社とまったく同じ資産(たとえば設備・工場)を用意して、まったく同じ製品を販売し始めたとしましょう。しかしながら実際には両者の経営成績は同じにはなりません(おそらくオリジナルのほうが儲かるはずです)。 同じことをしているのに差が出るのはなぜなのか、ということを突き詰めて考えると、たとえば優秀企業のほうはすでに市場で認知度があるのでさほど広告せずとも顧客が買っていくとか(ブランド価値)過去の実績を信頼してくれる顧客がいっぱいいるので付属品なども含めたくさん買ってもらえるとか(顧客リスト)従業員にベテランが多く細かな指示を出さなくても柔軟に対応できるとか(従業員の熟練度)材料供給業者と長期契約がなされており通常より安く仕入れられることが決まっているとか(契約上の有利な地位)とか、そういった貸借対照表上では表示されないような要因が影響しているからです。 会社を買収する場合、持っている資産は両者同じなのですが、実際につけられる値段はもちろん先のオリジナル企業のほうが高くなります。昨日今日のまねっ子会社はいうなれば何のノウハウもない単なる設備の塊に過ぎませんから、その程度の値段しかつきません(単なる設備の塊ならなにも企業買収しなくても設備業者から新品・最新式のものを買えばいいだけです)。両者の値段の差はすなわちオリジナル企業のさまざまな無形資産に対する対価です。投資家はオリジナル企業には設備のほかにも様々なノウハウが付着しており、そのおかげで将来的にそのまねっ子会社よりもより多くを稼ぎ出す力があると期待できるから(余分に払ってもより大きく回収できるという思惑があるから)単なる設備の塊としての値段よりも余分にお金をだしてもいいと思うわけです。 このような「より多くを稼ぎ出す力」を専門的にまとめて「超過収益力」とか「のれん」とか言ったりするのですが、無形資産というのはこの企業の持つ「超過収益力」をその要因別に分類したものということができます。***************** この無形資産あるいは知財というものが最近各方面で注目を浴びる背景には(もちろんそれだけではないのでしょうが)世界的にこれらのものにかかわる会計基準が改正されてきたということがあります。もっとも有名なのは米国会計基準書(SFAS)の142号というのがあるでしょう(私が先ほど無形資産は会計用語だといったのは、そういう意味です)。 実際、これらの無形資産の話は別に新しいものではなく、会計の「理論」の世界では古くから扱われてきたもの(「のれんの要因分析」とかと呼んでました)です。ただしそれが現実の会計基準となり強制されはじめたことで、「実務」の問題となり、企業さん達がうろたえだしたので、それを商売のタネにしようとする人が増えてきたということなのだと思います(もちろん私もその一人です)。 日本の国内基準では強制とはなっていないのですが、いずれそうなることでしょう(日本の会社のなかでも米国で上場している会社では先駆けてすでに採用しているところがあります)。私の会社でもまずそういった「意識の高い」会社さんにアプローチして実務を重ね(お金を取りながら実験台になってもらうといのも恐縮ですが・・・)いずれ日本で強制適用されるときには「実績を積んだ商品」として売り込んでいくことを考えています(同様のことを税効果会計とか年金会計とか、最近では減損会計とか企業結合会計とかでやっています)。
2004年01月11日
コメント(1)
-
M&Aの押し売り-補足
昨日の日記には、いくつかリアクションをいただいたので、軽い補足説明をしたいと思います。まずああいった内容のものを日記とした動機ですが、一つには、私の昨日の個人的重大事件として新たな営業担当が出た、ということがあり日記にその事実を単純に残しておきたいということがありました。自分自身の頭の整理の意味もあったかと思います。 もう一つには、私の日記を見てくださるかたの中には学生さんあるいは中途で投資銀行・ファンド、会計事務所・法律事務所などでM&A関係をやっているとこへの就職を希望されている方もおられるやもしれませんので、実際にそのような会社に入れば、各社HPなどで謳われているような、かっこいい「アドバイザリー業務」など以外にも、かっこ悪い(?)仕事もさせられる、という、別の一面もご紹介できたらな、と思い昨日は長々と書きました。**************ノルマと書いたりして、愚痴っぽい感じになっていますが、私としては決して100%イヤイヤというわけでもありません。この世界で(願わくば独立して)やっていく上では、あのテのことができるようになっていく必要があると思っており、このHPの紹介文に書いたような私の妄想?に一歩でも近づく上では合目的的なチャンスを与えてもらえたのと思っています。大変だと思いますが、それなりには前向きです。***************昨日の日記では、「買えない」でいる新しいファンドさんを小馬鹿にしてたかのようですが、決してそんなつもりはありません。実際に「買えない」苦しみを味わっているのは無名PEFに限ったことではありません。何年も前に鳴り物入りで日本に上陸した外資系の有名・実力派PEFでも、結局集めたお金をすべて運用しきれず、存在感を失ってしまっているもの、すでに東京事務所を引き払ってしまったものがいくつもあります。かつて私の会社も彼らを今後の業界のメインプレーヤーと睨み、いろいろ一生懸命に働きかけをしていましたが、もう案件ルートとしては死に体です・・・。その他でも、例の親方日の丸の再生ファンドもなかなか案件が買えず苦慮していますよね。こういったことが今の厳しい現実みたいです。もちろん何百億円ものお金を集めるのだって大変難しいことですが、リスク分散させられるだけの案件の数を掘り出すのはこれまた大変なことで、さらにはリターンを生むまでにターゲットを体質改善させる、というのですから、想像したって並大抵のことではありません。 私自身、夢として単に「独立してPEF立ち上げたい」と書きましたが、もちろん立ち上げればそれでいいという意味ではなく、5年・10年先まで生き残るものを作りたいという意味ですが、現実をきちんと直視するなら妄想のレベルでしょう。いわんや、いま現実に戦っている方々を嘲笑することなどできません。
2004年01月08日
コメント(0)
-
M&Aの押し売り
会社で新年早々の営業会議にて、本年の「飛び込み営業の担当産業」がきまりました。私の担当は非鉄金属と外食となりました。 Ryunosukeさんも新年のミッションステートメントで「MA案件の発掘」というのを上げらてました。(パクリというわけではないのですが)私にとっても、同様のことが今年のテーマとなっています。ただ私の場合はミッションというよりかは社命、ノルマというやや主体性に欠く取り組みですが・・・************ 自己紹介や日記でも触れているのですが、私はM&A関係の仕事をしています。「M&Aの押し売り」というのも変に思われるかもしれません。しかし実際にはやってます。 M&Aというのは人間にたとえるなら、会社同士の結婚、養子縁組(時には口減らし・人身売買?)。そんなもの、必要性を感じていないところに突然押し売りをしても、すぐに話がまとまるものではありません。プレゼンしてすぐに仕事を取れる確率は限りなくゼロに近いです。ではなぜそんな無駄な努力をするのでしょうか。 M&Aは多くの場合、ひとたび公表してから失敗・挫折すると会社の評判を大きく傷つけます。また公表すれば反対勢力(ライバル会社、時には従業員)が邪魔もしてきます。従ってどの会社も案件の段取りは「必ず公表の前に」ごく限られた社内の人たちが極秘に投資銀行や法律・会計事務所を集めて、綿密に段取りを行ってしまい、プレスリリースはいわばディール・スケジュールの通過点的な「儀式」という場合がほとんどです。 従って具体的な案件がプレスリリースされてから、当該会社の代表番号に電話をしても当然に門前払いとなってしまいます。新聞発表直後には、いろんな投資銀行、ファンド、コンサルがいっせいに大代表に電話を掛け捲りますから、受付の方も、もはや担当部署に取り次いではくれません。特に最近はM&A・企業再建ブームで「お金はあるのに買えない」ファンドさんがたくさんあり、優良・大型案件には競争熾烈ですから(特に新しいファンドさんは新聞に出るような有名案件を手がけて名前を売りたいというとこが多いですから)その傾向は顕著になってきています(でも実際にはダメもとで我々も電話しますが・・・) したがって、まずは日常から飛び込みプレゼンを通じて、M&A専門家としての自分たちの存在を知らしめ、利用価値を理解してもらい、なにかの時には連絡をもらえる、といった細い細いルートをいろんなとこに張り巡らせておき、先ほど述べたような秘密裏の検討段階に声を掛けていただけるようにしておくことが大事なわけです。たとえ事前にタッチできなくても、社内でグループ戦略を担う部署のキーパーソンへのコンタクト方法がわかっていれば、プレス後に間抜けな電話をするにしても、大代表番号よりかはグッと確率は高まるわけです。 では、具体的にどんなことをするかというと、それほどたいしたことをするわけではありません。要はこれまで取引のなかった会社さんに行って、過去の取り扱い案件を例にしたりして、我々のスキルセットを説明したり、時には具体的な案件の提案したりするわけです。先ほど述べたとおりの意図でやっていることですから、「名刺代わりの挨拶」としては十分という感じです。 うまく和めば、会社で発信しているフリーペーパーやメールマガジンやら、基準・法改正のセミナーとか勉強会への参加を勧め、「キーパーソンへのコンタクト方法」を聞き出すわけです。 かつては「まずは一発かます」的にまったくこちらのプレゼンに耳を貸さず、あからさまに「お前らに一体何ができるんだー」的な態度をとられる先も結構ありましたが、最近はM&A自体が日本の商慣習としてこなれてきたのか、比較的大人の対応をしてくださる担当部署の方が多くなってきました。金を払う立場といえ、表立って傲慢な態度をしめすよりかは、いろいろな業者を上手に使いまわすほうがトク、ということなのでしょう。
2004年01月07日
コメント(2)
-
持株会社制について
本日の日経朝刊より、「エイベックスが持株会社制に移行」と。その心は、縮小しつつあるCDセールス市場に対応するためには事業多角化(他市場進出・拡大)が必要であり、それを効率的に行うためのグループ資源運用(重複回避)を図るためとのこと。 最近よく耳にする音楽CDの市場縮小。よく新聞などで目にするのはナップスターのようなネット上での無償交換などが原因として言われています。ほかにも考え付く要因としては、不景気による消費不振とか、少子化とか、レンタル・マンガ喫茶・ダウンロード配信などへのシフトにより単価下落・利ざや縮小があるでしょうか。以前に扱ったCDショップのバイアウト案件でも議論になりましたが、やはりこれらのことが買収の潜在リスクとしてあげられてました。ただ、これらは非常にわかりやすい(誰にでも想像・納得しやすい)のですが、これらはどちらかというと表面的原因(現象)のようです。 むしろ深刻な根本的原因として捉えられていたのは「若年層への携帯電話の普及」ということでした。つまりは、消費者の中心世代である10後半~20代の財布の中でのプライオリティとして、CDというのは携帯料金に負けてしまっている、ということです。意識的に天秤にかけてはいないにしても、気づいたら携帯を使いすぎてて毎月支払いがキツイ、次第にCDは買わなくなりレンタルやマンガ喫茶で聴くようになる、というメカニズムです。不景気・少子化で市場規模が頭打ちになってくると、携帯電話という隣接市場に消費者の所得を奪われ、それが購入枚数の低下・レンタルその他の低価格化シフトにつながる、という風にターゲット会社の人たちは分析してました。 確かに月4~5万円程度のお小遣い+バイト代では、携帯払って、デート・コンパして、服を買って、美容院に行ってたら多くは残らないし、その残った部分をさらに高級バッグ・腕時計、車のローン、海外旅行のための貯金やらと奪いあうわけですから、CDなんて月に何枚も買ってもらえない、「レンタルで十分!」といわれてしまっても仕方ない感じはします。同様のことをゲームソフト会社の人も言っておりました。 レコード会社のほうは、敵である携帯電話とは一方で争いながらも、他方では着メロなどで携帯からも収入を得る仕組みを作って対応しているようです(これはゲーム業界も同じです)が、エイベックスが持株会社制に移行して事業ポートフォリオを見直すとかというのは、着メロ事業だけではまだ対応不十分ということなのでしょう(基本的に携帯サイト事業は競争の激しい事業みたいですし)。一度案件関与した業界にはディール後も継続して業界ウォッチするほうなのですが、エイベックスが新たにどんなビジネスモデルを出すのか(携帯電話と戦うのか)、注目したいです。
2004年01月06日
コメント(1)
-
会社を売る・買う
本日の日経朝刊より「買収・再生ファンド、追加設立相次ぐ」、みずほキャピタルやフェニックスがあいついで数百億円規模の新ファンドを立ち上げており、その背景には、これまでの投資が高リターンで実を結びつつあり、機関投資家の出資熱を増しているとのこと。 私の身の回りでは、日本の景気が回復基調になりつつあり、今後は大企業の組織再編や大型倒産にからむ大きな「掘り出し物・売り物」が少なくなってくる、M&Aビジネスは下火になるか、という感じでしたが、上記のような記事は新年早々うれしい限りです。 実際過去の統計では企業倒産は景気の下降局面よりむしろ景気の回復局面のほうが多いといわれてます。過去のように濡れ手に粟の儲け話はなくなりつつありますがもうしばらくはこの業界でも食べていける見たいですね。 本当ならこの最後の大波に自分自身のファンドで勝負したいとこですが。誰か500億円くらい任せてくれないですかね。
2004年01月04日
コメント(4)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去
- (2025-04-08 00:00:18)
-
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- 税金・地方交付税から行政法まで!国…
- (2025-11-19 09:04:40)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- チェンマイに佇む男達 寺本悠介の場…
- (2025-11-20 10:06:55)
-