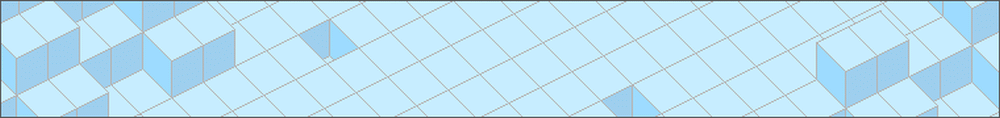2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年11月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
マイホームを新築したら・・・2
その「フラット35」で借り入れし、住宅を購入される方から、お電話をいただきました。「『フラット35』を借りるのですが、保険は1年ごとにしようと思うのです。」と。これが、私のお勧めする、何年の火災保険に入るか?、いくらの火災保険に入るか?すべて決めるのはお客様です。ということに合致している方です。この方は、・2300万円で家を建てられている。・1年ごとに保険料を支払うようにしたい。ということです。条件に合致し、最も安い保険料で加入できるF社をお勧めしました。と同時に、家財の必要性もお話したところ、「そうですね。じゃ300万円で。」ということになり、そのような見積もりをさせてもらいました。建物 2300万円家財 300万円 となり、この場合の保険料が44,780円となりました。そこで、そこでです。マイホームの火災保険。その保険期間も、保険の金額も決定権は、すべてがお客様にあるのです。住宅ローンで2300万円借りたからといって、火災保険が2300万円でなければならない理由はありません。常々、建物に比して家財の弱さからの家財保険の重要性を、訴えている私です。東日本大震災の地震保険でもしかりです。そこで、建物 2000万円家財 600万円としてみてはどうでしょう。建物 2300万円 建物 2000万円家財 300万円 家財 600万円どちらも総額が同じなので、建物が全損 2300万円 2000万円家財も全損 300万円 600万円計 2600万円 2600万円とまったく同じ保険金がでるのですが、仮に建物半焼し復旧に1100万円必要家財が消火作業で全損となった場合には、建物損害が1100万円 1100万円 1100万円家財は全損 300万円 600万円計 1400万円 1700万円となり、大きな開きが出てきます。こう考えると、お客様にとっても、ついでに言えば住宅ローンの会社にとっても、よいのではないでしょうか?反対に建物のすべてが損壊して家財の一部が残るといったことは、私にはどうも考えられないので、建物の保険(金額)を少し抑えてでも、家財にもバランスよく保険をかけられることをお勧めします。ちなみにF社では、建物 2300万円 建物 2000万円家財 300万円 家財 600万円保険料44780円 45680円 その差は900円/年です。すべてを決めるのは、お金を払う貴方なのです。
2012.11.05
コメント(0)
-
マイホームを新築したら・・・
マイホームを新築する。http://youtu.be/7xaDBituWbUマイホームを手に入れる。家族の夢が広がる一大イベントです。 家族の夢が、楽しい将来がそこには詰まっています。想像するだけで楽しくて、ワクワクしてきますね。しかし、住宅を手に入れた人の多くが頭を悩ますのは・・・お金の問題です。それぞれの家庭で、それぞれの事情があると思いますが、住宅ローンをどうするか?そして、火災保険をどうするか?火災保険を悩んでいる人のなかに、保険料に頭を悩ませている人がいますが、「火災保険を住宅ローンと同じ期間入らないといけない」と思い込んでる人が多いのは、私からすると、正しい情報が届いてなくて、かわいそうだと思います。夢のマイホームを手に入れる。その過程で必ず越えなければればならないお金の問題。今回は住宅購入の際にありがちな、火災保険の常識・非常識に注目してみました。住宅を購入する際、全額自己資金の人ってやっぱりそう多くはないでしょう。多くの人は住宅ローンを利用することになると思いますが、一昔前(10年程前)は、都市銀や地銀が住宅ローンの主役であり、住宅ローンの提案と同時に火災保険の販売も行っていたのです。しかしこれは、「金を貸してやるから保険にも入れ」といわんばかりの、お客さんの選択肢をなくする行為に等しいと、金融庁から厳しく指導されたのでしょう。都市銀・地銀の火災保険販売は次第に下火になります。続いて第二地銀や信用金庫からも、住宅ローン&長期火災保険のセット販売は見られなくなります。もちろん一部の金融機関ではまだあると聞きますが、私が保険の仕事を通して得た実感はこのようなものです。都市銀行や地銀では、所得の低い人の住宅ローンが通りにくいと、耳にしますが、そのこともいくらか関係しているかもしれません。さて、ここまで書きますと、住宅ローンを販売している金融機関が、「厚かましくも火災保険までセットで販売して、手数料を稼ごうとしている。」ように感じますが、そうとも言い切れない側面が見えてきます。それは、保険会社が住宅ローンの実行されている現場に、「長期火災保険を販売しませんか?」と、働きかけている。保険会社が絵を描いていると考えるのが、おそらく正解でしょう。そこで、今回取り上げるのが、「保険期間は『フラット35』お借り入れ期間と同じ年数以上の期間を一括でお申し込みいただく必要があります。」※1という文言を受けて、お客様が「困った」と相談に見えたのですが、これを誰が言っているか?住宅ローン(金融機関)会社か?保険会社か?この紙を書いて配っているのは、施工した工務店(ハウスメーカー)なのですが、お客様から、「そんな決まりが有るのですか?」とたずねられた私は、「ぅうんまぁ・・・そんな決まりは有りませんね。」「というよりも、そんな事を言ってはいけない事になっている筈ですが・・・」まず、保険会社ですが、そんな事を言うはずもない。というよりも、言える立場にありませんね。次に、住宅ローン(金融機関)会社ですが、ここも、そんなことを言うのは有り得ません。都銀・地銀と同じ話で、金融庁の目が光っていますから。すると残るのは、工務店(ハウスメーカー)です。この紙を配布している工務店は、保険会社の代理店をしているのでしょう。もしかすると、住宅ローンの代理店もしているかもわかりません。保険会社と住宅ローンの代理業務をしている者が※1のような事を、発言するのは、私からすると大変驚きです。まして、紙に書いているなんて考えられない事です。業務停止や資格剥奪等の処分があるかもしれませんから。しかし住宅の工務店(販売店)なら話は別です。保険やローンを売れなくなっても、もともと本業ではないのですから、こんな大胆なことがいえるわけです。聞けば、住宅ローンも都銀・地銀はある程度以上の所得がないと、借りられず、より借りやすい「フラット35」のシェアが伸びていると聞く。都銀・地銀から第二地銀や信用金庫などへ、そしてまた「フラット35」の代理店へと、より低いほうへ水が流れるごとくに、火災保険の販売現場もそれにつられて、低きへ流れているのです。「フラット35」を借りても、決して長期の火災保険でないといけないということはありません。何年の保険に入るか?それをどこで入るか?すべてを決めるのは、お金を払う貴方なのです。hp → http://krc-okayama.com/blog→ http://krc-okayama.com/blog/
2012.11.05
コメント(1)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 福袋2026🔹MLB ロサンゼルス・ドジャ…
- (2025-11-16 19:23:16)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【楽天ユーザー必見】お買い物マラソ…
- (2025-11-16 20:30:05)
-
-
-

- 政治について
- 【片山さつき大臣に正念場】※緊急速…
- (2025-11-16 18:49:04)
-