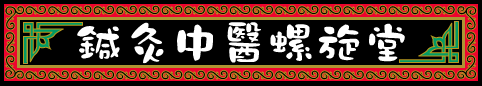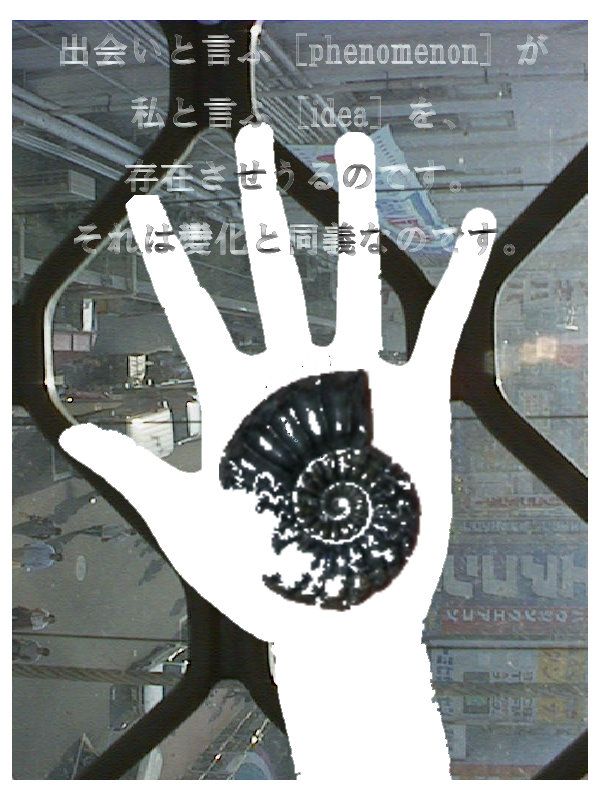カテゴリ
カテゴリ未分類
(240)【 ほん 】
(11)【 映画 】
(2)【オススメ アイテム】
(25)【 PC 電脳雑貨 】
(52)【 龍 玉 随 想 記 】
(233)鍼灸中医
(64)大陸生活
(44)【 中国雑貨 】
(16)写真
(11)【 植物 】
(3)虫
(1)キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
全て
| カテゴリ未分類
【 中国雑貨 】
| 【 PC 電脳雑貨 】
| 【 ほん 】
| 大陸生活
| 鍼灸中医
| 【 龍 玉 随 想 記 】
| 【オススメ アイテム】
| 写真
| 【 映画 】
| 【 植物 】
| 虫
カテゴリ: 鍼灸中医
■日本の針灸術はなるべくと痛みや火傷などから遠避かろうと、必死に修錬をしたり、次々と新しい道具を開発したりするのでした。
しかし、中国の針灸はちょっと違う。
▼まず針が太い。
日本で使われる針は、φ0.20mmを「三番」として、0.18、0.16が二番、一番と0.02mmずつ細くなっていきます。あとは「五番」と言う太い針が0.24mmです。
中国では通常目にするのが、日本で言うところの「八番」。普段髪の毛ほどの細い鍼を使っている我々からすれば、ハリガネのような印象です。
▼針管を使わない
「針管」ほど日本の針術の特徴を表す物は無いでしょう。
※一般の方へ少々説明いたしますと;針を皮下に刺入する時に、針を筒の中に入れてるのです。その筒を「針管」と呼びます。各種の「針管」は利用する針よりも2-3mmほど短くなっています。セットした状態で、針管から飛び出た針の竜頭をポンと叩けば、痛みを感じる暇も無く刺入できると言う寸法です。
針管の発明に関しては伝説があります。ある実在した有名な鍼師は、あまりに鍼が下手で一度破門されてしまい、失意の内に偶然発明したのが針管であった、と。
中国の鍼は太い⇔針管を使わない →操作しやすい鍼へ発展
日本の鍼は細い⇔針管を使う →より細い・痛くない鍼へ発展
以上の図式が出来上がります。これを何百年と積み重ねて、今の形に落ち着いています。
■中国には細い鍼を作る技術が無い・・・わけではありません。現在では細い鍼も発売されています。
▼中国では刺入後の「得気」や「補瀉手技」を大切にします。したがって、刺入後に激しく操作するため、その形は手指との摩擦が得やすいように独特に進化しています。当然、細過ぎれば操作時に針体が曲がってしまいます。
また、日本は刺入後に激しく操作することは無いために、のっぺりとした形をしています。(写真)
▼「中医針灸だから太い鍼を」とか「痛みを無くす為に細い鍼を」と言う考え方ではナンセンスでしょうね。
※一体、道具としての鍼それはどんな意味を持っているのか、が私の研究と自信の医療のテーマでもありました。道具としての鍼と言う観点は、今後この随筆のキーワードであります。
■補瀉手技・・・プラスとマイナスの二つの刺激方法で、代表的なものを日中で比較して見ましょう。
日本・・・迎隨、開闔、呼吸、母子配穴
▼この様に、日本は刺す前段階と刺した後で補瀉をしますが、中国では正に鍼が刺さっている状態で補瀉(操作)をします。当然中国の補瀉操作は独特の「得気感覚」や「酸・麻・重・脹」の感覚、痛みが発生します。
また中医針灸ではこの操作を重要視するために、鍼柄の形が進化しているのです。日本の鍼はのっぺりと退化した形になっています。
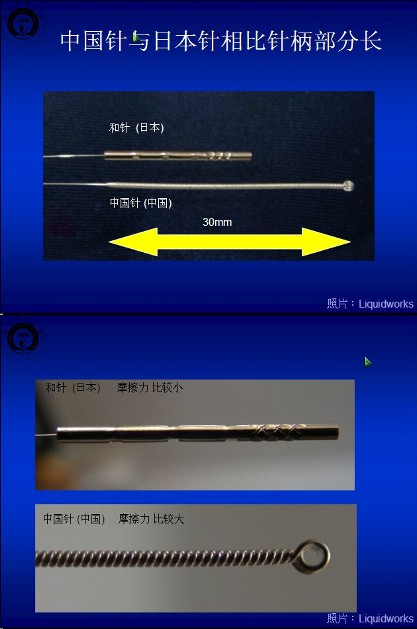
しかし、中国の針灸はちょっと違う。
▼まず針が太い。
日本で使われる針は、φ0.20mmを「三番」として、0.18、0.16が二番、一番と0.02mmずつ細くなっていきます。あとは「五番」と言う太い針が0.24mmです。
中国では通常目にするのが、日本で言うところの「八番」。普段髪の毛ほどの細い鍼を使っている我々からすれば、ハリガネのような印象です。
▼針管を使わない
「針管」ほど日本の針術の特徴を表す物は無いでしょう。
※一般の方へ少々説明いたしますと;針を皮下に刺入する時に、針を筒の中に入れてるのです。その筒を「針管」と呼びます。各種の「針管」は利用する針よりも2-3mmほど短くなっています。セットした状態で、針管から飛び出た針の竜頭をポンと叩けば、痛みを感じる暇も無く刺入できると言う寸法です。
針管の発明に関しては伝説があります。ある実在した有名な鍼師は、あまりに鍼が下手で一度破門されてしまい、失意の内に偶然発明したのが針管であった、と。
中国の鍼は太い⇔針管を使わない →操作しやすい鍼へ発展
日本の鍼は細い⇔針管を使う →より細い・痛くない鍼へ発展
以上の図式が出来上がります。これを何百年と積み重ねて、今の形に落ち着いています。
■中国には細い鍼を作る技術が無い・・・わけではありません。現在では細い鍼も発売されています。
▼中国では刺入後の「得気」や「補瀉手技」を大切にします。したがって、刺入後に激しく操作するため、その形は手指との摩擦が得やすいように独特に進化しています。当然、細過ぎれば操作時に針体が曲がってしまいます。
また、日本は刺入後に激しく操作することは無いために、のっぺりとした形をしています。(写真)
▼「中医針灸だから太い鍼を」とか「痛みを無くす為に細い鍼を」と言う考え方ではナンセンスでしょうね。
※一体、道具としての鍼それはどんな意味を持っているのか、が私の研究と自信の医療のテーマでもありました。道具としての鍼と言う観点は、今後この随筆のキーワードであります。
■補瀉手技・・・プラスとマイナスの二つの刺激方法で、代表的なものを日中で比較して見ましょう。
日本・・・迎隨、開闔、呼吸、母子配穴
▼この様に、日本は刺す前段階と刺した後で補瀉をしますが、中国では正に鍼が刺さっている状態で補瀉(操作)をします。当然中国の補瀉操作は独特の「得気感覚」や「酸・麻・重・脹」の感覚、痛みが発生します。
また中医針灸ではこの操作を重要視するために、鍼柄の形が進化しているのです。日本の鍼はのっぺりと退化した形になっています。
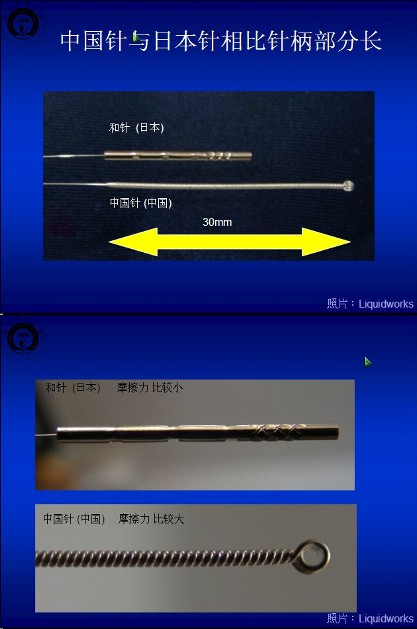
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[鍼灸中医] カテゴリの最新記事
-
2018年はり・きゅう師/あん摩マッサージ… 2018年03月29日
-
中医鍼灸2018卒後研修、大募集 2018年03月27日
-
『がんと鍼灸』の原稿がupされまんた 2017年09月05日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.