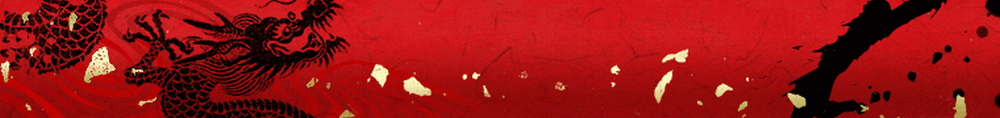カテゴリ: カテゴリ未分類
世界は広い。
音楽はさらに広い。
そして、人々の生活はもっと広い。
週末、「ジプシー・キャラバン」という映画を観た。
ルーマニアの「タラフ」と「ファンファーラ・チョクルリ-ア」。
マケドニアの「エスマ」。
インドの「マハラジャ」。
スペインの「アントニオ・エル・ピパ・フラメンコ・アンサンブル」。
ルーツにジプシーの音楽を持つという5つの音楽集団が、北米の町を演奏して回るというドキュメンタリーの音楽映画だった。
様々な迫害を受けながら世界中に散逸していったロマの血脈。それは、ある特定の「土地」だけに伝統音楽というものが根付くのではなく、厳しい迫害を受けながらジプシーの誇りのもとそれぞれの地で耐えてきた人々の「生活」や「思い」に根付くということの証左でもある。
そんな中で、昨日、NHKの西表島で生きる若者の暮らしを題材にしたドキュメントを観た。主人公の青年は都会生まれのやまとんちゅう。西表に移り住み、米づくりやイノシシとりや魚釣りなどを島のおじいたちに教えてもらい、強く生きている若者家族。
その生活の中で、島の伝統的な祭りや踊りや唄などの、いわゆる伝統芸能も教えてもらっている。うらやましい、と思う反面、本来、伝統芸能はそこに生活があってなりたつのであり、芸能の部分だけ抽出して継承するなんてことはそもそもナンセンスなのかも知れない、と当たり前のことを当たり前に見せつけられたようで、ちょっと寂しい感じもした。
伝統の音楽や芸能が根付く民族の生活。一言で生活というが、それは、もっと正確に言えば、「自給自足」の生活、「自活」の生活だ。田植えがあるから田植え歌がある。収穫があるから収穫の踊りがある。神に豊穣を祈るから「世乞い(ゆーくい)」のような芸能もある。
と考えた時に、「自給自足」という原生活から遠く離れた、現代人がどうやって伝統芸能を受け継ぐことができるのか。
何かしら、圧倒され続けてしまった週末だった。
音楽はさらに広い。
そして、人々の生活はもっと広い。
週末、「ジプシー・キャラバン」という映画を観た。
ルーマニアの「タラフ」と「ファンファーラ・チョクルリ-ア」。
マケドニアの「エスマ」。
インドの「マハラジャ」。
スペインの「アントニオ・エル・ピパ・フラメンコ・アンサンブル」。
ルーツにジプシーの音楽を持つという5つの音楽集団が、北米の町を演奏して回るというドキュメンタリーの音楽映画だった。
様々な迫害を受けながら世界中に散逸していったロマの血脈。それは、ある特定の「土地」だけに伝統音楽というものが根付くのではなく、厳しい迫害を受けながらジプシーの誇りのもとそれぞれの地で耐えてきた人々の「生活」や「思い」に根付くということの証左でもある。
そんな中で、昨日、NHKの西表島で生きる若者の暮らしを題材にしたドキュメントを観た。主人公の青年は都会生まれのやまとんちゅう。西表に移り住み、米づくりやイノシシとりや魚釣りなどを島のおじいたちに教えてもらい、強く生きている若者家族。
その生活の中で、島の伝統的な祭りや踊りや唄などの、いわゆる伝統芸能も教えてもらっている。うらやましい、と思う反面、本来、伝統芸能はそこに生活があってなりたつのであり、芸能の部分だけ抽出して継承するなんてことはそもそもナンセンスなのかも知れない、と当たり前のことを当たり前に見せつけられたようで、ちょっと寂しい感じもした。
伝統の音楽や芸能が根付く民族の生活。一言で生活というが、それは、もっと正確に言えば、「自給自足」の生活、「自活」の生活だ。田植えがあるから田植え歌がある。収穫があるから収穫の踊りがある。神に豊穣を祈るから「世乞い(ゆーくい)」のような芸能もある。
と考えた時に、「自給自足」という原生活から遠く離れた、現代人がどうやって伝統芸能を受け継ぐことができるのか。
何かしら、圧倒され続けてしまった週末だった。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.