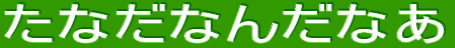2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年01月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

石垣積み
息子が所属する少年野球チームが出場する駅伝大会の応援に行ってきました。息子達が通う小学校は、児童数44名の小規模校です。4年生以上の野球部は、普段まさに全員野球で頑張っています。12区間でたすきをつなぐ今日の駅伝大会も、他のチームが6年生を中心に出場する中、4年生も交えたチームでなんと3位で走りきりました。息子も今年4月には中学生になります。ただ、残念なのは中学校には野球部がないのです。なんといっても3学年で30数名という超!小規模校なのです。野球を続けたいという理由から、他の中学校に進学する子もいます。それでますます生徒数が減る、という悪循環です。いかんともしがたい状況なのです(T▽T)今日の午後は石垣積みをしました。正確に言うと、石を積んでいく作業は親父がぼちぼちとやっています。そのために日曜日を利用して、バックホーで床堀りしたり、石を運んだりするのです。棚田の石垣は決して永久に壊れないわけではなく、やはり補修作業が必要になります。建地ブロックを使うこともできるのですが、やはり自然石を使って積んでおきたいものです。不思議なもので、崩れたところをあらためて積もうとすると、以前あった石では何故か足りなくなります。もともと石垣があったのに石が足りないのは本当に不思議です。
2006.01.29
コメント(4)
-

これを読め!
ホリエモン―まったく人騒がせなやつである。彼については、メディアがいろんな角度から分析をしているようだし、いろんな人のブログでも書かれているようなので私ごときがコメントすることは何もないのだが、一言だけ言わせてもらえば、ホリエモンよ、この本を読め!!「明徳」経営論 - 社長のリーダーシップと倫理学著者の永野芳宣氏は指摘する:・「21世紀に入って数年間の特徴は、国境を越えて激しく動く投機ないし投機ファンドの跳梁であった。それは何十兆円、ひょっとすると100兆円を超える規模、といわれる金融資本のグローバルな活動が背景ある。その動きに刺激され、異常な株価操作が発生し、企業のM&A(企業買収や合併)や企業倒産、これらに関連する度を越した企業犯罪が生み出されてきた。」・「特に最近の企業犯罪を生む重要な原因の一つに、グローバリズムがら発した、インターネットとIT技術の急激な発達ということが挙げられる。通信衛星や光ファイバーなどを駆使したインターネットによって、情報伝達が超スピード化した。これが異常な商取引を招いたのだ。」・「ITの登場によって過激化した資本の論理は、企業体の経営者にCSRの理念を忘却させ、常識では考えられないような詐欺的なモラルハザードが生じたり、テロ的行為を起こさせたりすることもあるのだ。」経営者は、常にコンプライアンスとCSRについて、十分な認識と推進を心がけておかなければならない。この本では、「和」の精神とこれを支える「儒教的教養」をテーマに、経営における社長のリーダーシップに必要なのは「明徳」であると説く。「良心に恥じない、正義を重んじる行動をとる。」・・・このことを「明徳」という言葉で語っている。コンプライアンス違反の企業不祥事が繰り返される。いくら倫理規定や法令規定などを整備しても、経営者の認識が十分でなければ何にもならないのだ。著者は言う:経営者はもちろん従業員も含め企業体の関係者が、「明徳」の思想を事業活動における正しい判断材料として持つこと。それがコンプライアンスすなわち正義を実現することにつながるのである。
2006.01.26
コメント(2)
-
マニフェスト型選挙
水俣市では、次の日曜日29日に「市長選挙」が告示されます。今年は、水俣病公式発見から50年の節目の年でもあり、次のリーダーは誰になるのか、たいへん気になるところです。今日は、その「市長選挙」に向けての公開討論会「水俣未来づくり公開討論会2006」が開かれるということで出かけて行きました。主催は、水俣青年会議所の会員らでつくる「水俣未来づくり公開討論会2006」実行委員会。行財政改革や地域活性化など重要施策について、数値目標や手段を明示した公約(ローカル・マニフェスト)をもとに、争点を明らかにするローカル・マニフェスト型の討論会ということです。それぞれの長期構想や重要施策などの質問について答えがあらかじめ提出してもらってあり、ローカルマニュフェストとしてまとめてあります。そのマニュフェストにそって、コーディネーターの神吉信之さんが討論を進めていきます。田舎の選挙といえば、地縁血縁が票を集める大きな要素でしたが、やはりこれからは、きちんと政策を争点としてリーダーを選んでいくことが大切であり、政策論争をきちんとやることは我々有権者にとっては大きな判断材料になりますね。たいへん有意義な討論会だったと思います。ただ、一方は政治家としての経歴も長い現職の市長。それに対しもう一方はまったくの新人。これが同じ土俵で討論するのには無理があるようにも感じました。政策論争だけではどうしてもベテランのほうが有利になります。コーディネーターの役割が非常に大切な部分です。現職の市長は、これまでの成果をどう評価し次にどうつなげていくのかが問われるのでしょうし、新人にとっては、具体的な政策を持つことは当然必要でしょうが、根本的な考え方、姿勢、意欲、人間性なども評価の対象となります。いずれにしても今回の討論会はたいへんいい企画でした。今後地方選挙においても、こうした取り組みはますます重要になってくると思われます。なんといっても、いい政治家を選ぶには有権者が賢くなることが前提になるのです。水俣市長選挙候補表明者の公開討論会用マニフェスト ↓ ↓http://www.minamatajc.jp/to-ronkai/ローカル・マニフェスト推進ネットワーク ↓ ↓http://www.localmanifesto.com/
2006.01.24
コメント(0)
-
柿を植えました
太秋柿の植付けをしました。といっても、わずか14本ほどですが、植付けが終わって減反の荒れていた田んぼがきれいになって気持ちいいです。太秋柿は、果実が大きいうえにたいへん甘く、食感がリンゴみたいにサクサクとしており、これまでの柿とは違った美味しさです。現在、JAが一生懸命力を入れ産地づくりをすすめています。なかなか新しい作物の振興はむずかしい面がありますが、この太秋は、選択としてはなかなか良かったのでは、と思っています。その理由として、1、もともと果樹の産地であり、新たに指導員を育てたり、 共選場を建設したりする必要がないこと。2、まとまった量が出荷できるようになるまでには数年かかるが、 すでに熊本果実連が一元販売をしており、量が少ない時期からの 販売がやりやすい。3、現在これといった特産物がない中山間地域に向いており、 しかも耕作放棄地となっているような減反田を再活用できる。などなどです。小生も果樹栽培はまったくのシロウトですので、うまくいくか心配ですが、まずはちゃんと出荷できるようなものが収穫できるよう、頑張ってみますネ。
2006.01.22
コメント(2)
-
それみたことか
予想はしていましたが、それにしても早すぎです(-_-#)米国から輸入された牛肉に脊柱(せきちゅう)(背骨)が混入していたことが確認され、再び米国産牛肉の輸入が全面禁止になりました。だから言わんこっちゃないんです。もともと管理体制のずさんさは指摘されていたわけですし、起こるべくして起こったことと言わざるを得ない事態ですから、この責任はまさに日本政府(小泉総理)にあります。食品安全委員会は輸入を再開するに当たって1.生後20カ月齢以下の牛に限る 2.病原体が蓄積しやすい脊髄(せきずい)など特定部位を除去する――という2つの条件を付けていました。それが守られていなかった! 輸入再開からわずか1ヶ月ですよ!どういうことだ! 責任者出て来い!!な~んて、怒っているふりをしながら実はよろこんでいるんですよ(*^^*)ヤッター、(≧∇≦)ノ彡 バンバン! てな感じですな。やっぱ国産ですよ! 国産!!しっかり国産の農畜産物を食べましょうよ!米国産牛肉なんてもういらないですよ。美味しい国産牛肉があるじゃないですか。美味しい国産の野菜や果物、肉を食べて、それで農家も元気になっていく。都市も農村も元気になって、自然も守られる。すべてがうまくいくじゃないですか!そういう道を選択しましょうよ! それが正しく生きる道だと思うけどなぁ。。
2006.01.21
コメント(3)
-
参勤交代
朝、歯磨きをしていたら前歯が欠けてしまいました(⌒ロ⌒;)もともと虫歯で治療をしたことがあったのですが、だんだん薄くなっていき、最近は透けるようになっていました。鏡を見るとメチャかっこわるいです。とほほ(T▽T)さっそく歯医者を予約し、夕方行ってきました。待合室で雑誌を読んでいると、おもしろい記事を見つけました。週間文春 1月19日号「パソコンを捨てて農作業せよ!」 養老孟司▼ここ数十年の日本社会の問題は都市化に尽きる。田舎が消えた。しかし、街だけでは生きられない。だれかが米を作り、作物を栽培し、山林を維持していかなければならない。▼人間は頭だけで生きているのではない。▼年に1ヶ月は田舎に住んで、田畑や山林で身体を使って働く。田植えや草取りや杉の間伐をする。それを義務づける。▼それを参勤交代と呼び、まずは霞ヶ関のお役人から始める。なんと素晴らしい提案なのでしょう\(^O^)/さすが、養老先生! 農業や林業の大切さがわかっていらっしゃる。山童はうれしかったです。(;;)ゥゥゥ泣霞ヶ関のお役人には是非やって欲しいですよね。一般の企業の人には、義務づけとまではいかないまでも、ボランティア休暇制度を、農業や林業の分野まで対象を広げてもらえばありがたいと思いますねぇ。あまり広まってはいないようですが、現在のボランティア休暇は災害時の支援活動や障害者・お年寄りのための福祉活動が対象となっているようです。>年に1ヶ月は田舎に住んで、田畑や山林で身体を使って働く。田植えや草取りや杉の間伐をする。そうした活動を、国や企業が支援するようになるとおもしろいですね。品目横断的経営安定対策などという政策より、ずっといい。
2006.01.20
コメント(0)
-
ゆっくりお茶を飲もう
お茶の生産者のみなさんと一緒に、熊本県の平成17年度茶共進会表彰式に行ってきました。共進会というのは、いわゆる品評会で、その年の優れたお茶を表彰するものです。熊本で生産されたお茶の中から、色沢や水色、滋味、味わい、香気などから優れたお茶が選ばれます。最近では、お茶の消費量はすっかり減ってきています。ドリンク原料は増えているものの、リーフ茶の消費は減りつづけているようです。先日の「九州百姓出会いの会」の中で、熊大の徳野教授から指摘がありましたが、現在の日本の家族構成をみてみると、一人世帯がなんと25.6パーセント、二人世帯が23.6%ということで、家族が非常に小さくなってきています。一人世帯、二人世帯が約半分になるわけで、そうなると外食や中食が中心となり、家での食事が減ることで当然お茶の消費量も減ると考えられます。外食レストランも最近ではほとんどお茶ではなく水を出しますから、ほんとに日本人はお茶を飲まなくなってきているようです。共進会の結果を見てみると、おもしろいことに上位の成績のお茶がけっして高く買われているわけではありません。共進会は総合的な評価をしますが、入札は茶商の好みが大きく左右します。総合的に優れているからといって、お茶屋さんが欲しがるというわけではないようです。お茶屋さんは、自分の店の商品づくりにあった茶葉を買うわけです。いいお茶をゆっくり味わうと、やはりそれぞれに個性があり、味わいがあります。そうしたお茶の味わい方というのを現代人は捨て去ってしまいました。スローライフ、スローフードというのは、「ゆっくりお茶を飲む」というところから始めていかなければならないのかもしれません。
2006.01.17
コメント(1)
-
九州百姓出会いの会
芦北町の御立岬公園で開かれた、「第28回九州百姓出会いの会」に出かけてきました。この「九州百姓出会いの会」というは、農民作家 山下惣一さんや農と自然の研究所代表 宇根豊さんたちが発起人となり、1980年から始まりました。名前の通り九州各地から百姓達が集まり、語り合い、一緒に飲み、交流する場。今回も山下惣一さん、宇根豊さん、合鴨水稲同時作の古野隆雄さん、熊本大学の徳野貞雄教授といった大御所をはじめ、九州各地から百姓や百姓見習い、公務員や生協職員など40名弱の参加者がありました。今年のテーマは「日本には農業はなくても良かろうたい?」。旧田浦町役場横の農業改善センターで、15日午後2時から始まりました。まずは参加者の自己紹介をしたあと、鹿児島大学教授 岩元 泉 さんが講演。「最近の農業政策について」と題し、経営所得安定対策等大綱の詳しい説明や、FTAの問題点、下支えのない直接支払い政策などについて詳しいお話を聞くことができました。その後御立岬公園へ会場を移し、食事の後は夜なべ談義。議論も白熱します。16日は、討論会。WTO体制を「推進する側」と「否定する側」に分かれてのディベートです。WTO体制を「推進する側」として日本政府代表 宇根大臣の主張は説得力があります。これに対抗し農業の必要性を主張するのは、なかなかむずかしいようです。参加者の皆さんの議論を聞きながら、自分自身の思考の浅さを実感しました。これまで地元で開催される時しか参加していませんが、夜なべ談義や討論会などを通して、「百姓の持つ世界の奥深さは計りしれないものがあるなあ!」という感じを持ちます。そして、そうした世界に生きているということに誇りも感じます。「百姓」の世界はやっぱり素晴らしいです\(^O^)/
2006.01.16
コメント(5)
-

デジタルデバイド
インターネットは便利な反面、危険な側面を持っていることは否めませんね。なんでもありの無法地帯と言っても過言ではありません。最近我家では、子供たちもインターネットを自由に使いこなすようになったので、変なサイトを覗いたりしないように、「i-フィルター4」というソフトを使うことにしました。自分ではそんなつもりはなくても、検索の結果によってアダルトサイトが表示されたりすることが良くありますよね。・・・お父さんはけっこう喜んで見たりしますが f(^_^)「i-フィルター4」を使うとそうした見せたくないサイトをブロックすることができます。さっそくインストールしてみました。ところが・・・・・ソースネクストの「ウイルスセキュリティ」と一緒に使うことができません。 ※ OSがまだ98SEなのです(TT)結局、「ウイルスセキュリティ」はアンインストールすることになってしまいました。しかし、ウイルス対策ソフトなしでは心配です。他のソフトを入れなければなりません。ウイルス対策ソフトはいろいろありますが、「i-フィルター4」との相性はどうなのでしょう?デジタルアーツのサポートページを調べてみました。やはり一緒には使えないソフトがいくつかあります。動作するとしてあるソフトも、実際に使ってみないと問題なく動くか心配です。そこで、体験版を試してみることにしました。トレンドマイクロ「ウイルスバスター体験版」をダウンロード。しかし、山童の住む久木野はまだブロードバンドが使えません。なんと! 体験版のダウンロードに3時間!最新パターンファイルのアップデートに30分!「i-フィルター4」の最新ファイルデータのダウンロードに30分!デジタルデバイドを痛感します。ひたすら待ちつづけ、なんとかダウンロードは済んだものの、今度はすべてのサイトがまったく表示されなくなってしまいました。あぁぁ仕方なく、一旦「i-フィルター4」をアンインストールし、再度インストールのやり直し。今度はうまくいきました。ホッ(∩∩)なんだかんだで、1日がかりの作業になってしまいました。まあ、でもこれで、ウイルス対策も有害サイト対策もできて安心です。お父さんは、たまに「i-フィルター4」を終了させて、ムフフなサイトを見たりもしますけどね(*^^*)デジタルアーツ i-フィルター 4.0
2006.01.14
コメント(2)
-
ミナマタ 50年と100年
水俣に住むものにとって、「水俣病」はあまりにも大きく重い歴史である。海に流されたメチル水銀は、人びとの体を蝕み、命を奪い、人と自然・人と人との関係をずたずたにし、地域社会をも崩壊させた。その苦しみは今なお続く、現在進行形の公害事件である。今年は、その「水俣病」の公式発見から50年目となる大きな節目の年である。また、今日12日は、水俣病の原因企業チッソの創立100年目の日でもある。50年とはいっても、「水俣病」は過去のものとなったわけではない。すべての被害者が完全に救済されたとはいえる状況ではない。今なお、解決すべき様々な問題・課題が残っている。今年はこの50年の節目に、いろいろな事業が計画されている。・水俣病犠牲者慰霊碑の落成行事・胎児性水俣病患者、障がい者の想いを伝える創作舞台芸術の創作・上演・「みなまた塾」講座の開催・「みなまたの50年」フォーラムの開催・シンポジウム「(仮)水俣病問題が持つ歴史的・社会的な意味について」の開催 etc被害者の救済策はもとより、その教訓をいかに活し、地域の再生をどうはかっていくのか、水俣病事件をあらためて問い直していく再スタートの年になるのだろうと思うし、単なるイベントにとどまらず、これからの50年をしっかりと考えていくことが大切だろう。水俣に住む私たちにとって、「水俣」はやはり愛すべき故郷である。豊かな自然や暖かな人情にあふれる素晴らしい土地である。水俣市民は、「水俣病」がもたらしたものをあまねく受け入れている。その上でその教訓を活かしながら新しい街づくりに取り組んでいる。私達はこれからもこの「水俣」に住む続けたい。誇りある郷土であってほしい願っている。チッソ 12日に創立100周年 水俣病公式確認から今年で50年(熊本日々新聞)http://kumanichi.com/news/local/index.cfm?id=20060112200005&cid=main水俣病公式確認50年実行委員会ホームページhttp://www.minamatacity.jp/jp/50th/top.htm
2006.01.12
コメント(2)
-

スケートに行ったどー!
今日で冬休みも終わりです。いつも子供達は最後の日に慌てて宿題をしているので、この冬休みは、8日までに宿題が終わったら、9日はスケートに連れて行くと約束をしていました。順調に宿題も終わり(^-^)v、今日は子供達を連れて熊本市のアクアドームへと出かけて行きました。アクアドームは、平成11年に開催された第54回国民体育大会~くまもと未来国体~の水泳競技場としてつくられました。水泳・スケート・バスケットができます。子供達はといえば、息子が2回目、娘達は始めてのスケートです。2時間ぐらい滑って、それぞれなんとか滑れるようになったようです。6歳の次女も、手を引いてやるとなんとかついて来ます。何度か通うとうまくなるのでしょう。でも、近くにあればともかく、年1回やったぐらいではねぇ( ̄^ ̄;)以前は熊本にもいくつかのスケート場がありました。阿蘇には野外のスケート場もあったんですよ。今はここだけかなぁ?やっぱり熊本はウインタースポーツには縁遠いようです(T▽T)アクアドームくまもと公式サイト
2006.01.09
コメント(0)
-
消費者を分類する
今日(1月6日)の日本農業新聞に、マーケティングプロデューサー 平岡豊氏(我が家のあいがもオーナーでもある)が、「5タイプの消費者」というコラムを書かれている。頭脳タイプ安全とか遺伝子組み替えなどに敏感五感タイプグルメ派で、鮮度や風味、食感などに魅力を感じている。週刊誌などの「お取りよせ便」にも関心が高い。胃袋タイプ満腹感が第一。心情タイプ食物を大切にし、お米はお百姓さんが八十八回も手間をかけているから粗末にしてはいけないと考えるし、初物や縁起物にも目配りをする。財布タイプ国民の食料だから安いのが当然だとし、家計も厳しいので食費に多くは使えないと主張している。平岡氏は、こうした多様な消費者を踏まえた上で、適切な戦略を立てるべき、と主張する。また、五感タイプや心情タイプの人たちにも積極的に発言できる場があっていいのに、現状では、頭脳タイプへの対応が大きくなり、「絶対に安全なものを安価で」という意見が絶対的な正論となってしまっている、と言う。一方、熊本大学教授 徳野貞雄氏は、「農業への理解度」と「食費への支出度」から、消費者を4つに分類する。農業に理解があり、お金を出してもいい。農業への理解はある。しかし、お金は出したくない。農業に対する理解はない。でも安全なものにはお金は出す。農業に理解はない。お金も使いたくない。徳野教授は、タイプ別な対応というのではなく、農家が消費者を選んでつきあうべきだと主張する。「農業に理解があり、お金を出してもいい」という消費者とは「親戚づきあい」。「理解もない。お金も出さない。」という消費者は「放っておけ!」という感じだ。消費者を分類し、どの層をターゲットに戦略を立てるのかということは当たり前の話だろうが、農業の現場には欠けていた視点かもしれない。消費者のみなさん、あなたがたも選別されているのですよ(・ω・)
2006.01.06
コメント(1)
-
初夢!!
一富士、二鷹、三茄子あなたの初夢はどんな夢でしたか?小生の初夢はちょっとエッチな夢でした。日記には書けません(*^^*) ムフフ次に見た夢はスケートの夢でした。これは真央ちゃんの影響かな(o^v^o)寝ている時に見る夢とは違いますが、人生に夢を持つことはとっても大切なことだと思っています。夢を持てば目標もでき、生きがいが生まれます。もちろん「夢が見つからない」なんて悩む必要はないですが、ちょっとした「やりたいこと」「欲しいもの」ならいっぱいありますよね。小生が今年やりたいこと、欲しいものは、「自転車旅行」「CDデビュー」「ソロコンサート」「デジタル一眼レフカメラ」・・etc将来の夢は、ちょっと大きくなりますが、「山村テーマパーク」をつくること。テーマパークといっても、莫大な投資をして人工的なものを造るのではなく、山村に住む人が、活き活きと農業や林業を営み、文化を守りながら、そこにグリーンツーリズムを組み合わせていけば、テーマパークができあがります。水俣市では現在、「村まるごと博物館」という取り組みを行っています。この延長線上に「村まるごとテーマパーク」があると考えています。実現不可能な夢ではないですよね。ただ現実には、小生の住む村も高齢化が進み、農業・林業の営み、文化の継承もとぎれてしまいそうです。「山村(農村)テーマパーク」という夢は、活き活きとした農村・山村をつくる、という目標でもあります。しかし現在の農山村は、元気がなくなりつつあります。この夢は泡と消えてしまうのでしょうか? 現実のものとなるのでしょうか?♪あ~なたの夢を~ あ~きらめないで~♪なんて岡村孝子の歌を口ずさみながら、今日もしっかりがんばろう(^^)/
2006.01.05
コメント(0)
-
枝打ち
この正月の休みを利用して、ヒノキの枝打ちに行った。最近は、枝打ちして無節材がとれるかどうかはほとんど価格に反映しないので、あまり念入りに枝打ちを行うことはないのだが、やはり、枝打ちをすることで間伐などの作業がしやすくなるし、通直な材を作るのには欠かせない作業であることには変わりはない。本来ならば成長に合わせてまめに行わなければならない作業なのだが、ちょっと遅れ気味になってしまう。要するに、枝が太くなりすぎて、枝打ちの傷が大きくなってしまうのだ。できるだけ傷をつけないように作業をする。一番いいのは鎌による枝打ちである。後の巻き込みが早い。しかし、枝が大きくなりすぎて、鎌ではできない枝も多い。そうした枝は鋸を使うしかない。腰より下の部分は鉈を使うので、鎌、鋸、鉈の3つの道具を持ち歩くことになる。こうした道具はしっかりと刃を研いでおくのがプロの仕事だ。なまくら刀では満足いく仕事はできないのだ。午後から出かけたので、大した仕事はできなかったが、やはり、山がきれいになっていく様は気持ちいい。まったく経済的には採算が合わなくなってしまった林業であるが、山仕事の爽快さは何ものにも替えられないものなのだ。
2006.01.03
コメント(2)
-

森と棚田で考えた
山童の住む村には、猪や狸や蝮や雉や狢や人間などいろんな動物が住んでいます。これらはすべて地域の貴重な宝なのですが、その中でも、ぜひ一度は会っていただきたい一匹、いや違った一人が「自由飲酒党総裁」こと、久木野ふるさとセンター愛林館館長 沢畑亨 氏です。愛林館は、「エコロジー(風土・循環・自立)に基づくむらおこし」というテーマを掲げ、さまざまな活動を行っています。※ 具体的な活動の内容については愛林館のホームページをご覧ください。→ コチラ 館長の個人サイトは→ コチラ紹介が少し遅くなってしまいましたが、昨年の暮れ、その沢畑館長が本を出しました\(^O^)/ヤッターそれがこれです ↓↓森と棚田で考えた森と棚田について書かれた文章をまとめてあり、森や棚田を守ることの意味や愛林館が何を目指し、どういう活動をしているのかもよくわかります。詳しい内容は、まぁ読んでくださいませm(_ _)m在庫もいっぱいあるようですし、σ(^_^;)?視点・発想がおもしろいですから、読んでみて損はしないと思いますよ。たぶん(⌒ロ⌒;)2005年12月24日(土)、熊本日々新聞の新生面でも紹介されています。 ↓↓http://kumanichi.com/iken/index.cfm?id=20051224
2006.01.02
コメント(1)
-
「ど真剣」に生きる
稲盛和夫氏が言われている言葉です。・・・・・・一日一日を「ど真剣」に生きなくてはならない、と私はよく社員に言っていますが、一度きりの人生をムダにすることなく、「ど」がつくほど真摯に、真剣に生き抜いていく――そのような愚直なまでの生き様を継続することは、平凡な人間をもやがて非凡な人物へと変貌させるのです。今年の抱負は二つあります。ひとつめは、この 「ど真剣」 です。「愚直」という言葉もいいですね。しっかりやります!!もうひとつは、 「リラックス」 です。これまでは、「緊張」の連続の後に「脱力」という感じでした。「緊張」と「脱力状態」の繰り返しといった日々でした。今年はこの「脱力状態」のところを「リラックス」できるようにしたいと思っています。つまり、「脱力」ではなくて、「充電」できるようにしたいというわけです。「リラックス状態」の中で、忘れていた感覚や新しい感性を研ぎ澄ましていきたいと思っています。さあ、新しい一年が始まりました。今年はいい年になりそうな予感がします!!みなさん、今年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m
2006.01.01
コメント(5)
全16件 (16件中 1-16件目)
1