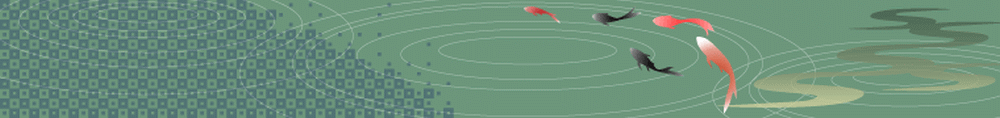カテゴリ: 歴史・考古学
・・・・皆様こんにちは、わたくし「オシリス葬祭」営業部のランプシニトスと申します。この度はわが社のご奉仕について説明させていただきます。
人間亡くなりますと、その魂である「カア」が口から出ていってしまいます。このカアはあちこちさまようのですが決して消滅することはございません。ましてやカアは時々遺体に戻って来ることもございます。昨今野蛮なギリシャ人が遺体を焼いて灰にしたり、傲慢なペルシア人が遺体を鳥に食べさせたりしておりますがとんでもないことで、このように遺体が無くなってしまうとカアの戻る場所が無くなってしまいさまよう事になってしまいます。そんなことでは故人のあの世(イアルの野)での幸福な暮らしは望むべくもありません。そのためにご遺体はミイラとして保存しておき、時々食べ物もお供えしなければならないのです。わが国エジプトではもう数千年もそうしております。
イアルの野は一面の葦の原で、緑溢れ水量豊かなそれは素晴らしく美しい田園地帯です。故人はイアルの野で現世と同じように自給自足の悠悠自適な農耕に従事し、神々に親しく接しつつ永遠の生命を得ます。
お葬式の手順ですが、ご不幸のあった家庭の女性の方々には顔に泥を塗ってもろ肌脱ぎになっていただき胸を叩きながら大声で泣いていただきます。男性も同様です。こうして死者への哀悼を示すのです。しめやかなムードを盛り上げる泣き上手な「泣き女」もこちらでご用意させていただきます。
さて肝心のご遺体ですが、これは既に述べましたとおり腐ってなくならないよう、葬儀が終了しましたのち、専門職人の手でミイラに加工する必要があります。こちらに木製の見本模型がございますが、松竹梅3コースございます。
「松」コースの場合、鼻孔から腐りやすい脳髄を刃物や薬品で取り出し、黒曜石で腹部を切開してこれまた腐りやすい内臓を取り出します。取り出した内臓は椰子油で清め別途壷(カノプス)に収めますのでご安心ください。心臓のみは故人の記憶や精神が宿る神聖な器官ですので防腐処置ののちご遺体に戻します。内臓を取り出した腹腔には防腐のため没薬と香料(肉桂と乳香を除く)を詰めて縫い合わせ、ご遺体を天然ソーダ(ナトリウム化合物)にきっちり70日間漬けます。
こうすることで水分が抜かれて腐りやすい脂肪などは取り除かれ、肉体の保存率が良くなります。これが済みますとご遺体を取り出して洗い、亜麻布の包帯で丁寧に巻き、防腐のための蜂蜜を塗りさらに樹脂(天然ゴム)を塗りつけて真空パックして、ご親族にお引渡しということになります。ミイラを収める人型の木棺の料金もセット価格に含まれて居りますのでご安心ください。
「竹」コースの場合、内臓を取り出す過程を簡易化するため注射器で薬品を肛門から流し込んで栓をし、全身を70日間ソーダ漬けにいたします。その後栓を取りますと溶けた内臓が流れ出ます。このコースでは、包帯を巻く作業以降をご遺族にご負担していただきます。「梅」コースの場合、下剤で腸内を洗浄するだけでソーダ漬けにし、その後の作業はご遺族の負担となります。このコースの場合、ご遺体が腐る多少のリスクがございます。
先日ミイラ職人が死後間も無い美貌のご婦人の遺体に辱めを加えていたというショッキングなニュースがございましたが、わが社ではそのようなことを防止するため死後4日目以降にミイラ製作に取りかからせていただいております。なおナイル河で溺死もしくはワニに襲われた方のご遺体は神に属しますので、わが社ではお扱いいたしかねます。
愛するご家族とのお別れを演出し、故人の来世における永遠の暮らしを幸福なものとするために、我が「オシリス葬祭」に是非ともご用命くださいませ。
なおイアルの野での農耕作業が面倒だという方のために、故人に代わり農耕に従事させるためのウシャブティ(像)のご用命も承っております。・・・・
・・・とまあふざけたことを書いてみたが、これはヘロドトス「歴史」巻2、85~90節に書いてある古代エジプトの葬送に関する記述をいじったものである。
価格についてはヘロドトスは書いていないので、古代エジプトで雄牛1頭が銅50デベンしたという取引記録に基き、現代日本の牛1頭(去勢牛)の平均価格40万円を基準として、松竹梅それぞれ社葬規模・参列者100人規模・40人規模の葬儀の葬儀会社による設定平均価格に換算してみた。特に日本で高価なお墓の値段を考慮していないし、まあ「お遊び」なので当時と現代の物価の違いは言いっこ無しである(なお銅の生産量が桁違いな現代では、銅1デベンはおよそ30円くらいでしかない)。なおドイツでは墓地代も含めて葬送・埋葬におよそ50万円かかるらしい。
現代の法律では遺体を埋葬せずミイラにしたら犯罪になるんだよなあ(一部の共産主義国のぞく)。そういや最近そういう宗教団体があったっけ(あれは「死んでない」と言い張っていたのだから違うか)。
なんでこういう日記を書いたかというと、以下のニュースを見たためである。
(引用開始)
<ミイラ発見>エジプト・カイロの遺跡で 早大研究所が発表
エジプト・カイロ近郊のダハシュール北遺跡を調査している早稲田大学エジプト学研究所は21日、約3750年前の古代エジプト中王国・第13王朝期と見られるミイラを発見したと発表した。未盗掘で、未破壊の完全な形で発見された例としては最古級という。保存状態は極めて良く、当時の墓制や宗教慣行など今後の研究に寄与しそうだ。
ミイラを納めた木棺は今月5日、地下約5メートルで見つかった。棺には「セヌウ」という男性の名前と、行政官を意味する「アチュ」という称号が書かれている。ミイラは白い布で包まれ、顔を覆うマスクには青や赤、黒など鮮やかな彩色が残っている。ミイラ自体の調査はまだだが、装身具など豊かな副葬品があるのは確実という。
ミイラや棺は副葬品目当ての盗掘で破壊された例がほとんど。しかし、今回は、棺を収めた穴の上部に岩が詰められていたことなどから発見されにくく、無事だった。
内田杉彦・明倫短期大学助教授(エジプト学)の話 保存状態のいい史料が少ない時代のものであり、貴重な発見だ。当時の宗教慣行などを知るうえで重要な手がかりになる。【栗原俊雄】(毎日新聞) - 1月21日20時23分更新
(引用終了)
いやはや大発見だ。あれ、コメントを求められている内田さんて、去年酒席でご一緒したなあ。吉村先生も学会でお見かけしたことがある(とても忙しそうだった)。突っ込んだ質問をした聴衆(おじさん)に「それはご自分で調査なさってください」と答えていたのが印象に残っている。早稲田の調査隊には昔テレビ番組で高橋由美子や宜保愛子が参加していたが、宜保さんはともかく高橋由美子みたいなのが参加してくれたら調査も楽しいだろうなあ・・・・。
・・・さて、手元の本にはエジプトでミイラがいつ頃から作られ始めたのか書いてないが、乾燥したエジプトでは遺体が自然にミイラになることもあり、それを見たエジプト人が来世観と結びつけて人工的にやり始めたらしい。
ミイラ作りは最初は王の独占物で、臣民は王に仕える事で永遠の生命の分け前に与るという考え方だったらしい。ところが第6王朝の崩壊で王権が失墜した第一中間期(紀元前2145年頃~)からミイラ作りは臣下にも広まり「大衆化」していった。ミイラを作れない貧乏人は「死者の裁判」の観念を発達させ、正しい行いをすれば肉体を失ってもあの世で永遠に暮らせると信じた。
副葬された財宝目当てのみならず、ミイラは薬(漢方薬)になるというので、アラブ時代以降は盗掘されることも多かった。
ヨーロッパ近代初期では死んだ王の心臓とかを取り出したりしているが、あれは古代エジプトの風習と何か関係するのだろうか(eugen9999さんによれば、ハプスブルク家に起源があるようです)。上にも書いたけど、共産主義国ではミイラ製作が絶対権力の象徴として今も健在ですね。
歴史(上)

人間亡くなりますと、その魂である「カア」が口から出ていってしまいます。このカアはあちこちさまようのですが決して消滅することはございません。ましてやカアは時々遺体に戻って来ることもございます。昨今野蛮なギリシャ人が遺体を焼いて灰にしたり、傲慢なペルシア人が遺体を鳥に食べさせたりしておりますがとんでもないことで、このように遺体が無くなってしまうとカアの戻る場所が無くなってしまいさまよう事になってしまいます。そんなことでは故人のあの世(イアルの野)での幸福な暮らしは望むべくもありません。そのためにご遺体はミイラとして保存しておき、時々食べ物もお供えしなければならないのです。わが国エジプトではもう数千年もそうしております。
イアルの野は一面の葦の原で、緑溢れ水量豊かなそれは素晴らしく美しい田園地帯です。故人はイアルの野で現世と同じように自給自足の悠悠自適な農耕に従事し、神々に親しく接しつつ永遠の生命を得ます。
お葬式の手順ですが、ご不幸のあった家庭の女性の方々には顔に泥を塗ってもろ肌脱ぎになっていただき胸を叩きながら大声で泣いていただきます。男性も同様です。こうして死者への哀悼を示すのです。しめやかなムードを盛り上げる泣き上手な「泣き女」もこちらでご用意させていただきます。
さて肝心のご遺体ですが、これは既に述べましたとおり腐ってなくならないよう、葬儀が終了しましたのち、専門職人の手でミイラに加工する必要があります。こちらに木製の見本模型がございますが、松竹梅3コースございます。
「松」コースの場合、鼻孔から腐りやすい脳髄を刃物や薬品で取り出し、黒曜石で腹部を切開してこれまた腐りやすい内臓を取り出します。取り出した内臓は椰子油で清め別途壷(カノプス)に収めますのでご安心ください。心臓のみは故人の記憶や精神が宿る神聖な器官ですので防腐処置ののちご遺体に戻します。内臓を取り出した腹腔には防腐のため没薬と香料(肉桂と乳香を除く)を詰めて縫い合わせ、ご遺体を天然ソーダ(ナトリウム化合物)にきっちり70日間漬けます。
こうすることで水分が抜かれて腐りやすい脂肪などは取り除かれ、肉体の保存率が良くなります。これが済みますとご遺体を取り出して洗い、亜麻布の包帯で丁寧に巻き、防腐のための蜂蜜を塗りさらに樹脂(天然ゴム)を塗りつけて真空パックして、ご親族にお引渡しということになります。ミイラを収める人型の木棺の料金もセット価格に含まれて居りますのでご安心ください。
「竹」コースの場合、内臓を取り出す過程を簡易化するため注射器で薬品を肛門から流し込んで栓をし、全身を70日間ソーダ漬けにいたします。その後栓を取りますと溶けた内臓が流れ出ます。このコースでは、包帯を巻く作業以降をご遺族にご負担していただきます。「梅」コースの場合、下剤で腸内を洗浄するだけでソーダ漬けにし、その後の作業はご遺族の負担となります。このコースの場合、ご遺体が腐る多少のリスクがございます。
先日ミイラ職人が死後間も無い美貌のご婦人の遺体に辱めを加えていたというショッキングなニュースがございましたが、わが社ではそのようなことを防止するため死後4日目以降にミイラ製作に取りかからせていただいております。なおナイル河で溺死もしくはワニに襲われた方のご遺体は神に属しますので、わが社ではお扱いいたしかねます。
愛するご家族とのお別れを演出し、故人の来世における永遠の暮らしを幸福なものとするために、我が「オシリス葬祭」に是非ともご用命くださいませ。
なおイアルの野での農耕作業が面倒だという方のために、故人に代わり農耕に従事させるためのウシャブティ(像)のご用命も承っております。・・・・
・・・とまあふざけたことを書いてみたが、これはヘロドトス「歴史」巻2、85~90節に書いてある古代エジプトの葬送に関する記述をいじったものである。
価格についてはヘロドトスは書いていないので、古代エジプトで雄牛1頭が銅50デベンしたという取引記録に基き、現代日本の牛1頭(去勢牛)の平均価格40万円を基準として、松竹梅それぞれ社葬規模・参列者100人規模・40人規模の葬儀の葬儀会社による設定平均価格に換算してみた。特に日本で高価なお墓の値段を考慮していないし、まあ「お遊び」なので当時と現代の物価の違いは言いっこ無しである(なお銅の生産量が桁違いな現代では、銅1デベンはおよそ30円くらいでしかない)。なおドイツでは墓地代も含めて葬送・埋葬におよそ50万円かかるらしい。
現代の法律では遺体を埋葬せずミイラにしたら犯罪になるんだよなあ(一部の共産主義国のぞく)。そういや最近そういう宗教団体があったっけ(あれは「死んでない」と言い張っていたのだから違うか)。
なんでこういう日記を書いたかというと、以下のニュースを見たためである。
(引用開始)
<ミイラ発見>エジプト・カイロの遺跡で 早大研究所が発表
エジプト・カイロ近郊のダハシュール北遺跡を調査している早稲田大学エジプト学研究所は21日、約3750年前の古代エジプト中王国・第13王朝期と見られるミイラを発見したと発表した。未盗掘で、未破壊の完全な形で発見された例としては最古級という。保存状態は極めて良く、当時の墓制や宗教慣行など今後の研究に寄与しそうだ。
ミイラを納めた木棺は今月5日、地下約5メートルで見つかった。棺には「セヌウ」という男性の名前と、行政官を意味する「アチュ」という称号が書かれている。ミイラは白い布で包まれ、顔を覆うマスクには青や赤、黒など鮮やかな彩色が残っている。ミイラ自体の調査はまだだが、装身具など豊かな副葬品があるのは確実という。
ミイラや棺は副葬品目当ての盗掘で破壊された例がほとんど。しかし、今回は、棺を収めた穴の上部に岩が詰められていたことなどから発見されにくく、無事だった。
内田杉彦・明倫短期大学助教授(エジプト学)の話 保存状態のいい史料が少ない時代のものであり、貴重な発見だ。当時の宗教慣行などを知るうえで重要な手がかりになる。【栗原俊雄】(毎日新聞) - 1月21日20時23分更新
(引用終了)
いやはや大発見だ。あれ、コメントを求められている内田さんて、去年酒席でご一緒したなあ。吉村先生も学会でお見かけしたことがある(とても忙しそうだった)。突っ込んだ質問をした聴衆(おじさん)に「それはご自分で調査なさってください」と答えていたのが印象に残っている。早稲田の調査隊には昔テレビ番組で高橋由美子や宜保愛子が参加していたが、宜保さんはともかく高橋由美子みたいなのが参加してくれたら調査も楽しいだろうなあ・・・・。
・・・さて、手元の本にはエジプトでミイラがいつ頃から作られ始めたのか書いてないが、乾燥したエジプトでは遺体が自然にミイラになることもあり、それを見たエジプト人が来世観と結びつけて人工的にやり始めたらしい。
ミイラ作りは最初は王の独占物で、臣民は王に仕える事で永遠の生命の分け前に与るという考え方だったらしい。ところが第6王朝の崩壊で王権が失墜した第一中間期(紀元前2145年頃~)からミイラ作りは臣下にも広まり「大衆化」していった。ミイラを作れない貧乏人は「死者の裁判」の観念を発達させ、正しい行いをすれば肉体を失ってもあの世で永遠に暮らせると信じた。
副葬された財宝目当てのみならず、ミイラは薬(漢方薬)になるというので、アラブ時代以降は盗掘されることも多かった。
ヨーロッパ近代初期では死んだ王の心臓とかを取り出したりしているが、あれは古代エジプトの風習と何か関係するのだろうか(eugen9999さんによれば、ハプスブルク家に起源があるようです)。上にも書いたけど、共産主義国ではミイラ製作が絶対権力の象徴として今も健在ですね。
歴史(上)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[歴史・考古学] カテゴリの最新記事
-
宣伝です 2015年10月22日
-
ウズベキスタン 1:1 日本 2008年10月15日
Re:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
turkuvaz
さん
まことに流暢な語り口で・・・不謹慎ですが、愉しませていただきました^^。(そちら方面での才能もおありでは?)
ミイラ作りにも3段階あったんですね。自分なら何コースがいいかしら・・中くらいの好きな日本人らしく「竹」コースにしとこうかしら・・?
(2005年01月24日 02時56分05秒)
ミイラ作りにも3段階あったんですね。自分なら何コースがいいかしら・・中くらいの好きな日本人らしく「竹」コースにしとこうかしら・・?
(2005年01月24日 02時56分05秒)
Re[1]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>turkuvazさん
>まことに流暢な語り口で・・・不謹慎ですが、愉しませていただきました^^。(そちら方面での才能もおありでは?)
語り口が流暢なのはヘロドトスの原文のおかげもあるでしょうね。
ちょっと不謹慎だったかもしれませんが、古代エジプト人は全く違う死生感を持っていたようですね。宴会の最中にミイラの模型を廻したりするところは一見中世ヨーロッパの「Memento mori」に似ていますが、方向は全く逆みたいです。
>ミイラ作りにも3段階あったんですね。自分なら何コースがいいかしら・・中くらいの好きな日本人らしく「竹」コースにしとこうかしら・・?
うーん。僕はやっぱりどれも嫌です(笑)。人間タダでは死ねないというのは古代も現代も同じみたいですね。
この日記を書くために、牛の値段や葬式の価格(日記中に挙げた値段より高めかもしれません)の勉強が出来ました。 (2005年01月24日 03時34分11秒)
>まことに流暢な語り口で・・・不謹慎ですが、愉しませていただきました^^。(そちら方面での才能もおありでは?)
語り口が流暢なのはヘロドトスの原文のおかげもあるでしょうね。
ちょっと不謹慎だったかもしれませんが、古代エジプト人は全く違う死生感を持っていたようですね。宴会の最中にミイラの模型を廻したりするところは一見中世ヨーロッパの「Memento mori」に似ていますが、方向は全く逆みたいです。
>ミイラ作りにも3段階あったんですね。自分なら何コースがいいかしら・・中くらいの好きな日本人らしく「竹」コースにしとこうかしら・・?
うーん。僕はやっぱりどれも嫌です(笑)。人間タダでは死ねないというのは古代も現代も同じみたいですね。
この日記を書くために、牛の値段や葬式の価格(日記中に挙げた値段より高めかもしれません)の勉強が出来ました。 (2005年01月24日 03時34分11秒)
いつのよでも
風船君
さん
葬儀代などで頭が痛いですね。
今のお墓は三百万円とか 兄が頭を抱えています。
ぜんぜん 風葬のように跡形も残さないとか
ものすごく残すとかわかれていますね。
東南アジアは タイ人は 火葬で墓をもちません
カンボジア人は 墓が大好き
家くらいの大きさの墓で丸ごと寝せて安置します。
また家の前に棺を置いてイルミネーションで照らしているのもあります。
(2005年01月24日 08時18分51秒)
今のお墓は三百万円とか 兄が頭を抱えています。
ぜんぜん 風葬のように跡形も残さないとか
ものすごく残すとかわかれていますね。
東南アジアは タイ人は 火葬で墓をもちません
カンボジア人は 墓が大好き
家くらいの大きさの墓で丸ごと寝せて安置します。
また家の前に棺を置いてイルミネーションで照らしているのもあります。
(2005年01月24日 08時18分51秒)
Re:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
みさき116
さん
なんとも、手馴れた感じで「葬儀屋さん」になられたのかと思いました。
ミイラの作り方にそんなランクがあるなんて、初めて知りました。
いつも、とても勉強になります♪
吉村教授、とうとう発見したんですか~
以前テレビで途中経過を放送しているのを見ました。 (2005年01月24日 12時52分51秒)
ミイラの作り方にそんなランクがあるなんて、初めて知りました。
いつも、とても勉強になります♪
吉村教授、とうとう発見したんですか~
以前テレビで途中経過を放送しているのを見ました。 (2005年01月24日 12時52分51秒)
死の壁
eugene9999
さん
昨年、出版された養老孟司『死の壁』にハプスブルグ家の風習が書かれていました。死体から心臓だけを取り出して、わざわざ銀製のケースに入れて教会に収めていたようです。これはハプスブルグ家の在った地方でもその家だけに伝わる風習らしいのですが、いつ頃まで行われていたかは書かれていませんでした。オーストリア・ハンガリー二重帝国まで行われていたのでしょうかねえ・・・
>ヨーロッパ近代初期では死んだ王の心臓とかを取り出したりしているが (2005年01月24日 13時22分26秒)
>ヨーロッパ近代初期では死んだ王の心臓とかを取り出したりしているが (2005年01月24日 13時22分26秒)
オシリス葬祭営業部御中
fox173
さん
「お値段」は、どの時代でも、やはり遺体の措置の費用が大きかったんでしょうか
こんなこと言うと何ですが、ナイル河で死ぬと、お得なように思います。
遺族の費用負担は小さいし、オシリス様も棺桶に入れられれナイル川に投げ込まれた・・と聞いたことがありますし。
共産国というと、ホーチミンが本人の希望を無視して遺体保存されてしまったのも哀しいもので、早く葬ってあげて欲しいです。
日本だと仏舎利とか、即身仏とかだなと思い、検索で「山形県白鷹町の即身仏」というのを見つけました。日本で最後期の地域公認ミイラかと思います。
♯♯♯♯♯
嘉永7年(1854年)光明海上人という僧が「100年経ったら掘りだせ」と遺言して地下に入った。その言い伝えに基づき昭和53年にその入定窟と伝えられていた墳墓を掘ってみたところ、言い伝え通りに石室(いしむろ)の中から遺体が出てきた。その発掘の時の模様を写した写真や出土した木棺の一部や副葬品なども展示。 (2005年01月24日 15時37分47秒)
こんなこと言うと何ですが、ナイル河で死ぬと、お得なように思います。
遺族の費用負担は小さいし、オシリス様も棺桶に入れられれナイル川に投げ込まれた・・と聞いたことがありますし。
共産国というと、ホーチミンが本人の希望を無視して遺体保存されてしまったのも哀しいもので、早く葬ってあげて欲しいです。
日本だと仏舎利とか、即身仏とかだなと思い、検索で「山形県白鷹町の即身仏」というのを見つけました。日本で最後期の地域公認ミイラかと思います。
♯♯♯♯♯
嘉永7年(1854年)光明海上人という僧が「100年経ったら掘りだせ」と遺言して地下に入った。その言い伝えに基づき昭和53年にその入定窟と伝えられていた墳墓を掘ってみたところ、言い伝え通りに石室(いしむろ)の中から遺体が出てきた。その発掘の時の模様を写した写真や出土した木棺の一部や副葬品なども展示。 (2005年01月24日 15時37分47秒)
Re:いつのよでも(01/23)
artaxerxes
さん
>風船君さん
>葬儀代などで頭が痛いですね。
>今のお墓は三百万円とか 兄が頭を抱えています。
お墓がこんなに高いのは日本くらいじゃないでしょうか(お墓だけではないですが)。まだよく調べてませんが、ドイツは「永代使用」という考え方自体が無さそうです。
うちは幸か不幸か両親用のお墓はもうあるので、その点で頭を悩ますことは無いのですが・・。
>ぜんぜん 風葬のように跡形も残さないとか
>ものすごく残すとかわかれていますね。
>東南アジアは タイ人は 火葬で墓をもちません
>カンボジア人は 墓が大好き
>家くらいの大きさの墓で丸ごと寝せて安置します。
>また家の前に棺を置いてイルミネーションで照らしているのもあります。
カンボジアのはすごいですね。いや面白い。
葬制というのは人間行動の中でももっとも保守的で継続性が高いので、考古学(民族学にも?)には格好の研究対象です。各地のお墓事情をもっと調べていきたいです。 (2005年01月24日 19時29分26秒)
>葬儀代などで頭が痛いですね。
>今のお墓は三百万円とか 兄が頭を抱えています。
お墓がこんなに高いのは日本くらいじゃないでしょうか(お墓だけではないですが)。まだよく調べてませんが、ドイツは「永代使用」という考え方自体が無さそうです。
うちは幸か不幸か両親用のお墓はもうあるので、その点で頭を悩ますことは無いのですが・・。
>ぜんぜん 風葬のように跡形も残さないとか
>ものすごく残すとかわかれていますね。
>東南アジアは タイ人は 火葬で墓をもちません
>カンボジア人は 墓が大好き
>家くらいの大きさの墓で丸ごと寝せて安置します。
>また家の前に棺を置いてイルミネーションで照らしているのもあります。
カンボジアのはすごいですね。いや面白い。
葬制というのは人間行動の中でももっとも保守的で継続性が高いので、考古学(民族学にも?)には格好の研究対象です。各地のお墓事情をもっと調べていきたいです。 (2005年01月24日 19時29分26秒)
Re[1]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>みさき116さん
>なんとも、手馴れた感じで「葬儀屋さん」になられたのかと思いました。
お葬式は結構場数を踏んでいるんですよね。ああ、もちろん葬儀屋ではなく参列者としてです(笑)。
>ミイラの作り方にそんなランクがあるなんて、初めて知りました。
>いつも、とても勉強になります♪
ヘロドトスの記述はミイラ作りが大衆化した時代のものですから、現代日本の葬儀屋事情に通じるかもしれませんね。
>吉村教授、とうとう発見したんですか~
>以前テレビで途中経過を放送しているのを見ました。
吉村先生のおかげで日本でのエジプト学への関心が高いのですから、我々(僕はエジプト学が専門ではないですが)は感謝しないといけないです。 (2005年01月24日 19時32分03秒)
>なんとも、手馴れた感じで「葬儀屋さん」になられたのかと思いました。
お葬式は結構場数を踏んでいるんですよね。ああ、もちろん葬儀屋ではなく参列者としてです(笑)。
>ミイラの作り方にそんなランクがあるなんて、初めて知りました。
>いつも、とても勉強になります♪
ヘロドトスの記述はミイラ作りが大衆化した時代のものですから、現代日本の葬儀屋事情に通じるかもしれませんね。
>吉村教授、とうとう発見したんですか~
>以前テレビで途中経過を放送しているのを見ました。
吉村先生のおかげで日本でのエジプト学への関心が高いのですから、我々(僕はエジプト学が専門ではないですが)は感謝しないといけないです。 (2005年01月24日 19時32分03秒)
Re:死の壁(01/23)
artaxerxes
さん
>eugene9999さん
> 昨年、出版された養老孟司『死の壁』にハプスブルグ家の風習が書かれていました。死体から心臓だけを取り出して、わざわざ銀製のケースに入れて教会に収めていたようです。これはハプスブルグ家の在った地方でもその家だけに伝わる風習らしいのですが、いつ頃まで行われていたかは書かれていませんでした。オーストリア・ハンガリー二重帝国まで行われていたのでしょうかねえ・・・
-----
養老さんそんな本も出しているのですか。まあ脳と死との関わりは大きいでしょうかし。
さてハプスブルク家はもともとスイスの山中の出なのですが、その当時の風習をのちのちまで続けていたということでしょうか。山岳地帯での葬制との関連とか、あの地に居たケルト人との関わりなど、想像が膨らみます。もしくは土俗化したキリスト教とかも関係あるのでしょうかね。
ウィーンの聖シュテファン寺院には歴代の心臓を納めた一室があったと思います。20世紀はともかく、結構遅くまで残っていたのではないかと思います。
そういえば先日「ルイ17世?の心臓」と伝わるものが本人のものかどうかDNA鑑定されたというニュースがありましたが(本物とされました)、あれは婚姻関係にあったハプスブルク家から入ってきたのでしょうかね。 (2005年01月24日 19時38分45秒)
> 昨年、出版された養老孟司『死の壁』にハプスブルグ家の風習が書かれていました。死体から心臓だけを取り出して、わざわざ銀製のケースに入れて教会に収めていたようです。これはハプスブルグ家の在った地方でもその家だけに伝わる風習らしいのですが、いつ頃まで行われていたかは書かれていませんでした。オーストリア・ハンガリー二重帝国まで行われていたのでしょうかねえ・・・
-----
養老さんそんな本も出しているのですか。まあ脳と死との関わりは大きいでしょうかし。
さてハプスブルク家はもともとスイスの山中の出なのですが、その当時の風習をのちのちまで続けていたということでしょうか。山岳地帯での葬制との関連とか、あの地に居たケルト人との関わりなど、想像が膨らみます。もしくは土俗化したキリスト教とかも関係あるのでしょうかね。
ウィーンの聖シュテファン寺院には歴代の心臓を納めた一室があったと思います。20世紀はともかく、結構遅くまで残っていたのではないかと思います。
そういえば先日「ルイ17世?の心臓」と伝わるものが本人のものかどうかDNA鑑定されたというニュースがありましたが(本物とされました)、あれは婚姻関係にあったハプスブルク家から入ってきたのでしょうかね。 (2005年01月24日 19時38分45秒)
Re:オシリス葬祭営業部御中(01/23)
artaxerxes
さん
>fox173さん
>「お値段」は、どの時代でも、やはり遺体の措置の費用が大きかったんでしょうか
>こんなこと言うと何ですが、ナイル河で死ぬと、お得なように思います。
>遺族の費用負担は小さいし、オシリス様も棺桶に入れられれナイル川に投げ込まれた・・と聞いたことがありますし。
お客様、ナイルで溺死した方のご遺体は神殿に属するので、ご家族はご遺体に指1本触れることも許されないのでございます。費用負担(「松」コースを神殿や溺死した場所の市民が共同負担)は無い代わりに、私的な弔いも許されません。(ランプシニトス)
>共産国というと、ホーチミンが本人の希望を無視して遺体保存されてしまったのも哀しいもので、早く葬ってあげて欲しいです。
なんと、ホーチミンもそうなのですか。元祖のレーニンも本人の意向を無視してミイラにされましたね。この風習はさすがにアラブ圏(ナセルやアサド、アタチュルク)には入ってきませんでした。
1989年に共産体制の滅びたブルガリアでは、ミイラ化されていた最初の書記長の遺体が火葬にされました。そうなった場合、金日成とかはどうなるんでしょうかね。いろんな意味での記念に残してもらいたい気もしますが。
>日本だと仏舎利とか、即身仏とかだなと思い、検索で「山形県白鷹町の即身仏」というのを見つけました。日本で最後期の地域公認ミイラかと思います。
「湯殿山麓呪い村」という小説もありましたね。映画を見ましたが、あれはえぐかった。あれってどうして東北地方で盛んに行われたのでしょうね。
そういえば早稲田のエジプト調査隊を率いていた桜井清彦先生は、若い頃東北地方の即身仏の研究をされて本も出しています。 (2005年01月24日 19時48分26秒)
>「お値段」は、どの時代でも、やはり遺体の措置の費用が大きかったんでしょうか
>こんなこと言うと何ですが、ナイル河で死ぬと、お得なように思います。
>遺族の費用負担は小さいし、オシリス様も棺桶に入れられれナイル川に投げ込まれた・・と聞いたことがありますし。
お客様、ナイルで溺死した方のご遺体は神殿に属するので、ご家族はご遺体に指1本触れることも許されないのでございます。費用負担(「松」コースを神殿や溺死した場所の市民が共同負担)は無い代わりに、私的な弔いも許されません。(ランプシニトス)
>共産国というと、ホーチミンが本人の希望を無視して遺体保存されてしまったのも哀しいもので、早く葬ってあげて欲しいです。
なんと、ホーチミンもそうなのですか。元祖のレーニンも本人の意向を無視してミイラにされましたね。この風習はさすがにアラブ圏(ナセルやアサド、アタチュルク)には入ってきませんでした。
1989年に共産体制の滅びたブルガリアでは、ミイラ化されていた最初の書記長の遺体が火葬にされました。そうなった場合、金日成とかはどうなるんでしょうかね。いろんな意味での記念に残してもらいたい気もしますが。
>日本だと仏舎利とか、即身仏とかだなと思い、検索で「山形県白鷹町の即身仏」というのを見つけました。日本で最後期の地域公認ミイラかと思います。
「湯殿山麓呪い村」という小説もありましたね。映画を見ましたが、あれはえぐかった。あれってどうして東北地方で盛んに行われたのでしょうね。
そういえば早稲田のエジプト調査隊を率いていた桜井清彦先生は、若い頃東北地方の即身仏の研究をされて本も出しています。 (2005年01月24日 19時48分26秒)
例の問題も片付いてので
風船君
さん
Re:例の問題も片付いてので(01/23)
artaxerxes
さん
>風船君さん
ご苦労様でした。
>お墓の写真おもしろいですよね。
>日本の葬儀も面白くて特に土葬は面白いですね。
僕はお墓を見るのが好きという変な趣味?があって、古いお墓を見ると飽きないですね。掘り返すとなると話は別ですが。あと霊感とかがまるでないので「妙なもの」を連れて帰ったり、ということもありません。
こっちの教会の地下室には王侯の大きな棺がむき出しで安置してあったりします(ナポレオンもそうですね)。
>アンコールワットのソバは水葬なんですよ。
>よく死体が浮いています。
水葬というとガンジス河ですが、カンボジアは何か関連があるのでしょうかね。
日本には川は多いですが水葬というのはあまり聞きませんね。そういうのは勘弁して欲しいけど。
(2005年01月24日 20時06分30秒)
ご苦労様でした。
>お墓の写真おもしろいですよね。
>日本の葬儀も面白くて特に土葬は面白いですね。
僕はお墓を見るのが好きという変な趣味?があって、古いお墓を見ると飽きないですね。掘り返すとなると話は別ですが。あと霊感とかがまるでないので「妙なもの」を連れて帰ったり、ということもありません。
こっちの教会の地下室には王侯の大きな棺がむき出しで安置してあったりします(ナポレオンもそうですね)。
>アンコールワットのソバは水葬なんですよ。
>よく死体が浮いています。
水葬というとガンジス河ですが、カンボジアは何か関連があるのでしょうかね。
日本には川は多いですが水葬というのはあまり聞きませんね。そういうのは勘弁して欲しいけど。
(2005年01月24日 20時06分30秒)
Re:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
jasmine~
さん
新聞のトップにミイラの(マスクの)写真が載っていました。すごいものを発見しましたね。
ミイラの漢方薬って何に効くんだろう・・・。
「不老不死」とか。
(2005年01月24日 21時38分14秒)
ミイラの漢方薬って何に効くんだろう・・・。
「不老不死」とか。
(2005年01月24日 21時38分14秒)
Re[1]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>jasmine~さん
>新聞のトップにミイラの(マスクの)写真が載っていました。すごいものを発見しましたね。
>
>ミイラの漢方薬って何に効くんだろう・・・。
>「不老不死」とか。
-----
ミイラって漢字で「木乃伊」と書くのですが、江戸時代には労咳(結核)の特効薬として日本にも輸入されていたみたいです。
ただミイラ本体ではなくミイラを作るための薬品(蜂蜜の一種)がそれだったという説もあって、よく分かりません。確かにヘロドトスも防腐剤として蜂蜜をミイラ製作に使う、と別の所で書いています(エジプトのみならずメソポタミアやペルシアでも使われていたとか)。
あとミイラの語源ですが、アラビア語ではムミヤというのですが、本来天然アスファルトのことみたいです。これはミイラに塗られていた黒い天然ゴムをアスファルトと勘違いしたためにこう呼ばれたのですが、同時に薬でもあった天然アスファルトがミイラから染み出していると勘違いしてミイラを薬にすることが始まった、と言われているようです。
上の説とは矛盾していますが、私は漢方薬には疎いのでよく分かりません。
(2005年01月25日 00時17分39秒)
>新聞のトップにミイラの(マスクの)写真が載っていました。すごいものを発見しましたね。
>
>ミイラの漢方薬って何に効くんだろう・・・。
>「不老不死」とか。
-----
ミイラって漢字で「木乃伊」と書くのですが、江戸時代には労咳(結核)の特効薬として日本にも輸入されていたみたいです。
ただミイラ本体ではなくミイラを作るための薬品(蜂蜜の一種)がそれだったという説もあって、よく分かりません。確かにヘロドトスも防腐剤として蜂蜜をミイラ製作に使う、と別の所で書いています(エジプトのみならずメソポタミアやペルシアでも使われていたとか)。
あとミイラの語源ですが、アラビア語ではムミヤというのですが、本来天然アスファルトのことみたいです。これはミイラに塗られていた黒い天然ゴムをアスファルトと勘違いしたためにこう呼ばれたのですが、同時に薬でもあった天然アスファルトがミイラから染み出していると勘違いしてミイラを薬にすることが始まった、と言われているようです。
上の説とは矛盾していますが、私は漢方薬には疎いのでよく分かりません。
(2005年01月25日 00時17分39秒)
Re[2]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
turkuvaz
さん
> 語り口が流暢なのはヘロドトスの原文のおかげもあるでしょうね。
原文で読まれてるんですか!?すごい。
ところで、私もいずれ古代史の勉強をしたいと思っているのですが、ヘロドトスの「歴史」やストラボンの「地誌学(地理)」を読むのに、ちょうどいい出版社など、ご存知でしたらお教えくださいませんか。
先日、ストラボンを読みたいと思って検索したのですが、日本語では3万円以上するものしかなく、ハーバード大学から出ているものを取り寄せようかと考えているのですが・・・(これだと、1冊20ドルちょっとで、希望する巻だけ読める)。 (2005年01月25日 00時41分47秒)
原文で読まれてるんですか!?すごい。
ところで、私もいずれ古代史の勉強をしたいと思っているのですが、ヘロドトスの「歴史」やストラボンの「地誌学(地理)」を読むのに、ちょうどいい出版社など、ご存知でしたらお教えくださいませんか。
先日、ストラボンを読みたいと思って検索したのですが、日本語では3万円以上するものしかなく、ハーバード大学から出ているものを取り寄せようかと考えているのですが・・・(これだと、1冊20ドルちょっとで、希望する巻だけ読める)。 (2005年01月25日 00時41分47秒)
Re[3]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>turkuvazさん
>原文で読まれてるんですか!?すごい。
紛らわしかったですね。原文というのはもちろん日本語に訳されたものです。さすがにギリシャ語(しかも古代ギリシャ語)は出来ません。今は研究論文や報告書とかを読むためにロシア語をやりたいとは思っていますが、さすがに古代ギリシャ語にまで手は出ないです。
古本屋で格安で買ったドイツ語版とギリシャ語原典版は持っていますが、いつも引用するのは岩波文庫から出ている松平千秋氏による日本語訳(全三巻)です。
>ところで、私もいずれ古代史の勉強をしたいと思っているのですが、ヘロドトスの「歴史」やストラボンの「地誌学(地理)」を読むのに、ちょうどいい出版社など、ご存知でしたらお教えくださいませんか。
>先日、ストラボンを読みたいと思って検索したのですが、日本語では3万円以上するものしかなく、ハーバード大学から出ているものを取り寄せようかと考えているのですが・・・(これだと、1冊20ドルちょっとで、希望する巻だけ読める)。
ヘロドトスは上に挙げたものが一番読みやすいかと思いますが、ストラボンは岩波文庫にも無かったでしたかね。あっても膨大なので全館揃えるのは大変でしょう。僕は持っていません。
もうお持ちかもしれませんが、Arkeoloji ve Sanat yayinlariからはストラボン「地理誌」のアナトリアに関連する部分のみをトルコ語に訳したのが出ています(僕はまだ買っていません)。
Antik anadolu Cografyasi(Geographika):
(Cev. Adnan Pekman)
http://www.arkeolojisanat.com (2005年01月25日 01時16分22秒)
>原文で読まれてるんですか!?すごい。
紛らわしかったですね。原文というのはもちろん日本語に訳されたものです。さすがにギリシャ語(しかも古代ギリシャ語)は出来ません。今は研究論文や報告書とかを読むためにロシア語をやりたいとは思っていますが、さすがに古代ギリシャ語にまで手は出ないです。
古本屋で格安で買ったドイツ語版とギリシャ語原典版は持っていますが、いつも引用するのは岩波文庫から出ている松平千秋氏による日本語訳(全三巻)です。
>ところで、私もいずれ古代史の勉強をしたいと思っているのですが、ヘロドトスの「歴史」やストラボンの「地誌学(地理)」を読むのに、ちょうどいい出版社など、ご存知でしたらお教えくださいませんか。
>先日、ストラボンを読みたいと思って検索したのですが、日本語では3万円以上するものしかなく、ハーバード大学から出ているものを取り寄せようかと考えているのですが・・・(これだと、1冊20ドルちょっとで、希望する巻だけ読める)。
ヘロドトスは上に挙げたものが一番読みやすいかと思いますが、ストラボンは岩波文庫にも無かったでしたかね。あっても膨大なので全館揃えるのは大変でしょう。僕は持っていません。
もうお持ちかもしれませんが、Arkeoloji ve Sanat yayinlariからはストラボン「地理誌」のアナトリアに関連する部分のみをトルコ語に訳したのが出ています(僕はまだ買っていません)。
Antik anadolu Cografyasi(Geographika):
(Cev. Adnan Pekman)
http://www.arkeolojisanat.com (2005年01月25日 01時16分22秒)
Re[4]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
上で紹介したホームページは工事中だそうです。
完成してから紹介しますよね?普通。まあトルコらしいといえばトルコらしいかな。
ともあれこの本は普通のやや大きめの本屋でも見かけます。アンカラでは何ヶ所かで売ってましたが、シワスにはろくな本屋が無いのでもうここ数年見ていません。 (2005年01月25日 01時19分42秒)
完成してから紹介しますよね?普通。まあトルコらしいといえばトルコらしいかな。
ともあれこの本は普通のやや大きめの本屋でも見かけます。アンカラでは何ヶ所かで売ってましたが、シワスにはろくな本屋が無いのでもうここ数年見ていません。 (2005年01月25日 01時19分42秒)
Re[5]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
turkuvaz
さん
>Antik anadolu Cografyasi(Geographika):
(Cev. Adnan Pekman)
そんなのがあったんですね(恥)。
アンタルヤでもあればいいなあ~。
早速探してみます。
(2005年01月25日 01時42分16秒)
(Cev. Adnan Pekman)
そんなのがあったんですね(恥)。
アンタルヤでもあればいいなあ~。
早速探してみます。
(2005年01月25日 01時42分16秒)
Re[6]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>turkuvazさん
>そんなのがあったんですね(恥)。
>アンタルヤでもあればいいなあ~。
>早速探してみます。
-----
トルコの出版業界は最近は侮れないですね。10年くらい前はろくな本が無かったのですが(あってもセンスが悪く落丁・乱丁は当たり前)。上に挙げたASY社とEge yayinlariは特にいい本を出しているように思います。
Arkeo AtlasというAtlas誌のアナトリア考古学特集号(年1冊)もお勧めです。まだ古典時代にまで達していませんが(去年の段階でヒッタイトまで出ています)。こっちはミグロスの雑誌コーナーでも売ってました。 (2005年01月25日 19時44分40秒)
>そんなのがあったんですね(恥)。
>アンタルヤでもあればいいなあ~。
>早速探してみます。
-----
トルコの出版業界は最近は侮れないですね。10年くらい前はろくな本が無かったのですが(あってもセンスが悪く落丁・乱丁は当たり前)。上に挙げたASY社とEge yayinlariは特にいい本を出しているように思います。
Arkeo AtlasというAtlas誌のアナトリア考古学特集号(年1冊)もお勧めです。まだ古典時代にまで達していませんが(去年の段階でヒッタイトまで出ています)。こっちはミグロスの雑誌コーナーでも売ってました。 (2005年01月25日 19時44分40秒)
Re[7]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
turkuvaz
さん
> トルコの出版業界は最近は侮れないですね。10年くらい前はろくな本が無かったのですが(あってもセンスが悪く落丁・乱丁は当たり前)。
アンタルヤはなにしろ文化後進都市ですからね・・。
仮にも大学のある都市とは思えないほど、本屋が貧弱で・・・。
> Arkeo AtlasというAtlas誌のアナトリア考古学特集号(年1冊)もお勧めです。まだ古典時代にまで達していませんが(去年の段階でヒッタイトまで出ています)。
こちらの方は、私も購読しています^^。グラフィックがなかなか綺麗で、眺めてるだけでも愉しいですね。 (2005年01月25日 20時06分53秒)
アンタルヤはなにしろ文化後進都市ですからね・・。
仮にも大学のある都市とは思えないほど、本屋が貧弱で・・・。
> Arkeo AtlasというAtlas誌のアナトリア考古学特集号(年1冊)もお勧めです。まだ古典時代にまで達していませんが(去年の段階でヒッタイトまで出ています)。
こちらの方は、私も購読しています^^。グラフィックがなかなか綺麗で、眺めてるだけでも愉しいですね。 (2005年01月25日 20時06分53秒)
Re[2]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
jasmine~
さん
artaxerxesさん
> ミイラって漢字で「木乃伊」と書くのですが、江戸時代には労咳(結核)の特効薬として日本にも輸入されていたみたいです。
> ただミイラ本体ではなくミイラを作るための薬品(蜂蜜の一種)がそれだったという説もあって、よく分かりません。確かにヘロドトスも防腐剤として蜂蜜をミイラ製作に使う、と別の所で書いています(エジプトのみならずメソポタミアやペルシアでも使われていたとか)。
手元にあった漢方の雑誌を見たけど、生薬に木乃伊は紹介されていませんでした。今は無いでしょうね。。マニアな漢方薬屋さんは持っているかもしれませんが。
蜂蜜の一種だったら確かに結核には栄養があって効きそうですね。面白いですね~。
(2005年01月25日 22時21分41秒)
> ミイラって漢字で「木乃伊」と書くのですが、江戸時代には労咳(結核)の特効薬として日本にも輸入されていたみたいです。
> ただミイラ本体ではなくミイラを作るための薬品(蜂蜜の一種)がそれだったという説もあって、よく分かりません。確かにヘロドトスも防腐剤として蜂蜜をミイラ製作に使う、と別の所で書いています(エジプトのみならずメソポタミアやペルシアでも使われていたとか)。
手元にあった漢方の雑誌を見たけど、生薬に木乃伊は紹介されていませんでした。今は無いでしょうね。。マニアな漢方薬屋さんは持っているかもしれませんが。
蜂蜜の一種だったら確かに結核には栄養があって効きそうですね。面白いですね~。
(2005年01月25日 22時21分41秒)
Re[8]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>turkuvazさん
>アンタルヤはなにしろ文化後進都市ですからね・・。
>仮にも大学のある都市とは思えないほど、本屋が貧弱で・・・。
シワスにも大学はありますが、アンタルヤよりももっとひどいこと請け合い?です。博物館もひどいですし。
アンタルヤは有数の観光地だけにそういうのは充実していると思ったのですが。 (2005年01月26日 02時20分04秒)
>アンタルヤはなにしろ文化後進都市ですからね・・。
>仮にも大学のある都市とは思えないほど、本屋が貧弱で・・・。
シワスにも大学はありますが、アンタルヤよりももっとひどいこと請け合い?です。博物館もひどいですし。
アンタルヤは有数の観光地だけにそういうのは充実していると思ったのですが。 (2005年01月26日 02時20分04秒)
Re[3]:ミイラで得る幸福な来世(01/23)
artaxerxes
さん
>jasmine~さん
>手元にあった漢方の雑誌を見たけど、生薬に木乃伊は紹介されていませんでした。今は無いでしょうね。。マニアな漢方薬屋さんは持っているかもしれませんが。
ミイラも「文化財」ですからね。中国とかだと売ってそうな気もする。新彊とかならミイラも入手できそうですし。
>蜂蜜の一種だったら確かに結核には栄養があって効きそうですね。面白いですね~。
ローヤルゼリーとかも健康食品として売ってますしね。防腐効果があるというのは知りませんでした。 (2005年01月26日 02時22分17秒)
>手元にあった漢方の雑誌を見たけど、生薬に木乃伊は紹介されていませんでした。今は無いでしょうね。。マニアな漢方薬屋さんは持っているかもしれませんが。
ミイラも「文化財」ですからね。中国とかだと売ってそうな気もする。新彊とかならミイラも入手できそうですし。
>蜂蜜の一種だったら確かに結核には栄養があって効きそうですね。面白いですね~。
ローヤルゼリーとかも健康食品として売ってますしね。防腐効果があるというのは知りませんでした。 (2005年01月26日 02時22分17秒)
補陀落渡海
fox173
さん
水葬ではないですが、熊野那智や四国の室戸岬や足摺岬などの補陀落渡海を思い出しました。出られないように外から板で封じたりした小屋を設けた小船に乗り、南海の彼方、観音がいるという補陀落浄土を目指し、小屋の中でお経を唱えながら行くという捨身行でした。補陀落渡海船には鳥居が設けられたのも多かったようです。仏教なものが入る前から、海の彼方に死後の世界があるという考えはあったし、死んだ体も浄め祓えば生き返ると思っていたのかも知れません。熊野の近くの串本で江戸末まで、「海の三昧」というのがあったそうです。浜に置いた棺が、満ち潮で流れ行くのを見送る。死んでしまうと、船に乗って生きてお経を唱えながら行くというのは無理なので棺を置くのだとか。こちらの方が原形なのかもしれません。庶民は補陀落渡海船は高価なので、死んでから送ったのでは、という説もあり、エジプトでも葬儀費用が出せないので、密かに死者をナイル川に送りだす人もいたかもと思います。
補陀落渡海は、、明治42(1909)年 天俊という僧が足摺岬沖に補陀落入水したというのもあります。記録が寺の縁起などに残っているのは、上人と言われるような僧が、単に補陀落浄土(ポタラカ)に行くというより、いずれ如来や菩薩とともに帰って来て、衆生を救う為ということだったようです。一般人が、真似てやる場合も多くて、酷いのになると、船に乗った者が、岸から遠ざかるまでに、逃げたくなって喚いても温かく見送られてしまった例もあるようです。
他の海岸へ辿り着く場合も少なくなかったようです。
琉球王府が編纂した『琉球国由来記』(1713年)に収められた金峰山観音寺の縁起によると、日本の僧侶である日秀は、補陀落山を目指したものの沖縄に着き寺を開いた、というのもあります。類似の事を意図的にやる亡命者もいたたかも。
(2005年01月26日 04時03分53秒)
補陀落渡海は、、明治42(1909)年 天俊という僧が足摺岬沖に補陀落入水したというのもあります。記録が寺の縁起などに残っているのは、上人と言われるような僧が、単に補陀落浄土(ポタラカ)に行くというより、いずれ如来や菩薩とともに帰って来て、衆生を救う為ということだったようです。一般人が、真似てやる場合も多くて、酷いのになると、船に乗った者が、岸から遠ざかるまでに、逃げたくなって喚いても温かく見送られてしまった例もあるようです。
他の海岸へ辿り着く場合も少なくなかったようです。
琉球王府が編纂した『琉球国由来記』(1713年)に収められた金峰山観音寺の縁起によると、日本の僧侶である日秀は、補陀落山を目指したものの沖縄に着き寺を開いた、というのもあります。類似の事を意図的にやる亡命者もいたたかも。
(2005年01月26日 04時03分53秒)
Re:補陀落渡海(01/23)
artaxerxes
さん
>fox173さん
詳細な書きこみ、ありがとうございました。
なるほど、処理(というのもなんですが)に困って意図的にナイル河に遺体を放り込んだ例は多かったかもしれないですね。
あの世とは違いますが、海の彼方から神的存在が来訪してくるというのは沖縄の「ニライ・カナイ」(あってるかな?)を連想させますね。秋田の「なまはげ」も、海からではないにしろ、来訪神という性格は南洋諸島に通じるものがあると読んだことがあります。
日本考古学では最近弥生時代の沖縄産の貝を加工した腕輪が、南洋と沿岸部との繋がりを示す遺物として注目されています。まさに「黒潮の道」(黒潮だけではないですが)ですね。日本の基層文化への想像をかきたてます。
補陀落渡海した有名人というと、平維盛とか一条兼定が連想されます。後者は家臣によってむりやり海に押し出されたのですが。 (2005年01月26日 04時16分09秒)
詳細な書きこみ、ありがとうございました。
なるほど、処理(というのもなんですが)に困って意図的にナイル河に遺体を放り込んだ例は多かったかもしれないですね。
あの世とは違いますが、海の彼方から神的存在が来訪してくるというのは沖縄の「ニライ・カナイ」(あってるかな?)を連想させますね。秋田の「なまはげ」も、海からではないにしろ、来訪神という性格は南洋諸島に通じるものがあると読んだことがあります。
日本考古学では最近弥生時代の沖縄産の貝を加工した腕輪が、南洋と沿岸部との繋がりを示す遺物として注目されています。まさに「黒潮の道」(黒潮だけではないですが)ですね。日本の基層文化への想像をかきたてます。
補陀落渡海した有名人というと、平維盛とか一条兼定が連想されます。後者は家臣によってむりやり海に押し出されたのですが。 (2005年01月26日 04時16分09秒)
Re:補陀落渡海(01/23)
artaxerxes
さん
>fox173さん
今になって思い出しましたが、ナイル対岸(西岸)にあるピラミッドへは船を使って移動したのでエジプトでも本来葬送には船はつきものでした。
海とあの世との繋がりがもっとも顕著なのはヴァイキングで、彼らは石を船形に並べたお墓を作っています。場合によっては船(ボート)そのものと一緒に火葬して埋葬していたみたいです。 (2005年01月26日 06時14分08秒)
今になって思い出しましたが、ナイル対岸(西岸)にあるピラミッドへは船を使って移動したのでエジプトでも本来葬送には船はつきものでした。
海とあの世との繋がりがもっとも顕著なのはヴァイキングで、彼らは石を船形に並べたお墓を作っています。場合によっては船(ボート)そのものと一緒に火葬して埋葬していたみたいです。 (2005年01月26日 06時14分08秒)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
Vortrag 18.6.2003

Einfuehrung

Yayoi-Zeit

3/4 Jhdt. n. Chr.

5/6. Jhdt. n.Chr.

7. Jhdt. n. Chr.

日本語版
過去の日記

考古学・歴史日記03年

考古学・歴史日記02年後半

考古学・歴史日記02年中頃

考古学・歴史日記02年前半

考古学・歴史日記01年
各国史

EU-25/2004(南欧)

EU-25/2004(中欧)

EU-25/2004(東欧)

EFTA諸国

ヨーロッパのミニ国家

EU加盟候補国

西アジア

アメリカ史(上) 建国

アメリカ史(中) 大国

アメリカ史(下) 超大国

カフカス諸国

バルカン半島(非EU)

EU加盟国(北欧)

スペイン史(1) 前近代

スペイン史(2) 近現代

EU-27/2007

中央アジア
ヘロドトス「歴史」を読む

その2

その3
他責志向と自己責任論
 New!
七詩さん
New!
七詩さん
韓国人って やはり… alex99さん
分かるかなぁ分かん… シャルドネと呼ばれた三浦十右衛門さん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
韓国ソウル!文家の掟 shaquillさん
 New!
七詩さん
New!
七詩さん韓国人って やはり… alex99さん
分かるかなぁ分かん… シャルドネと呼ばれた三浦十右衛門さん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
韓国ソウル!文家の掟 shaquillさん
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.